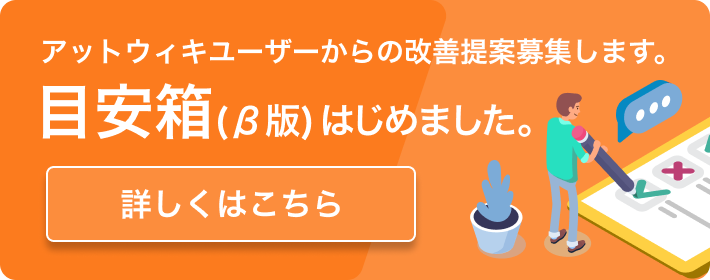「DECIDE THE FATE(前編)」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「DECIDE THE FATE(前編)」(2013/02/10 (日) 16:50:04) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
薄汚れた空気、鼻を突くほどの腐臭。
もしこの空間を色で表現することがあれば、恐らく緑色といえるだろう。自然からくる色ではなく、汚れた毒々しい色として。
そこはマンホールの下、下水管の中。街の汚水が流れ込む、誰もが寄り付かないであろう空間。
その空間を、体を引きずるように歩く者がいた。
間桐雁夜。
この薄汚れた空気も、誰もが入ることを躊躇うであろう不潔さも、彼にとっては慣れたものだった。
聖杯戦争が始まって以来、彼はずっとこの空間で過ごしてきたのだから。
ケイネス・エルメロイ・アーチボルト。アインツベルンの魔術師。そして遠坂時臣。
彼等と比べたとき、自分の魔術などどうということのないものだという自覚はあった。
加えてこのボロボロの体。戦うことなどできるはずもない。
だからこそバーサーカーを戦わせる間、身を隠すことで己の安全を確保し確実に生存できるようにしてきたのだ。
臆病者と言えばそれまでだが、身の程を弁えた上での戦略である以上仕方のないことでもある。
事実、この中にいる間は誰一人として雁夜を見つけられはしていない。気付いていたとしてもこのような不潔な場所に積極的に入ろうとは思わないだろう。
それに、
「ぐ…っ、がはっ…!!」
こうして虫と血の混じったものを吐き出す姿など、他のマスターに見られたら格好の餌食になるだけなのだから。
歩みは非常に遅い。
数歩歩くたびにこうやって血を吐きながら歩いている様だ。
もし彼がトキによって治癒の秘孔を突かれていなければ先ほどの戦いに使った蟲によって魔力を食いつぶされていただろう。
しかし、それほどまでの状態で進みながら、雁夜は今自分がどこへ向かっているのかすら把握していなかった。
「…凛ちゃん」
なぜ彼女がいたのか。
なぜ自分の知る彼女より成長してこんなところにいるのか。
なぜあれほどまでに葵さんに似ていたのか。
そんなことにまで考えが及ばない。
今思うのは、それとは別のこと。
(俺は…、凛ちゃんを殺せるのか…?)
考えたこともなかった。
桜ちゃんを救うため、聖杯戦争に参加した。
他の魔術師を、遠坂時臣を殺し、自分の命すらも捨ててもいいと考えていた。
では、もしも桜ちゃんと凛ちゃんのどちらかを選べ、と言われたら選べるのだろうか。
俺は桜ちゃんと凛ちゃんを幸せにしたかった。
桜ちゃんを凛ちゃんと葵さんのところに帰して幸せに、葵さんを―――
葵さんを―――
「葵さん―――」
そうだ、葵さんはもういないのだ。彼女は俺が殺したのだ。
時臣もいない。葵さんもいない。
あの笑顔はもう見られない。桜ちゃんと凛ちゃんと共に笑う姿をもう見ることができない。
いっそ、壊れてしまえば楽だっただろう。あるいはあの事実に目を背けていられたら楽だっただろう。
だが、思い出してしまった。それと同時に気付いてしまった。
己の罪に。己の業に。
今の間桐雁夜は正常に頭が回ってはいない。だが、だからこそ遠坂凛が大きくなっていたという事実も難しいことを考えずに受け入れることができた。
だからこそ、ある事実に気付いてしまった。遠坂葵を、遠坂時臣を殺したことで、彼女を一人きりにしてしまったのだということに。
「俺に凛ちゃんを殺すことは――」
できない。
自分には一つを救うために他のものを捨てる覚悟はできなかった。
ある世界における少年のような生き方は。
だからこそここまで歪んでしまったことまでは気付けない。
それでもあの蟲倉の少女を救う。それだけは変えられない。
今、それが無くなっては間桐雁夜という人間を保つことができないのだから。
己の進む先すらも定まらず、道に迷うまま、雁夜の足は進む。ゆっくりと、まるで蟲のように。
◆
アサシン、トキは霊体化した状態でそのまま進む主の姿を地上から見つめていた。
霊体化しているのは主の苦痛を少しでも和らげるため。地上にいるのは万が一の警戒のため。
そして歩みに手を貸さないのは彼自身のため。
これは彼自身の問題、選んだ道。
サーヴァントである自分では彼の歪みは直してはやれない。体の傷は直せても進むべき道までは示せない。
だが、今のまま進んでも彼には破滅しかないことも分かる。
彼の心からは一人の少女への思い、そしてその親であり彼自身とは浅からぬ因縁を持つ者への歪んだ思いがあった。
すでに人を救う身でなく、戦いに身を投じる存在となった今でも、関わりを持ってしまった彼だけでも救えないだろうかと。
かつての生き様から、アサシンというクラスにふさわしくない思考を持ってしまっている。
それはサーヴァントとなった自分の存在を、少しでも生前に近づけたいが故のただの傲慢なのだろうか。
考えても答えなど出ない。
ふと見上げた空。未だ明ける気配の見えぬ夜の闇に彩られた空間。
かつての世界と比べて夜の闇自体は薄い。それでもある程度の星を見ることはできた。
中でも強く輝く、ある形に並んだ七つの星。
北斗七星。
その傍には、蒼く光る星が煌いていた。
◆
(あれは、死兆星か…)
間桐邸にてふと外の空を見上げたラオウ。
彼にも同じものが見えていた。
かつてその拳で多くの人間の命を奪った。相手が強者であるならなおのこと、それが見えるかを問い、見えると述べたものを天へと還していった。
それをしなくなったのはいつからだろうか。そう、自身も死兆星を見たあの戦いからだ。
真の強者と戦うとき際は天すらも結末を測ることができなくなる。だから問うことをやめた。
無論この場においては多くの強者が集まっている。
何しろ過去、未来を問わず名を馳せた英雄、英霊達が相手だ。自身も世紀末の世界に拳王として名を馳せたからこそその偉大さがわかる。
死兆星などいつ見えてもおかしくはない。
だが、この空気には微かに既視感を感じていた。
血が、心が躍るこの感覚。かつて同じものを感じ取ったことがあるはずだ。
それがいつだったのかまでは思い出せない。記憶が磨耗している。
それでも確実に分かることがあった。
(この家に、何者かが近づいてきているな…)
◆
道のり自体は体が自然に覚えている。
かつてバーサーカーのマスターであったときに通った道なのだから。
どこから出ればあの忌々しい家にたどり着くのかも、全部分かっている。
会わねばならない子がいるから、そこがどんなに憎いモノの棲家であっても行かなければならない。
かつての己の家に。
彼には自業自得の面もあるとはいえ、あまり幸運だとはいえるものではない。
だが、かつて臓硯が言ったように運そのものが悪いとまではいえないのかもしれない。
時臣に敗北したときも、言峰綺礼の気まぐれが無ければ死んでいたであろうから。逆に苦しみが長続きしたという意味では、不幸といえるかもしれないが。
それでも、今この時までは生き残ることができる運があった。蝕まれた体もまだ動くし、他のマスターやサーヴァントと遭遇することもなかった。
その時までは。
間桐邸の門をくぐったとき、それは現れた。
いや、気付いた瞬間には目の前にいたというのが正しいかもしれないが。
突如魔力の奔流と共に周辺の大気が爆発したのだ。
爆音。衝撃。
危うくその熱に巻き込まれそうになった雁夜を、霊体化を解くと同時、自ら操る闘気をもって吹き飛ばした。
「ぐ…、誰だ!」
「少し止まってもらいましょうか」
問いかける雁夜の目の前に、白いコートを纏った男が現れた。
サーヴァントが顕現したことによる魔術回路の痛みに顔を顰めつつ、男、おそらくはサーヴァントを睨みつける。
そんな様子を気にも留めず、しかし下手に攻め込むこともせずに慎重に距離を取って観察している。
攻め込んでこないのはおそらく今の一瞬でこちらの力量を把握したためか。
雁夜はそのマスターとしての目を持って目の前のサーヴァントを測る。
ステータスは基本的に低いものが多いが魔力値が非常に高い。おそらくはキャスターのクラスか。
接近戦に強いアサシンなら負けることはないはず。だが気になることがある。
キャスターがここにいるということは、この家には何者かが侵入している。つまり、それは――
「…ぁ、はぁ…、お前、桜ちゃんを、どうした…?」
「…サクラ?どなたのことかは存じ上げませんが、この家に入るというのであれば私は止めなければいけないのですよね。お引取り願いたいのですが」
魔術師にとって自宅というものは工房と同義。
雁夜がどうこうしたものではないが、この家にも結界は張ってあったはずだ。容易く入れるものではない。
つまり、強力な魔術師が、あるいはサーヴァントが侵入したのだとしたら。
(桜ちゃんが危ない――)
「アサシン、俺は家に入る、この場は――」
「了解した」
無論、トキとて気がかりではあった。
しかしここは他ならぬ雁夜自身の家。地の利はあるはずだろう。
内部の気配までは結界ゆえか探ることはできないが、マスターしかいないのであれば令呪を使う隙くらいはあるはずだろう。
返事を待たず、体を引きずるように家に向かう雁夜。
当然入らせるわけにはいかない。足止めをしようとキャスターはそちらを向く。
だがそちらに意識を向けた一瞬でトキは目の前に迫った。
手刀を突き出すトキの目の前で、キャスターは瞬時に両手を重ね合わせた後手刀の前に突き出した。
流石のトキも警戒心から手刀を止め、後ろに下がった。
手を重ね合わせた瞬間走った赤い魔力の奔流をトキは見逃していない。
キャスターは知略に長けたサーヴァント。警戒しすぎているということはないはずだ。
そもそもキャスターが前線に出ているという点からして不自然なのだから。
一方でキャスターも少なからず焦りはあった。
目の前の男は接近戦において無類の強さの持ち主だ。
加えてどうしたことかこの邸に張られていたはずの結界が機能していない。
別に通しても私見では何の問題もないのだが、門番という役割の手前、一応全力を尽くしているようには見せなければいけない。
だがこのサーヴァント、油断ができるはずもない。
「ふん、苦戦しているようだな」
と、にらみ合う2人の元にあるサーヴァントが実体化する。
その顔を見た時、トキは自身の表情が変わるのを抑えられなかった。
「どうしましたかライダー、自分のマスターに命令でもされましたか?」
「その男はお前の手には余る。俺が相手をしよう」
「あなたはそれで大丈夫なのですか?」
「それで死ぬようなら、あの小僧もそこまでよ」
「…分かりました」
静かにキャスターは消え去り、場には男が2人。
この場において、彼等2人の関係を知っているものはいなかった。この当事者を除いて。
場には静かに闘気が渦巻いている。
「……」
「……」
ライダー、ラオウの視線にもアサシン、トキは怯む気配すら見せず、逆に鋭い視線を返す。
元より2人はサーヴァント。生前の己の想いはどうあれ、戦うしかない宿命。
ゆえに今更交わす言葉などない。
ただ一言。
「あなたは…、この聖杯戦争に何を望む?」
その問いかけに対し、ラオウはただ一言、こう返した。
「 天 !」
もはやこれ以上の言葉は不要だった。
ここにトキとラオウ、2人の宿命の対決が再現された。
◆
「くそ、ライダーのやつ僕の指示も待たずに!!」
「しかしあのサーヴァント、私では相手をすることができないほどには強敵のようでした。
彼のことはライダーに任せては?この家にマスターの方は侵入してしまったようですし」
「何…?!何やってんだよお前!!
ああクソ、僕たちはそっちに向かうぞ!バーサーカー、来い!!」
◆
全身の痛みももはや気にならない。気にしている暇などない。
今はそんなどころではない。
もしこの家に魔術師が侵入したというのなら、桜ちゃんが危ない。
一刻も早くあの蟲蔵に行って無事を確かめなければいけない。
もし、今彼女まで失ったら、俺は―――
「おい、待てよ」
歩いていたのはあの工房に繋がる道中の廊下。
あの少女のことばかり考えていたせいか、その存在には声をかけられるまで気付かなかった。
「お前、人んちで何してんだよ?」
「…っ、お前が、魔術師か?」
目の前にいたのは特徴的な髪型の、高校生くらいの少年。
初めて見たはずなのになぜかどこかであったことがあるような気がしてきた。
その後ろには先ほど見た白いコートのサーヴァント、そして、黒い鎧と霧を纏ったサーヴァント。
一人は言うまでもない、かつてサーヴァントとして従えたバーサーカーだ。
バーサーカーがいたという事実にはそこまで驚きはしなかったが、複数のサーヴァントを連れているということには驚かされた。
つまり、外のアサシンが相手をしているであろう相手も加えれば、少なくとも三体のサーヴァントを従えているということなのだから。
「仮にも間桐の家に堂々と入り込むなんて、いい度胸してるよなぁ?」
「はぁ…はぁ…、桜ちゃんはどうした?この家で何をしていた?」
「桜?あいつがここにいるわけねえだろ。あんたこそ誰なんだよ」
「俺は…、間桐雁夜、間桐の魔術師だ」
「雁夜…、おじさん?」
「え、まさか、…慎二君か…?」
面識がないわけではなかった。
雁夜自身その存在は知っていたし、慎二にも記憶におじさんという存在は残っている。
だが、だからこそそこまでの仲というわけではない。昔話に花を咲かせるような関係でもない。
しかし疑問は生まれてくるものである。
「あ、あれ、でも慎二君は…、え…?」
「おい、キャスター、お前何か知ってるだろ。答えろ」
「…ここが電脳空間であることはすでに聞いていると思うのですが。
どうやら平行世界へのアクセスも可能だったようですね」
その言葉の意味を悟るのは慎二の方が早かった。
いや、雁夜が何も知らなさすぎたというところだろう。
「電脳…世界?何を言ってるんだ?」
「あんた自分のサーヴァントから聞かなかったのかよ。ここはな、現実じゃない。僕達はバーチャル世界のデータなんだってさ」
「は…?どういうことだ…?」
「あんたは過去から、僕はあんたより未来から来たってことだよ」
「み…らい…」
「分かんないかな?たぶん最後におじさんと会ってから10年以上は経ってると思うんだよね」
慎二の話している意味は、意味は分かるが理解することはできない。
しかし、その言葉で一つの可能性に気付いた。
あの時の葵さんに似た、遠坂凛の存在。
待て、だとしたら―――と、あることに思い当たった。
「んだよ…、間桐にも魔術師いたんじゃないか…」
(何で僕じゃなかったんだよ)
「ちっ、まあいいや。あんたも間桐の人間なら分かるよな?この戦いの重要性をさ。
僕達に手を貸せよ」
頼む様子でもなく上から目線でそう命令する慎二。しかしそれに怯む様子もなく、雁夜はある一つの質問を問う。
今の彼にとっては戦う理由である、全てのものについて。
「…一つだけ聞かせてくれ。桜ちゃんは、どうなったんだ?」
だが、ある意味その質問をした時点で、彼等の決裂は必然だったのだろう。
「……あぁ?」
慎二の顔が露骨に不機嫌そうに歪む。
それまではまだ口調は悪くも愛想笑いくらいはしていた表情。
しかし今の表情は嫌悪感をはっきりと表し、雁夜を見る視線も見下しきったものになっている。
「あんたもか。あんたもかよ。そうかい。
みんなして桜桜桜桜!あいつのことばっかり!!
じいさんも衛宮のやつも!僕に魔術の才能がないからってあいつばっかり!」
「し…慎二君…?」
「ああ、桜のことだったか?
元気だよ。今も元気に――――――じいさんに魔術習っているよ」
「―――!」
頭の中が真っ白になった。
その発言は、慎二にとっては事実だろう。魔術師そのものに対して大きな劣等感を持っている彼にとっては。
だが、雁夜にとっては違う。間桐の魔術は自身がおぞましいと感じ、魔術から背を向けるほどに醜悪なものであると考えていた。
あの慎二が大きくなるような月日が経っても、今だにあの蟲倉の中から出られていない。その意味を、身を持って知っている。
そんな感情に気付く間もなく、苛立ちが残る慎二はさらにこんな言葉を投げかける。
今更あのような存在を思い出さされた苛立ちを、優越を言葉にすることで解消しようとした。
「あーあ、ちょっと魔術が使えるからって自分の方が優れてるとか勘違いして生意気なんだよあいつは。
僕のこと魔術が使えないって見下しやがって。他のことは何もできないくせにさぁ」
間桐慎二には魔術師、そして妹である桜に対して大きな劣等感を持っていた。
それもあの日、ライダー(メデューサ)のマスターになった日にはある程度解消はされた。
しかし友人、衛宮士郎や憧れであった遠坂凛にも相手にされず、結局ライダーは敗北。自身もバーサーカーの手で命を落とした。
だが今の自分は違う。あいつより強力なサーヴァントを得て支配下におき、さらに2人のサーヴァントをも御し得たのだ。
なのに目の前の男、おじさんも自分のことなど見ていない。気にしているのは桜なのだ。
その嫉妬は、劣等感は冷静さを鈍らせ、己の力の誇示をするためだけに言葉を口走らせる。
その苛立ちの言葉を受け取っているのは、他ならぬ間桐雁夜。
桜に対する罵倒を受けて、彼が冷静でいられるはずもない。
そして――
「だから教えてやったんだよ!あいつの地位を、を、その体にな!!絶対僕に逆らえないように!」
「――――――――――――」
その言葉の意味が分からないほど、雁夜も愚かではなかった。
パリッ
そして理解した瞬間、雁夜の中で何かが壊れた。
彼の中にあった、笑顔を浮かべる少女の顔が、音を立てて割れた。
「き―――――貴っ様ああああぁぁぁぁ!!!」
激昂と憎しみの爆発。
それは体の痛み、苦しみすらも忘れさせ、一瞬で、一斉に刻印蟲を羽化させた。
普通の家と比べて広いとはいえそこまで開けた場所とはいえない間桐邸の廊下で羽音を鳴らす蟲たち。
それを前にして慎二は、
「はん、もういい。あんたウザいよ」
取り乱すこともなく、しかし不快感は露にキャスターに命じた。
「やれ」
◆
振りぬかれた拳は宙を舞う。
何も捕らえなかったはずのそれはただの風圧で離れた場所にある石造りの塀に亀裂を入れた。
それほどの拳圧にも怯むこともなく避けた、狙われた相手は目にも止まらぬ手刀を一瞬で5発体に打ち込む。
しかしそれも大した効果を示すこともない。むしろ避ける必要などないと言わんばかりに不動の態勢を保ち続ける。
そう、まさにお前の拳は全て知り尽くしているとでも言っているように。
「ぬうッ!!」
「はああああああ!!」
再び振られたラオウの拳。しかしそれがトキを捕らえることは無く、地面にめり込みラオウの動きをとめる。
そしてそのまま背後を――取らずにラオウの胸に拳を打ち付ける。
今度の一撃は先ほど以上の効き目をもたらす。
が、トキは直後に後ろに飛び退いた。
避けたとはいえ莫大な拳圧はトキの体に大きな負担をかけていた。
もしここで背後を取っていればこのダメージはなかっただろう。しかしトキは、ラオウが背後を取られた対応の技を持っていることを知っていた。それにより生前不覚をとったこともある。
だからこそ肉を斬らせて骨を絶つ覚悟でその一撃を放った。
しかし、
(まだ、浅いか…)
それでも膝をつくことなく態勢を立て直すラオウ。
剛の拳と柔の拳。2人のもつ相反する拳。
筋力を上げるスキル、高い筋力も受け止めるスキル。
単体であれば強力な力であったろうこれらは、互いにぶつかり合ったことでその長所を打ち消しあっていた。
故に2人の戦闘は単純な技術、力量での戦いとなっていた。
しかしその戦闘能力はほぼ互角。互いの宝具も知り尽くしている。だからこそラオウは黒王号を呼ぶことはできない。
長期戦になるのは必須。だがそうなってしまうと不利なのはトキのほうである。
(この体、果たしていつまで持つか)
病に蝕まれた体。それはこうしてサーヴァントとなったトキの体にも影響を与えていた。
もしこの場で倒れたのであれば、それは生前の再現でしかない。
あの時と違う攻撃を放っても結果はそう変わりはしない。
ラオウとトキ。
この兄弟が共に間桐の血を持つものに呼ばれ、その間桐邸においてこうしてあいまみえている。それは何の因果であろうか。
あるいはこうなることは、彼等が同じ血の人間に召喚されたときには既に決まっていた運命であるとでもいうのだろうか。
しかしその戦いも生前と全く同じものにはなりはしない。
今の彼等はサーヴァントであるのだから。
つまりマスターとの関係は切っても切れぬもの。
「む…」
そのまま戦闘を再開しようとしたトキの動きが止まった。
そしてその姿がすぐさま掻き消えた。霊体化するかのように瞬時に消える魔力、しかし決して霊体化ではないその現象。
ラオウは目を見張る。
「ぬぅ…!?もしや…!!!」
この場でトキが姿を消す理由。
それに気付いたラオウはすぐさま霊体化して自身もトキの向かったであろう方に急いだ。
◆
「はん、いきがっておきながらそんなものかよ!」
「が…ぁ…」
それはきっと愚策ともいえるものだっただろう。
例え間桐慎二が魔術師としては失格といえるほどに魔術の行使ができない男であっても。
その近くにサーヴァントがいたなら十分な脅威となりえる。
大量の蟲を一斉に放った雁夜であったが、それは慎二を怯ませることもできていなかった。
元より”これ”を、慎二はずっと見てきたのだ。今更恐れるに足るものではない。
そして、キャスターへの指示の元、一瞬でそれらを焼き払った。
廊下の壁の一角を錬成し、瞬時に爆発。刻印蟲どころかその先にいる雁夜の体すらも爆風に巻き込んだのだった。
「ちっ、こんなやつに魔術回路なんかあるんじゃ、そりゃ間桐の家も衰退もするだろうな!
それじゃあさ、死にたくなかったらその令呪、こっちに渡してもらおうか」
「が…、こ、と…わる…!」
「そうかい。キャスター、あれをやれ」
命令と共にキャスターが雁夜の体に触れる。
次の瞬間、雁夜の右手が爆音と共に吹き飛んだ。
まるでそこに爆弾でも仕掛けられたかのように。
「ぐああああああああ!!!!」
「ふん、聞かないようだったらこいつを死なない程度に痛めつけておけ」
「はいはい」
もはや悲鳴すら出せずに体を痙攣させる雁夜。
確かに、この瞬間までは間桐慎二の絶対的優位は揺るがなかった。
それにその策自体はそう間違ったものではない。
問題は、この策を過信しすぎたこと。
一般人でしかない小鳩、生存の呪縛に囚われたスザク。彼等相手であればこの策は有用なものであった。
雁夜は魔術師でこそなかった。しかし雁夜には雁夜なりに命を掛ける度胸があった。
大切なもののために残りの命を1ヶ月までに縮めるほどには。
慎二自身侮っていたところもあった。この程度の男が魔術師であったということを馬鹿にするほどに。
もしここで殺しておけばそうはならなかったかもしれない。
令呪が光る瞬間、屈したと判断しなければ。
「令呪を、持って…命ずる…!!」
もう一つ不運があった。
もし雁夜のサーヴァントがアサシンでなければ。あるいは俊敏がもう少し低ければ。
確率は低いがそれを避けることは、あるいはできたかもしれない。
「アサシン―――こいつらを殺せええええ!!!」
まだ、慎二にはバーサーカーという駒が残っていた。
そしてここは自分の家、自分の領域。地の利はこちらにあると考えていた。
今回の事態、勝手な行動に走るラオウや侵入者、間桐雁夜への対応というイレギュラーなことに若干振り回されたというのもある程度は事実。
それでもまだ挽回自体は可能であるはずだった。
「ば、バーサーカー!僕を守れ――」
「北斗―――有情断迅拳」
しかし今回ばかりは運が悪かった。
令呪発動を聞いたと同時、すぐ傍にいたバーサーカーに指示を出そうとし、しかし言い終わる前に、何かが慎二の近くを通り過ぎた。
命令を断片であれ聞き届けたバーサーカーは、アサシンに並ぶその俊敏性を生かしてどうにか慎二の傍に腕を組んで飛び出した。
彼が現れた場所から離れた位置にいたキャスターには視認の後反応する猶予があった。
それが届く直前には、背後にあった壁が無くなった部屋の一室に飛び込んでいた。
気がつけば雁夜の目の前まで移動していたアサシン――トキ。
北斗有情断迅拳。それはトキがかつてとある大軍団を相手に放った北斗神拳の奥義。
相手が対魔力を備えていなければ、例え何百という軍勢であろうと、一瞬で殺しうるであろう技。
強敵相手には決め手に欠けるが、そうでない相手には少ない隙で膨大な数を倒しうる、宝具として昇華されたトキの拳。
「?!」
次の瞬間、バーサーカーの腕とわき腹が弾けた。
狂化していようと痛みは感じるはずにも関わらず、当惑するかのようにおかしな動きをとり続ける。
まるでそれに快感を感じているとでも言わんばかりに。
そして、守ったはずの慎二に対しても、その余波は届いてしまっていた。
「ぎゃああ!何これ!腕が!腕があ!うわ、しかも何かすごい気持ちいいんだけど!
うあああ!何だよ!何だよこれぇ!!」
腕だけではない。足も関節とは逆方向に曲がり、頭も少しずつ膨れている。もう数秒もあれば弾けるだろう。
慎二自身、体の異常には気付いており、その身に近づく死の気配も感じ取っていた。にも関わらず、苦痛を感じず、逆に体は快感に包まれ始めている。
あまりに不自然で得体のしれない感覚と近づく死への恐怖から、股間を濡らす慎二。
だが、それでも慎二はまだ運に見放されてはいなかった。
「間に合ったか」
突如その背後に現れた、慎二自身のサーヴァント、ライダーが慎二の体を数箇所、その太い指で突いた。
電流が流れるような感覚と共に、慎二は体に魔力を送り込まれるのを感じた。
それと同時に快感と体の膨れは止まる。
元々彼等は同じ北斗神拳の使い手。加えてサーヴァントとしてのスキルランクはこちらのほうが上。
秘孔を突かれた者への対処など造作もなかった。
「しばらく安静にしていろ。それで元に戻る。
マスター狙いに移行するか。アサシンとはいえそこまで堕ちたかトキよ!」
何も言わず、トキは雁夜の体を突き、腕の出血を止める。
そして一秒と待たせず動けぬ慎二の元へ向かおうとする。が、それを許すラオウではない。
「そんなにそのようなマスターに従うか!ならば良かろう!小僧を殺したくば、この俺を倒してからにせい!」
剛拳が唸り、風が巻き起こる。その勢いは、崩れた壁に積まれた瓦礫を宙に吹き上げ、粉塵を巻き起こす。
それを避けたトキは、ラオウへの攻撃に移ろうとし、しかし壁を赤い魔力が走ったのを確認した瞬間全身から闘気を放出、粉塵を吹き飛ばす。
しかしその衝撃に屋敷の廊下は耐え切れず崩壊。ラオウと共に下の階に落ちる。
「キャスター!余計なことをするな!貴様はその小僧を守っていろ!!」
ラオウがキャスターに指示を出せば、令呪の効果で逆らうことができない。
そもそも手出し以前にキャスターのことだ。機会があれば背後から、などということも十分にあり得る。だから釘を刺しておいたのだ。
「やれやれ…」
ライダーとアサシンのいなくなった廊下に、ドアを開けて出るキャスター。
守れと言われた以上守らなければステータス低下は免れない。
何しろ爆発させたはずの蟲がそこにはまた大量に沸いているのだから。
慎二に噛み付こうとするその内の一体を踏みつけ、再び空気に対して錬成を行う。
可燃性ガスとなった周囲の気体は、ほんの小さな火花で爆発を起こすほどのものとなっている。
飛び立った蟲は一斉に爆発、気味の悪い音を発しながら地面に燃え落ちていく。
「む…?」
「な、おい、おじさんはどこ行ったんだよ?!」
そうして煙の収まった先には、誰もいなかった。
本来であればそこで倒れ付しているはずの男がいなくなっているのだ。
殺されかけたという動揺から立ち直った慎二は、怒りを露にキャスターとバーサーカーを怒鳴りつける。
「お前ら何逃がしてくれてんだよ!!あんな死にかけのマスター一人仕留めることもできないのか!?」
「アサシンの乱入さえなければよかったのですがね」
「くそ!バーサーカー!奴を探して殺せ!!」
「■■…、…■■…!」
腕から血を流しつつも、どうにか起き上がることには成功したバーサーカー。
よろよろと立ち上がり、態勢を立て直すと同時に屋敷を駆け回り始めた。
「くそ…、くそ…!畜生!!
ふざけるなよ…!!クソォォォォォォ!!」
近くにいるキャスターの存在も忘れて声を上げる慎二。
一度うまくいかなかったからといって、その程度のことであればここまでみっともなく叫んだりはしなかっただろう。
ただ、相手が悪かっただけの話。
相手の魔術師が間桐であったこと。桜の名前をここで聞くはめになったこと。一瞬でも死の淵に追いやられかけたこと。
そして何より、間桐慎二という存在を歯牙にも掛けていないと(少なくとも本人はそう)感じたこと。
どれか一つでも欠けていれば、ここまで激昂はしなかっただろう。
ただ、よく似ていながら全く反対の存在であった、近い血を分けたもの。それが圧倒的に相性が悪かっただけの話。
◆
そして、そういう意味では今のラオウも同じ状態であったといわざるを得ないだろう。
家としては広大であるが、空間としてはあまり広大とはいえない間桐邸。
そこで戦っているのは、北斗神拳を競った兄弟。屋敷内が無事で済む保障など無い。
ラオウの右腕から放たれた闘気は家に置かれた壁を破壊し、トキの体から放出される闘気は床に亀裂を生む。
しかしそんな事実にも、トキは元よりラオウすら気にすることなく戦っている。
限られた空間。それは機動力を生かすトキと巨体から生み出す破壊力を持って攻めるラオウではどこかしら不利になる要素である。
しかし彼等はそれをものともせず戦っている。室内での戦闘などをハンデとするようでは北斗神拳伝承者候補になどなることはできない。
「フ、相も変わらず見事なこなしよ。あの時に勝るとも劣らぬほどに拳は研ぎ澄まされておるわ」
「……」
こうして会話している間も、互いの間には闘気が渦巻き、一瞬の気を抜くことすら許される状況ではない。
「だからこそ解せぬ。貴様のように北斗神拳にも己の生にも野望にも拘ることをしなかった者が、今更何を聖杯に願うというのだ?」
「あなたがそれを問うか。では逆に聞かせてもらう。なぜあなたはあれを使わない?」
恐らくそれが人間であるトキであれば知ることは無かっただろう。
しかし今の彼は、英霊の座より召喚されたサーヴァント。だからこそある事実を知っていた。
ラオウが、戦いの果てに哀しみを背負い無想転生を習得したということを。
北斗神拳2000年の歴史の中でも、これを習得し得た伝承者はほとんどいない。増してや伝承者でも無いものが習得するとなれば。
それは宝具として昇華し得るほどのものであるはずだ。
なのに、ラオウは今まで一度もそれを使っていない。もし使っていれば、トキを一蹴することなど造作もないだろうに。
「そのような事。俺は天を握る男。常に宝具に頼って戦うなど、そのようなマネができるものか。
お前を無想転生抜きで倒すことができずして、どうして聖杯に辿り着けよう」
トキは知らないことであったが、実はこの無想転生には膨大な魔力消費が掛かる。
いかなる攻撃も回避し、逆に相手には回避不能の一撃を加えるもの。もしこれを回避できるとすれば、それは同じ無想転生を習得したものだけだろう。
だからこそだろうか。これを使用するのはここ一番という相手でなければならない。増してや今のマスターは魔術回路を持たない者なのだから。
そうでなくてもトキの技を受けて負傷している者からさらに魔力を供給させるとあまりに負担が大きい。計らずもトキはラオウの最強宝具の使用を躊躇わせる一因を作ったことになる。
ラオウの言葉の中にはそのような含みは無い。だが、それが本心なのか、あるいはその事実を悟らせないための虚構か、あるいは両方であるかはラオウにすら分かっていない。
「そうか。しかしこちらは手加減などせぬぞ」
「構うな、存分に掛かってこい。トキ!」
その言葉と共に、二人の戦いは激しさを増して再会された。
|NEXT|
|[[DECIDE THE FATE(後編)]]|
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: