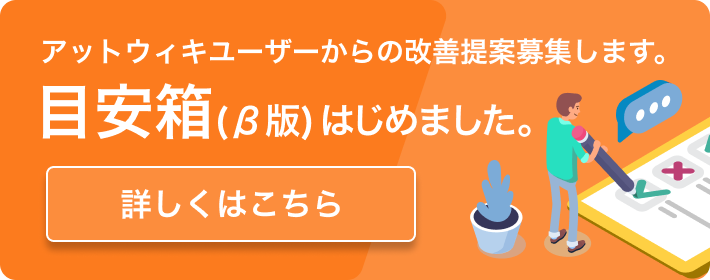「FINAL DEAD LANCER(前編)」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「FINAL DEAD LANCER(前編)」(2014/02/21 (金) 21:56:22) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
「…………………」
金田一には今、自分の目の前に広がる光景が信じられなかった。
否、信じたくなかった。
目を凝らし、もう一度だけ確認する。
だが、現実は何ひとつ変わらない。
「………なんてこった」
まるで数年前に二週間だけ過ごした田舎の村の懐かしい旧友に会いに行った矢先に、その村で起こった連続殺人事件の犯人が旧友の一人だったかのようなやるせない表情で呟いた。
「肉が、無い……」
由緒正しい寺の冷蔵庫に肉類など入っている筈がない。
それが、金田一が直面している(少なくとも本人にとっては)極めて切実な問題だった。
「そりゃあおぬし、寺に肉などあるわけなかろう。
というか一晩ぐらい我慢できんのか?」
ライダーの痛烈なツッコミに項垂れる金田一。
彼は食べ盛りの高校生。腹持ちの良くない和菓子だけで一晩過ごすなどとてもではないが出来ることではなかった。
「だってしょうがないだろ?腹が減っては戦は出来ぬって言うじゃんか。
ここ、米とか野菜ばっかりでカップ麺すら無いんだぜ?いや、何でか酒はあったけど」
「それがさっきわしが持ってきた和菓子を全部平らげた奴の言う事か。
おぬしの辞書にペース配分という言葉はないんかい!」
再び項垂れる金田一。ぐぅの音も出ない。
と、そこで何かを思い出したように顔を上げた。
「そうだ、なあライダー。さっきポケットにカードみたいなのが入ってたんだよ。
俺、ポケットにそんなの入れた覚えがないんだけど、何か分からないか?」
「おお、それは参加者全員に配布されているクレジットカードだ。
限度額は無いから残金を気にする必要はないぞ」
「えっ、マジで!?じゃあこのカードがあれば、高級寿司も焼肉も食べ放題ってこと!?」
「おぬし……いくらなんでも発想が貧困すぎるぞ…」
冷めた視線を送るライダーを他所に、金田一は両手でカードを持ちながらクルクルと小躍りしていた。
「それでおぬし、何か妙案は浮かんだのか?」
「ああ、その事なんだけどさ、ライダー。
お前、さっき魔術師とか超常の力を持ったマスターがいるみたいなこと言ってたけど、あれってどういう意味なんだ?」
金田一の疑問に、ライダーは表情を険しくしながら答えた。
「……うむ、それについてはちと話が長くなる。場所を移そう」
ライダーの神妙な表情から、この話がただ事ではないと悟った金田一は、何も言わずにライダーの後について台所を後にした。
「魔術師というのは、まあ一言で言ってしまえばおぬしのような一般人にとっては傍迷惑極まりない連中のことだ」
開口一番、ライダーは魔術師をバッサリと切るような、身も蓋もない事を口にした。
それから、ライダーはおおまかな魔術師の概要を語り始めた。
「魔術師とは、“根源”、いわばアカシックレコードに到達するために魔術を研究する者たちの事を指す。
そして、魔術とは魔力を用いて人為的に神秘や奇跡を起こす術全般のことをいう。
まあ、実際のところはもっと複雑なのだが、今覚えておくべきことは、個人差こそあれ魔術師は一般人とは隔絶した能力を持っていることと、根源へと至る手段として聖杯を狙う魔術師が参加している可能性が高いことだ」
「ちょっと良いか?さっきから魔術とか魔術師って言ってるけど、それってつまり魔法みたいなものなんじゃないのか?」
金田一の質問に、ライダーは頷きながら答えた。
「良い質問だ。魔術と魔法には大きな違いがある。
それは、文明の力で再現できるかどうかだ。他の技術で再現できるものは魔術と呼ばれ、逆に再現できないものが魔法とされる。
例えば、火や風を操るとか、空を飛ぶ術は魔術に分類され、時間を操作したり、魂を物質化する術は魔法にあたる、という具合にな」
ちなみに、ライダーが生きた時代には、封神台と呼ばれる一定以上のランクの人物の魂を封じ込める、第三魔法を体現したような装置が存在していたりする。
「それと、ここからが重要なのだが、魔術師という人種は根源へと到達するためなら手段を選ばぬ。それこそ、親族や師弟などの身内を除いたあらゆる者を犠牲にすることさえ厭わぬだろう。
しかも質の悪い事に、魔術師は往々にして社会の裏に潜み、法の裁きを逃れておる。
魔術師の総本山ともいえる魔術協会も、神秘、つまり魔術の秘匿を最優先とし、魔術師たちの行為を黙認している」
「な、何だよそれ……!警察じゃあ捕まえられないのかよ!?」
憤慨する金田一から視線は逸らさず、ライダーは首を横に振った。
「無理だ。彼奴等は魔術を駆使してその存在や痕跡を悉く隠蔽する上に、代を重ねた魔術師の家の多くは表の世界に対して影響力を持つ。
仮に魔術の存在や魔術師の所業を告発しようとする者がいたとしても、協会は刺客を差し向けて始末する。はっきりと言ってしまえば、この聖杯戦争で彼奴等に現代日本の倫理や常識などというものは微塵も期待できん。
故に、心するのだ金田一よ。おぬしがこれから相対するのは、そういった手段を選ばぬ連中なのだからな」
強く言い聞かせるような口調のライダーに、金田一も思わず勢いよく首を縦に振る。
実際のところ、ライダーの説明には彼自身の魔術師に対する嫌悪感がにじみ出た、やや偏向された部分があるのだが、これは彼の生前の戦いに起因する。
太公望が生きた時代は、殷王朝に巣食う皇后・蘇 妲己と、その配下である妖怪仙人らに代表される力を持つ者が、無力な人間を食い物にするというある種の弱肉強食といえる時代だった。
そして、太公望(幼名は呂望という)もまた、幼少の頃、妲己の発案によって行われた大規模な人狩りによって生まれ育った村を、一族を皆殺しにされた。偶然その場から離れていたために難を逃れた彼が自分の村だった場所に戻ってきた時、瀕死の老人と出会った。
憎しみを募らせる彼に、老人はこう語った。
“憎いですか?呂望様、復讐をしたいですか?
おやめなさい、やるだけ無駄な事なのですから………”
その声には、どうしようもない諦観があった。そういう時代だったのだ。
“世の中全体がこうなのです…全てを変えないと…いつまでも…こんな事が…続……”
そう言って、老人は息を引き取った。
それが、呂望という名の少年の終わりであり、太公望という英雄の始まりだった。
この後、呂望は仙人界のひとつ、崑崙山の教主である元始天尊に才を見出され、彼の弟子となり、太公望という名を授かった。そしていつしか、太公望はある理想を思い描くようになった。
―――わしは仙道のおらぬ安全な人間界をつくろう
強大な力を持つ仙人によって、普通の人々が脅かされる事のない世界にする。
その志を胸に、太公望は師である元始天尊から与えられた任務、封神計画を遂行していくこととなる。
そのような経緯から、太公望は普通の人間を蔑ろにする魔術師を快く思っていなかった。(それでも例外を認めないというほどではないが)
また、少々お人好しすぎるきらいのある金田一に警戒心を持たせる必要があったという事情もある。
当の金田一も、納得はできないなりにどうにか事実を咀嚼しようとしていたが、事態は彼に深く考える時間を与えてはくれなかった。
「御主人!」
偵察のために円蔵山の周辺を飛んでいた四不象が慌てた様子でやって来た。
「こっちにマスターとサーヴァントが向かってきてるっス!しかも二組っス!」
それを聞いたライダーは一瞬驚いた表情を浮かべたものの、すぐに考え込むような様子を見せ、数十秒ほど経ってから結論を出した。
「よし、そやつらに会ってみよう。こんな短時間のうちに他人と協力するマスターならば、殺し合いに乗っていない可能性もある。
そうでなくとも、ある程度の慎重さは持ち合わせているだろう。金田一、おぬしも来るか?」
恐らく、ライダーは自分の覚悟を問うているのだろう。
そう悟った金田一は、強く頷いてライダーと共に四不象に跨った。
事態が大きく動こうとしていた。
「……おい」
「どうした?別についてこなくとも俺は一向に構わないぞ?
それとも、ボディーガードでもしてくれるのか?」
「そんなわけあるか!お前が何するかわからないから、こうして見張ってるだけだ!」
衛宮士郎とルルーシュ・ヴィ・ブリタニア、そして二人のセイバー。
彼らは深山町の住宅街を通って、柳洞寺へと向かっていた。
先ほどの(険悪な)初対面の時に行なった情報交換で、士郎が「前回の聖杯戦争で、柳洞寺の地下の大聖杯を破壊した」という言葉が根拠である。
勿論この聖杯戦争の舞台がムーンセルである以上、そこに聖杯が存在するなどとはルルーシュも考えていないが、それでも何かしらの手掛かりを掴める可能性はある。というより、他にアテもないので柳洞寺に向かうしかないのが実情ではあるのだが。
その他、士郎から聞かされた魔術師なるものの存在や、かの騎士王が女性であったという衝撃の事実を頭の中で整理しながら、士郎に問いかける。
「それで?俺の話は信じる気になったか、衛宮士郎」
露悪的な態度を崩さないルルーシュにムッとしながらも、士郎もまた自身の見解を述べた。
「確かに、言われてみれば街っていうか、人が変な感じはする。
けど、ムーンセルだの量子空間なんてのを信じるかどうかっていうのとは、話が別だ」
先ほど、士郎もまたルルーシュからムーンセルに関する情報を聞かされたが、今のところは半信半疑だった。冬木市の住人である士郎からすれば、今自分がいる場所がバーチャル空間の類だなどと言われてすぐに納得できるわけがない。まだ固有結界の産物やアンリ・マユの仕業とでも言われた方が信じられるぐらいだ。
どうにも生気を感じにくい奇妙な通行人たちの存在が無ければ、今頃はただの虚言だと完全に切って捨てていただろう。
「大体、それが本当なら何でセイバーはムーンセルの事を何も知らないんだよ。
サーヴァントには聖杯から必要な知識が与えられるはずじゃないか」
「それは俺にもまだわからん。まさか正確な情報を与えられていないサーヴァントがいるなど予想外だったからな。それよりもあれを見ろ」
ルルーシュが指したその場所には、倒れた電柱や破砕されたコンクリートやブロックの欠片が散乱していた。気の早い参加者が既に一戦交えた跡だと想像するのは容易い事だった。
だがその直後、ルルーシュや士郎が目を疑う事が起こった。
散々に破壊された道路や電柱がひとりでに、まるで時を巻き戻すかのように修復されはじめたのだ。
「……おい、衛宮士郎。魔術師というのはこんな芸当もできるのか?」
「……いや、俺の知ってる魔術師でも遠隔でこんな真似するのは多分無理だ」
半ば唖然とした様子の二人の傍に、ガウェインが歩み寄ってきた。
「ムーンセルの修復機構が働いたようですね。見ての通り、今回の聖杯戦争ではマスターやサーヴァントによる一定以上の器物の破壊については、ムーンセルが自動で修復を行うシステムになっています」
「……だそうだ。これで信じる気になったか?」
内心の動揺をおくびにも出さずに再度問うルルーシュに、士郎はまだ複雑そうな面持ちではあったものの、静かに頷いた。
ルルーシュが今後どう行動するかはわからないが、ここまでの言動を鑑みるに積極的に殺し合いに乗ることはなさそうだ。柳洞寺を調べ終わったら、お互い別行動をとるのも手だろう。
そう考え、しばらく歩いているうちに、柳洞寺の手前に到着した。
すると、セイバーが私服姿から鎧姿になり、士郎たちよりも一歩前へ出た。
「シロウ、中からサーヴァントの気配がします。既にここに陣取っていたようです」
「やっぱりキャスターか?」
「いえ、神殿や魔術工房が敷設されている様子はありません。もしそうなら、この付近は既に異界同然と化しているはずですから」
セイバーの言葉に幾分安堵する。何しろ前回の聖杯戦争では、すぐに脱落したとはいえキャスターが柳洞寺に神殿を作り、街の人々から魔力を奪っていたのだから。
「よし、じゃあ慎重に進んで行こう。けど、こっちから先に仕掛けるのはなしだ。
……お前もだぞ、ルルーシュ」
「ふん、そういうことは自分のサーヴァントにでも言い聞かせた方が良いんじゃないか?
それに、向こうから仕掛けてきた時は貴様が止めても勝手に応戦させてもらうぞ」
相変わらずのルルーシュの態度だが、士郎は敢えて反論はしなかった。セイバーの突撃癖は自身がよく知っているからだ。それに、士郎とてただの平和主義者ではない。無防備な状態で敵マスターと相対する事がどれだけ危険かは身をもって知っている。
「ああ、そうなったらこっちも戦うさ。俺だって、こんなところで死ぬわけにいかないからな」
「ふむ、気合の入っているところ悪いが、生憎わしらは戦う気はないぞ?」
どこかから聞こえた声に全員が周囲の様子を窺う。
「上です!」
セイバーの声に全員が上を向く。第四次聖杯戦争を経験しているセイバーだからこそ、相手が空中にいる可能性に最も早く気付く事ができた。
そこにいたのは、カバのような奇妙な生き物に乗ったサーヴァントらしき少年と、学生服(何故か夏服のようだが)を着た高校生ぐらいの少年だった。
「ライダーのサーヴァント、ですね?」
「いかにも。そう言うおぬしらはセイバー、それも鎧の意匠からして同郷の出身と見るが?」
ライダーの問いに、セイバーとガウェインは無言で返す。一分ほどの沈黙の後、場を代表してルルーシュが口を開いた。
「戦う気は無いと言ったな。それは貴様のマスターの意思か?」
「うむ、その通りだ。わしらはこの聖杯戦争を打破することを考えておる。
そこで率直に言うが、わしらと同盟を組んではくれぬか?おぬしらはどうも殺し合いに乗っているとは思えぬのでな」
ライダーの提案に、士郎もルルーシュも暫し考え込む。
元々、自分達も殺し合いに乗っているわけではない。仮にこの提案が罠であったとしても、最優のサーヴァントたるセイバーが二騎がかりであれば容易に切り抜けられるだろう。それはそれでサーヴァント同士の戦闘を直接見る良い機会になる。士郎はそこまで打算的な考えではないが、用心のためにいつでも魔術回路を起動できるようにしている。
だが、返事を返す前に言わなければならない事があった。
「なあ、同盟を組むってのは良いんだけどさ、その前にお前のマスターを下に降ろしてやった方が良いんじゃないか?」
士郎に言われて後ろを振り向くと、金田一が顔を真っ青にしながらガクガクと震えていた。
「ラ、ラ、ライダー、無理、もう無理。お、降ろして……」
「おぬし、高所恐怖症なら早く言わんかい!」
「い、いや、高所恐怖症じゃなくても無理だって!尻尾の先っちょあたりしかケツ引っ掛けられるとこ無いじゃんか!ちょ、頼むからもう勘弁してくれ!」
「ギャー!!痛いっス!暴れないでっスよ金田一くん!」
「ああっ!揺らすでない!バランスが取れぬではないか!!」
いきなりコント(本人達にとっては切実だが)を始めたライダー主従を、四人は何ともいえない気持ちで見つめていた。というか騎乗スキルが全く仕事をしていないのはどういう事なのだろう。
「ヘルプミー!!」
ライダーの絶叫が虚しく響き渡り、場にはどこか弛緩した空気が流れていた。
「ひ、ひどい目に遭った……」
「まあ……その、何だ、大丈夫か?」
数分後、どうにか態勢を立て直して無事地面に着地したライダーらは、寺に入って自己紹介をしようとしたが、現在はその予定を変更して山中の獣道、というより絶壁に近い地形を進んでいた。士郎から、前回の聖杯戦争で大聖杯があったとされる地下大空洞を確認しようという提案があったからだ。
「しかし、この山にそんな空洞があったとは。とんだ盲点だったのう」
「それは仕方ないでしょう。あの空洞はサーヴァントでも相当近づかなければ気付かない程に高度な魔術で入口が隠蔽されていますから」
セイバーとライダーの会話を聞きながら、ルルーシュは黙々と思考を重ねていた。
天才と呼ぶに相応しい頭脳を持つ彼をもってしても、この数時間の間に得た様々な情報を整理するには時間が必要だった。そして、聖杯の破壊に必要な事だとはいえ、自分達がこうして調べ物をしている間にも殺し合いが進行している以上、一秒たりとも時間を無駄にしたくはない。
「着いたぞ、この辺りが入口だ」
と、士郎が立ち止まって手招きしてくる。
「ってちょっと衛宮さん、そこ行き止まりじゃないか。確かに通れそうな岩の隙間はあるけど…すぐ先の岩にぶつかっちゃうぜ?」
金田一の指摘を柳に風とばかりに受け流し、士郎は岩場に身を乗り出す。
「まあ口で言うより見た方が早いよな。俺が先に行くから、皆はよく見ててくれ」
そう言うや否や、士郎は岩の隙間に入っていく。そのまま数メートルほど先の岩にぶつかるかと思われたが、士郎の身体はその岩をすり抜けるように通り抜けていった。
「う、うそぉ……」
「……な、なるほどな。魔術による隠蔽とはこういう事か」
トリックもクソもない光景に顔を引き攣らせる金田一とルルーシュだったが、すぐに気を取り直して入口に向かって行った。
中に入って最初に彼らを迎えたのは、闇だった。今が夜であることを差し引いても、何ひとつ見通せない。
「気をつけて進んでくれよ。ここ、相当急な斜面になってるからな。
背中を地面につけて、ゆっくり進むんだ」
先導する士郎に従って後の五人も斜面を進む。広さの関係で一人ずつしか入れないため、金田一、ルルーシュ、セイバー、ガウェイン、最後にやや間を開けてライダーの順で入っていった。
螺旋状の急斜面を百メートルほど進み、ようやく大人数で進めるだけの広い洞穴に出た。もっとも、あまり体力の無い金田一や、彼に輪をかけて体力の無いルルーシュはその段階で既に肩で息をしている有様だった。普段から身体を鍛えている士郎や、肉体言語を得意とする某赤い魔術師ならともかく、そのような基礎体力の無い二人が大きな怪我もなくここまで辿り着いただけでも賞賛すべき事だろう。
洞穴の内部は、光苔の一種が自生しているためか緑色に照らされており、視界の心配をする必要はなさそうだった。
「シロウ、ここには以前のような魔力の気配も、いえ、その残滓すらありません。やはりここには何も……」
「…かもな。でも、一応奥まで調べてみよう」
そう言って、(疲労した金田一とルルーシュのために数分休憩を取った後)一行は洞穴の奥へと進んでいった。途中で学校のグラウンド程度の広さの空間を経由して、最深部まで辿り着いた結果判った事は、何もないという事だった。
「やっぱり無かったか……」
ガックリと項垂れる士郎。残っていなければおかしいほど濃密だった魔力の残滓すら感じられないとなると、件のムーンセル云々の話もどうやら完全に信じざるを得ないようだ。
「そう落ち込むでない。確かに手掛かりになるようなものは無かったが、それでも得られたものは大きい。
この洞穴は、戦略的には非常に有用な場所になり得るのだからな。おぬしには感謝しておる」
気を遣ったのであろうライダーの言葉に、士郎も多少だが元気を取り戻した。
確かに気を落としている場合ではない。元々今回の聖杯の正体など全く判っていなかったのだ。それが振り出しに戻っただけの事だ。
「さて、ここなら他のマスターやサーヴァントの目を気にする必要もない。
改めて情報交換をするかのう。今後の段取りも考えねばならぬしな」
ライダーの提案に全員が頷き、情報交換と作戦会議が行われる運びとなった。
「日本が侵略されたって……。いくら並行世界って言ったって、そんなに歴史が変わっっちまうもんなのかよ」
「それはお互い様だろう。俺からすればブリタニアが存在しない上に、日本が侵略されていない世界がある方が驚きだ」
情報交換は世界観の違いによる互いの驚きこそあったものの、つつがなく進んだ。互いに戦意がない事に加え、マスターである三人全員が他人と協調する事の必要性を感じていたのが大きかった。また、ムーンセルから十分な知識を与えられなかったセイバーも、ここで漸く正確な情報を得ることができた。そして、タイミングを見計らったところでライダーと金田一が先ほど自分達で話し合った考察を話した。
「なるほどな。確かに裏に人間がいると仮定すれば、殺し合いを行う意味や勝者に願いを叶える権利を与えることにも説明がつく。並行世界の人間を招くことにしても、無機質な記録装置では有り得ないことだとは思っていた」
ルルーシュは得心がいったとばかりに頷いていた。彼もこの聖杯戦争そのものに対して疑問は持っていたが、ゲームが始まってすぐにあちこち移動を繰り返していたこともあり、そこまで具体的な考察はできていなかった。
一方で士郎は、考察の深さに感心しながらも、ある一つの事柄が気になっていた。
「けど、結局セイバーは何でムーンセルから正しい情報を貰えなかったんだ?
もっと言えば、何でサーヴァントで情報量に差をつける必要があるんだ?」
「それは私も不思議に思っていました。聖杯戦争が全てにおいて公正な戦いではないことは分かっていますが、これはそれ以前の問題だ。
令呪に関するルール一つをとっても、知らないままなら使い切ってそのまま脱落してしまう可能性すらあったのですから」
セイバーの指摘は非常に尤もな事だった。通常のマスターとサーヴァントの関係であれば、使い切れば死ぬというルールが無くとも令呪を全て使い切ることなど考えにくい事ではあるが、士郎とセイバーの場合はなまじ深い信頼関係を築けているだけに、全ての令呪を使ってしまいかねない面があった。
そんな彼らの疑問に、金田一が言いにくそうに口を開いた。
「それなんだけど…ちょっと思いついた推理があるんだ。
ただ、怒らないで最後まで聞いてほしいんだけど、良いスか?」
「?…ああ、別にいいぞ」
妙に歯切れの悪い金田一を若干不思議に思いながらも、士郎は先を促した。
「衛宮さんとセイバーさんは、より殺し合いをスムーズに進行させるために選ばれたんじゃないかな。二人とも別の聖杯戦争を経験してて、聖杯を否定してる上に、殺し合いに乗ってないってとこが逆に殺し合いの促進に繋がるんだ」
「何でさ。俺もセイバーも、殺し合いを止める側だぞ。
そりゃあ俺はまだまだ未熟だし、セイバーに負担をかけてる部分も多いけど、間違っても殺し合いの手助けなんてしないぞ」
どこか矛盾した金田一の物言いに反論する士郎だが、金田一は静かに首を横に振って続きを語り始めた。
「じゃあ聞くけど、もし最初に出会ったのが俺たち以外の人間で、ある程度話しが通じるマスターだったらどうしてた?前の聖杯戦争の事を持ち出して、聖杯は穢れてるから殺し合いに乗るのはやめろって言うんじゃないかな?」
「そりゃあまあ…ムーンセルの事とか知らなかったらそう言って回ってたかもしれないとは思うけどさ。別にそう言ったところでそこまで問題になんてならないだろ?」
「それがなるんだよ。マスターの中には、前の聖杯戦争とか魔術の事なんて全然知らない奴だっているはずだ。実際、俺やルルーシュっていう前例がいるわけだから、その可能性は決して低くないだろう。
それだけじゃなく、このムーンセルはビックリするぐらい中身がリアルに作られてる。誰かに言われなきゃここが仮想空間だなんて思えないぐらいにね。そうなれば、いざ参加したのは良いものの、聖杯の存在を完全には信じきれない場合もあるだろう。そんな人間が、別の聖杯戦争の参加者から話しを聞かされたら、どうなる?」
その問いに士郎はやや口ごもったが、すぐに反論した。
「ちょっと待て金田一。お前の言いたい事はわかるけど、考えが極端すぎるぞ。
他のマスターだって馬鹿じゃないだろうし、地上で聖杯戦争があったからこっちにも間違いなく聖杯があるだろうなんて、そんな短絡的な思考にはそうそうならないだろ。
お前が言うように、魔術を知らなくて、聖杯の存在を信じきれない連中なら尚更だ」
「…本当にそうかな?俺はさ、こんな殺し合いに参加しよう、しなきゃいけないって本気で考える人間ってのは、相当追い詰められた人だと思うんだ。それこそ、聖杯なんてものに縋らなきゃいけないほど、どうしようもない状況に陥った人が。
そういう人に限って、少ない情報から誤った判断をしてしまって、取り返しのつかない事をしてしまうんだ。…俺、そういう人を何人も見てきたからわかるよ」
追い詰められた人間は往々にして視野狭窄に陥り、少ない情報や知識を自分の都合の良いように解釈した結果、さらに暴走していってしまう場合がある。そうした人間が持つ弱さや脆さを、復讐の絡んだ殺人事件を数多く解決してきた金田一はよく知っていた。
逆に士郎の知る聖杯戦争のマスターは、今は亡き友人である間桐慎二や、魔術の師である遠坂凛のような例外を除けば皆自身の目的に向かって邁進し、殺人を躊躇わないある種超越した精神性と狡猾さを併せ持った者ばかりだった。それ故に、士郎には金田一が考えるようなごく普通の人間がマスターになっているという事がピンとこなかった。
段々と議論が水掛け論の様相を呈してきたその時、上から地鳴りのような音とともに、微かにだが洞穴全体が揺れた。
「これは……!?」
「サーヴァント同士の戦闘かもしれません。一度地上へ戻りましょう」
ガウェインの提案に従い、ひとまず会議を中断して一行は入口まで引き返した。
そして急斜面の近くまで戻ったところで、来る時にはなかった木の枝を見つけた。
それを見たライダーが、真剣な表情で全員に告げた。
「これは…間違いない。地上、それもこのすぐ近くで戦闘が起こっておる」
「何でわかるんだ?」
「うむ、実はさっきここに潜る時にスープーに近くを偵察するように言っておいたのだ。そして、戦闘を行なっているサーヴァントを見かけたらここに適当な木の枝を投げ入れておくようにもな。何しろ地下ではスープーの声も届かぬ可能性もあったしな」
「なるほどな。とにかく、ここで立ち止まっていても仕方ない、事情は上に戻ってからあのカバに聞こう」
そうして、一行は急斜面を登り(この時、金田一とルルーシュはまたも息を切らす羽目になったが)、地上へ戻った。
「あ、御主人!」
「うむ、スープーよ、ドンパチしているマスターとサーヴァントはどんな連中だったかきちんと覚えておるか?」
「ハイっス!片方は青いタイツに赤い槍を持った男の人と銀髪の眼鏡をかけた男の人の組み合わせで、もう片方は何かメカメカしい大きな人と銀髪に赤い目の小さい女の子の組み合わせだったっス!」
それを聞いた途端、士郎の表情が一変した。脳裏によぎるのは大聖杯を封印するために逝ってしまった雪の少女。有り得ないと思いながらも、内心の焦りを抑えきれない。
「シロウ!?」
セイバーが制止する間もなく、士郎は凄まじい勢いで獣道を駆け上がり、柳洞寺の外へと走っていってしまった。
「すみません、私はシロウを追います。ガウェイン、ライダー、貴方がたはここの守りをお願いします」
そう言うや、セイバーは一陣の風となって士郎の後を追っていった。
そんな彼らに、ルルーシュは露骨に苛立ちを募らせる。知り合いでもいるのかもしれないが、もう少し慎重になることはできないのか。
「ええい、あの猪主従め……!仕方ない、俺達も行くぞ、ガウェイン」
腹立たしいが、今後有用な駒になりうる者をここでみすみす失うわけにもいかない。それに、考えようによってはこれは有利な状況でサーヴァント同士の戦闘を見る良い機会でもある。もっとも、その機会が衛宮士郎の蛮勇としか思えない行動によって齎された事が余計にルルーシュの苛立ちを煽っているのだが。
「ではわしらがここに残ろう。だが二十分経っても戻らなければわしらも駆けつけるぞ。戦力の逐次投入は愚策だが、ここを他のマスターに明け渡すわけにもいかぬしな」
ライダーの提案に頷くと、ルルーシュとガウェインも士郎たちを追っていった。
「大丈夫かなぁ…」
「なーに、あやつらは最優と謳われるセイバーのサーヴァントだ。それも二騎がかりなら、よほどの相手でもない限り心配はあるまい」
ぽつりと漏れた金田一の不安を打ち消すようにライダーが励ます。
二人と一匹だけになった柳洞寺に、ただ夜風だけが吹いていた。
to be Continued……
「…………………」
金田一には今、自分の目の前に広がる光景が信じられなかった。
否、信じたくなかった。
目を凝らし、もう一度だけ確認する。
だが、現実は何ひとつ変わらない。
「………なんてこった」
まるで数年前に二週間だけ過ごした田舎の村の懐かしい旧友に会いに行った矢先に、その村で起こった連続殺人事件の犯人が旧友の一人だったかのようなやるせない表情で呟いた。
「肉が、無い……」
由緒正しい寺の冷蔵庫に肉類など入っている筈がない。
それが、金田一が直面している(少なくとも本人にとっては)極めて切実な問題だった。
「そりゃあおぬし、寺に肉などあるわけなかろう。
というか一晩ぐらい我慢できんのか?」
ライダーの痛烈なツッコミに項垂れる金田一。
彼は食べ盛りの高校生。腹持ちの良くない和菓子だけで一晩過ごすなどとてもではないが出来ることではなかった。
「だってしょうがないだろ?腹が減っては戦は出来ぬって言うじゃんか。
ここ、米とか野菜ばっかりでカップ麺すら無いんだぜ?いや、何でか酒はあったけど」
「それがさっきわしが持ってきた和菓子を全部平らげた奴の言う事か。
おぬしの辞書にペース配分という言葉はないんかい!」
再び項垂れる金田一。ぐぅの音も出ない。
と、そこで何かを思い出したように顔を上げた。
「そうだ、なあライダー。さっきポケットにカードみたいなのが入ってたんだよ。
俺、ポケットにそんなの入れた覚えがないんだけど、何か分からないか?」
「おお、それは参加者全員に配布されているクレジットカードだ。
限度額は無いから残金を気にする必要はないぞ」
「えっ、マジで!?じゃあこのカードがあれば、高級寿司も焼肉も食べ放題ってこと!?」
「おぬし……いくらなんでも発想が貧困すぎるぞ…」
冷めた視線を送るライダーを他所に、金田一は両手でカードを持ちながらクルクルと小躍りしていた。
「それでおぬし、何か妙案は浮かんだのか?」
「ああ、その事なんだけどさ、ライダー。
お前、さっき魔術師とか超常の力を持ったマスターがいるみたいなこと言ってたけど、あれってどういう意味なんだ?」
金田一の疑問に、ライダーは表情を険しくしながら答えた。
「……うむ、それについてはちと話が長くなる。場所を移そう」
ライダーの神妙な表情から、この話がただ事ではないと悟った金田一は、何も言わずにライダーの後について台所を後にした。
「魔術師というのは、まあ一言で言ってしまえばおぬしのような一般人にとっては傍迷惑極まりない連中のことだ」
開口一番、ライダーは魔術師をバッサリと切るような、身も蓋もない事を口にした。
それから、ライダーはおおまかな魔術師の概要を語り始めた。
「魔術師とは、“根源”、いわばアカシックレコードに到達するために魔術を研究する者たちの事を指す。
そして、魔術とは魔力を用いて人為的に神秘や奇跡を起こす術全般のことをいう。
まあ、実際のところはもっと複雑なのだが、今覚えておくべきことは、個人差こそあれ魔術師は一般人とは隔絶した能力を持っていることと、根源へと至る手段として聖杯を狙う魔術師が参加している可能性が高いことだ」
「ちょっと良いか?さっきから魔術とか魔術師って言ってるけど、それってつまり魔法みたいなものなんじゃないのか?」
金田一の質問に、ライダーは頷きながら答えた。
「良い質問だ。魔術と魔法には大きな違いがある。
それは、文明の力で再現できるかどうかだ。他の技術で再現できるものは魔術と呼ばれ、逆に再現できないものが魔法とされる。
例えば、火や風を操るとか、空を飛ぶ術は魔術に分類され、時間を操作したり、魂を物質化する術は魔法にあたる、という具合にな」
ちなみに、ライダーが生きた時代には、封神台と呼ばれる一定以上のランクの人物の魂を封じ込める、第三魔法を体現したような装置が存在していたりする。
「それと、ここからが重要なのだが、魔術師という人種は根源へと到達するためなら手段を選ばぬ。それこそ、親族や師弟などの身内を除いたあらゆる者を犠牲にすることさえ厭わぬだろう。
しかも質の悪い事に、魔術師は往々にして社会の裏に潜み、法の裁きを逃れておる。
魔術師の総本山ともいえる魔術協会も、神秘、つまり魔術の秘匿を最優先とし、魔術師たちの行為を黙認している」
「な、何だよそれ……!警察じゃあ捕まえられないのかよ!?」
憤慨する金田一から視線は逸らさず、ライダーは首を横に振った。
「無理だ。彼奴等は魔術を駆使してその存在や痕跡を悉く隠蔽する上に、代を重ねた魔術師の家の多くは表の世界に対して影響力を持つ。
仮に魔術の存在や魔術師の所業を告発しようとする者がいたとしても、協会は刺客を差し向けて始末する。はっきりと言ってしまえば、この聖杯戦争で彼奴等に現代日本の倫理や常識などというものは微塵も期待できん。
故に、心するのだ金田一よ。おぬしがこれから相対するのは、そういった手段を選ばぬ連中なのだからな」
強く言い聞かせるような口調のライダーに、金田一も思わず勢いよく首を縦に振る。
実際のところ、ライダーの説明には彼自身の魔術師に対する嫌悪感がにじみ出た、やや偏向された部分があるのだが、これは彼の生前の戦いに起因する。
太公望が生きた時代は、殷王朝に巣食う皇后・蘇 妲己と、その配下である妖怪仙人らに代表される力を持つ者が、無力な人間を食い物にするというある種の弱肉強食といえる時代だった。
そして、太公望(幼名は呂望という)もまた、幼少の頃、妲己の発案によって行われた大規模な人狩りによって生まれ育った村を、一族を皆殺しにされた。偶然その場から離れていたために難を逃れた彼が自分の村だった場所に戻ってきた時、瀕死の老人と出会った。
憎しみを募らせる彼に、老人はこう語った。
“憎いですか?呂望様、復讐をしたいですか?
おやめなさい、やるだけ無駄な事なのですから………”
その声には、どうしようもない諦観があった。そういう時代だったのだ。
“世の中全体がこうなのです…全てを変えないと…いつまでも…こんな事が…続……”
そう言って、老人は息を引き取った。
それが、呂望という名の少年の終わりであり、太公望という英雄の始まりだった。
この後、呂望は仙人界のひとつ、崑崙山の教主である元始天尊に才を見出され、彼の弟子となり、太公望という名を授かった。そしていつしか、太公望はある理想を思い描くようになった。
―――わしは仙道のおらぬ安全な人間界をつくろう
強大な力を持つ仙人によって、普通の人々が脅かされる事のない世界にする。
その志を胸に、太公望は師である元始天尊から与えられた任務、封神計画を遂行していくこととなる。
そのような経緯から、太公望は普通の人間を蔑ろにする魔術師を快く思っていなかった。(それでも例外を認めないというほどではないが)
また、少々お人好しすぎるきらいのある金田一に警戒心を持たせる必要があったという事情もある。
当の金田一も、納得はできないなりにどうにか事実を咀嚼しようとしていたが、事態は彼に深く考える時間を与えてはくれなかった。
「御主人!」
偵察のために円蔵山の周辺を飛んでいた四不象が慌てた様子でやって来た。
「こっちにマスターとサーヴァントが向かってきてるっス!しかも二組っス!」
それを聞いたライダーは一瞬驚いた表情を浮かべたものの、すぐに考え込むような様子を見せ、数十秒ほど経ってから結論を出した。
「よし、そやつらに会ってみよう。こんな短時間のうちに他人と協力するマスターならば、殺し合いに乗っていない可能性もある。
そうでなくとも、ある程度の慎重さは持ち合わせているだろう。金田一、おぬしも来るか?」
恐らく、ライダーは自分の覚悟を問うているのだろう。
そう悟った金田一は、強く頷いてライダーと共に四不象に跨った。
事態が大きく動こうとしていた。
「……おい」
「どうした?別についてこなくとも俺は一向に構わないぞ?
それとも、ボディーガードでもしてくれるのか?」
「そんなわけあるか!お前が何するかわからないから、こうして見張ってるだけだ!」
衛宮士郎とルルーシュ・ヴィ・ブリタニア、そして二人のセイバー。
彼らは深山町の住宅街を通って、柳洞寺へと向かっていた。
先ほどの(険悪な)初対面の時に行なった情報交換で、士郎が「前回の聖杯戦争で、柳洞寺の地下の大聖杯を破壊した」という言葉が根拠である。
勿論この聖杯戦争の舞台がムーンセルである以上、そこに聖杯が存在するなどとはルルーシュも考えていないが、それでも何かしらの手掛かりを掴める可能性はある。というより、他にアテもないので柳洞寺に向かうしかないのが実情ではあるのだが。
その他、士郎から聞かされた魔術師なるものの存在や、かの騎士王が女性であったという衝撃の事実を頭の中で整理しながら、士郎に問いかける。
「それで?俺の話は信じる気になったか、衛宮士郎」
露悪的な態度を崩さないルルーシュにムッとしながらも、士郎もまた自身の見解を述べた。
「確かに、言われてみれば街っていうか、人が変な感じはする。
けど、ムーンセルだの量子空間なんてのを信じるかどうかっていうのとは、話が別だ」
先ほど、士郎もまたルルーシュからムーンセルに関する情報を聞かされたが、今のところは半信半疑だった。冬木市の住人である士郎からすれば、今自分がいる場所がバーチャル空間の類だなどと言われてすぐに納得できるわけがない。まだ固有結界の産物やアンリ・マユの仕業とでも言われた方が信じられるぐらいだ。
どうにも生気を感じにくい奇妙な通行人たちの存在が無ければ、今頃はただの虚言だと完全に切って捨てていただろう。
「大体、それが本当なら何でセイバーはムーンセルの事を何も知らないんだよ。
サーヴァントには聖杯から必要な知識が与えられるはずじゃないか」
「それは俺にもまだわからん。まさか正確な情報を与えられていないサーヴァントがいるなど予想外だったからな。それよりもあれを見ろ」
ルルーシュが指したその場所には、倒れた電柱や破砕されたコンクリートやブロックの欠片が散乱していた。気の早い参加者が既に一戦交えた跡だと想像するのは容易い事だった。
だがその直後、ルルーシュや士郎が目を疑う事が起こった。
散々に破壊された道路や電柱がひとりでに、まるで時を巻き戻すかのように修復されはじめたのだ。
「……おい、衛宮士郎。魔術師というのはこんな芸当もできるのか?」
「……いや、俺の知ってる魔術師でも遠隔でこんな真似するのは多分無理だ」
半ば唖然とした様子の二人の傍に、ガウェインが歩み寄ってきた。
「ムーンセルの修復機構が働いたようですね。見ての通り、今回の聖杯戦争ではマスターやサーヴァントによる一定以上の器物の破壊については、ムーンセルが自動で修復を行うシステムになっています」
「……だそうだ。これで信じる気になったか?」
内心の動揺をおくびにも出さずに再度問うルルーシュに、士郎はまだ複雑そうな面持ちではあったものの、静かに頷いた。
ルルーシュが今後どう行動するかはわからないが、ここまでの言動を鑑みるに積極的に殺し合いに乗ることはなさそうだ。柳洞寺を調べ終わったら、お互い別行動をとるのも手だろう。
そう考え、しばらく歩いているうちに、柳洞寺の手前に到着した。
すると、セイバーが私服姿から鎧姿になり、士郎たちよりも一歩前へ出た。
「シロウ、中からサーヴァントの気配がします。既にここに陣取っていたようです」
「やっぱりキャスターか?」
「いえ、神殿や魔術工房が敷設されている様子はありません。もしそうなら、この付近は既に異界同然と化しているはずですから」
セイバーの言葉に幾分安堵する。何しろ前回の聖杯戦争では、すぐに脱落したとはいえキャスターが柳洞寺に神殿を作り、街の人々から魔力を奪っていたのだから。
「よし、じゃあ慎重に進んで行こう。けど、こっちから先に仕掛けるのはなしだ。
……お前もだぞ、ルルーシュ」
「ふん、そういうことは自分のサーヴァントにでも言い聞かせた方が良いんじゃないか?
それに、向こうから仕掛けてきた時は貴様が止めても勝手に応戦させてもらうぞ」
相変わらずのルルーシュの態度だが、士郎は敢えて反論はしなかった。セイバーの突撃癖は自身がよく知っているからだ。それに、士郎とてただの平和主義者ではない。無防備な状態で敵マスターと相対する事がどれだけ危険かは身をもって知っている。
「ああ、そうなったらこっちも戦うさ。俺だって、こんなところで死ぬわけにいかないからな」
「ふむ、気合の入っているところ悪いが、生憎わしらは戦う気はないぞ?」
どこかから聞こえた声に全員が周囲の様子を窺う。
「上です!」
セイバーの声に全員が上を向く。第四次聖杯戦争を経験しているセイバーだからこそ、相手が空中にいる可能性に最も早く気付く事ができた。
そこにいたのは、カバのような奇妙な生き物に乗ったサーヴァントらしき少年と、学生服(何故か夏服のようだが)を着た高校生ぐらいの少年だった。
「ライダーのサーヴァント、ですね?」
「いかにも。そう言うおぬしらはセイバー、それも鎧の意匠からして同郷の出身と見るが?」
ライダーの問いに、セイバーとガウェインは無言で返す。一分ほどの沈黙の後、場を代表してルルーシュが口を開いた。
「戦う気は無いと言ったな。それは貴様のマスターの意思か?」
「うむ、その通りだ。わしらはこの聖杯戦争を打破することを考えておる。
そこで率直に言うが、わしらと同盟を組んではくれぬか?おぬしらはどうも殺し合いに乗っているとは思えぬのでな」
ライダーの提案に、士郎もルルーシュも暫し考え込む。
元々、自分達も殺し合いに乗っているわけではない。仮にこの提案が罠であったとしても、最優のサーヴァントたるセイバーが二騎がかりであれば容易に切り抜けられるだろう。それはそれでサーヴァント同士の戦闘を直接見る良い機会になる。士郎はそこまで打算的な考えではないが、用心のためにいつでも魔術回路を起動できるようにしている。
だが、返事を返す前に言わなければならない事があった。
「なあ、同盟を組むってのは良いんだけどさ、その前にお前のマスターを下に降ろしてやった方が良いんじゃないか?」
士郎に言われて後ろを振り向くと、金田一が顔を真っ青にしながらガクガクと震えていた。
「ラ、ラ、ライダー、無理、もう無理。お、降ろして……」
「おぬし、高所恐怖症なら早く言わんかい!」
「い、いや、高所恐怖症じゃなくても無理だって!尻尾の先っちょあたりしかケツ引っ掛けられるとこ無いじゃんか!ちょ、頼むからもう勘弁してくれ!」
「ギャー!!痛いっス!暴れないでっスよ金田一くん!」
「ああっ!揺らすでない!バランスが取れぬではないか!!」
いきなりコント(本人達にとっては切実だが)を始めたライダー主従を、四人は何ともいえない気持ちで見つめていた。というか騎乗スキルが全く仕事をしていないのはどういう事なのだろう。
「ヘルプミー!!」
ライダーの絶叫が虚しく響き渡り、場にはどこか弛緩した空気が流れていた。
「ひ、ひどい目に遭った……」
「まあ……その、何だ、大丈夫か?」
数分後、どうにか態勢を立て直して無事地面に着地したライダーらは、寺に入って自己紹介をしようとしたが、現在はその予定を変更して山中の獣道、というより絶壁に近い地形を進んでいた。士郎から、前回の聖杯戦争で大聖杯があったとされる地下大空洞を確認しようという提案があったからだ。
「しかし、この山にそんな空洞があったとは。とんだ盲点だったのう」
「それは仕方ないでしょう。あの空洞はサーヴァントでも相当近づかなければ気付かない程に高度な魔術で入口が隠蔽されていますから」
セイバーとライダーの会話を聞きながら、ルルーシュは黙々と思考を重ねていた。
天才と呼ぶに相応しい頭脳を持つ彼をもってしても、この数時間の間に得た様々な情報を整理するには時間が必要だった。そして、聖杯の破壊に必要な事だとはいえ、自分達がこうして調べ物をしている間にも殺し合いが進行している以上、一秒たりとも時間を無駄にしたくはない。
「着いたぞ、この辺りが入口だ」
と、士郎が立ち止まって手招きしてくる。
「ってちょっと衛宮さん、そこ行き止まりじゃないか。確かに通れそうな岩の隙間はあるけど…すぐ先の岩にぶつかっちゃうぜ?」
金田一の指摘を柳に風とばかりに受け流し、士郎は岩場に身を乗り出す。
「まあ口で言うより見た方が早いよな。俺が先に行くから、皆はよく見ててくれ」
そう言うや否や、士郎は岩の隙間に入っていく。そのまま数メートルほど先の岩にぶつかるかと思われたが、士郎の身体はその岩をすり抜けるように通り抜けていった。
「う、うそぉ……」
「……な、なるほどな。魔術による隠蔽とはこういう事か」
トリックもクソもない光景に顔を引き攣らせる金田一とルルーシュだったが、すぐに気を取り直して入口に向かって行った。
中に入って最初に彼らを迎えたのは、闇だった。今が夜であることを差し引いても、何ひとつ見通せない。
「気をつけて進んでくれよ。ここ、相当急な斜面になってるからな。
背中を地面につけて、ゆっくり進むんだ」
先導する士郎に従って後の五人も斜面を進む。広さの関係で一人ずつしか入れないため、金田一、ルルーシュ、セイバー、ガウェイン、最後にやや間を開けてライダーの順で入っていった。
螺旋状の急斜面を百メートルほど進み、ようやく大人数で進めるだけの広い洞穴に出た。もっとも、あまり体力の無い金田一や、彼に輪をかけて体力の無いルルーシュはその段階で既に肩で息をしている有様だった。普段から身体を鍛えている士郎や、肉体言語を得意とする某赤い魔術師ならともかく、そのような基礎体力の無い二人が大きな怪我もなくここまで辿り着いただけでも賞賛すべき事だろう。
洞穴の内部は、光苔の一種が自生しているためか緑色に照らされており、視界の心配をする必要はなさそうだった。
「シロウ、ここには以前のような魔力の気配も、いえ、その残滓すらありません。やはりここには何も……」
「…かもな。でも、一応奥まで調べてみよう」
そう言って、(疲労した金田一とルルーシュのために数分休憩を取った後)一行は洞穴の奥へと進んでいった。途中で学校のグラウンド程度の広さの空間を経由して、最深部まで辿り着いた結果判った事は、何もないという事だった。
「やっぱり無かったか……」
ガックリと項垂れる士郎。残っていなければおかしいほど濃密だった魔力の残滓すら感じられないとなると、件のムーンセル云々の話もどうやら完全に信じざるを得ないようだ。
「そう落ち込むでない。確かに手掛かりになるようなものは無かったが、それでも得られたものは大きい。
この洞穴は、戦略的には非常に有用な場所になり得るのだからな。おぬしには感謝しておる」
気を遣ったのであろうライダーの言葉に、士郎も多少だが元気を取り戻した。
確かに気を落としている場合ではない。元々今回の聖杯の正体など全く判っていなかったのだ。それが振り出しに戻っただけの事だ。
「さて、ここなら他のマスターやサーヴァントの目を気にする必要もない。
改めて情報交換をするかのう。今後の段取りも考えねばならぬしな」
ライダーの提案に全員が頷き、情報交換と作戦会議が行われる運びとなった。
「日本が侵略されたって……。いくら並行世界って言ったって、そんなに歴史が変わっっちまうもんなのかよ」
「それはお互い様だろう。俺からすればブリタニアが存在しない上に、日本が侵略されていない世界がある方が驚きだ」
情報交換は世界観の違いによる互いの驚きこそあったものの、つつがなく進んだ。互いに戦意がない事に加え、マスターである三人全員が他人と協調する事の必要性を感じていたのが大きかった。また、ムーンセルから十分な知識を与えられなかったセイバーも、ここで漸く正確な情報を得ることができた。そして、タイミングを見計らったところでライダーと金田一が先ほど自分達で話し合った考察を話した。
「なるほどな。確かに裏に人間がいると仮定すれば、殺し合いを行う意味や勝者に願いを叶える権利を与えることにも説明がつく。並行世界の人間を招くことにしても、無機質な記録装置では有り得ないことだとは思っていた」
ルルーシュは得心がいったとばかりに頷いていた。彼もこの聖杯戦争そのものに対して疑問は持っていたが、ゲームが始まってすぐにあちこち移動を繰り返していたこともあり、そこまで具体的な考察はできていなかった。
一方で士郎は、考察の深さに感心しながらも、ある一つの事柄が気になっていた。
「けど、結局セイバーは何でムーンセルから正しい情報を貰えなかったんだ?
もっと言えば、何でサーヴァントで情報量に差をつける必要があるんだ?」
「それは私も不思議に思っていました。聖杯戦争が全てにおいて公正な戦いではないことは分かっていますが、これはそれ以前の問題だ。
令呪に関するルール一つをとっても、知らないままなら使い切ってそのまま脱落してしまう可能性すらあったのですから」
セイバーの指摘は非常に尤もな事だった。通常のマスターとサーヴァントの関係であれば、使い切れば死ぬというルールが無くとも令呪を全て使い切ることなど考えにくい事ではあるが、士郎とセイバーの場合はなまじ深い信頼関係を築けているだけに、全ての令呪を使ってしまいかねない面があった。
そんな彼らの疑問に、金田一が言いにくそうに口を開いた。
「それなんだけど…ちょっと思いついた推理があるんだ。
ただ、怒らないで最後まで聞いてほしいんだけど、良いスか?」
「?…ああ、別にいいぞ」
妙に歯切れの悪い金田一を若干不思議に思いながらも、士郎は先を促した。
「衛宮さんとセイバーさんは、より殺し合いをスムーズに進行させるために選ばれたんじゃないかな。二人とも別の聖杯戦争を経験してて、聖杯を否定してる上に、殺し合いに乗ってないってとこが逆に殺し合いの促進に繋がるんだ」
「何でさ。俺もセイバーも、殺し合いを止める側だぞ。
そりゃあ俺はまだまだ未熟だし、セイバーに負担をかけてる部分も多いけど、間違っても殺し合いの手助けなんてしないぞ」
どこか矛盾した金田一の物言いに反論する士郎だが、金田一は静かに首を横に振って続きを語り始めた。
「じゃあ聞くけど、もし最初に出会ったのが俺たち以外の人間で、ある程度話しが通じるマスターだったらどうしてた?前の聖杯戦争の事を持ち出して、聖杯は穢れてるから殺し合いに乗るのはやめろって言うんじゃないかな?」
「そりゃあまあ…ムーンセルの事とか知らなかったらそう言って回ってたかもしれないとは思うけどさ。別にそう言ったところでそこまで問題になんてならないだろ?」
「それがなるんだよ。マスターの中には、前の聖杯戦争とか魔術の事なんて全然知らない奴だっているはずだ。実際、俺やルルーシュっていう前例がいるわけだから、その可能性は決して低くないだろう。
それだけじゃなく、このムーンセルはビックリするぐらい中身がリアルに作られてる。誰かに言われなきゃここが仮想空間だなんて思えないぐらいにね。そうなれば、いざ参加したのは良いものの、聖杯の存在を完全には信じきれない場合もあるだろう。そんな人間が、別の聖杯戦争の参加者から話しを聞かされたら、どうなる?」
その問いに士郎はやや口ごもったが、すぐに反論した。
「ちょっと待て金田一。お前の言いたい事はわかるけど、考えが極端すぎるぞ。
他のマスターだって馬鹿じゃないだろうし、地上で聖杯戦争があったからこっちにも間違いなく聖杯があるだろうなんて、そんな短絡的な思考にはそうそうならないだろ。
お前が言うように、魔術を知らなくて、聖杯の存在を信じきれない連中なら尚更だ」
「…本当にそうかな?俺はさ、こんな殺し合いに参加しよう、しなきゃいけないって本気で考える人間ってのは、相当追い詰められた人だと思うんだ。それこそ、聖杯なんてものに縋らなきゃいけないほど、どうしようもない状況に陥った人が。
そういう人に限って、少ない情報から誤った判断をしてしまって、取り返しのつかない事をしてしまうんだ。…俺、そういう人を何人も見てきたからわかるよ」
追い詰められた人間は往々にして視野狭窄に陥り、少ない情報や知識を自分の都合の良いように解釈した結果、さらに暴走していってしまう場合がある。そうした人間が持つ弱さや脆さを、復讐の絡んだ殺人事件を数多く解決してきた金田一はよく知っていた。
逆に士郎の知る聖杯戦争のマスターは、今は亡き友人である間桐慎二や、魔術の師である遠坂凛のような例外を除けば皆自身の目的に向かって邁進し、殺人を躊躇わないある種超越した精神性と狡猾さを併せ持った者ばかりだった。それ故に、士郎には金田一が考えるようなごく普通の人間がマスターになっているという事がピンとこなかった。
段々と議論が水掛け論の様相を呈してきたその時、上から地鳴りのような音とともに、微かにだが洞穴全体が揺れた。
「これは……!?」
「サーヴァント同士の戦闘かもしれません。一度地上へ戻りましょう」
ガウェインの提案に従い、ひとまず会議を中断して一行は入口まで引き返した。
そして急斜面の近くまで戻ったところで、来る時にはなかった木の枝を見つけた。
それを見たライダーが、真剣な表情で全員に告げた。
「これは…間違いない。地上、それもこのすぐ近くで戦闘が起こっておる」
「何でわかるんだ?」
「うむ、実はさっきここに潜る時にスープーに近くを偵察するように言っておいたのだ。そして、戦闘を行なっているサーヴァントを見かけたらここに適当な木の枝を投げ入れておくようにもな。何しろ地下ではスープーの声も届かぬ可能性もあったしな」
「なるほどな。とにかく、ここで立ち止まっていても仕方ない、事情は上に戻ってからあのカバに聞こう」
そうして、一行は急斜面を登り(この時、金田一とルルーシュはまたも息を切らす羽目になったが)、地上へ戻った。
「あ、御主人!」
「うむ、スープーよ、ドンパチしているマスターとサーヴァントはどんな連中だったかきちんと覚えておるか?」
「ハイっス!片方は青いタイツに赤い槍を持った男の人と銀髪の眼鏡をかけた男の人の組み合わせで、もう片方は何かメカメカしい大きな人と銀髪に赤い目の小さい女の子の組み合わせだったっス!」
それを聞いた途端、士郎の表情が一変した。脳裏によぎるのは大聖杯を封印するために逝ってしまった雪の少女。有り得ないと思いながらも、内心の焦りを抑えきれない。
「シロウ!?」
セイバーが制止する間もなく、士郎は凄まじい勢いで獣道を駆け上がり、柳洞寺の外へと走っていってしまった。
「すみません、私はシロウを追います。ガウェイン、ライダー、貴方がたはここの守りをお願いします」
そう言うや、セイバーは一陣の風となって士郎の後を追っていった。
そんな彼らに、ルルーシュは露骨に苛立ちを募らせる。知り合いでもいるのかもしれないが、もう少し慎重になることはできないのか。
「ええい、あの猪主従め……!仕方ない、俺達も行くぞ、ガウェイン」
腹立たしいが、今後有用な駒になりうる者をここでみすみす失うわけにもいかない。それに、考えようによってはこれは有利な状況でサーヴァント同士の戦闘を見る良い機会でもある。もっとも、その機会が衛宮士郎の蛮勇としか思えない行動によって齎された事が余計にルルーシュの苛立ちを煽っているのだが。
「ではわしらがここに残ろう。だが二十分経っても戻らなければわしらも駆けつけるぞ。戦力の逐次投入は愚策だが、ここを他のマスターに明け渡すわけにもいかぬしな」
ライダーの提案に頷くと、ルルーシュとガウェインも士郎たちを追っていった。
「大丈夫かなぁ…」
「なーに、あやつらは最優と謳われるセイバーのサーヴァントだ。それも二騎がかりなら、よほどの相手でもない限り心配はあるまい」
ぽつりと漏れた金田一の不安を打ち消すようにライダーが励ます。
二人と一匹だけになった柳洞寺に、ただ夜風だけが吹いていた。
to be Continued……
----
|NEXT|
|[[FINAL DEAD LANCER(中編)]]|
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: