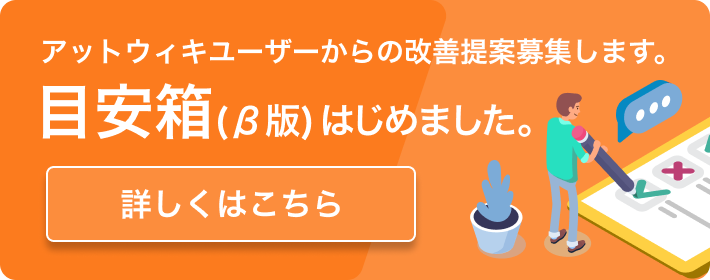「No.20」(2012/10/15 (月) 19:26:52) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
*No.20
一人の少女が死んだとき、彼の心もまた死んだ。
彼の家は人造人間(フランケンシュタイン)創造の名門だった。
フランケンシュタイン。最初の創造主と最初に生み出された怪物の名前が混同されたその存在は、死体と電気の力を用いて創造される。
だが、人造人間は本人の死体を全て使って創造しても、生前とは必ず異なる。
記憶の障害か人格の変貌、またはその両方を起こし、生前とは別の存在になる。
人造人間として蘇った少女も例に漏れなかった。
彼は少女を人間に戻すと誓い、人造人間の研究を続け、欧州を駆け回り十年。
だが、いまだに解決の糸口さえ見えなかった。
そんな折、唐突に召喚された先での神父の言葉は、彼には新しい希望に思えた。
人造人間創造の技術では、もしかしたら死者蘇生は不可能かもしれない。
ならば、人造人間創造以外の技術なら?
自分をこの場に召喚した力なら?
死して後、三日後に復活を果たしたという主の力を宿した聖杯なら?
彼は迷信を信じない。宗教を信じない。本当に主が使った聖杯かどうかに興味は無い。
ただ、聖杯が自分を召喚したという事実を認めた。
それだけの未知なる力なら、あの神父が言うようにいかなる願いも叶うのではないか。
完全な死者蘇生、永遠の命の法を実現できるのではないだろうか。
それが彼、アシュヒト=リヒターの参戦した理由だった。
アシュヒトが右足の義足を鳴らし、扉を潜った先はビルの屋上だった。
周囲には自分のいるビルディングと同等か、それ以上の高さを誇る建造物が立ち並んでいる。
遠くに見える看板を輝かせる照明は、ガス灯ではない。電気の光だ。
周囲の建築物は高度な科学技術で製造されているようだ。そうアシュヒトは判断した。
「やれやれ、まるでウェルズのタイム・マシンに乗った気分です」
アシュヒトはため息をついた。どうやら自分は何百年か後の世界に来てしまったらしい。
「おい、そこのお前」
突然背後から投げかけられた言葉に向かってアシュヒトは素早く振り返り、手に持つトランクから特注の銃「鋼鉄の腕」を取り出した。
装填されているのは、対人造人間用帯電弾。発射時に微量の電流を発生し、人造人間のガルバーニ電流を狂わせ、肉体、機能を誤作動させる。
電流は人造人間以外に効果は無いが、50口径、12.7mmの弾丸は人体を容易に破壊する威力を秘めている。
アシュヒトは引き金に指をかけ、声の主に銃口を向けたまま姿を確認する。
声の主は剣士の格好をした白尽くめの女だった。
肩や腰などに装甲を付けた白いアンダースーツに、同じく白いマントを羽織っている。
その背には細身の身体に不釣合いな大剣を収めていた。年頃の女性としては異様極まる姿だ。
だが、最も異様なのは女の顔であった。
白磁よりも尚白い肌。暗闇で輝く銀色の瞳。ややウェーブのかかった白髪。
女の容貌に、アシュヒトは「人造人間か」と思った。
それほど女は常人離れした、高級なビスクドールの様な美しさをたたえていたのだ。
「なあ、お前が私のマスターでいいのか?」
容姿とは不釣合いな、おどけた拍子の声がアシュヒトに投げかけられる。
「私達の他に誰もいない以上、そういうことでしょう」
アシュヒトは銃の引き金から指を離し、トランクに収めた。
右手袋を外し、令呪を女に向けて見えるように手を掲げる。
「アシュヒト=リヒター。私の名前です」
「了解、マスター」
令呪を確認した女は、ひょうげた感じのままで軍人のように敬礼をした。
「サーヴァント・セイバー。真名はテレサ。
今後ともよろしくな」
「こちらこそ」
微笑を浮かべたサーヴァント・テレサの挨拶に対し、アシュヒトは手袋をはめなおしながら、淡々とした口調で返礼した。
「これから我々は一時パートナーを組み、聖杯獲得を目指すわけですが一つ質問があります。
あなたはどんな願いを抱いて、参戦を決意したのですか?」
「お前はどうなんだ? 引き返すチャンスもあったってのに、何でわざわざ殺し合いなんかしたがる?」
「質問を質問で返すのは……まあ、いいでしょう」
アシュヒトは眼鏡のブリッジを中指で押し上げた。
「私には生き返らせたい人がいます。どんな手段を使ってでも」
アシュヒトの回答にそうか、とテレサは呟き。
「私はな、生き返りたいんだよ。まだあいつに何もしてやれなかったからな」
微笑を崩さぬまま、自分の願望を口にした。
「さて、自己紹介も終わったしそろそろ行くとしようか。既に移動を始めている連中がいるしな」
「マスターの居場所が分かるのですか?」
「まあな、そいつは道すがら話すよ」
驚くアシュヒトを尻目に、テレサはビル屋上の出入口に歩みだした。
アシュヒトも後を追うが、テレサはアシュヒトを置いてさっさと出入口のドアを開けて中に入ってしまった。
「やれやれ……」
アシュヒトがビルの内に入ると、テレサはエレベーターの扉を前にして立ちすくんでいた。
「服装から想像がつきましたが、あなたも今より過去の時間から召喚されたようですね」
「時間というか、世界そのものが違うんだよ。
こんなもの、生きてた頃には見たことも聞いたことも無いぞ」
エレベーターの扉の傍にある複数のボタンをテレサは眺め、どれを押そうか指をさ迷わせている。
その姿をアシュヒトは無視し、下矢印のボタンを押して扉を開いた。
アシュヒトのいた時代は電動エレベーターが普及を始めた頃である。故に大体の使用法は、見当がついていた。
「おお、勝手に開いた」
「頭の悪そうな台詞です。そんな調子であなたは大丈夫ですか」
アシュヒトの容赦無い突っ込みに、憮然とするテレサ。
「いや、私はサーヴァントだから、この世界に関して知識が与えられているんだが……微妙に感覚がついてこないんだよな」
「戦闘でもそんな調子では困ります」
「分かってるよ」
「うおっ!? ……っと、ふうん。成る程、私達を入れた箱ごと下るのか。
いや、分かってはいるんだがな……」
エレベーターが下がり、身体が一瞬浮き上がる様な感覚に驚くテレサを、アシュヒトはじっと見つめていた。
「何だよ」
「いえ、別に」
あくまで無表情なアシュヒトに、テレサはそっぽを向いてふんと鼻を鳴らした。
「ところで先ほど話した、マスターの探索についてですが」
テレサのにが虫をかみつぶしたような表情を、アシュヒトは見てみぬふりをして尋ねた。
「ああ、そいつは」
と、テレサは気持ちを切り替え、自分の特殊能力について説明した。
テレサが他のマスター、サーヴァントを察知できるのは生前から所有していたずば抜けた能力、妖気感知が宝具として昇華されたためである。
その能力は半径数キロ圏内の魔力を感知し、相手の位置や魔力の大きさを探索できるというものだ。
さらに戦闘では、敵の魔力の流れを読み取り、動きの先読みを可能とする。
そこまで聞いたところで、アシュヒトが口を挟んだ。
「魔力はおおよそ見当がつきますが、妖気とは何でしょう」
「言ったろ、世界が違うって。私の世界では、妖魔って奴らが人を襲って喰ってたんだよ。
そいつらが発するのが妖気だ」
「するとあなたが背負った大剣から察するに、妖気感知ができるあなたは妖魔を倒す戦士だったのですか」
「……ま、そんなところだ」
テレサはわずかに言いよどんだ。アシュヒトは微妙な口調の変化に気付いたが、その理由をあえて尋ねようとはしなかった。
テレサの宝具は敵との戦闘、および他マスターの捜査に関して大きなアドバンテージとなるだろう。
今はそれが分かれば十分だ。
そうアシュヒトは思い、テレサとの話を打ち切った。
エレベーターが一階へと下る最中、アシュヒト=リヒターは改めて自分の願望を確認する。
私の目的は、人間のエルム=L=レネゲイドを取り戻すことだ。
目的の前には聖杯も、殺し合いも、このサーヴァントも全て手段に過ぎない。
絶対にエルムを人間の頃の身代わりのまま、人造人間のままではいさせない。
エルムを殺したのは自分の責任だから。エルムは自分の恋人なのだから。
人造人間の、偽りの恋人では終わらせない。
この場にいるマスター全員を皆殺しにしてでも聖杯を手に入れ、エルムを人間に戻す。最低でも、その糸口を掴む。
『少し長く、エルムを待たせることになりそうですね』
テレサは遠い、異世界の故郷に思いを馳せつつ、聖杯戦争について考える。
私の目的は、蘇ってクレアと共に暮らす事だ。
あの時、プリシラに情けをかけたばかりに私は殺され、こんな所で殺し合いの駒扱いされている。
あの後、クレアは一体どうなったのだろう。
イレーネたちに助けられたのか、覚醒したプリシラに殺されたのか。
もし後者なら、聖杯への願い事が一つ増えるわけだが。
それより、勝ち残った後の算段の前に決めなければならないことがある。敵マスターに関してだ。
私にはサーヴァントとしての基本的な知識がある。自分は魂の情報とやらから組み立てられた複製品というやつらしい。
つまりサーヴァントは人間では無いのだから、遠慮なく殺せる。
だが、マスターは人間だ。
もしサーヴァントと離れたマスターにばったり出くわしたら、私はそいつを殺せるだろうか。
クレアを助けるために盗賊共を斬り殺した時とは、状況が違う。
怒りではなく、誰かのためでもなく、自分の欲望で人間を殺すことになる。
それどころか、クレアとさほど歳が違わないマスターがいる可能性さえあるのだ。
そんなマスターを殺した時、クレアは私をどう思うだろう。軽蔑するだろうか、恐怖するだろうか。
だけど召喚された以上、もう後戻りはできない。ならば無用な情けは捨てよう。
何を犠牲にしても私は必ずあの地へ帰る。
私はクレアのために生きると誓ったのだから。
『クレア、私は必ずお前の元へ戻るよ』
エルムが死に、人造人間として蘇った瞬間から心が停止したままのアシュヒト。
クレアと出会い、重く沈んだ心が動き出したテレサ。
無表情のまま、エレベーターの階数表示板を見つめるアシュヒト。
腕を胸の前で組み、微笑を顔に浮かべるテレサ。
性も心も表情も、対称的な二人の抱いた思いは全く同じ。
『『どんな手段を使ってでも、何を犠牲にしても勝ち残る』』
それが両者の共通した決意だった。
【参加者No.20 アシュヒト=リヒター@エンバーミング】
【サーヴァント・セイバー(テレサ)@クレイモア】
*No.20
一人の少女が死んだとき、彼の心もまた死んだ。
彼の家は人造人間(フランケンシュタイン)創造の名門だった。
フランケンシュタイン。最初の創造主と最初に生み出された怪物の名前が混同されたその存在は、死体と電気の力を用いて創造される。
だが、人造人間は本人の死体を全て使って創造しても、生前とは必ず異なる。
記憶の障害か人格の変貌、またはその両方を起こし、生前とは別の存在になる。
人造人間として蘇った少女も例に漏れなかった。
彼は少女を人間に戻すと誓い、人造人間の研究を続け、欧州を駆け回り十年。
だが、いまだに解決の糸口さえ見えなかった。
そんな折、唐突に召喚された先での神父の言葉は、彼には新しい希望に思えた。
人造人間創造の技術では、もしかしたら死者蘇生は不可能かもしれない。
ならば、人造人間創造以外の技術なら?
自分をこの場に召喚した力なら?
死して後、三日後に復活を果たしたという主の力を宿した聖杯なら?
彼は迷信を信じない。宗教を信じない。本当に主が使った聖杯かどうかに興味は無い。
ただ、聖杯が自分を召喚したという事実を認めた。
それだけの未知なる力なら、あの神父が言うようにいかなる願いも叶うのではないか。
完全な死者蘇生、永遠の命の法を実現できるのではないだろうか。
それが彼、アシュヒト=リヒターの参戦した理由だった。
アシュヒトが右足の義足を鳴らし、扉を潜った先はビルの屋上だった。
周囲には自分のいるビルディングと同等か、それ以上の高さを誇る建造物が立ち並んでいる。
遠くに見える看板を輝かせる照明は、ガス灯ではない。電気の光だ。
周囲の建築物は高度な科学技術で製造されているようだ。そうアシュヒトは判断した。
「やれやれ、まるでウェルズのタイム・マシンに乗った気分です」
アシュヒトはため息をついた。どうやら自分は何百年か後の世界に来てしまったらしい。
「おい、そこのお前」
突然背後から投げかけられた言葉に向かってアシュヒトは素早く振り返り、手に持つトランクから特注の銃「鋼鉄の腕」を取り出した。
装填されているのは、対人造人間用帯電弾。発射時に微量の電流を発生し、人造人間のガルバーニ電流を狂わせ、肉体、機能を誤作動させる。
電流は人造人間以外に効果は無いが、50口径、12.7mmの弾丸は人体を容易に破壊する威力を秘めている。
アシュヒトは引き金に指をかけ、声の主に銃口を向けたまま姿を確認する。
声の主は剣士の格好をした白尽くめの女だった。
肩や腰などに装甲を付けた白いアンダースーツに、同じく白いマントを羽織っている。
その背には細身の身体に不釣合いな大剣を収めていた。年頃の女性としては異様極まる姿だ。
だが、最も異様なのは女の顔であった。
白磁よりも尚白い肌。暗闇で輝く銀色の瞳。ややウェーブのかかった白髪。
女の容貌に、アシュヒトは「人造人間か」と思った。
それほど女は常人離れした、高級なビスクドールの様な美しさをたたえていたのだ。
「なあ、お前が私のマスターでいいのか?」
容姿とは不釣合いな、おどけた拍子の声がアシュヒトに投げかけられる。
「私達の他に誰もいない以上、そういうことでしょう」
アシュヒトは銃の引き金から指を離し、トランクに収めた。
右手袋を外し、令呪を女に向けて見えるように手を掲げる。
「アシュヒト=リヒター。私の名前です」
「了解、マスター」
令呪を確認した女は、ひょうげた感じのままで軍人のように敬礼をした。
「サーヴァント・セイバー。真名はテレサ。
今後ともよろしくな」
「こちらこそ」
微笑を浮かべたサーヴァント・テレサの挨拶に対し、アシュヒトは手袋をはめなおしながら、淡々とした口調で返礼した。
「これから我々は一時パートナーを組み、聖杯獲得を目指すわけですが一つ質問があります。
あなたはどんな願いを抱いて、参戦を決意したのですか?」
「お前はどうなんだ? 引き返すチャンスもあったってのに、何でわざわざ殺し合いなんかしたがる?」
「質問を質問で返すのは……まあ、いいでしょう」
アシュヒトは眼鏡のブリッジを中指で押し上げた。
「私には生き返らせたい人がいます。どんな手段を使ってでも」
アシュヒトの回答にそうか、とテレサは呟き。
「私はな、生き返りたいんだよ。まだあいつに何もしてやれなかったからな」
微笑を崩さぬまま、自分の願望を口にした。
「さて、自己紹介も終わったしそろそろ行くとしようか。既に移動を始めている連中がいるしな」
「マスターの居場所が分かるのですか?」
「まあな、そいつは道すがら話すよ」
驚くアシュヒトを尻目に、テレサはビル屋上の出入口に歩みだした。
アシュヒトも後を追うが、テレサはアシュヒトを置いてさっさと出入口のドアを開けて中に入ってしまった。
「やれやれ……」
アシュヒトがビルの内に入ると、テレサはエレベーターの扉を前にして立ちすくんでいた。
「服装から想像がつきましたが、あなたも今より過去の時間から召喚されたようですね」
「時間というか、世界そのものが違うんだよ。
こんなもの、生きてた頃には見たことも聞いたことも無いぞ」
エレベーターの扉の傍にある複数のボタンをテレサは眺め、どれを押そうか指をさ迷わせている。
その姿をアシュヒトは無視し、下矢印のボタンを押して扉を開いた。
アシュヒトのいた時代は電動エレベーターが普及を始めた頃である。故に大体の使用法は、見当がついていた。
「おお、勝手に開いた」
「頭の悪そうな台詞です。そんな調子であなたは大丈夫ですか」
アシュヒトの容赦無い突っ込みに、憮然とするテレサ。
「いや、私はサーヴァントだから、この世界に関して知識が与えられているんだが……微妙に感覚がついてこないんだよな」
「戦闘でもそんな調子では困ります」
「分かってるよ」
「うおっ!? ……っと、ふうん。成る程、私達を入れた箱ごと下るのか。
いや、分かってはいるんだがな……」
エレベーターが下がり、身体が一瞬浮き上がる様な感覚に驚くテレサを、アシュヒトはじっと見つめていた。
「何だよ」
「いえ、別に」
あくまで無表情なアシュヒトに、テレサはそっぽを向いてふんと鼻を鳴らした。
「ところで先ほど話した、マスターの探索についてですが」
テレサのにが虫をかみつぶしたような表情を、アシュヒトは見てみぬふりをして尋ねた。
「ああ、そいつは」
と、テレサは気持ちを切り替え、自分の特殊能力について説明した。
テレサが他のマスター、サーヴァントを察知できるのは生前から所有していたずば抜けた能力、妖気感知が宝具として昇華されたためである。
その能力は半径数キロ圏内の魔力を感知し、相手の位置や魔力の大きさを探索できるというものだ。
さらに戦闘では、敵の魔力の流れを読み取り、動きの先読みを可能とする。
そこまで聞いたところで、アシュヒトが口を挟んだ。
「魔力はおおよそ見当がつきますが、妖気とは何でしょう」
「言ったろ、世界が違うって。私の世界では、妖魔って奴らが人を襲って喰ってたんだよ。
そいつらが発するのが妖気だ」
「するとあなたが背負った大剣から察するに、妖気感知ができるあなたは妖魔を倒す戦士だったのですか」
「……ま、そんなところだ」
テレサはわずかに言いよどんだ。アシュヒトは微妙な口調の変化に気付いたが、その理由をあえて尋ねようとはしなかった。
テレサの宝具は敵との戦闘、および他マスターの捜査に関して大きなアドバンテージとなるだろう。
今はそれが分かれば十分だ。
そうアシュヒトは思い、テレサとの話を打ち切った。
エレベーターが一階へと下る最中、アシュヒト=リヒターは改めて自分の願望を確認する。
私の目的は、人間のエルム=L=レネゲイドを取り戻すことだ。
目的の前には聖杯も、殺し合いも、このサーヴァントも全て手段に過ぎない。
絶対にエルムを人間の頃の身代わりのまま、人造人間のままではいさせない。
エルムを殺したのは自分の責任だから。エルムは自分の恋人なのだから。
人造人間の、偽りの恋人では終わらせない。
この場にいるマスター全員を皆殺しにしてでも聖杯を手に入れ、エルムを人間に戻す。最低でも、その糸口を掴む。
『少し長く、エルムを待たせることになりそうですね』
テレサは遠い、異世界の故郷に思いを馳せつつ、聖杯戦争について考える。
私の目的は、蘇ってクレアと共に暮らす事だ。
あの時、プリシラに情けをかけたばかりに私は殺され、こんな所で殺し合いの駒扱いされている。
あの後、クレアは一体どうなったのだろう。
イレーネたちに助けられたのか、覚醒したプリシラに殺されたのか。
もし後者なら、聖杯への願い事が一つ増えるわけだが。
それより、勝ち残った後の算段の前に決めなければならないことがある。敵マスターに関してだ。
私にはサーヴァントとしての基本的な知識がある。自分は魂の情報とやらから組み立てられた複製品というやつらしい。
つまりサーヴァントは人間では無いのだから、遠慮なく殺せる。
だが、マスターは人間だ。
もしサーヴァントと離れたマスターにばったり出くわしたら、私はそいつを殺せるだろうか。
クレアを助けるために盗賊共を斬り殺した時とは、状況が違う。
怒りではなく、誰かのためでもなく、自分の欲望で人間を殺すことになる。
それどころか、クレアとさほど歳が違わないマスターがいる可能性さえあるのだ。
そんなマスターを殺した時、クレアは私をどう思うだろう。軽蔑するだろうか、恐怖するだろうか。
だけど召喚された以上、もう後戻りはできない。ならば無用な情けは捨てよう。
何を犠牲にしても私は必ずあの地へ帰る。
私はクレアのために生きると誓ったのだから。
『クレア、私は必ずお前の元へ戻るよ』
エルムが死に、人造人間として蘇った瞬間から心が停止したままのアシュヒト。
クレアと出会い、重く沈んだ心が動き出したテレサ。
無表情のまま、エレベーターの階数表示板を見つめるアシュヒト。
腕を胸の前で組み、微笑を顔に浮かべるテレサ。
性も心も表情も、対称的な二人の抱いた思いは全く同じ。
『『どんな手段を使ってでも、何を犠牲にしても勝ち残る』』
それが両者の共通した決意だった。
【参加者No.20 アシュヒト=リヒター@エンバーミング】
【サーヴァント・セイバー(テレサ)@クレイモア】
----
|BACK||NEXT|
|019:[[No.19]]|投下順|021:[[No.21]]|
|019:[[No.19]]|時系列順|021:[[No.21]]|
|BACK|登場キャラ|NEXT|
|&color(yellow){聖杯戦争開幕}|アシュヒト=リヒター&セイバー|037:[[La Danse Macabre(前編)]]|
----
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: