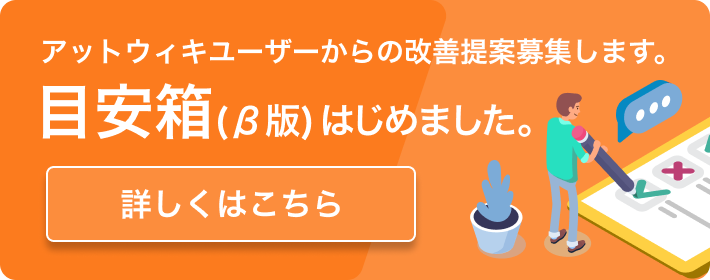「Last Phantasm」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「Last Phantasm」(2013/11/07 (木) 14:12:43) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
ここは地獄だ。
炎が舞い、瓦礫が散乱し、一帯にはむせかえるような血の臭い。
その地獄を作り出したのは自分であり相棒であり、目の前の敵だった。
「小僧よ、これで終わりだ。貴様はここで潰える」
目の前に立つ敵、この地獄をものともしない絶対王者が放つ冷たい宣告。
確かにそうだ、自分は力及ばず精魂尽き果てここに屍を晒そうとしている。
自分を導いてくれた男の援助を以ってして尚この覇者には一矢報いるのが精一杯だった。
ここで終わりか、そんな弱音をまるで他人事のように心中で吐き出した。
チリチリと脳が刺激される。さあ終わらせろ、お前には最後の牙があるだろう、と。
これを使えば自分は死ぬ、代わりに全身と心を苛む苦痛からも逃れられる、天国へ行けるのだ。
ああ、それは何と甘美な誘惑だろうか。
——————それで良いのか。
心のどこか、意識さえしていない声が聞こえる。
誰の声なのか、あるいは自分自身の声なのか、それすらも判然としない。
だがほんの刹那思い出した、あの暖かで充実した日々を、ここにいる友の事を。
自分があの男に敗れれば、その牙は友へと向けられる。
それだけは——————
「…俺は…終わる。でも…終わらない」
友情と忠誠、恐怖と信仰が心の中で入り交じる。
何となくだが、自分は今笑っているだろう。
何に対して、そもそもどうしてこの状況で笑えるのか自分でも最早判然とはしないのだが。
己の結末は変わらない、心の弱い自分では脳髄を刺激する命令(コマンド)には抗いようもなく、その気にもならない。
それでも、この末期の足掻きが遺す足跡が少しでも友の運命を変えられるのならば。
あの王者を勝利という栄光から引き摺り下ろすことが出来るのなら。
「勝つのはお前でも…俺でもない。勝つのは… …だ」
1 最後の絆
「ルルーシュ」
地下室の魔術工房の扉を開けようかというところでガウェインが耳打ちをしてきた。
どうやら鳴上悠が花村に渡したデータファイルの中身の解析と解凍に成功したらしい。
「わかった、ならば先に皆の前で公開した方が良いだろうな」
「よろしいので?」
「それが筋というものだろう」
有益なものとは限らないが花村に贈られたものである以上ルルーシュやガウェインが先に中身を見るべきではないだろう。
作戦会議がまだ終わっていない以上後回しにしても良いことかもしれないが、時には心の整理が論理を上回ることもある。
仲間たちにも話したところまずそのファイルの中身を見てみようという運びになった。
「解析に時間がかかってしまい申し訳ありませんでした。
このファイルには二種類のフォルダが格納されており、一つは大容量のメディアファイルでした」
「なあガウェインさん、それってここで再生出来るのか?」
「ええ、すぐにでも。キャスター、手伝っていただけますか?」
「わかった」
「始めるぞ」
ガウェインが手渡したデータファイルをキャスターが魔法で変換し、宙空にウィンドウを出現させるとノイズの走った映像が流れ始めた。
やがてノイズは少しずつ小さくなり鮮明な映像が映し出され、まるで誰かの視点を映しているような、誰かに抱えられているのかどこかを飛び回っているような光景が広がった。
ふと視点が動いた。この映像の視点の主が見上げた先にあったのは既に脱落した蒼い槍兵の姿だった。
その貌は狂気に染まってはおらず、理性ある歴戦の戦士のそれだった。
「なっ…ランサーだって!?」
「じゃあもう一人は、悠、なのか……!?」
士郎、花村の動揺を余所に映像の再生は続いた。
突然ランサーが悠(らしき人物)を道路に降ろし、どこからか飛来した光弾を手にした朱槍で打ち払った。
無数の弾幕を事も無げに全て切り払っていくが、ランサーの視線は既に光弾ではなくその奥を見据えているようだった。
『見えてねえとでも思ったか、間抜けが』
嘲りながら構えるランサーの眼前に現れたのは士郎らにとって因縁のある敵、ライダーのサーヴァントである仮面ライダーディケイドだった。
どうやらランサーはディケイドの存在をどのタイミングでかはわからないがキャッチしていたらしい。
銃を剣に変形させ迫るライダーに対処するべくランサーが前進する。
『ペルソナ!』
悠の叫びと共に、黒い人影が顕現した。間違いなくイザナギだろうと士郎は結論付けた。
悠がイザナギにアロンダイトを手渡す。どうやら時間的に士郎やルルーシュらと一戦交えた後と考えて間違いなさそうだ。
『マハタルカジャ、マハラクカジャ!』
「あれ、あいつのペルソナってあんな感じだったっけ…?
何か俺と戦った時とビミョーに違うような気がするんだけど……」
「そういやあれって悠が最初に使ってたペルソナだったっけか。
しばらく見ねえなと思ってたら、いつの間にか滅茶苦茶強くなってたんだよな」
補助魔法の恩恵を受けたランサーの槍撃がライダーの装甲を削っていく。
ライダーは時折反撃を繰り出すも大英雄クラスのサーヴァントに通じる筈もなく簡単に捌かれていく。
圧倒的なランサーの攻勢。だが直接刃を交えたセイバーやもう一人のライダー、火野映司には違和感を抱かせる光景でしかなかった。
「おかしい、ディケイドがこうも考えなしな戦い方をするとは思えない…」
「同感です、それに切嗣の姿が見えないということは……」
『決めるぞ、ランサー!』
悠がイザナギをライダーの背後に回り込ませ、ランサーと共に挟撃する。
先行したイザナギが矛とアロンダイトを振るう。仮面ライダーの装甲といえど宝具による一撃は無視できないのかライドブッカーで攻撃を弾く。
そこへ飛来するランサーの一撃。組んで数時間とは思えない連携から繰り出された必殺の槍は防げるものではない。
——————と思うようならば、仮面ライダーディケイドを甘く見ているとの謗りを免れまい。
イザナギの攻撃を受け止め態勢を崩されたにも関わらずライダーはそのままカードを取り出し腰のバックルに装填する。
恐らく直感のスキルによって自身がカードを装填する刹那の隙を見出したのだろう。
閃光。しかしその程度でランサーが追撃の手を緩めるはずもない、朱槍がライダーに直撃する。
しかしライダーも然る者、カブトに変身した事で装甲が増し命を刈り取るはずの槍撃を寸でのところで受け流すことに成功した。
『なんだ、このサーヴァント?』
『アーチャーかと思えば剣を振るい、更に姿まで変えるとは。面白い英霊もいたもんだな』
事前情報が無ければ驚愕に値するライダーの戦法にもランサーは怯む様子が無い。
むしろライダーが凌いだ事実を喜んでいる節すらあった。
『大した防御力だ。だが……遅い!』
しかしそれでも形勢は変わらない、むしろ悪化したと言ってもいい。
ランサーと悠の猛攻を凌ぐべく装甲の厚い形態を選んだライダーだが俊敏さが落ちている。
例え装甲が増したとしてもそれを貫く一撃を放てばいい、ランサーは手数を抑えて僅かな隙を見つけて溜めを作り、より強力な槍撃を見舞っていく。
また牽制の攻撃は全て肘などの関節部に向けて放っている。重装甲と動きの柔軟さは決して同居できないことをランサーは知っているのだろう。
更にイザナギも再びライダーの背後に回り挟撃の構えを取る。
だが。
乾いた銃声。その直後、映像の視界が大きく揺れた。
それを見てセイバーがやはり、と零した。切嗣が遠方から狙撃したのだろう。
「あっ……!!」
『悠ッ!』
花村の動揺と映像のランサーの叫びは同時だった。
誰もが鳴上悠の死を感じた次の瞬間、再び視界が大きく動き、狙撃手が映像に映った。
『切り札を使うまでも——』
『イザナギッ!』
悠の怒声に呼応してイザナギが狙撃手・衛宮切嗣目掛けて猛然と突進する。
切嗣は仕留めたことを確信していたのだろう、動揺が顔に表れている。
『っ……蘇生しただと!?』
「ちょっと待て!あいつ、一体どうやって立ち直ったんだ!?
蘇生魔術なんてものすごく高位の魔術じゃないか!」
「あ、思い出した!あいつ前にもやられたと思ったら当たり前のように飛び起きた事があったわ!」
『Time alter——double accel!』
しかし切嗣は我流魔術、固有時制御の加速でイザナギの剣戟から逃れキャレコを発砲し反撃する。
が、イザナギには傷の一つもつかない、銃弾の大半をアロンダイトと矛で切り払っているのもそうだがたまに命中しても効いている様子を見せない。
イザナギに物理耐性など無いが、単純にペルソナ自体の耐久性が銃弾の威力を遥かに超えているからだ。
だが、それでも尚切嗣はイザナギの攻撃を固有時制御を駆使して巧みに回避していく。
『マハ……ジオ!』
膠着した戦況に痺れを切らしたのか悠が属性魔法に訴えてきた。
どんなに速く動けようとも攻撃の範囲でカバーすれば良いと考えたのだろう。
それ自体は決して間違いではない、人間の身体は基本的に電撃に耐えられるように出来てはいないのだから。
だが士郎には一見妙手に見えるそれが完全な悪手であることがわかっていた。
切嗣が両手に持った銃を放り捨て一梃の拳銃をイザナギに向ける。
発砲、そして命中。たったそれだけのことであれほどの精強さを誇ったイザナギは影も形もなくなった。
あまりの事態に花村は勿論ルルーシュや名無ですら開いた口が塞がらないといった様子だ。
『……イザナギ?…っ、ペルソナ!出ない!? ぺ……ペルソナ!』
必死にペルソナを出そうとする悠の声も虚しくイザナギが再び顕現する様子はない。
そうこうしているうちに切嗣は余裕を持って放り捨てた銃を拾い、悠との距離を詰めていく。
にも関わらず悠が動く様子はない、そのまま眼前に迫った切嗣に短機関銃の銃把で殴られ映像の視界が大きく動いた。
『がぁっ……』
『悠!』
『おっと、お前の相手は俺だ』
ふと、視点の主が変わった。ランサーのものだろう視界の中で、一瞬の隙を突きライダーがバックルにカードを装填する。
次の瞬間ライダーの装甲が弾け飛び鈍い音とともに視界が揺れた、どうやら背後から攻撃されたらしい。
ランサーも懸命に反撃するが今のライダーには全く通用しない。
補助魔法の効力が失われたせいだろうがそれにしても動きに精彩を欠いている、明らかに本来の力を出せていない。
「何だこれは?ディケイドが速いのは認めるが明らかにランサーが弱くなっているぞ」
「…多分今の切嗣の弾丸で魔力供給を絶たれたんだ、あれは撃たれた相手の魔術回路に意図的にフィードバックを起こして暴走させる効果がある。
鳴上に外傷が無かったのは普通の魔術師とペルソナ使いじゃ勝手が違ったってことだと思う」
『さっきは好き放題やってくれたな。今度は俺の番だろ?』
『てめえ、どきやがれ!』
サーヴァントの性能はマスターからの魔力供給あってこそ発揮される。
例えカタログスペックが優れていようとマスターからの供給が乏しければすぐに魔力は欠乏し加速度的に力は落ちていく。
今のランサーはまさにそれ、供給元を絶たれればさしものクー・フーリンも十分な力は出せない。
例えペルソナの補助が無くなったとしても魔力供給さえ健在ならばこうまで一方的にはならない。
『ペルソナ! イザナギ! 出ろ、出ろ……イザナギッ!
ペルソナ、ペルソナ! ペルソナ……! どうして……!? 俺の……イザナギィッ!』
『無駄だよ。君はもう、空っぽなのさ』
再び視点が悠に戻る。壊れた機械のように呪文を紡ぐ悠に誰もが同情と憐憫の念を禁じ得なかった。
特に花村などは信じ難いといわんばかりだ、彼にとっての鳴上悠とはいついかなる時でも頼れるリーダーだったからだ。
あの空間での会話で悠が何を思ってこの戦いに参加したか知ってはいても、心を折られる瞬間を見せつけられて動揺するなという方が酷であろう。
『失ったものは戻らない。死んだ人間はもう帰ってこない。君の魔術は、もう使えない』
『から、っぽ……?』
『そうさ。僕と同じだ』
『戻らない……もう、いない……俺の、ペルソナ……』
「爺さん…」
「っ………!!」
「目を逸らすなマスター、これは我々にも起こり得たもう一つの未来だ」
『空っぽ……俺は……俺には……何も、ない……。
違う……俺は……! 空っぽじゃない! 俺には、まだ……!』
『違わないさ。その幻を抱いて……溺死しろ』
「あ……ゆ、悠!!」
銃弾の装填を終えた切嗣が悠に照準を合わせている。
だが悠に動く様子はない、ショックからまだ立ち直れていないのだ。
無意味と分かっていて花村が立ち上がった、まさにその瞬間の事だった。
『避けろ、マスターッ!』
ライダーには似つかわしくない切迫した叫び声。
すると悠の視界の向こう側、切嗣の背後につい先ほど相対したばかりの人物が飛び込んできた。
左腕の肘から先が消えていて、先ほど見た奇妙な義肢も無いがそれは紛れもなく枢木スザクその人だった。
「スザクだと!?このタイミングで何故……そうか!」
『Time alter——double accel!』
ルルーシュの呟きを余所に事態は加速していく。
切嗣は固有時制御を発動して急速に後退、スザクがその後を追っていく。
それ以上は悠の視界を通している映像故に何もわからなかった。
再びランサー視点。映像にはいつの間にかバーサーカー、ランスロットが参入しランサー、ライダー、バーサーカーによる膠着状態が形成されていた。
ふと映像の外から放られたアロンダイトをバーサーカーが受け取る。
それを隙と見たかライダーが二体を同時に相手取るための一手を打つ。
カメンライド《龍騎》——ファイナルフォームライド≪リュウキドラグレッダー≫。
この場に集う面々は知識として知っている赤竜をバーサーカーに差し向け自身はランサーへと向かっていく。
だが同時にこれがこれ以上ない悪手であることもまたここにいる全員にとって周知の事実であった。
僅か数秒後、突如としてライダーの形態が龍騎から元のディケイドに戻った。
動揺している様子からそれが意図して起こったものでないことは明白だった。
『俺の力を……!?』
ランサーの眼を借りた映像の視界が動くとそこにはドラグレッダーを支配し、そこらの鉄柱を即席の宝具に変えたバーサーカーの姿があった。
ライダーが立ち直るより早くバーサーカーが赤竜ならぬ黒龍、ドラグブラッカーに漆黒の火炎を浴びせかける。
跳躍して躱したライダーの動きを読んでいたかの如く眼前に移動したバーサーカーの鉄柱がライダーを打ちつけ地に叩き落とす。
『貴様か……ハッ、二度は逃さんぞ!』
バーサーカーがライダーを攻撃したその間隙をランサーが見逃すはずがない。
隙を突いた状態ならば弱体化した彼でも戦えると考えたのだろうが現実は非情である。
狂っているとは思えないほどの武技の前に数合で敗れ吹き飛ばされる。
これはセイバーの予想だが供給途絶による弱体化さえなければ渡り合うぐらいのことは出来ただろう。
ライダーには無理だがランサーにはそれが可能なだけの技量が本来あるのだ。
『借り物の力で……調子に乗るなよッ!』
『待て、ライダー! それは……』
『バーサーカー!』
頭に血が上っているのか怒りの赴くまま切り札———恐らくコンプリートフォーム———を解き放とうとするライダーにそれを制止する切嗣の声を尻目にスザクは地面に這い蹲った悠を担いでドラグブラッカーに乗り逃走を図る。
映像の視界を見る限りランサーも追いかけようとはしたようだがすぐにランサーの跳躍力でも飛び乗れない高度に達してしまった。
弱体化がここでも尾を引く形になったらしい。
『退く……のか?』
『逃がすかよ! 龍騎だけでも取り返す!』
切嗣とライダーがバーサーカーに気を取られランサーへの注意が疎かになっている。
怨敵を仕留めるためか、バーサーカーよりもまずは切嗣へと襲いかかる。
目に見えて動きが速くなっている様子からして供給の途絶から立ち直りつつあるのかもしれない。
『いただく——』
『させ……るかああぁッ!』
『でぃぃぃやっ!』
『俺! 参じょう……あれ?……な……なんだこりゃぁぁっ!?』
それは一瞬の出来事だった。
ランサーの槍が切嗣を捉えたと誰もが思った次の瞬間ランサーの前にライダーとファイナルフォームライドで召喚されたと思しきモモタロスが現れ、そして朱槍に胸を穿たれていた。
この映像からは死角になっているが恐らくライダーがクロックアップで先回りしたのだろう。
『凌いだだと……!ここまでか……ライダー、この勝負預けておくぞ!』
防がれたランサーだがその後の行動は迅速だった。
一瞬でその場を離れ探知のルーンと思しき魔術を使ってバーサーカーの後を追っていく。
そして、またも視界が入れ替わった。
『…あ、あんたは?』
『僕は枢木スザクだ、わかっているだろうがここにランサーが来られるとは思わないことだ』
そこは街の上空だった。恐らく強奪したドラグブラッカーの上に乗っているのだろう。
声音からして完全に憔悴している悠だが状況を理解していないわけではなかったらしい、腕を翳して令呪を使おうとする。
『ラ、ランサー……!』
『待て、やめろ!態度次第だが君をここで殺すつもりはない。
もしそうならこんな回りくどい真似をせずに君を殺している。
君に聞きたいことがある、君らは僕のバーサーカーと交戦したな?
その時の右足の傷が治らないのはどういうことか教えてくれ』
言い方こそ穏当だが誰がどう見ても拒否が出来る状態ではない。
状況のせいか、あるいは精神状態のせいかはたまた両方か、悠はバーサーカーとの交戦からこの時点までの出来事を不必要なまでに詳細に話した。
あるいは話しても良い情報とそれ以外の区別さえつかなくなっていたのかもしれないが。
『…お、俺にどうしてほしいんだ?』
『僕らと共闘してほしい、いくら君らが強くても柳洞寺にいる敵とまともに戦えないことぐらいもうわかっているだろう?
数に対抗するにはこちらも数を作るしかない、それに同盟することでそれ以外の敵にも対処しやすくなる、悪い話ではないと思うが?』
『それは…確かにそう、だけど……いや、わかった』
『ただし条件は付けさせてもらう、ランサーに令呪で“現在より四十八時間、鳴上悠のサーヴァントは枢木スザクとそのサーヴァントに対し攻撃を禁ずる”と命じてもらう』
『なっ……!?そんなこと、出来るわけ……』
『ならこう付け加えるのはどうだ?“ただし、枢木スザクとそのサーヴァントから攻撃を受けた場合は、以上の誓約を一方的に破棄する事ができる”と』
ルルーシュから見ればかなり甘い条件を付けられても悠は何とも言わない。
痺れを切らしたのかスザクはやおら悠の胸倉を掴んだ。
『無理だというならそれでも構わない、ここで死んでもらうだけだ。
そもそもこちらの都合とはいえ命を助けてもらって何の対価も支払わずに済むとでも本気で思っているのか?
ああ、令呪でランサーを呼んでも別に良い。そうしたところで今の君らに僕とバーサーカーが敗北する可能性など万に一つもないし仮に僕らから逃げられても君はやはり令呪を一画失うだけだ。
そしてそうなれば君らは単独で、弱ったまま僕やさっきのマスターと戦わなければならないというわけだ、ここまで言ってもまだどちらが得かわからないか?』
『うっ……わ、わかった』
スザクの迫力に押されたか悠は承諾の意思を示し、そこから徐々にノイズが濃くなっていった。
これで映像は終わりかと思ったがガウェインとキャスターは首を横に振る、どうやらまだ続きはあるらしい。
「やっぱり…切嗣はイリヤが死んだから後戻り出来なくなっちまったんだな」
「…そうですね、彼が敵マスターに対してここまで饒舌になったところは私も見たことがない」
もし切嗣を説得出来る可能性を持つ者がいるとすれば、それはイリヤスフィール・フォン・アインツベルン以外に有り得ない。
彼女が死に、その事実を切嗣が認知した時点で言葉で切嗣を止める術は永遠に失われた、そう悟らざるを得なかった。
しかし、だとしても今の士郎には決して死を受け容れるわけにはいかない理由がある。
大切な人がいる、帰らなければならない場所がまだあるから。
——————裏切るのか。
怨嗟の声が聞こえた。多くの人々の声だった。
在りし日の、幼い日々を共に過ごした切嗣がいた。あの大火災で見殺しにした人々がいた。
自らと起源を同じくする赤の弓兵がいた。桜を救うために見捨てた人々がいた。
——————お前は贖罪もせず、またのうのうと生き残る道を選ぶつもりなのか。この裏切り者が。
「———ああ、裏切るとも」
目を閉じ、あの日のように衛宮士郎はまた彼らを切り捨てた。
誰かを愛し守るということは他の誰かを救わないということ、この瞬間士郎の中で初めて衛宮切嗣は明確に乗り越えるべき対象に、倒すべき敵となった。
衛宮士郎は間桐、いや遠坂桜をこれからも守っていくために衛宮切嗣という正義の味方を切り捨てた。
目を開けた時にはもう声も、誰かの幻影も消えていた。
「それにしてもおかしくないか?枢木がディケイドの龍を奪ってたなら何でさっきの戦いで使ってなかったんだ?」
「だよなあ、大体あいつと切嗣っておっさん、本当に同盟なんかしてるのかよ。
あんなの俺が見たって敵にしかならなさそうに見えるんだけど」
「いや、これがバトルロイヤルである以上接触したという事実こそが重要なのであってその過程自体は…まあどうでも良いとまでは思わないが利害の一致を超えることはそうないだろう。
それに今の映像でスザクは柳洞寺にいた俺達を敵と見倣し鳴上悠と同盟を結んだ。
だがこれだけでは片手落ち、恐らくだがこの後鳴上とランサーの戦力を盾に衛宮切嗣にも共闘を持ちかけ、いいや迫っただろうな」
しかし、とルルーシュは同時に考える。
この映像が真実でスザクが切嗣とも同盟していたのならば何故昼間に切嗣は完全に単独で仕掛けてきたのか。
何故それまでの間自分達は放置されていたのか、数秒のうちに十通り以上のパターンを考え出した。
「だが結局三者同盟による柳洞寺攻略は為されなかった、いや出来なかったんだ。
衛宮切嗣にとって鳴上悠が仇敵である以上同盟の主軸はスザクになるしかない。
要するに———この後すぐにディケイドから奪った黒龍も生身だった手足も失うほどの事態に見舞われた、というわけだ」
そしてそれだけの事を可能にし、かつ深山町で活動していた可能性の高いチームは限られる。
最も可能性の高いのは冬木の御三家の出である間桐慎二とそのサーヴァントである拳王ラオウだ。
推測だが拳法使いならば武器を宝具化するバーサーカーに対して有利に戦えるかもしれない。
「映像を見る限りスザクが鳴上を脅していたのは上空、しかも巨大な黒龍に乗って魔力の塊である令呪まで使わせた。
…これで他陣営のサーヴァントに補足されないと考える方がどうかしている、見つけてくれと言っているようなものだ」
旧友の考えがあるのかないのかよくわからない行動に頭を抱えながらそう結論づける。
「キャスター、そもそも鳴上はどうやってこの映像をデータファイルに残したんだ?
お前が魔法で何か細工でもしたのか?」
「いや、いくら私でもそこまではさすがに出来ない。
恐らく鳴上と、皆の前には姿を見せなかったようだがランサーも協力したんだろう、自分を構成する情報からこちらに有益なあの映像をピックアップして形にして残したんだ。
…恐れ入るよ、あと僅かで完全に消えてしまうという時に誰かのためにそこまで出来るんだからな」
感慨深げに話すキャスターが見つめる先には花村がいる。
鳴上悠は親友が自分の二の舞にならない事を願ってこのデータを託したのだろう。
そう思っていた時、再びノイズが薄れ映像が鮮明になりだした。
もうすぐ陽が昇ろうとする時間帯、映像の視界は上下に大きく揺れている。
視界の主は鳴上悠なのだろう、顔を上げた先には傷ついたランサーがいる。
先ほどのような余裕はもうない、サーヴァント全員から見てただ脇目も振らずに飛んでいっているように見えた。
『…ランサー、本当にこれで良いのか?
今あいつらから逃げたって、他の敵に見つかったらどうしようも…』
『あのな、このまま素直に言うこと聞いたところで体よく使い捨てられて終わりだろうが。
しかもこっちはオレの真名まで知られてるってのに向こうのサーヴァントは真名はおろかステータス一つわからんときた。
あのバーサーカーのマスターがオレらを自由にするなんて間抜けを晒した今しか逃げ切る機会はねえんだよ』
映像の悠はよほど酷い顔をしているのだろうか、ランサーの声音はどこか張り詰めている。
恐らくこれまでもこうして迷っているマスターを叱咤してきたのだろう。
『とにかくだ、朝までどうにか逃げ続ければ襲われる可能性は相当減るはずだ。
こっちは神秘の秘匿なんて原則があるわけでもないが、進んで目立つ真似をしたがる酔狂なマスターはそういねえだろう。
動くのはその後でいい、今のお前さんには一旦落ち着いて考える時間が必要だ』
ランサーの言葉の直後に視界が微かに揺れる、どうやら悠が無言で頷いたらしい。
だが花村をはじめとしたこの場の面々の表情は暗い。
何故なら彼らはこの後の悠とランサーの辿る路を知っているのだから。
と、彼らの横を何かが通り過ぎた、自動車だった。
『ラ、ランサー!!』
『チッ、言ったそばからこれか!オレの運の悪さも大したもんだな…っと!』
ランサーが朱槍を一閃し、車を両断した。
しかし車は無数に飛んでくる、埒があかないと判断したのかランサーは悠を抱えたまま道路へと降り立つ。
『悠、一度地下に潜るぞ。当然奴さんは追いかけてくるだろうからお前は隠れてろ』
『あ、ああ…』
何者かが投げつけた自動車が飛び交う中ランサーは俊敏な動きで地下街に入っていく。
そして立ち入り禁止区画のドアの鍵を壊し、そこに悠を押し込みそのままランサーは立ち去った。
ペルソナを失っている今の悠ならば魔力探知で発見はされないという読みがあったのだろう。
『お、俺、は…俺は…空っぽ、なんかじゃ……!』
もしランサーに誤算と呼べるものがあったとすれば、それはランサーが思うより悠の心の傷が深かったことだろう。
間もなく悠は飛び出し、脇目も振らず走っていく。
恐らくだがランサーとのレイラインを辿っているのだろう、その動きには一切の迷いがない。
なまじ戦う力があっただけに無力な自分に耐えられないか、という感想をアレックスが心中でのみ漏らした。
『ほォう——殊勝ではないか。私を迎え撃とうというのか、ランサーよ。
マスターを隠して一騎打ちとは——古風ではないか。見た目通りの騎士ということか」
『そういうキサマはマスターを伴っておらんな——そして先程の攻撃——なるほど、アーチャーか』
地下の広場、サーヴァントが存分に戦うに相応しい闘技場でランサーと襲撃者ことアーチャーが対峙していた。
二人とも隠れて様子を覗き見る悠に気付いた様子はない、それだけ目の前の敵に神経を集中しているのだ。
と、突然こなたが天啓を得たかのように立ち上がった。
「ああ!この人だよ、この金髪の人がDIOだよ、うん、絶対間違いない!」
「マジか!?ってことはこいつが……!」
握り拳を作り怒りに身を震わせる花村にかける言葉を誰も持たなかった。
知り合いを殺される辛みは士郎やルルーシュには特によくわかる。
『ンン——気に入らんな。ランサーよ、キサマは今この私を——この悪の帝王を見下したか?」
『はっ、自分で帝王だなんて名乗ってりゃ世話ねぇな。キサマはせいぜい裸の王様というところだろうぜ』
『——よかろう、ランサーよ。キサマは——八つ裂きにして犬の餌にしてくれる!』
お互いに挑発の応酬、やがて———アーチャーが先に仕掛けた。
『そォら!』
五指に握ったナイフを一斉に投げ放つ。
だが矢よけの加護を持つランサーに対して効果はない、容易く突破されランサーが逆襲の刺突を放つ。
『ヌ——!』
『これで——』
『——勝ったと思ったか、ボケがッ!』
アーチャーの心臓目掛けての突きを身体を捻って回避、しかし完全にとはいかず胸板に一条の傷がつく。
この機を逃さずランサーが追撃を仕掛けるが、それは虚空より出現したペルソナに酷似した筋肉質の虚像によって阻まれた。
だが、ここにはその虚像を視認できた者とできなかった者がいた。
「何だ、槍が急に止まっただと?」
「おいおい何言ってんだよ、思いっきりスタンドっぽいやつが槍を止めてるじゃねえか」
「あ、やっぱ花村にも見えてんだなあれ、衛宮はどうよ?」
「ああ、俺にも見えてるぞ」
「うー…私は見えないや、これが一般人と超能力者の差か、はっきりわかんだね」
サーヴァントには揃ってスタンドの姿が見えているがマスターに関してはまばらだ。
花村、名無、士郎の三人には見えているがルルーシュ、こなたには見えていない。
『ザ・ワールド——』
『こいつは——!?』
『無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄ァァァァァ——!』
『ぐうっ——!』
アーチャーのスタンド「世界」はクロスレンジの格闘戦を得意とする。
至近距離にまで踏み込んだランサーに対しての奇襲としてはこれ以上ない効果を発揮し、数十発もの拳打を命中させて彼方に吹き飛ばした。
だがランサーは怯まない、あるはずの激痛を感じさせない動きで立ち上がった。
『テメエ——本当にアーチャーか? 格闘戦に対応した心象具現化とはな。
まったく、俺が会うアーチャーは変な奴ばかりだぜ』
『むう——血が止まらん。 ランサー、キサマのその槍。
そして私のナイフをすべて躱すとは——』
両者は互いの力について不可解なものを感じたようだがそれで怖じ気付くはずもない。
むしろ様子見は終わったとばかりに再度対峙した。
『ナイフ——違うな。察するなら飛び道具を無効化するスキルでも備えているか。チィ、生意気な』
『手負いと思って油断したか? だがアーチャー、キサマは俺と相性が悪いようだ——
二度も同じ手は食わん。その首、いただくぞ』
『首——首か。面白い冗談だ、ランサー。この私の首を取るだと? だが、あいにく——』
アーチャーが再び「世界」を具現化させるもランサーは構わず突っ込む。
「世界」のスペックを一度で見切ったが故の行動だろうが、士郎や花村たちマスターには映像に映るアーチャーのステータスが見えている。
明らかに上級クラスの能力値を誇るアーチャーがたかがナイフを投擲するだけに終わる筈がない、「世界」を左に回り込ませ自身は右に跳んでランサーを挟撃する。
『フン、小癪な真似を。だがキサマ、生身でこの俺に敵うと——』
『無駄無駄無駄無駄——』
『む!?』
『無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄————』
『き、キサマ——!?』
『無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄——————』
そう、アーチャーのサーヴァント、DIOは吸血鬼。
例え生身といえど常人を遥かに超越した身体能力を有するアーチャーに本体を叩くというスタンド使いの戦いのセオリーは通用しない。
生身のアーチャーの力を侮ったランサーの槍撃をごく短時間食い止めるだけならば決して不可能ではない、両手の五指に握ったナイフでランサーの槍を捌く。
そして一瞬で倒されることさえなければ事足りるのだ。
「世界」がランサーの背後から迫り、次の瞬間映像を見ていた———恐らくは戦いを肉眼で見ていた鳴上悠にとっても———信じ難い現象が起こった。
『——ふるえるぞハート! 凍りつく ほどクール!
WRYYYYYYYYYYYYYYYYYY!! 刻んでやろうッ! ザ・ワールドのビートッッ!!』
DIOがそう口にした直後、全身を痛めつけられ崩れ落ちるランサーの姿があった。
戦闘続行のスキルにも限界が存在することをもう一人のアーチャー、ジョン・ドゥと戦ったアレックスは知っている。
『——そして時は動き出す』
『なん……だと……? 』
『すまんな、ランサーよ。このDIO、今のボディを捨てる気はないのでな。首をとられるわけにはいかんのだよ』
「これが時間停止、わかってはいたが凄まじいものだな」
「一対一では敗北は必死、しかし向こうが数で攻めてくる以上多数で囲む戦法も使えないか…」
「………」
この場にいるもう一人のライダー、火野映司が歯を食いしばり拳を握り締めている様をこなたが複雑な面持ちで見ている。
生前仮面ライダーオーズが使用できた未来の技術を用いたコンボ・スーパータトバ。
スーパータカ、スーパートラ、スーパーバッタのコアメダル三枚からなるこの形態はオーズが持つ他の形態を超える力に時間停止能力さえ持っている。
だがその力をこの聖杯戦争で振るうことは有り得ない。
今回の聖杯戦争においてスーパータトバに変身するためのコアメダルを持ち込むことが叶わなかったからだが、しかしてその制約は当然のものでもあった。
ただでさえも多数の形態と能力を保有しコアメダルの力による低燃費まで併せ持つ彼がスーパータトバの力まで行使できるとあってはもはやゲーム自体が成立せず、マスターの資質や人格を無視して容易にほとんど全てのサーヴァントを打倒出来てしまうからだ。
アーチャー、DIOも時間停止能力を有してはいるがあちらには日光という明確な弱点が存在する上にオーズほどの汎用性もない。
月の聖杯戦争においてマスターを添え物同然にして勝ち進むサーヴァントは必要とされない。
もしオーズがスーパータトバに変身するためのメダルを所持したままなら、彼は英雄王ギルガメッシュと同じように月の裏側に封印される憂き目に遭っていただろう。
『よくやったと言ってやろう、ランサーよ。まさかここまで私を手こずらせるとはな。だが——』
『ランサァァァ——!』
「あっゆ、悠っ!?」
視界が動く、ランサーを救うためか鉄パイプを拾った悠が無謀な特攻を仕掛けた。
だが当然にしてサーヴァントに通用するはずもなく、あっさりと受け止められ鉄パイプがぐにゃりと曲がる。
『ほう、ランサーのマスターか。サーヴァントの危機にいてもたってもいられず——というところかな?』
『あ——ああ——』
『無謀だったな、ランサーのマスターよ。
だが心意気は買おう——その眩しいほどの勇気に免じて』
『何を——してやがる! アーチャァァァ— —!』
『私が君を——天国に連れて行ってやろう』
『や、やめ——あぁっ!』
悠の抵抗をものともせずアーチャーが悠然と吸血鬼の牙を首筋に突き立て血液を吸い上げる。
だが悠は死亡しなかった、不可思議そうな表情のアーチャーがすぐに牙を放したからだ。
『——Um? これはなんだ——マスターだからか? いや、違う——まさか——』
『うあぁっ!?』
『ほほう、これはこれは——なるほど——』
二度三度と血液を舐めた後、何か得心を得たのか破顔した。
『ふ——フハハハハハ! なるほどなるほど、そういうことか! スタンド使いは惹かれ合う——』
『あ——え?』
『私と君は! ここで出会う運命だったのだな! ハハ、ハハハハハハハ!』
『な、何を言ってやがる——?』
『ランサーよ、喜ぶがいい! 私はお前を殺しはせん。
君のマスターは——これから私の友人 となるのだからな! フハハハハハハハハハ!』
悠の後ろにいると思われるランサーにアーチャーがニッコリと微笑む。
そしてアーチャーの掌からボコリ、という嫌な音とともに肉の塊———間違いなく肉の芽———が生み出される。
『悠——!』
『ロードローラーだッ!』
『おおおおおおおおぉぉっ!』
悠の背後では轟音と共にアーチャー、いや「世界」とランサーの応酬が繰り広げられているのだろうがそれは悠の視点では見ることが出来ない。
そしてそうしている間にアーチャーは悠然と肉の芽を悠の額に埋め込んだ。
「悠っ!悠ぅぅぅっ!!」
「ええい、落ち着けマスター!これは過去に起こった事だ、もう変えることなど出来ん!」
「わかってるよ!わかってっけど…ちくしょう!!」
画面に手を伸ばそうとする花村をアレックスが羽交い締めにして取り押さえる。
あまりの形相にキャスターが一旦映像の再生を中断しなければならなかったほどだ。
しばらくしてようやく落ち着いたものの、やはり顔色は優れない。
「大丈夫かよ花村?」
「辛いのならば最後まで見る必要はありません、それを咎められる者などここには一人もいない」
「…いや、大丈夫なんかじゃねえけど最後まで、見るよ。
あいつが遺してくれたものなんだ、どんなにキツくたってそこから目を逸らすなんて死んでも御免だ」
花村の様子が不安ではあるがだからといっていつまでも中断しているわけにもいかない。
心配そうに見ていたキャスターだが心を鬼にして再度映像を再生する。
『悠——?』
『悠、というのか、君は——もっと君のことを知りたいな。教えてくれないか?』
「はい、DIO様。俺の名前は鳴上悠です」
わかっていたことだがそこには残酷な現実があった。
肉の芽の洗脳が完了した悠はさも親しげにアーチャーと手を取り合っている。
花村のみならず、ここにいる全てのマスターとサーヴァントにとって吐き気すら覚える光景だった。
『槍を向けるな、ランサー。我らはもう敵ではない』
『何を言ってやがる! 悠、そいつに何をされた!?』
『落ち着け、ランサー。もういいんだ。戦う必要なんてない』
映像の中で最も正常であろうランサーの叫びこそがまるで場違いなものであるかのような異質な状況だった。
怒り猛るランサーにアーチャーが勝者の余裕そのものの笑みを持って答える。
『うん? これが疑問かランサー。これはな、私の体の一部だ。
こいつで少し、脳を押してやるとだな——なんと! 私と友人になれるのだよ!』
『そうなんだ、ランサー。DIO様は敵じゃない。DIO様は俺たちを天国へと連れて行ってくれるんだ』
『なに——言ってるんだ? 悠?』
『ランサー、俺たちは間違ってたんだ。DIO様に歯向かうなんてどう かしてた。
こんな戦いで優勝しなくたって、DIO様が俺たちの願いを叶えてくれるんだよ』
「悠…、くそっ、あの野郎……!!」
悠の視点であるために映像の彼がどんな表情をしているのか正確にはわからない。
けれどランサーの顔を見れば容易に想像できる、恐らく新都で会った時のような、洗脳されていることに何の疑問も抱いていない微笑を浮かべているのだろう。
少なくとも確実に言えるのはこの肉の芽で洗脳された者は心の底からアーチャーを友と認識してしまうということだけだ。
あのサーヴァントは断じてマスターに近づけてはならない、というのがこの場の全サーヴァントの総意であることは言うまでもない。
『悠を——支配しやがったのか——!』
『人聞きが悪いな、ランサー。なあ悠、私と君は——友達だよな?』
『はい、DIO様。あなたの言うとおりです』
『なあ、悠——私は疲れた。少し休みたいのだが——
この街は人が多くて騒がしい。そうは思わないか?』
『その通りです、DIO様。俺が——俺とランサーが、他のマスターを間引いてきます』
『ユウゥ——君は素晴らしいな。私の望みを、口にせずとも察してくれる。
君こそ私の親友、いや心の友だ』
あまりにも白々しいアーチャーと悠の会話だがランサーを絶望させ、その怒りを買うには十分すぎるほどの効果があったらしい。
今やランサーの視線は常人はおろかそこらの達人さえ眼だけで殺せそうなまでの憎悪を湛えていた。
だがアーチャーに動じた様子はない、そればかりかさらにランサーを煽ってみせる。
『アーチャー、許さねえ——キサマ、必ずこの俺が——!』
『ランサー、一つ忠告しておこう。この肉の芽は——私を殺しても外すことはできんぞ』
『な、に?』
『この肉の芽は私の魔力をエネルギー源としている。私を殺せば—— 魔力を絶たれた肉の芽は、新たな餌を求めて宿主を食らう——わかるか?
暴走、するのだよ。脳に留まっていた肉の芽は全身にその触手を伸ばす——
さて、そうなったらどうなると思う?
死ねるのならまだ運がいい。記憶も、思い出も、すべて失って——
哀れな、ブタ以下の獣になる。ランサー、君はマスターを獣に貶めたいのか?』
『——キサマ』
そう、肉の芽の凶悪な部分はそこだ、例え本体たるアーチャー自身を倒したとて宿主を解放することは決して出来ない。
そればかりか人間ですらない怪物へと変貌してしまう悪魔の如き異能の力だ。
当然こんな話を聞かされてランサーが賭けに出られるはずもない。
『まあ、この聖杯戦争には高ランクの対魔力宝具を持つサーヴァントもいるかもしれん 探してみるかね?
それもいい。だが——悠。君は肉の芽——
私との絆がなくなることを願うだろうか? だとしたら、私は悲しい——』
『DIO様、それはありえません。俺はDIO様の部下——
この肉の芽は誇りです。手放すことなんて決してありえない』
『フ——安心したよ、悠。
ならば君の忠誠に——私も報いねばならないな』
何を考えたかアーチャーが再度悠の手を取る。
するとそこには花村と名無らにとって見覚えのある虚像が出現した。
『——イザナギ!』
『それが君のスタンド——いや、ペルソナ、か。 やはり私の感じた通り——君と私は惹かれ合う運命だったようだ』
『DIO様——感謝します。この力で、俺は——』
「ああ、あいつだ!俺らと戦った時のあいつのペルソナ!」
「やっぱりあのアーチャーの仕業かよ…クソッタレが!!」
普段非常に温厚な花村からは想像できない罵倒に誰もがこの時同意した。
見れば誰にでもわかる、あれは悠とアーチャーの間にある絆、そのマガイモノの結晶なのだと。
とはいえその力そのものは悠の中に眠っていたものに違いなく、また肉の芽には宿主本来の力を忠誠心と引き換えに弱めてしまう効果もある。
それでいてあれほどの脅威だったのだから悠の潜在能力の高さがよくわかるというものだ。
そして悠の言葉と共に映像には再び濃いノイズが走りだした。
「……お、おい花村、本当に大丈夫かお前?」
普段はどこまでもマイペースな名無が恐る恐るといった様子で花村を気遣う。
事前にわかっていた事とはいえさすがにこれは堪えたのではないだろうか、と。
花村もしばし険しい表情を作っていたが、やがて両手でパンと顔を叩いて真顔で全員へと向き直った。
「悪い、心配かけた。けど俺はもう大丈夫だ。
ただ…アーチャーは絶対に俺とアレックスにやらせてくれ」
「同感だマスター、奴の相手だけは他の誰にも譲れん」
「ああ、勿論だ。だが花村、皆の輪を乱して前線に出るようなことは———」
「わかってるって、そこまで馬鹿な真似はしねえさ」
いつも通りとまではいかないまでも単なる怒りや空元気ではない確かな意志を持って強く頷いた。
目には見えない一つの大きな壁を乗り越えた者の顔だった。
「ともあれこれでDIOのデータは基本ステータス、対魔力スキルのランク、容姿や声に具体的な戦闘スタイルまで含めて全て揃ったな。
これは極めて大きい、まさかつい一日前に殺されかけた相手に感謝する時が来るとはな」
「ああ、少なくともあいつが花村を想ってこれを遺したんだってことは俺にもわかる」
「ところでキャスターさん、これにはまだ続きがあるんですか?」
「ああ、どうやらそのようだ。見ろ、そろそろノイズが晴れる頃だ」
映像に映ったのは昼間の新都の街並みだった、先ほどの映像から随分と時間が経過している。
視界の主は鳴上悠か、激しい息遣いの音から息を切らせながら走っているようだ。
ふとランサーが実体化する。その貌は既に凶相に染まっておりどこかで令呪が行使されたことを示唆していた。
『ランサー、あそこだ!やれ、やるんだ!!』
焦燥と必死さを帯びた怒声が狂ったランサーを衝き動かす。
雄叫びをあげながら上空へと跳躍し前方を走る高級車目掛けて朱槍を投げ放った。
車を突き刺すと思われた投槍だが傍を走っていたバイクの動きに妨げられ地面に突き刺さるが、本能に染み付いた動きかランサーは槍の目の前に着地し即座に己の得物を拾う。
バイクに跨っていた大男がヘルメットを外しスーツ姿から戦装束に変化、それは紛うこと無きライダーのサーヴァント、狂王アシュナードその人であった。
『逃すなランサー、追え!!』
「あのオッサン、間違いねえ……!」
「ああ、アシュナードだな。だとすれば恐らくこれが鳴上悠の…」
余裕がないのかがなり立てる悠に従いランサーは狂化により増した俊足を持って敵ライダー、狂王アシュナードを追って駆けていく。
『嫌だ…DIOさん、陽介、俺、俺は——————!』
ブツブツと不気味な呟きを発する悠。肉の芽の支配と本来の友情との間で揺れていることが容易に想像できた。
数分後、ランサーとアシュナードのものと思しきけたたましい金属音と爆音とが聞こえてきた。
そして悠の視界に入った高級車からゴルフバッグを持った男、アシュナードのマスターが降りてきた。
その強烈な存在感から一目でマスターと見抜いたのかはたまた別の理由か悠は何の躊躇も迷いもなくペルソナを顕現させた。
『ジオンガァ!!』
以前士郎が受けたものより範囲は狭いが数段鋭く強烈な雷光が車を貫き爆発させる。
が、アシュナードのマスターには傷一つなく二振りの剣を油断なく構えている。
『またペルソナとやらか』
『やれ…伊邪那岐!』
伊邪那岐が突進し長刀をアシュナードのマスターへ振り下ろすが、一歩動かすことすら適わず交差させた剣によってあっさり受け止められた。
王者、覇者を体現したかの如き男の威容は一分の乱れすらも見られず、そこらのマスターではそれだけで身が竦んで動けなくなることだろう。
『問おう。小僧よ、貴様があのランサーのマスターか』
『…アギラオ!』
アシュナードのマスターの問いを悠は無視し、伊邪那岐が長刀の先端から火炎属性の中級魔法を発射し浴びせかける。
だがその炎は男が構え炎を纏わせた剣———紛れもなく宝具級の逸品———によって呑み込まれ逆にペルソナを燃え上がらせた。
『ぐああああ!』
『その程度の炎などこのわしには通じぬ。この身を焼きたくば火竜の息吹をもってこい』
『くっ…ジオンガ!』
『ふん。小僧、今度はわしの番だ』
それでも悠は怯まない。車の破壊にも用いた電撃属性の中級魔法を撃ち放つ。
男は避けようともせず二振りの剣を交差させた後奇妙な構えを取り、勢いをつけて全身を回転させた。
『王者の劫渦(バシリオス・ディーネ—)!』
先の花村との戦いでは様子見の体を残していたために使わなかったベルンの覇王ゼフィールが誇る不敗の剣技。
全てを蹂躙し尽くす覇王の進撃は伊邪那岐の電撃を弾き掻き消し咄嗟の防御すら突破し伊邪那岐の長刀を弾き飛ばした。
そしてペルソナ自体にも傷をつけたものの結果としてそれが致命傷になることは無かった。
『イザナギ、戻れ!』
紙一重のところで悠の操作が間に合い伊邪那岐を呼び戻したために致命傷は避けられたのだ。
『治癒の力を持つか。だがその程度の力でわしを討ち取れると思うな』
『負けない…俺は負けない。俺は空っぽじゃない…』
映像越しでさえ伝わってくる男のプレッシャーだが悠はそんなものを意にも介していないように見受けられる。
真っ当な人間には作用する恐怖による威圧もただ一つを盲信する狂信者には意味を為さない。
『サーヴァントが狂っているなら、マスターも同じか。
だが容赦はせん。消えるがいい』
『ガルーラ!』
再び迫り来る魔の進撃、悠は疾風の魔法を以って押し止めようと試みる。
『ぬぅぅん!』
だが暴君の蹂躙はその程度では止まらない、暴風など最初から存在していなかったかの如き勢いで風を切り裂き吹き散らした。
花村のペルソナと違い伊邪那岐には属性魔法の威力を増大させる技能がなく、それ故突破力や耐久力が桁違いの敵とは相性が悪いのである。
『炎に雷、そして風までも操るか。
しかしその風、花村とかいう小僧には及ばんな。
しょせんは子供だましよ』
『花…村?陽介…陽介のことか…』
『やつも遠からず切って捨てるが、まずは貴様だ。
我がバシリオス・ディーネーで冥府へ落ちよ!』
ふと、悠がしゃがみこんだのか映像の視界が急に下へと落ちた。
当然敵がその隙を逃すはずもない、回転する剣舞が立ちはだかった伊邪那岐の長刀を粉砕し片腕をもぎ取った。
『がああああ!』
『ふん、この程度…やつの方がまだ骨があったわ。
それに比べて貴様は期待外れだ』
『俺は…死…花村…違う…』
「ゆ、悠……」
「妙だな、てっきり鳴上はこいつらと相討ちになったと思っていたのだが…我々の考えが間違っていたというのか?」
半ば錯乱しているかのような悠を仕留めるべく男が必殺の構えを取る。
このままでは相討ちにもならずに悠が倒されるだろう。
『俺は…菜々子…花、村…………』
『バシリオス・ディーネー!』
『…………DIO…』
悠を討ち取ると思われた剣は命中せず頭上を通り過ぎていく。
それは偶然ではない、伊邪那岐が咄嗟に放った氷結魔法が男の足元を凍てつかせ踏み込みを狂わせたのだった。
生存本能によるものか、それ以外の要因によるものかは誰にもわかりはしないが。
『む!?』
『ガルーラ!』
さらに悠は自身に疾風魔法をぶつけることで死の旋風から逃れ距離を取ることに成功した。
通常ならば自殺行為、しかし今となっては誰も知らないことだが伊邪那岐には破魔と呪殺、万能を除く全ての属性攻撃に対する耐性が備わっている。
それ故に自身に魔法を当てたところでさしたる問題にはなり得ないのだった。
『氷…か。わしの踏み込みを狂わせたか。
よく凌いだ。だが二度はないぞ』
男が持つ剣のうち一本が神秘的な炎を纏う、あれがあの剣本来の力か。
セイバーは何故か表情を強ばらせ食い入るように剣を見ている。
ともあれ、あれほどの炎ならばペルソナの氷結魔法も瞬時に溶かせるだろう。
仮に対抗できるとすれば特定のペルソナのみが体得出来る最強の氷結魔法のみだろう。
『これで最後だ…バシリオス・ディーネー!』
『死なない…俺は…帰る…いや…行くんだ!
DIOさんの教えてくれた…天国へ!』
迫り来る暴力の大渦を前にして伊邪那岐が再度生み出した長刀を投擲、そして即座に破砕された。
あまりにも劣勢な状況、あと一秒と経たず鳴上悠の命運は尽きるだろう。
だが———
『コンセントレイト…メギドラぁぁぁぁぁあああ!』
立て続けに発動した二つの魔法、攻撃魔法の威力を底上げする補助魔法と耐性に威力を左右されずあらゆる敵を打ち砕く中級万能魔法がついに無双の剣戟を押しとどめた。
『ぬうう…消えぬ…!ぬあああああっ』
『伊邪那岐いい!』
剣と魔法の衝突を制したのは悠だった、大男を弾き飛ばし二振りの剣の一つを掠め取った。
見れば男もそれなりの手傷を負い地に片膝をついている、致命傷には程遠いものでしかないが。
『はあ、はあ、はあ…』
『…見事だ。ここまでやるとはな。
エッケザックスと封印の剣がなければ、わしは消し飛んでいただろう』
しかし魔法の乱用によって悠は大幅に消耗しているようだった。
狂化したランサーを維持しながらこれだけの魔法を連発すれば当然の帰結であった。
それに対して敵は未だ健在、地力の差がありすぎたのだ。
『はあ、はあ、はあ…!』
『あれだけの魔法を放てば、消耗もしよう。
ならば…わしの勝ちだな』
男がゆっくりと立ち上がり今度こそ悠にとどめを刺そうとする。
悠が奪った剣を伊邪那岐に持たせ投擲するが———狙いが外れ男の傍らを通り過ぎていった。
伊邪那岐が徐々に消えていく、魔力を使い切ってしまったのだろう。
『…くっ』
『もはや傀儡を維持する力もないか。存外手間取ったが、これまでだ』
『まだだ!』
「あいつ、額に手を…?」
「確か肉の芽は本体から魔力を送り込めるはずだったな。
そして今鳴上に魔力が供給されているとすれば…なるほどな、この戦いの構図が読めてきた」
『コンセントレイト』
『ぬう…バシリオス…!』
『遅い!メギドラぁぁ!』
今ここに互いの優劣は逆転した。
傷のために動きが鈍った男が剣舞の構えを取るも間に合わない。
剣と魔法、至近距離では剣が勝るが距離を詰められない状況ならば魔法を使う悠が勝つ。
パァン
だが一発の銃声が男の危機を救った。
銃弾を浴びたらしい悠の視界が揺れ、間もなく地に倒れ伏した。
「悠!まさか、これで死んじまったのか…!?」
「いや、そうではないらしいぞ、見てみろ」
『ガルーラぁ!』
『む…まだ生きて…!?』
悠はまだ生きていた。疾風魔法が高級車の残骸を吹き飛ばした先にいたのは肩まで伸ばした髪をカールさせた白人、アサシンのサーヴァントであるファニー・ヴァレンタインその人であった。
「ふん、やはり生きていたようだな」
『アサシンか』
『ほう、あのときのやつばらか。生きていたとはな』
男の傍にアシュナードが、悠の傍にランサーが戻り場は一転して膠着状態になった。
が、悠にとって好機であるはずのこの状況は悠自身の判断ですぐに破られた。
『ランサー、行け!』
ランサーがアシュナード目掛けて突貫し、それをグルグラントで受け止めるアシュナード。
アサシンをもまとめて相手取るつもりかアシュナードはランサーに対応しつつ周囲の瓦礫を破壊し隠れ潜むアサシンも同時に狩り立てていく。
そして訪れるのは先ほどと同じ状況、悠とアシュナードのマスターの一騎討ちである。
『小僧よ、これで終わりだ。貴様はここで潰える』
『…俺は…終わる。でも…終わらない』
誰もが口を閉じ、沈鬱な表情で映像に見入っていた。
今度こそ、これが鳴上悠の終焉だと誰もが内心で悟っているが故に。
『勝つのはお前でも…俺でもない。勝つのは… …だ』
「……え?」
そしてその瞬間は訪れる。映像の悠が右手を翳し最期の命令を発しようとする。
その動きには何の疑問も躊躇も見られなかった。
『小僧、何を』
『令呪を持って…命じる』
『貴様…まさか!』
『ランサー、宝具——刺し穿つ死棘の槍(ゲイ・ボルク)を使い、ライダーのマスターを殺せ』
令呪を発動した証である強烈な赤光が輝きを放つ。
鳴上悠をこの霊子虚構世界に繋ぎ止める最後の命綱、それがたった今消えて失せた。
致命的にして決定的、確実に鳴上悠はここで死ぬ。
『ライダー、騎竜を従え馳せ参じよ!』
令呪に対抗できるものは令呪をおいて他にない。
マスターの命令に従い転移したアシュナードが騎龍を従え己がマスターを連れて空へと駆けていく。
この結末がどうなるのかを士郎らは既に知っている、最も凶悪なあの主従は因果を覆すこと適わずこの地に散ったという結果は最初から出ている。
アシュナードを狙ったものならばまだ応じようはあっただろう、しかしマスターへの攻撃は狂王の鎧が如何に強固でも防ぎようがない。
だからこの二組の主従はこれで終わり、鳴上悠とランサーは令呪を全て失ったことで、二人の王者は魔槍にその身を貫かれたことでこの戦いから脱落した。
『………』
悠の身体が崩れ、黒いノイズに侵食されていく。
これが聖杯戦争に敗北した脱落者に待つ結末、衛宮士郎にとっては金田一に続いて二度目となる光景だ。
誰もが押し黙る中、ルルーシュだけが冷徹に自らの見解を述べていく。
「…この展開、何から何まで出来すぎているな。
そもそも錯乱した鳴上と狂ったランサーがあのライダーたちを先に補足出来るはずがない。
第三者からの情報提供———それこそDIOの指示でもない限りはな。
それに最後の令呪にしても自滅覚悟なら最初から使っておけばそれで済んだはず。
そうしなかったのは途中でそういう指示があったからだろうな」
誰の、などとはもう口にするまでもないことだった。
そして事実だとすればそんな自爆特攻じみた命令が下される理由もただ一つ———蜥蜴の尻尾切り。
「私が、肉の芽を解除しようとしたせいなのか…?
それがDIOに露見したから使い捨てられた、これではそうとしか…」
「おい何言ってんだリインちゃん!頼んだのは俺だ、誰かが悪いってんなら俺しかいねえよ!
リインちゃんは俺の無茶振りに応えてくれただけだ、そうだろ!?」
青ざめた様子で自虐するキャスターの肩を掴んで叫ぶ名無の顔は今までにないほど真剣だった。
全ては結果論、それはキャスターとて頭では理解していたが早期から共に行動していた仲間の友人を間接的にとはいえ死なせたという事実は彼女にとってあまりに重い。
『…、…け』
消えゆく間際、悠が何かを口にしようとする。
身体の大半が消え去り映像の視界も暗くなっていく中最期に何を言い残そうとしているのか、花村は涙を堪えて見届けようとしている。
『おれ、と…お、なじに…ならな…い、でくれ……』
「………!!」
その言葉を最後に映像は今度こそ本当に幕を閉じた。
限界だった、堰を切ったかのように花村は大声で涙を流した。
かつてランサーが他者に伝えること叶わじと諦め絶望したアーチャー、DIOの正体と戦術。
それらは時を越え形を変えて——————今、確かにここに届いた。
しばらく咽び泣いていた花村だがやがて落ち着きを取り戻した。
「さっき悠が令呪を使う前…大分掠れた声だったけど、“勝つのは陽介だ”って、そう聞こえたような気がすんだ。
自分でも有り得ねえって思うんだけどさ…それでも、やっぱり……」
「いや、俺にもそう聞こえたな。皆はどうだ?」
真っ先に肯定したルルーシュの問いに全員が頷いた。
勿論中には上手く聞き取れなかった者もいるが、キャスターを含め誰にも迷いはなかった。
つまりそういうことだった。
「はは、ありがとな、皆」
花村は思う。もし教会で名無とキャスターに出会えていなければ自分はきっとどこかで潰れてしまっていただろう。
この場において自分と悠は同じだった、彼も親身になって止めてくれる人間と出会えていれば違う道があったかもしれない。
自分がそうであれなかったのは確かに辛く悲しい。
だが、だからこそそれらを呑み込んで前に進もう、それが親友であり相棒だった男が望んでいたことなのだから。
「………?」
ふと違和感を感じポケットを探ると見覚えのない鍵が入っていた。
一見何の変哲もない鍵だが不思議と惹かれるものがある。
この鍵が何なのか、誰が使っていたものなのか、花村はまだ知らない。
2 いつか蘇る王
映像が終わり、皆が絶対に負けられないと決意を新たにしていた時ルルーシュがふと思い出したようにガウェインに問いかけた。
「そういえばガウェイン、フォルダは二種類あると言っていたがもう一つは何だったんだ?」
「それが…何者かの記憶フォルダのようなのですが、ロックが掛かっているのか詳細はよく分かりません。
この中の誰かの記憶であるならば反応を示すかもしれませんが……」
「そうか……」
記憶フォルダ、というのがどうにも引っかかる。
そもそもこのデータフォルダは鳴上悠が花村陽介に渡したもの、だとすれば先の映像だけで十分過ぎるように思える。
つまりこの記憶フォルダが花村のものであるとはどうにも考えにくい。
接した時間は短いが花村に記憶が欠損しているようには全く思えないからだ。
「まあいい、一人一人に試してみて反応すれば儲けものぐらいに捉えておけば良いだろう。
これから戦略もさらに詰めていかなければならないんだ、時間を無駄には出来ん」
ガウェインからキューブ状のフォルダを受け取る。
花村を除けば一番怪しいのはこなただろう、例の知識の出どころは本人にもわかっていないらしいとなればこのフォルダが鍵になるかもしれない。
ちなみにやはりと言うべきかルルーシュには何の反応も示さなかった。
フォルダをこなたに渡してみたが———反応はなかった。
「ああ、駄目かあ…」
「ふむ、泉が一番有り得ると思ったのだが…」
この後も士郎、名無、そして花村の順に渡していったがいずれにも反応しなかった。
マスターに全く反応しないというのは一体どういう事なのだろうか。
「ねえルルーシュ君、せっかくだから映司さんたちにも渡して試してみたら?
ほら、駄目で元々っていうしもしかしたらとんでもない秘策の鍵になるかもしれないよ」
「その可能性が高いとは思えないがな……、?いや、待て」
そういえばと思い出したことがあった、士郎のセイバーである。
奴の能力にだけ不自然な制限が掛かっていたのは何故なのか、殆どのサーヴァントのデータが揃った今思い返しても制限しなければならない特段の事情があるような性能とは考えにくい。
弱いというわけではない、むしろ各方面に偏りなく高い力を持っている優れたサーヴァントではあるだろう。
だがそれを言えばこの聖杯戦争にはより反則的なオンリーワンの力や宝具を持つ者が何人もいた。
アーチャー、DIOや仮面ライダーディケイドは言うに及ばず太公望や蘇妲己、サブラクに狂王アシュナードなど強力な英霊は確かにいたのである。
確かに宝具の火力においてセイバーと並び立つサーヴァントは———それこそ自分のガウェインも含めて———この聖杯戦争には存在しないだろうがそれは理由として弱すぎるように思えてならない。
結局この謎については今もってはっきりとはわかっていないのである。
「セイバー、まずお前だ。サーヴァントの中ではお前が一番可能性がある…かもしれん」
「はあ…今さら何かがあるとも思えませんが」
若干嘆息しながらキューブを受け取ったセイバーだがしかし、直後に予想に反した変化が起こった。
「な」
驚きの声は一瞬だった。
セイバーの掌に収まったキューブは高速で唸りをあげながら回転し眩いまでの輝きを放つ。
永遠とも一瞬とも思える光の奔流が消え去った後、彼女の記憶を司るキューブは跡形もなく消えていた。
「ああ———」
誰もが呆然とする中、ただ一人セイバーだけがどこか穏やかな、郷愁を感じさせるような声音を発した。
誰かが疑問の声を発するよりも早くセイバーは右腕を突き出しある物を具現化させた。
「あ…」
「叔父上、それは…!?」
それは衛宮士郎にとって初めて目にするはずの、しかし決して目を逸らせない懐かしさを抱かせるものだった。
ガウェインの誰何の声すら耳に入らない、ただひたすらに目の前のそれを凝視し続けていた。
「シロウ」
セイバーが士郎の眼前まで近づきそれを翳す。
担い手の魔力を込められたそれは暖かな光を発し、衛宮士郎の肉体、より正確にはその魔術回路に巣食った不浄を消し去っていく。
先ほど間桐桜に告げられ自身の身体を精査して漸く気付いた負の澱み、それらが痛みもなく取り払われていくのを確かに感じた。
「セイバー、それは」
「ええ、これもまた私の宝具の一つです。
まったく、このような方法で封印されているとは思いもしなかった。
世界から切り離されて召喚されたこの月でならこれもまた再現されて然るべきだったというのに、今まで使えないことに疑問さえ抱かなかった」
左手に黄金の聖剣を顕現させ右手に持ったそれに剣を収める。
口にせずとも誰もがそれで理解した、これこそがセイバーの持つ聖剣の本来の正しい在り方なのだと。
——————それは彼女がいつか辿り着く妖精郷。
伝承においてアーサー王に不死の力を授けた星の聖剣と対になる最終宝具。
その名を“全て遠き理想郷(アヴァロン)”。
所有者に加護を与え呪いや概念を跳ね除け活力を与える最強の聖剣を収めるに相応しい鞘である。
神秘はそれを超える神秘によって打ち払われる。
メダリオン、より正確には負の女神ユンヌが齎す負の魔力の残滓はこの黄金の鞘の加護により一切残らず除去された。
とはいえもし士郎が負の魔力を異常と認識出来ないほど肉体に馴染んでしまえば鞘の力を以ってしても取り返しのつかない事態に陥っていたかもしれない。
本来この聖杯戦争において世界との契約から切り離されたセイバーは最盛期の伝承を再現され、この鞘を最初から使用出来るはずだった。
剣と鞘の関係上セイバーのクラスの枠に反する宝具では有り得ないのだから当然だ。
しかしその強力さを警戒した何者かの手によって他の能力制限とは別個に取り上げられていた。
とはいえ英霊の持つ宝具そのものを本体から完全に切り離すことなどムーンセル本体以外に出来はしない。
故にセイバーが地上の聖杯戦争の記憶を有しているという事実を利用し「現在鞘を所持している」という記憶を抹消することで事実上鞘を保有していない状態に貶めていたのである。
その没収されていた記憶が今戻ったことによって鞘の存在を思い出し装備し使用することが可能になったのだった。
「けど何だって悠がそんなのを持ってたんだ?
俺も悠もここに来るまでサーヴァントだの聖杯戦争だのなんて知りもしなかったしましてあんたの宝具の事なんて……」
怪訝そうに話す花村を見てセイバーは静かに首を振る。
その顔は解けなかった謎が解けたような晴れやかさをも帯びていた。
「この記憶フォルダにはメッセージが添付されていました。
“シロウを守って”と。私の鞘の存在を知り得てなおかつこんな真似が出来る人物は一人しかいない」
「まさか…イリヤだっていうのか、セイバー?」
セイバーは無言で肯定した。
イリヤスフィール・フォン・アインツベルンには小聖杯としての機能がある。
そしてキャスターが先の魔法で行なったのはムーンセルへのアクセスによる脱落者のデータ再現だ。
そしてセイバーの推測通り、データを掘り起こされるにあたってムーンセルが保有する数多の情報に触れたイリヤスフィールは果たせなかった未練を果たすべくある一つの事を願った。
———“シロウを守れるものを渡してあげたい”
聖杯であるイリヤスフィールには自身の魔力の範疇で過程を無視して結果を得る力を持っていた。
無論データをごく僅かな時間再現されただけの彼女にはほとんど力など残っていなかったが———同時に全くの絶無でもなかった。
膨大な情報の海の中に分解されて放り捨てられたセイバーの鞘の記憶、それらを自身の残された力で再度組み立て鳴上悠が花村に渡したデータファイルに密かに紛れ込ませていた。
騎士王の鞘の存在を知る、異なる可能性世界からこの聖杯戦争に参加していた彼女だからこそ出来た離れ業だった。
様々な偶然の重なりがセイバーが再び鞘を手にするという奇跡を生み出した。
ここに来てようやく彼女は今回の聖杯戦争における衛宮士郎のサーヴァント・セイバーとして正常な状態に立ち戻った。
「俺、またイリヤに助けられたんだな…何もしてやれなかったっていうのに。
いや、イリヤだけじゃない。学園で桜にメダリオンの事を教えてもらわなかったらきっと気付きもしなかった」
「ええ、確かに。私達はここで出会った多くの人間に助けられ、生かされている」
金田一一とライダー、太公望はセイバーが当初持ち得なかった月の聖杯戦争の知識と情報を補ってくれた。
遠坂凛は死に行く自身を顧みずサーヴァント、キャスターを柳洞寺に向かわせ士郎を助けようとした。
当のキャスター、蘇妲己はとんだ食わせものだったわけだがそれでも結果的に、最終的には蘇妲己の助言が天海陸とセイバー、イスラを撃破する切っ掛けになった。
学園の上級AI、間桐桜は士郎が知らぬうちに取り込んだ負の魔力の存在と正体を教えてくれた。
そしてイリヤスフィールはセイバーの鞘を取り戻す鍵を齎した。
自分達だけで戦っていればとうの昔に志半ばで脱落していたことだろう。
「しかし残滓とはいえあのアシュナードの宝具による汚染を消し去ったのか。聖剣の鞘の名に恥じない凄まじい力だな」
「いえアレックス、それだけではありません。
この鞘の真名を解放することで私はあらゆる攻撃、交信を絶つことが出来る。
それは魔法の領域にあるDIOの時間停止とて例外とはなり得ない」
「何だと!?セイバー、それは本当か?」
驚愕するルルーシュの問いにセイバーは自信を持って頷いた。
アヴァロンはその真価を発揮させることで数百のパーツに分解してセイバーの周囲に展開、この世界とは異なる世界、「妖精郷」に身を置きありとあらゆる干渉を遮断する。
その力は現存する魔法さえ寄せ付けず、衛宮士郎が生きる世界において時間旅行、時間操作にあたる第五魔法もそれは同様。
例え世界を支配する力である帝王DIOのスタンドであろうとも異なる世界にいる者に対して干渉することは出来ない。
「おいおいすげえな、ってことはディケイドに超加速されてもへっちゃらなんじゃねえの?
どんなに速くても攻撃が効かないんならどうってことねえんだし」
「勿論直感で先読みしてタイミングを合わせて発動しなければ意味はありませんが、それは必ず何とかしてみせましょう。
何しろ今の我々には負けられない理由が多過ぎる」
「ああ、そうだな。これで条件はクリアされた、DIOとディケイドの両方に対抗できる力が揃った!」
無論、これはあくまで敵の反則的能力に対抗できるようになったというだけだ。
確かに鞘を取り戻した今のセイバーは他のほとんど全てのサーヴァントを寄せ付けない強さを誇る。
聖剣の鞘による加護は応用次第で攻撃にも転用できる、まさに評価規格外の宝具だ。
しかしアーチャーとライダーは数少ない、今のセイバーさえ殺し得る例外中の例外、規格外の強敵だ。
サーヴァントの域を逸脱した加速能力と世界を支配するに相応しい時間停止。
ごく僅かでも鞘を展開するタイミングを過てば即座に致命となるだろう。
実際に彼らを倒せるかどうかは戦術とサーヴァントの運用に懸かっているといえる。
「花村、それにアレックス」
二人に向き直ったルルーシュの表情はどこか強ばっている。
「頼みたいことがある。場合にもよるが、お前達には対DIOから外れてもらうことになるかもしれない」
「待てルルーシュ、それは」
語気を強めたアレックスを遮ってルルーシュが深く頭を下げた。
生前の彼を知る人間ならば誰もが疑うに違いない光景だった。
「だから頼んでいるんだ。奴らを相手に最もやってはならない事は一つの対策だけを用意してそれに満足してしまうことだ。
それにアレックス。お前の情報は既に漏れているんだ、搦手と狡猾さに秀でる奴らが何の対策も講じないとは思えない」
「俺がDIOに向かっていく、それ自体が罠だとでも言うのか?
我々がDIOの能力を知れたのは泉こなたの知識と鳴上悠が齎したデータがあればこそだ。
それを見越した対策をあちらが打てるとは思えんがな」
それでもルルーシュは首を縦には振らない。
「しかし進化の能力が時間停止に適用される可能性を警戒ぐらいはされているだろう。
それに、だ。お前の力は対バーサーカーやディケイドにも有効に働く。
気持ちはわかるがもう一度頼む。怒りに身を任せて視野を狭めないでくれ」
改めてルルーシュが二人に頭を下げた。
切実な誠意が込められているのが付き合いの短い彼らにも感じられる。
確かにアレックスの能力はアーチャー以外の敵にも有効に働く。
ライダーに対しては負傷を度外視して特殊能力の発動を阻害することに専心するという戦術を取れる。
以前は脅威だった数多の武装・能力による初見殺しの数々も今やその全てが余さず明らかになった。
アレックスに対して有効な攻撃のみに注意し、無理に倒そうとしなければ安定して足を止めることが出来るだろう。
バーサーカーもその点は同じだ、あの狂騎士の異能は手にした武器を宝具化するものであって宝具であれば無条件に支配できるわけではない。
武器と認識できないものは宝具であっても支配することは出来ないという限界が存在することが学園のデータベースで明らかになった。
アレックスは宝具の力で稼働するサーヴァントだが、目の前にいる敵を武器と認識できるのはそれこそ仮面ライダーディケイドぐらいのものだろう。
それにこの点に留意しておけばこちらのライダー、オーズでもバーサーカーの封殺は十分可能だ。
単純な話、わかりやすい武器以外の能力で戦えば相手の強みを発揮させずに済むからだ。
空を飛べるタジャドルコンボや超高速で動くラトラーターコンボならば容易く優位を奪える。
「言いたいことはわかるがな…」
「いや、アレックス。ここはルルーシュのが正しいと思う」
なおも渋るアレックスを制したのはマスターたる花村だった。
「良いのか?」
「心の底から納得できたわけじゃねえけどさ、でも悠は敵討ちを望んでたわけじゃなかった。
ちっと熱くなりすぎてたみてえだ。ありがとなルルーシュ、おかげで目が覚めたわ」
無理を言ったにも関わらず花村は笑顔すら浮かべて承諾してくれた。
逆にルルーシュの方が申し訳ない気持ちになるぐらいだ。
この戦いは誰かが感情的になって勝てる戦いではない、ルルーシュの必死さを見てそれを花村も再認識したのだった。
「しかし…まだ足りないな。セイバーの鞘にしても発動にはかなりの魔力が必要なんじゃないのか?」
「ええ、鞘を装備したことで私の魔力は増しましたが敵は燃費にも優れている。
鞘の真名解放は規模の違いからエクスカリバーほどの消耗はありませんがそれでも軽くはない。
長期戦になった時に持ちこたえられるかどうか…」
「魔力、か…。ってそういえばセイバー、さっきから俺から持っていく魔力が少なくなってないか?」
「何?」
士郎の指摘にルルーシュが怪訝そうにセイバーを見る。
それに対してセイバーは神妙な顔で答えた。
「ええ、それに関しては心配ありません。私の魔術回路も今は正常に稼働していますから」
「今は?以前は違ったというのか」
「…はい、日中の切嗣との戦いで本調子に戻るまで私の魔術回路は極端に出力を制限されていました。
シロウの供給に対して全く釣り合わない魔力しか生み出せなかったのです」
元来サーヴァントは魔術回路を備えるが自力ではほとんどそれを駆動させることが出来ない。
そこでマスターから供給される魔力を用いて魔術回路を動かし活動のための魔力を生成する、これがマスターからサーヴァントへの魔力供給のシステムの正体である。
真にサーヴァントがマスターから送られた魔力のみで活動しているなら人智を超えた力を発揮することなど到底不可能なのだから。
竜の因子を与えられて生まれたセイバーの魔術回路は他の並みいるサーヴァントと比較してなお規格外、それは最早魔術回路ではなく魔術炉心とでも形容すべき魔力を生み出す工場だ。
本来セイバーは魔力消費が多い代わりにこの魔術炉心によって魔力の生成量にも優れたサーヴァントなのである。
だがこの聖杯戦争の開始当初は魔術炉心の機能に強力なロックを掛けられ第五次の時よりは改善されたとはいえ十全な状態とはいえなかった。
セイバーの基本ステータスの低下はこの炉心の出力制限に起因するものだった。
制限が解除され炉心への火入れが行われた今では以前よりも少ない負担でより多くの魔力を生成できるようになっている。
「鞘が戻ったのでエクスカリバーを含めて数回は宝具も使用できますが何しろ今回の戦いは勝手が違う。
五体もの強敵を相手にして魔力が保つかどうかは未知数としか言えません。
生前同様に回路を動かせれば私の力もより戻るのですが…それは言っても仕方ありませんね。
私に限らずサーヴァントである以上は生前ほどの魔力を生み出すなどよほど外れた手段でも用いない限りはまず不可能なのですから」
「そうだよな…。今からもう一回柳洞寺に行って“紅の暴君”を刺して戻ってくる時間なんてないし……」
嘆息する士郎とセイバーを前にルルーシュが暫し考え込む。
これまでのセイバーの情報を頭の中で整理し組み立てていく。
やがて何かを思いついたか、確信めいた笑みを浮かべた。
「ならば、令呪で一時生前と同じ状態に戻すことは可能か?
そう、例えば———魔術回路を生前同様に機能させろ、といった具合にその一点に絞って令呪の力を注ぎ込めばどうだ?」
「!それは———確かにそれならば十分可能です。
魔術回路の機能が戻れば当然振るえる力も生前と同じになり魔力の回復量も格段に増す」
それはセイバー、アルトリア・ペンドラゴンだからこそ策として成立する令呪の使い道だった。
凡百のサーヴァントに同じ使い方をしたところでそう上手くはいかない。
サーヴァントといえど魔力保有量にさほど優れない者も珍しくはない、それならば単純な強化などに使った方がよほどに有効なのだ。
だが他の英雄とは桁違いの魔術炉心を有し、魔力放出によって人外の力を発揮するセイバーだけはその方法が極めて有効に機能する。
加えて今度の戦いは団体戦、長期戦が予想される状況下では有用性はさらに増す。
「お前、もしかして俺以上にセイバーの事を把握してないか?」
「戦力という意味ではその通りだと言っておこう、一たちと同盟した時から性能を活かすための策を考え続けていたんだからな」
士郎は確かに前回の聖杯戦争参加者としての経験を持ち合わせるが、ルルーシュもまたギアスを得て以来ゼロとして常に限られた物資や戦力を活かす算段を練り続けてきた。
今あるものを活かして戦うという点においては一日の長がある。
ルルーシュがセイバーの戦力を最大限活かす策を考えている一方でガウェイン、キャスターらも厄介な敵への対処を考えていた。
「アサシンや敵のキャスターもまた相当の難敵ですね…。
キャスターは隠形に優れない以上貴女と同じく後方から支援を行う可能性が高い。
あるいはこちらの防備を突き崩す策を用意している事も考えられます。
そしてアサシン、スタンド能力の特性を考慮すればどこから現れ奇襲を仕掛けても全く不思議ではない」
「対アサシンに関しては私の方で既に奴に対して有効な魔法をいくつかピックアップしてある。
ただバーサーカーの宝具を奪還されると不味いことになる、誰かが持っておく必要があるがあるだろうな」
現状のバーサーカー、ランスロットは先の戦いで与えたダメージに加えて最強宝具アロンダイトを失っているために弱体化している。
このため伝承において敗北したガウェインであっても善戦できる程度には戦力差は埋まっている。
しかし隠密行動に秀でたアサシンがアロンダイトを奪還してくる可能性がある以上油断は出来ない。
全員が地下室に移動したため無人の邸内に侵入されないよう屋敷にもサーチャーを飛ばしておりオーズもカンドロイドを放つなど協力してくれている。
「それと先ほど依頼した術式に関しては?」
「そちらもほぼ改造は済んだ、上手く使えば敵に逃げ場を与えず倒せる」
ガウェインが依頼した術式は一対一の決闘に特化したもの。
活用出来れば機動力に優れるライダーや隠密性に優れるアサシンの長所を封殺することも可能だ。
「戦わずしてここから脱出出来るのが一番の理想なんだがな……。
残念ながら脱出ポイントの割り出しにはもうしばらく時間が必要そうだ」
「やはり戦いは避けられないでしょうね……。
キャスター、くれぐれもご自愛を。貴女が倒れれば我々の脱出の可能性はそこで潰えてしまうのですから」
「ああ、わかっている」
そう、この戦いは極力犠牲を避けて勝利しなければならないのだ。
影の主催者が戦力を有している可能性は低くはない以上可能なら一人の犠牲も出すべきではない。
中でもキャスターはこの空間から脱出する鍵となる存在、名無共々絶対に死なせてはならない。
こちらは敵マスターの居所がわからないのに敵には狙われるという厳しい戦いになるのは想像に難くない。
救いがあるとすればこちらは必ずしも敵を殲滅する必要はなく、こちら側への攻撃を不可能にするだけの打撃を与えて撃退すれば良いという点ぐらいであろうか。
そしてもう一つ、ガウェインは悲観的な妄想ではなく確信していることがある。
ルルーシュのマスター適性はさほど高くなく、当然にして魔力供給も多くはない。
泉こなたはルルーシュよりも適性で劣るが彼らは魔力と令呪を未だ十分に温存しており、自分達とは違う。
ほぼ間違いなく次の戦いで我々は力を使い果たす、もしこの集団の中に切り捨てるべきものがあるとすればそれは——————
【深山町・遠坂邸地下室/未明】
【衛宮士郎@Fate/stay night】
[令呪]:2画
[状態]:健康
[装備]:携帯電話、ICレコーダー
※紅の暴君は破却しました
※体内の負の魔力が除去されました
【セイバー(アルトリア・ペンドラゴン)@Fate/stay night】
[状態]:健康
[道具]:無毀なる湖光(アロンダイト)@Fate Zero
※ムーンセルに課せられていた能力制限が解除されました
※ムーンセルから得られる知識制限が解除されました
※宝具「全て遠き理想郷(アヴァロン)」が使用可能になりました
またこれに伴い魔力量が大幅に増大しています
【ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア@コードギアス反逆のルルーシュ】
[令呪]:1画
[状態]:健康
[装備]:携帯電話、ニューナンブ
※枢木スザクが参加していることを知りましたが説得を断念しました
※マスター達は時空を超えて集められたのではないかと考えています
※枢木スザクが自分より過去(第二次トウキョウ決戦前後?)から参戦していると考えています
【セイバー(ガウェイン)@Fate/extra】
[状態]:魔力消費(中)
※リインフォースにある術式の改良を依頼しました
【泉こなた@らき☆すた】
[令呪]:3画
[状態]:健康
[装備]:携帯電話
【ライダー(火野映司)@仮面ライダーOOO/オーズ】
[状態]:健康、新たな決意
※遠坂邸内にカンドロイドを放っています
※この聖杯戦争ではスーパータトバコンボは原則使用できません
【花村陽介@ペルソナ4】
[令呪]:3画
[状態]:健康、強い覚悟と決意
[持ち物]:ミネラルウォーター@現実、カロリーメイト@現実・医薬品一式@現実
大学ノート@現実・筆記用具一式@現実・電池式充電器@現実・電池@現実 、契約者の鍵@ペルソナ4
携帯電話*携帯電話には名無鉄之介の名前が登録されています
予備の服@現実・食料@現実・スパナ@現実
※聖杯戦争のルールと仕組みを言峰神父から聞きました
(意図的に隠された情報があるかもしれません)
※ジライヤがスサノオに転生しました。
※契約者の鍵@ペルソナ4を入手しました
【ランサー(アレックス)@ARMS】
[状態]:魔力消費(小)、ARMSの進化(進行度小)
※アサシン(ヴァレンタイン)が生存していることに気付きました
【名無鉄之介@私の救世主さま】
[令呪]:2画
[状態]:健康
[持ち物]:エロ本(大量)@現実・携帯電話@現実(携帯電話には花村陽介の名前が登録されています) 予備の服@現実・鳴上悠のクレジットカード
※聖杯戦争のルールと仕組みを言峰神父から聞きました
(意図的に隠された情報があるかもしれません)
【キャスター(リインフォース)@魔法少女リリカルなのはA's】
[状態]:魔力消費(小)回復中、強い決意
※肉の芽の解除が可能です。ただし全力でやって誰にも邪魔されないのが条件です
※遠坂邸に工房を作成しました 。特別な防衛効果はありませんが土地の魔力をそのまま取り込めます
※深山町の各地にステルス性を高めたサーチャーを複数飛ばしています。主に遠坂邸、柳洞寺周辺、月海原学園、柳洞寺地下大空洞前を中心に索敵しています
※ガウェインから依頼された術式が完成しました
※転送魔法の使用にかかる魔力消費が本来より増大しています
※今まで月海原学園で調べたサーヴァントデータの内容を全員が共有しています
アーチャー(DIO)、アサシン(ヴァレンタイン)、ライダー(門矢士)、バーサーカー(ランスロット)のデータは詳細に把握しましたが、キャスター(キンブリー)の情報はごく一部に留まっています
※円蔵山の魔力集積地に蓄積していた悪性情報(負の魔力)は完全に浄化されました
また悪性情報の浄化機能が大幅に強化されています
※鳴上悠が渡したデータファイルの中身は「oath sign」、「It's just like OVER HEAVEN」、「Hard luck dance」の戦闘記録(悠及びランサー視点)とアルトリアの宝具「全て遠き理想郷(アヴァロン)」の記憶データでした
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: