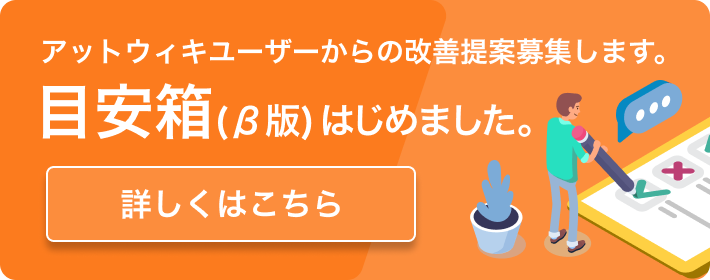「Re;Zero」(2014/06/23 (月) 10:03:56) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
そこは広大な空間だった。
壁や天井のない、どこまでも果てしなく続く白亜の領域。
純白の空と大地の狭間にただ一つ、宙に浮かぶ異物がある。
水晶の立方体に囲まれた単眼のオブジェクトだ。水晶はフォトニック純結晶によって構成された檻。
その内部に魔術師たちが追い求めてきたもの――月の中枢、聖杯がある。
西暦2032年。人類は月面で奇跡を発見した。
――ムーンセル・オートマトン。
太陽系最古の遺物。あるいは神の自動書記装置。あるいは七天の聖杯(セブンスヘブン・アートグラフ)。
その機能は万能、宇宙の物理法則すらも書き換える。故に、万能の願望機――『聖杯』と呼ばれる。
聖杯戦争とは、このムーンセルの所有権を巡って行われる闘争である。
己の魂を霊子化し、ムーンセルにアクセスしたウィザード達は、ムーンセルより己の剣たるサーヴァントを与えられる。
サーヴァントとは、人類史に燦然と名を残す英雄英傑を再現した存在。ウィザードはこのサーヴァントの主――マスターとなって、戦場を駆ける。
命と願いを天秤に掛け、万能の願望機を手にするために。
「そうだ、あれこそがムーンセル・オートマトンの中枢……すなわち『聖杯』だ」
囁いたのは、黒よりも暗い闇を身に纏う仮面の魔王ゼロ。
永遠を生きる者。偏在する可能性の収束点。混沌を体現する存在。月の癌――全ての争いの始まり。
その魔王と対峙するのは、やはり王と騎士。
王の名はルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。かつては魔王と同じくゼロを名乗り、やがて古き世界を壊し、新たな世界を創った男。
騎士の名はガウェイン。アーサー王に率いられし円卓の騎士の一人にして、アーサー王の甥である。太陽の騎士と称される、誉れ高き忠節の騎士。
「魔王、ゼロだと……!?」
ルルーシュは愕然と立ち尽くす。
トワイス・H・ピースマンより、ムーンセルに巣食う元凶の存在は知らされていた。そいつと戦う事を覚悟して花村陽介と泉こなたを帰還させ、ルルーシュはこの場に立っている。
そこに現れたのが、かつての自分と同じ名、同じ仮面を纏う存在である。
驚愕が通り過ぎた後、ルルーシュを満たしたのは燃え盛る怒りだった。
「……不愉快だな。ゼロの名は、ゼロの仮面は、誰とも知れぬ輩が勝手に使っていいものではない!」
奇跡を起こす男、ゼロ――それはルルーシュが生み出し、そしてゼロレクイエムにてルルーシュの命を捧げて世界に刻み付けた存在だ。
ゼロとは今や、単なるテロリストではなくなった。人々に溢れる全ての憎しみを精算し、新たな明日を迎える世界を支えていく安全装置となった。
故に、ゼロを名乗っていいのは盟友である枢木スザクだけだ。人並みの幸せを捨て、生涯をゼロとして世界のために捧げる――ルルーシュからこのギアスを受け取った、枢木スザクだけ。
眼前にいるゼロを名乗る男は、隆々たる体躯を誇っている。どう控え目に見てもゼロの名を託したスザクでは有り得ない。
実体の無い記号とはいえ、スザク以外の人物がゼロを名乗る事に、ルルーシュは激しく憤慨する。
「大方、俺を挑発するためにゼロを名乗ったのだろうが……なるほど、効果的だな。貴様と戦う理由がもう一つ増えた。
聖杯戦争を起こした元凶、そしてゼロの名を騙る痴れ者。許す訳にはいかないな。行くぞ、ガウェイン! 奴を倒し、聖杯を解体する!」
「ええ、ルルーシュ。参りましょう!」
英雄王ギルガメッシュとの戦いで消耗したルルーシュとガウェインに、万全の力は無い。
しかし後退は無い。ここは戦う場面だと、主従は言葉を交わさずとも理解している。
敵は一人、魔王ゼロを名乗る黒衣の男。
幾度もの戦いを経て高まったルルーシュの霊子ハッカーとしての感覚は、敵がサーヴァントを従えていない事を察知している。
ガウェインが斬りかかる。負傷しているとはいえさすがにセイバー、剣の英霊である。その踏み込みはまさに神速。
聖剣の切っ先は音よりも早く黒の仮面を断ち割る――事は無く。ゼロが掲げた掌に、聖剣は難なく受け止められていた。
「性急だな。私とお前には、まだ語るべき事がある……そうだろう?」
聖剣を受け止めながらも、ゼロの瞳はルルーシュしか映していない。
ガウェインの存在を、路傍の石ころのように無視している。意識する価値も無いとでも言うように。
対して、斬撃を防がれたガウェインもまた動けない。
聖剣を受け止めたゼロの掌――正確には、掌の僅か先に輝く光の印に触れた剣先が、どれほどの力を込めようとも微動だにしないのだ。
「これが私のワイアードギアス――“ザ・ゼロ”だ」
「ギアス……!?」
「そうだルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。私もギアスを持っている。絶対遵守のギアスを持つお前と同じくな。
そしてお前は先程、私をゼロの名を騙る痴れ者と言ったな……」
ゼロはガウェインの剣を拘束したまま、もう片方の手で仮面に触れる。
「しかし、違う……違うんだよ、ルルーシュ。私もまた、ゼロを名乗る資格を持つ者。何故なら――」
仮面の開閉機構が作動し、ゼロの素顔が晒される。
今度こそ、驚愕でルルーシュの呼吸が止まる。
「かつての私の名はルルーシュ・ヴィ・ブリタニア――もう一人のお前自身なのだから」
仮面の奥から現れたのは、ルルーシュと瓜二つどころではない、まさにルルーシュその人だった。
顔も、声も、眼差しも。全てが自分と完全に同一。
違いはただ一つ。ルルーシュは白の騎士を従え、ゼロ=ルルーシュは漆黒の魔王である事だ。
ゼロが拳を握る。光の印が消失し、ガウェインが身体の自由を取り戻す。瞬時に放たれたゼロの拳を、ガウェインが聖剣で受け、そして弾かれる。
魔王ゼロはサーヴァントではない。しかし決して人間でもない。セイバーたるガウェインを大きく吹き飛ばすほどの拳を放てる者が、人間であるはずがない。
「ガウェイン!?」
「――っ! ルルーシュ、下がってください! この男、只者ではない!」
接近戦の熟達者たるセイバーに匹敵する膂力は、サーヴァントと比しても遜色無い。
自分と同じ顔をした者がそれだけの力を誇る事実に、悪い夢でも見ているような気がする。
しかし――
「……魔王、ゼロ。違う世界の俺、と言う訳か。だが、この体験はもう済ませている」
動揺は一過性の物だった。ルルーシュは以前にも違う世界の自分と遭遇している。
遠坂邸の地下で攻め込んできたアサシンと対峙した時だ。アサシンの宝具によって引っ張り出されてきた別世界の自分を、ルルーシュは即座に射殺している。
ルルーシュにとってのルルーシュとは、今ここに在る己自身のみ。
親友であるスザクと決着を着けたように、この月の戦場では違う世界の自分だとて敵となる事に疑問は無い。
「そう言えば、そうだったな。お前はアサシン――ファニー・ヴァレンタインの宝具に遭遇していたか。」
そして、その体験こそがルルーシュに確信を与えている。
一つの世界に同じ存在は共存できない。ルルーシュが別世界の自分と遭遇した時、二人の身体は崩壊していった。
あの時はキャスターのお陰で命を拾えたが、キャスターがいないこの場ではルルーシュの消滅は必然であるはずだ。
だがルルーシュも、そして魔王ゼロも、身体に変調を来たす兆候は無い。
「お前は、俺ではない……! この俺と同じルルーシュ・ヴィ・ブリタニアという存在であるはずはない!」
「然り。故に我は魔王ゼロ。かつてルルーシュであり、今はエデンバイタルの魔王となった存在」
ゼロが再び仮面を纏う。
魔王ゼロ。ルルーシュがかつて名乗っていたゼロとは違う、おそらく正しい意味での魔王という力を持った存在だろう。
ガウェインが聖剣を構える。たとえ相手が主と同じ存在であったとしても、剣を向けるに躊躇いは無いという意志の証明。
ルルーシュもまた、友より託されし槍王イルバーンをゼロへと向ける。
「お前が違う世界の俺であろうと関係は無い。お前がこの聖杯戦争の源、多くの人を巻き込んだ元凶だというのなら、倒すのみだ」
「そして聖杯を砕くか。だが、理解しているか? その後に待つのはお前という存在の終焉だという事を」
出逢った時、ガウェインは言った――聖杯を壊した時、貴方は死ぬ事になる、と。
ルルーシュはゼロレクイエムにて、ゼロとなったスザクに討たれ、死んだはずだ。その時抱いた生存への未練をムーンセルが汲み取り、この場に招かれた。
だとするなら、聖杯を破壊すれば、ルルーシュは崩壊するムーンセルと共に消えるか、あるいは召喚される直前の状態に戻り――どちらにせよ、死ぬ事になる。
一足先に自らの世界へ帰った花村やこなたのように生きて元の世界に帰ろうとするならば、聖杯を破壊するのではなく、正しい方法で運用しなければならない。
万能の願望機たる聖杯の力を以ってすれば、死にゆくルルーシュの生体情報を改竄し新たな生命を得る事もできるだろう。
それだけではなく、最愛の妹であるナナリーが望んだ優しい世界を、永久不変に実現する事も可能だ。
「貴様が俺だというのなら、わかるはずだ。“撃っていいのは”――」
「――“撃たれる覚悟がある奴だけだ”。なるほど、お前は世界を託すに足る者を見つけたか」
しかし、ルルーシュは拒絶する。二度目の生も、願望機によって成し遂げられる平和も。
ルルーシュの世界はゼロレクイエムによって破壊され、そして再生する。
混乱はあるだろう。憎しみの収束点である悪逆皇帝が討たれたとしても、それで全てが丸く収まる訳ではない。だが希望もある。戦いではなく対話のテーブルにて平和を掴もうとする人々がいる。
優しい世界の実現を目指すナナリー、それを補佐するゼロ=スザク、そしてゼロに従うとギアスを掛けたシュナイゼル・エル・ブリタニア。かつての黒の騎士団のメンバー。
平和は人の手によって創られるべき物だ。聖杯などという、人の領分を超えた例外で達成して良いものではない。
「お前はまだ聖杯に到達してはいない。聖杯戦争が終結すれば、ムーンセルはただ一人生き残った最後のマスターを迎え入れる。
だが、ムーンセルは未だお前を勝利者とは認めていない。私が阻んでいるからな。
私はお前に用がある。聖杯戦争を勝ち残った最後のマスターであるルルーシュ・ヴィ・ブリタニア、お前にな。
お前も、私と戦わなくてはならない。私を倒さねば、誰であろうと聖杯にアクセスする事はできないのだからな」
「ふん、元よりそのつもりだ。だが、倒す前に聞いておく……貴様の目的は何だ。何故、この戦いを起こした?
本来の聖杯戦争とは、七人のマスターと七騎のサーヴァントの戦いらしいな。だがこの戦いは俺を含めて二十五人のマスターと、二十五騎のサーヴァントがいた。
何故、聖杯戦争を改変する必要があった?」
ルルーシュにはそれが引っかかっていた。
衛宮士郎から聞いた本来の聖杯戦争のフォーマットは、ルルーシュが言った通り七人プラス七騎のバトルロイヤルだ。
しかしこの戦いの参加者の数はおよそ四倍弱。ここまで規模を広げる必要とは、一体何なのか。
「15848回目だ」
「……何?」
「この聖杯戦争は、15848回目だ。これまでに15847回、失敗した。
本来の聖杯戦争を幾度繰り返そうとも、私の願いを託すに足るウィザードは現れなかった。故に私は聖杯戦争を改竄した。
数十のマスターとサーヴァントが入り乱れるこの戦いは混沌に溢れ、ムーンセルとて結末を予測する事は不可能だった。そして、お前が勝ち残った」
「待て……15847回も聖杯戦争を繰り返したのなら、最後に勝ち残った奴はいくらだっていたはずだ。そいつらはどうした?」
「言ったはずだ、失敗したと。期待外れだったマスターは全て処理してきた。彼らのデータは解体され、次回の聖杯戦争を行う資源として活用された」
ルルーシュは絶句する。15847回……通常の聖杯戦争だったとしても七人いるのだ。
単純に計算してもおよそ十一万人の犠牲者が出ている事になる。
「全ては、より強い魂を選定するためだ。この戦いは私にとっても賭けだった。
今回失敗すれば、力を使い果たした私はおそらく異物として認識され、ムーンセルのある世界から排除されていただろう。
だが、間に合った。お前が勝ち残り、私の前に現れた。これで私の望みは成就する」
「望みだと? それだけの犠牲を出して、何を成そうと言うんだ!」
「私の後を継ぐ、新たな魔王の誕生だ」
ゼロは、変わらずルルーシュしか見ていない。
仮面に阻まれその瞳を窺い知る事は出来ないが、それでもゼロはルルーシュに何らかの価値を見出している事はわかった。
「立ち塞がる敵を打ち倒し、あるいは手を取り合い、お前はこの熾天の座へと到達した。
かつて聖杯戦争を制した者、衛宮士郎とアルトリア・ペンドラゴン。欠落を埋めるために絆を捨てた者、鳴上悠とクー・フーリン。
自らを嘘で塗り固めた者、天海陸とイスラ・レヴィノス。知略を尽くし立ち回った者、ジョン・バックスとファニー・ヴァレンタイン。
そして盟友である枢木スザクとランスロット……お前が出逢い、戦ってきた者達は皆、強い意志を示しただろう?
彼らの願いに貴賎は無い。故に彼らは強く、また尊い。そして、そんな願いを持つ者が淘汰しあう事により、勝者の魂はより輝きを増す」
ゼロの指がルルーシュを指し示す。
今ゼロが名を挙げた者、名を挙げられなかった者、全ての屍を踏み越えて今ここに立っているルルーシュを。
「闘争こそが人の進化を促す。魔王の座を継げる程の強い魂を、私は求めていた。
そしてルルーシュ・ヴィ・ブリタニア、お前の魂は今、かつて無い程に強く鍛え上げられている。
数十の魂を生贄に、お前は魔王の器としてこれ以上ないほどに成長したのだ」
「俺が、魔王の器だと? では、魔王とは一体何だ! 何故こんな方法で選ばれなければならない!?」
「魔王とは、エデンバイタルの使者。言わばこの宇宙の監視者だ」
ゼロは語る。エデンバイタルとは何か……そしてエデンバイタルから遣わされた魔王という存在の意義を。
「エデンバイタルは宇宙誕生の遥か以前から万物を支配する法則にしてエネルギーだ。
神……と言っても差し支えはない。人は皆、エデンバイタルの集合意識より生まれ出て、肉体を得て個として成立する。
お前には、Cの世界やアーカーシャの剣と言えば理解が早いのではないか?」
「Cの世界、アーカーシャの剣……C.C.やシャルルのいたあの世界の事か!」
「それらも、そしてこのムーンセルも、本質的にはエデンバイタルと同義だ。人類の記憶と意識の集積体。そこには過去しか無い。
Cの世界そのものにギアスを掛けたお前には、語るまでもないな」
魔王ゼロは、ルルーシュの行ってきた行動全てを把握しているのだろう。
ルルーシュがシャルル・ジ・ブリタニアの思想を否定し、人類の無意識に、人の歩みを止めるなというギアスをかけた事も。
「エデンバイタルとは、言ってみればお前がギアスを掛けなかったCの世界のようなものだ。
過去しか持たない停滞した意識エネルギーは、やがて均一化して疲弊し、死滅を迎える。
故にエデンバイタルは現世に混沌を生み落とし、人の争いを活性化させ、新たな過去……つまりは明日を作り出す」
「では、魔王とは……!」
「そう、エデンバイタルの意志を代行する者。可能性宇宙の滅びを防ぎ、世界の明日を存続させる者。
すなわち我、魔王ゼロなり」
魔王とは、滅ぼされるべき絶対悪などではない。
宇宙の熱的死から可能性を守護する者。もし滅ぼせば、遠からず宇宙そのものが滅びを迎える事になる。
正しく宇宙の監視者、あるいは安全装置と呼べる者。
「だが……だがそれならば、何故貴様は次の魔王など求める。それだけの力を持っているのなら、代わりを求める必要など無いはずだ」
「私は永く魔王で在り続けた。故に私の可能性は尽きた……停滞した。
古きは滅び、新しきを迎えねばならない。そう、お前が成し遂げたゼロレクイエムのようにな」
「何っ……!?」
「理解できない訳ではないだろう、ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。同じ存在である事など関係なく、私とお前は非常に近しい存在だ。
私が背負う魔王と言う名と、お前が起こしたゼロレクイエムという行動。
どちらも世界の明日を求めるという点では一致している。その過程で膨大な犠牲を払うというところもな」
ゼロの言葉に、ルルーシュは咄嗟に反論する事ができなかった。
確かに、ルルーシュの起こしたゼロレクイエムは世界に新たな明日を齎しただろう。
しかし、忘れてはならない。ゼロレクイエム達成の陰には、凄まじい数の犠牲が出ている事を。
権益を手放す事に同意しなかったブリタニアの貴族達、ルルーシュに反逆する黒の騎士団やシュナイゼル麾下の軍勢、その他にも武力を背景にした徹底的な弾圧を行った。
全ては世界の憎しみをルルーシュに集めるための、必要な犠牲だった――が、それはあくまでルルーシュの理屈であり、決して正しい訳でも肯定されるべき物でもない。
「私が、数ある平行世界の中でもお前を選んだのは……お前だけが、私と同じ結論に達していたからだ。
地球と宇宙という規模の差こそあれ、やがて来たる滅びを回避し、人々に明日を迎えさせるための人柱となる。
私にお前が理解できるように、お前も私を理解できるはずだ」
「俺と、お前が同じ……か。確かにそうかもしれんな。なるほど、お前の言う魔王の存在価値とやらもわからんではない。
だが、それなら最初から俺を選べば良かったはずだ。こんな馬鹿げた戦いを起こさずとも、俺だけを連れてくる事はできたはずだ!」
「そんな事をしても意味が無い。言っただろう、強き魂が必要なのだと。
別に、お前が勝ち残ると予測してお前を選んだ訳ではない。事実、お前は幾度も命を落としかけた。
私としては別にそれでも構わなかった。その場合、別の誰かがこうして私の前に立っていただろうからな。
必要なのはルルーシュ・ヴィ・ブリタニアではない。最後まで勝ち残ったマスターが偶然お前だった、それだけの話だ」
魔王ゼロにとって必要なのは、最後まで生き残った者=最も強く成長した者。
今回はそれがたまたま別世界の己であるルルーシュだった、というだけだ。
「そして、私の目論見通り、お前は魔王の器たる資格を備えた。あの英雄王さえも打ち破ったのだから不足は無い。
無論、お前と共に英雄王と戦った花村陽介と泉こなたにもまた、魔王の器たる資格はあった。
お前が彼らをムーンセルから排除した事で、魔王を継げるのはお前だけとなったが。
結果論ではあるが、彼らとの別れもまた、お前を成長させている。予想外ではあったが、歓迎すべきイレギュラーだ」
「全て……お前の掌の上という事か。では、俺がおとなしく魔王とやらを継ぐ気がないという事も、当然理解しているな?」
「ああ。私としても、お前のサーヴァントがいては魔王の継承が行えない。故にそのサーヴァントを消去する必要がある」
ルルーシュとゼロが会話している間、一切口を挟む事なく控えていたガウェインが前に出た。
我が王が敵と対話するのなら、騎士は側で王を護るのが勤め。残り少ない魔力を活性化させ、僅かなりとはいえ消耗は癒えている。
ゼロが黒きマントをはためかせ、ルルーシュへと手招きをする。
「前置きが長くなったな。さあ、来るがいい……ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。
鍛え上げた力をここに示せ。古き魔王たる我を滅ぼし、新たな魔王となりて宇宙に混沌を導くために」
「俺は魔王などになる気は無い。そして、お前を生かしておく気も無い……行け、ガウェイン!」
「ええ、ルルーシュ。今こそ決着を着ける時です!」
ルルーシュの指示を狼煙に、ガウェインが駆ける。
魔王ゼロの力は未知数――警戒すべきはガウェインの斬撃すらも無効化した掌の光印だ。
初太刀は真っ向からの斬り下ろしと見せかけ、剣先は複雑な軌跡を辿りゼロの右肘を狙う。
瞬間、ゼロのマントが沸き立ち、鋭い刃となって噴出した。影の刃は聖剣を下から叩き、軌道を跳ね上げる。
その隙を逃さず、ゼロの片足が唸りを上げてガウェインの頭部へと襲いかかった。
「……っ!」
ガウェインは体勢を低くし、避ける。頭上を行き過ぎる蹴りに込められた威力を察し、ガウェインの眼光が鋭く引き絞られた。
魔王ゼロが武器を持っていないのは、その必要がないからだと悟る。四肢を用いた肉弾戦の一つ一つが、聖剣の一撃に匹敵しかねない。
ゼロの手足を包む燐光こそがその力の源、エデンバイタルのエネルギー。ガウェインはこれを、かつての主である騎士王の業、魔力放出と同質の物であると推測した。
今対峙しているのはAランクのサーヴァント以上の力を持つ存在であると、改めて認識する。
だが、それだけだ。
これが騎士王や湖の騎士であったなら、ガウェインの斬撃は剣を以って弾かれただろう。光の御子ならばその槍で、戦友である槍兵ならば異形化させたその腕で。
ゼロの防御のやり方は、多彩な特殊能力を振るったディケイドやオーズといったライダーに近い。メインで使う武器ではなく、オプションとして備える異能で敵の選択肢を潰す。
どちらが上という訳ではないが、確実なのは一つ。魔王ゼロの接近戦の技量は、ガウェインがこれまで剣を交えた者達には及ばないという事だ。
魔王ゼロがどれだけの異能を誇ろうと、こと接近戦という土俵で勝負する限りはやがてガウェインの速度が勝る。
「コードキャスト……ハドロン砲!」
そしてルルーシュも援護が入る。かつてランスロットと戦った時にも使った、セイバーの対魔力を利用した戦術だ。
ルルーシュから放たれた赤い雷光はゼロとガウェインに等しく襲いかかる。が、ガウェインは対魔力の効果で何もせずともその雷光を打ち消してしまう。
しかしゼロはそうもいかない。魔力放出と同質のスキルを持ってはいても、対魔力までは無かったようだ。
ゼロが交差させた両手にあの光が灯る。ガウェインの斬撃を完全に停止させた絶対防御。ルルーシュのコードキャストはあっさりと吹き散らされる。
その隙にガウェインは、ゼロの軸足を狙って剣を奔らせる。両腕が塞がっているゼロは、再びマントを硬質化させ、ガウェインの剣を受け止めるようとした。
このマントは掌の光と違ってガウェインの動きを妨げる効果は無い。ただ硬いだけだ。そして、ただ硬いだけの物質などセイバーの剣の前では障害になるはずがない。
“転輪する勝利の剣”――その柄に収められた擬似太陽が駆動し、聖剣の刀身を真紅の炎でコーティングする。
炎刃は易々とゼロのマントを灼き尽くし、押し留める物の無くなった聖剣を振り抜かせる。
「――ガウェイン」
その時、王であるルルーシュと同じ声で、魔王ゼロがガウェインの名を呼んだ。
無論、その程度でガウェインが動揺するはずは無い。剣先は迷いなく突き進む。
あわやゼロの片足を斬り飛ばさんと迫ったガウェインの聖剣は――ゼロの影より突き上がってきた鋭利な刃に受け止められた。
聖剣を通じてガウェインの手に伝わったのは、金属的な衝撃。
「これは……っ」
瞬間、動きを止めた隙を逃さなかったゼロの拳がガウェインに打ち込まれた。
受け止めた純白の鎧に亀裂が入るほどのすさまじい威力。
叩き込まれた慣性に逆らわず、ガウェインはルルーシュの元へと後退した。
「さすがはAランクのサーヴァント。全力は発揮できないはずだが、接近戦では私を上回るか。
これでは些か手間取るな。では私も呼ぶとしようか――“私のガウェインを”」
「まさか……!」
「来い、ガウェイン!」
魔王ゼロが、ガウェインの名を呼ぶ。
その影から伸びていた刃が上昇していく。二メートルほどのゼロの影から、巨大な黒い機体が飛び出してきているのだ。
量子シフトにより召喚される、あり得るはずのない異形。その名を、ルルーシュは知っている。
「ナイトメアフレーム……ガウェイン!」
何故ならば、それはかつての己の愛機。全長六メートルを超える鋼鉄の騎馬。
黒く染め上げられたボディ、両肩に備えられた二対のハドロン砲、指先のスラッシュハーケン、全てがルルーシュの記憶にあるそれと一致する。
“黒き魔王の玉座”ガウェイン。魔王ゼロは、そのガウェインの頭部に傲然と立っている。
誰かが代わりにKMFのガウェインを操縦しているという訳ではない。魔王にとってはどこだろうと今立っている場所が操縦席と同義なのだ。
KMFガウェインは背部の飛翔滑走翼を展開し空へと舞い上がっていく。
「さて、こうすればセイバーに打つ手は限られるはずだが」
「甘く見られたものですね。たとえ空へ逃げようとも、その頭上には常に太陽の輝きがあるのです!」
ガウェインが握る聖剣、その柄の擬似太陽が再び駆動する。巻き起こる炎熱は聖剣の刃となり、その身を長く伸ばしていく。
地上の敵を薙ぎ払ったと言われる聖剣は、ガウェインの可視出来る範囲まで刀身を延長させられる。
飛翔していくKMFに追いつき追い抜くほどの速度で、ガウェインは天をも貫かんばかりの刺突を放った。
先程はKMFガウェインの装甲に弾かれたが、今度はその硬度をも認識した上での一撃だ。
果たして聖剣の切っ先はKMFガウェインの胴体を貫通して反対側へ抜けていく。KMFの体勢が崩れる。
「ガウェインの装甲を抜くとはな。だがそちらの攻撃が届くという事は、逆もまた然りだ」
乗機が傷ついたところで魔王には何の痛痒もないのか、相も変わらずの静かな声が通る。
魔王ゼロがKMFの背に回り、装甲を貫いたガウェインの剣を掴む。その瞬間、魔王ゼロに斬りかかった時と同じく、剣にかかるすべての運動エネルギーが停止した。
剣を引き戻そうとしたガウェインの意志に背き、天に高く突き上げられた聖剣の刀身はぴくりとも動かない。
「チェックメイトだ」
KMFガウェインが両手の指をガウェインへと向ける。その指先一つ一つが鋭利な刃を射出するスラッシュハーケンだ。
指先とはいえそこはKMFの巨体である。ハーケン一つ一つが、人の頭部ほどの大きさがある。
十の連弾がそれぞれ違う軌跡でガウェインへと放たれる。
「ガウェイン、これを使え!」
聖剣を封じられたガウェインに、ルルーシュは槍王イルバーンを投げ渡す。
サーヴァントの宝具でなくとも、槍王もまた神話級の魔術礼装の一つ。そしてガウェインはセイバーである前に一人の騎士だ。当然、馬上で振るう武器たる槍の心得はある。
ガウェインが聖剣を手放し、槍王を掴み取る。ぶんと旋回した槍王が、次々に飛来するスラッシュハーケンを片っ端から打ち落とす。
凄まじい衝撃。あるいは、ゼロの拳打と同じかそれ以上の。間断なく畳み掛けてくる爪撃は、一撃を弾くたびに残り少ない体力をごっそりと持っていく。
そして見る間に魔王ゼロとKMFガウェインは空から落ちてくる――接近してくる。
スラッシュハーケンを放ちつつ、脚部のランドスピナーを展開したKMFガウェインが足を蹴り出した。ゼロの蹴りとは比べ物にならない質量がガウェインへと迫る。
「避けろ、ガウェイン!」
さすがにこれは受け止められない。ルルーシュの指示に逆らわず、ガウェインは跳躍してKMFガウェインがの蹴りを飛び越える。
が、ランドスピナーが別の生き物のように可動してガウェインの進路上に飛び出てきた。
避け切れず、ガウェインがまともにランドスピナーに衝突した。
「がぁっ……!」
人形のようにガウェインが弾かれる。地に落ち、二度三度と跳ね飛んで転がっていく。
ルルーシュは急いで駆け寄り、こなたから渡された礼装で回復のコードキャストを起動、ガウェインへと施す。
「ル、ルルーシュ……」
「喋るな、ガウェイン。すぐに治療する!」
見れば、ガウェインの魔力で編んだ鎧が粉々に砕かれていた。耐久力に優れたセイバーを一撃でここまで痛めつけるとは。
魔王が操るKMFは、ルルーシュがかつて搭乗していたそれとは似て非なる物のようだ。魔王と同じく、エデンバイタルのエネルギーで強化されているのか。
ともあれ、ルルーシュが連続で使用したコードキャストによりガウェインのダメージは少しずつ回復していく。
それを止める様子もなく、魔王ゼロとKMFは再び大地に降り立った。
「お前は自らのサーヴァントとしてそのガウェインを引き当てたが、私はそれに関与していない。
因果な物だな。この戦いを引き起こしたのは“私”、この戦いを勝ち残ったのは“お前”。
お前の剣は“ガウェイン”、私の騎馬もまた“ガウェイン”。ふふ、エデンバイタルの導きというには些か滑稽だな」
同じ“ガウェイン”の名を冠していても、その有り様は全く違う。
ルルーシュと共に歩むガウェインと、ゼロの意のままに動くガウェイン――意志なき鉄の人形に遅れを取る訳にはいかないと、ガウェインは己を叱咤して立ち上がる。
「ルルーシュ、治療はもう結構です。魔力を温存してください」
「待てガウェイン、お前の傷はまだ……」
ルルーシュの言葉を待たず、ガウェインはイルバーンを支えに立ち上がる。
しかし、負傷は癒やし切れていない。小刻みに震えるその姿の、何と弱々しい事か。
そんなガウェインの眼前に、彼自身の聖剣が突き立てられた。
ガウェインからの魔力が途絶え通常通りの長さに復帰したそれを、魔王ゼロが投げてよこしたのだ。
「拾え。この程度で終わるはずは無いだろう」
ゼロは勝ち誇っている訳でも、慢心している訳でもない。
魔王が両手を広げると、足元のKMFガウェインもまた同じ体勢を取る。
その動作が何を意味するか、ルルーシュは瞬時に理解した。
ゼロが放り投げた聖剣をガウェインに押し付け、自身は代わりにイルバーンを引っ掴む。
「先程、ハドロン砲と言ったな。あんな紛い物ではない、本物を見せてやろう……ハドロン砲、発射」
ゼロの言葉に連動し、KMFガウェインの両肩が展開――破壊エネルギーを凝縮していく。
ハドロン砲の威力は誰よりもルルーシュが知っている。故にルルーシュは一切の逡巡無く、コードキャストを起動させた。
「ガウェイン、力を貸せ!」
主が何を求めているか瞬時に理解したガウェインは、王の前で聖剣を天に掲げる。
ルルーシュが槍王イルバーンをガウェインのガラティーンに重ね合わせた。
「絶対守護領域……!」
「聖剣よ、我らを護り給え!」
ガウェインの力を上乗せして展開した防御のコードキャストは、“聖剣集う絢爛の城”を敵ではなく自分に向けて使用するような物だ。
聖剣を以ってせねば破壊できない炎熱の結界――それはルルーシュとガウェインを灼き尽くす事無く、ただ外界からの護りとして機能する。
今のガウェインの状態では、射角が広く発射後も弾道を操作できるハドロン砲は避けきれないと判断し、ルルーシュは受け止める事を選択した。
津波の如きKMFガウェインのハドロン砲が絶対守護領域に着弾する。
「ぐうううううっ……!」
「ルルーシュ、耐えてください!」
イルバーンを通じて凄まじい負荷がルルーシュの全身に駆け巡る。身体がバラバラに弾けてしまいそうだ。
だが、屈しはしない。ルルーシュを支えるガウェインが側にいる限り、王として騎士より先に倒れる訳にはいかない。
コードキャストの展開で、もともと少なかった魔力が消し飛んでいく。
「ほう。対軍宝具に匹敵する我がガウェインの攻撃を防ぐか。そうこなくてはな」
ゼロの呟きはとてもルルーシュには届かない。
濁流の如く放射される破壊エネルギーは、閃光と轟音を伴ってこの場にいる全員の視覚と聴覚を奪っている。
それは、逆に言えばルルーシュとガウェインの声もゼロには届かないという事でもある。
「が……ガウェイン! もう少しだけ、耐えろ!」
「ルルーシュ、何か策が……?」
「この攻撃が止んだ時……奴を倒すぞ!」
それだけでガウェインは主の意図を察する。
どの道、ここまで追い込まれては戦闘を継続させる事も難しい。ならば乾坤一擲の一撃に懸けるのみ。
もはや力を温存する必要は無い。宝具を駆動させるための魔力すらもつぎ込んで、防御結界の維持に尽力する。
流れた時間は一瞬か、はたまた永遠か、ルルーシュにはどちらとも判別がつかない。
確かなのはルルーシュとガウェイン、二人とも限界を迎える寸前まで魔力を放出し尽くし、KMFガウェインのハドロン砲を凌いだという事だ。
「この辺りが潮か。ルルーシュ、お前を殺してしまっては元も子もない。サーヴァントだけを排除させてもらう」
ゼロがKMFガウェインに命じ、ハドロン砲の放射をストップさせる。
ルルーシュが地に膝をつき、同時に喀血する。絞り出した魔力の量は生命の維持すらも危ういレベルだ。
しかしその眼光は依然鋭く、魔王ゼロを刺し貫く。
「……令呪を以って命じる! 我が騎士よ、全力で戦え!」
血を吐きながらもルルーシュが令呪を解き放つ。
魔力を枯渇させていたガウェインの全身に、新たなガソリンが注ぎ込まれる。
令呪一画を純粋な魔力として変換し、ガウェインに補給したのだ。
鉛のように重かった手足に力が漲る。砕けた鎧さえ復元される。
「重ねて令呪で命じる! ガウェイン――その聖剣を以って魔王を討ち果たせ!」
それはガウェインが誇る唯一の宝具、“転輪する勝利の剣”の開放許可。
ルルーシュとガウェイン、双方が望む行動を指示され、ガウェインの魔力が再度爆発的に増加する。
消費した魔力を全て補って余りあるほどの膨大な力を、ガウェインは全て聖剣へと送り込んでいく。
「令呪か――!」
魔王ゼロは再度、KMFガウェインにハドロン砲を撃たせるべく命令を飛ばす。
だが遅い。令呪というブーストを得て加速するガウェインと、魔王ゼロから魔力を組み上げて駆動するKMFガウェインとでは、力の収束率に厳然たる開きがある。
ガウェインが聖剣を振り上げる。
「この輝きの前に夜は退け、虚飾を払うは星の聖剣――エクスカリバー・ガラティーン!」
ついに真名を解き放たれた、ガウェインの最終宝具。
その輝きはまさに太陽。地上一切を灼き払う灼熱の断罪。
魔王の漆黒さえも呑み込む、三千世界を遍く照らす太陽の具現。
ただでさえ大軍を一撃のもとに消し去る聖剣は、更に二画の令呪の後押しを受けている。この一撃に限って言えば、あるいは騎士王の聖剣や英雄王の乖離剣にさえも匹敵するだろう。
地平線の彼方まで届く灼熱の奔流は、魔王ゼロのガウェインが遅れて放ったハドロン砲を容易く吹き散らしてその巨体を呑み込んだ。
炎熱の波は留まるところを知らず、魔王とKMFのみならずその向こう――フォトニック純結晶の檻に抱かれたムーンセルの中枢までも、その輝きで塗り潰していく。
背後にムーンセル中枢があるからこそ、ゼロは回避という選択が出来なかった。それを見越してガウェインは聖剣を解き放ったのだ。
先のハドロン砲よりも長い時間、聖剣は灼熱を吐き出し続ける。
やがてガウェインの魔力が尽き、炎が陽炎となって消えゆくその時には、魔王とその騎馬は熾天の座から姿を消していた。
「……っは、ぁ」
「よく……やった。ガウェイン」
ガウェインが荒い息を吐き、聖剣を下ろす。赤熱化した刀身は、触れるだけで地面を融かすほどに高温だ。
令呪の支援を受けた日輪の剣はかつてない力を発揮し、魔王ゼロごとKMFガウェインを一瞬で蒸発させた。いかに魔王といえど、あれだけの熱量の直撃を受け流す事などできなかったようだ。
ルルーシュの知る兵器に換算すれば、ハドロン砲や輻射波動など足元にも及ばない。それこそフレイヤ並み、あるいはそれ以上の威力だったのだから。
「魔王ゼロは……倒したのか?」
どこにも魔王の姿は無い。砕け散ったKMFの破片には隠れるほどの大きさもなく、ルルーシュの前に広がるのは変わらず浮かぶ立方体のオブジェのみ。
魔王と名乗った存在にしては呆気ないものだが、かと言ってどこかに潜んでいる様子は無く、礼装で周囲を探査しても魔王らしき痕跡はどこにも無い。
入念に周囲を調べ、その末にようやく魔王を倒したと結論を得て、ルルーシュは腰を下ろした。
これで、長きに渡る戦いは終わった。
聖杯戦争を歪めた魔王は討たれ、ルルーシュとガウェインが真の勝利者となった。
しかし――
「ムーンセルは……無傷、か」
ルルーシュはムーンセルをゼロごと消滅させるつもりで、ガウェインに聖剣を使わせた。
魔王とKMFの存在が聖剣の威力を減衰させたか、あるいはそもそもそんな方法では破壊できないのか、どちらにしろムーンセルは依然としてそこにある。
「ならば、直接アクセスするだけだ。今ならムーンセルは俺を迎え入れる……そうだな、ガウェイン?」
「ええ……もはや我らを阻む者はない。魔王がムーンセルを掌握していたというのなら、魔王を討った今、あなたこそが月に残った最後のウィザードになる。
往ってください、ルルーシュ。今こそあなたの願いを果たす時です」
そうルルーシュに告げるガウェインは、しかし自らは動こうとしない。
ルルーシュにもわかっている。ついに、別れの時が来たのだ。
槍を杖にして立ち上がり、ルルーシュはガウェインと向かい合う。
――お目覚めですか?
ガウェイン。この聖杯戦争を共に駆け抜けてきた、ルルーシュの剣。
死にゆくはずのルルーシュに二度目の生の始まりを告げた者。
出逢った時に交わした言葉は、ルルーシュの心中に一言一句刻まれている。
――貴方はルルーシュ・ヴィ・ブリタニア陛下。私は貴方に仕えるべく召喚された、ガウェインと言う者です。
かつての愛機と名を同じくする、誉れ高き円卓の騎士が一人。
太陽の騎士と異名を取る、Aランクのセイバー。
最初は、ガウェインという名と巡り逢う奇妙な縁に、おかしささえ感じたものだ。
――聖杯を壊した時、貴方は死ぬ事になる。それでも構わないのですね?
聖杯を破壊する。ルルーシュにとっては揺るぎなきその願いは、通常のサーヴァントにしてみれば言語道断の物だろう。
サーヴァントとてマスターと同じく願いがあり、その願いを叶えるために聖杯を欲し、聖杯に到るために戦う。
であれば、ルルーシュが聖杯を破壊すると宣言した瞬間、ガウェインに斬られても何の不思議も無かった。
ルルーシュを外れのマスターとして処理し、次のマスターに選ばれる確率に賭ける。願いを叶えたいのならばそれくらいはするだろう。
――我が剣は忠義の剣。貴方を我が主と定め、我が命を貴方に捧げると誓う!
だが、ガウェインはそんなルルーシュに剣を捧げると言った。
ルルーシュが聖杯を破壊すればがガウェインの願いは叶わない。
それでも構わないと、そもそも聖杯に懸ける願いなど無いと微笑み、ガウェインはルルーシュに仕えると決めたのだ。
――貴方の定めた道は確かに王の道。騎士としてこれほどの誉れはありません。
生前には成し得なかった、正しき騎士として最期まで王を支える事。
もし次があるのなら。二度目の生があるのなら、今度こそ、自らの全てを王に捧げよう。そう願っていた。
そして、ガウェインは忠義を尽くすに足る王に出逢った。
茨の道を歩む孤高の王。誰からも理解されず、しかし誰かの幸せを願いその身を投げ出せる者。
ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアがガウェインを召喚したのは、決して偶然などではない。
ルルーシュという存在そのものに、ガウェインの魂が惹かれたのだ。そんな王の騎士として、戦場を馳せる。これ以上に望む事などあるはずが無い。
ガウェインの願いは、ルルーシュに出逢った瞬間に叶えられていたのだ。
「ルルーシュ、あなたと過ごした時間は二日にも満たない短い物でした。だがこの二日間は私にとって、どんな武勲にも勝る価値があった。
あなたという王に仕え、幾人もの戦友を得て、叔父上ともう一度肩を並べて戦い、そして友と決着を着けられた」
生前のガウェインは、王を疑う事はしなかった。
騎士王の選ぶ道は全て正しく、間違いなどあるはずが無い、そう信じていた。故に騎士王を裏切ったランスロットを許せず、判断を誤り続けてしまった。
だが今ならわかる。ゆらぎがあってこそ人であり、人のまま王になるからこそ尊いのだと。
過ちを悔い、成長の糧として学び、次の機会には乗り越える。そして前に進み続ける。
ルルーシュという人間は、どんな苦難に見舞われようとも絶対に前進を止めない人物だ。完璧ではない故にミスを犯す。敵に怒り、仲間と共に笑い、悲しむ。
敗北の屈辱を舐めてなお、折れず曲がらず反逆し続ける。かつて剣を捧げた騎士王とは違うが、これもまた気高き王道。
そんなルルーシュに従う事は、ガウェイン自身にも影響を与えていた。
もし仮に、ガウェインのマスターがルルーシュではない別の誰かだったとしたら。きっとガウェインは、この場に立ってはいないだろう。
ルルーシュが戦いの中で成長したように、ガウェインもまた王の在り方に影響されていたのかもしれない。
「本当に、夢の様な時間でした。私などには過ぎた栄誉です。だから、あなたには感謝しています、ルルーシュ。
私のマスターが……私の王が、あなたで良かった」
今、万感の思いを込めて、ガウェインは王に別れを告げる。これより先は共に行く事は出来ない。
ルルーシュがムーンセルにアクセスし、最後のマスターとして自壊を命じれば、ルルーシュは再び死の運命に回帰する。
過去の英霊を電子的に再現された存在であるガウェインもまた、ムーンセルの崩壊と共に消滅するだろう。
死出の道行に供をする事は許されない。だからこそ、ここで別れる。敬愛する王の結末を見届ける。それこそが騎士としての最後の勤め。
「往かれよ、我が王よ。私はここであなたを見ています。
あなたが眠りにつくその時まで、私はあなたを見守りましょう」
聖剣を地に突き立てる。もはや武器は必要ない。ルルーシュが聖杯にアクセスし、全てを終わらせる時を待つ。
そんなガウェインを前にして、ルルーシュの内から出る言葉はただ一つ。
「……ガウェイン。お前の忠義、決して忘れん。さらばだ」
言葉少なに、別れだけ告げる。これ以上の言葉など必要は無い。
ガウェインの在り方を認め、彼が捧げた忠義を確かな記憶として死を迎える。それこそが、ルルーシュが彼の騎士に報いる最大の恩賞となる。
踵を返し、歩き出す。遅々とした歩みだが、一歩一歩着実に聖杯へと近づいていく。
背中にガウェインの視線を感じる。見届けると言ったガウェインの言葉に偽り無く、きっと最期まで見守っているのだろう。
そう思うだけで前に進む力になる。死ぬ時に一人ではない事が、こんなにも安心するものであると初めて知った。
思い出す。最初の死――あるべき本来の死を迎えた時、そこにはナナリーがいた。
あの時、ナナリーは泣いていた。結局、最後まで最愛の妹に真意を伝える事は出来ず、傷つけてばかりだった。
済まないと思う。申し訳ないと思う。それでも、ルルーシュは後悔はしていない。
間もなくルルーシュは死ぬ。だが幸い、ナナリーがそれを知る事は無い。ルルーシュが生きている事も、そして死ぬ事も。誰にも知られず、この月の中でひっそりと終わるのだ。
これで全てがゼロに戻る。ゼロレクイエムにてルルーシュの世界は再生に向かい、聖杯が解体される事で二度と聖杯戦争は起こらない。
無論、失った者達が戻る訳ではない。そのマイナスは決して消えない。
だが、それでも。
「花村と、泉。お前達が生きて、俺や衛宮、金田一や名無を覚えていてくれるなら……」
決して、無意味な死ではないはずだ。
心残りがあると言えば、再会の約束を果たせない事か。今頃、あの二人は自分の世界に戻れているだろうか。
戻れていたとして、そこはムーンセルの支配力が及ばない世界。
ペルソナとサーヴァントの複合体であるアレックスと、メダルに姿を変えた火野映司は、そう長くは存在を保てないだろう。
彼らにも、ルルーシュとガウェインのように逃れられない別れは来る。
「だが、お前達なら大丈夫だ……そう、信じている」
別れる事よりも、出逢えた事が嬉しい。陽介とこなたなら、そう思ってくれるはずだ。
戦いの中で背負った悲しみに負けず、日常を生きていく事ができる。そんな強さを持っていると、ルルーシュは信じられる。
やがてルルーシュは聖杯に到った。
手が届く距離。触れてみて、思念を送る。結晶体が振動し、膨大な情報がルルーシュに向けて開示される。
万能の願望機。事象を書き換え、あらゆる願いを叶える聖杯。その中枢――フォトニック深淵領域への道が開かれた。
最後に、もう一度振り返る。ガウェインは変わらず、ルルーシュを見守っている。
はず、だった。
ガウェインのを背後から貫く影――魔王ゼロ。
滅びたはずの魔王が、太陽の騎士を串刺しにして、ボロ屑のように放り捨てていた。
「なっ……!」
「言っていなかったな。私を滅ぼせる者はこの宇宙には存在しない――今はまだ、な」
その声は耳元で聞こえた。
振り返る寸前、首筋を掴まれる。ルルーシュの細首など容易く砕けるであろう豪腕は、紛れも無く魔王のそれだ。
ガウェインを倒し、一瞬にしてルルーシュの背後へと移動……否、転移してきた。
魔王は滅びてなどいなかった。この転移の力によって何処かへと姿を消し、ルルーシュがガウェインから離れて一人になる時を待っていたのだと、ようやくにして理解する。
「我がガウェインを破壊したのは見事だった。が、どれほどの宝具を誇ろうと私には通じない。
私のワイアードギアス――“ザ・ゼロ”の前では、森羅万象が無へと帰するのだから」
掴まれた首を無理やり捻り、ルルーシュは何とかゼロへと顔を向けていく。
ゼロは本当に無傷だった。四肢も黒のマントも、全て健在だ。ゼロのギアスを単なる運動の停止だと見誤ったのが、ルルーシュとガウェインの敗因。
だが予測するなど不可能だ。ゼロのギアスは、個にして神たるエデンバイタルと同等――人智を超えた力なのだから。
手にしていたイルバーンをゼロの仮面へと叩きつける。技巧も魔術も無い、反射的な行動だった。
穂先はゼロの仮面へ突き立ち、亀裂を走らせる。が、内部まで届いてはいない。
ゼロが仮面へ突き立ったイルバーンに軽く触れた瞬間、ルルーシュの手から忽然とイルバーンが消失する。
名無から託され、何度も危地を切り抜けてきた武器さえも奪われた。
「お前にはもう必要無い。武器も……そしてサーヴァントも」
イルバーンがなければコードキャストは発動させられない。
ゼロはルルーシュを無力化した事を確認すると、締め付けていた指を解く。床に放り出されたルルーシュは、視線を巡らせてガウェインを見る。
ガウェインは、死にかけていた。
ムーンセルによって除外されるデータが始まっている。だが、ルルーシュにその兆候は無い。
ここ熾天の座では通常の聖杯戦争のルールは適用されないのか、あるいは連動してルルーシュも死ぬ事を恐れたゼロが細工をしたのか。
いずれにしろ、心臓を破壊されてはいかにサーヴァントとて絶命は避けられない。
令呪を用いようとも、魔力の器たる肉体が徹底的に破壊されている以上、あの状態からの復帰は絶望的だ。
「ガウェイン……」
「…………ぁ」
伏したガウェインが、血と共に言葉を絞り出そうとする。
その瞳は悔いに満ちていた。最後の最後で仕損じた、誤った。王を守れず先に逝く事を、心から悔いている表情だった。
「そんな顔で、死ぬな……!」
そうではない。ガウェインとの別れは、こんな形であってはならない。
忠義の騎士が無念と共に果てる事など、絶対に許してはいけない。
その思いは、叫びとなって迸る。
「誇れ、ガウェイン! お前は俺の、この俺の道を斬り開いてきた騎士だ!
お前がいたから俺はここまで来れた! お前の忠義が、俺をここへ導いたんだ!
だからガウェイン……俺は、お前を誇る! 俺の騎士は、誰よりも強く、気高い……太陽のような男だ!」
ルルーシュの手に残された令呪が輝きを放つ。三画目の令呪を使えば自らも消滅する、そんなルールは頭の中から吹き飛んでいた。
ガウェインに落ち度は無いと。後悔の内に死ぬのではなく、自らを肯定して眠りにつけと。
この令呪は何の命令にもなっていない。ガウェインの傷を癒やす事も、魔王に一矢を報いる事も無い。
ただガウェインの心を救いたい、その一心で叫んでいた。
「――――――――」
思いは、届いたのか。
目を見開いたガウェインが何かを言おうとして口を開く。
その言葉が紡がれる寸前――ガウェインは消えた。
「ガウェ……イン」
「その悲しみは無意味だ。サーヴァントは死ねばムーンセルによって情報を回収され、いずれまた誰かのサーヴァントとして召喚される。
奴とて例外ではない。道具が壊れただけでそこまで感傷的になる必要は無いだろう」
無感動にゼロが言う。
ゼロはルルーシュが令呪を使うのを止めはしなかった。最後の令呪を使ったところで、ルルーシュは消滅しないと知っていたからだ。
この熾天の座は聖杯戦争のルールの外にある。ガウェインが消去されたのは、ゼロがそうなるようにムーンセルを操作したからに過ぎない。
ルルーシュから全てを奪い、魔王の役割を受け入れさせる。そのためだけにガウェインを殺し、消し去ったのだ。
「無意味だと……? 貴様はあいつを、ガウェインの死を……無意味だと言うのか!」
「すぐにお前もそう感じるようになる。お前も魔王となるのだから」
「ふざけるな! 俺は貴様のようにはならない!」
「お前の意志などどうでもいい。エデンバイタルは既にお前を選んでいる。
抗う事など出来ない……さあ、内なる扉を開け。私を滅ぼす力、魔王の資格たるお前のワイアードギアスを目覚めさせるのだ」
ルルーシュはゼロに引きずり起こされる。
ゼロが突き付けてきた掌に光が灯る。ザ・ゼロではない、エデンバイタルと呼ばれる意識エネルギーの光だ。
そのエネルギーを、ゼロはルルーシュへと染み込ませていく。
「ぐわあああっ!」
「やはり私と同じ器か。私の中のエデンバイタルがこうまで馴染み易いとは。これならば、あるいはザ・ゼロそのものを目覚めさせる事も不可能ではない」
「やめろ……! 俺の中に……入って、くるな!」
「受け入れろ。エデンバイタルと同化すれば、お前は私を滅ぼす力を得る。そしてお前は宇宙に混沌を撒く存在となる。かつての私と同じように」
「その結果……どうなる! お前が俺だというのなら、俺が辿る結末とて……お前と同じはずだ!」
「だろうな。だからその時は、お前がもう一度この聖杯戦争を引き起こすのだ。
このシステムが新たな魔王を生む事は、お前という実例を以って証明された。ならば後は繰り返すだけでいい」
「そんな事を……!」
認めるものか。だがその思いは言葉にならない。
余りにも膨大なエデンバイタルの情報量は、未だ魔王たりぬルルーシュの脳では処理しきれない。
故に魔王ゼロはルルーシュの意識を喪失させる。エデンバイタルが、ルルーシュの無意識領域で生体情報を書き換えた時が、魔王新生の瞬間だ。
ルルーシュには既にワイアードギアスの萌芽が芽吹いている。ルルーシュの瞳で激しく明滅するエデンバイタルの輝きがその証拠。
抗う事もできず、ルルーシュの意識は暗い闇へと落ちていく。
「ようやく……終わる。永遠に続くと思っていた俺の旅は、ここで終わる。お前には済まないとは思うがな」
意識を失ったルルーシュには、ゼロの言葉は届いていない。
だからこそ、今だけは魔王ゼロではなく、ただのルルーシュに戻る事が出来る。
仮面を外したゼロが、項垂れるルルーシュにそっと囁きかけた。
「もしかすると俺は……お前に、嫉妬していたのかもしれない。
俺と同じルルーシュという存在でありながら、お前は人として生き、世界を変えて、死んだ。魔王にならざるを得なかった俺には、お前の生き方は眩しい物だった。
だから、なのか……お前が勝ち残ったと知った時は、少し、期待したよ。お前なら、あるいは俺を、魔王という存在を否定し、違う未来を創り出せるのではないか、と」
ゼロレクイエム――ルルーシュが計画した世界再生の策は成った。
それは魔王の目から見ても瞠目に値する結果だ。ギアスを用いたとはいえ、ルルーシュはあくまで己の意志と力で世界を変えた。
無論スザクやその他の協力者の力も大きい。が、何より重要なのはルルーシュ個人の覚悟だ。
世界を壊し、世界を創る。ルルーシュの言葉に偽りは無く、古き世界は破壊され新たな世界が産声を上げた。
しばらく混乱は続くだろう。だがその痛みを乗り越える強さを、あの世界の人々は手に入れた。
「俺は、お前が変えたあの世界を尊いと思う。だからこそ、新たな魔王は必要なんだ。
混沌なくして宇宙は変化しない。俺が魔王であり続ければ、いずれお前の世界も停滞に呑み込まれ、死を迎える。
滅びを防ぐにはこうするしかない」
それが一時の延命処置であったとしても、宇宙が滅びを迎えるよりはマシだと、ゼロは思う。
「許しは請わない。いずれお前も俺と同じ選択をする時が来る。
その時、お前が新たな魔王を選び出すか、あるいはそれ以外の道を見出すのか――それを知る事ができないのは、少し残念だとも思うよ」
誰の記憶にも残らない言葉は、ここで終わる。
ゼロは再び仮面をかぶり、沈黙のままルルーシュの変化を見据えている。
やがてエデンバイタルは完全にルルーシュへ定着し、生体情報の書き換えを終えた。ルルーシュの意識が回復する。
瞼を開けたルルーシュのその瞳には、ザ・ゼロと同じ紋章が瞬いている。ワイアードギアスが発現したのだ。
それも、ザ・ゼロと同等かそれ以上の――
「これでいい。ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア、お前こそが新たな魔王ゼロ……いや、“魔王C.C.”だ。さあ、そのギアスで私を滅ぼし、無二の魔王となるがいい」
「ああ……そうだな、もう一人の俺よ。俺はお前を滅ぼす……」
発現したワイアードギアスの使い方は既に理解している。
ルルーシュがゼロの腕を取る。そしてもう片方の手を握り締める。
その掌には、陽介から託された契約者の鍵がある。
「だが! 俺は魔王にはならない!」
ルルーシュが怒号と共に繰り出した拳は、槍王イルバーンが突き立った一筋の亀裂へと叩き込まれる。
ゼロと同じくエデンバイタルの光を纏ったその一撃は、ゼロの仮面を粉々に砕き割った。
◇ ◆ ◇
全て失った。
騎士も、武器も、戦う意志も。全てを魔王に砕き散らされた。
後はもう、魔王のされるがままだ。エデンバイタルは着々とルルーシュの魂を改竄していく。
どこまでも底のない暗闇に落ちていく感覚。この感覚は知っている。これは、そう――
「負けたのか、俺は」
土の味――敗北の味だった。
ガウェインと出逢い、仲間と数多の戦いを潜り抜け、魔王と対峙した。そして敗北した。
士郎や名無、そして彼らのサーヴァント達という犠牲の上に辿り着いた決戦に、勝つ事が出来なかった。
ルルーシュの剣であるガウェインも、名無から託されたイルバーンも、ルルーシュの手を離れた。
もう打つ手が無い。
「奴の、魔王の役割を……受け入れるしか……ないか」
だが、それは悪なのだろうか。
ゼロの言う事を信じるなら、ゼロはゼロで宇宙の存続のために動いているのだ。
魔王がこの宇宙の維持に必要だというのなら、ルルーシュが魔王となるのが正しい選択ではないのだろうか。
そうすれば、ナナリーが生きる世界も、陽介やこなたが帰った世界も、護ることに繋がる。
「……なら、俺は……」
抗う事を止めて、受け入れる。
言葉にすれば簡単な事。
だが――
「俺は……こんなになっても、まだ……」
諦められない。
ゼロに屈服し、負けを認めて、魔王になる。
ただそれだけの事を、どうしても受け入れられない。
「どうする事もできないっていうのに……」
今やルルーシュに残されているのは、絶対遵守のギアスだけだ。
いや、もう一つあった。
意識する。陽介との別れの際、彼から譲り受けた物――契約者の鍵を。
「花、村……泉……」
遠く離れてしまった友の事を想う。
再会の約束は、魔王になればきっと叶うだろう。
だがあの二人に、魔王となった姿を見せる事は――運命に屈した様を見せる事は、絶対に嫌だ。
――だったらさ。立つしかねーよな?
その時、懐かしい声が聞こえた。ここにいるはずのない、再会を誓った友の声が。
契約者の鍵から声が、想いが伝わる。
――だから、俺も行くっつったのによ。一人で突っ込んで負けて、そんでウジウジ後悔してるなんて。カッコ悪いぜ、ルルーシュ。
――まあまあ、あんまりいじめないであげようよ。ルルーシュ君も頑張ったんだからさ。
鉛のように重い瞼をこじ開ける。星明かり一つ無い暗闇の中にあって、はっきりと見える。
花村陽介と泉こなたが、そこにいる――
――ほら、立てよルルーシュ。まだ……やれるだろ?
――もうちょっとだよ。一人じゃ立てないなら、ほら。私たちの手を取って。
こなたがルルーシュの手を握る。
伝わってくる暖かさは、決して幻などではない、本物の熱を感じさせる。
――言ったはずだぜ、今度会った時はぶん殴ってやるって。でもまあ、今のお前を殴るのはさすがにちょっとって思うからな。
陽介がにやりと笑う。
そしてこなたと同じく、ルルーシュの手を取った。
――だから、次だ。次会った時にお前を殴る。今は、手を貸してやるよ。
――素直じゃないなあ、もう。
――へへ。なあ、ルルーシュ……悠はもういねーけど、お前はまだ生きてる。だから、諦めんなよ。生きてるなら何度だってやり直せる。
――疲れたのなら、私達たちが肩を貸すよ。でもね、立ち上がるのはルルーシュくんの足なんだ。
――俺達にできるのは、お前を信じて手を差し伸べる事だけだ。ああ、俺と泉はお前を信じるぜ。なんたって俺達は。
――友達だからね!
「友達……ああ、そうか。お前達は、俺の……」
――周り、見てみろよ。俺達だけじゃないぜ。
――みんな、ルルーシュくんが立ち上がるって信じてるんだよ。
陽介に促され、辺りを見回す。
アレックス、火野映司、衛宮士郎、セイバー、名無鉄之介、リインフォース、そして枢木スザク。
みな、ルルーシュを見ている。
これだけの仲間と絆を紡ぎ、ルルーシュは歩いてきたのだ。
「……ああ、そうだな。俺はまだ……」
何もない、全てを失ったと思った。だがそうではない。
武器が無い。サーヴァントがいない。それが、一体どうしたというのか。
そんなものは――戦わない理由には、抗わない理由にはならない。
「俺は……!」
反逆する。
理不尽な運命、強大な敵、歪んだ世界――その全てに反逆する。
それこそがルルーシュ・ヴィ・ブリタニアという存在の起源。
「俺は誰にも従わない……相手が神や魔王であったとしても、絶対に!」
空っぽだった肉体に、もう一度立ち上がる力が湧いてくる。
押し付けられた役割などいらない。
常に自分の意志で生きる。それが、ルルーシュという人間が己に課したただひとつのルール。
陽介とこなたに手を引かれ、それでも最後は自分の足で、ルルーシュは立ち上がる。
――もう、大丈夫だよな?
「ああ……すまないな。最後まで面倒をかけた」
――最後じゃないよ。絶対もう一度会うって、約束したでしょ。
「ふ……そうだったな。ならばこれ以上負けている暇などない。
さっさと魔王を片付けて……お前達に会いに行くとしよう!」
――おう、待ってるぜ!
――私、ここではみんなのお世話になりっぱなしだったよね。だから、次はみんなで一緒に遊ぼう! 遊びなら私の右に出る人はいないよ!
「ああ、約束する。俺の方からお前達に会いに行く!」
――これで最後なんだ。持ってけよ、俺達の力!
――頑張って、ルルーシュ君! きっと勝てるよ!
繋いだ手だけが紡ぐもの。
陽介とこなた、二人からの贈り物。
確かな絆を握り締め、ルルーシュの意識は覚醒していく。
戦場へ――魔王が待つ、熾天の座へと帰還する。
◇ ◆ ◇
「何だと……!?」
ルルーシュの拳によって、魔王ゼロの仮面は砕かれ、生身のゼロの顔がむき出しになった。
当然、鍛えていないルルーシュの拳も同様に砕けている。
だがそんな事を意に介さず、ルルーシュはさらに距離を詰めていく。
「何故、魔王として覚醒していない!? エデンバイタルはお前を呑み込んだはずだ……!」
「ああ、その通りだ。確かに俺はエデンバイタルの海に沈んだ。
だがお前が言ったんだ、エデンバイタルは人の集合意識だと。そこにあるのは魔王の意志だけじゃない!
俺達が繋いだ絆もまた、個から解き放たれ集合意識へ還る。その絆が俺を俺のまま、ここへ導いた!」
ペルソナ使いが操るペルソナは、人の無意識領域に棲まうもの。
一度精神世界で陽介とリンクしたルルーシュとこなたには、無意識領域の繋がり――コミュニティとも呼ばれるものが存在している。
そして、エデンバイタルの流入によりルルーシュの知覚は瞬間的に無限大まで加速した。
違う世界に分かれてしまった陽介とこなたに、意識を接続できるほどに。
「あいつらが思い出させてくれた。誰が相手だろうと、俺は絶対に従わない。
この命ある限り反逆し続ける――それがこの俺、ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアだ!」
「……だが、それで何が変わる。魔王にならないままワイアードギアスに目覚めたとて、私に抗う事は出来まい」
視線を絡ませる。ルルーシュに発現したワイアードギアスがどのようなものであっても、ゼロのワイアードギアス“ザ・ゼロ”ならば無効化できる。
ギアスをギアスで封じられるのならば、競えるのは肉体の基礎性能のみ。多少エデンバイタルを扱えるようになっても、ルルーシュに勝ち目など無い事は自明の理だ。
「魔王を受け入れろ、ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。お前が選ぶべき道はそれだけだ」
「断る。俺は魔王にはならないし、お前から逃げるつもりも無い。
俺はルルーシュ・ヴィ・ブリタニアとして、かつてルルーシュ・ヴィ・ブリタニアであったお前を滅ぼす!」
「不可能だ、お前には」
「ああ、不可能だろう……俺だけではな。だからこそ、俺は一人ではないのだ!」
ルルーシュの瞳が、黄金の輝きを放つ。
“ザ・ゼロ”と同じ紋様を展開する、そのギアスこそが。
「これが俺のワイアードギアス――森羅万象に命じる力、“ザ・ギアス”!」
呪い――あるいは願い。ギアスそのものの名を冠した、ギアスの中のギアス。
ルルーシュが本来宿していた絶対遵守のギアスを発展させた、神にすら匹敵する力。
瞳から放たれた光の印は、幾重にも重なりゼロへと迫る。
ゼロは、“ザ・ゼロ”での迎撃を選ばなかった。未知のギアスに不用意に干渉するリスクを避けたのだ。
結果、“ザ・ギアス”の光はゼロの背後――ムーンセルの中枢、聖杯へと叩き込まれる。
瞬間、ゼロはルルーシュの狙いを悟る。
「ルルーシュ、貴様っ!」
「ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアが命じる! 聖杯よ――我が騎士をここに呼び戻せ!」
“ザ・ゼロ”がムーンセルをハッキングできるのならば、同等のギアスである“ザ・ギアス”もまた干渉が可能だと言う事だ。
そして今、ルルーシュの手には令呪がある。
花村陽介と泉こなたがムーンセルから脱出する際、二人から異物として剥がれ落ちた最後の令呪。夢の中で、二人から託された最後の希望。
今のルルーシュは、サーヴァントを統べるマスターたる資格を備えている。
果たして――ムーンセルは、ルルーシュの要請をマスターの正当な権利として受諾した。
ムーンセルがデータベースを閲覧し、ルルーシュと組み合わせるべきサーヴァントを検索する。中でも一際強く反応を示した者を与えるとムーンセルは決定した。
ルルーシュとゼロの間に、灼熱の尖塔が立ち昇る。纏うは白の鎧、振るうは日輪の聖剣。
ゼロが咄嗟に打ち込んだ拳は、輝く聖剣にしかと受け止められた。
「……ガウェイン!」
「ここに! 我が王よ、遅参致しました」
太陽の騎士は、王の元へと帰還した。
その姿は消去された時のまま、満身創痍である。
「俺を忘れてはいないだろうな?」
「無論です、ルルーシュ。あなたの命令――しかと聞き届けました。
月が太陽の輝きを隠す事など出来はしない。私は変わらず、あなたの騎士であり続けている」
だが、今のガウェインに負傷など何の障害にもならない。
自らを誇れ。王の最後の命令は、騎士の魂をこれ以上ないほどに燃え猛らせた。
敗戦を経てなお、王は膝を屈する事をよしとせず、騎士を呼んだのだ。これに奮起せずして何が騎士か。
ルルーシュは聖杯を背後に、再び魔王と対峙する。傍らにいる太陽の騎士の存在が、ルルーシュの力を押し上げてくれる。
「ムーンセルへのハッキングが仇となったか。サーヴァントの消去が間に合わないとはな」
「お前でも予測できない事があるか。魔王といえども万能ではないようだな」
「エデンバイタルに呑み込まれず、人のままで逆に支配したというか。
ならばルルーシュ、お前はもはや魔王の器などではない。お前はまさに――エデンバイタルの魔人だ」
ゼロの脳裏に古い名が思い浮かぶ。
エデンバイタルの魔人――その存在は、遥か遠き過去にもう一人いた。
そいつの名にあやかって、今のルルーシュを表すのならば。
「ルルーシュ・ザ・コードギアス……!」
今やルルーシュは、魔王ゼロに匹敵する力を得た。
“ザ・ゼロ”と同等のギアス、“ザ・ギアス”。そして再召喚されたガウェイン。
魔王ゼロのガウェインは破壊され、未だ再生していない。
だが、まだゼロに分がある。再召喚されたとてガウェインの負傷は癒えていない。未だ無傷のゼロなら、仕留める事は容易いはずだ。
「魔王ゼロ、もう一人の俺よ。決着を着けるぞ!」
「魔人ルルーシュ、もう一人の私! いいだろう……来い!」
三人が、同時に駆け出す。
誰よりも早く踏み込むのは、やはりガウェイン。
宝具の開放も何もない、全身の勢いを乗せた真っ直ぐな突きを放つ。
ゼロが両手に展開した“ザ・ゼロ”が、聖剣を三度、完全に停滞させる。
森羅万象を無に帰す力。ゼロはガウェイン本体をも無に帰そうと、聖剣を直に掴む。
「ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアが命じる! 止まるな、ガウェイン――進み続けろ!」
「うおおおおぉぉぉっっ!」
「こ、この力……!?」
そこにルルーシュの“ザ・ギアス”が飛ぶ。
森羅万象を無に帰す力は、森羅万象に命じる力によって相殺され、効果を失くす。
故にガウェインの剣は止まらない。切っ先が僅かに、“ザ・ゼロの”光印へと突き刺さる。
「“ザ・ゼロ”を超えるのか……!」
「さらに令呪を以って命じる! ガウェイン――貫け!」
「おおおおおおぉぉっ……!」
花村陽介の令呪が輝き、ガウェインを後押しする。
聖剣はさらに突き込まれ、“ザ・ゼロ”を突破し魔王ゼロの掌へと侵攻した。
「ぐっ……!」
「重ねて令呪を以って命じる! ガウェイン――俺に勝利を捧げてみせろ!」
「……イエス、ユア……マジェスティ!」
駄目押しに、泉こなたの令呪を解き放つ。
ワイアードギアスと令呪二画、合わせて三重のブーストがガウェインの剣に宿る。
擬似太陽が脈動し、聖剣は万物を灼き尽くす炎を纏う。
ガウェインは王に捧げる忠義の言葉を叫ぶ。そして全力以上の全力で、聖剣を突き抜いた。
「…………」
光が弾ける――静寂が戦場に染み渡る。
ルルーシュの眼前で、ガウェインの聖剣は、忠義の剣閃は――確かに魔王の中心を刺し貫いていた。
“ザ・ゼロ”を打ち破られ、肉体に重大な損傷を負い、魔王はついに崩れ、倒れる。
「……俺達の勝ちだ、魔王ゼロ」
「……そのようだ。私に与えられた時は……尽きた」
ゼロは地に伏し、ルルーシュはそれを見下ろしている。
今度は先程のようなブラフではない。
ルルーシュのワイアードギアスによって互角の条件に引きずり降ろされた魔王は、全ての虚飾を取り払われたも同然。
故に全力でルルーシュらに挑み、そして敗北したのだ。
こうなってはもはや、ルルーシュに魔王を継承させる事は不可能だろう。
ただ滅び、宇宙が熱的死を迎えていくのをエデンバイタルの彼岸から傍観するしか無い。
「いや、そうはならない」
しかし、ルルーシュは断言する。
そんな事は起こらない――起こさせない、と。
ナナリーの生きる世界、陽介やこなたの帰る世界を、失わせる訳にはいかない。
「何……?」
「エデンバイタルと繋がって知った。お前の宇宙が滅びたのは、お前があまりに長く魔王で居続けたせいなのだろう。
変化のないエデンバイタルの意識エネルギーは停滞し、死を迎える。なら、魔王という存在に収束した可能性を、解き放ってやればいい」
「どういう、意味だ」
「お前がやった事の逆をするだけだ。ムーンセルの事象改竄能力を用いて、エデンバイタルをハッキングする。
そして、魔王というシステムそのものを消去する。そうすれば、世界が魔王を核に存在するなどという事はなくなるだろう」
「馬鹿な……そんな事をすれば、世界はすぐに停滞する。ギアスという混沌無しでは、世界は変化を保てないのだぞ」
「何故そう言える? お前は所詮自分の世界を見てきただけだ。
花村、泉、金田一……ギアスなど無くとも彼らの世界は回っている。
エデンバイタルの干渉こそが、可能性を殺し意識を停滞させるのではないのか?」
「根拠の無い空想だ。そんな不確かな物に全宇宙の存亡を賭けるというのか!」
ゼロは真実、宇宙の行く末を案じているのだろう。
だが一つ、彼は見落としている事がある。
最初から魔王の視点で行動するあまり、人の可能性を信じていない。
ルルーシュが示した強さもまた、その可能性の中から生まれた物だ。
人が人のままで魔王を超えられる。ならば魔王とは、決して絶対の存在ではない。
「もう少しだけ信じてみろ。お前が愛する人間は、無知で愚かで、過ちを犯す生き物だ。
だが、過ちを糧に成長する事もできる。人はいずれ魔王など必要としなくなる。その可能性を、俺は信じる」
それだけ告げて、ルルーシュはゼロに背を向ける。
もはや魔王は敵ではない。それだけの力も、心も、もはやゼロには残っていない。
歩んでいく先はムーンセルの中枢、フォトニック深淵領域。
ガウェインに目を遣る。騎士が頷く。
「我が王、ルルーシュ。あなたの道行きに太陽の輝きが共にあらん事を」
「我が騎士、ガウェイン。忠道、大儀であった」
お互いに一言ずつ告げて、すれ違う。これ以上は必要無い。
ガウェインとの間に確かな絆を感じる。それだけで十分だ。
ルルーシュはガウェインに背を向けて、一人、月の中枢へと踏み入っていく。
「……これが、聖杯か」
そこはまるで、海の中にいるような――情報の大海の只中に、ルルーシュは浮かんでいる。
手を伸ばさずとも情報に触れられる。
太陽系最古の遺物。膨大な過去を収めた、万能の願望機。
ムーンセルは今こそようやく、ルルーシュを最後のマスターだと判定してその鍵を開いていた。
今なら、何でも出来る。
不死の命、別世界への転移、過去の改変、望む事が望むだけ叶えられる。
「以前の俺なら、飛びついていたかもしれんな……」
苦笑し、ルルーシュは願いをムーンセルへと入力する。
魔王ゼロのいた世界を検索。
その世界に存在するエデンバイタルの観測、そして介入。
システムの改竄。
「エデンバイタルはムーンセルと同質の存在。
故に、エデンバイタルを根底から改竄するのならば、ムーンセルもまた全てを擲たねばならない。
俺もまた、月と共に消えるか……」
ムーンセル・オートマトンを全力で稼働させるのならば、中枢でそれを指揮するウィザードは欠かせない。
エデンバイタルのシステムを書き換え終えた時、ムーンセルもまた自壊するように設定する。
聖杯が誰の手にも渡らないように。もう二度とこんな戦いが起きる事のないように。
そしてムーンセルが自壊すれば、ルルーシュは死の運命に回帰する。約束された死に帰っていくのだ。
「約束は、果たせない……か」
命令はすぐさま実行に移され、ムーンセルが唸りを上げる。
次々と現れては消える情報を捌きながら、ルルーシュは友を想う。
花村陽介は、鳴上悠の喪失に向き合うだろう。その痛みから逃げず、立ち向かい、そして乗り越えるはずだ。
泉こなたは、日常へと戻るのだろう。だが、前よりもほんの少し、強くなったかもしれない。
彼らの変化を見届ける事ができないのが、未練だ。
「贅沢になったものだな、俺も。全てを捨てると一度は決意したはずなのに」
いつまでも悔やんでいる訳にも行かない。
と、ムーンセルが自壊を始めたのがわかる。
首尾よくエデンバイタルを改竄しているようだ。これでもう、魔王という存在は生まれない。
その果てにエデンバイタルの意識エネルギーが停滞し、やがて滅びを迎えるならば、それはもう仕方がない。
人がそのように選択した結果なのだ。自ら選んだ先の滅びならば、それは魔王がいようといまいと不可避のものだ。
だが同時に、そうはならないとも確信している。
人という存在を論理で表現し切る事は出来ない。誰しも自らの内に混沌を抱え込んでいる。
ルルーシュが世界を変えたいと思ったように、自らの意志で行動する人間という者は必ず現れる。
魔王がおらずとも、混沌の種は尽きる事は無い。
「だって、こんなにも――宇宙には星々が、命が溢れているのだからな」
ルルーシュの目に映るのは、満天の星空だ。
煌めく光の一つ一つが命ならば、可能性はその生命の数だけ広がっている。
「信じろ、魔王……俺やお前がいなくとも、可能性は無限の分岐を増やしていく。
その中から必ず、明日への希望は生まれるはずだ」
目を閉じる。
星々に抱かれて、ルルーシュの旅は終わる。
願わくば、次に目覚める時があれば、優しい世界であってほしい――
伸ばした手は誰かに強く掴まれる。
そして、ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアという存在は、月と共に消滅した。
◇ ◆ ◇
目覚めは、割と早く訪れた。
小鳥の囀りが耳をくすぐる。朝日が瞼を貫いて眼球を灼く。草の香りが鼻につく。頬を撫でる風が心地いい。
ルルーシュは、ゆっくりと目を開けた。
「ここは……?」
そこは、見知らぬ草原だった。
熾天の座でも、冬木市でも、ましてゼロレクイエム最後の地でもない。
完全に見た記憶の無い、緑の平野だった。
「何だ? 何故、俺は生きて……?」
あの聖杯戦争は夢だったとでも言うのか。
そんなはずはないと思うものの、傷や令呪は一つも残っておらず、夢ではないと証明する物がない。
慌てて立ち上がる。と、懐からこぼれ落ちた物があった。
「これは、花村の……」
契約者の鍵だ。それを見た瞬間、記憶が圧倒的な現実感を伴って脳裏に再現される。
ルルーシュは確かに魔王ゼロを倒し、今度こそムーンセルにアクセスして、自壊を命じた。
エデンバイタルは改変され、聖杯は解体されたはずなのだ。
その結果ルルーシュは死ぬはずだった。本来あるべき死の運命に戻るはずだった。
だが今、生きてこの草原にいる。
「やっと起きたか、馬鹿者め。女を待たせるとはマナーを知らないボウヤだな」
聞き覚えのある声がする。
振り向けばやはり、そこにいたのは全ての始まりである緑の髪の魔女――C.C.だった。
「C.C.……? 何故お前がここにいる。いや、そもそも何故俺は生きている?
ゼロレクイエムはどうなった? スザクは? ナナリーは?」
「うるさい。お喋りな男は嫌いだ」
矢継ぎ早に質問するルルーシュを無視して、C.C.は持っていた包みを放り渡す。
混乱しながら包みを開くと、そこにはいかにも凡庸な普段着が一式入っていた。
「さっさと着替えろ。いくらE.U.の田舎町とはいえ、その皇帝衣装は目立ちすぎる」
「は? 待て、どういう事なんだ。説明しろ、C.C.! なんで俺は生きているんだ!?」
「知らんよ。私はただ、呼ばれただけだ。今日この場に来るようにとな」
「呼ばれた……?」
これ以上聞いてもC.C.に答える気はなさそうだったので、ルルーシュはおとなしく服を着替える。
着ていた皇帝の衣服は血に塗れている。と言っても聖杯戦争の負傷ではなく、ゼロレクイエムにてスザクに刺し貫かれた時の出血だろう。
皇帝服は包みにまとめる。いくつか処分の方法を考えて、それどころではないと思い直した。
「着替えたな、では行くぞ」
「待てC.C.、いい加減に説明をしろ!」
「あれに乗る。お前は前だ」
相変わらずのマイペースぶりで、C.C.はさっさと進んでいく。
その先には一台の馬車があった。荷台に藁を満載した、古き良き原始的な移動装置だ。
C.C.は荷台に乗って寝転がり、ルルーシュに御者席へ座れと手を振って指示してきた。
「私はもう馬の面倒を見る気はない。お前が運転しろ」
「C.C.! いい加減にしろ!」
「うるさい奴だ。頼まれたんだよ、お前の事をよろしく頼むとな」
「頼まれた? 一体誰にだ!」
「お前にだよ、ルルーシュ」
「……は?」
瞬間、曖昧だった記憶の霧が晴れる。
魔王ゼロを打ち倒し、聖杯に接続した後だ
全てを終えて、目を閉じたルルーシュの手を掴む者がいた。
ガウェインではないとしたら、それは魔王ゼロしか有り得ない。
「あいつ、まさか……!」
ガウェインが止めなかったのは何故か。
それは、魔王ゼロにルルーシュを害する気がなかったからではないか。
あの時、ゼロは魔王ゼロではなく、ルルーシュだった。
魔王という存在が消え、エデンバイタルとの接続を断たれたゼロならば、自らをルルーシュ・ヴィ・ブリタニアであるとムーンセルに誤認させる事も可能なはずだ。
そしてルルーシュと入れ替わり、ルルーシュをムーンセルの外へと弾き出した。ご丁寧に死ぬはずの運命までも書き換えて。
ゼロ自身は崩壊に巻き込まれると知りながらも、ルルーシュの代わりに聖杯を自壊させた。
そう考えれば辻褄は合う。
「Cの世界を通じてお前に連絡をとったという事なのか」
「私だって驚いたさ。いきなりお前の声で呼ばれて、更にここに来てみれば死んだはずのお前が呑気に寝ているんだからな。
ああ、そういえば伝言を預かっている。“魔王でも魔人でもなく、人として生きて死ね”、だそうだ」
「人として……?」
「まあ、いいんじゃないか。どうせお前が生きてる事を知ってる人間は私以外は誰もいないんだ。
適当に名前を変えて、あちこちを放浪する生活なら、大した騒ぎになる事もないだろう。ナナリーやスザクに会う訳にはいかないだろうがな」
「そんな適当な……」
だが、思い直す。
魔王ゼロがルルーシュを救って代わりに滅びたのは、もう一度人の可能性を信じてみる気になったからではないのだろうか。
魔王として生きざるを得なかった自分の代わりに、人の生を全うしろと……そういうメッセージ。
ならば、ルルーシュが自身の生死に拘るのは、その願いを否定するという事になる。
スザクには、生きろと命じられた。
陽介とこなたとは、再会の約束をした。
魔王ゼロには、人として生きて死ねと託された。
ならば……ルルーシュが、一個の人間として選ぶべきは。
「……まったく。せっかく撃たれる覚悟を決めたというのに、また生きたくなってきたじゃないか……」
「悩むようだったら、理由をやる。私のために生きてみろ。
忘れているようだが、お前には責任があるんだぞ。私の面倒を見るという責任がな。
女を待たせたんだ、ちょっとやそっとの借りじゃないぞ」
「この魔女め……だが、確かにお前には借りがある。
借りっぱなしは癪だしな……まあ、いいさ。一人旅は退屈だからな。付き合ってやるよ」
「じゃあさっさと出発しろ。私は腹が減った。ピザが食べたい」
「やれやれ。おい、金はあるのか? 俺は一銭も持っていないぞ」
「心配するな。ジェレミアの財布を持ってきている」
「……そうか。いや、何も言うまい」
C.C.は相変わらずC.C.だった。その変わらない有り様に、どこか安心する自分がいる。
少なくとも一人、自分と共に歩む人がいる。それならば、もう少し生きてみるのも悪くないのかもしれない。
この、ルルーシュが創った世界で。ナナリーやスザクが生きるこの世界で、もう一度人として生きる。
それでも、いつか死を迎える時は来るだろう。その時――あの魔王に教えてやろう。
きっと、大丈夫だと。魔王などいなくとも、この宇宙は続いていく。
馬車はゆっくりと動き出す。
目的もあてもない、ゼロから始める気ままな旅。
人として生きると決めたのなら、このくらいの適当さがちょうどいいのだろう。
そう、始まりがゼロならば――これからいくらだって、積み重ねていけるのだから。
「ルルーシュ、退屈だ。何か話をしろ」
「そうだな。では、俺の……友人の話をしてやろう」
「ん? スザクの事か」
「いや……そうでもあるが、それだけじゃない。話せば長くなるな」
「いいさ、時間はたっぷりあるんだ。好きに話せ」
さて、どこから話したものか。
そうだ、と思いつく。C.C.ならば、神根島のような手付かずの遺跡の場所を知っているかもしれない。
思考エレベータを開き、別の世界へと扉を開く。
そうすればまた会えるかもしれない。再会を約束した、二人の友と。
決めた。まずは会いに行こう。この鍵も返さなければならないのだから。
嬉しそうなルルーシュの気配を察して、C.C.も微笑む。
「ギアスという王の力は、人を孤独にする。ふふ……少しだけ違っていたか? なあ、ルルーシュ」
問いかけてくる彼女に、笑みを返す。
見上げれば、空には輝く太陽がある。
あの騎士と同じ、暖かく柔らかな光。
この光が照らしてくれるのならば、行き先に迷う事はないだろう。
道はどこまでも続いていて、旅も続いていく。
そしてきっと、この旅路の果てに――――。
「――約束を、果たしに来たぞ――」
&color(blue){ 二次キャラ聖杯戦争 終幕}
そこは広大な空間だった。
壁や天井のない、どこまでも果てしなく続く白亜の領域。
純白の空と大地の狭間にただ一つ、宙に浮かぶ異物がある。
水晶の立方体に囲まれた単眼のオブジェクトだ。水晶はフォトニック純結晶によって構成された檻。
その内部に魔術師たちが追い求めてきたもの――月の中枢、聖杯がある。
西暦2032年。人類は月面で奇跡を発見した。
――ムーンセル・オートマトン。
太陽系最古の遺物。あるいは神の自動書記装置。あるいは七天の聖杯(セブンスヘブン・アートグラフ)。
その機能は万能、宇宙の物理法則すらも書き換える。故に、万能の願望機――『聖杯』と呼ばれる。
聖杯戦争とは、このムーンセルの所有権を巡って行われる闘争である。
己の魂を霊子化し、ムーンセルにアクセスしたウィザード達は、ムーンセルより己の剣たるサーヴァントを与えられる。
サーヴァントとは、人類史に燦然と名を残す英雄英傑を再現した存在。ウィザードはこのサーヴァントの主――マスターとなって、戦場を駆ける。
命と願いを天秤に掛け、万能の願望機を手にするために。
「そうだ、あれこそがムーンセル・オートマトンの中枢……すなわち『聖杯』だ」
囁いたのは、黒よりも暗い闇を身に纏う仮面の魔王ゼロ。
永遠を生きる者。偏在する可能性の収束点。混沌を体現する存在。月の癌――全ての争いの始まり。
その魔王と対峙するのは、やはり王と騎士。
王の名はルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。かつては魔王と同じくゼロを名乗り、やがて古き世界を壊し、新たな世界を創った男。
騎士の名はガウェイン。アーサー王に率いられし円卓の騎士の一人にして、アーサー王の甥である。太陽の騎士と称される、誉れ高き忠節の騎士。
「魔王、ゼロだと……!?」
ルルーシュは愕然と立ち尽くす。
トワイス・H・ピースマンより、ムーンセルに巣食う元凶の存在は知らされていた。そいつと戦う事を覚悟して花村陽介と泉こなたを帰還させ、ルルーシュはこの場に立っている。
そこに現れたのが、かつての自分と同じ名、同じ仮面を纏う存在である。
驚愕が通り過ぎた後、ルルーシュを満たしたのは燃え盛る怒りだった。
「……不愉快だな。ゼロの名は、ゼロの仮面は、誰とも知れぬ輩が勝手に使っていいものではない!」
奇跡を起こす男、ゼロ――それはルルーシュが生み出し、そしてゼロレクイエムにてルルーシュの命を捧げて世界に刻み付けた存在だ。
ゼロとは今や、単なるテロリストではなくなった。人々に溢れる全ての憎しみを精算し、新たな明日を迎える世界を支えていく安全装置となった。
故に、ゼロを名乗っていいのは盟友である枢木スザクだけだ。人並みの幸せを捨て、生涯をゼロとして世界のために捧げる――ルルーシュからこのギアスを受け取った、枢木スザクだけ。
眼前にいるゼロを名乗る男は、隆々たる体躯を誇っている。どう控え目に見てもゼロの名を託したスザクでは有り得ない。
実体の無い記号とはいえ、スザク以外の人物がゼロを名乗る事に、ルルーシュは激しく憤慨する。
「大方、俺を挑発するためにゼロを名乗ったのだろうが……なるほど、効果的だな。貴様と戦う理由がもう一つ増えた。
聖杯戦争を起こした元凶、そしてゼロの名を騙る痴れ者。許す訳にはいかないな。行くぞ、ガウェイン! 奴を倒し、聖杯を解体する!」
「ええ、ルルーシュ。参りましょう!」
英雄王ギルガメッシュとの戦いで消耗したルルーシュとガウェインに、万全の力は無い。
しかし後退は無い。ここは戦う場面だと、主従は言葉を交わさずとも理解している。
敵は一人、魔王ゼロを名乗る黒衣の男。
幾度もの戦いを経て高まったルルーシュの霊子ハッカーとしての感覚は、敵がサーヴァントを従えていない事を察知している。
ガウェインが斬りかかる。負傷しているとはいえさすがにセイバー、剣の英霊である。その踏み込みはまさに神速。
聖剣の切っ先は音よりも早く黒の仮面を断ち割る――事は無く。ゼロが掲げた掌に、聖剣は難なく受け止められていた。
「性急だな。私とお前には、まだ語るべき事がある……そうだろう?」
聖剣を受け止めながらも、ゼロの瞳はルルーシュしか映していない。
ガウェインの存在を、路傍の石ころのように無視している。意識する価値も無いとでも言うように。
対して、斬撃を防がれたガウェインもまた動けない。
聖剣を受け止めたゼロの掌――正確には、掌の僅か先に輝く光の印に触れた剣先が、どれほどの力を込めようとも微動だにしないのだ。
「これが私のワイアードギアス――“ザ・ゼロ”だ」
「ギアス……!?」
「そうだルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。私もギアスを持っている。絶対遵守のギアスを持つお前と同じくな。
そしてお前は先程、私をゼロの名を騙る痴れ者と言ったな……」
ゼロはガウェインの剣を拘束したまま、もう片方の手で仮面に触れる。
「しかし、違う……違うんだよ、ルルーシュ。私もまた、ゼロを名乗る資格を持つ者。何故なら――」
仮面の開閉機構が作動し、ゼロの素顔が晒される。
今度こそ、驚愕でルルーシュの呼吸が止まる。
「かつての私の名はルルーシュ・ヴィ・ブリタニア――もう一人のお前自身なのだから」
仮面の奥から現れたのは、ルルーシュと瓜二つどころではない、まさにルルーシュその人だった。
顔も、声も、眼差しも。全てが自分と完全に同一。
違いはただ一つ。ルルーシュは白の騎士を従え、ゼロ=ルルーシュは漆黒の魔王である事だ。
ゼロが拳を握る。光の印が消失し、ガウェインが身体の自由を取り戻す。瞬時に放たれたゼロの拳を、ガウェインが聖剣で受け、そして弾かれる。
魔王ゼロはサーヴァントではない。しかし決して人間でもない。セイバーたるガウェインを大きく吹き飛ばすほどの拳を放てる者が、人間であるはずがない。
「ガウェイン!?」
「――っ! ルルーシュ、下がってください! この男、只者ではない!」
接近戦の熟達者たるセイバーに匹敵する膂力は、サーヴァントと比しても遜色無い。
自分と同じ顔をした者がそれだけの力を誇る事実に、悪い夢でも見ているような気がする。
しかし――
「……魔王、ゼロ。違う世界の俺、と言う訳か。だが、この体験はもう済ませている」
動揺は一過性の物だった。ルルーシュは以前にも違う世界の自分と遭遇している。
遠坂邸の地下で攻め込んできたアサシンと対峙した時だ。アサシンの宝具によって引っ張り出されてきた別世界の自分を、ルルーシュは即座に射殺している。
ルルーシュにとってのルルーシュとは、今ここに在る己自身のみ。
親友であるスザクと決着を着けたように、この月の戦場では違う世界の自分だとて敵となる事に疑問は無い。
「そう言えば、そうだったな。お前はアサシン――ファニー・ヴァレンタインの宝具に遭遇していたか。」
そして、その体験こそがルルーシュに確信を与えている。
一つの世界に同じ存在は共存できない。ルルーシュが別世界の自分と遭遇した時、二人の身体は崩壊していった。
あの時はキャスターのお陰で命を拾えたが、キャスターがいないこの場ではルルーシュの消滅は必然であるはずだ。
だがルルーシュも、そして魔王ゼロも、身体に変調を来たす兆候は無い。
「お前は、俺ではない……! この俺と同じルルーシュ・ヴィ・ブリタニアという存在であるはずはない!」
「然り。故に我は魔王ゼロ。かつてルルーシュであり、今はエデンバイタルの魔王となった存在」
ゼロが再び仮面を纏う。
魔王ゼロ。ルルーシュがかつて名乗っていたゼロとは違う、おそらく正しい意味での魔王という力を持った存在だろう。
ガウェインが聖剣を構える。たとえ相手が主と同じ存在であったとしても、剣を向けるに躊躇いは無いという意志の証明。
ルルーシュもまた、友より託されし槍王イルバーンをゼロへと向ける。
「お前が違う世界の俺であろうと関係は無い。お前がこの聖杯戦争の源、多くの人を巻き込んだ元凶だというのなら、倒すのみだ」
「そして聖杯を砕くか。だが、理解しているか? その後に待つのはお前という存在の終焉だという事を」
出逢った時、ガウェインは言った――聖杯を壊した時、貴方は死ぬ事になる、と。
ルルーシュはゼロレクイエムにて、ゼロとなったスザクに討たれ、死んだはずだ。その時抱いた生存への未練をムーンセルが汲み取り、この場に招かれた。
だとするなら、聖杯を破壊すれば、ルルーシュは崩壊するムーンセルと共に消えるか、あるいは召喚される直前の状態に戻り――どちらにせよ、死ぬ事になる。
一足先に自らの世界へ帰った花村やこなたのように生きて元の世界に帰ろうとするならば、聖杯を破壊するのではなく、正しい方法で運用しなければならない。
万能の願望機たる聖杯の力を以ってすれば、死にゆくルルーシュの生体情報を改竄し新たな生命を得る事もできるだろう。
それだけではなく、最愛の妹であるナナリーが望んだ優しい世界を、永久不変に実現する事も可能だ。
「貴様が俺だというのなら、わかるはずだ。“撃っていいのは”――」
「――“撃たれる覚悟がある奴だけだ”。なるほど、お前は世界を託すに足る者を見つけたか」
しかし、ルルーシュは拒絶する。二度目の生も、願望機によって成し遂げられる平和も。
ルルーシュの世界はゼロレクイエムによって破壊され、そして再生する。
混乱はあるだろう。憎しみの収束点である悪逆皇帝が討たれたとしても、それで全てが丸く収まる訳ではない。だが希望もある。戦いではなく対話のテーブルにて平和を掴もうとする人々がいる。
優しい世界の実現を目指すナナリー、それを補佐するゼロ=スザク、そしてゼロに従うとギアスを掛けたシュナイゼル・エル・ブリタニア。かつての黒の騎士団のメンバー。
平和は人の手によって創られるべき物だ。聖杯などという、人の領分を超えた例外で達成して良いものではない。
「お前はまだ聖杯に到達してはいない。聖杯戦争が終結すれば、ムーンセルはただ一人生き残った最後のマスターを迎え入れる。
だが、ムーンセルは未だお前を勝利者とは認めていない。私が阻んでいるからな。
私はお前に用がある。聖杯戦争を勝ち残った最後のマスターであるルルーシュ・ヴィ・ブリタニア、お前にな。
お前も、私と戦わなくてはならない。私を倒さねば、誰であろうと聖杯にアクセスする事はできないのだからな」
「ふん、元よりそのつもりだ。だが、倒す前に聞いておく……貴様の目的は何だ。何故、この戦いを起こした?
本来の聖杯戦争とは、七人のマスターと七騎のサーヴァントの戦いらしいな。だがこの戦いは俺を含めて二十五人のマスターと、二十五騎のサーヴァントがいた。
何故、聖杯戦争を改変する必要があった?」
ルルーシュにはそれが引っかかっていた。
衛宮士郎から聞いた本来の聖杯戦争のフォーマットは、ルルーシュが言った通り七人プラス七騎のバトルロイヤルだ。
しかしこの戦いの参加者の数はおよそ四倍弱。ここまで規模を広げる必要とは、一体何なのか。
「15848回目だ」
「……何?」
「この聖杯戦争は、15848回目だ。これまでに15847回、失敗した。
本来の聖杯戦争を幾度繰り返そうとも、私の願いを託すに足るウィザードは現れなかった。故に私は聖杯戦争を改竄した。
数十のマスターとサーヴァントが入り乱れるこの戦いは混沌に溢れ、ムーンセルとて結末を予測する事は不可能だった。そして、お前が勝ち残った」
「待て……15847回も聖杯戦争を繰り返したのなら、最後に勝ち残った奴はいくらだっていたはずだ。そいつらはどうした?」
「言ったはずだ、失敗したと。期待外れだったマスターは全て処理してきた。彼らのデータは解体され、次回の聖杯戦争を行う資源として活用された」
ルルーシュは絶句する。15847回……通常の聖杯戦争だったとしても七人いるのだ。
単純に計算してもおよそ十一万人の犠牲者が出ている事になる。
「全ては、より強い魂を選定するためだ。この戦いは私にとっても賭けだった。
今回失敗すれば、力を使い果たした私はおそらく異物として認識され、ムーンセルのある世界から排除されていただろう。
だが、間に合った。お前が勝ち残り、私の前に現れた。これで私の望みは成就する」
「望みだと? それだけの犠牲を出して、何を成そうと言うんだ!」
「私の後を継ぐ、新たな魔王の誕生だ」
ゼロは、変わらずルルーシュしか見ていない。
仮面に阻まれその瞳を窺い知る事は出来ないが、それでもゼロはルルーシュに何らかの価値を見出している事はわかった。
「立ち塞がる敵を打ち倒し、あるいは手を取り合い、お前はこの熾天の座へと到達した。
かつて聖杯戦争を制した者、衛宮士郎とアルトリア・ペンドラゴン。欠落を埋めるために絆を捨てた者、鳴上悠とクー・フーリン。
自らを嘘で塗り固めた者、天海陸とイスラ・レヴィノス。知略を尽くし立ち回った者、ジョン・バックスとファニー・ヴァレンタイン。
そして盟友である枢木スザクとランスロット……お前が出逢い、戦ってきた者達は皆、強い意志を示しただろう?
彼らの願いに貴賎は無い。故に彼らは強く、また尊い。そして、そんな願いを持つ者が淘汰しあう事により、勝者の魂はより輝きを増す」
ゼロの指がルルーシュを指し示す。
今ゼロが名を挙げた者、名を挙げられなかった者、全ての屍を踏み越えて今ここに立っているルルーシュを。
「闘争こそが人の進化を促す。魔王の座を継げる程の強い魂を、私は求めていた。
そしてルルーシュ・ヴィ・ブリタニア、お前の魂は今、かつて無い程に強く鍛え上げられている。
数十の魂を生贄に、お前は魔王の器としてこれ以上ないほどに成長したのだ」
「俺が、魔王の器だと? では、魔王とは一体何だ! 何故こんな方法で選ばれなければならない!?」
「魔王とは、エデンバイタルの使者。言わばこの宇宙の監視者だ」
ゼロは語る。エデンバイタルとは何か……そしてエデンバイタルから遣わされた魔王という存在の意義を。
「エデンバイタルは宇宙誕生の遥か以前から万物を支配する法則にしてエネルギーだ。
神……と言っても差し支えはない。人は皆、エデンバイタルの集合意識より生まれ出て、肉体を得て個として成立する。
お前には、Cの世界やアーカーシャの剣と言えば理解が早いのではないか?」
「Cの世界、アーカーシャの剣……C.C.やシャルルのいたあの世界の事か!」
「それらも、そしてこのムーンセルも、本質的にはエデンバイタルと同義だ。人類の記憶と意識の集積体。そこには過去しか無い。
Cの世界そのものにギアスを掛けたお前には、語るまでもないな」
魔王ゼロは、ルルーシュの行ってきた行動全てを把握しているのだろう。
ルルーシュがシャルル・ジ・ブリタニアの思想を否定し、人類の無意識に、人の歩みを止めるなというギアスをかけた事も。
「エデンバイタルとは、言ってみればお前がギアスを掛けなかったCの世界のようなものだ。
過去しか持たない停滞した意識エネルギーは、やがて均一化して疲弊し、死滅を迎える。
故にエデンバイタルは現世に混沌を生み落とし、人の争いを活性化させ、新たな過去……つまりは明日を作り出す」
「では、魔王とは……!」
「そう、エデンバイタルの意志を代行する者。可能性宇宙の滅びを防ぎ、世界の明日を存続させる者。
すなわち我、魔王ゼロなり」
魔王とは、滅ぼされるべき絶対悪などではない。
宇宙の熱的死から可能性を守護する者。もし滅ぼせば、遠からず宇宙そのものが滅びを迎える事になる。
正しく宇宙の監視者、あるいは安全装置と呼べる者。
「だが……だがそれならば、何故貴様は次の魔王など求める。それだけの力を持っているのなら、代わりを求める必要など無いはずだ」
「私は永く魔王で在り続けた。故に私の可能性は尽きた……停滞した。
古きは滅び、新しきを迎えねばならない。そう、お前が成し遂げたゼロレクイエムのようにな」
「何っ……!?」
「理解できない訳ではないだろう、ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。同じ存在である事など関係なく、私とお前は非常に近しい存在だ。
私が背負う魔王と言う名と、お前が起こしたゼロレクイエムという行動。
どちらも世界の明日を求めるという点では一致している。その過程で膨大な犠牲を払うというところもな」
ゼロの言葉に、ルルーシュは咄嗟に反論する事ができなかった。
確かに、ルルーシュの起こしたゼロレクイエムは世界に新たな明日を齎しただろう。
しかし、忘れてはならない。ゼロレクイエム達成の陰には、凄まじい数の犠牲が出ている事を。
権益を手放す事に同意しなかったブリタニアの貴族達、ルルーシュに反逆する黒の騎士団やシュナイゼル麾下の軍勢、その他にも武力を背景にした徹底的な弾圧を行った。
全ては世界の憎しみをルルーシュに集めるための、必要な犠牲だった――が、それはあくまでルルーシュの理屈であり、決して正しい訳でも肯定されるべき物でもない。
「私が、数ある平行世界の中でもお前を選んだのは……お前だけが、私と同じ結論に達していたからだ。
地球と宇宙という規模の差こそあれ、やがて来たる滅びを回避し、人々に明日を迎えさせるための人柱となる。
私にお前が理解できるように、お前も私を理解できるはずだ」
「俺と、お前が同じ……か。確かにそうかもしれんな。なるほど、お前の言う魔王の存在価値とやらもわからんではない。
だが、それなら最初から俺を選べば良かったはずだ。こんな馬鹿げた戦いを起こさずとも、俺だけを連れてくる事はできたはずだ!」
「そんな事をしても意味が無い。言っただろう、強き魂が必要なのだと。
別に、お前が勝ち残ると予測してお前を選んだ訳ではない。事実、お前は幾度も命を落としかけた。
私としては別にそれでも構わなかった。その場合、別の誰かがこうして私の前に立っていただろうからな。
必要なのはルルーシュ・ヴィ・ブリタニアではない。最後まで勝ち残ったマスターが偶然お前だった、それだけの話だ」
魔王ゼロにとって必要なのは、最後まで生き残った者=最も強く成長した者。
今回はそれがたまたま別世界の己であるルルーシュだった、というだけだ。
「そして、私の目論見通り、お前は魔王の器たる資格を備えた。あの英雄王さえも打ち破ったのだから不足は無い。
無論、お前と共に英雄王と戦った花村陽介と泉こなたにもまた、魔王の器たる資格はあった。
お前が彼らをムーンセルから排除した事で、魔王を継げるのはお前だけとなったが。
結果論ではあるが、彼らとの別れもまた、お前を成長させている。予想外ではあったが、歓迎すべきイレギュラーだ」
「全て……お前の掌の上という事か。では、俺がおとなしく魔王とやらを継ぐ気がないという事も、当然理解しているな?」
「ああ。私としても、お前のサーヴァントがいては魔王の継承が行えない。故にそのサーヴァントを消去する必要がある」
ルルーシュとゼロが会話している間、一切口を挟む事なく控えていたガウェインが前に出た。
我が王が敵と対話するのなら、騎士は側で王を護るのが勤め。残り少ない魔力を活性化させ、僅かなりとはいえ消耗は癒えている。
ゼロが黒きマントをはためかせ、ルルーシュへと手招きをする。
「前置きが長くなったな。さあ、来るがいい……ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。
鍛え上げた力をここに示せ。古き魔王たる我を滅ぼし、新たな魔王となりて宇宙に混沌を導くために」
「俺は魔王などになる気は無い。そして、お前を生かしておく気も無い……行け、ガウェイン!」
「ええ、ルルーシュ。今こそ決着を着ける時です!」
ルルーシュの指示を狼煙に、ガウェインが駆ける。
魔王ゼロの力は未知数――警戒すべきはガウェインの斬撃すらも無効化した掌の光印だ。
初太刀は真っ向からの斬り下ろしと見せかけ、剣先は複雑な軌跡を辿りゼロの右肘を狙う。
瞬間、ゼロのマントが沸き立ち、鋭い刃となって噴出した。影の刃は聖剣を下から叩き、軌道を跳ね上げる。
その隙を逃さず、ゼロの片足が唸りを上げてガウェインの頭部へと襲いかかった。
「……っ!」
ガウェインは体勢を低くし、避ける。頭上を行き過ぎる蹴りに込められた威力を察し、ガウェインの眼光が鋭く引き絞られた。
魔王ゼロが武器を持っていないのは、その必要がないからだと悟る。四肢を用いた肉弾戦の一つ一つが、聖剣の一撃に匹敵しかねない。
ゼロの手足を包む燐光こそがその力の源、エデンバイタルのエネルギー。ガウェインはこれを、かつての主である騎士王の業、魔力放出と同質の物であると推測した。
今対峙しているのはAランクのサーヴァント以上の力を持つ存在であると、改めて認識する。
だが、それだけだ。
これが騎士王や湖の騎士であったなら、ガウェインの斬撃は剣を以って弾かれただろう。光の御子ならばその槍で、戦友である槍兵ならば異形化させたその腕で。
ゼロの防御のやり方は、多彩な特殊能力を振るったディケイドやオーズといったライダーに近い。メインで使う武器ではなく、オプションとして備える異能で敵の選択肢を潰す。
どちらが上という訳ではないが、確実なのは一つ。魔王ゼロの接近戦の技量は、ガウェインがこれまで剣を交えた者達には及ばないという事だ。
魔王ゼロがどれだけの異能を誇ろうと、こと接近戦という土俵で勝負する限りはやがてガウェインの速度が勝る。
「コードキャスト……ハドロン砲!」
そしてルルーシュも援護が入る。かつてランスロットと戦った時にも使った、セイバーの対魔力を利用した戦術だ。
ルルーシュから放たれた赤い雷光はゼロとガウェインに等しく襲いかかる。が、ガウェインは対魔力の効果で何もせずともその雷光を打ち消してしまう。
しかしゼロはそうもいかない。魔力放出と同質のスキルを持ってはいても、対魔力までは無かったようだ。
ゼロが交差させた両手にあの光が灯る。ガウェインの斬撃を完全に停止させた絶対防御。ルルーシュのコードキャストはあっさりと吹き散らされる。
その隙にガウェインは、ゼロの軸足を狙って剣を奔らせる。両腕が塞がっているゼロは、再びマントを硬質化させ、ガウェインの剣を受け止めるようとした。
このマントは掌の光と違ってガウェインの動きを妨げる効果は無い。ただ硬いだけだ。そして、ただ硬いだけの物質などセイバーの剣の前では障害になるはずがない。
“転輪する勝利の剣”――その柄に収められた擬似太陽が駆動し、聖剣の刀身を真紅の炎でコーティングする。
炎刃は易々とゼロのマントを灼き尽くし、押し留める物の無くなった聖剣を振り抜かせる。
「――ガウェイン」
その時、王であるルルーシュと同じ声で、魔王ゼロがガウェインの名を呼んだ。
無論、その程度でガウェインが動揺するはずは無い。剣先は迷いなく突き進む。
あわやゼロの片足を斬り飛ばさんと迫ったガウェインの聖剣は――ゼロの影より突き上がってきた鋭利な刃に受け止められた。
聖剣を通じてガウェインの手に伝わったのは、金属的な衝撃。
「これは……っ」
瞬間、動きを止めた隙を逃さなかったゼロの拳がガウェインに打ち込まれた。
受け止めた純白の鎧に亀裂が入るほどのすさまじい威力。
叩き込まれた慣性に逆らわず、ガウェインはルルーシュの元へと後退した。
「さすがはAランクのサーヴァント。全力は発揮できないはずだが、接近戦では私を上回るか。
これでは些か手間取るな。では私も呼ぶとしようか――“私のガウェインを”」
「まさか……!」
「来い、ガウェイン!」
魔王ゼロが、ガウェインの名を呼ぶ。
その影から伸びていた刃が上昇していく。二メートルほどのゼロの影から、巨大な黒い機体が飛び出してきているのだ。
量子シフトにより召喚される、あり得るはずのない異形。その名を、ルルーシュは知っている。
「ナイトメアフレーム……ガウェイン!」
何故ならば、それはかつての己の愛機。全長六メートルを超える鋼鉄の騎馬。
黒く染め上げられたボディ、両肩に備えられた二対のハドロン砲、指先のスラッシュハーケン、全てがルルーシュの記憶にあるそれと一致する。
“黒き魔王の玉座”ガウェイン。魔王ゼロは、そのガウェインの頭部に傲然と立っている。
誰かが代わりにKMFのガウェインを操縦しているという訳ではない。魔王にとってはどこだろうと今立っている場所が操縦席と同義なのだ。
KMFガウェインは背部の飛翔滑走翼を展開し空へと舞い上がっていく。
「さて、こうすればセイバーに打つ手は限られるはずだが」
「甘く見られたものですね。たとえ空へ逃げようとも、その頭上には常に太陽の輝きがあるのです!」
ガウェインが握る聖剣、その柄の擬似太陽が再び駆動する。巻き起こる炎熱は聖剣の刃となり、その身を長く伸ばしていく。
地上の敵を薙ぎ払ったと言われる聖剣は、ガウェインの可視出来る範囲まで刀身を延長させられる。
飛翔していくKMFに追いつき追い抜くほどの速度で、ガウェインは天をも貫かんばかりの刺突を放った。
先程はKMFガウェインの装甲に弾かれたが、今度はその硬度をも認識した上での一撃だ。
果たして聖剣の切っ先はKMFガウェインの胴体を貫通して反対側へ抜けていく。KMFの体勢が崩れる。
「ガウェインの装甲を抜くとはな。だがそちらの攻撃が届くという事は、逆もまた然りだ」
乗機が傷ついたところで魔王には何の痛痒もないのか、相も変わらずの静かな声が通る。
魔王ゼロがKMFの背に回り、装甲を貫いたガウェインの剣を掴む。その瞬間、魔王ゼロに斬りかかった時と同じく、剣にかかるすべての運動エネルギーが停止した。
剣を引き戻そうとしたガウェインの意志に背き、天に高く突き上げられた聖剣の刀身はぴくりとも動かない。
「チェックメイトだ」
KMFガウェインが両手の指をガウェインへと向ける。その指先一つ一つが鋭利な刃を射出するスラッシュハーケンだ。
指先とはいえそこはKMFの巨体である。ハーケン一つ一つが、人の頭部ほどの大きさがある。
十の連弾がそれぞれ違う軌跡でガウェインへと放たれる。
「ガウェイン、これを使え!」
聖剣を封じられたガウェインに、ルルーシュは槍王イルバーンを投げ渡す。
サーヴァントの宝具でなくとも、槍王もまた神話級の魔術礼装の一つ。そしてガウェインはセイバーである前に一人の騎士だ。当然、馬上で振るう武器たる槍の心得はある。
ガウェインが聖剣を手放し、槍王を掴み取る。ぶんと旋回した槍王が、次々に飛来するスラッシュハーケンを片っ端から打ち落とす。
凄まじい衝撃。あるいは、ゼロの拳打と同じかそれ以上の。間断なく畳み掛けてくる爪撃は、一撃を弾くたびに残り少ない体力をごっそりと持っていく。
そして見る間に魔王ゼロとKMFガウェインは空から落ちてくる――接近してくる。
スラッシュハーケンを放ちつつ、脚部のランドスピナーを展開したKMFガウェインが足を蹴り出した。ゼロの蹴りとは比べ物にならない質量がガウェインへと迫る。
「避けろ、ガウェイン!」
さすがにこれは受け止められない。ルルーシュの指示に逆らわず、ガウェインは跳躍してKMFガウェインがの蹴りを飛び越える。
が、ランドスピナーが別の生き物のように可動してガウェインの進路上に飛び出てきた。
避け切れず、ガウェインがまともにランドスピナーに衝突した。
「がぁっ……!」
人形のようにガウェインが弾かれる。地に落ち、二度三度と跳ね飛んで転がっていく。
ルルーシュは急いで駆け寄り、こなたから渡された礼装で回復のコードキャストを起動、ガウェインへと施す。
「ル、ルルーシュ……」
「喋るな、ガウェイン。すぐに治療する!」
見れば、ガウェインの魔力で編んだ鎧が粉々に砕かれていた。耐久力に優れたセイバーを一撃でここまで痛めつけるとは。
魔王が操るKMFは、ルルーシュがかつて搭乗していたそれとは似て非なる物のようだ。魔王と同じく、エデンバイタルのエネルギーで強化されているのか。
ともあれ、ルルーシュが連続で使用したコードキャストによりガウェインのダメージは少しずつ回復していく。
それを止める様子もなく、魔王ゼロとKMFは再び大地に降り立った。
「お前は自らのサーヴァントとしてそのガウェインを引き当てたが、私はそれに関与していない。
因果な物だな。この戦いを引き起こしたのは“私”、この戦いを勝ち残ったのは“お前”。
お前の剣は“ガウェイン”、私の騎馬もまた“ガウェイン”。ふふ、エデンバイタルの導きというには些か滑稽だな」
同じ“ガウェイン”の名を冠していても、その有り様は全く違う。
ルルーシュと共に歩むガウェインと、ゼロの意のままに動くガウェイン――意志なき鉄の人形に遅れを取る訳にはいかないと、ガウェインは己を叱咤して立ち上がる。
「ルルーシュ、治療はもう結構です。魔力を温存してください」
「待てガウェイン、お前の傷はまだ……」
ルルーシュの言葉を待たず、ガウェインはイルバーンを支えに立ち上がる。
しかし、負傷は癒やし切れていない。小刻みに震えるその姿の、何と弱々しい事か。
そんなガウェインの眼前に、彼自身の聖剣が突き立てられた。
ガウェインからの魔力が途絶え通常通りの長さに復帰したそれを、魔王ゼロが投げてよこしたのだ。
「拾え。この程度で終わるはずは無いだろう」
ゼロは勝ち誇っている訳でも、慢心している訳でもない。
魔王が両手を広げると、足元のKMFガウェインもまた同じ体勢を取る。
その動作が何を意味するか、ルルーシュは瞬時に理解した。
ゼロが放り投げた聖剣をガウェインに押し付け、自身は代わりにイルバーンを引っ掴む。
「先程、ハドロン砲と言ったな。あんな紛い物ではない、本物を見せてやろう……ハドロン砲、発射」
ゼロの言葉に連動し、KMFガウェインの両肩が展開――破壊エネルギーを凝縮していく。
ハドロン砲の威力は誰よりもルルーシュが知っている。故にルルーシュは一切の逡巡無く、コードキャストを起動させた。
「ガウェイン、力を貸せ!」
主が何を求めているか瞬時に理解したガウェインは、王の前で聖剣を天に掲げる。
ルルーシュが槍王イルバーンをガウェインのガラティーンに重ね合わせた。
「絶対守護領域……!」
「聖剣よ、我らを護り給え!」
ガウェインの力を上乗せして展開した防御のコードキャストは、“聖剣集う絢爛の城”を敵ではなく自分に向けて使用するような物だ。
聖剣を以ってせねば破壊できない炎熱の結界――それはルルーシュとガウェインを灼き尽くす事無く、ただ外界からの護りとして機能する。
今のガウェインの状態では、射角が広く発射後も弾道を操作できるハドロン砲は避けきれないと判断し、ルルーシュは受け止める事を選択した。
津波の如きKMFガウェインのハドロン砲が絶対守護領域に着弾する。
「ぐうううううっ……!」
「ルルーシュ、耐えてください!」
イルバーンを通じて凄まじい負荷がルルーシュの全身に駆け巡る。身体がバラバラに弾けてしまいそうだ。
だが、屈しはしない。ルルーシュを支えるガウェインが側にいる限り、王として騎士より先に倒れる訳にはいかない。
コードキャストの展開で、もともと少なかった魔力が消し飛んでいく。
「ほう。対軍宝具に匹敵する我がガウェインの攻撃を防ぐか。そうこなくてはな」
ゼロの呟きはとてもルルーシュには届かない。
濁流の如く放射される破壊エネルギーは、閃光と轟音を伴ってこの場にいる全員の視覚と聴覚を奪っている。
それは、逆に言えばルルーシュとガウェインの声もゼロには届かないという事でもある。
「が……ガウェイン! もう少しだけ、耐えろ!」
「ルルーシュ、何か策が……?」
「この攻撃が止んだ時……奴を倒すぞ!」
それだけでガウェインは主の意図を察する。
どの道、ここまで追い込まれては戦闘を継続させる事も難しい。ならば乾坤一擲の一撃に懸けるのみ。
もはや力を温存する必要は無い。宝具を駆動させるための魔力すらもつぎ込んで、防御結界の維持に尽力する。
流れた時間は一瞬か、はたまた永遠か、ルルーシュにはどちらとも判別がつかない。
確かなのはルルーシュとガウェイン、二人とも限界を迎える寸前まで魔力を放出し尽くし、KMFガウェインのハドロン砲を凌いだという事だ。
「この辺りが潮か。ルルーシュ、お前を殺してしまっては元も子もない。サーヴァントだけを排除させてもらう」
ゼロがKMFガウェインに命じ、ハドロン砲の放射をストップさせる。
ルルーシュが地に膝をつき、同時に喀血する。絞り出した魔力の量は生命の維持すらも危ういレベルだ。
しかしその眼光は依然鋭く、魔王ゼロを刺し貫く。
「……令呪を以って命じる! 我が騎士よ、全力で戦え!」
血を吐きながらもルルーシュが令呪を解き放つ。
魔力を枯渇させていたガウェインの全身に、新たなガソリンが注ぎ込まれる。
令呪一画を純粋な魔力として変換し、ガウェインに補給したのだ。
鉛のように重かった手足に力が漲る。砕けた鎧さえ復元される。
「重ねて令呪で命じる! ガウェイン――その聖剣を以って魔王を討ち果たせ!」
それはガウェインが誇る唯一の宝具、“転輪する勝利の剣”の開放許可。
ルルーシュとガウェイン、双方が望む行動を指示され、ガウェインの魔力が再度爆発的に増加する。
消費した魔力を全て補って余りあるほどの膨大な力を、ガウェインは全て聖剣へと送り込んでいく。
「令呪か――!」
魔王ゼロは再度、KMFガウェインにハドロン砲を撃たせるべく命令を飛ばす。
だが遅い。令呪というブーストを得て加速するガウェインと、魔王ゼロから魔力を組み上げて駆動するKMFガウェインとでは、力の収束率に厳然たる開きがある。
ガウェインが聖剣を振り上げる。
「この輝きの前に夜は退け、虚飾を払うは星の聖剣――エクスカリバー・ガラティーン!」
ついに真名を解き放たれた、ガウェインの最終宝具。
その輝きはまさに太陽。地上一切を灼き払う灼熱の断罪。
魔王の漆黒さえも呑み込む、三千世界を遍く照らす太陽の具現。
ただでさえ大軍を一撃のもとに消し去る聖剣は、更に二画の令呪の後押しを受けている。この一撃に限って言えば、あるいは騎士王の聖剣や英雄王の乖離剣にさえも匹敵するだろう。
地平線の彼方まで届く灼熱の奔流は、魔王ゼロのガウェインが遅れて放ったハドロン砲を容易く吹き散らしてその巨体を呑み込んだ。
炎熱の波は留まるところを知らず、魔王とKMFのみならずその向こう――フォトニック純結晶の檻に抱かれたムーンセルの中枢までも、その輝きで塗り潰していく。
背後にムーンセル中枢があるからこそ、ゼロは回避という選択が出来なかった。それを見越してガウェインは聖剣を解き放ったのだ。
先のハドロン砲よりも長い時間、聖剣は灼熱を吐き出し続ける。
やがてガウェインの魔力が尽き、炎が陽炎となって消えゆくその時には、魔王とその騎馬は熾天の座から姿を消していた。
「……っは、ぁ」
「よく……やった。ガウェイン」
ガウェインが荒い息を吐き、聖剣を下ろす。赤熱化した刀身は、触れるだけで地面を融かすほどに高温だ。
令呪の支援を受けた日輪の剣はかつてない力を発揮し、魔王ゼロごとKMFガウェインを一瞬で蒸発させた。いかに魔王といえど、あれだけの熱量の直撃を受け流す事などできなかったようだ。
ルルーシュの知る兵器に換算すれば、ハドロン砲や輻射波動など足元にも及ばない。それこそフレイヤ並み、あるいはそれ以上の威力だったのだから。
「魔王ゼロは……倒したのか?」
どこにも魔王の姿は無い。砕け散ったKMFの破片には隠れるほどの大きさもなく、ルルーシュの前に広がるのは変わらず浮かぶ立方体のオブジェのみ。
魔王と名乗った存在にしては呆気ないものだが、かと言ってどこかに潜んでいる様子は無く、礼装で周囲を探査しても魔王らしき痕跡はどこにも無い。
入念に周囲を調べ、その末にようやく魔王を倒したと結論を得て、ルルーシュは腰を下ろした。
これで、長きに渡る戦いは終わった。
聖杯戦争を歪めた魔王は討たれ、ルルーシュとガウェインが真の勝利者となった。
しかし――
「ムーンセルは……無傷、か」
ルルーシュはムーンセルをゼロごと消滅させるつもりで、ガウェインに聖剣を使わせた。
魔王とKMFの存在が聖剣の威力を減衰させたか、あるいはそもそもそんな方法では破壊できないのか、どちらにしろムーンセルは依然としてそこにある。
「ならば、直接アクセスするだけだ。今ならムーンセルは俺を迎え入れる……そうだな、ガウェイン?」
「ええ……もはや我らを阻む者はない。魔王がムーンセルを掌握していたというのなら、魔王を討った今、あなたこそが月に残った最後のウィザードになる。
往ってください、ルルーシュ。今こそあなたの願いを果たす時です」
そうルルーシュに告げるガウェインは、しかし自らは動こうとしない。
ルルーシュにもわかっている。ついに、別れの時が来たのだ。
槍を杖にして立ち上がり、ルルーシュはガウェインと向かい合う。
――お目覚めですか?
ガウェイン。この聖杯戦争を共に駆け抜けてきた、ルルーシュの剣。
死にゆくはずのルルーシュに二度目の生の始まりを告げた者。
出逢った時に交わした言葉は、ルルーシュの心中に一言一句刻まれている。
――貴方はルルーシュ・ヴィ・ブリタニア陛下。私は貴方に仕えるべく召喚された、ガウェインと言う者です。
かつての愛機と名を同じくする、誉れ高き円卓の騎士が一人。
太陽の騎士と異名を取る、Aランクのセイバー。
最初は、ガウェインという名と巡り逢う奇妙な縁に、おかしささえ感じたものだ。
――聖杯を壊した時、貴方は死ぬ事になる。それでも構わないのですね?
聖杯を破壊する。ルルーシュにとっては揺るぎなきその願いは、通常のサーヴァントにしてみれば言語道断の物だろう。
サーヴァントとてマスターと同じく願いがあり、その願いを叶えるために聖杯を欲し、聖杯に到るために戦う。
であれば、ルルーシュが聖杯を破壊すると宣言した瞬間、ガウェインに斬られても何の不思議も無かった。
ルルーシュを外れのマスターとして処理し、次のマスターに選ばれる確率に賭ける。願いを叶えたいのならばそれくらいはするだろう。
――我が剣は忠義の剣。貴方を我が主と定め、我が命を貴方に捧げると誓う!
だが、ガウェインはそんなルルーシュに剣を捧げると言った。
ルルーシュが聖杯を破壊すればがガウェインの願いは叶わない。
それでも構わないと、そもそも聖杯に懸ける願いなど無いと微笑み、ガウェインはルルーシュに仕えると決めたのだ。
――貴方の定めた道は確かに王の道。騎士としてこれほどの誉れはありません。
生前には成し得なかった、正しき騎士として最期まで王を支える事。
もし次があるのなら。二度目の生があるのなら、今度こそ、自らの全てを王に捧げよう。そう願っていた。
そして、ガウェインは忠義を尽くすに足る王に出逢った。
茨の道を歩む孤高の王。誰からも理解されず、しかし誰かの幸せを願いその身を投げ出せる者。
ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアがガウェインを召喚したのは、決して偶然などではない。
ルルーシュという存在そのものに、ガウェインの魂が惹かれたのだ。そんな王の騎士として、戦場を馳せる。これ以上に望む事などあるはずが無い。
ガウェインの願いは、ルルーシュに出逢った瞬間に叶えられていたのだ。
「ルルーシュ、あなたと過ごした時間は二日にも満たない短い物でした。だがこの二日間は私にとって、どんな武勲にも勝る価値があった。
あなたという王に仕え、幾人もの戦友を得て、叔父上ともう一度肩を並べて戦い、そして友と決着を着けられた」
生前のガウェインは、王を疑う事はしなかった。
騎士王の選ぶ道は全て正しく、間違いなどあるはずが無い、そう信じていた。故に騎士王を裏切ったランスロットを許せず、判断を誤り続けてしまった。
だが今ならわかる。ゆらぎがあってこそ人であり、人のまま王になるからこそ尊いのだと。
過ちを悔い、成長の糧として学び、次の機会には乗り越える。そして前に進み続ける。
ルルーシュという人間は、どんな苦難に見舞われようとも絶対に前進を止めない人物だ。完璧ではない故にミスを犯す。敵に怒り、仲間と共に笑い、悲しむ。
敗北の屈辱を舐めてなお、折れず曲がらず反逆し続ける。かつて剣を捧げた騎士王とは違うが、これもまた気高き王道。
そんなルルーシュに従う事は、ガウェイン自身にも影響を与えていた。
もし仮に、ガウェインのマスターがルルーシュではない別の誰かだったとしたら。きっとガウェインは、この場に立ってはいないだろう。
ルルーシュが戦いの中で成長したように、ガウェインもまた王の在り方に影響されていたのかもしれない。
「本当に、夢の様な時間でした。私などには過ぎた栄誉です。だから、あなたには感謝しています、ルルーシュ。
私のマスターが……私の王が、あなたで良かった」
今、万感の思いを込めて、ガウェインは王に別れを告げる。これより先は共に行く事は出来ない。
ルルーシュがムーンセルにアクセスし、最後のマスターとして自壊を命じれば、ルルーシュは再び死の運命に回帰する。
過去の英霊を電子的に再現された存在であるガウェインもまた、ムーンセルの崩壊と共に消滅するだろう。
死出の道行に供をする事は許されない。だからこそ、ここで別れる。敬愛する王の結末を見届ける。それこそが騎士としての最後の勤め。
「往かれよ、我が王よ。私はここであなたを見ています。
あなたが眠りにつくその時まで、私はあなたを見守りましょう」
聖剣を地に突き立てる。もはや武器は必要ない。ルルーシュが聖杯にアクセスし、全てを終わらせる時を待つ。
そんなガウェインを前にして、ルルーシュの内から出る言葉はただ一つ。
「……ガウェイン。お前の忠義、決して忘れん。さらばだ」
言葉少なに、別れだけ告げる。これ以上の言葉など必要は無い。
ガウェインの在り方を認め、彼が捧げた忠義を確かな記憶として死を迎える。それこそが、ルルーシュが彼の騎士に報いる最大の恩賞となる。
踵を返し、歩き出す。遅々とした歩みだが、一歩一歩着実に聖杯へと近づいていく。
背中にガウェインの視線を感じる。見届けると言ったガウェインの言葉に偽り無く、きっと最期まで見守っているのだろう。
そう思うだけで前に進む力になる。死ぬ時に一人ではない事が、こんなにも安心するものであると初めて知った。
思い出す。最初の死――あるべき本来の死を迎えた時、そこにはナナリーがいた。
あの時、ナナリーは泣いていた。結局、最後まで最愛の妹に真意を伝える事は出来ず、傷つけてばかりだった。
済まないと思う。申し訳ないと思う。それでも、ルルーシュは後悔はしていない。
間もなくルルーシュは死ぬ。だが幸い、ナナリーがそれを知る事は無い。ルルーシュが生きている事も、そして死ぬ事も。誰にも知られず、この月の中でひっそりと終わるのだ。
これで全てがゼロに戻る。ゼロレクイエムにてルルーシュの世界は再生に向かい、聖杯が解体される事で二度と聖杯戦争は起こらない。
無論、失った者達が戻る訳ではない。そのマイナスは決して消えない。
だが、それでも。
「花村と、泉。お前達が生きて、俺や衛宮、金田一や名無を覚えていてくれるなら……」
決して、無意味な死ではないはずだ。
心残りがあると言えば、再会の約束を果たせない事か。今頃、あの二人は自分の世界に戻れているだろうか。
戻れていたとして、そこはムーンセルの支配力が及ばない世界。
ペルソナとサーヴァントの複合体であるアレックスと、メダルに姿を変えた火野映司は、そう長くは存在を保てないだろう。
彼らにも、ルルーシュとガウェインのように逃れられない別れは来る。
「だが、お前達なら大丈夫だ……そう、信じている」
別れる事よりも、出逢えた事が嬉しい。陽介とこなたなら、そう思ってくれるはずだ。
戦いの中で背負った悲しみに負けず、日常を生きていく事ができる。そんな強さを持っていると、ルルーシュは信じられる。
やがてルルーシュは聖杯に到った。
手が届く距離。触れてみて、思念を送る。結晶体が振動し、膨大な情報がルルーシュに向けて開示される。
万能の願望機。事象を書き換え、あらゆる願いを叶える聖杯。その中枢――フォトニック深淵領域への道が開かれた。
最後に、もう一度振り返る。ガウェインは変わらず、ルルーシュを見守っている。
はず、だった。
ガウェインのを背後から貫く影――魔王ゼロ。
滅びたはずの魔王が、太陽の騎士を串刺しにして、ボロ屑のように放り捨てていた。
「なっ……!」
「言っていなかったな。私を滅ぼせる者はこの宇宙には存在しない――今はまだ、な」
その声は耳元で聞こえた。
振り返る寸前、首筋を掴まれる。ルルーシュの細首など容易く砕けるであろう豪腕は、紛れも無く魔王のそれだ。
ガウェインを倒し、一瞬にしてルルーシュの背後へと移動……否、転移してきた。
魔王は滅びてなどいなかった。この転移の力によって何処かへと姿を消し、ルルーシュがガウェインから離れて一人になる時を待っていたのだと、ようやくにして理解する。
「我がガウェインを破壊したのは見事だった。が、どれほどの宝具を誇ろうと私には通じない。
私のワイアードギアス――“ザ・ゼロ”の前では、森羅万象が無へと帰するのだから」
掴まれた首を無理やり捻り、ルルーシュは何とかゼロへと顔を向けていく。
ゼロは本当に無傷だった。四肢も黒のマントも、全て健在だ。ゼロのギアスを単なる運動の停止だと見誤ったのが、ルルーシュとガウェインの敗因。
だが予測するなど不可能だ。ゼロのギアスは、個にして神たるエデンバイタルと同等――人智を超えた力なのだから。
手にしていたイルバーンをゼロの仮面へと叩きつける。技巧も魔術も無い、反射的な行動だった。
穂先はゼロの仮面へ突き立ち、亀裂を走らせる。が、内部まで届いてはいない。
ゼロが仮面へ突き立ったイルバーンに軽く触れた瞬間、ルルーシュの手から忽然とイルバーンが消失する。
名無から託され、何度も危地を切り抜けてきた武器さえも奪われた。
「お前にはもう必要無い。武器も……そしてサーヴァントも」
イルバーンがなければコードキャストは発動させられない。
ゼロはルルーシュを無力化した事を確認すると、締め付けていた指を解く。床に放り出されたルルーシュは、視線を巡らせてガウェインを見る。
ガウェインは、死にかけていた。
ムーンセルによって除外されるデータが始まっている。だが、ルルーシュにその兆候は無い。
ここ熾天の座では通常の聖杯戦争のルールは適用されないのか、あるいは連動してルルーシュも死ぬ事を恐れたゼロが細工をしたのか。
いずれにしろ、心臓を破壊されてはいかにサーヴァントとて絶命は避けられない。
令呪を用いようとも、魔力の器たる肉体が徹底的に破壊されている以上、あの状態からの復帰は絶望的だ。
「ガウェイン……」
「…………ぁ」
伏したガウェインが、血と共に言葉を絞り出そうとする。
その瞳は悔いに満ちていた。最後の最後で仕損じた、誤った。王を守れず先に逝く事を、心から悔いている表情だった。
「そんな顔で、死ぬな……!」
そうではない。ガウェインとの別れは、こんな形であってはならない。
忠義の騎士が無念と共に果てる事など、絶対に許してはいけない。
その思いは、叫びとなって迸る。
「誇れ、ガウェイン! お前は俺の、この俺の道を斬り開いてきた騎士だ!
お前がいたから俺はここまで来れた! お前の忠義が、俺をここへ導いたんだ!
だからガウェイン……俺は、お前を誇る! 俺の騎士は、誰よりも強く、気高い……太陽のような男だ!」
ルルーシュの手に残された令呪が輝きを放つ。三画目の令呪を使えば自らも消滅する、そんなルールは頭の中から吹き飛んでいた。
ガウェインに落ち度は無いと。後悔の内に死ぬのではなく、自らを肯定して眠りにつけと。
この令呪は何の命令にもなっていない。ガウェインの傷を癒やす事も、魔王に一矢を報いる事も無い。
ただガウェインの心を救いたい、その一心で叫んでいた。
「――――――――」
思いは、届いたのか。
目を見開いたガウェインが何かを言おうとして口を開く。
その言葉が紡がれる寸前――ガウェインは消えた。
「ガウェ……イン」
「その悲しみは無意味だ。サーヴァントは死ねばムーンセルによって情報を回収され、いずれまた誰かのサーヴァントとして召喚される。
奴とて例外ではない。道具が壊れただけでそこまで感傷的になる必要は無いだろう」
無感動にゼロが言う。
ゼロはルルーシュが令呪を使うのを止めはしなかった。最後の令呪を使ったところで、ルルーシュは消滅しないと知っていたからだ。
この熾天の座は聖杯戦争のルールの外にある。ガウェインが消去されたのは、ゼロがそうなるようにムーンセルを操作したからに過ぎない。
ルルーシュから全てを奪い、魔王の役割を受け入れさせる。そのためだけにガウェインを殺し、消し去ったのだ。
「無意味だと……? 貴様はあいつを、ガウェインの死を……無意味だと言うのか!」
「すぐにお前もそう感じるようになる。お前も魔王となるのだから」
「ふざけるな! 俺は貴様のようにはならない!」
「お前の意志などどうでもいい。エデンバイタルは既にお前を選んでいる。
抗う事など出来ない……さあ、内なる扉を開け。私を滅ぼす力、魔王の資格たるお前のワイアードギアスを目覚めさせるのだ」
ルルーシュはゼロに引きずり起こされる。
ゼロが突き付けてきた掌に光が灯る。ザ・ゼロではない、エデンバイタルと呼ばれる意識エネルギーの光だ。
そのエネルギーを、ゼロはルルーシュへと染み込ませていく。
「ぐわあああっ!」
「やはり私と同じ器か。私の中のエデンバイタルがこうまで馴染み易いとは。これならば、あるいはザ・ゼロそのものを目覚めさせる事も不可能ではない」
「やめろ……! 俺の中に……入って、くるな!」
「受け入れろ。エデンバイタルと同化すれば、お前は私を滅ぼす力を得る。そしてお前は宇宙に混沌を撒く存在となる。かつての私と同じように」
「その結果……どうなる! お前が俺だというのなら、俺が辿る結末とて……お前と同じはずだ!」
「だろうな。だからその時は、お前がもう一度この聖杯戦争を引き起こすのだ。
このシステムが新たな魔王を生む事は、お前という実例を以って証明された。ならば後は繰り返すだけでいい」
「そんな事を……!」
認めるものか。だがその思いは言葉にならない。
余りにも膨大なエデンバイタルの情報量は、未だ魔王たりぬルルーシュの脳では処理しきれない。
故に魔王ゼロはルルーシュの意識を喪失させる。エデンバイタルが、ルルーシュの無意識領域で生体情報を書き換えた時が、魔王新生の瞬間だ。
ルルーシュには既にワイアードギアスの萌芽が芽吹いている。ルルーシュの瞳で激しく明滅するエデンバイタルの輝きがその証拠。
抗う事もできず、ルルーシュの意識は暗い闇へと落ちていく。
「ようやく……終わる。永遠に続くと思っていた俺の旅は、ここで終わる。お前には済まないとは思うがな」
意識を失ったルルーシュには、ゼロの言葉は届いていない。
だからこそ、今だけは魔王ゼロではなく、ただのルルーシュに戻る事が出来る。
仮面を外したゼロが、項垂れるルルーシュにそっと囁きかけた。
「もしかすると俺は……お前に、嫉妬していたのかもしれない。
俺と同じルルーシュという存在でありながら、お前は人として生き、世界を変えて、死んだ。魔王にならざるを得なかった俺には、お前の生き方は眩しい物だった。
だから、なのか……お前が勝ち残ったと知った時は、少し、期待したよ。お前なら、あるいは俺を、魔王という存在を否定し、違う未来を創り出せるのではないか、と」
ゼロレクイエム――ルルーシュが計画した世界再生の策は成った。
それは魔王の目から見ても瞠目に値する結果だ。ギアスを用いたとはいえ、ルルーシュはあくまで己の意志と力で世界を変えた。
無論スザクやその他の協力者の力も大きい。が、何より重要なのはルルーシュ個人の覚悟だ。
世界を壊し、世界を創る。ルルーシュの言葉に偽りは無く、古き世界は破壊され新たな世界が産声を上げた。
しばらく混乱は続くだろう。だがその痛みを乗り越える強さを、あの世界の人々は手に入れた。
「俺は、お前が変えたあの世界を尊いと思う。だからこそ、新たな魔王は必要なんだ。
混沌なくして宇宙は変化しない。俺が魔王であり続ければ、いずれお前の世界も停滞に呑み込まれ、死を迎える。
滅びを防ぐにはこうするしかない」
それが一時の延命処置であったとしても、宇宙が滅びを迎えるよりはマシだと、ゼロは思う。
「許しは請わない。いずれお前も俺と同じ選択をする時が来る。
その時、お前が新たな魔王を選び出すか、あるいはそれ以外の道を見出すのか――それを知る事ができないのは、少し残念だとも思うよ」
誰の記憶にも残らない言葉は、ここで終わる。
ゼロは再び仮面をかぶり、沈黙のままルルーシュの変化を見据えている。
やがてエデンバイタルは完全にルルーシュへ定着し、生体情報の書き換えを終えた。ルルーシュの意識が回復する。
瞼を開けたルルーシュのその瞳には、ザ・ゼロと同じ紋章が瞬いている。ワイアードギアスが発現したのだ。
それも、ザ・ゼロと同等かそれ以上の――
「これでいい。ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア、お前こそが新たな魔王ゼロ……いや、“魔王C.C.”だ。さあ、そのギアスで私を滅ぼし、無二の魔王となるがいい」
「ああ……そうだな、もう一人の俺よ。俺はお前を滅ぼす……」
発現したワイアードギアスの使い方は既に理解している。
ルルーシュがゼロの腕を取る。そしてもう片方の手を握り締める。
その掌には、陽介から託された契約者の鍵がある。
「だが! 俺は魔王にはならない!」
ルルーシュが怒号と共に繰り出した拳は、槍王イルバーンが突き立った一筋の亀裂へと叩き込まれる。
ゼロと同じくエデンバイタルの光を纏ったその一撃は、ゼロの仮面を粉々に砕き割った。
◇ ◆ ◇
全て失った。
騎士も、武器も、戦う意志も。全てを魔王に砕き散らされた。
後はもう、魔王のされるがままだ。エデンバイタルは着々とルルーシュの魂を改竄していく。
どこまでも底のない暗闇に落ちていく感覚。この感覚は知っている。これは、そう――
「負けたのか、俺は」
土の味――敗北の味だった。
ガウェインと出逢い、仲間と数多の戦いを潜り抜け、魔王と対峙した。そして敗北した。
士郎や名無、そして彼らのサーヴァント達という犠牲の上に辿り着いた決戦に、勝つ事が出来なかった。
ルルーシュの剣であるガウェインも、名無から託されたイルバーンも、ルルーシュの手を離れた。
もう打つ手が無い。
「奴の、魔王の役割を……受け入れるしか……ないか」
だが、それは悪なのだろうか。
ゼロの言う事を信じるなら、ゼロはゼロで宇宙の存続のために動いているのだ。
魔王がこの宇宙の維持に必要だというのなら、ルルーシュが魔王となるのが正しい選択ではないのだろうか。
そうすれば、ナナリーが生きる世界も、陽介やこなたが帰った世界も、護ることに繋がる。
「……なら、俺は……」
抗う事を止めて、受け入れる。
言葉にすれば簡単な事。
だが――
「俺は……こんなになっても、まだ……」
諦められない。
ゼロに屈服し、負けを認めて、魔王になる。
ただそれだけの事を、どうしても受け入れられない。
「どうする事もできないっていうのに……」
今やルルーシュに残されているのは、絶対遵守のギアスだけだ。
いや、もう一つあった。
意識する。陽介との別れの際、彼から譲り受けた物――契約者の鍵を。
「花、村……泉……」
遠く離れてしまった友の事を想う。
再会の約束は、魔王になればきっと叶うだろう。
だがあの二人に、魔王となった姿を見せる事は――運命に屈した様を見せる事は、絶対に嫌だ。
――だったらさ。立つしかねーよな?
その時、懐かしい声が聞こえた。ここにいるはずのない、再会を誓った友の声が。
契約者の鍵から声が、想いが伝わる。
――だから、俺も行くっつったのによ。一人で突っ込んで負けて、そんでウジウジ後悔してるなんて。カッコ悪いぜ、ルルーシュ。
――まあまあ、あんまりいじめないであげようよ。ルルーシュ君も頑張ったんだからさ。
鉛のように重い瞼をこじ開ける。星明かり一つ無い暗闇の中にあって、はっきりと見える。
花村陽介と泉こなたが、そこにいる――
――ほら、立てよルルーシュ。まだ……やれるだろ?
――もうちょっとだよ。一人じゃ立てないなら、ほら。私たちの手を取って。
こなたがルルーシュの手を握る。
伝わってくる暖かさは、決して幻などではない、本物の熱を感じさせる。
――言ったはずだぜ、今度会った時はぶん殴ってやるって。でもまあ、今のお前を殴るのはさすがにちょっとって思うからな。
陽介がにやりと笑う。
そしてこなたと同じく、ルルーシュの手を取った。
――だから、次だ。次会った時にお前を殴る。今は、手を貸してやるよ。
――素直じゃないなあ、もう。
――へへ。なあ、ルルーシュ……悠はもういねーけど、お前はまだ生きてる。だから、諦めんなよ。生きてるなら何度だってやり直せる。
――疲れたのなら、私達たちが肩を貸すよ。でもね、立ち上がるのはルルーシュくんの足なんだ。
――俺達にできるのは、お前を信じて手を差し伸べる事だけだ。ああ、俺と泉はお前を信じるぜ。なんたって俺達は。
――友達だからね!
「友達……ああ、そうか。お前達は、俺の……」
――周り、見てみろよ。俺達だけじゃないぜ。
――みんな、ルルーシュくんが立ち上がるって信じてるんだよ。
陽介に促され、辺りを見回す。
アレックス、火野映司、衛宮士郎、セイバー、名無鉄之介、リインフォース、そして枢木スザク。
みな、ルルーシュを見ている。
これだけの仲間と絆を紡ぎ、ルルーシュは歩いてきたのだ。
「……ああ、そうだな。俺はまだ……」
何もない、全てを失ったと思った。だがそうではない。
武器が無い。サーヴァントがいない。それが、一体どうしたというのか。
そんなものは――戦わない理由には、抗わない理由にはならない。
「俺は……!」
反逆する。
理不尽な運命、強大な敵、歪んだ世界――その全てに反逆する。
それこそがルルーシュ・ヴィ・ブリタニアという存在の起源。
「俺は誰にも従わない……相手が神や魔王であったとしても、絶対に!」
空っぽだった肉体に、もう一度立ち上がる力が湧いてくる。
押し付けられた役割などいらない。
常に自分の意志で生きる。それが、ルルーシュという人間が己に課したただひとつのルール。
陽介とこなたに手を引かれ、それでも最後は自分の足で、ルルーシュは立ち上がる。
――もう、大丈夫だよな?
「ああ……すまないな。最後まで面倒をかけた」
――最後じゃないよ。絶対もう一度会うって、約束したでしょ。
「ふ……そうだったな。ならばこれ以上負けている暇などない。
さっさと魔王を片付けて……お前達に会いに行くとしよう!」
――おう、待ってるぜ!
――私、ここではみんなのお世話になりっぱなしだったよね。だから、次はみんなで一緒に遊ぼう! 遊びなら私の右に出る人はいないよ!
「ああ、約束する。俺の方からお前達に会いに行く!」
――これで最後なんだ。持ってけよ、俺達の力!
――頑張って、ルルーシュ君! きっと勝てるよ!
繋いだ手だけが紡ぐもの。
陽介とこなた、二人からの贈り物。
確かな絆を握り締め、ルルーシュの意識は覚醒していく。
戦場へ――魔王が待つ、熾天の座へと帰還する。
◇ ◆ ◇
「何だと……!?」
ルルーシュの拳によって、魔王ゼロの仮面は砕かれ、生身のゼロの顔がむき出しになった。
当然、鍛えていないルルーシュの拳も同様に砕けている。
だがそんな事を意に介さず、ルルーシュはさらに距離を詰めていく。
「何故、魔王として覚醒していない!? エデンバイタルはお前を呑み込んだはずだ……!」
「ああ、その通りだ。確かに俺はエデンバイタルの海に沈んだ。
だがお前が言ったんだ、エデンバイタルは人の集合意識だと。そこにあるのは魔王の意志だけじゃない!
俺達が繋いだ絆もまた、個から解き放たれ集合意識へ還る。その絆が俺を俺のまま、ここへ導いた!」
ペルソナ使いが操るペルソナは、人の無意識領域に棲まうもの。
一度精神世界で陽介とリンクしたルルーシュとこなたには、無意識領域の繋がり――コミュニティとも呼ばれるものが存在している。
そして、エデンバイタルの流入によりルルーシュの知覚は瞬間的に無限大まで加速した。
違う世界に分かれてしまった陽介とこなたに、意識を接続できるほどに。
「あいつらが思い出させてくれた。誰が相手だろうと、俺は絶対に従わない。
この命ある限り反逆し続ける――それがこの俺、ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアだ!」
「……だが、それで何が変わる。魔王にならないままワイアードギアスに目覚めたとて、私に抗う事は出来まい」
視線を絡ませる。ルルーシュに発現したワイアードギアスがどのようなものであっても、ゼロのワイアードギアス“ザ・ゼロ”ならば無効化できる。
ギアスをギアスで封じられるのならば、競えるのは肉体の基礎性能のみ。多少エデンバイタルを扱えるようになっても、ルルーシュに勝ち目など無い事は自明の理だ。
「魔王を受け入れろ、ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。お前が選ぶべき道はそれだけだ」
「断る。俺は魔王にはならないし、お前から逃げるつもりも無い。
俺はルルーシュ・ヴィ・ブリタニアとして、かつてルルーシュ・ヴィ・ブリタニアであったお前を滅ぼす!」
「不可能だ、お前には」
「ああ、不可能だろう……俺だけではな。だからこそ、俺は一人ではないのだ!」
ルルーシュの瞳が、黄金の輝きを放つ。
“ザ・ゼロ”と同じ紋様を展開する、そのギアスこそが。
「これが俺のワイアードギアス――森羅万象に命じる力、“ザ・ギアス”!」
呪い――あるいは願い。ギアスそのものの名を冠した、ギアスの中のギアス。
ルルーシュが本来宿していた絶対遵守のギアスを発展させた、神にすら匹敵する力。
瞳から放たれた光の印は、幾重にも重なりゼロへと迫る。
ゼロは、“ザ・ゼロ”での迎撃を選ばなかった。未知のギアスに不用意に干渉するリスクを避けたのだ。
結果、“ザ・ギアス”の光はゼロの背後――ムーンセルの中枢、聖杯へと叩き込まれる。
瞬間、ゼロはルルーシュの狙いを悟る。
「ルルーシュ、貴様っ!」
「ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアが命じる! 聖杯よ――我が騎士をここに呼び戻せ!」
“ザ・ゼロ”がムーンセルをハッキングできるのならば、同等のギアスである“ザ・ギアス”もまた干渉が可能だと言う事だ。
そして今、ルルーシュの手には令呪がある。
花村陽介と泉こなたがムーンセルから脱出する際、二人から異物として剥がれ落ちた最後の令呪。夢の中で、二人から託された最後の希望。
今のルルーシュは、サーヴァントを統べるマスターたる資格を備えている。
果たして――ムーンセルは、ルルーシュの要請をマスターの正当な権利として受諾した。
ムーンセルがデータベースを閲覧し、ルルーシュと組み合わせるべきサーヴァントを検索する。中でも一際強く反応を示した者を与えるとムーンセルは決定した。
ルルーシュとゼロの間に、灼熱の尖塔が立ち昇る。纏うは白の鎧、振るうは日輪の聖剣。
ゼロが咄嗟に打ち込んだ拳は、輝く聖剣にしかと受け止められた。
「……ガウェイン!」
「ここに! 我が王よ、遅参致しました」
太陽の騎士は、王の元へと帰還した。
その姿は消去された時のまま、満身創痍である。
「俺を忘れてはいないだろうな?」
「無論です、ルルーシュ。あなたの命令――しかと聞き届けました。
月が太陽の輝きを隠す事など出来はしない。私は変わらず、あなたの騎士であり続けている」
だが、今のガウェインに負傷など何の障害にもならない。
自らを誇れ。王の最後の命令は、騎士の魂をこれ以上ないほどに燃え猛らせた。
敗戦を経てなお、王は膝を屈する事をよしとせず、騎士を呼んだのだ。これに奮起せずして何が騎士か。
ルルーシュは聖杯を背後に、再び魔王と対峙する。傍らにいる太陽の騎士の存在が、ルルーシュの力を押し上げてくれる。
「ムーンセルへのハッキングが仇となったか。サーヴァントの消去が間に合わないとはな」
「お前でも予測できない事があるか。魔王といえども万能ではないようだな」
「エデンバイタルに呑み込まれず、人のままで逆に支配したというか。
ならばルルーシュ、お前はもはや魔王の器などではない。お前はまさに――エデンバイタルの魔人だ」
ゼロの脳裏に古い名が思い浮かぶ。
エデンバイタルの魔人――その存在は、遥か遠き過去にもう一人いた。
そいつの名にあやかって、今のルルーシュを表すのならば。
「ルルーシュ・ザ・コードギアス……!」
今やルルーシュは、魔王ゼロに匹敵する力を得た。
“ザ・ゼロ”と同等のギアス、“ザ・ギアス”。そして再召喚されたガウェイン。
魔王ゼロのガウェインは破壊され、未だ再生していない。
だが、まだゼロに分がある。再召喚されたとてガウェインの負傷は癒えていない。未だ無傷のゼロなら、仕留める事は容易いはずだ。
「魔王ゼロ、もう一人の俺よ。決着を着けるぞ!」
「魔人ルルーシュ、もう一人の私! いいだろう……来い!」
三人が、同時に駆け出す。
誰よりも早く踏み込むのは、やはりガウェイン。
宝具の開放も何もない、全身の勢いを乗せた真っ直ぐな突きを放つ。
ゼロが両手に展開した“ザ・ゼロ”が、聖剣を三度、完全に停滞させる。
森羅万象を無に帰す力。ゼロはガウェイン本体をも無に帰そうと、聖剣を直に掴む。
「ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアが命じる! 止まるな、ガウェイン――進み続けろ!」
「うおおおおぉぉぉっっ!」
「こ、この力……!?」
そこにルルーシュの“ザ・ギアス”が飛ぶ。
森羅万象を無に帰す力は、森羅万象に命じる力によって相殺され、効果を失くす。
故にガウェインの剣は止まらない。切っ先が僅かに、“ザ・ゼロの”光印へと突き刺さる。
「“ザ・ゼロ”を超えるのか……!」
「さらに令呪を以って命じる! ガウェイン――貫け!」
「おおおおおおぉぉっ……!」
花村陽介の令呪が輝き、ガウェインを後押しする。
聖剣はさらに突き込まれ、“ザ・ゼロ”を突破し魔王ゼロの掌へと侵攻した。
「ぐっ……!」
「重ねて令呪を以って命じる! ガウェイン――俺に勝利を捧げてみせろ!」
「……イエス、ユア……マジェスティ!」
駄目押しに、泉こなたの令呪を解き放つ。
ワイアードギアスと令呪二画、合わせて三重のブーストがガウェインの剣に宿る。
擬似太陽が脈動し、聖剣は万物を灼き尽くす炎を纏う。
ガウェインは王に捧げる忠義の言葉を叫ぶ。そして全力以上の全力で、聖剣を突き抜いた。
「…………」
光が弾ける――静寂が戦場に染み渡る。
ルルーシュの眼前で、ガウェインの聖剣は、忠義の剣閃は――確かに魔王の中心を刺し貫いていた。
“ザ・ゼロ”を打ち破られ、肉体に重大な損傷を負い、魔王はついに崩れ、倒れる。
「……俺達の勝ちだ、魔王ゼロ」
「……そのようだ。私に与えられた時は……尽きた」
ゼロは地に伏し、ルルーシュはそれを見下ろしている。
今度は先程のようなブラフではない。
ルルーシュのワイアードギアスによって互角の条件に引きずり降ろされた魔王は、全ての虚飾を取り払われたも同然。
故に全力でルルーシュらに挑み、そして敗北したのだ。
こうなってはもはや、ルルーシュに魔王を継承させる事は不可能だろう。
ただ滅び、宇宙が熱的死を迎えていくのをエデンバイタルの彼岸から傍観するしか無い。
「いや、そうはならない」
しかし、ルルーシュは断言する。
そんな事は起こらない――起こさせない、と。
ナナリーの生きる世界、陽介やこなたの帰る世界を、失わせる訳にはいかない。
「何……?」
「エデンバイタルと繋がって知った。お前の宇宙が滅びたのは、お前があまりに長く魔王で居続けたせいなのだろう。
変化のないエデンバイタルの意識エネルギーは停滞し、死を迎える。なら、魔王という存在に収束した可能性を、解き放ってやればいい」
「どういう、意味だ」
「お前がやった事の逆をするだけだ。ムーンセルの事象改竄能力を用いて、エデンバイタルをハッキングする。
そして、魔王というシステムそのものを消去する。そうすれば、世界が魔王を核に存在するなどという事はなくなるだろう」
「馬鹿な……そんな事をすれば、世界はすぐに停滞する。ギアスという混沌無しでは、世界は変化を保てないのだぞ」
「何故そう言える? お前は所詮自分の世界を見てきただけだ。
花村、泉、金田一……ギアスなど無くとも彼らの世界は回っている。
エデンバイタルの干渉こそが、可能性を殺し意識を停滞させるのではないのか?」
「根拠の無い空想だ。そんな不確かな物に全宇宙の存亡を賭けるというのか!」
ゼロは真実、宇宙の行く末を案じているのだろう。
だが一つ、彼は見落としている事がある。
最初から魔王の視点で行動するあまり、人の可能性を信じていない。
ルルーシュが示した強さもまた、その可能性の中から生まれた物だ。
人が人のままで魔王を超えられる。ならば魔王とは、決して絶対の存在ではない。
「もう少しだけ信じてみろ。お前が愛する人間は、無知で愚かで、過ちを犯す生き物だ。
だが、過ちを糧に成長する事もできる。人はいずれ魔王など必要としなくなる。その可能性を、俺は信じる」
それだけ告げて、ルルーシュはゼロに背を向ける。
もはや魔王は敵ではない。それだけの力も、心も、もはやゼロには残っていない。
歩んでいく先はムーンセルの中枢、フォトニック深淵領域。
ガウェインに目を遣る。騎士が頷く。
「我が王、ルルーシュ。あなたの道行きに太陽の輝きが共にあらん事を」
「我が騎士、ガウェイン。忠道、大儀であった」
お互いに一言ずつ告げて、すれ違う。これ以上は必要無い。
ガウェインとの間に確かな絆を感じる。それだけで十分だ。
ルルーシュはガウェインに背を向けて、一人、月の中枢へと踏み入っていく。
「……これが、聖杯か」
そこはまるで、海の中にいるような――情報の大海の只中に、ルルーシュは浮かんでいる。
手を伸ばさずとも情報に触れられる。
太陽系最古の遺物。膨大な過去を収めた、万能の願望機。
ムーンセルは今こそようやく、ルルーシュを最後のマスターだと判定してその鍵を開いていた。
今なら、何でも出来る。
不死の命、別世界への転移、過去の改変、望む事が望むだけ叶えられる。
「以前の俺なら、飛びついていたかもしれんな……」
苦笑し、ルルーシュは願いをムーンセルへと入力する。
魔王ゼロのいた世界を検索。
その世界に存在するエデンバイタルの観測、そして介入。
システムの改竄。
「エデンバイタルはムーンセルと同質の存在。
故に、エデンバイタルを根底から改竄するのならば、ムーンセルもまた全てを擲たねばならない。
俺もまた、月と共に消えるか……」
ムーンセル・オートマトンを全力で稼働させるのならば、中枢でそれを指揮するウィザードは欠かせない。
エデンバイタルのシステムを書き換え終えた時、ムーンセルもまた自壊するように設定する。
聖杯が誰の手にも渡らないように。もう二度とこんな戦いが起きる事のないように。
そしてムーンセルが自壊すれば、ルルーシュは死の運命に回帰する。約束された死に帰っていくのだ。
「約束は、果たせない……か」
命令はすぐさま実行に移され、ムーンセルが唸りを上げる。
次々と現れては消える情報を捌きながら、ルルーシュは友を想う。
花村陽介は、鳴上悠の喪失に向き合うだろう。その痛みから逃げず、立ち向かい、そして乗り越えるはずだ。
泉こなたは、日常へと戻るのだろう。だが、前よりもほんの少し、強くなったかもしれない。
彼らの変化を見届ける事ができないのが、未練だ。
「贅沢になったものだな、俺も。全てを捨てると一度は決意したはずなのに」
いつまでも悔やんでいる訳にも行かない。
と、ムーンセルが自壊を始めたのがわかる。
首尾よくエデンバイタルを改竄しているようだ。これでもう、魔王という存在は生まれない。
その果てにエデンバイタルの意識エネルギーが停滞し、やがて滅びを迎えるならば、それはもう仕方がない。
人がそのように選択した結果なのだ。自ら選んだ先の滅びならば、それは魔王がいようといまいと不可避のものだ。
だが同時に、そうはならないとも確信している。
人という存在を論理で表現し切る事は出来ない。誰しも自らの内に混沌を抱え込んでいる。
ルルーシュが世界を変えたいと思ったように、自らの意志で行動する人間という者は必ず現れる。
魔王がおらずとも、混沌の種は尽きる事は無い。
「だって、こんなにも――宇宙には星々が、命が溢れているのだからな」
ルルーシュの目に映るのは、満天の星空だ。
煌めく光の一つ一つが命ならば、可能性はその生命の数だけ広がっている。
「信じろ、魔王……俺やお前がいなくとも、可能性は無限の分岐を増やしていく。
その中から必ず、明日への希望は生まれるはずだ」
目を閉じる。
星々に抱かれて、ルルーシュの旅は終わる。
願わくば、次に目覚める時があれば、優しい世界であってほしい――
伸ばした手は誰かに強く掴まれる。
そして、ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアという存在は、月と共に消滅した。
◇ ◆ ◇
目覚めは、割と早く訪れた。
小鳥の囀りが耳をくすぐる。朝日が瞼を貫いて眼球を灼く。草の香りが鼻につく。頬を撫でる風が心地いい。
ルルーシュは、ゆっくりと目を開けた。
「ここは……?」
そこは、見知らぬ草原だった。
熾天の座でも、冬木市でも、ましてゼロレクイエム最後の地でもない。
完全に見た記憶の無い、緑の平野だった。
「何だ? 何故、俺は生きて……?」
あの聖杯戦争は夢だったとでも言うのか。
そんなはずはないと思うものの、傷や令呪は一つも残っておらず、夢ではないと証明する物がない。
慌てて立ち上がる。と、懐からこぼれ落ちた物があった。
「これは、花村の……」
契約者の鍵だ。それを見た瞬間、記憶が圧倒的な現実感を伴って脳裏に再現される。
ルルーシュは確かに魔王ゼロを倒し、今度こそムーンセルにアクセスして、自壊を命じた。
エデンバイタルは改変され、聖杯は解体されたはずなのだ。
その結果ルルーシュは死ぬはずだった。本来あるべき死の運命に戻るはずだった。
だが今、生きてこの草原にいる。
「やっと起きたか、馬鹿者め。女を待たせるとはマナーを知らないボウヤだな」
聞き覚えのある声がする。
振り向けばやはり、そこにいたのは全ての始まりである緑の髪の魔女――C.C.だった。
「C.C.……? 何故お前がここにいる。いや、そもそも何故俺は生きている?
ゼロレクイエムはどうなった? スザクは? ナナリーは?」
「うるさい。お喋りな男は嫌いだ」
矢継ぎ早に質問するルルーシュを無視して、C.C.は持っていた包みを放り渡す。
混乱しながら包みを開くと、そこにはいかにも凡庸な普段着が一式入っていた。
「さっさと着替えろ。いくらE.U.の田舎町とはいえ、その皇帝衣装は目立ちすぎる」
「は? 待て、どういう事なんだ。説明しろ、C.C.! なんで俺は生きているんだ!?」
「知らんよ。私はただ、呼ばれただけだ。今日この場に来るようにとな」
「呼ばれた……?」
これ以上聞いてもC.C.に答える気はなさそうだったので、ルルーシュはおとなしく服を着替える。
着ていた皇帝の衣服は血に塗れている。と言っても聖杯戦争の負傷ではなく、ゼロレクイエムにてスザクに刺し貫かれた時の出血だろう。
皇帝服は包みにまとめる。いくつか処分の方法を考えて、それどころではないと思い直した。
「着替えたな、では行くぞ」
「待てC.C.、いい加減に説明をしろ!」
「あれに乗る。お前は前だ」
相変わらずのマイペースぶりで、C.C.はさっさと進んでいく。
その先には一台の馬車があった。荷台に藁を満載した、古き良き原始的な移動装置だ。
C.C.は荷台に乗って寝転がり、ルルーシュに御者席へ座れと手を振って指示してきた。
「私はもう馬の面倒を見る気はない。お前が運転しろ」
「C.C.! いい加減にしろ!」
「うるさい奴だ。頼まれたんだよ、お前の事をよろしく頼むとな」
「頼まれた? 一体誰にだ!」
「お前にだよ、ルルーシュ」
「……は?」
瞬間、曖昧だった記憶の霧が晴れる。
魔王ゼロを打ち倒し、聖杯に接続した後だ
全てを終えて、目を閉じたルルーシュの手を掴む者がいた。
ガウェインではないとしたら、それは魔王ゼロしか有り得ない。
「あいつ、まさか……!」
ガウェインが止めなかったのは何故か。
それは、魔王ゼロにルルーシュを害する気がなかったからではないか。
あの時、ゼロは魔王ゼロではなく、ルルーシュだった。
魔王という存在が消え、エデンバイタルとの接続を断たれたゼロならば、自らをルルーシュ・ヴィ・ブリタニアであるとムーンセルに誤認させる事も可能なはずだ。
そしてルルーシュと入れ替わり、ルルーシュをムーンセルの外へと弾き出した。ご丁寧に死ぬはずの運命までも書き換えて。
ゼロ自身は崩壊に巻き込まれると知りながらも、ルルーシュの代わりに聖杯を自壊させた。
そう考えれば辻褄は合う。
「Cの世界を通じてお前に連絡をとったという事なのか」
「私だって驚いたさ。いきなりお前の声で呼ばれて、更にここに来てみれば死んだはずのお前が呑気に寝ているんだからな。
ああ、そういえば伝言を預かっている。“魔王でも魔人でもなく、人として生きて死ね”、だそうだ」
「人として……?」
「まあ、いいんじゃないか。どうせお前が生きてる事を知ってる人間は私以外は誰もいないんだ。
適当に名前を変えて、あちこちを放浪する生活なら、大した騒ぎになる事もないだろう。ナナリーやスザクに会う訳にはいかないだろうがな」
「そんな適当な……」
だが、思い直す。
魔王ゼロがルルーシュを救って代わりに滅びたのは、もう一度人の可能性を信じてみる気になったからではないのだろうか。
魔王として生きざるを得なかった自分の代わりに、人の生を全うしろと……そういうメッセージ。
ならば、ルルーシュが自身の生死に拘るのは、その願いを否定するという事になる。
スザクには、生きろと命じられた。
陽介とこなたとは、再会の約束をした。
魔王ゼロには、人として生きて死ねと託された。
ならば……ルルーシュが、一個の人間として選ぶべきは。
「……まったく。せっかく撃たれる覚悟を決めたというのに、また生きたくなってきたじゃないか……」
「悩むようだったら、理由をやる。私のために生きてみろ。
忘れているようだが、お前には責任があるんだぞ。私の面倒を見るという責任がな。
女を待たせたんだ、ちょっとやそっとの借りじゃないぞ」
「この魔女め……だが、確かにお前には借りがある。
借りっぱなしは癪だしな……まあ、いいさ。一人旅は退屈だからな。付き合ってやるよ」
「じゃあさっさと出発しろ。私は腹が減った。ピザが食べたい」
「やれやれ。おい、金はあるのか? 俺は一銭も持っていないぞ」
「心配するな。ジェレミアの財布を持ってきている」
「……そうか。いや、何も言うまい」
C.C.は相変わらずC.C.だった。その変わらない有り様に、どこか安心する自分がいる。
少なくとも一人、自分と共に歩む人がいる。それならば、もう少し生きてみるのも悪くないのかもしれない。
この、ルルーシュが創った世界で。ナナリーやスザクが生きるこの世界で、もう一度人として生きる。
それでも、いつか死を迎える時は来るだろう。その時――あの魔王に教えてやろう。
きっと、大丈夫だと。魔王などいなくとも、この宇宙は続いていく。
馬車はゆっくりと動き出す。
目的もあてもない、ゼロから始める気ままな旅。
人として生きると決めたのなら、このくらいの適当さがちょうどいいのだろう。
そう、始まりがゼロならば――これからいくらだって、積み重ねていけるのだから。
「ルルーシュ、退屈だ。何か話をしろ」
「そうだな。では、俺の……友人の話をしてやろう」
「ん? スザクの事か」
「いや……そうでもあるが、それだけじゃない。話せば長くなるな」
「いいさ、時間はたっぷりあるんだ。好きに話せ」
さて、どこから話したものか。
そうだ、と思いつく。C.C.ならば、神根島のような手付かずの遺跡の場所を知っているかもしれない。
思考エレベータを開き、別の世界へと扉を開く。
そうすればまた会えるかもしれない。再会を約束した、二人の友と。
決めた。まずは会いに行こう。この鍵も返さなければならないのだから。
嬉しそうなルルーシュの気配を察して、C.C.も微笑む。
「ギアスという王の力は、人を孤独にする。ふふ……少しだけ違っていたか? なあ、ルルーシュ」
問いかけてくる彼女に、笑みを返す。
見上げれば、空には輝く太陽がある。
あの騎士と同じ、暖かく柔らかな光。
この光が照らしてくれるのならば、行き先に迷う事はないだろう。
道はどこまでも続いていて、旅も続いていく。
そしてきっと、この旅路の果てに――――。
「――約束を、果たしに来たぞ――」
&color(blue){ 《二次キャラ聖杯戦争 終幕》}
----
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: