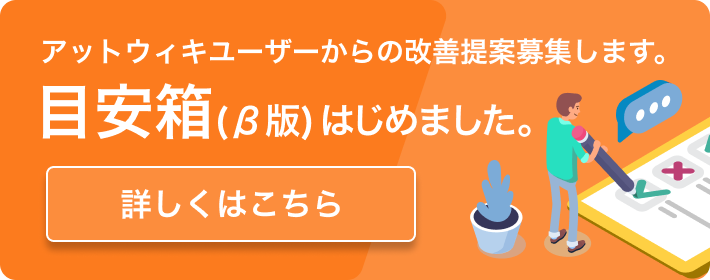「終わりに向かう物語」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「終わりに向かう物語」(2014/05/18 (日) 19:20:39) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
日は落ちた。三度目の夜。
紛れも無くこれが最後の夜であると、誰もが確信している。
午前零時。
暗闇の中にあってなお、太陽の如き輝きを放つ一人の男――名をギルガメッシュ。
金の髪、赤い瞳、黄金の鎧。只人が見れば無意識に頭を垂れる、圧倒的な存在感を放っている。
彼こそは人の歴史に燦然と名を刻む、万夫不当の英雄王だ。
そしてその側には、英雄王とは対照的に漆黒の礼服に身を包む長身痩躯の男が一人。
言峰綺礼。神父のNPCにして、ギルガメッシュのマスターとしてこの聖杯戦争に参戦したイレギュラー要素である。
彼らは、敵を待っている。
もうすぐここに――西と東の街を結ぶ冬木市の要所、冬木大橋へと、敵がやってくる。
「英雄王よ、一つ質問がある」
綺礼の問いに、ギルガメッシュは目線で先を促す。
この決戦の地に着いて、ギルガメッシュはただの一言も発していない。
緊張している……という訳ではない。その視線は遥か彼方、これより雌雄を決する人間たちの来訪を待ち受けている。。
「何故、この場所を選んだのか、ということだ。お前に戦場の有利不利などないのだろうが、ゼロに依頼してまでここに拘った理由があるのか?」
「ふ……ん。大した理由ではない」
ギルガメッシュの目線は言峰から天へと巡る。
否、彼が見ているものは空ではない。過去の情景を思い出すように、ギルガメッシュは浅く瞼を下ろす。
「いつか、どこか、までは覚えておらんが。このような場所で、我は賊を裁いた記憶がある。
奴は、正しく英雄であった。この俺が手ずから誅する価値のある、な」
「ほう……英雄王にそこまで言わせるとはな。よほど名のあるサーヴァントだったか」
「我とは違う王道を掲げた益荒男だ。奴の覇道は、あれはあれで見応えのあるものだった」
昔を懐かしむように、ギルガメッシュは述懐する。
豪放磊落を地で行く真の英雄との、譲れぬ王道と掲げた誇りをぶつけあった一戦。
長き眠りと倦怠の中にあって、あの鮮烈な記憶は未だ忘却の海に沈んではいない。
「ではここを選んだのは、これからやって来る彼らが、その英雄某に比肩し得ると見定めたから、か」
「さてな。此度は王と王の戦いではない……そこまでの期待はしてはおらん」
ただ、と英雄王は付け加える。
「この橋を戦場とするなら、余計な小細工はいらん。ただ前進し、ただ敵を粉砕する。
勝ち残った、より強い者だけがこの橋を渡り切ることができる……明快であろう」
そう語るギルガメッシュの眼には、隠し切れない喜悦と戦意が入り交じっている。
拳王、狂王、騎士王、紅世の王、不死者、破壊者、抜剣者。仙人、妖狐、円卓の騎士、妖魔狩り、錬金術士。
スタンド使い、エンジェロイド、戦国最強、光の御子。魔法少女、北斗神拳の使い手、ルーンナイト、神話級礼装の防衛プログラム。
散りゆく者は皆、いずれ劣らぬ当千の強者ばかりだった。
「ここまでの顔ぶれを揃えた聖杯戦争は歴史上そうはあるまい。そして奴らは勝ち残ってきた。それが運であれ、実力であれ。結果的に今、生きているということに意味がある。
生を渇望する意思――曇りなき魂。ゼロが求めているものを、奴らは磨き上げ、研ぎ澄ませてきた。
ならばこそ、奴らは我の前に立つ資格がある。我の手で試す価値がある。人の内なる可能性を示す……その行く末を見定めるのが我の仕事である故な」
「裁く……ではなく、試す、か」
「今宵、我は王としてではなく試練として、奴らの前に立ち塞がる。
奴らが我を超えられぬのならば……ゼロもとんだ道化に成り下がるというものよ」
「なるほどな。ゼロに言われただけでなく、お前自身にも彼らと戦う理由があるということか」
得心がいった、と神父は頷く。その姿には気負いも緊張もない。理由というならば、このNPCこそここにいる意味が無い。
「何、私も同じだ。彼らがこの戦いでどこまで成長し、そしてどこに辿り着くのか……その果てを見てみたいのだよ」
「異なことを言う。もし敗北すれば見届けるも何もないではないか」
「それはそれで構わんさ。私を……いや、お前を超えるということは、彼らの可能性は人の臨界を極めたという証左。
ゼロが求める次代の魔王も必ずやそこにいるだろう。新たな魔王の誕生を見届けて消えるのなら、何の不満もない」
そう、魔王ゼロもこの戦いを見ている。
ギルガメッシュが打倒され新たな魔王の器が生まれるか。あるいは魔王たるべき者は現れず、ギルガメッシュによって魔王そのものが滅ぼされるか。
魔王が滅びれば、秩序と混沌の天秤は崩れあらゆる宇宙はいずれ緩やかに壊死していくだろう。
ギルガメッシュはそれでも構わない。人が進化の果てに選んだ結末ならば、黙して受け入れるだけだ。
だが――予感がある。期待、と言ってもいい。
それはか細く不確かなもの。しかしそれでも、信じてみたいと思わせる。
「……来たか」
閉じていた瞼を開く。橋の向こう側――遮るものなき前方に、五つの影が現れている。
ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。悪逆皇帝、奇跡を起こす男。
ガウェイン。円卓の騎士、太陽の聖剣を担う者。
泉こなた。力なき幸運の星、天秤の支柱となる者。
火野映司。欲望の王、古の力を宿す仮面の戦士。
花村陽介。ワイルドカード、受け継がれる絆と力。そして傍らには信念を貫く槍の男。
マスターが三人、サーヴァントが二人。
皆一様に先刻とは比べ物にならない王気を纏い、確かな意志と共にギルガメッシュと対峙している。
誰の眼にも恐怖はない。感じていないのではなく、呑み込んでいる。何の力もない小娘でさえも、英雄王の視線に怯まず睨み返してくる。
「どうやら彼らもただ遊んでいた訳ではないようだな。
特にあの三人……マスターたちは、どうしたことか、保有する魔力が桁違いに増大している」
「それでこそよ。無策で突っ込んでくるようなら踏み潰してやるところだが……ああ、それでこそだ。
我が相手をするのだ。死力を超えた全力を以って挑んでこそ、初めて戦いになるというものよ」
笑み、ギルガメッシュはゆっくりと前進していく。その手には龍を象った匣がある。
もはや言葉など意味を成さない。此処から先に意味があるのは、雌雄を決する力のみ。
戦を前に、この傲岸不遜を形にした男が常ならあり得ない準備をした。
古の竜を迎え撃つは、新たなる龍の力。鎧を脱ぎ捨て、宝物庫から呼び出した鏡へと、匣を掲げる。
炎が巻き起こる。瞳と同じ、鮮烈な赤。
「――変身」
顕現するは龍の戦士。
英雄王ギルガメッシュが出陣する。
◇ ◆ ◇
最後の時間は何事もなく過ぎた。
精神世界から帰還し、決戦に向けての打ち合わせを終え、休息を取る。
こなたは母親が既に亡くなっていて、父親と従姉妹の三人暮らしのため家事には長けている。こなたと陽介が驚いたのは、ルルーシュもまた料理が達者なことだった。
「うわー、美味しいねこれ。ちょっとした店で食べるくらいのレベルじゃない?」
「そんな大したものじゃない。妹や弟によく作ってやっていただけだ」
「へえ、お前兄弟がいるのか」
どこか懐かしむ口調で言うルルーシュに、彼の作ったカレーを食べながら陽介が答えた。
料理の得意な兄、に親友を連想する。故郷を思う気持ちが一層強くなる。
「じゃあ、絶対帰ってやらないとな。もちろん俺も、泉も」
「……ああ、そうだな」
元の世界に帰ったところで、ルルーシュが妹の前に姿を見せる訳にはいかない。
と言うより、首尾よくギルガメッシュとその背後にいる者を倒せて元の世界に帰還したとしても、ルルーシュにはこなたや陽介のように元の日常に帰るという結末は望めない。
ガウェインはかつて“死の直前にある”とルルーシュを評した。ならば、ムーンセルより解放されれば、その後は本来向かうべき結末――死が待っているだけだ。
ルルーシュはその最期に文句などない。やるべきことをやり遂げたのだから、あとはただ舞台から降りればいいだけだ、だが。
(あいつは…スザクは俺に生きろと言った)
元の世界に戻れば、今もゼロとして活動しているスザクがいる。そのスザクは、この聖杯戦争でルルーシュが看取ったスザクとは別人だ。
故に、その言葉に従う必要はない。ないのだが――本当に、それでいいのかと思う部分もある。
今更死を恐れてはいない。しかし、もし元の世界に戻った後に俺は死ぬ、などと言えば、陽介もこなたもきっと迷ってしまうだろう。
言わないでいる、あるいは嘘をつくことは簡単だ。今までにも散々やってきた。
しかしルルーシュは、運命共同体となった二人の友を偽ることに強い躊躇いを覚えている。
(生きろ…か。難しい注文だな、スザク。俺がお前に課した命令は、こうも重いものだったと今更ながらに思い知るよ)
仮に生きて元の世界に戻った場合どうなるだろうか。
こなたは、今までと変わらぬ日常を送るだろう。彼女は元々日向の世界にいる人間だ。
陽介は、鳴上悠の死を親しい者に注げると言った。辛い役目だが、それをしなければあの冬の日から一歩も前に進めないのだと。
ではルルーシュはどうするか。
最愛の妹であるナナリーの前に姿を見せる訳にはいかない。ルルーシュは世界の憎しみを集めて死んだのだから、世界に無用な混乱を招くことになる。
無論、ゼロとして活動するスザクや、カレンといった縁者も同様。かつてのルルーシュを知る人間には全て、出会ってはいけない。
結局、残るのはあの魔女くらいだ。
(そう言えば、あいつはどうしているだろうな。願いを叶えてはやれなかったが…)
ルルーシュが世界を変えるきっかけになった、ギアスを与える魔女。今も一人で世界を彷徨っているのだろうか。
もしスザクの言葉を守って生き続けるとするなら、彼女と一緒に生きるのも悪くない。
(…未練だな。すべて捨てたと思っていたが、そう簡単に忘れられるものでもないらしい)
それはこの戦いで得たものも同じだ。友を得ることなど、スザク以外にはないだろうと思っていた。
しかし今、ルルーシュの周りには友がいる。彼らだけはなんとしても元の世界に送り届けてやりたい……今はそれが一番望みであることは間違いない。
ガウェインを見る。騎士は、口に出さずともルルーシュの思いを汲み取ってくれる。
(そう、ギルガメッシュを討つのは俺たちだ。その結果俺たちが果ててしまおうとも…泉と花村が先に進めるのなら、悔いはない)
仮面を被る。秘めた願いを見透かされないように。
最後の夜は更けていく。
◇ ◆ ◇
「あれは…たしか、ディケイドが変身していた…」
「うん、仮面ライダー龍騎だ」
日付が変わる時刻。決戦の場、未遠川に架かる冬木大橋に赴いた一行を出迎えたのは英雄王と神父のNPC。
書状にはこの二人が相手になると書かれていたので驚きはない。何故NPCが、という問いも、その向こうにムーンセルを支配する黒幕がいるのなら不思議ではないからだ。
問題は、黄金の鎧を纏っていた英雄王がその姿を変えたことだ。
仮面ライダーディケイド、仮面ライダーオーズ。二人の「ライダー」に準ずる、三人目の「」仮面ライダー」に。
宙を泳ぐ赤龍が吐き出す炎が、数百メートルの距離を隔ててなおマスターたちの肌をチリチリと焦がす。
「全部のパラメータがBクラス以上!?」
「あらゆる財宝を所有する、英雄王の宝物庫…まさか、仮面ライダーの変身道具まで収めているというのか…!」
接敵した瞬間、ルルーシュたちの目論見は早くも瓦解した。
強大な戦力を次々と投射する英雄王を打倒するには、何らかの手段でガウェインとの接近戦に持ち込むしかない。それが、ルルーシュたちの狙いだった。
至近距離で切り札たるエクスカリバー・ガラティーンの全力を叩き込めば、いかな英雄王とて必ずや打ち砕ける。
問題は、どうやって聖剣の間合いまでガウェインを踏み込ませるか――だったのだが、
「ガウェイン、やれるか?」
「いえ……難しいでしょう。私の宝具もルルーシュのコードキャストも、基本属性は火です。今の英雄王には、効果が半減すると見て間違いない」
エクスカリバー・ガラティーンは太陽の灼熱で敵を焼き尽くす宝具。
決闘術式「聖剣集う絢爛の城」は、炎の壁で相手を覆い自由を奪う術式。
どちらも燃え盛る炎の熱を骨子とする。ゆえに、炎を司る仮面ライダーである龍騎に対してはスペック通りの効果が見込めない可能性が非常に高い。
「で、でもよ。火野さんと同じ姿になったってことは、その剣を飛ばす攻撃はできない訳だろ? じゃあ手数で俺たちが勝てるんじゃ」
陽介の発言は、ギルガメッシュ=龍騎が後背に出現させた無数の刀剣によって遮られる。
仮面ライダーに変身していようと関係なく、英雄王の基本戦術は健在だ。本人を強化しつつ、さらに宝物も自在に操る。これでは数で優っていても何のアドバンテージもない。
「……来ます!」
綺羅星の如き宝具の群れが流星となって射出される。
その上方には、王の支配下に置かれたドラグレッダーが炎をまき散らしまっすぐに向かってくる。
本体たるギルガメッシュもまた、どこからか飛来した剣を手に悠々と歩き出す。
三面からの同時侵攻。迷っている時間はない。迎撃に飛び出すガウェインに続こうとした映司を、こなたが引っ張って止める。
「…映司さん、あれを使おう!」
こなたが言うと同時に、映司の胸から三枚のメダルが飛び出してくる。色は紫……この聖杯戦争では一度も使っていない、恐竜系等のメダルだ。
本来映司の自由意志では使えないこのメダルが飛び出してきたということはすなわち、この状況が絶対的な危機であるということ。
そして――
「これは…そうか、こなたちゃんから供給される魔力がすごく増えたから…!」
火野映司、仮面ライダーオーズのマスターである泉こなたが、ウィザードとして飛躍的に成長したためだ。
今のこなたは、消耗の激しいプトティラコンボを用いるに足る十分な魔力を保有している。
映司がコンボの制御に気を回さずとも問題ない――つまりは消耗を気にせず全力で戦えるほどの。
かつてディケイドは自身のマスターとこなたを比較して、その未熟ぶりを突いた。
ここに来て、仮面ライダーオーズに初めて全力で、いや全力以上で戦う機会が巡ってきたのだ。
「…いいかい、こなたちゃん?」
「うん。私も一緒に戦うから…きっと大丈夫だよ!」
何の力もない非力なマスター。そんな者はもうどこにもいない。
今、ここにいるのは…映司を支え、肩を並べて戦う「相棒」にほかならない。
映司が思い出すのは、かつての相棒の姿だ。似ても似つかないのに、何故か懐かしい気持ちになる――三枚のメダルを、掴み取った。
ベルトに叩き込んだメダルが魔力を循環させ、火野映司の全身を覆う。
緑でも黄色でも白でも青でも赤でもない、本来もう失われたはずの禁断の力。その力が今、必要だ。仲間たちを守るために。
かつて見た悪夢を振り払う。マスターたちには傷一つつけさせないという、固い決意とともに。
「変身!」
仮面ライダーオーズが有する最強の宝具――プトティラコンボ。
力強く翼が広がり、長く伸びた尻尾が大地を打つ。迫り来る刃の嵐と赤龍をじっと見据える。翼が羽ばたき、重力の鎖から解き放たれたオーズが弾丸のように突っ込んでいく。
「――ゥゥゥゥゥウオオオオオオオオオオオオオォォォォッ!!!」」
獣の如き咆哮が放たれる。
ドラグレッダーが吐き出した灼熱のブレスを、オーズが冷気のブレスでもって迎撃した。超高温と極低温が激突し、空気さえも震わせる。
その衝撃は降り注ぐ英雄王の宝具を散り散りに吹き飛ばし、橋の橋脚に次々と突き立たせた。
そして、ガウェインがその只中を駆け抜けていく。狙いは英雄王ギルガメッシュの首、ただ一つ。
ギルガメッシュが再度宝物庫を開くが、間に合わない。ガウェインの踏み込みは陽介のペルソナによって強化されている。
音すらも置き去りにする一撃は、しかしギルガメッシュが構えた龍の尾を模した剣に受け止められた。
「英雄王、討ち取らせていただく!」
「音に聞こえたキャメロットの騎士か。ふん、騎士王が倒れた今も剣を置かぬは滑稽よな」
「今の私の主はルルーシュだ…ゆえに、ここは押し通る!」
ガウェインが気合とともに聖剣を一閃させると、寸前に後退したギルガメッシュの胸元に一筋の傷が刻まれる。
さすがにセイバーと正面から斬り合うのは英雄王といえども荷が重い。セイバーとは接近戦だけに特化したサーヴァントなのだから。
すかさず追撃に入ろうとしたガウェイン、しかし後方から迫る気配が許さない。身を翻すと、ドラグレッダーが大きく開けた顎で今にも食らいついてくるところだった。
ガウェインはなんとか回避したが、次は体勢を整えたギルガメッシュの斬撃が来た。
剣を構え直す時間はない。一直線に突き込まれる剣閃――受け止めたのは、飛び込んできたオーズの斧だ。肉食恐竜の頭を象った意匠の斧が、龍尾の剣と拮抗する。
「来たか、雑種。貴様の欲望、我が喰らい尽くしてやろう」
「遠慮しときます……よ!」
オーズがギルガメッシュの剣を弾く。だが、ギルガメッシュが接近戦ではガウェインに及ばないように、オーズもまたギルガメッシュには届かない。
閃く幾つもの斬光は目にも止まらず、剣の英霊たるガウェインならば防げただろうが、騎兵であるオーズではそうも行かなかった。
ギルガメッシュもまた神話に名を刻む英霊だ。セイバーには譲るとはいえ、刀剣の扱いは並みの英霊を軽く凌駕する。
援護に入ろうとするガウェインは、再び襲い来るドラグレッダーとバビロンの宝具たちに足止めされた。
プトティラコンボの尻尾、テイルディバイダーを振り回して隙を狙うが、ギルガメッシュは虚空から飛び出てきた剣を片手で掴み、受け止めた。
「やはり竜種には竜種よな。楽しいぞ、雑種!」
余裕すら感じさせるギルガメッシュに、映司は答えられない。
オーズ・プトティラコンボと龍騎なら、パワーはオーズに軍配が上がる。しかしこの場合、装着者に差があった。
変身しなければ人間とさほど変わりがない火野映司と、元から一流の英霊であるギルガメッシュでは、スペックに天と地ほどの開きがある。
ギルガメッシュが本来持つ膂力や速度に、龍騎の力が上乗せされた形だ。オーズに拮抗せずとも、近いレベルまで迫っている。そして、差が縮まれば物を言うのは両者の戦闘技術になる。
仮面ライダー龍騎というスタイルに限って言うなら、今のギルガメッシュはオリジナルの龍騎やディケイドをも凌駕しているかもしれない。
「それでも、ここは退けないんだ!」
至近距離で冷気のブレスを吐きつける。対抗してギルガメッシュが一挙動でガントレットに叩き込んだカードが新たな力を召喚。オーズの眼前に巨大な盾が現れ、冷気を完全にシャットアウトした。
凍りついた盾をメダガブリューで殴りつける。粉々に砕ける。その向こうにギルガメッシュは既にいない。ギルガメッシュは跳躍し、ドラグレッダーに騎乗していた。
ギルガメッシュはドラグレッダーの頭部を傲岸に踏みつける。龍は暴君の怒りに触れぬよう、直ちにその意図を組んで高く舞い上がる。
「フハハハ…やるな。ここまで勝ち残ったのは伊達ではないか」
ギルガメッシュは一旦引いた。何故、と戸惑うも一呼吸置けることはオーズにとっても好都合だ。ガウェインとともに後退し、マスターたちの元へと舞い戻る。
「こなたちゃん、大丈夫?」
「うん、私は平気。映司さんこそ大丈夫?」
「俺も平気。前よりずっと安定して紫のメダルを使えてると思うよ。こなたちゃんのおかげでね」
その言葉は嘘ではない。本来プトティラは長く使えば暴走の危険があるコンボだが、ここまでの戦闘でその兆候は感じられなかった。
こなたから供給される魔力が潤沢なため、映司の状態も安定しているからだ。
「とはいえ、お前たち二人がかりでも詰め切れんか。花村、もう一度補助魔法を頼む」
「おう。頼むぜ、アレックス!」
マスターたちはサーヴァントの攻防を見ているしかなかった。
サーヴァントとペルソナの融合体を操る陽介といえども、超級のサーヴァントたちの闘争に割って入ることはできなかった。
ガウェインやオーズが何気なく弾く剣の一本でさえ、陽介が防ぐには重すぎる。ルルーシュやこなたでは言うまでもない。
「あの龍が厄介だな。どうにかして仕留められないか?」
「難しいですね。ギルガメッシュは常に龍の周りに宝具を展開し、護衛させている。まずはあの宝具の防壁を突破しなければ」
陽介が補助魔法をかけ直し、こなたが回復をする。
オーズ、ガウェイン共に万全の状態に復帰するが、それはあくまで振り出しに戻ったというだけだ。
「もし奴が宝具を無尽蔵に呼び出せるのなら、長期戦は不利だ。一気に決めるしかない」
「じゃあ……あれ、やる?」
こなたが言う「あれ」とは、一発限りの切り札のことだ。
マーガレット名付けるところの「至高の魔弾」。サーヴァントすらも傷つけ得る、とっておきの鬼札だ。
「いや、駄目だ。あれは俺たち三人が全力を傾けねばならない。向こうのマスターがその隙を見逃すとは思えん」
ルルーシュが否定する。サーヴァントたちの攻防の間、ルルーシュはじっと綺礼を観察していた。
サーヴァントたちに割って入れないのはこちらと同じだろうが、それにしてもあの神父は動かなさすぎた。
神父はルルーシュと同じくこちらを観察していた…隙を見せればそこに食らいついてくる、そんな不気味さを感じた。
ギルガメッシュがマスターに直接攻撃してこないのは、姑息な真似はしないという王たる誇りがあるからだろう。
あるいは正面から力づくでガウェインとオーズを打ち破ることに意義を感じているのかもしれない。だがマスターまでそうだとは限らない。
「じゃあ、私が礼装であの人を見張って、ルルーシュくんがそれに備える。陽介くんが映司さんとガウェインさんの援護をする…これでどうかな」
敵対者の情報を表示するこなたの礼装なら、偵察にはうってつけである。
もし綺礼が動けば、ルルーシュが対応する。立ち向かうことは難しくても、こなたを連れて退避するくらいは十分に可能だ。
「相談は終わったか? では、再開するぞ」
結論を待たず、ギルガメッシュが再度侵攻してきた。
剣と炎の嵐が降り注ぐ。「壊刃」サブラクに匹敵する、広範囲に渡る破壊。
オーズがガウェインを掴み、炎は冷気のブレスで迎撃、宝具の雨の間隙を縫って突撃する。
一瞬後には先程と同じ光景が繰り広げられる。龍から降りたギルガメッシュへガウェインが斬りかかり、オーズがその援護につく。
しかし、今度は陽介が加わる。
ペルソナのアレックスが両腕を変形させる。ペルソナがただ魔法を放つだけではギルガメッシュには通じないだろう。
だが、サーヴァントの力を受け継ぐアレックスなら…サーヴァントの力を再現することができるアレックスなら、話は別だ。
ペルソナ使いの枠を超えた高密度の魔力が荷電粒子に変換され、まばゆく輝く槍となる。
「力を貸してくれ、アレックス……行くぜ!」
真っ直ぐに放たれた荷電粒子の槍は、オーズに気を取られていたドラグレッダーに直撃した。
炎を司る龍といえど、雷光にはさほどの耐性はない…龍が身を焼く激痛に絶叫を上げる。
「ちっ、竜種といえどこの程度か」
ガウェインがすかさずドラグレッダーの首を落とそうと跳躍するが、その瞬間にギルガメッシュはアドベントのカード効果を解除。鏡像が砕けるようにドラグレッダーが掻き消える。
空振りしたガウェインだが、龍が戦線を離れた今こそ好機とすぐさまギルガメッシュに詰め寄る。
頭上にはオーズ。今度はいくら宝具を展開しようと一手遅れるということはない。
「威勢のいいことだ。だが一つ忘れてはいないか?」
しかし、ギルガメッシュは怯まない。口元には酷薄な笑み。
「貴様らのマスターが仕事をしたように…我のマスターも遊んでいるわけではないらしいぞ」
オーズが急停止。ギルガメッシュに気を取られていたが、いつの間にか綺礼の姿がない。
急ぎ振り返り、マスターたちを見る。ルルーシュとこなたではない。襲われていたのは、ドラグレッダーを攻撃した陽介だった。
全力を振り絞ったために、陽介はしばらく動けない。その隙を言峰綺礼は狙っていたのだ。
「陽介くん!」
「よそ見をしている暇があるのか、雑種 」
――ファイナルベント――
鳴り響いたのは、必殺を告げる死神の声だった。
◇ ◆ ◇
陽介が荷電粒子の槍を放った一瞬、視界が閃光に染め上げられたその一瞬だけ、こなたは綺礼の姿を見失った。
綺礼にはその一瞬で十分だった。夜闇に紛れて姿を隠し、人間離れした脚力をもって一気に陽介に接近――全力を開放した直後のアレックスへと拳の一撃を叩き込むには。
アレックスの姿が歪む。膨大な力を流し込まれたために、姿を構成する魔力が乱れに乱れたためだ。
ペルソナのダメージは本体へとフィードバックされる。腹に叩き込まれた一撃が骨と内臓をまとめて幾つか押し潰す。
陽介は血を吐きながら吹き飛んだ。
「がっ……はっ!」
「陽介!」
ルルーシュがコードキャストを放つ。
赤い雷は、神父が両手に生み出した刃渡り1メートルに満たない剣を投擲することによって、すべて見当違いの方向へと誘導させられた。
「ふむ、一撃で仕留めるつもりだったが。やはりペルソナ使いとは普通人よりも頑丈なものだな」
ルルーシュが立ち塞がったことにより、陽介にはそれ以上の追撃は加えられなかった。こなたが急いで駆け寄り、回復のコードキャストを陽介に施す。
元々アレックスが高い再生能力と耐久性を有していたため、ペルソナとなった今はその特性をやや引き継いでいる。そのため陽介は即死することはなかったものの、かなりの深手を負っていた。
「さて…些か呆気ない気もするが。どうやら向こうも決着がつきそうだ。こちらも終わらせるか」
とん、と神父が軽く一歩を踏み出す。それだけで、ルルーシュには目の前にナイトメアフレームが降りてきたような錯覚を覚える。
この神父は、ペルソナであるアレックスをたやすく殴り飛ばした。ただのNPCではありえない。近接戦に不慣れなルルーシュが太刀打ち出来る相手ではない。
「花村陽介とは別の意味で、君には期待していたが。打つ手なしかね、ルルーシュくん」
「くっ……」
神父のずっと後ろ、サーヴァントたちの戦いも佳境に入っていた。ギルガメッシュが龍を召喚し、空高く舞い上がっていく。
こなたの宝具を使わずともわかる。あの魔力の高まりは、勝負を決めに来ているのだ。
「泉、花村はどうだ?」
「待って、まだ時間かかるよ! 傷が深すぎる」
陽介も、こなたも動けない。
ルルーシュ一人では神父に抗えない。
「では、ここまでだな」
「いや、そうでもない!」
ならば――少し早いが、カードを切る。
ルルーシュは開戦当初から槍王イルバーンをずっと地面に突き立てていた。持つのが重かったから…というのもない訳ではないが、ルルーシュの十八番を実行するためだ。
こなたの礼装により、冬木大橋の構造データは既に把握している。なぜだかやたらと硬くなるように情報が変化させられていたが、今のルルーシュとイルバーンなら改竄は可能だ。
ルルーシュはイルバーンに命令を下す。
「チェックメイトには早すぎたな!」
「これは――足場を!?」
綺礼が立っている橋そのものを、情報を分解し消去する。
ルルーシュがかつて得意としていた足場破壊戦術を、ようやく披露する機会を得た。
砂のように崩れ去っていく橋に巻き込まれまいと、綺礼が退いていく。破壊の規模としてはせいぜい十メートルというところだが、僅かながらに時間を稼げた。
視線の先、ギルガメッシュは今にもガウェインたちに襲いかかろうとしている。
ルルーシュは右腕に意識を集中し、叫んだ。
「令呪をもって命ずる!ガウェインよ、ギルガメッシュを斬り捨てろ!」
スザクから託された令呪が蓄えた魔力を解放、ムーンセルの定めた法則を歪める。彼の騎士であるガウェインに力を与えんがために。
ギアスではない絶対遵守の命令が、発動した。
◇ ◆ ◇
「これは……!」
天へと駆け上がっていくギルガメッシュ。
瞬時に後を追ったオーズと違い、翼なきガウェインはただ見上げることしかできない。宝具を放とうにも今のギルガメッシュには効果は薄く、オーズまで巻き込んでしまう。
ギルガメッシュの行動を許せば、確実にオーズかガウェインのどちらかが敗北する。それだけのエネルギーを秘めた攻撃だ。
だというのに何もできず結果を待つしかないという焦燥がガウェインを蝕んだ、そのとき。
急激に沸き上がってきた魔力。体内からではない、これは――
「ルルーシュ…!」
かつて無二の友ランスロットとの決闘の時にも感じた力の本流が、またしてもガウェインを奮い立たせる。
今ここに、王命は下された。
「ならば、往くのみ!」
ガウェインの姿が消失する。
次に実体化した場所は、遥か天空――オーズも、ギルガメッシュも超えて、さらに上。
ギルガメッシュとオーズが同時にガウェインを振り仰ぐ。両者の顔には驚愕が張り付いている。
大地を斬り裂かんばかりの斬撃を、ギルガメッシュへと振り下ろす。対してギルガメッシュは、とっさにファイナルベントの矛先をガウェインへ向けて放つ。
「はあああああああぁぁっ!」
「ぐっ――」
太陽の聖剣は龍騎には通用しない。だがそれは、宝具を全面解放した時の話だ。
聖剣をただの刃として振るうのなら、龍騎だろうとギルガメッシュだろうと届き得る。
ガウェインの全力と、令呪を上乗せした一撃は龍騎のファイナルベントに拮抗する力を生み出していた。
「セイヤァァァ――――――!」
そして、ギルガメッシュの全力と拮抗しているということは、下から迫ってくるオーズに対応する余力はないということ。
メダガブリューが飲み込んだセルメダルが魔力となって迸り、純粋な破壊力として現れる。
プトティラコンボの必殺技、グランド・オブ・レイジ。凄まじいエネルギーを内包したアックスモードのメダガブリューを叩きつける技だ。
龍騎のファイナルベント、ドラゴンライダーキックの三倍近い威力を誇るその攻撃が、ギルガメッシュへと直撃する。
「貴様ら、よもやここま――」
ギルガメッシュの驚愕、あるいは惨事はかき消される。
ガウェインの聖剣。ドラゴンライダーキック。グランドオブレイジ。三極の巨大な力の激突は、漆黒の空を白に染め上げるほどの閃光を放った。
「やったか……?」
地上で天を見上げていたルルーシュ達も、思わず言葉を飲み込むほどの輝き。
令呪一画とかなりの魔力を持って行かれたが、どうやら乾坤一擲の攻撃は成功したようだ。
「つ…ゴホッ、ガフッ。くっそ……痛え!」
「花村。気がついたか?」
「おかげさんでな…うお、なんだこの光!」
「映司さんたちがやったんだ。あっ、降りてきた!」
やがて光が霧散していくとともに、空からガウェインを抱えたオーズがゆっくりと降りてくる。二人とも全身に傷を負っている。特にガウェインがひどい。
必殺技を放っていたオーズと違い、ガウェインはただ聖剣を振るっただけだ。自らが放つエネルギーに守られていない分、他の二人とは受ける衝撃も段違いだっただろう。
着地した二人を、勝利を確信したマスターたちが出迎える。だが、サーヴァントたちは険しい目を空へと向けたままだ。
「申し訳ありません、ルルーシュ。仕損じりました…!」
ガウェインが苦渋に満ちた声で言う。オーズもまたそれを否定しない。
二人の視線の先には、ガウェインの言葉通り――ギルガメッシュが、五体満足のまま存在していた。
「中々面白い趣向だったぞ、雑種ども」
そう楽しそうに告げるギルガメッシュとて、無傷ではない。全身の装甲は砕け、黄金率を保っていた肌も無残に焼け焦げている。
しかし眼光に微塵の衰えはない。それはつまり、戦いはまだまだ続くということだ。
「王律権キシャル――我が財を砕き、この身に傷をつけるとはな。楽しませてくれるものよ」
ガウェインとオーズの攻撃は、ギルガメッシュが展開した宝具によって威力を半減させられた。
宝具は破壊したものの、ギルガメッシュを討ち果たすことはできず、オーズとガウェインがダメージを負っただけだ。
「へっ、じゃあ今度こそ完璧にとどめを刺してやりゃいいんだろ! そんなズタボロの状態なら楽勝だっての」
しかし膝を屈することなく、陽介が気炎を吐く。
仕留め損なったとはいえ、ギルガメッシュの傷も深い。対してオーズとガウェインは、負傷しているとはいえ動けないほどではない。
ドラグレッダーもまた半死半生の深手であり、回復した陽介ならば今度こそ倒し切れるだろう。
「ククク…言うではないか、雑種。ではこうしよう」
ギルガメッシュは焦らず、一枚のカードを引き抜く。サバイブ――と刻まれたカードをガントレットに装填。
「あれは……!」
唯一その行為の意味を知るオーズが、絶望に顔を歪める。
五人の見ている前で、ギルガメッシュとドラグレッダーが業火に包まれた。
「なんだ!?」
「こなたちゃん、俺とガウェインさんを回復して!早く…!」
ただ一人状況を理解したオーズが、体勢を整えるべくこなたを急かす。
何事かわからずとも、オーズの様子からただ事ではないと判断したこなたが全力でサーヴァントを癒やす。陽介もそれに続いた。
「伏して仰げ。これが王の威光である――」
炎の中からギルガメッシュの声が響く。躍り出てきたドラグレッダーにはもう傷一つない。無双龍ドラグレッダー改め、烈火龍ドラグランザー。
続いて姿を見せた龍騎も全身の装甲が元通り復元され、また意匠も力強いものへと変化している。
サバイブ・烈火のカードを得て現れる、龍騎の強化形態――龍騎サバイブ。仮面ライダー龍騎の、真なる全力の姿である。
あらゆるパラメータがワンランク上昇し、マグマの如き灼熱を衣のように纏っている。
「今までは、本気じゃなかったってこと……?」
力を取り戻した龍騎サバイブを前に、こなたの声も震えている。
通常形態の龍騎ですら、全力でかかっても仕留め切れなかった。なのに、そのさらに上がある。
こなただけではなく、ルルーシュもまた、心を支配する絶望に屈しそうになっていた。令呪という切り札を切り、二人のサーヴァントが全力を叩き付けてなお、軽くあしらわれた。
「まだだ……まだ何か、活路があるはずだ!」
口では仲間を鼓舞するためにそう言っても、そう簡単に打開策を考え付けはしない。
もはや残っている令呪はみな一画のみだ。それを使うということは死を意味する。
無論、己の命を勘定に入れなければもう一画は使える。鳴上悠が示したことだ。もう一度令呪を使うことでギルガメッシュを倒せるなら、ルルーシュは迷わずそうするだろう。
しかし、そうではない。ガウェインの宝具は龍騎にさえ通じないのだ。その強化形態である龍騎サバイブには言わずもがな。
もう一度眼前に転移させて斬撃をさせようにも、二度も同じ攻撃が通じる相手とは思えない。
至高の魔弾は論外だ。効いたところで、一発でギルガメッシュを倒せるわけではない。
「……奴は、神父はどうした!?」
マスターを狙えば、という思考に行き着いた時には遅かった。足場破壊から逃れた綺礼は既にギルガメッシュの後ろにいる。
「惜しかったな。一度は勝てると思い、それが覆された時の君たちの表情…中々に見応えがあったよ」
ルルーシュたちの絶望を味わうかのように、綺礼が述懐する。
「ギルガメッシュが本気を出す以上、もう私の仕事はないな。主演目はもう終わってしまっただろうが…さて、君たちはどのような結末を迎えるのか」
――ファイナルベント――
ギルガメッシュが手にした銃にカードを差し込むと、ドラグランザーの体が折り畳まれ、バイク形態へと変形していく。
バイクに騎乗したギルガメッシュが腕を掲げる。彼の背後に無数の空間震動が起き、数十もの宝具が顔を覗かせた。
「さあ――幕だ。雑種ども。王の前に頭を垂れよ!」
十分に楽しんだと、ギルガメッシュは終わりを告げる。もう遊びはない、本気の、全力の一撃。
ドラグランザーが鎌首をもたげ、灼熱の火球を吐き出す。後を追うようにバイクが発進する。
龍騎サバイブのファイナルベント、ドラゴンファイヤーストーム。火球とドラグランザーそのもので、敵対者を打ち砕く必殺技だ。
さらに英雄王が指を鳴らす。それを合図に、宝具が次々と射出されてくる。
炎と宝具の弾幕、そして龍の特攻。人の形をした破滅が差し迫ってくるのを、誰もが見ていることしかできない。
「……ルルーシュ、みな、下がってください」
否、ただ一人――ガウェインだけが、闘志を失わず立ちはだかった。
「何をする気だ、ガウェイン!」
「この剣ならば、あの龍に対抗できるかもしれません」
その手には陽介が持っていた封印の剣がある。かの騎士王ですら封じ込めた、異世界の大陸に名を残す伝説の竜殺し。
今までは、万が一ギルガメッシュがマスターを狙った時のために陽介が持っていたが、この状況ではもう陽介が持つ意味が無い。
「何とか、一手は凌ぎます。そこから先を――」
その先を言わず、ガウェインは前進する。否、言えなかったのだ。
ここを凌いだところで、どうするというのか。もはや打てる手はないのに。
「ガウェインっ……!」
迫り来る火球と刃を、ガウェインは聖剣と封印の剣を交差させて叩き落としていく。
その剣技はまさしく、彼の友であるランスロットが見せたもの。太陽の騎士は親友との戦いの中で、二刀を扱う彼の武技を己に刻みつけていた。
炎は龍騎となったギルガメッシュに効果が薄い――ならば、それはガウェインにも同じことが言える。
斬り割った火球が至近距離で爆発しても意に介さず、ガウェインはひたすらに前進し続ける。
「おおおおおぉぉぉっ……!」
「健気なものよな。良かろう、一思いに踏み潰してやろうではないか」
嘲るようにギルガメッシュが速度を上げる。
宝具の迎撃に気を取られたガウェインは、その疾走に対応できない。
「ガウェインさんっ!」
オーズがガウェインの前に飛び込んだ。バズーカモードのメダガブリューを使うもう一つの技、ストレインドゥームをドラグランザーの鼻先に撃ち放つ。
斬撃を繰り出すグランド・オブ・レイジに対して、ストレインドゥームは衝撃波として放つ。
だが――弱い。グランド・オブ・レイジに注ぎ込んだ力が大きすぎた。本来の半分の威力も再現出来ていない。
当然、ドラグランザーの疾走は止まらなかった。オーズの放った衝撃波はあっさりと吹き散らされる。
だがオーズも諦めない。全力で冷気のブレスを放射し、少しでもドラグランザーの勢いを殺そうとする。
ドラグランザーが生む熱量はドラグレッダーの比ではなく、先ほどは何とか相殺できたが、今度は押し込まれる。
やがて限界に達したオーズが弾き飛ばされる。大地に叩き付けられたオーズのベルトからメダルが排出され、変身が強制的に排除された。
「感謝します、ライダー…!」
だが――それで十分。ドラグランザーの速度は確かに減少した。ガウェインはその機を見逃さない。
機を見定めたガウェインがガラティーンを放り投げ、封印の剣を両手で握る。ガウェインの魔力を込められた封印の剣は炎を纏い、ドラグランザーの機首へと突き込まれた。
しかし、拮抗しない。ガウェインが踏ん張った両足が地面を削り、徐々に後退させられる。
最も力の集中しているドラグランザーの頭部、突進の勢い、そしてギルガメッシュ自身の力。あらゆる条件がセイバーの時とは違いすぎる。
「その剣は我の蔵にもないものだ。さて、どこまで保つか見せてみるがいい」
楽しげなギルガメッシュとは逆に、ガウェインは死力を振り絞る。それでも、届かない。封印の剣の効果で何とかドラグランザーの疾走を押し留めているものの……封印までには至らない。
そして封印の剣に細かいヒビが走っていく。激戦に次ぐ激戦、そして巨大な力のぶつかり合い。
マスターの宝具として顕現した封印の剣では、超級のサーヴァントたちの戦いに、最後まで付いて行くことができないのだ。
「っ……」
やがて、剣は砕け散った。同時にガウェインも崩れ落ちる。
致命傷は負っていないが、魔力を放出し尽くしたその姿はもう、敗残兵そのものだ。
「中々楽しめたぞ、キャメロットの騎士」
だが、龍騎サバイブのファイナルベントを凌ぎ切った。
ギルガメッシュが褒美とばかりにバイクを降りて、剣を片手にガウェインへと歩み寄る。
時間がないと見た映司が立ち上がり、もう一度変身しようとメダルを取り出す。が、過度に魔力を消費した体は自由にならず、メダルを取り落としてしまう。
「ガウェイン!」
「くっ、アレックス!」
ルルーシュがガウェインへと魔力を供給し、陽介が疾風魔法を使ってガウェインの背を押す。
ギルガメッシュがそんなマスターたちを見て嘲笑する。状況は好転せず、ただ審判の時を先延ばしにするだけだ。
そんな中、こなたは転がってきたメダルを拾う。
「……映司さん」
そのメダルの色は赤。そして――ひび割れている。
以前聞いた、映司の相棒の命が入っていたメダルだ。
「このメダルを、使うの?」
映司にとっては、特別なコアメダル。
魔力を消耗した今のオーズでも、このメダル自体が魔力を供給してくれるため問題なく使用できる。
そして……一度きりしか使えないと、映司は言った。
「……こなたちゃん」
「ううん、わかるよ。きっとここが選ぶ場面。本当にギリギリの場所なんだってことだよね。
映司さんが大切にしてたメダルを使わなきゃいけないくらいの状況なんだって」
これを使うのは、オーズが力を失うことを覚悟した上でのこと。
そう理解しているからこそ、こなたも覚悟を決めることができる。
「こなたちゃん…俺に力を貸してほしい。みんなが、生きて帰るために」
「いいよ。だって私たち、相棒だからね!」
あっさりとこなたは言う。結果次第で死ぬかもしれないのに、微塵の躊躇いもなく。
これほどの信頼を裏切ることは、映司にはできない。
「今日も、明日も生きていくために、今戦わなきゃいけない。生きることは戦うことだって誰かが言ってたけど、今なら私にもわかる気がする。
戦わないと生き残れない…でも私、死ぬつもりなんてないから。勝って……生きて帰るよ! そのために戦うんだ!」
こなたは力強く言い切る。絶望に負けない強い意志が、その瞳には確かにある。
だからこそ、映司も覚悟を決められる。
たとえこの一撃で己が砕け散ってしまうとしても――この優しいマスターだけは、なんとしても。
「力が欲しい、アンク……俺に、みんなを守れる力をくれ!」
――タカ!
――クジャク!
――コンドル!
もはや懐かしい、相棒の声が聞こえた気がする。映司は笑い、最後の変身を成し遂げた。
龍騎と同じ、いやそれ以上の熱さ――炎。かつてないほどの力が沸き上がってくるのを感じる。
映司はそれを、アンクとこなたが側にいるからだと確信する。
タジャドルコンボに変身したオーズの胸から、七枚の恐竜メダルが飛び出てきて、オーズの左腕にあるタジャスピナーへとセットされた。
七枚の恐竜メダルから生み出される膨大なエネルギーがタジャスピナーの中で循環・増幅し、巨大な力へと練り上げられていく。
恐竜メダルを一発きりの弾丸として放つ――形は違えど、これもブロークン・ファンタズム。
異変を察したルルーシュが陽介に指示し、ガウェインを風で吹き飛ばす。ギルガメッシュが、オーズが生み出すエネルギーの奔流を見て笑う。
「ほう、それが貴様の切り札か、欲望の王。いいぞ、そうでなくてはな!」
「オオオオオオオオオオオオオオオォォォォォッ――――!!!!」
そして、オーズの最後の技が発動した。
ロストブレイズ――失われた炎が、もう一度オーズの、映司の力となる。
映司の力と、アンクのメダルと、こなたの思い。すべてを巻き込み、一つの巨大な渦になる。
「ぶ、ブラックホール……!」
「ほう、まだ足掻くか。楽しませてくれる」
目前の現象がどれほど凄まじいか、ルルーシュとて理解しきれない。確かなのは、ギルガメッシュが怯むことなくオーズへと向かっていくということだけだ。
オーズが威を振るうなら、受け止め、正面から打ち砕いてこそ、真の王とでも言うように。
ギルガメッシュは変身を解く。そして虚空より三軸の刀身を持つ奇妙な剣を手にし、相克渦動するエネルギーの中心――オーズの元へと突入していく。
「これを見せるつもりはなかったのだがな。しかしこういう趣向とあっては、我も本気を出すに吝かではない。
さあ、咆えろ――エア!」
それは、世界を切り裂いた剣。
あらゆる宝具の原典を所有するギルガメッシュただ一人だけが持つ――神話の神の名を冠した、ギルガメッシュの真の宝具。
三層のからなる力場を回転させ、空間そのものを斬り裂く対界宝具。騎士王のエクスカリバーすらも凌駕する、本来存在してはならない禁断の力。
オーズの生み出したブラックホールすらも呑み込む、最強にして無尽の破壊がもたらされる。
「原初を語る。元素は混ざり、固まり…万象織りなす星を生む!
フハハハハハハ! 死して拝せよ! エヌマ――
――――――――――――ぐっ!」
「天地乖離す開闢の星」――乖離剣エアの真名が解放されれば、この場にいるギルガメッシュ以外の全てが消し飛んだだろう。
だがそうはならなかった。乖離剣を構えるギルガメッシュの腕を、一筋の閃光が射抜いたからだ。
ギルガメッシュの腕を射抜いたのはオーズでも、ガウェインでもない。
「雑種、どもが――!?」
ギルガメッシュが早々に無力と判断し、捨て置いたマスターたち。彼らがやってのけたのだ。
束ねた力を一つにして放つ――あらゆる防御を突き抜け、対象へと確実に着弾する、至高の魔弾。
衛宮切嗣が遺した弾丸。名無鉄之介が遺した槍王イルバーン。鳴上悠が遺したペルソナの力。自分たちだけではない、陽介たちが築き上げてきた絆の具現が、古の英雄王に確かに傷をつけた。
「映司さんっ!!」
こなたが叫ぶ。
至高の魔弾によって真名解放を妨げられた乖離剣は、予定されていた破壊を引き起こさない。
一瞬の停滞は致命的なズレとなる。宝具は不発――ギルガメッシュは、膨れ上がったブラックホールを前に微動だにできない。
ゲート・オブ・バビロンを使うも、射出した端からブラックホールへと吸い込まれてしまう。
自らの敗北を悟った英雄王は目を見開く。
「そうか、これがゼロの求めていた――」
そしておそらく、ギルガメッシュ自身も求めていたもの。
この結果は必然などではなかった。彼らは数時間前までは、ギルガメッシュに圧倒され逃げ惑うだけの弱者だった。
しかし、今。彼らはギルガメッシュを超える。
ほんの僅かな時間で見違えるほどに成長して。徹底的に叩き潰しても、何度でも立ち上がる。
人を試す王を――見守り、時には裁き、決して甘えさせない孤高の王の試練を、超える。
人の可能性。成長の証。厳しい試練の果てに得た無二の宝。それをこの目で見られた。
「――行くがいい、雑種ども。ここから先は、お前たちの道だ」
烈火龍が何とか脱出しようとするが、英雄王が射出した宝剣に頭を刺し貫かれ、一足先に消える。
直後にギルガメッシュの体は暗黒の穴に呑み込まれ、重力の井戸の底へ沈んでいく。
だが、悔いはない。
古の英雄王は――静かに舞台を降りた。
◇ ◆ ◇
「今度こそ……やった、のか……?」
呆然と、ルルーシュが呟く。ギルガメッシュはブラックホールに呑まれ、消えた。
ブラックホールはギルガメッシュという巨大な力を呑み込み、ワームホールと化して今も膨張し続けている。
オーズがロストブレイズを解き放つ瞬間、彼らは精神世界で手に入れた力――ミックスレイド・至高の魔弾を放っていた。
ギルガメッシュにはロストブレイズすらも凌駕する力があるかも知れない。ならば、その発動を邪魔してやることだけが、こなたたちが勝利するたった一つの方法だった。
ギルガメッシュが最後に放とうとした宝具は、おそらく彼をしてなお、全力の集中を要するものだったのだろう。
でなければいかにサーヴァントにも通じるとはいえ、こなたたちの攻撃を許すとは思えない。
「――見事だ。これは本当に、予想外の結末だった」
サーヴァントを失った神父のNPCは、満面に笑みを浮かべてこなたたちに賛辞を送る。
陽介が構えようとするものの、綺礼にはもはや戦闘の意思はなく、両手を軽く掲げる。その手先が黒く染まる――NPCといえども、敗者の運命からは逃れられない。
「何故、俺たちを阻まなかった? お前なら、やろうと思えば横槍を入れられたかもしれんだろう」
「勝つことが私の――私たちの目的ではないのでな。とはいえ、手を抜いたわけではない。あれだけの力が放出されている中で動くことなどできんさ」
嘯く神父が本気かどうか定かではないが、それこそサーヴァントか至高の魔弾レベルの力でもない限りは、あのブラックホールの影響を受けて身動きが取れなかったのは不思議ではない。
マスターもサーヴァントも、力を出し尽くした末に掴んだ勝利だ。誰もが地面に腰を下ろし、立ち上がれずにいる。
「ガウェイン、無事か」
「ルルーシュ…さすがに、堪えましたね…」
封印の剣を砕かれ、ファイナルベントを受け止めたガウェインは全身に傷を負っている。しかし、ガウェインは健在だった。
紫色のメダルを弾丸に、最後の一撃を放った映司とは――違う。
「映司…さん」
「こなたちゃん……」
オーズはただでさえプトティラコンボでギルガメッシュと死闘を繰り広げ、さらにタジャドルコンボで恐竜メダル七枚のロストブレイズを放ったのだ。
特に英雄王すら葬り去るほどの一撃を放った代償は大きい。ギルガメッシュがあの時解放しようとしていた宝具を止めるには、それ以上の出力で、ロストブレイズを叩き込むしかなかった。
その結果、英雄王は虚空の彼方に消え――
「火野!」
「え、映司さん、あんた……」
ライダー――火野映司もまた、限界を超えてしまっていた。
変身は解け、こぼれ落ちたメダルも全て砂と消えていく。
「あはは…ごめんね、陽介くん、ルルーシュくん。絶対に死なないって言ってみたけど…そううまくはいかなかったみたい」
映司が死ぬということは、つまりこなたも死ぬということ。
死の恐怖に身を浸しながら、それでもこなたはいつもそうであるように、二人の仲間に笑いかけてみせた。
本当はみっともなく泣き喚いて、もっと生きたいと叫びたいのをぐっと堪えて。そうしなければ、陽介たちが前に進めないと知っているから。
「でもさ、あんな強いやつ倒したんだから、これはもう私たちの勝ちだよね。後はスタッフロールだけっていうか」
「泉……待て、まだ諦めるな! 何か方法があるはずだ!」
「アレックス! 火野さんを治すんだ!」
しかし、誰よりもこなたと映司の死を認めないのは、他ならない陽介とルルーシュだった。
陽介が映司へと回復魔法を連発し、ルルーシュもこなたから強引に取り上げた礼装で続く。
しかし――映司、そしてこなたも既に魔力が枯渇している。傷を癒やそうにも、情報が消去されていくほうが早い。
消去速度を遅らせることはできても、根本的な解決にはならない。
「くっそ……どうにかならねえのかよ、ルルーシュ! このまま泉を死なせていいわけねえだろ、」
「わかっている! 俺だってもう仲間が死ぬのを認める気はない! だが、どうすれば……!」
ふと、陽介はこの場にいるもう一人に意識を向ける。
陽介でもルルーシュでもこなたでもない――言峰綺礼。この戦いの始まりを告げたムーンセルのNPC。
陽介たち参加者側ではない、運営側の構成要素。
「なあ、あんた! もしかしてあんたなら何とか出来るんじゃねーのか!?」
藁にもすがる思いで、陽介は綺礼へと問いかけた。
ルルーシュは何を言っているんだこいつは、という目で陽介を見たが、考えてみればその方法が一番可能性がありそうだと思い直す。
「神父よ、一つ疑問がある。貴様とあのギルガメッシュの参戦は、聖杯戦争に元々ありえた要素か?」
「いいや、違う。私も奴もイレギュラー…飛び入り参加のようなものだ」
「ならば俺たちは、本来ならばする必要のない、無駄な戦いをした。そういうことで間違いはないな?」
「ふむ……まあその通りだ。この参戦は我らの気まぐれ故のものだからな」
ならば、とルルーシュは畳み掛ける。
「イレギュラーに対処した相応の見返りがあってしかるべきだろう! 泉は本来ここで死ぬことはない!
お前たち運営側のNPCが本当に聖杯戦争の管理を司っているのなら、正しい結果を歪めてはならないはずだ!」
「そうだ、バイトしたらその分の給料もらえるのが社会ってもんだ! 少しくらい埋め合わせをしろよな!」
二人の少年が轟々とまくし立てる。必死になって、こなたを救う術を模索してくれている。
こなたの頬を、恐怖からではない涙が、一滴、流れる。
「俺たちは、いい友達に会えたね。こなたちゃん」
「……うん。もちろん、映司さんもだよ!」
こなたと映司は笑い合う。数日間の付き合いであっても、ここまで互いを思い合うことができる――それはとても幸せなことだから。
ルルーシュと陽介に押し切られた――という訳でもないだろうが、神父のNPCは一本、指を立てる。
「一つ、手立てがないでもない」
「本当か、おっさん!?」
「もちろんだとも。それは――他ならない君自身だよ、花村陽介」
綺礼は立てた指を陽介に向けて倒す。
そして指を滑らせる。その先には陽介のペルソナ/サーヴァントのアレックスが佇んでいる。
「君は既に一度やってみせただろう。サーヴァントの情報を分解し、自身のペルソナとして再構成する――システムにない、奇跡というやつを」
「あ、あれか…でもあれは、賢者の石があったからできたことだろ?」
「あるではないか。賢者の石に匹敵する宝具が、そこに」
綺礼が示したのは、映司の手にたった一つ残った、ひび割れたコアメダル。かつてアンクの魂が宿っていた、たった一枚の特別なメダルだ。
メダルに人格を宿せることはアンクが実証している。賢者の石の代替として使うのならば、十分すぎる。
「でも、泉はペルソナ使いじゃないぜ。どうやって火野さんをペルソナ化させるんだよ?」
「……違う、花村。ペルソナ化させるんじゃない。そのメダルを、火野映司としてムーンセルに認識させる――つまりこういうことだろう」
ルルーシュが導き出した答えに、綺礼は満足気に頷く。
サーヴァントを失ったマスターはムーンセルにより失格と判定され、消去される。
ならば「サーヴァントが肉体を失ってもそこにまだ存在している」とシステムを欺瞞できれば、消去は免れる。
まさに陽介自身が今も証明し続けていることだ。
(それに、ゼロが求めている魂はたった一つ。私の目から見ても、この三者のうち誰もがその資格を満たしていると判断する。ならば二人は不要だ)
綺礼は、これは声に出さなかった。
仮に火野映司の人格をメダルに宿すことができたとしても、残るのはサーヴァントを持たない少女が一人だけ。
それではつまらない。言峰綺礼は魔王ゼロに協力しているとはいえ、ゼロの配下ではないのだ。
魔王の元へ辿り着き、さらなる物語を紡げる者。それはもう一人に確定している。
魔王ゼロと最も近しく、そして遠い者――この演劇の幕を下ろす者は、魔王ゼロとその者を置いて他にない。
「さあ、どうする? 泉こなたを救うというなら協力しよう。英雄王を倒したのだ、それくらいの褒章は与えられるべきだからな」
「……泉。映司さん。いいよな?」
「こっちからお願いしたいくらいだよ、陽介くん。それでこなたちゃんを助けられるなら」
「陽介くん、ルルーシュくん……ありがとう」
こうして、綺礼の協力を得て陽介は映司の魂をメダルに移し替える作業を行った。これにはルルーシュは手が出せない。
「まさか俺がアンクと同じ姿になるなんて、思っても見なかったな……」
魂の改竄は綺礼のおかげで滞りなく済んだ。映司の魂はメダルへと移行し、こなたも消滅から免れる。
「おっと、時間のようだな」
そしてついに、綺礼も消滅の時を迎える。上級NPCだからか、意外なほどに長く存在し続けていたが、やはり限界はあったようだ。
綺礼は頭上に今も広がり続けるワームホールを見る。
おそらくゼロは今、このワームホールを何とか収めようと奔走していることだろう。
なにせ解放直前の英雄王の宝具を呑み込んだのだ。生半可な干渉で打ち消せるものではないはず。
そして、ゼロの手が取られている今、この瞬間ならば。
「このワームホールを通れば、おそらくムーンセルの外側に出られるだろう」
綺礼が何気なく告げた真実は、皆を驚愕させるに足るものだった。
聖杯を破壊する――目的こそ一貫していれども、その後どうするかは全く定まっていなかったのだから。
「外側に出る……現実の世界に帰れるってこと!?」
「そうだ。これほどの規模のワームホールならば、出口は確実にムーンセルの外に繋がっている。サーヴァントに守られているならば、あの空間の中でも消え去ることはないだろう。
そして外に出た後は、魂は肉体のある次元へと自然に引っ張られるはずだ。一度ムーンセルの支配を脱してしまえば、我々もそれ以上追うことはできない」
「おいおい、それって……やったじゃんルルーシュ! 帰れるんだってよ!」
こなたと陽介は喜ぶが、それほど元の世界に未練のないルルーシュには一つやり残した仕事がある。
それを完遂しない限り、いつかまたこのような戦いに引き戻される可能性はゼロではない。
「泉、花村。お前たちは帰れ……自分の世界に」
「え? ルルーシュくんは帰らないの?」
「俺は、聖杯を破壊する。最初からそのつもりだったからな」
そしてピースマンの語った、ムーンセルを歪めたすべての黒幕。ルルーシュはそいつと対峙しなければならない。
サーヴァントを失ったこなたと陽介を付き合わせる気はない。
どのみちギルガメッシュとの戦いで消耗しきった彼らでは、いてもいなくてもそれほど変化はないのだ。
ならば――彼らだけでも生き延びてくれる確証が得られたほうが、ルルーシュは心置きなく最後の決戦に臨める。
それで勝てるかどうかはわからない。いや、勝つためにはむしろ絶対に仲間の力が必要だ。
しかし。
「なら、俺も行くぜ。お前だけにいいカッコはさせないからな!」
「陽介くん……それじゃ、私も」
「いや、泉はダメだって! もう映司さんだって戦えないんだし、ここで帰った方がいいって!」
こなたを説得にかかる陽介を見て、ルルーシュはある決意を固める。
やはり、この二人が死んでいいはずがない。抜けられるのなら抜けるべきだ。この狂った世界から。
ガウェインを見る。彼は、目を伏せ頷いた。それがいい、と。
覚悟を決める。二度と使わないと決めた力――だが、今は。
「花村」
「おいルルーシュ、お前からも言ってやれよ。泉はここで――」
しっかりと、視線を合わせる。
ルルーシュの瞳が輝く。
「花村、お前は帰れ。自分のいるべき場所へ」
放たれたのは、絶対遵守の命令。
命令したのは、花村陽介。
人の意志を歪め、弄ぶ卑劣な力――ギアスを、ルルーシュは陽介へと使った。
「ルルーシュくん、何してるの!?」
「ここから先は俺とガウェインだけでいい。お前にも花村にも、帰りを待つ人がいるだろう」
動きを止めた陽介の瞳が、凄まじい早さで動いている。ペルソナ使いである陽介には、ギアスの効き目が薄いのかもしれない。
ガウェインに指示し、陽介を担ぎ上げさせる。ガウェインはそのまま、もう片方の手にこなたを抱えた。
「ガウェインさん!」
「ここまで我が王に付き添っていただき、ありがとうございました。ミス・泉。そしてライダー。花村殿とランサーにも、どうかよろしくお伝え下さい」
「一人でなんて無茶だよ!」
「いや……俺の勘だが、おそらく一人でなければ意味が無いんだ。この聖杯戦争を起こした奴は、たった一人の勝者を求めている。
どうなるにせよ、もう戦えるサーヴァントを連れているのは俺だけだ。だから俺が行く――」
「……っざけんなよ、ルルーシュ! ……置いてかれるのなんて……ごめんだ!」
ギアスに抵抗しているのか、陽介の言葉は絶え絶えだ。
彼は心の底からルルーシュを案じている。こなたも同様だろう。
だが、だからこそ――
「泉、花村。お前たちのお陰で、俺は生きる意思を捨てずにここまで来られた。
感謝している…本当に。だから今度は、俺に、お前たちを守らせてくれ」
後ろに陽介とこなたの存在を感じることで、絶対に負けられないと己を奮い立たせる。
二人を人質にして、最後の一人になる。それが、ルルーシュの選んだこの聖杯戦争の結末。
「ガウェイン」
主の命を受け、ガウェインが二人をワームホールの中へと放り投げる。
その体が消える寸前、
「ルルーシュ! てめえ、今度会ったときに、絶対、絶対――ぶん殴ってやっからな!」
「ルルーシュくん、死なないで! 約束だよ! きっと、もう一度――!」
二人が何かをルルーシュに投げる。それは二人がそれぞれ持っていた物。
契約者の鍵と、各種の礼装。もういない二人の、最後の残り香。
やがてワームホールは収縮していく。今飛び込めばナナリーのいる世界に戻れる――が、ルルーシュはそうしなかった。
陽介とこなたから託された道具を強く握り締め、ルルーシュは神父へと向き直る。
「この後はどうすればいい」
「ふ…心配せずとも、すぐに迎えが来る。そうだ、これも持っていけ」
綺礼はそう言って、残っていた自らの令呪をルルーシュへと分け与えた。
「何故、ここまで俺に肩入れする?」
「フフ…なに、この先でそれがきっと必要になる。無駄に捨てるよりは、と思っただけだ。
ああ――だが、君を前にした時の彼を観察できないのは…残念といえば残念だ…な」
神父のNPCも、消えた。夜の橋に、残ったのはルルーシュとガウェインだけ。
三日間に及ぶ聖杯戦争の果て、残ったのは――ルルーシュとガウェイン、この主従だけだ。
「……ついに、俺たちだけか」
「ですがルルーシュ。我ら二人きり、ではありません」
笑みを浮かべながら言うガウェインに、そうだな、と頷きを返す。ここに来るまで、ルルーシュはたくさんの出会いと別れを経験した。
全てを鮮明に思い出せる。敵であれ、味方であれ、誰もが懸命に願いを叶えようと戦っていた。彼らの存在は、強くルルーシュの中に刻まれている。
その願いを弄ぶ者――全ての元凶を、排除する。
それをもって、ルルーシュの二度目の生は幕を閉じるだろう。
「……! これは」
佇んでいたルルーシュとガウェインを残し、冬木大橋が――否、冬木市そのものが解体されていく。
聖杯戦争が終結したためもはや冬木市を維持する必要もないためだろう。
どこまでも暗く先が見えない奈落を落ちていく。
やがてその底に、黒よりも暗い仮面を見つける。
ルルーシュにはその仮面に馴染みがある――当たり前だ、自分も身に付けていた物なのだから。
足が地面につき、仮面を拾おうと一歩踏み出したところで、
「まさか……お前が残るとはな。神父の干渉の結果か……。
だが、いい。お前になら資格はある……他でもない、この私が誰よりもそれを知っている……」
仮面が、喋った。
影が盛り上がり仮面に吸い込まれ、人の形を成していく。
かつて奇跡を起こす男と呼ばれ、世界を革命し――そして、ルルーシュ自身を終わらせたはずの記号。
ルルーシュは、驚愕と共にその名を口にする。
「貴様は……ゼロ……!?」
「そうだ。我が名は魔王ゼロ。歓迎するぞ、もう一人の私。
そしてようこそ、我が後継者――新しき魔王の器よ」
たどり着いた、終端の果て。
盤面に残った駒は、キングとキング、ただ二人。
ゼロとゼロは邂逅し。そして最後のTURNが始まる。
これは、終わりに向かう物語――。
&color(blue){【花村陽介@ペルソナ4 生還】}
&color(blue){【泉こなた@らき☆すた 生還】}
&color(blue){【ライダー(火野映司)@仮面ライダーOOO/オーズ 生還】}
&color(red){【言峰綺礼@Fate/extra 消滅】}
&color(red){【ギルガメッシュ@Fate/extra CCC 消滅】}
【月の裏側/???】
【ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア@コードギアス反逆のルルーシュ】
[令呪]:3画
[状態]:魔力消費(大)
[装備]:槍王イルバーン@私の救世主さま、鳳凰のマフラー、聖者のモノクル、遠見の水晶玉@Fate/EXTRA
[道具]:契約者の鍵@ペルソナ4
※槍王イルバーン、他礼装を装備することで、コードキャストを発動できます。
hadron(R2) 両眼から放つ魔力砲。収束・拡散発射が可能。 効果:ダメージ+スタン。
絶対守護領域 決着術式“聖剣集う絢爛の城”をデチューンした術式。 効果:小ダメージを無効化。
heal(16) 効果:HPを小回復
view_status() 効果: 敵対者の情報を表示
view_map() 効果:アリーナの階層データを全表示
【セイバー(ガウェイン)@Fate/extra】
[状態]:ダメージ(大)、魔力消費(極大)
※『聖者の数字』発動不可
【魔王ゼロ@コードギアス ナイトメア・オブ・ナナリー】
----
日は落ちた。三度目の夜。
紛れもなくこれが最後の夜であると、誰もが確信している。
時は、午前零時。
暗闇の中にあってなお、太陽の如き輝きを放つ一人の男――名をギルガメッシュ。
金の髪、赤い瞳、黄金の鎧。只人が見れば無意識に頭を垂れる、圧倒的な存在感を放っている。
彼こそは人の歴史に燦然と名を刻む、万夫不当の英雄王だ。
そしてその側には、英雄王とは対照的に漆黒の礼服に身を包む長身痩躯の男が一人。
言峰綺礼。神父のNPCにして、ギルガメッシュのマスターとしてこの聖杯戦争に参戦したイレギュラー要素である。
彼らは、敵を待っている。
もうすぐここに――西と東の街を結ぶ冬木市の要所、冬木大橋へと、敵がやってくる。
「英雄王よ、一つ質問がある」
綺礼の問いに、ギルガメッシュは目線で先を促す。
この決戦の地に着いて、ギルガメッシュはただの一言も発していない。
緊張している……という訳ではない。その視線は遥か彼方、これより雌雄を決する人間たちの来訪を待ち受けている。。
「何故、この場所を選んだのか、ということだ。お前に戦場の有利不利などないのだろうが、ゼロに依頼してまでここに拘った理由があるのか?」
「ふ……ん。大した理由ではない」
ギルガメッシュの目線は言峰から天へと巡る。
否、彼が見ているものは空ではない。過去の情景を思い出すように、ギルガメッシュは浅く瞼を下ろす。
「いつか、どこか、までは覚えておらんが。このような場所で、我は賊を裁いた記憶がある。
奴は、正しく英雄であった。この俺が手ずから誅する価値のある、な」
「ほう……英雄王にそこまで言わせるとはな。よほど名のあるサーヴァントだったか」
「我とは違う王道を掲げた益荒男だ。奴の覇道は、あれはあれで見応えのあるものだった」
昔を懐かしむように、ギルガメッシュは述懐する。
豪放磊落を地で行く真の英雄との、譲れぬ王道と掲げた誇りをぶつけあった一戦。
長き眠りと倦怠の中にあって、あの鮮烈な記憶は未だ忘却の海に沈んではいない。
「ではここを選んだのは、これからやって来る彼らが、その英雄某に比肩し得ると見定めたから、か」
「さてな。此度は王と王の戦いではない……そこまでの期待はしてはおらん」
ただ、と英雄王は付け加える。
「この橋を戦場とするなら、余計な小細工が入る余地はない。ただ前進し、ただ敵を粉砕する。
勝ち残った、より強い者だけがこの橋を渡り切ることができる。明快であろう?」
そう語るギルガメッシュの眼には、隠し切れない喜悦と戦意が入り交じっている。
拳王、狂王、騎士王、紅世の王、不死者、破壊者、抜剣者。仙人、妖狐、円卓の騎士、妖魔狩り、錬金術士。
スタンド使い、エンジェロイド、戦国最強、光の御子。魔法少女、北斗神拳の使い手、ルーンナイト、神話級礼装の防衛プログラム。
散りゆく者は皆、いずれ劣らぬ当千の強者ばかりだった。
「ここまでの顔ぶれを揃えた聖杯戦争は歴史上そうはあるまい。そして奴らは勝ち残ってきた。それが運であれ、実力であれ。結果的に今、生きているということに意味がある。
生を渇望する意思――曇りなき魂。ゼロが求めているものを、奴らは磨き上げ、研ぎ澄ませてきた。
ならばこそ、奴らは我の前に立つ資格がある。我の手で試す価値がある。人の内なる可能性を示す……その行く末を見定めるのが我の仕事である故な」
「裁く……ではなく、試す、か」
「今宵、我は王としてではなく試練として、奴らの前に立ち塞がる。
奴らが我を超えられぬのならば……ゼロもとんだ道化に成り下がるというものよ」
「なるほどな。ゼロに言われただけでなく、お前自身にも彼らと戦う理由があるということか」
得心がいった、と神父は頷く。その姿には気負いも緊張もない。理由というならば、このNPCこそここにいる意味がない。
「何、私も同じだ。彼らがこの戦いでどこまで成長し、そしてどこに辿り着くのか……その果てを見てみたいのだよ」
「異なことを言う。もし敗北すれば見届けるも何もないではないか」
「それはそれで構わんさ。私を……いや、お前を超えるということは、彼らの可能性は人の臨界を極めたという証左。
ゼロが求める次代の魔王も必ずやそこにいるだろう。新たな魔王の誕生を見届けて消えるのなら、何の不満もない」
そう、魔王ゼロもこの戦いを見ている。
ギルガメッシュが打倒され新たな魔王の器が生まれるか。あるいは魔王たるべき者は現れず、ギルガメッシュによって魔王そのものが滅ぼされるか。
魔王が滅びれば、秩序と混沌の天秤は崩れあらゆる宇宙はいずれ緩やかに壊死していくだろう。
ギルガメッシュはそれでも構わない。人が進化の果てに選んだ結末ならば、黙して受け入れるだけだ。
だが――予感がある。期待、と言ってもいい。
それはか細く不確かなもの。しかしそれでも、信じてみたいと思わせる。
「……来たか」
閉じていた瞼を開く。橋の向こう側――遮るものなき前方に、五つの影が現れている。
ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。悪逆皇帝、奇跡を起こす男。
ガウェイン。円卓の騎士、太陽の聖剣を担う者。
泉こなた。力なき幸運の星、天秤の支柱となる少女。
火野映司。欲望の王、古の力を宿す仮面の戦士。
花村陽介。ワイルドカード、受け継がれる絆と力。そして傍らには信念を貫く槍兵のペルソナ。
マスターが三人、サーヴァントが二人。
皆一様に先刻とは比べ物にならない王気を纏い、確かな意志と共にギルガメッシュと対峙している。
誰の眼にも恐怖はない。感じていないのではなく、呑み込んでいる。何の力もない小娘でさえも、英雄王の視線に怯まず睨み返してくる。
「どうやら彼らもただ遊んでいた訳ではないようだな。
特にあの三人……マスターたちは、どうしたことか、保有する魔力が桁違いに増大している」
「それでこそよ。無策で突っ込んでくるようなら踏み潰してやるところだが……ああ、それでこそだ。
我が相手をするのだ。死力を超えた全力を以って挑んでこそ、初めて戦いになるというものよ」
笑み、ギルガメッシュはゆっくりと前進していく。その手には龍を象った匣がある。
もはや言葉など意味を成さない。此処から先に意味があるのは、雌雄を決する力のみ。
戦を前に、この傲岸不遜を形にした男が常ならあり得ない準備をした。
古の竜を迎え撃つは、新たなる龍の力。鎧を脱ぎ捨て、宝物庫から呼び出した鏡へと、匣を掲げる。
炎が巻き起こる。瞳と同じ、鮮烈な赤。
「――変身」
顕現するは龍の戦士。
英雄王ギルガメッシュが出陣する。
◇ ◆ ◇
最後の時間は何事もなく過ぎた。
精神世界から帰還し、決戦に向けての打ち合わせを終え、休息を取る。
こなたは母親が既に亡くなっていて、父親と従姉妹の三人暮らしのため家事には長けている。こなたと陽介が驚いたのは、ルルーシュもまた料理が達者なことだった。
「うわー、美味しいねこれ。ちょっとした店で食べるくらいのレベルじゃない?」
「そんな大したものじゃない。妹や弟によく作ってやっていただけだ」
「へえ、お前兄弟がいるのか」
どこか懐かしむ口調で言うルルーシュに、彼の作ったカレーを食べながら陽介が答えた。
料理の得意な兄、に親友を連想する。故郷を思う気持ちが一層強くなる。
「じゃあ、絶対帰ってやらないとな。もちろん俺も、泉も」
「……ああ、そうだな」
元の世界に帰ったところで、ルルーシュが妹の前に姿を見せる訳にはいかない。
と言うより、首尾よくギルガメッシュとその背後にいる者を倒せて元の世界に帰還したとしても、ルルーシュにはこなたや陽介のように元の日常に帰るという結末は望めない。
ガウェインはかつて“死の直前にある”とルルーシュを評した。ならば、ムーンセルより解放されれば、その後には本来向かうべき結末――死が待っているだけだ。
ルルーシュはその最期に文句などない。やるべきことをやり遂げたのだから、あとはただ舞台から降りればいいだけだ――だが。
(あいつは…スザクは俺に生きろと言った)
元の世界に戻れば、今もゼロとして活動しているスザクがいる。そのスザクは、この聖杯戦争でルルーシュが看取ったスザクとは別人だ。
故に、その言葉に従う必要はない。
ないのだが――本当に、それでいいのかと思う部分もある。
今更死を恐れてはいない。しかし、もし元の世界に戻った後に俺は死ぬ、などと言えば、陽介もこなたもきっと迷ってしまうだろう。
言わないでいる、あるいは嘘をつくことは簡単だ。今までにも散々やってきた。
しかしルルーシュは、運命共同体となった二人の友を偽ることに強い躊躇いを覚えている。
(生きろ…か。難しい注文だな、スザク。俺がお前に課した命令は、こうも重いものだったと今更ながらに思い知るよ)
仮に生きて元の世界に戻った場合どうなるだろうか。
こなたは、今までと変わらぬ日常を送るだろう。彼女は元々日向の世界にいる人間だ。
陽介は、鳴上悠の死を親しい者に注げると言った。辛い役目だが、それをしなければあの冬の日から一歩も前に進めないのだと。
ではルルーシュはどうするか。
最愛の妹であるナナリーの前に姿を見せる訳にはいかない。ルルーシュは世界の憎しみを集めて死んだのだから、世界に無用な混乱を招くことになる。
無論、ゼロとして活動するスザクや、カレンといった縁者も同様。かつてのルルーシュを知る人間には全て、出会ってはいけない。
結局、残るのはあの魔女くらいだ。
(そう言えば、あいつはどうしているだろうな。願いを叶えてはやれなかったが…)
ルルーシュが世界を変えるきっかけになった、ギアスを与える魔女。今も一人で世界を彷徨っているのだろうか。
もしスザクの言葉を守って生き続けるとするなら、彼女と一緒に生きるのも悪くない。
(…未練だな。すべて捨てたと思っていたが、そう簡単に忘れられるものでもないらしい)
それはこの戦いで得たものも同じだ。友を得ることなど、スザク以外にはないだろうと思っていた。
しかし今、ルルーシュの周りには友がいる。彼らだけはなんとしても元の世界に送り届けてやりたい……今はそれが一番望みであることは間違いない。
ガウェインを見る。騎士は、口に出さずともルルーシュの思いを汲み取ってくれる。
(そう、ギルガメッシュを討つのは俺たちだ。その結果俺たちが果ててしまおうとも…泉と花村が先に進めるのなら、悔いはない)
仮面を被る。秘めた願いを見透かされないように。
最後の夜は更けていく。
◇ ◆ ◇
「あれは……たしか、ディケイドが変身していた……」
「うん、仮面ライダー龍騎だ」
日付が変わる時刻。決戦の場、未遠川に架かる冬木大橋に赴いた一行を出迎えたのは英雄王と神父のNPC。
書状にはこの二人が相手になると書かれていたので驚きはない。何故NPCが、という問いも、その向こうにムーンセルを支配する黒幕がいるのなら不思議ではないからだ。
問題は、黄金の鎧を纏っていた英雄王がその姿を変えたことだ。
仮面ライダーディケイド、仮面ライダーオーズ。二人の「ライダー」に準ずる、三人目の「仮面ライダー」に。
宙を泳ぐ赤龍が吐き出す炎が、数百メートルの距離を隔ててなおマスターたちの肌をチリチリと焦がす。
「全部のパラメータがBクラス以上!?」
「あらゆる財宝を所有する、英雄王の宝物庫…まさか、仮面ライダーの変身道具まで収めているというのか…!」
開戦した瞬間、ルルーシュたちの目論見は早くも瓦解した。
強大な戦力を次々と投射する英雄王を打倒するには、何らかの手段でガウェインとの接近戦に持ち込むしかない。それが、ルルーシュたちの狙いだった。
至近距離で切り札たるエクスカリバー・ガラティーンの全力を叩き込めば、いかな英雄王とて必ずや打ち砕ける。
問題は、どうやって聖剣の間合いまでガウェインを踏み込ませるか――だったのだが。
「ガウェイン、やれるか?」
「いえ……難しいでしょう。私の宝具もルルーシュのコードキャストも、基本属性は火です。今の英雄王には、効果が半減すると見て間違いない」
エクスカリバー・ガラティーンは太陽の灼熱で敵を焼き尽くす宝具、そして決闘術式「聖剣集う絢爛の城」は、炎の壁で相手を覆い自由を奪う術式だ。
どちらも燃え盛る炎熱を力とする。ゆえに、炎を司る仮面ライダーである龍騎に対しては、スペック通りの効果が見込めない可能性が非常に高い。
「で、でもよ。火野さんと同じ姿になったってことは、あの剣を飛ばす攻撃はできない訳だろ? じゃあ手数で俺たちが勝てるんじゃ」
陽介の発言は、ギルガメッシュ=龍騎が後背に出現させた無数の刀剣によって遮られる。
仮面ライダーに変身していようと関係なく、英雄王の基本戦術は健在だ。本人を強化しつつ、さらに宝物も自在に操る。これでは数で優っていても何のアドバンテージもない。
「……来ます!」
綺羅星の如き宝具の数々が、流星となって射出される。
その上方には、王の支配下に置かれたドラグレッダーが炎をまき散らしまっすぐに向かってくる。
本体たるギルガメッシュもまた、どこからか飛来した剣を手に悠々と歩き出す。
三面からの同時侵攻。迷っている時間はない。
ガウェインが迎撃に飛び出す。続こうとした映司は、こなたが引っ張って止めた。
「……映司さん、あれを使おう!」
こなたが言うと同時に、映司の胸から三枚のメダルが飛び出してくる。色は紫……この聖杯戦争では一度も使っていない、恐竜系等のメダルだ。
本来映司の自由意志では使えないこのメダルが飛び出してきたということはすなわち、この状況が絶対的な危機であるということを意味する。
そして――。
「これは……そうか、こなたちゃんから供給される魔力がすごく増えたから……!」
火野映司――仮面ライダーオーズのマスターである泉こなたは、ウィザードとして飛躍的に成長した。故に本来は制御できない恐竜メダルを、こうして自らの意志で取り出すことができる。
今のこなたは、消耗の激しいプトティラコンボを用いるに足る十分な魔力を保有している。映司がコンボの制御に気を回さずとも問題ない――つまりは消耗を気にせず全力で戦えるほどの。
かつてディケイドは自身のマスターとこなたを比較して、その未熟ぶりを突いた。
ここに来て、仮面ライダーオーズに初めて全力で、いや全力以上で戦う機会が巡ってきたのだ。
「……いいかい、こなたちゃん?」
「うん。私も一緒に戦うから。だからきっと――きっと大丈夫だよ!」
何の力もない非力なマスター。そんな者はもうどこにもいない。
今ここにいるのは、映司を支え、肩を並べて戦う「相棒」にほかならない。
映司が思い出すのは、かつての相棒の姿だ。似ても似つかないのに、何故か懐かしい気持ちになる――感傷を呑み込み、三枚のメダルを掴み取った。
ベルトに叩き込んだメダルが魔力を循環させ、火野映司の全身を覆う。
緑でも黄色でも白でも青でも赤でもない、本来もう失われたはずの禁断の力。その力が今、必要だ。
かつて見た悪夢を振り払う。マスターたちには傷一つつけさせないという、固い決意とともに。
「変身!」
仮面ライダーオーズが有する最強の宝具――プトティラコンボ。
力強く翼が広がり、長く伸びた尻尾が大地を打つ。迫り来る刃の嵐と赤龍をじっと見据える。翼が羽ばたき、重力の鎖から解き放たれたオーズが弾丸のように突っ込んでいく。
「――ゥゥゥゥゥウオオオオオオオオオオオオオォォォォッ!!!」」
獣の如き咆哮が放たれる。
ドラグレッダーが吐き出した灼熱のブレスを、オーズが冷気のブレスで以って迎撃した。超高温と極低温が激突し、空気さえも震わせる。
その衝撃は降り注ぐ英雄王の宝具を散り散りに吹き飛ばし、橋の橋脚に次々と突き立たせた。
そして、ガウェインがその只中を疾風のように駆け抜けていく。狙いは英雄王ギルガメッシュの首、ただ一つ。
ギルガメッシュが再度宝物庫を開くが、間に合わない。ガウェインの踏み込みは陽介のペルソナによって強化されている。
音すらも置き去りにする一撃は、しかしギルガメッシュが構えた龍の尾を模した剣に受け止められた。
「英雄王、討ち取らせていただく!」
「音に聞こえたキャメロットの騎士か。ふん、騎士王が倒れた今も剣を置かぬは滑稽よな」
「今の私の主はルルーシュだ……故に! ここは、押し通る!」
ガウェインが気合とともに聖剣を一閃させる。寸前に後退したギルガメッシュの胸元に一筋の傷が刻まれる。
さすがにセイバーと正面から斬り合うのは英雄王といえども荷が重い。セイバーとは接近戦に特化したサーヴァントなのだから。
すかさず追撃しようとしたガウェインだが、後方から迫る気配がそれを許さない。身を翻すと、ドラグレッダーが顎を大きく広げ食らいついてくるところだった。
ガウェインはなんとか回避する。しかし、次は体勢を整えたギルガメッシュの斬撃が来た。
剣を構え直す時間はない。一直線に突き込まれる剣閃――受け止めたのは、飛び込んできたオーズの斧だ。
肉食恐竜の頭を象った意匠の斧が、龍尾の剣と拮抗して火花を散らせる。
「来たか、雑種。貴様の欲望、我が喰らい尽くしてやろう」
「遠慮しときます……よ!」
オーズがギルガメッシュの剣を弾く。だが、ギルガメッシュが接近戦ではガウェインに及ばないように、オーズもまたギルガメッシュには届かない。
閃く幾つもの斬光は目にも止まらない。剣の英霊たるガウェインならば防げただろうが、騎兵であるオーズではそうも行かなかった。
ギルガメッシュもまた神話に名を刻む英霊だ。セイバーには譲るとはいえ、刀剣の扱いは並みの英霊を軽く凌駕する。
援護に入ろうとするガウェインは、再び襲い来るドラグレッダーとバビロンの宝具たちに足止めされた。
プトティラコンボの尻尾――テイルディバイダーを振り回して隙を狙うが、ギルガメッシュは虚空から飛び出てきた剣を片手で掴み、難なく受け止めた。
「やはり竜種には竜種よな。楽しいぞ、雑種!」
余裕すら感じさせるギルガメッシュに、映司は答えられない。
オーズ・プトティラコンボと通常フォームの龍騎なら、パワーはオーズに軍配が上がる。しかしこの場合、装着者に差があった。
変身しなければ人間とさほど変わりがない火野映司と、元から一流の英霊であるギルガメッシュでは、素のスペックに天と地ほどの開きがある。
ギルガメッシュが本来持つ膂力や速度に、龍騎の力が上乗せされた形になるからだ。その結果、ギルガメッシュの能力はオーズに拮抗せずとも近いレベルまで迫っている。
そして、武器の性能差が縮まれば物を言うのは両者の戦闘技術になる。
仮面ライダー龍騎というスタイルに限って言うなら、今のギルガメッシュはオリジナルの龍騎やディケイドをも凌駕しているかもしれなかった。
「それでも、ここは退けないんだ!」
至近距離で冷気のブレスを吐きつける。対抗してギルガメッシュが一挙動でガントレットに叩き込んだカードが新たな力を召喚。オーズの眼前に巨大な盾が現れ、冷気を完全にシャットアウトした。
凍りついた盾をメダガブリューで殴りつけ、粉々に砕く。しかしその向こうにギルガメッシュは既にいない。ギルガメッシュは跳躍し、ドラグレッダーに騎乗していた。
ギルガメッシュはドラグレッダーの頭部を傲岸に踏みつける。龍は暴君の怒りに触れぬよう、直ちにその意図を組んで高く舞い上がる。
「フハハハ……やるな。ここまで勝ち残ったのは伊達ではないか」
ギルガメッシュは一旦引いていく。
何故、と戸惑うも、一呼吸置けることは好都合だ。ガウェインとともに後退し、マスターたちの元へと舞い戻る。
「こなたちゃん、大丈夫?」
「うん、私は平気。映司さんこそ大丈夫?」
「俺も平気。前よりずっと安定して紫のメダルを使えてると思うよ。こなたちゃんのおかげでね」
その言葉は嘘ではない。本来プトティラは長く使えば暴走の危険があるコンボだが、ここまでの戦闘でその兆候はまったく感じられなかった。
こなたから供給される魔力が潤沢なため、映司の精神状態も安定しているからだ。
「とはいえ、お前たち二人がかりでも詰め切れんか。花村、もう一度補助魔法を頼む」
「おう。頼むぜ、アレックス!」
マスターたちはサーヴァントの攻防を見ているしかなかった。
サーヴァントとペルソナの融合体を操る陽介といえども、超級のサーヴァントたちの闘争に割って入ることはできなかった。
ガウェインやオーズが何気なく弾く剣の一本でさえ、陽介が防ぐには重すぎる。ルルーシュやこなたでは言うまでもない。
「あの龍が厄介だな。どうにかして仕留められないか?」
「難しいですね。ギルガメッシュは常に龍の周りに宝具を展開し、護衛させている。まずはあの宝具の防壁を突破しなければ」
「でも、前に戦った時より飛んでくる宝具は減ってる。多分、龍騎を同時に使ってるからそこまで魔力が回らないんだと思う」
先刻のギルガメッシュとの戦いでは、あの弾幕を防ぐにはガタキリバコンボを使わざるを得なかった。
今は減った宝具の代わりにドラグレッダーが加わっている。速度と規模を落として破壊力を上げたということだが、現在のプトティラなら何とか対応できる。
陽介が補助魔法をかけ直し、こなたが回復をする。
オーズ、ガウェインともに万全の状態に復帰するが、それはあくまで振り出しに戻ったというだけだ。
「もし奴が宝具を無尽蔵に呼び出せるのなら、長期戦は不利だ。一気に決めるしかない」
「じゃあ……あれ、やる?」
こなたが言う「あれ」とは、一発限りの切り札のことだ。
マーガレット名付けるところの「至高の魔弾」。サーヴァントすらも傷つけ得る、とっておきの鬼札。
威力もさることながら、何よりも敵にとっては道の手札ということが大きい。
「いや、駄目だ。あれは俺たち三人が全力を傾けねばならない。向こうのマスターがその隙を見逃すとは思えん」
ルルーシュが否定する。サーヴァントたちの攻防の間、ルルーシュはじっと綺礼を観察していた。
サーヴァントたちに割って入れないのはこちらと同じだろうが、それにしてもあの神父は動かなさすぎた。
神父はルルーシュと同じくこちらを観察していた……隙を見せればそこに食らいついてくる、そんな不気味さを感じた。
ギルガメッシュがマスターに直接攻撃してこないのは、姑息な真似はしないという王たる誇りがあるからだろう。
あるいは正面から力づくでガウェインとオーズを打ち破ることに意義を感じているのかもしれない。だが、マスターまでそうだとは限らない。
「じゃあ、私が礼装であの人を見張って、ルルーシュくんがそれに備える。陽介くんが映司さんとガウェインさんの援護をする…これでどうかな」
敵対者の情報を表示するこなたの礼装なら、偵察にはうってつけである。
もし綺礼が動けば、ルルーシュが対応する。立ち向かうことは難しくても、こなたを連れて退避するくらいは十分に可能だ。
「相談は終わったか? では、再開するぞ」
結論を待たず、ギルガメッシュが再度侵攻してきた。
剣と炎の嵐が降り注ぐ。「壊刃」サブラクに匹敵する、広範囲に渡る破壊だ。
オーズがガウェインを掴み、炎は冷気のブレスで迎撃、宝具の雨の間隙を縫って突撃する。
一瞬後には先程と同じ光景が繰り広げられる。龍から降りたギルガメッシュへガウェインが斬りかかり、オーズがその援護につく。
しかし、今度は陽介が加わる。
ペルソナのアレックスが両腕を変形させる。ペルソナがただ魔法を放つだけではギルガメッシュには通じないだろう。
だが、サーヴァントの力を受け継ぐアレックスなら…サーヴァントの力を再現することができるアレックスなら、話は別だ。
ペルソナ使いの枠を超えた高密度の魔力が荷電粒子に変換され、まばゆく輝く槍となる。
「力を貸してくれ、アレックス……行くぜ!」
真っ直ぐに放たれた荷電粒子の槍は、オーズに気を取られていたドラグレッダーに直撃した。
炎を司る龍といえど、雷光にはさほどの耐性はない。龍が身を焼く激痛に絶叫を上げる。
「ちっ、竜種といえどこの程度か」
ガウェインがすかさずドラグレッダーの首を落とそうと跳躍するが、その瞬間にギルガメッシュはアドベントのカード効果を解除した。鏡像が砕けるようにドラグレッダーが掻き消える。
空振りしたガウェインだが、龍が戦線を離れた今こそ好機とすぐさまギルガメッシュに詰め寄る。
頭上にはオーズがいる。今度はいくら宝具を展開しようと一手遅れるということはない。
「威勢のいいことだ。だが一つ忘れてはいないか?」
しかし、ギルガメッシュは怯まない。口元には酷薄な笑みが浮かぶ。
「貴様らのマスターが仕事をしたように、我のマスターも遊んでいるわけではないらしいぞ」
オーズが急停止。ギルガメッシュに気を取られていたが、いつの間にか綺礼の姿がない。
急ぎ振り返り、マスターたちを見る。ルルーシュとこなたではない。襲われていたのは、ドラグレッダーを攻撃した陽介だった。
全力を振り絞ったために、陽介はしばらく動けない。その隙を言峰綺礼は狙っていたのだ。
「陽介くん!」
「よそ見をしている暇があるのか、雑種」
――ファイナルベント――
鳴り響いたのは、必殺を告げる死神の声だった。
◇ ◆ ◇
陽介が荷電粒子の槍を放った瞬間。視界が閃光に染め上げられたその一瞬だけ、こなたは綺礼の姿を見失った。
綺礼にはその一瞬で十分だった。夜闇に紛れて姿を隠し、人間離れした脚力をもって一気に陽介に接近し――全力を開放した直後のアレックスへと拳の一撃を叩き込むには。
アレックスの姿が歪む。膨大な力を流し込まれたために、姿を構成する魔力が乱れに乱れたためだ。
ペルソナのダメージは本体へとフィードバックされる。腹に叩き込まれた一撃が骨と内臓をまとめて幾つか押し潰す。陽介は血を吐きながら吹き飛んだ。
「がはっ!」
「陽介! 貴様っ……!」
ルルーシュがとっさにコードキャストを放った。同時に綺礼は刃渡り1メートルに満たない剣――黒鍵を両手指に生み出す。
赤い雷は、神父が黒鍵を投擲することにより、すべて見当違いの方向へと誘導させられた。
「ふむ、一撃で仕留めるつもりだったが、仕損じたか。やはりペルソナ使いとは普通人よりも頑丈なのだな」
ルルーシュが立ち塞がったことにより、陽介にはそれ以上の追撃は加えられなかった。こなたが急いで駆け寄り、回復のコードキャストを陽介に施す。
アレックスはサーヴァント時に高い再生能力と耐久性を有していたため、ペルソナとなった今はその特性をやや引き継いでいる。
そのため陽介は即死することはなかったものの、かなりの深手を負っていた。
「さて……些か呆気ない気もするが、どうやら向こうも決着がつきそうだ。こちらも終わらせるか」
とん、と神父が軽く一歩を踏み出す。それだけで、ルルーシュには目の前にナイトメアフレームが降りてきたような錯覚を覚える。
この神父は、ペルソナであるアレックスをたやすく殴り飛ばした。半分はサーヴァントである、超常の存在をだ。
決してただのNPCではありえない。近接戦に不慣れなルルーシュが太刀打ち出来る相手ではなかった。
「花村陽介とは別の意味で、君には期待していたが。打つ手なしかね、ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア」
「くっ……」
神父のずっと後ろ、サーヴァントたちの戦いも佳境に入っていた。ギルガメッシュが龍を召喚し、空高く舞い上がっていく。
こなたの宝具を使わずともわかる。あの魔力の高まりは、勝負を決めに来ているのだ。
「泉、花村はどうだ?」
「待って、まだ時間かかるよ! 傷が深すぎる!」
陽介も、こなたも動けない。
ルルーシュ一人では神父に抗えない。
「では、ここまでだな」
「いいや、そうでもない!」
ならば――少し早いが、カードを切る。
ルルーシュはサーヴァントたちの戦いをただ見ていたわけではない。
陽介とこなたのようにサーヴァントを補助することはできないが、ルルーシュだからこそやれることもある。
戦いが始まってからずっと、槍王イルバーンを地面に突き立てていたのだ。
こなたの礼装により、冬木大橋の構造データは既に把握している。なぜだかやたらと硬くなるように情報が変化させられていたが、今のルルーシュとイルバーンなら改竄は可能だ。
ルルーシュはイルバーンに命令を下す。
「チェックメイトには早すぎたな!」
「これは――足場を!?」
綺礼が立っている橋そのものを、情報を分解し消去する。ルルーシュがかつて得意としていた足場破壊戦術を、ようやく披露する機会を得た。
砂のように崩れ去っていく橋に巻き込まれまいと、綺礼が退いていく。破壊の規模としてはせいぜい十メートルというところだが、僅かながらに時間を稼げた。
視線の先、ギルガメッシュは今にもガウェインたちに襲いかかろうとしている。
「使うぞ――スザク!」
逡巡の暇はない。
ルルーシュは右手に意識を集中し、叫んだ。
「令呪を以って命ずる! 我が騎士ガウェインよ、ギルガメッシュを斬り捨てろ!」
スザクから託された令呪が蓄えた魔力を解放、ムーンセルの定めた法則を歪める。彼の騎士であるガウェインに力を与えんがために。
ギアスではない絶対遵守の命令が、発動した。
◇ ◆ ◇
「これは!?」
天へと駆け上がっていくギルガメッシュ。
瞬時に後を追ったオーズと違い、翼なきガウェインはただ見上げることしかできない。宝具を放とうにもガラティーンは今のギルガメッシュには効果は薄く、逆にオーズを巻き込むだけだ。
このままギルガメッシュの行動を許せば、確実にオーズかガウェインのどちらかが敗北する。それだけのエネルギーを秘めた攻撃だ。
だというのに何もできず結果を待つしかない。焦燥がガウェインを蝕んだ、そのとき。
急激に沸き上がってきた魔力が、ガウェインの全身を満たす。しかし体内からではない、これは――。
「……ルルーシュ!」
かつて無二の友ランスロットとの決闘の時にも感じた力の本流が、またしてもガウェインを奮い立たせる。
今、王命は下された。我が手の内には剣がある。倒すべき敵もまた、ここに。
「ならば……往くのみ!」
ガウェインの姿が消失する。次に実体化した場所は、遥か天空――オーズも、ギルガメッシュも超えて、さらに上。
ギルガメッシュとオーズが同時にガウェインを振り仰ぐ。両者の顔には驚愕が張り付いている。
大地を斬り裂かんばかりの斬撃を、ギルガメッシュへと振り下ろす。対してギルガメッシュは、とっさにファイナルベントの矛先をガウェインへ向けて放つ。
「はあああああああぁぁっ!」
「ぐっ――」
太陽の聖剣は龍騎には通用しない。だがそれは、宝具を全面解放した時の話だ。
聖剣をただの刃として振るうのなら、龍騎だろうとギルガメッシュだろうと斬り裂ける。
ガウェインの全力と、令呪を上乗せした一撃は龍騎のファイナルベントに拮抗する力を生み出していた。
「セイヤァァァ――――――!」
そして、ギルガメッシュの全力と拮抗しているということは、下から迫ってくるオーズに対応する余力はないということだ。
メダガブリューが飲み込んだセルメダルが魔力となって迸り、純粋な破壊力として現れる。
プトティラコンボの必殺技――グランド・オブ・レイジ。凄まじいエネルギーを内包したアックスモードのメダガブリューを叩きつける技だ。
龍騎のファイナルベント、ドラゴンライダーキックの三倍近い威力を誇るその攻撃が、ギルガメッシュへと直撃する。
「貴様ら、よもやここま――」
ギルガメッシュの驚愕、あるいは賛辞は轟音にかき消される。
令呪の後押しを得たガウェインの斬撃、ドラゴンライダーキック、そしてグランドオブレイジ。
三極の巨大な力の激突は、漆黒の空を白に染め上げるほどの閃光を放った。
「やったか!?」
地上で天を見上げていたルルーシュ達も、思わず言葉を飲み込むほどの輝き。
令呪一画とかなりの魔力を持って行かれたが、どうやら乾坤一擲の攻撃は成功したようだ。
「つ…ゴホッ、ガフッ。くっそ……痛え!」
「花村。気がついたか?」
「おかげさんでな…うお、なんだこの光!」
「映司さんたちがやったんだよ。あっ、降りてきた!」
やがて光が霧散していくとともに、空からガウェインを抱えたオーズがゆっくりと降りてくる。二人とも全身に傷を負っている。特にガウェインがひどい。
必殺技を放っていたオーズと違い、ガウェインはただ聖剣を振るっただけだ。自らが放つエネルギーに守られていない分、他の二人とは受ける衝撃も段違いだっただろう。
着地した二人を、勝利を確信したマスターたちが出迎える。だが、サーヴァントたちは険しい視線を空へと向けたままだ。
「申し訳ありません、ルルーシュ。仕損じりました…!」
ガウェインが苦渋に満ちた声で言う。オーズもまたそれを否定しない。
二人の視線の先には、ガウェインの言葉通り、ギルガメッシュが五体満足のまま存在していた。
「中々面白い趣向だったぞ、雑種ども」
そう愉快そうに告げるギルガメッシュとて、無傷ではない。全身の装甲は砕け、黄金率を保っていた肌も無残に焼け焦げている。
しかし眼光に微塵の衰えはない。それはつまり、戦いはまだまだ続くということだ。
「王律権キシャル――我が財を砕き、この身に傷をつけるとはな。楽しませてくれるものよ」
ガウェインとオーズの攻撃は、ギルガメッシュが展開した宝具によって威力を半減させられていた。
宝具は破壊したもののギルガメッシュを討ち果たすことはできず、オーズとガウェインがダメージを負っただけだ。
「へっ、じゃあ今度こそ完璧にとどめを刺してやりゃいいんだろ! そんなズタボロの状態なら楽勝だっての」
しかし膝を屈することなく、陽介が気炎を吐く。
仕留め損なったとはいえ、ギルガメッシュの傷も深いのだ。対してオーズとガウェインは、負傷しているとはいえ動けないほどではない。
ドラグレッダーもまた半死半生の深手であり、回復した陽介ならば今度こそ倒し切れるだろう。
「ククク……言うではないか、雑種。ではこうしよう」
ギルガメッシュは焦らず、一枚のカードを引き抜く。サバイブ――と刻まれたカードをガントレットに装填。
「あれは……!」
唯一その行為の意味を知るオーズが、絶望に顔を歪める。
五人の見ている前で、ギルガメッシュとドラグレッダーが業火に包まれた。
「こなたちゃん、俺とガウェインさんを回復して!早く…!」
ただ一人状況を理解したオーズが、体勢を整えるべくこなたを急かす。
何事かわからずとも、オーズの様子からただ事ではないと判断したこなたが全力でサーヴァントを癒やす。陽介もそれに続いた。
「伏して仰げ。これが王の威光である――!」
炎の中からギルガメッシュの声が響く。躍り出てきたドラグレッダーにはもう傷一つない。
その名は無双龍ドラグレッダー改め、烈火龍ドラグランザー。
続いて姿を見せた龍騎も全身の装甲が元通り復元され、また意匠も力強いものへと変化している。
サバイブ・烈火のカードを得て現れる、龍騎の強化形態――龍騎サバイブ。仮面ライダー龍騎の、真なる全力の姿である。
あらゆるパラメータがワンランク上昇し、マグマの如き灼熱を衣のように纏っている。
「今までは、本気じゃなかったってこと……?」
力を取り戻した龍騎サバイブを前に、こなたの声も震えている。
通常形態の龍騎ですら、全力でかかっても仕留め切れなかった。なのに、そのさらに上がある。
こなただけではなく、ルルーシュもまた、心を支配する絶望に屈しそうになっていた。令呪という切り札を切り、二人のサーヴァントが全力を叩き付けてなお、軽くあしらわれたのだ。
「まだだ……まだ何か、活路があるはずだ!」
口では仲間を鼓舞するためにそう言っても、そう簡単に打開策を考え付けはしない。
こなたにはまだ令呪が二画残っているが、もはやオーズには同じ攻撃を行えるだけの魔力がない。令呪は威力の底上げではなく魔力の充填にしか使えないだろう。
至高の魔弾は論外だ。効いたところで、一発でギルガメッシュを倒せるわけではない。
「……奴は、神父はどうした!?」
マスターを狙えば、という思考に行き着いた時には遅かった。
足場破壊から逃れた綺礼は既にギルガメッシュの後ろにいる。
「惜しかったな。一度は勝てると思い、それが覆された時の君たちの表情は、中々に見応えがあったよ」
ルルーシュたちの絶望を味わうかのように、綺礼が述懐する。
「ギルガメッシュが本気を出す以上、もう私の仕事はないな。主演目はもう終わってしまっただろうが……さて、君たちはどのような結末を迎えるのか」
――ファイナルベント――
ギルガメッシュが手にした銃にカードを差し込むと、ドラグランザーの体が折り畳まれ、バイク形態へと変形していく。
バイクに騎乗したギルガメッシュが腕を掲げる。彼の背後に無数の空間震動が起き、数十もの宝具が顔を覗かせた。
「さあ――幕だ。雑種ども。王の前に頭を垂れよ!」
十分に楽しんだと、ギルガメッシュは終わりを告げる。もう遊びはない、本気の、全力の一撃。
ドラグランザーが鎌首をもたげ、灼熱の火球を吐き出す。後を追うようにバイクが発進する。
龍騎サバイブのファイナルベント、ドラゴンファイヤーストーム。火球とドラグランザーそのもので、敵対者を打ち砕く必殺技だ。
さらに英雄王が指を鳴らす。それを合図に、宝具が次々と射出されてくる。
炎と綺羅の弾幕、そして龍の特攻。人の形をした破滅が差し迫ってくるのを、誰もが見ていることしかできない。
「……ルルーシュ、みな、下がってください」
否、ただ一人――ガウェインだけが、闘志を失わず立ちはだかった。
「何をする気だ、ガウェイン!」
「この剣ならば、あの龍に対抗できるかもしれません」
その手には陽介が持っていた封印の剣がある。かの騎士王ですら封じ込めた、異世界の大陸に名を残す伝説の竜殺し。
今までは、万が一ギルガメッシュがマスターを狙った時のために陽介が持っていたが、この状況ではもう陽介が持つ意味が無い。
「何とか、一手は凌ぎます。そこから先を――」
その先を言わず、ガウェインは前進する。否、言えなかったのだ。
ここを凌いだところで、どうするというのか。もはや打てる手はないのに。
「ガウェインっ……!」
迫り来る火球と刃を、ガウェインは聖剣と封印の剣を交差させて叩き落としていく。
その剣技はまさしく、彼の友であるランスロットが見せたもの。太陽の騎士は親友との戦いの中で、二刀を扱う彼の武技を己に刻みつけていた。
炎は龍騎となったギルガメッシュに効果が薄い――ならば、それはガウェインにも同じことが言える。
斬り割った火球が至近距離で爆発しても意に介さず、ガウェインはひたすらに前進し続ける。
「おおおおおぉぉぉっ……!」
「健気なものよな。良かろう、一思いに踏み潰してやろうではないか」
嘲るようにギルガメッシュが速度を上げる。
宝具の迎撃に気を取られたガウェインは、その疾走に対応できない。
「ガウェインさんっ!」
オーズがガウェインの前に飛び込んだ。バズーカモードのメダガブリューを使うもう一つの技、ストレインドゥームをドラグランザーの鼻先に撃ち放つ。
斬撃を繰り出すグランド・オブ・レイジに対して、ストレインドゥームは衝撃波を放つ。
だが――弱い。グランド・オブ・レイジに注ぎ込んだ力が大きすぎた。映司の残された僅かな魔力では、本来の半分の威力も再現できないからだ。
当然、ドラグランザーの疾走は止まらなかった。オーズの放った衝撃波はあっさりと吹き散らされる。
だがオーズも諦めない。全力で冷気のブレスを放射し、少しでもドラグランザーの勢いを殺そうとする。
ドラグランザーが生む熱量はドラグレッダーの比ではなく、先ほどは何とか相殺できたが、今度は押し込まれる。
やがて限界に達したオーズが弾き飛ばされる。大地に叩き付けられたオーズのベルトからメダルが排出され、変身が強制的に排除された。
「感謝します、ライダー……!」
だが――それで十分。ドラグランザーの速度は確かに減少した。ガウェインはその機を見逃さない。
機を見定めたガウェインがガラティーンを放り投げ、封印の剣を両手で握る。ガウェインの魔力を込められた封印の剣は炎を纏い、ドラグランザーの機首へと突き込まれた。
しかし、拮抗は一瞬の刹那のみ。ガウェインが踏ん張った両足が地面を削り、徐々に後退させられる。
最も力の集中しているドラグランザーの頭部、突進の勢い、そしてギルガメッシュ自身の力。あらゆる条件がセイバーの時とは違いすぎる。
剣の英霊と封印の剣を以ってしても、今の英雄王の突進を止めるには足りなかった。
「その剣は我の蔵にもないものだ。さて、どこまで保つか見せてみるがいい」
楽しげなギルガメッシュとは逆に、ガウェインは死力を振り絞る。それでも、届かない。
封印の剣の効果で何とかドラグランザーの疾走を押し留めているものの……封印までには至らない。
そして封印の剣に細かいヒビが走っていく。激戦に次ぐ激戦、そして巨大な力のぶつかり合い。
マスターの宝具として顕現した封印の剣では、超級のサーヴァントたちの戦いに、最後まで付いて行くことができないのだ。
「っ……」
やがて、剣は砕け散った。同時にガウェインも崩れ落ちる。
致命傷は負っていないが、魔力を放出し尽くしたその姿はもう、敗残兵そのものだ。
「中々楽しめたぞ、キャメロットの騎士」
満足気に、英雄王が呟く。
多大な消耗と引き換えだが、ガウェインは確かに龍騎サバイブのファイナルベントを凌いでみせた。
これなるは英雄王が手ずから裁くに値する、真の英霊である――ギルガメッシュが褒美とばかりにバイクを降りて、剣を片手にガウェインへと歩み寄る。
時間がないと見た映司が立ち上がり、もう一度変身しようとメダルを取り出す。が、過度に魔力を消費した体は自由にならず、メダルを取り落としてしまう。
「ガウェイン!」
「くっ、アレックス!」
ルルーシュがガウェインへと魔力を供給し、陽介が疾風魔法を使ってガウェインの背を押す。
ギルガメッシュがそんなマスターたちを見て嘲笑する。状況は好転せず、ただ審判の時を先延ばしにするだけだ。
そんな中、こなたは転がってきたメダルを拾う。
「……映司さん」
そのメダルの色は赤。そして――ひび割れている。
以前聞いた、映司の相棒の命が入っていたメダルだ。
「このメダルを、使うの?」
映司にとっては、特別なコアメダル。
魔力を消耗した今のオーズでも、このメダル自体が魔力を供給してくれるため問題なく使用できる。
そして……一度きりしか使えないと、映司は言った。
「……こなたちゃん」
「ううん、わかるよ。きっとここが選ぶ場面。本当にギリギリの場所なんだってことだよね。
映司さんが大切にしてたメダルを使わなきゃいけないくらいの状況なんだって」
これを使うのは、オーズが力を失うことを覚悟した上でのこと。
そう理解しているからこそ、こなたも覚悟を決めることができる。
「こなたちゃん……俺に力を貸してほしい。みんなが、生きて帰るために」
「いいよ。だって私たち、相棒だからね!」
あっさりとこなたは言う。結果次第で死ぬかもしれないのに、微塵の躊躇いもなく。
これほどの信頼を裏切ることは、映司にはできない。
「今日も、明日も生きていくために、今戦わなきゃいけない。生きることは戦うことだって誰かが言ってたけど、今なら私にもわかる気がする。
戦わないと生き残れない…でも私、死ぬつもりなんてないから。勝って……生きて帰るよ! そのために戦うんだ!」
こなたは力強く言い切る。絶望に負けない強い意志が、その瞳には確かにある。
だからこそ、映司も覚悟を決められる。
たとえこの一撃で己が砕け散ってしまうとしても――この優しいマスターだけは、なんとしても。
「力が欲しい、アンク! 俺に――みんなを守れる力をくれ!」
――タカ!
――クジャク!
――コンドル!
「映司さん、いっけぇぇぇ――――――――っ!!!」
令呪を解き放つこなたの声に重なり、かつての相棒の声が聞こえた気がする。
三枚の赤いメダルからも、活火山のような魔力が溢れ出てくる。同時に体の――否、魂の最奥からも爆発的な魔力が生まれた。
命令も何もない。ただひたすらに、映司を信じ抜くこなたの意志が、映司にかつてない力を与える。
龍騎サバイブと同じ、いやそれ以上の熱さ――炎。
仮面ライダーオーズ・タジャドルコンボ。火野映司の、最後の変身。
「行くよ、アンク……!」
タジャドルコンボに変身したオーズの胸から、七枚の恐竜メダルが飛び出てきて、オーズの左腕にあるタジャスピナーへとセットされた。
七枚の恐竜メダルから生み出される膨大なエネルギーがタジャスピナーの中で循環・増幅し、巨大な力へと練り上げられていく。
恐竜メダルを一発きりの弾丸として放つ――形は違えど、これもブロークン・ファンタズム。
異変を察したルルーシュが陽介に指示し、ガウェインを風で吹き飛ばす。ギルガメッシュが、オーズが生み出すエネルギーの奔流を見て笑う。
「それが貴様の切り札か、欲望の王。いいぞ、そうでなくてはな!」
「オオオオオオオオオオオオオオオォォォォォッ――――!!!!」
そして、オーズの最後の技が発動した。
ロストブレイズ――失われた炎が、もう一度オーズの、映司の力となる。
映司の力と、アンクのメダルと、こなたの思い。すべてを巻き込み、一つの巨大な渦になる。
「ぶ、ブラックホール……!」
「ほう、まだ足掻くか。楽しませてくれる」
目前の現象がどれほど凄まじいか、ルルーシュとて理解しきれない。確かなのは、ギルガメッシュが怯むことなくオーズへと向かっていくということだけだ。
オーズが威を振るうなら、受け止め、正面から打ち砕いてこそ、真の王とでも言うように。
ギルガメッシュは変身を解く。そして虚空より三軸の刀身を持つ奇妙な剣を手にし、相克渦動するエネルギーの中心――オーズの元へと突入していく。
「これを見せるつもりはなかったのだがな。しかしこういう趣向とあっては、我も本気を出すに吝かではない。
さあ、咆えろ――エア!」
それは、世界を切り裂いた剣。
あらゆる宝具の原典を所有するギルガメッシュただ一人だけが持つ――神話の神の名を冠した、ギルガメッシュの真の宝具。
三層のからなる力場を回転させ、空間そのものを斬り裂く対界宝具。騎士王のエクスカリバーすらも凌駕する、本来存在してはならない禁断の力。
オーズの生み出したブラックホールすらも呑み込む、最強にして無尽の破壊がもたらされる。
「原初を語る。元素は混ざり、固まり…万象織りなす星を生む!
フハハハハハハ! 死して拝せよ! エヌマ――
――――――――――――ぐっ!」
「天地乖離す開闢の星」――乖離剣エアの真名が解放されれば、この場にいるギルガメッシュ以外の全てが消し飛んだだろう。
だがそうはならなかった。乖離剣を構えるギルガメッシュの腕を、一筋の閃光が射抜いたからだ。
ギルガメッシュの腕を射抜いたのはオーズでも、ガウェインでもない。
「雑種、どもが――!?」
ギルガメッシュが早々に無力と判断し、捨て置いたマスターたち――彼らがやってのけたのだ。
束ねた力を一つにして放つ。あらゆる防御を突き抜け、対象へと確実に着弾する、至高の魔弾。
衛宮切嗣が遺した弾丸。名無鉄之介が遺した槍王イルバーン。鳴上悠が遺したペルソナの力。
自分たちだけではない、陽介たちが築き上げてきた絆の具現が、古の英雄王に確かに傷をつけた。
「映司さんっ!!」
こなたが叫ぶ。
至高の魔弾によって真名解放を妨げられた乖離剣は、予定されていた破壊を引き起こさない。
一瞬の停滞は致命的なズレとなる。宝具は不発――ギルガメッシュは、膨れ上がったブラックホールを前に微動だにできない。
ゲート・オブ・バビロンを使うも、射出した端からブラックホールへと吸い込まれてしまう。
自らの敗北を悟った英雄王は目を見開く。
「セイヤァァァァ――――――――――――ッッ!!!!」
「そうか、これがゼロの求めていた――」
そしておそらく、ギルガメッシュ自身も求めていたもの。
この結果は必然などではなかった。彼らは数時間前までは、ギルガメッシュに圧倒され逃げ惑うだけの弱者だった。
しかし、今。彼らはギルガメッシュを超える。厳しい試練を乗り越え、新たな地平を開く。
ほんの僅かな時間で見違えるほどに成長して。徹底的に叩き潰しても、何度でも立ち上がる。
人を試す王を――見守り、時には裁き、決して甘えさせない孤高の王の試練を、超える。
人の可能性。成長の証。厳しい試練の果てに得た無二の宝。それをこの目で見られた。
ならば、この遊戯には確たる意味があったのだ。英雄王が見定めるに足る価値が、確かにあった。
「――行くがいい、雑種ども。ここから先は、お前たちの道だ」
烈火龍が何とか脱出しようとするが、英雄王が射出した宝剣に頭を刺し貫かれ、一足先に消える。
直後にギルガメッシュの体は暗黒の穴に呑み込まれ、重力の井戸の底へ沈んでいく。
だが、あのような目をした者たちに倒されるのならば、悔いはない。
古の英雄王は――こうして、静かに舞台を降りた。
◇ ◆ ◇
「今度こそ……やった、のか……?」
呆然と、ルルーシュが呟く。ギルガメッシュはブラックホールに呑まれ、消えていった。
ブラックホールはギルガメッシュという巨大な力を呑み込み、ワームホールと化して今も膨張し続けている。
オーズがロストブレイズを解き放つ瞬間、彼らは精神世界で手に入れた力――ミックスレイド・至高の魔弾を放っていた。
ギルガメッシュにはロストブレイズすらも凌駕する力があるかも知れない。ならば、その発動を邪魔してやることだけが、こなたたちが勝利するたった一つの方法だった。
彼が最後に放とうとした宝具は、おそらく彼をしてなお、全力の集中を要するものだったのだろう。
でなければいかにサーヴァントにも通じるとはいえ、こなたたちの攻撃を許すとは思えない。
「――見事だ。これは本当に、予想外の結末だった」
サーヴァントを失った神父のNPCは、満面に笑みを浮かべてこなたたちに賛辞を送る。
陽介が構えようとするものの、綺礼にはもはや戦闘の意思はなく、両手を軽く掲げる。その手先が黒く染まる――NPCといえども、敗者の運命からは逃れられない。
「何故、俺たちを阻まなかった? お前なら、やろうと思えば横槍を入れられたかもしれんだろう」
「勝つことが私の――私たちの目的ではないのでな。とはいえ、手を抜いたわけではない。あれだけの力が放出されている中で動くことなどできんさ」
嘯く神父が本気かどうか定かではないが、それこそサーヴァントか至高の魔弾レベルの力でもない限りは、あのブラックホールの影響を受けて身動きが取れなかったのは不思議ではない。
マスターもサーヴァントも、力を出し尽くした末に掴んだ勝利だ。誰もが地面に腰を下ろし、立ち上がれずにいる。
「ガウェイン、無事か」
「ルルーシュ、さすがに、堪えましたね……」
封印の剣を砕かれ、ファイナルベントを受け止めたガウェインは全身に傷を負っている。しかし、ガウェインは健在だった。
紫色のメダルを弾丸に、最後の一撃を放った映司とは――違う。
「映司…さん」
「こなたちゃん……」
オーズはただでさえプトティラコンボでギルガメッシュと死闘を繰り広げ、さらにタジャドルコンボで恐竜メダル七枚のロストブレイズを放ったのだ。
特に英雄王すら葬り去るほどの一撃を放った代償は大きい。ギルガメッシュがあの時解放しようとしていた宝具を止めるには、それ以上の出力で、ロストブレイズを叩き込むしかなかった。
その結果、英雄王は虚空の彼方に消え――
「火野!」
「え、映司さん、あんた……」
ライダー――火野映司もまた、限界を超えてしまっていた。
変身は解け、こぼれ落ちたメダルも次々に砂と消えていく。
「あはは……ごめんね、陽介くん、ルルーシュくん。絶対に死なないって言ってみたけど……そううまくはいかなかったみたい」
映司が死ぬということは、つまりこなたも死ぬということ。死の恐怖に身を浸しながら、それでもこなたはいつもそうであるように、二人の仲間に笑いかけてみせた。
戦う力のないこなたは、しかしずっとこうして笑って見せてきた。その行為がどれだけ仲間たちに力を与えてきたか、彼女は知らない。
本当はみっともなく泣き喚いて、もっと生きたいと叫びたいのをぐっと堪えて。そうしなければ、陽介たちが前に進めないと知っているから。
「でもさ、あんな強いやつ倒したんだから、これはもう私たちの勝ちだよね。後はスタッフロールだけっていうか」
「泉……待て、まだ諦めるな! 何か方法があるはずだ!」
「アレックス! 火野さんを治すんだ!」
しかし、誰よりもこなたと映司の死を認めないのは、他ならない陽介とルルーシュだった。
陽介が映司へと回復魔法を連発し、ルルーシュもこなたから強引に取り上げた礼装で続く。
しかし――映司、そしてこなたも既に魔力が枯渇している。傷を癒やそうにも、情報が消去されていくほうが早い。
消去速度を遅らせることはできても、根本的な解決にはならない。
「くっそ……どうにかならねえのかよ、ルルーシュ! このまま泉を死なせていいわけねえだろ、」
「わかっている! 俺だってもう仲間が死ぬのを認める気はない! だが、どうすれば……!」
ふと、陽介はこの場にいるもう一人に意識を向ける。
陽介でもルルーシュでもこなたでもない――言峰綺礼。この戦いの始まりを告げたムーンセルのNPC。
陽介たち参加者側ではない、運営側の構成要素。
「なあ、あんた! もしかしてあんたなら何とか出来るんじゃねーのか!?」
藁にもすがる思いで、陽介は綺礼へと問いかけた。
ルルーシュは何を言っているんだこいつは、という目で陽介を見たが、考えてみればその方法が一番可能性がありそうだと思い直す。
「神父よ、一つ疑問がある。貴様とあのギルガメッシュの参戦は、聖杯戦争に元々ありえた要素か?」
「いいや、違う。私も奴もイレギュラー…飛び入り参加のようなものだ」
「ならば俺たちは、本来ならばする必要のない、無駄な戦いをした。そういうことで間違いはないな?」
「ふむ……まあその通りだ。この参戦は我らの気まぐれ故のものだからな」
ならば、とルルーシュは畳み掛ける。
「イレギュラーに対処した相応の見返りがあってしかるべきだろう! 泉は本来ここで死ぬことはない!
お前たち運営側のNPCが本当に聖杯戦争の管理を司っているのなら、正しい結果を歪めてはならないはずだ!」
「そうだ、バイトしたらその分の給料もらえるのが社会ってもんだ! 少しくらい埋め合わせをしろよな!」
二人の少年が轟々とまくし立てる。必死になって、こなたを救う術を模索してくれている。
こなたの頬を、恐怖からではない涙が、一滴、流れる。
「俺たちは、いい友達に会えたね。こなたちゃん」
「……うん。もちろん、映司さんもだよ!」
こなたと映司は笑い合う。数日間の付き合いであっても、ここまで互いを思い合うことができる――それはとても幸せなことだから。
ルルーシュと陽介に押し切られた――という訳でもないだろうが、神父のNPCは一本、指を立てる。
「一つ、手立てがないでもない」
「本当か、おっさん!?」
「もちろんだとも。それは――他ならない君自身だよ、花村陽介」
綺礼は立てた指を陽介に向けて倒す。
そして指を滑らせる。その先には、陽介のペルソナにしてサーヴァントのアレックスが佇んでいる。
「君は既に一度やってみせただろう。サーヴァントの情報を分解し、自身のペルソナとして再構成する――システムにない、奇跡というやつを」
「あ、あれか…でもあれは、賢者の石があったからできたことだろ?」
「あるではないか。賢者の石に匹敵する宝具が、そこに」
綺礼が示したのは、映司の手にたった一つ残った、ひび割れたコアメダル。かつてアンクの魂が宿っていた、たった一枚の特別なメダルだ。
メダルに人格を宿せることはアンクが実証している。賢者の石の代替として使うのならば、十分すぎる。
「でも、泉はペルソナ使いじゃないぜ。どうやって火野さんをペルソナ化させるんだよ?」
「……違う、花村。ペルソナ化させるんじゃない。そのメダルを、火野映司としてムーンセルに認識させる――つまりこういうことだろう」
ルルーシュが導き出した答えに、綺礼は満足気に頷く。
サーヴァントを失ったマスターはムーンセルにより失格と判定され、消去される。
ならば「サーヴァントが肉体を失ってもそこにまだ存在している」とシステムを欺瞞できれば、消去は免れる。
まさに陽介自身が今も証明し続けていることだ。
(それに、ゼロが求めている魂はたった一つ。私の目から見ても、この三者のうち誰もがその資格を満たしていると判断する。ならば二人は不要だ)
綺礼は、これは声に出さなかった。
仮に火野映司の人格をメダルに宿すことができたとしても、残るのはサーヴァントを持たない少女が一人だけ。
それではつまらない。言峰綺礼は魔王ゼロに協力しているとはいえ、ゼロの配下ではないのだ。
魔王の元へ辿り着き、さらなる物語を紡げる者。それはもう一人に確定している。
魔王ゼロと最も近しく、そして遠い者――この演劇の幕を下ろす者は、魔王ゼロとその者を置いて他にない。
「さあ、どうする? 泉こなたを救うというなら協力しよう。英雄王を倒したのだ、それくらいの報酬は与えられるべきだからな」
「泉、映司さん。いいよな?」
「こっちからお願いしたいくらいだよ、陽介くん。それでこなたちゃんを助けられるなら」
「陽介くん、ルルーシュくん……ありがとう」
こなたは涙ぐむ。覚悟はしていても……やはり、生きられるのならば生きたいのだ。
こうして、綺礼の協力を得て陽介は映司の魂をメダルに移し替える作業を行った。
「まさか俺がアンクと同じ姿になるなんて、思っても見なかったな……」
「おっと、時間のようだな」
魂の改竄は綺礼のおかげで滞りなく済んだ。映司の魂はメダルへと移行し、こなたも消滅から免れる。
そしてついに、綺礼も消滅の時を迎える。上級NPCだからか、意外なほどに長く存在し続けていたが、やはり限界はあったようだ。
綺礼は頭上に今も広がり続けるワームホールを見る。
おそらくゼロは今、このワームホールを何とか収めようと奔走していることだろう。なにせ解放直前の英雄王の宝具を呑み込んだのだ。生半可な干渉で打ち消せるものではないはず。
そして、ゼロの手が取られている今、この瞬間ならば。
「このワームホールを通れば、おそらくムーンセルの外側に出られるだろう」
綺礼が何気なく告げた真実は、皆を驚愕させるに足るものだった。
聖杯を破壊する――目的こそ一貫していれども、その後どうするかは全く定まっていなかったのだから。
「外側に出る……現実の世界に帰れるってこと!?」
「そうだ。これほどの規模のワームホールならば、出口は確実にムーンセルの外に繋がっている。サーヴァントに守られているならば、あの空間の中でも消え去ることはないだろう。
そして外に出た後は、魂は肉体のある次元へと自然に引っ張られるはずだ。一度ムーンセルの支配を脱してしまえば、我々もそれ以上追うことはできない」
「おいおい、それって……やったじゃんルルーシュ! 帰れるんだってよ!」
こなたと陽介は喜ぶが、それほど元の世界に未練のないルルーシュには一つやり残した仕事がある。
それを完遂しない限り、いつかまたこのような戦いに引き戻される可能性はゼロではない。
「泉、花村。お前たちは帰れ……自分の世界に」
「え? ルルーシュくんは帰らないの?」
「俺は、聖杯を破壊する。最初からそのつもりだったからな」
そしてピースマンの語った、ムーンセルを歪めたすべての黒幕。ルルーシュはそいつと対峙しなければならない。
サーヴァントを失ったこなたと陽介を付き合わせる気はない。どのみちギルガメッシュとの戦いで消耗しきった彼らでは、いてもいなくてもそれほど変わりはない。
ならば――彼らだけでも生き延びてくれる確証が得られたほうが、ルルーシュは心置きなく最後の決戦に臨める。
それで勝てるかどうかはわからない。いや、勝つためにはむしろ絶対に仲間の力が必要だ。
しかし。
「なら、俺も行くぜ。お前だけにいいカッコはさせないからな!」
「陽介くん……それじゃ、私も」
「いや、泉はダメだって! もう映司さんだって戦えないんだし、ここで帰った方がいいって!」
こなたを説得にかかる陽介を見て、ルルーシュはある決意を固める。
やはり、この二人が死んでいいはずがない。抜けられるのなら抜けるべきだ。この狂った世界から。
ガウェインを見る。彼は、目を伏せ頷いた。それがいい、と。
覚悟を決める。二度と使わないと決めた力――だが、今は。
「花村」
「おいルルーシュ、お前からも言ってやれよ。泉はここで――」
しっかりと、視線を合わせる。
ルルーシュの瞳が輝く。
「花村、お前は帰れ。自分のいるべき場所へ」
放たれたのは、絶対遵守の命令。
命令したのは、花村陽介。
人の意志を歪め、弄ぶ卑劣な力――ギアスを、ルルーシュは陽介へと使った。
「ルルーシュくん、何してるの!?」
「ここから先は俺とガウェインだけでいい。お前にも花村にも、帰りを待つ人がいるだろう」
動きを止めた陽介の瞳が、凄まじい早さで動いている。ペルソナ使いである陽介には、ギアスの効き目が薄いのかもしれない。
ガウェインに指示し、陽介を担ぎ上げさせる。ガウェインはそのまま、もう片方の手にこなたを抱えた。
他に方法がないとはいえ、やはり仲間にギアスを使うことはルルーシュにとって苦痛だ。この上こなたにまでギアスを掛けることは、流石にできなかった。
「ガウェインさん!」
「ここまで我が王に付き添っていただき、ありがとうございました。ミス・泉。そしてライダー。花村殿とランサーにも、どうかよろしくお伝え下さい」
「一人でなんて無茶だよ!」
「いや……俺の勘だが、おそらく一人でなければ意味が無いんだ。この聖杯戦争を起こした奴は、たった一人の勝者を求めている。
どうなるにせよ、もう戦えるサーヴァントを連れているのは俺だけだ。だから俺が行く――」
「……っざけんなよ、ルルーシュ! ……置いてかれるのなんて……ごめんだ!」
ギアスに抵抗しているのか、陽介の言葉は絶え絶えだ。
彼は心の底からルルーシュを案じている。こなたも同様だろう。
だが、だからこそ――。
「泉、花村。お前たちのお陰で、俺は生きる意思を捨てずにここまで来られた。
感謝している……本当に。だから今度は、俺に、お前たちを守らせてくれ。
お前たちの未来と、お前たちの生きていく世界……必ず俺が勝ち取ってみせる」
後ろに陽介とこなたの存在を感じることで、絶対に負けられないと己を奮い立たせる。
二人をこの箱庭から放逐し、最後の一人になる。それが、ルルーシュの選んだ聖杯戦争の結末。
「ガウェイン」
主の命を受け、ガウェインが二人をワームホールの中へと放り投げる。
その体が消える寸前。
「ルルーシュ! てめえ、今度会ったときに、絶対、絶対――ぶん殴ってやっからな!」
「ルルーシュくん、死なないで! 約束だよ! きっと、もう一度――!」
それは、再会の約束。
これでお別れなど許さない。絶対にまた、三人でもう一度出逢う。
花村陽介と泉こなたがルルーシュ・ヴィ・ブリタニアに掛けた――ギアス。
切なる願いをルルーシュに託し、陽介とこなたはこの聖杯戦争から退場した。
「そのギアス……確かに受け取った」
二人が消える間際、ルルーシュに向かって投げた物を受け止める。
契約者の鍵と、各種の礼装。もういない二人の、最後の残り香。
やがてワームホールは収縮していく。今飛び込めばナナリーのいる世界に戻れる――が、ルルーシュはそうしなかった。神父へと向き直る。
「この後はどうすればいい」
「ふ……心配せずとも、すぐに迎えが来る。そうだ、これも持っていけ」
綺礼はそう言って、残っていた自らの令呪をルルーシュへと分け与えた。
刻まれた令呪は三画。最初の状態に戻った令呪を見て、怪訝そうに問いかける。
「何故、ここまで俺に肩入れする?」
「フフ…なに、この先でそれがきっと必要になる。無駄に捨てるよりは、と思っただけだ。
ああ――だが、君を前にした時の彼を観察できないのは…残念といえば残念だ…な」
そして神父のNPCも消えた。夜の橋に、残ったのはルルーシュとガウェインだけ。
三日間に及ぶ聖杯戦争の果て、残ったのは――ルルーシュ・ヴィ・ブリタニアと騎士ガウェイン、この主従だけだ。
「……ついに、俺たちだけか」
「ですがルルーシュ。我ら二人きり、ではありません。我らの背は多くの朋友によって支えられています」
笑みを浮かべながら言うガウェインに、そうだな、と頷きを返す。ここに来るまで、ルルーシュはたくさんの出会いと別れを経験した。
全てを鮮明に思い出せる。敵であれ、味方であれ、誰もが懸命に願いを叶えようと戦っていた。彼らの存在は、強くルルーシュの中に刻まれている。
その願いを弄ぶ者――全ての元凶を、排除する。
それを以って、ルルーシュの二度目の生は幕を閉じるのかもしれない。
しかし、躊躇いはない。そして恐れもしない。
今のルルーシュには約束がある。いつかきっと――その約束がある限り、ルルーシュは死ぬつもりはない。
「……! これは」
佇んでいたルルーシュとガウェインを残し、冬木大橋が――否、冬木市そのものが解体されていく。
聖杯戦争が終結したためもはや冬木市を維持する必要もないためだろう。
地面が雪のように崩れ、どこまでも暗く先が見えない奈落を落ちていく。
一秒とも百秒ともわからない空白の時間を経て、やがて暗闇の底に黒よりも暗い仮面を見つける。
ルルーシュにはその仮面に馴染みがある――当たり前だ、自分も身に付けていた物なのだから。
足が地面につき、思わず仮面を拾おうと一歩踏み出したところで。
「まさか……お前が残るとはな。神父の干渉の結果か……。
だが、いい。お前になら資格はある……他でもない、この私が誰よりもそれを知っている……」
仮面が、喋った。
影が盛り上がり仮面に吸い込まれ、人の形を成していく。
現れたのは、かつて奇跡を起こす男と呼ばれ、世界を革命し、ルルーシュ自身を終わらせたはずの記号――つまりは、自分自身。
ルルーシュは、驚愕と共にその名を口にする。
「貴様は……ゼロ……!?」
「そうだ。我が名は魔王ゼロ。歓迎するぞ、もう一人の私。
そしてようこそ、我が後継者――新しき魔王の器よ」
たどり着いた、終端の果て。
盤面に残った駒は、キングとキング、ただ二人。
ゼロとゼロは邂逅し、そして最後のTURNが始まる。
これは、終わりに向かう物語――。
&color(yellow){【花村陽介@ペルソナ4 生還】}
&color(yellow){【泉こなた@らき☆すた 生還】}
&color(yellow){【ライダー(火野映司)@仮面ライダーOOO/オーズ 生還】}
&color(red){【言峰綺礼@Fate/extra 消滅】}
&color(red){【ギルガメッシュ@Fate/extra CCC 消滅】}
【月の裏側/???】
【ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア@コードギアス反逆のルルーシュ】
[令呪]:3画
[状態]:魔力消費(大)
[装備]:槍王イルバーン@私の救世主さま、鳳凰のマフラー、聖者のモノクル、遠見の水晶玉@Fate/EXTRA
[道具]:契約者の鍵@ペルソナ4
※槍王イルバーン、他礼装を装備することで、コードキャストを発動できます。
hadron(R2) 両眼から放つ魔力砲。収束・拡散発射が可能。 効果:ダメージ+スタン。
絶対守護領域 決着術式“聖剣集う絢爛の城”をデチューンした術式。 効果:小ダメージを無効化。
heal(16) 効果:HPを小回復
view_status() 効果: 敵対者の情報を表示
view_map() 効果:アリーナの階層データを全表示
【セイバー(ガウェイン)@Fate/extra】
[状態]:ダメージ(大)、魔力消費(極大)
※『聖者の数字』発動不可
【魔王ゼロ@コードギアス ナイトメア・オブ・ナナリー】
----
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: