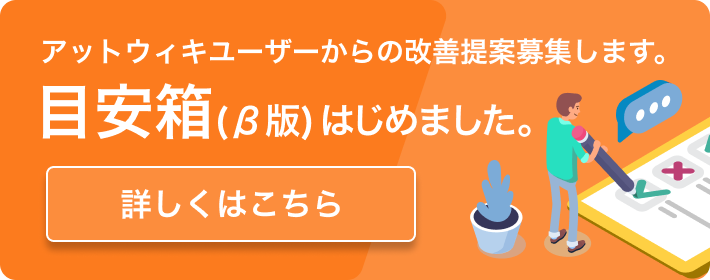「真実と憎悪の果てに」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「真実と憎悪の果てに」(2013/05/22 (水) 10:55:12) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
柳洞寺。
冬木における聖杯降霊の候補地の一つとされ、第五次聖杯戦争の終結の場となる地。
並行世界の記録をも可能としたムーンセルはこの地における戦いの結末をも記録している。
正義の味方を目指す少年と「答え」を見出した騎士王がこの世全ての悪の生誕を望む神父と人類最古の英雄王を打ち倒し、永遠の別れを迎える世界。
自らの未来を見せつけられ、そして乗り越えた少年が英雄王を打ち破り、かつての理想を失っていた錬鉄の英雄が「答え」を得る世界。
かつて養父から受け継いだ理想を捨て去り、ただ一人の少女の味方になることを決めた少年と、少年の味方になることを決めた少女が真に聖杯戦争を終わらせる世界。
そして今、月のSE.RA.PHに再現されたこの柳洞寺にて、どの歴史とも異なる戦いが始まろうとしていた。
・侍
今しがた降りてきた階段を一歩一歩と登っていく。
心なしか周囲には甘ったるい、蠱惑的な空気が満ちているように感じられた。
衛宮士郎とセイバー、ある世界において地上の聖杯戦争の勝者となった主従は遠坂凛殺害の元凶たるキャスターのサーヴァント、蘇妲己を討つべく歩みを進めていた。
この聖杯戦争が始まってからいくつもの苦難に晒されたためか強ばった表情で横を歩く士郎を気にかけながら、セイバーは己の内にある違和感を拭いきれずにいた。
キャスターは衛宮切嗣と内応し、ルルーシュにギアスを使わせ金田一とライダーの死因を作った。
天海陸や彼のサーヴァントらの話から考えれば、これが間違えようのない結論である。
だが、それでも騎士王の類い稀な直感は自身でも正体のわからない警鐘を鳴らしていた。
(この違和感が一体何を意味するのかはわからない、だが、それならば前へ進む事で確かめるまで)
これから待ち受けているのは最弱のクラスなれど容易ならざる敵手だ。
セイバーは脳裏に渦巻く疑念を振り払い、視界に入った山門を向き―――
「止まってください、シロウ!」
山門に立ちはだかる、その男を捉えた。
群青色の陣羽織を身に纏い、およそ非常識なまでに長大な日本刀を手にしたその姿は、まさしく日本の侍そのものであった。
だが問題はそんな事ではない、真に異常なのは男の纏うその気配。
他の英霊たちと比して非常に微弱であるものの、確かにサーヴァントとしての存在感を放っていた。
だがこれはどういう事だ。
衛宮切嗣のサーヴァントはライダー、如何にキャスターと繋がっていたといえど切嗣とこのサーヴァントに関係性があるとは考えにくい。
いや、そもそもつい先ほどまで山門の警備に就いていたガウェインが他のサーヴァントの存在を見落とすなど有り得るのか。
「如何に精巧に似せようとも、やはりここは偽りの箱庭でしか有り得ぬ。
私が愛した花鳥風月はここには無い、何とも侘しいことよ。
貴様もそうは思わぬか、セイバー」
「…貴公が何者かはあえて問うまい。だが何故私がセイバーだと断定できる。
私がこの手に握るのは何も剣とは限るまい、それともキャスターの入れ知恵か」
いつでも斬りかかれる態勢のまま、慎重に探りを入れる。
だが、侍は一瞬不思議そうな顔をした後、何かに納得したのか鷹揚に頷いた。
「…そうか、私は貴様を知っているが、貴様は私を知らぬのだな。
いや、これも並行世界とやらの妙というやつか、ままならぬものだ。
しからば改めて名乗ろう。私はアサシンのサーヴァント、佐々木小次郎。
貴様らが討たんとする女狐めがこの地に招きし亡霊よ」
「―――!?」
真名とはサーヴァントにとって絶対に秘すべきもの。
この異常な聖杯戦争であってもその本質が変わることはない。
だというのにこの男は堂々と己が真名を謳い上げた。
セイバーの驚愕は無理からぬ事であろう。
その表情を読み取ったアサシンは微笑を浮かべた。
「言ったはずだぞ、私は貴様を知っていると。
であればこちらから名乗るは当然の礼儀であろう?
それに―――私が名乗ったところで、貴様にとっての私は倒すべき障害でしかない。
そら、お互い為すべき事は何も変わりはすまい?」
「―――成る程、確かにその通りだ。
だが生憎と我々は先を急いでいる、まかり通るぞアサシン!」
セイバーの全身から魔力が猛り、風が唸りを上げる。
セイバーの世界ではついに実現しなかった異色の暗殺者との戦いの火蓋が切って落とされようとしたところで―――
「待て、セイバー!」
これまで沈黙を保ってきた彼女のマスターの制止が入った。
「シロウ?」
「俺達が倒すべきなのはキャスターだ。
お前をこんなところで消耗させるわけにはいかない」
あのアサシンが何者であれ、キャスターが召喚したサーヴァントである以上考えられる目的は時間稼ぎとセイバーの力を削る事と見て間違いない。
それにキャスターは奥からこちらの様子を窺っていることだろう。
衛宮士郎とセイバー、どちらの手の内を隠しておくべきかなど思考するまでもなく明白だ。
「勝算はあるのですか?」
「俺一人で何とか出来るとは言わない、でも隙ぐらいは作ってみせる。
だからセイバー、俺を信じてチャンスを待っていてくれ」
セイバーは無言で頷き、再び剣を構え直した。
だがその構えは攻めのそれではない、アサシンを近づけない守りの姿勢だ。
「ふむ、私は一向に構わぬぞ少年。
男子三日会わざればというやつか、随分と見違えた。
そなたの磨いた牙、見事私に突き立ててみよ」
アサシンはといえば、何故か構えを取らぬまま自然体の様相だ。
だが不思議と侮られているとは思わなかった。
きっとこの男にとってはこれが戦いの姿勢なのだろう。
「言ってろ。投影、開始(トレースオン)」
自己の内に埋没し、この状況に最も適した剣を探し出す。
見たところあのアサシンが持つ刀は普通の刀剣と比べれば業物の部類には入るが、英霊たちの持つ宝具と比較すればなまくらも同然。
「I am the born of my sword(体は剣で出来ている)」
ならばこの宝具こそが奴にとっての弱点となるだろう。
この剣の前では魔術師とサーヴァントの実力差など何の意味も持ちはしない。
もっともセイバーが壁になってくれているからこそ安全に撃てるのであまり偉そうな事は言えないが。
同時に投影した黒塗りの弓にそれをつがえ、魔力を込める。
アサシンは動かない、否、動けない。
彼はセイバーの実力をその身を以って知っている。
防戦でこそ最も力を示すアサシンが無理に斬りかかったところでセイバーを突破することなど到底不可能。
故に侍は動かず留まる。その美貌に不敵な笑みを浮かべたまま。
「食らいつけ―――“赤原猟犬”(フルンディング)!!」
二十秒か、あるいは三十秒か。
刹那とも永遠ともいえる膠着の後、衛宮士郎のつがえた弓から鮮烈な赤光が放たれた。
北欧の英雄ベオウルフが用いたとされるこの剣は必ず敵を斬るという概念を持つ。
魔弾として射出された魔剣は音速をも凌駕しアサシンへと殺到する。
「ほう、生前合戦に出た事などついぞ無かったが、燕ではなく矢を斬るもまた一興」
だが、それでも尚この侍は悠然とした物腰を崩さない。
この程度の獲物を斬れぬなら、この身は決して燕を斬る事など出来はしなかった。
如何に速かろうと、ただこちらへ飛ぶだけの矢弾などアサシンには何ほどの脅威でもない。
「ふっ―――!」
一閃。
アサシンが長刀を持った腕を振るう。
だがその動作の何と速く、流麗な事か。
態勢すら崩さぬただのひと振りは宝具である魔弾をいともたやすく弾いた。
「なっ―――!」
その光景に、驚きを隠せない。
赤原猟犬を弾かれた、という事実にではない。敵はサーヴァント、そんな事は予想の範疇だ。
真の異常はその後、未だ刃こぼれ一つないその得物である
群青色の侍が手にするは宝具ですらないただの長刀。
そんななまくらで真名解放を行なった宝具を迎撃しようものなら一撃で刀身を折られるが道理。
されど、その道理を覆すのが魔剣士、佐々木小次郎だ。
アサシンは力によって赤原猟犬を弾いたのではない。もとよりそんな膂力は無い。
彼はただ、魔弾の力に逆らわず刀身で威力を殺し受け流すことによって見事得物を失うことなく弾いてみせたのだ。
言葉にすればそれだけだが、音速を超える矢の弾速、重量、威力、そして刀を振るうタイミング。
それらを一つも過つ事なく見切ったその絶技がただの一刀に込められていた。
―――だが、北欧の魔剣の真価はここより発揮される。
「むっ―――!?」
逸早く異変を察知したのは暗殺者のサーヴァント。
その有り得ざる異常に目を奪われる。
本来、どれほどの腕を誇る射手であろうと一度放たれた矢の軌道を変える事など不可能。
それはこと弓術という一点ならば英霊にも比肩する腕を持つ衛宮士郎であろうと同じ事。
しかし必ず敵を斬る概念を帯びたこの剣はその定理を覆す。
矢として撃ち出されたこの宝具は射手が健在である限り何度でも標的へ食らいつく。
対抗手段はただ一つ、魔弾に射抜かれるよりも早く射手を倒すこと。
だが最高の俊敏さを誇るアサシンを以ってしてもそれを実行に移すことは出来ない。
射手である士郎の前にはセイバーというあまりにも強大な護衛がいるからだ。
この状況、既にしてアサシンは王手をかけられている。
「はっ―――!」
再び一閃。
侍の超絶技巧は二度も猟犬の顎をいなしてみせた。
だが、それも程なくして限界が訪れる。
(なるほど、これが合戦場を飛び交う矢というものか。
しかし……これ以上は流石に刀が保たぬか)
その事実は誰よりもアサシンが認識していた。
彼自身の剣の力量は全サーヴァントでも頂点に立つ程だ。
―――だが悲しいかな、アサシンの愛刀物干し竿の強度は主人の技量に対して絶望的なまでに脆い。
むしろ二度も赤原猟犬を退けたことが埒外の奇跡なのだ。
だがそれもここで終わり。三度目を防いだ時がこの刀の折れる時。
そして四度目でアサシンは凶弾の前に為す術も無くその身を撃ち抜かれる。
(ならば―――)
だが、それはアサシンの終焉を意味しない。
なるほど確かにただの一閃では空を駆ける猟犬を地に落とすにはまるで不足だ。
だが知るがいい錬鉄の魔術師よ、この侍が生涯を懸けて到達せし秘奥の剣を。
「秘剣――――――」
ここに来てアサシンが初めて構えを取る。
それは無形を常とするこの侍が会得したただ一つの必殺剣。
この男にのみ許された究極の魔技。
「――――――燕返し」
それは果たしてただの一閃であったのか。否、断じて否だ。
セイバーは確かに見た。
軌道を変え三度迫り来る赤原猟犬、その切っ先ではなく剣の腹に向けて振るわれた三つの斬撃を。
縦、横、斜めの三方向から全く同時に繰り出された円の結界の如き剣閃は迫る魔剣の刀身を見事断ち切ってみせた。
これこそが佐々木小次郎、その名を冠した無銘の剣士が空を飛ぶ燕を打ち落とすためだけに生涯に渡って剣を振るい続けた果てに到達した魔法の剣技。
多重次元屈折現象(キシュア・ゼルレッチ)。
生涯を剣に捧げた男の才と努力、その結実は宝具である魔弾をすら凌駕した。
そして。
「――――――こ、ふっ……!」
男の命運もまた、そこで燃え尽きた。
因果逆転の魔槍とは異なる意味での必殺魔剣。
それを振り抜いた瞬間にのみ生ずる刹那の隙を剣の英霊は見逃さなかった。
神速の踏み込みでアサシンを切り裂いたセイバーは惜しみない暗殺者に惜しみない賛辞を贈る。
「私には、いや、我が円卓の騎士の誰であっても到達し得ないであろう見事な剣技でした。
貴方にとってこの結末は不本意なものでしょうが―――」
「良い、気にするな。お互い巡り合わせが悪かったのだろうよ。
それに―――私とそなたの勝負付けは既に終わっていた。
もとより、招かれざる亡霊には過ぎた夢だったのだ」
口から、切り裂かれたその身から夥しいまでの血液が溢れる。
だがそれでも尚、アサシンからは些かも優雅さは失われていなかった。
「征け。女狐めは奥でお前達を待っている。
かつて地上で私を呼んだ魔女も大概の魔性だったが、あれはそれ以上よ。
どうせ碌な性根ではあるまい、速やかに止めを刺すが人のためというもの」
士郎もセイバーも、無言で頷き山門の先へと進む。
最後に一度だけ、誇り高き剣士の姿をその目に焼き付けて。
・オオカミ少年は牙を隠す
「嘘……」
「………」
情報を集めるために月海原学園へと足を踏み入れた陸、こなたら一行。
真っ先に確認した脱落者を表示した掲示板に記された名前の数は彼らの想像を遥かに越えていた。
「19人だって……!?まだ始まってから半日と少ししか経ってないんだぞ!?」
陸が嘘を交えない、心底からの驚愕を口にする。
それはこの四人の心中を代弁するものであった。
遠坂凛と金田一一に関しては覚悟はしていたが、それでもこの人数は異常に過ぎる。
「…何で?どうしてみんなそんなに殺し合いなんてしたがるの?
わからない、わかりたくない、だっておかしいでしょこんなの!」
「こなたちゃん、落ち着いて!」
取り乱すこなたを映司が宥めすかす。
無理もない、と陸は思う。
あくまで勝ち残る事を選んだ自分と違ってこなたは完全に巻き込まれた一般人なのだ。
むしろここまで曲りなりにも平静さを保っていた事をこそ賞賛すべきだろう。
そしてこれから先、自分はそんな彼女をも殺すのだ。
「みんな、動揺するのはわかるけどとにかく一旦冷静になろう。
脱落した参加者はこれで全体の約四割、確かに多いが悲観していても始まらない。
この脱落者に関して僕なりに考察した事を聞いてほしい」
そんなメンバーの間に広がった悪い空気すらも利用しようというのだろう、イスラがさも沈痛そうな面持ちで場をまとめにかかる。
その悪辣さに思うところが無いわけでもないが、だからといって止める理由もない。
こなたや映司と同じように黙って続きを促すことにした。
「まずどうして半日でこれだけの犠牲が出たのか、それは参加者間のやる気、モチベーションの差だと思う。
この聖杯戦争にはさっきの衛宮切嗣のような勝ち残るために容赦なく敵を殺しに回る人間もいれば、リクやリン、コナタのように殺し合いに反対する人間もいる。
幸い僕らは早期に手を結ぶことが出来たが他のマスターはそうじゃなかった。
勝ち残る覚悟を決めた者とそうでない者、遭遇して戦闘になった時、どちらが勝つかなんて事は語るまでもないだろう」
確かにそういう考え方もあるか、と納得した。
考えてみればこなたや凛はもとより柳洞寺にいた衛宮士郎らも殺し合いに乗っていなかった。
だとすればそんな思考のマスターがもっといた、という結論は不思議でもなんでもない。
「セイバー、君は俺達も殺し合いに乗った方が良いと思うのか?」
「そうは言わないよ、第一こう言っては何だけどリクやコナタが無理をしてやる気を出したところで戦い慣れした連中相手に勝ち残れるとは思えない。
僕らはこれまで通り、殺し合いに反抗するスタンスを通そう。
それにしばらくは大規模な戦いは起こらないだろうからね」
「「どうしてそんな事が言い切れるんだよ?」」
上手く間を持たせるために適度に質問する振りをしながらイスラに先を促す。
それにイスラは鷹揚に頷きながら答えた。
「これだけの犠牲者が出るほど各地で戦いが起こったんだ、どの陣営も大きく疲弊しているだろう。
となれば少なくとも夜まで、場合によっては丸一日は休息や偵察に費やされるはずさ。
だから、今すぐ僕らが他の参加者に襲われる可能性はかなり低い。
そこでだ、ここらで当初の目的を達成しておこうじゃないか。
コナタとライダーには図書室で情報を集めた後、リンの家に向かってほしい」
「えっ、ちょっと待ってよ。りっくんとセイバーさんは?」
「「さっきセイバーと話し合って決めたことなんだけど…オレ達は柳洞寺へ行こうと思う」」
陸の言葉にこなたと映司が愕然とする。
当然だ、危険な鉄火場とわかっている戦場に限りなく最弱に近い二人が踏み込もうというのだから。
「…駄目だ、それは。士郎君たちの援護に行くなら俺の方が向いている。
第一セイバー、キャスターには天敵一人で当たった方が良いと言ったのは君だろう」
「確かにシロウ達の援護という意味もあるけど、それ以上に僕自身の戦力補強の意味合いが大きいね。
まだ詳しくは話せないが、僕はマナ、要するに大気中の魔力が集まる霊地にある儀式を行うことによってその場の魔力を自身に集める事ができるんだ。
そうすれば僕の戦力は格段に上がる。もう君達のお荷物にはならないさ」
やや自嘲を込めて虚実を交えた説明をするイスラ。
知らない人間が見れば、こいつは本気で今まで足を引っ張ってきたことを悔やんでいると思うのだろう。
やはりどれだけ付き合ってもイスラを好きにはなれそうもないが、ここはこのサーヴァントに同調しなければならない。
「「火野さ…ライダーは今までずっとオレ達を体を張って守ってくれた。
だから今度はオレ達がみんなのために命を賭ける番だ。
それに…多分より危険なのは泉達の方だ、考えてもみてくれ、柳洞寺には間違いなくオレ達に味方してくれる衛宮がいるけど遠坂邸は今どうなってるかわからない。
オレ達が合流するまで絶対に無理はしないでくれ。…もう仲間を失うのはたくさんだ」」
「りっくん…」
自分でも反吐が出るような酷い嘘で同情を誘う。
ああ、きっと今オレは演技でもないのに酷い顔をしてるんだろう。
その証拠に二人は心から心配そうに自分を見ている。
「今までお荷物だった僕が言っても説得力が無いかもしれないが、例えキャスターがまだ生き残っていたとしてもやられてやるつもりはないさ。
さっきまでは不意打ちだったから不甲斐ないところを見せてしまったが、相手がキャスターだとわかっていればやりようはある。
僕の貯蔵魔力を度外視すれば切り札を使うことも出来ないわけじゃない。
それに、これからの事を考えれば今のうちに戦力を増強しておく必要があるんだ。
これだけの人数が脱落したんだ、今生き残っているのはそれなりに修羅場を潜った者ばかりだろう。
そんな連中を相手に生き残るには僕達も力をつけなければいけない」
駄目押しとばかりに別行動の必要性を説くイスラにこなたと映司もようやく納得した。
出発の前に映司の口から衛宮切嗣のライダー、仮面ライダーディケイドの情報を教えてもらい、学園を離れる。
「りっくん!約束だよ、絶対にまた会おうね!」
嘘にまみれた剣の主従の真意など知る由もなく、こなたと映司は自分達に出来ることをと図書室に足を運んでいった。
【深山町・月海原学園/昼】
【泉こなた@らき☆すた】
[令呪]:3画
[状態]:健康
[装備]:携帯電話、乗用車
【ライダー(火野映司)@仮面ライダーOOO/オーズ】
[状態]:魔力消費(微)
「くっくく、アーッハハハハハハハハ!!
いやあ見事な演技だったよリク!見たかいコナタとライダーのあの顔!
君も一段と演技が堂に入ってきたじゃないか!ぷっくくくく…」
「だから爆笑するなって言ってるだろこの馬鹿!」
柳洞寺に続く階段を登りながら、先ほどから人目がないのを良いことに爆笑するイスラに辟易しつつ先を目指す。
目指す先は柳洞寺の敷地、その中枢だ。
だが、先にこなた達に語った別行動の目的は半分が真実、半分が嘘だ。
柳洞寺にイスラの宝具、紅の暴君(キルスレス)を突き立てて大量の魔力を得る、というのは紛れもない真実だ。
ついでに言えばこれからに備えて、とりわけ衛宮切嗣に対抗するため戦力を増強する必要があるというのも偽らざる本音である。
しかし、戦力を得る理由はこなたらを守るためなどでは断じてない。
「シロウ達なら首尾良くキャスターを打倒できるだろう。
でもキャスターもそれは承知している、あらゆる手を尽くして彼らに消耗を強いてくる。
僕らはそうしてキャスター討伐で疲弊したシロウとセイバーを後ろから撃てば良い」
「そりゃあそうだろうけどな、キャスターの方が生き残る可能性もあるんじゃないのか?
オレ達はキャスターの事を何も知らない、思いもよらない切り札を持ち出してくるかもしれないだろ」
「その場合でも問題は無いよ、リク。
そもそもキャスターがセイバー、それも名高いアーサー王を相手にして戦力を出し惜しみするなんて土台不可能だ。
つまり万に一つキャスターがシロウとセイバーを下せてもまず間違いなく余力なんて残らない。
君の言う切り札とやらが僕らに向けられる可能性は無視しても良いほど小さいものだ」
そう、陸とイスラにはこなた達と共に行動できない理由があった。
まず第一に紅の暴君で魔力を汲み上げる様子を見られることによって真名が露見するリスク。
サーヴァント達は聖杯から時空を越えた知識を授けられている。
裏切りの反英雄であるイスラの真名を知られれば、いくらお人好しなこなたや映司といえどもこちらへの信用を大きく落とすことになるだろう。
そして―――こちらが最も大きな理由だが、陸とイスラはこの機を生かして衛宮士郎と、可能ならルルーシュをも葬り去る算段であった。
二人とも今は自分達の嘘に騙されていてくれているが、この先何かの拍子に真実に辿り着く可能性も決して零ではないのだ。
キャスターに加え、キャスターから話を聞いたであろう士郎とルルーシュを始末すればもう凛を殺害した件を咎めることが出来る者はいなくなる。
それに今を逃せばもっともらしい理由をつけてこなた達と別行動できる機会はもう巡ってこないかもしれないし、時間が経てば第三者に柳洞寺を占拠される可能性も否めない。
リスクがあるのは承知の上、だからこそこれまで温存していた力が活きてくる。
「キャスター戦で疲弊したシロウ達はもとより、この山の霊脈を乗っ取ってしまえば令呪を2画失ったルルーシュも敵じゃない。
まあ流石にガウェイン卿を相手にして僕自身が正面から倒せる自信は無いけどリク、君は別だろう?
随分我慢させてしまったね、これでようやく僕達の聖杯戦争を始められる」
そうなのだ、刃旗という圧倒的な力を有しながら陸がこれまで策謀に徹さざるを得なかった理由は偏にイスラの弱さにある。
紅の暴君を用いた伐剣覚醒、その比類なき力を魔力不足で引き出すことが出来なかったが故にイスラ・レヴィノスは最弱だった。
しかしこれからは違う、この冬木市最大の魔力集積地を利用すればイスラは最優のクラスの名に恥じない力を取り戻す。
そして全マスターでも最強に近い陸の戦力で以って正面から全ての敵を打倒することも夢ではない。
「…ああ、そうだな。こうなったらもう泉や火野さんも用済みだ。
それに遠坂から奪った魔力はまだ温存してるんだろ?」
「もちろん。少し性能は落ちるしそう長時間は無理だが伐剣覚醒そのものは使えるよ。
これを使う相手がシロウ達になるかキャスターになるかはここからじゃまだ分からないけどね。
それとリク、コナタとライダーはせっかく僕達を味方と思ってくれてるんだ、用済みなんてひどいこと言わずに最後の最後まで利用し尽くしてあげようじゃないか」
「お前にだけはひどいと言われたくないよ」
そんな応酬をしながらついに山門近くまで辿り着いた。
ここからは無駄口は無しだ、お互いにそう気を引き締め―――
「良からぬ気配が近づいてきているとは感じておったが、よもや人の皮を被った蛇蝎の類であったとは。
あの少年とセイバーを葬るとはまた穏やかではないな、そうであれば私も門番の役目を果たさねばなるまいよ」
―――既にここにいるはずのない男の声を聞いた。
・再びの魔剣士
「サーヴァント……!?」
「いかにもこの身はアサシンのサーヴァント、佐々木小次郎に相違ない」
「はあ!?真名を!?」
山門に立ち塞がるように現れた別のサーヴァント。
日本の剣豪・佐々木小次郎を名乗ったその男はどこから出てきたサーヴァントだというのか。
少なくとも先ほどまで柳洞寺にいた面子のサーヴァントでは有り得ない。
もしそうなら彼らの口からこの男の存在が出なかったことに説明がつかない。
かといって陸やイスラと同じく漁夫の利を狙ったマスターの差し金とも考えにくい。
そう考えるにはあまりに動きが早すぎるし何よりサーヴァントのこのような酔狂な名乗りを許しはしまい。
だとすれば、俄には信じ難いが残る可能性はただ一つ。
「キャスターの用意した手駒、そんなところかい?」
「然り。如何な外法を用いたか、あの女狐めが亡霊に過ぎぬこの身を山門を憑き代に呼び出したというわけだ」
「おい、ちょっと待てよセイバー!
サーヴァントがサーヴァントを召喚したっていうのか!?
そんなルール違反が出来るのかよ!?」
「出来なくはないだろうね、何しろ向こうは本職のキャスターだ。
媒介はそうだな…さっき死んだという、ライダーのマスターの令呪じゃないかな?」
イスラの推測にアサシンは沈黙を以って応じた。
その沈黙をイスラは肯定と受け取った。
あるいは、もう言葉を話す事すら苦痛なのかもしれない。
「しかしまあ、そんなことはどうでもいいか。
少なくとも、今君がこうして存在している理由に比べれば些細な事さ。
まったく君のそれは一体どうなっているんだい?僕の呪いが形無しじゃないか」
―――信じ難い事に、アサシンは明らかな致命傷を負いながら未だ気力だけで存在を保っていた。
「何、おぬしらの良からぬ気配を感じたものでな。
これはまだ死んではおれぬと思い立ったまでのこと。
いや、醜く生き足掻いてこそ得られるものもまたあったようだ。
―――何しろ、セイバーの戦を邪魔立てする不埒者どもをこの手で斬れるのだからな」
その口と胴体からは生きているのが不思議なほどの血液が流れていた。
元々は優美であったのだろう陣羽織は血に染まり、今や見る影もない。
手にした長刀物干し竿は先ほど赤原猟犬を迎撃し、打ち落とした代償に刀身が歪んでいる。
だが、そんな死に体であってもイスラにはアサシンの戦力は些かも衰えていないように感じられた。
「やれやれ、たかが敵サーヴァントにどうしてそこまで入れ込むのか僕には理解できないよ」
「この月の聖杯戦争にしか招かれなかった貴様らには知り得ぬ事よ。
―――ああ、そうだな。確かにあの時私は次こそはと月に願ったものだ。
いやいや我ながら実に未練がましい、またもこうして化けて出てしまったのだからな」
陸とイスラの知らない何かへの執着を振り払うように一度だけ頭を振り、刀を掲げる。
その静謐な闘志は陸にとって全く未知のものだった。
だがイスラはそんな相手の心情などお構いなしに紅剣を手に取り、召喚術の構えを取る。
「生憎と僕は純正なセイバーじゃなくてね、代わりといっては何だけどキャスターの真似事が出来る。
だから君がそこから動けない存在だということも手に取るようにわかる。
さて、そこまで分かっていて僕が君の得意そうな距離に入るとでも?」
決まりきった結末を記す必要はない。
佐々木小次郎の名で召喚された無銘の魔剣士は異界の召喚術士の前に一太刀浴びせることも適わず月の聖杯戦争から完全に退場した。
招かれざる亡霊は露と消え、後には荒れ果てた瓦礫だけが残された。
“……ここまでか、先に逝っているぞセイバー。
いや、良い夢を見させてもらった―――“
【アサシン(佐々木小次郎)@Fate/stay night 消滅】
アサシンを無傷で撃破した後、山門を潜り境内へ入る。
警戒しながら中に入ると、そこにはキャスターの気配は微塵も感じられず、代わりにどこから調達したのか黒塗りの洋弓を手にし、ムーンセルによる修復が始まった本堂を見つめる見知った少年がいた。
「「衛宮、無事だったんだな。
キャスターは…どうしたんだ?それにあんたのセイバーは?」」
「…キャスターは俺達が倒した。
セイバーは…少し席を外してる、まあすぐ戻るよ」
こちらに向き直った士郎だが、どうも様子がおかしい。
その表情はどこか凍っているようにも感じられ、遠坂凛の仇敵を討ち果たしたという達成感はどこにも見られない。
「それよりお前らこそどうしたんだ。
泉とライダーは一緒じゃないのか?
それにさっきの物音は?」
「いや、実は死にかけのサーヴァントの妨害に遭ってね。
それと二人には学園に残ってもらっているよ。
調べ物をしてもらってからリンの家で落ち合う予定でいる。
君らも一緒に来ないか?
キャスターを倒したなら、これからの事を考える必要がありそうだしね。
さっきのアサシンの事を含めて本格的な情報交換をするべきだろう」
イスラが友好的な笑顔を貼り付けたまま士郎の隙を伺う。
凛の一件から令呪を警戒しているのか、すぐに襲いかかる気はなさそうだ。
「そうか。本当にあいつらはいないんだな、良かった」
「………?」
イスラも気付いたようだがやはり何かがおかしい。
まるで自分達が何か致命的な見落としをしていて、まだそれに気付けていないかのような―――
いや、そもそも“何故士郎は陸とイスラがここに来た事に全く驚きを見せないのか?”
「なあセイバー、いや、天海でもいい。
アンリマユ、宝石剣ゼルレッチ、大聖杯に小聖杯。
この単語のうちどれか一つでも聞き覚えはないか?」
「「……いや、オレは知らない。セイバーは?」」
「残念ながら僕も知らない、リンや君が参加したという聖杯戦争に関わることなのかい?」
イスラが警戒の度合いを若干引き上げながら答える。
士郎はといえば一度だけ目を閉じて天を仰ぎ、無表情のままこちらを見つめる。
「そうか、やっぱり知らないのか。
…キャスターは知ってたぞ」
その言葉が引鉄だった。
身体能力を強化しているのか素早い動作でどこからか矢を取り出し、陸に二射続けて撃ち放った。
「ハッ!」
だがそれらは当然のように陸の前に出たイスラの魔剣に阻まれる。
しかし事はそれだけで終わらなかった。
「…!リク、横だっ!!」
爆音と共に林からミサイルの如きスピードで飛び出してきたセイバー、アルトリア・ペンドラゴン。
その手に握る不可視の剣の切っ先は真っ直ぐ陸に向けられていた。
士郎の射撃とほぼ同時の変則的十字砲火(クロスファイア)。
陸の前に飛び出し、矢を迎撃したイスラは間に合わない。
「う、うわああああああっ!!!」
恐怖と生存本能から無意識のうちに顕醒し、意識圏を張った。
だが無情にもセイバーの剛剣は意識圏を容易く切り裂き、刃の直撃こそ免れたが風王結界の衝撃だけで十数メートルも吹き飛ばされ、反対側の林の木に全身を打ちつけられた。
すぐさまイスラが駆け寄り、陸を庇う形で前に立つ。
「なるほど。姿を変え、大剣を持ち既存の魔術とは異なる障壁か。
それにこの反応速度、確かにこれならばサーヴァントであっても短時間ならば引きつけられる。
やはり我々を欺き、凛を殺したのは貴方達だったか」
「…これは一体どういうつもりだい?
しかもいきなり濡れ衣を着せにくるとは大した挨拶じゃないか。
大体僕らがリンを殺しただなんて、まさかキャスターにでも操られているのか?」
「この期に及んでまだそのような戯言を口にするか。
確かにキャスターは潔白ではなかった、だから我々が倒した。
だが同時に、凛を直接殺したのは彼女ではないとはっきり分かったのだ」
「何…だと…?」
確信を込めて敵意をぶつけるセイバーにさしものイスラも一瞬頭が真っ白になった。
何故だ、どこで露見した。
いや、状況から考えて情報の出どころがキャスターであることは間違いない。
だが何故あれほど憎んでいたキャスターの言を今になって信じる気になっている。
一体何がどうなればさっきの今でここまで態度が変わるのか。
イスラが事態を好転させようと必死に思考を巡らせている時、士郎が地面に落ちた反魔の水晶を拾い眼前に突き出した。
「言ってなかったけどな、俺はある魔術に特化した魔術使いなんだ。
その魔術からの派生で、物の構造を把握する解析の魔術が使えるんだよ。
その物の創造理念から基本骨子、構成材質、製作技術、成長経験に蓄積年月に至るまで全て解析できる。
リィンバウムだとかわからない単語もあるけど、とにかくコイツが対魔力の代わりになるような魔術道具の一種だってことは今解析したことで服の上からでもすぐにわかった。
要するに天海、お前はルルーシュのギアスにかかってもいなければただの一般人でもないって事だ」
「「ま、待ってくれ、違うんだ。確かにこの力を隠してたことは謝るよ。
で、でもだからってオレ達は間違っても遠坂を殺したりなんかしてない!
その水晶だって、ルルーシュにギアスをかけられた後でセイバーに頼んで作って」」
「天海」
弁解の言葉は士郎の大声に阻まれた。
その双眸からは今や怒りの色がはっきりと見て取れる。
「…お前、俺の話を聞いてたか?
俺は物の構造を全て解析できると言ったんだぞ。
この水晶がどこかから“呼び出された”のは今日の午前7時49分22秒から37秒までの間。
ルルーシュが柳洞寺を出たのが午前9時、どう考えても時間が合わないんだよ。
仮にこれを用意した理由がキャスターへの対策だったとしたって、お前がギアスにかかっていない事だけは絶対に間違いのない真実だ」
「な…馬鹿な…そんな……」
聞いていない、そんな自分達の嘘をピンポイントで暴ける魔術が存在するなんて聞いてない。
皮肉にも、嘘がバレないようにと用意した反魔の水晶と刃旗使いとしての今の陸の姿が彼らの嘘を裏付ける動かぬ証拠となってしまったのだ。
金魚のように口をパクパクと動かしながら愕然とする陸に追い討ちをかけるように更なる衝撃を突きつけられる。
「それからお前のセイバーが持ってる宝具、そいつには確かに魔力を吸奪する機能があるな。
…いや、その剣は本来世界から魔力を汲み出して使うものなんだ。
銘は“紅の暴君(キルスレス)”。セイバー、これでアイツの真名わかるか?」
「はい、生まれた時より絶息の呪詛を与えられ、その苦しみから逃れるために多くの組織を渡り歩き裏切り続けた反英雄イスラ・レヴィノス。
どうやら異界のサーヴァントに関する知識は私にも付与されていたようです」
「……!!」
イスラの表情が衝撃と絶望に歪む。
魔術師という存在を侮っていたつもりは毛頭なかった。
しかしそれでもこの衛宮士郎という魔術師はあまりにも異常だ。
この宝具にどれだけの神秘が込められていると思っている、それを何故そうも簡単に分析できる。
この男に疑われ解析の魔術を使われた、たったそれだけの事でこれまで陸とイスラが苦心して積み上げてきた戦略は呆気なく崩壊した。
陸の刃旗と反魔の水晶を見られたことにより発覚した二人の嘘、更にはこれまでひた隠しにしてきた悪名高いイスラの真名。
それらが全て露見してしまった今、如何に舌先三寸を得意とするイスラもこの状況を覆して士郎とセイバーを騙せる策を弄することは出来なかった。
「一つ聞かせてくれ、どうして君達は僕らが疑わしいと思ったんだい?」
どうして自分達の嘘がわかったのか、とは聞かない。
それはイスラにとってささやかな最後の抵抗だった。
「ああ、俺達も最初はお前らを全く疑ってなかった。
そこに疑問を抱いたのは――――――」
・妲己ちゃんのスーパーネタばらしタイム
―――時をしばらく遡る。
アサシンを撃破して山門を通り、奥まで進むと焼け落ちた本堂の前で佇む一人の女、キャスターを見つけた。
しかしどうもおかしい、キャスターのサーヴァントならばセイバークラスのサーヴァントを迎撃するにあたって必須ともいえる魔術工房、あるいは神殿らしき空間はどう見てもここには存在しない。
「あらぁ~ん、いらっしゃぁ~い。
あの小次郎ちゃんをほとんど消耗ZEROで倒しちゃうなんてわらわビックリだわぁん」
「そのような世辞は結構。確認するがキャスター、先のアサシンは貴様がハジメの令呪を使って召喚した者だな?
如何に魔術師の英霊といえど相応の媒介が無ければサーヴァントレベルの存在を召喚するなど不可能、可能に出来るものがあったとすれば彼しか考えられない」
「さっすが普通に魔術が世間に在る時代に生きたセイバーちゃんは見る目が違うわねぇん。
でもぉん、それがどうしたのぉん?
わらわの立場なら利用できるものは全て利用するのは当たり前でしょぉん?」
「確かに、許し難くはあるが貴様の立場からすれば最善の方法だったのだろう。
だが―――私からすれば貴様を討つ事への躊躇いがまた一つ消えただけの事だ……!」
不可視の刀身をキャスターに向け構えを取る。
最弱の英霊といえどここまで自分達を苦しめた相手だ、油断はしない。
士郎もまた、魔術回路を励起させ不意打ちに備える。
だが、予想に反してキャスターはこちらにフッと微笑んだ後両手に持つ扇型の宝具、五火七禽扇(ごかしちきんおう)を地面に投げ捨てた。
「やーめたぁん♥」
「なっ……!?」
「…どういうつもりだ、よもや事ここに至って命乞いが通るとでも思っているのか?」
「だぁってぇ~ん、ここでわらわが頑張って戦ってもお互いデッドエンドからの道場行き確定なのよぉん?
それなら貴方たちを助けてあげた方がまだ実りがあるでしょぉん?」
デッドエンドだの道場だの訳の分からない単語は聞き流すとしてキャスターの発言と行動の意図がわからない。
いやそもそも何故追い込まれているからといって戦いを放棄するのか。
このキャスターならば最悪この土地との契約を切って捲土重来を期すことも不可能ではないはずだ。
「世迷言も甚だしい。ここで倒れるのは貴様だけだ、キャスター」
「いつでもどこでもわらわって信用が無いのねぇん、悲しいわぁ~ん。
ああ見える、見えるわぁん!味方と信じた人間に後ろから刺されて道場送りにされる士郎ちゃんとセイバーちゃんの姿が!」
あまりにも白々しい大粒の涙を流しながら相変わらず要領を得ない発言を繰り返す。
警戒を解いたわけではないが、これでは埒があかないと士郎が話しかける。
「ちょっと待て、味方に刺されるってどういう意味だよ。
言っとくけどな、ルルーシュや他に俺達に味方してくれてる奴らはしばらくここには入ってこないぞ。
お前みたいな奴には天敵になるサーヴァント一人で戦った方が良いからな」
「ふぅ~ん、それって天海陸ちゃんのサーヴァントの入れ知恵かしらぁん?」
「何でそれを…!いや、そうか。お前のその帽子は…!」
解析魔術を使ったことによって性能が判明したキャスターの宝具、金霞帽(きんかぼう)。
使い魔の類ではなくその宝具の索敵能力で自分達の動きを察知していたという事か。
「じゃあわらわも聞きたいのだけどぉん、どうしてその陸ちゃんが自分のサーヴァントだけを連れてこっちに向かってきているのかしらぁん?」
「何だと…!?いや、その手には乗らない。
これ以上虚言を弄するならすぐにでも斬って捨てるぞキャスター!」
猛るセイバーを歯牙にもかけずにクスクスと不気味な笑いを浮かべるキャスター。
そんなセイバーに取り合わずに士郎にある提案を持ちかける。
「士郎ちゃん、もし気になるならこの場でわらわの金霞帽を投影しても構わないわよぉん?
貴方解析とかコピーとか得意でしょぉん?
これが貴方にとって投影したら危険なものかどうかなんてもうわかってるはずよぉん」
「…………わかった、今だけ乗ってやる。投影開始(トレースオン)」
セイバーを手で制しつつ金霞帽を投影する。
神秘と化学の両側面が入り交じった仙人界の宝貝は士郎の投影魔術とは相性が悪く、ワンランクどころの性能低下では済まなかった。
しかしそれでも今この場では必要十分な性能を発揮した。
衛宮士郎と投影した金霞帽の組み合わせで可能なことは精々が数百メートルをごく短時間索敵する程度のことだ。
しかも燃費も異常に悪く姿を隠す機能は再現できない、本物と比べれば贋作どころか粗悪品と呼ぶしかない。
だがそれで十分だった。
肥大化した視野は学園から離れて柳洞寺に向けて移動している天海陸と実体化した陸のセイバーをしっかりと捉えていた。
こちらへの援軍か?だがそれにしてはあまりにも歩みが遅すぎる。
何より目を疑ったのは―――何がおかしいのかゲラゲラと嗤う陸のセイバーだ。
先ほどの温和ながら誠実そのものだった印象とは似ても似つかない。
(何だ、これ―――?)
士郎の背筋を冷たいものが走った。
自分達は何か、とんでもない間違いを犯したままここに来てしまったのではないか。
未だ確かな正体のわからない不安が際限なく膨れ上がっていく。
「シロウ……これは……」
パスが繋がっているからか、セイバーにも同じ光景が知覚できたようだ。
表情から察するに彼女もまた士郎と同じことを考えていたようだ。
キャスターの方を見れば、いっそう不気味な笑いを浮かべている。
「ねえ士郎ちゃん、セイバーちゃん。
貴方たちは“何を理由にして何のために”わらわを討ちに来たのぉん?」
「…それは。いや、貴様が凛のサーヴァントでないことは既に分かっている!
貴様はアーチャーを殺し彼女の新たなサーヴァントに収まり、令呪を使われた腹いせに凛を殺したのだ!
それだけではない!先ほども切嗣と結託してルルーシュのギアスの情報を切嗣に流し、ガウェインを操らせて貴様を最も警戒していたライダーとハジメを殺させた!
百歩譲ってリクたちが殺し合いに乗っていて、漁夫の利を得るためにここに向かっているのだとしてもこの事実は最早動かない!」
「アンリマユ、宝石剣ゼルレッチ、大聖杯にアインツベルンの用意した小聖杯」
「っ!?」
キャスターの口にした四つの単語は二人を動揺させるには十分な重みがあった。
ムーンセルの事情に詳しい太公望やガウェインも士郎達に聞くか学園で調べるまで第五次聖杯戦争の詳細は知りもしなかった。
であれば、それはキャスターが真実遠坂凛のサーヴァント、それも殺し合いの末の妥協混じりの契約ではなく初期から彼女に配され、一定の信用を得ていたのでなければ知り得ぬ情報ではないのか―――
「それともう一つ、わらわがその切嗣ちゃんとかいう子と結託して太公望ちゃんを排除する。
確かによく出来た筋書きではあるけれど、何か肝心な事を忘れてないかしらぁん?
実際にわらわ側にはそれなりに利益があったけれど、その切嗣ちゃんとやらはマスターの制御のないキャスターのサーヴァントの言う事をあっさり真に受けて数時間足らずで作戦決行しちゃうようなお間抜けさんなのぉん?」
「!!!」
セイバーの瞳が限界まで見開かれる。
わかった、先ほどから感じていた僅かな違和感の正体がわかってしまったのだ。
セイバーはかつて衛宮切嗣のサーヴァントであったが故に。
切嗣は良くも悪くも非常に慎重かつ周到な男である。
そして切嗣が動く時は殆どの場合一定以上の勝機あってのことだ。
その切嗣が裏切りのクラスたるキャスターの齎した情報を元にして動く?
有り得ない、そんなことは決して有り得ない。
それが衛宮士郎の養父ではなく魔術師殺し・衛宮切嗣であればなおさらだ。
「先ほどのランサーとの戦闘はお互い宝具を使った以上相当に目立っていたはず。
切嗣かあのライダーがそれを監視していたとすれば、キャスターからの情報提供などなくてもルルーシュのギアスは把握できる…!
いや、それだけの確信がなければ切嗣がああも大胆な策に出るはずがない!」
「…セイバー、それだけじゃない。
こいつの宝具と能力でアーチャーを、あの野郎を倒すのは…恐らく無理だ。
こいつは防性に特化したサーヴァントだ、攻撃にはまるで向いていない」
地面に落ちた五火七禽扇とキャスター自身を見比べた士郎が分析の結果を伝える。
確かにこのキャスター、蘇妲己は魔術師の英霊としては一級品だ。
が、それは戦闘者として一流であることを意味しない。
それに無限の武具を扱えるアーチャーを五火七禽扇だけで圧倒するのは無理がある。
先ほど失った宝具、傾世元禳にしても同じ事だ。
アーチャー、英霊エミヤが持つ固有結界“無限の剣製”には使い方次第でAランク以上の威力を叩き出す剣も防御突破の概念を持つ剣もいくらでも存在する。
加えて奴自身防御用の宝具も少数ながら投影できる。
こと直接戦闘で英霊エミヤシロウが蘇妲己に痛手も与えられず完敗する事など士郎には考えられない。
遠坂凛という強力なマスターがついているのであれば尚更だ。
「それに、貴方たちが信じていた“妲己ちゃん☆黒幕説”を吹き込んだ人間。
それって果たして誰だったのかしらねぇん?」
「…!確かにこれは全てリクや彼のサーヴァントが言っていた事だ。
だがリクはルルーシュのギアスにかかっていた!
我々に嘘などつける、はずが……いや、待て」
嘘がつけない?ギアスにかかっていた?
その理屈では直前にキャスターの襲撃を受けているのに陸のセイバーが何の対策もしなかったということになる。
ルルーシュのギアスはサーヴァントからすれば直前の魔力の高まりや微細な予備動作が丸見えだ。
キャスターに敗北したという前例があるのにそれを未然に防げなかった、というのは流石に手落ちが過ぎないだろうか?
それに金田一も陸のセイバーの不自然な能力の低さに疑問を持っていた。
加えて短い間だが行動を共にしたことで彼のセイバーが何らかの形でキャスターの適性を持っている可能性は十分有り得るとセイバーは踏んでいる。
にも関わらず主人を守るために何の対策も用意せずルルーシュのギアスを止める素振りすらなかったというのか?
「なあセイバー、もし天海のセイバーが魔術やそれに近い能力を持ってるとしたら、前提が全てひっくり返ることになる。
実際俺から見てもあいつは純粋な剣使いって感じじゃなかった。
お前と一緒に戦ってるんだからそのぐらいは見分けられる」
「…今となってはその可能性も疑わざるを得ないようですね。
私はキャスターならばどのような小細工を弄していても不思議ではない、そう思っていた。
勿論今もこのキャスター、蘇妲己は信用に値しないサーヴァントです。
しかし、リクのセイバーに魔術の心得があるとすれば、小細工を使うという可能性はそのまま彼らにも該当する…!」
例えば、天海陸とそのサーヴァントには最初からギアスあるいは魔術への対抗策があったとすれば。
士郎とセイバーが信じてきた“ギアスをかけられた人間は嘘がつけない”という論拠は根本から崩れることになる。
そしてギアスをかけられた際に天海陸が嘘の証言を行なったとすれば、そうする理由はもはや一つしかないのでは―――?
「…しかし、だからといってキャスター、貴様が信用できるという事にはなり得ない。
確かにリクにも注意を向けるべきなのかもしれない。
だが、我々の思考を誘導する貴様の罠という可能性とて捨てきれない」
「確かにわらわの言葉ではこれが限界ねぇん。
魔術師のサーヴァントは信用できない、実に正しい一般論よぉん。
じゃあ、わらわ以外の貴方達が信用する人間の言葉ならどうかしらぁん?」
そう言うやキャスターは懐から黒い長方形の物体を取り出し、士郎の足元に転がした。
見たところそれはICレコーダーのようだった。
罠に乗るようで癪ではあったが自分達の考えが正しければ既に事態は切迫しつつある。
魔術的な仕掛けが施されていない事を確認し、慎重に再生ボタンを押した。
『あ~テステス、本日は晴天なり。
って聖杯戦争中のSE.RA.PHで雨なんぞ降るわけもないか。
わしはライダーのサーヴァント、真名は太公望。
今これを誰かが聞いておるという事はわしらは道半ばで脱落したという事だろう。
もしこれを聞いている者が殺し合いに乗らず、この聖杯戦争からの脱出を考えておるのであれば今からわしが話すことを聞いてほしい』
聞こえてきたのはつい先ほど消滅した仲間、太公望の声だった。
しかし何故こんなものが、そもそもこんな代物を残しているなら何故教えてくれなかったのか。
そんな士郎の疑念に答えるはずもなく、ICレコーダーはただ機械的に仲間の声を再生していく。
『まず話しておきたいのは脱出を志す人間にとってある意味最大の障害となるであろう者たちと現在わしらが関わっておる参加者の死の真相についてだ。
事の発端は午前8時20分頃、マスターを失ったキャスターのサーヴァント、わしの同郷でもある蘇妲己が柳洞寺に駆け込んできたことだった――――――』
ここからは士郎達も知っている事だった。
といってもあの時点でキャスターが話した情報が主だったものであるが。
一応この段階で判明していた陸とこなた及び彼らのサーヴァントの情報も入っていた。
『―――以上がわしと仲間たちで協議した現時点での行動方針だ。
そしてここからはわし自身のこの事件に関する見解を述べたい』
「っ!!」
これは士郎達も聞いていないことだ。
いや、恐らく太公望自身落ち着いたら話す気でいたのかもしれない。
何しろルルーシュは別行動中で士郎に至ってはお世辞にも平静とはいえない精神状態だったのだから。
『まず恐らく最も怪しいであろう妲己だが…わしはこやつが遠坂凛殺しの直接の犯人ではないと思う。
だがこやつが潔白ということもない。
こやつは索敵と自身の隠匿に特化した宝具“金霞帽”と絶大な防御力と強力な誘惑(テンプテーション)能力を備える羽衣型の宝具“傾世元禳”を持っておる。
まず口実を作ってマスターと別行動を取り、それら宝具を上手く使い他者が遠坂凛を殺しやすい状況を作り出す。
そして首尾良く遠坂凛を殺させた後、魔力探知にかかりにくいNPCを操ってマスターの令呪のみを手にし、この円蔵山という土地と契約した。
まあぶっちゃけわしがあやつに直接聞いて確かめたというのもあるがな。
ともかくあやつは自分は極力手を汚さず他人に手を下させるタイプだ、直接マスターを殺すなんてチープな真似はするまいよ』
そんな話は初耳だ、しかし太公望を責めるのも酷だろう。
知り合い同士でしか通じない論拠をあの状態の士郎が素直に受け入れられたかどうかは怪しい。
『もちろんそれだけというわけではない。
最大の理由はあやつがこの土地との契約が出来たという点だ。
人間相手の契約と違って土地との契約というのはあまり融通がきかん。
加えてムーンセルは管理の怪物、自らのマスター以外の令呪で土地との再契約が出来るなどという事態を容認することはまず有り得ん。
そもそも本来マスターが主体となる聖杯戦争で、サーヴァントだけが他人と再契約することも消滅の危機もなく存命しているという事自体が反則ギリギリの行為だからな。
それは妲己であろうと変わらん。他人から見れば万能に見えるあやつもサーヴァント化している以上少なからず制約は受ける。
これらの事から、少なくとも妲己のマスターが遠坂凛であったというのはほぼ疑いない事実だ』
「…………」
太公望の解説を聞きながらキャスターを見れば、妙に得意げな顔で笑っている。
やはりこれは―――
「わらわの用意したもの、ではないわよぉん」
こちらの考えを見透かしたように否定の言葉が入った。
「わらわならNPCを操ってこういう現代機器を手に入れることは出来るわぁん。
でもそれを読まれる可能性がある時点でこれを使って自分の潔白を証明なんて策は取らないわぁん。
多分太公望ちゃんが金田一ちゃんのクレジットカードを使って勝手に買ったものでしょうねぇん。
もしかしたらスープーちゃんに買いに行かせた可能性もあるけれどぉん」
ちっちっちと指を振りながら語るキャスターに釈然としないものを感じながらも続きを聞く。
『では妲己でなければ誰が遠坂凛を殺したのか。
…うむ、もったいぶってすまんが、これに関してはハッキリとした名前を出す事は控えたい。
現時点でわしらが知っておる情報は大半が伝聞かつ断片的なのだ。
わしが少ない情報から誤った推理をし、全くの見当違いな人物を犯人として脳裏に浮かべている可能性があるからだ。
だが伝えられることが何もないというわけでもない。
これは聖杯戦争だ、敵マスターを殺すという行為に至ったからには必ず相応の理由がある。
もしこれが内部犯であれば、犯人には単に敵マスターを倒す以上に、遠坂凛個人を殺すことによって得られる明確なメリットがあったはずだ。
故にもしこの件について調べるのであれば当時遠坂凛の周辺にいた人物。
とりわけ遠坂凛の死亡後に利益や恩恵を得た人間がいたかどうかをまずは疑うのだ。
最も利益を得た人間こそが最も疑わしい、まあ推理の基本と言われれば反論は出来んのだが。
それとわしが脱落した後もまだ妲己が生きているようであれば、早急に止めを刺すのだ。
あやつは文字通りの意味で人を人とも思わぬ愉快犯、わしらの監視が無くなれば何をしたとしても不思議ではない。
良いか、止めを刺すのだぞ。絶対にキッチリと止めを刺すのだぞ』
一度再生を切る。続きはあるようだが今は状況が差し迫っている。
目の前にはキャスターが、そして今や限りなく怪しい人物となった天海陸とセイバーが何を狙ってかこの柳洞寺に近づいている。
早急に結論を出さなければならない。
「…最も利益を得た人間。少なくともコナタとライダーではないでしょう。
特にライダーは先ほども私と共に最前線で戦っていた。
その他の状況から鑑みても凛の死で大きな恩恵を得たとは考えにくい」
「だとしたら……天海、なのか?」
「マスターとサーヴァント、どちらが主導しているのかまではわかりませんが恐らく。
現に彼ら、特にセイバーの方は能力の低さ故に先ほどは危険度の低いルルーシュ達の護衛に回っていました。
切嗣のライダーに狙撃こそされましたがあれは誰にとっても計算に入れられる要素ではなかった。
そして何より、私達はリクのセイバーの助言に従ってキャスター討伐に赴いた。
いいえ、はっきりと言えばあのセイバーこそがリク達の集団の中で最も大きな発言力を持っている」
「ああ、確かにあいつがリーダーシップを取っていた。
あとは遠坂を殺した理由か目的だけど、あいつの能力の低さから考えたら答えは一つしかない。
弱いサーヴァントが手っ取り早く自分を強化するなら魂喰いしかないんだ。
そしてターゲットが遠坂なら、その効率だって段違いだ」
これまでバラバラだった点と点が繋がり、一本の線になっていく。
未だ確定ではないが、もう彼らを無条件で味方とは考えるべきではないだろう。
とすれば残る問題は―――
「お話は終わったかしらぁ~ん?
さっ、わらわの気が変わらないうちにザクっとスパっとやっちゃってぇ~ん♥
一流の悪役ヒロインは引き際を弁えてるものなのよぉん」
相変わらず抵抗の様子すら見せないキャスターである。
この女は聖杯戦争の趨勢自体眼中にないのではないだろうか?
「その前に問うておこう、貴様が凛を見殺しにしたというのは事実か?」
「そうよぉん、ご主人様は魔術師のわりに良い人だったのだけれど、ちょっと正義感が強すぎたわぁん。
わらわって束縛されるのあんまり好きじゃないのよねぇん」
「……そうか、ならば最早何も言うことはない」
今度こそ迷わず剣を構え念のため周囲の魔力に気を配り、そして一息に無防備なキャスターに迫り、その心臓に刃を突き立てた。
微かな吐血を漏らしながらもその微笑が崩れることはない。
「…キャスター、あんた一体何を考えてるんだ?
あんたは間接的でも遠坂を裏切ったんだろ?
だったら、どうして俺達に手を貸すような真似をしたんだ?
アサシンまで召喚したのは勝つためじゃなかったのか?」
その微笑みの意味が、彼女の思考がわからなくて。
思わず士郎の口から出たのは最も気になっていたことだった。
全身が崩れゆく中、キャスターは最期の時まで超越者じみた余裕を崩すことなく答えた。
「わらわは基本楽しければオールオッケーなのよん。
小次郎ちゃんを召喚したのもその方が面白そうだから。
この聖杯戦争も最上とはいかなかったけど中々楽しかったわぁん。
陸ちゃんへのささやかな意趣返しも出来たし、士郎ちゃんたちの苦悶に歪む顔も中々見ごたえがあったわねぇん。
でもそうねぇん、敢えて一つだけ理由を挙げるなら―――」
一度だけ意味深に目を閉じ、悪戯っぽい笑みを浮かべた。
「―――わらわが遠坂凛のサーヴァントだから、かしらぁん」
そんな言葉を残して、稀代の悪女・蘇妲己は完全に消滅した。
主を策略で見殺しにしながら、最後の最後で主命を果たした魔術師の英霊。
その真意はどこにあったのか、それを知る者はもういない。
【キャスター(蘇妲己)@藤崎竜版封神演義 消滅】
・虚飾を払うは―――
それからはほとんど陸とイスラも知っている通りだ。
二人に強い不信感を抱いた士郎とセイバーは一計を案じた。
まず士郎が二人に第五次聖杯戦争に関する事柄を聞く。
このムーンセルの聖杯戦争にしか参加していない英霊でもその事について知っている可能性、つまりは蘇妲己が凛のサーヴァントではないという可能性もまだ僅かには存在していたからだ。
そしてイスラの返答によって蘇妲己が凛のサーヴァントであることが概ね証明されたと同時、士郎の射撃と数百メートル以上離れた地点から全開の魔力放出で一瞬にして距離を詰めたセイバーの同時攻撃で陸とイスラの正体を暴いた。
といってもこの攻撃で二人を殺すつもりはなかった。
一瞬でもイスラを足止めし、セイバーの直接攻撃―――本当に何の能力も持っていないようなら寸止めが出来るよう剣に込めた力は三割程度に抑えていたが―――で陸の正体を見極めるという策だった。
いや、実際には策とも呼べない強引な賭けだった。
これでもし陸とイスラがシロであれば今度こそ殺人者の謗りを免れないところだったのだ。
この場にルルーシュでもいればもっと穏当かつ確実な策を閃いたのかもしれないが。
しかし結果としてこれで陸とイスラの正体はほぼ完全に露見した。
どころか陸がギアスにかかっていなかったという物証まで入手できたのは期待以上の成果といっていい。
「これで全ての疑問は解決した。
凛を殺す際、どうやってあのオーズを引き離したかが引っ掛かっていた。
しかしそれほどの力ならばごく短時間彼の注意を引くぐらいは可能だったはずだ。
…まだ何か言うことはありますか?」
セイバーの最後通牒に等しい言葉に陸もこれ以上言い逃れは出来ないことを悟った。
「ハハッ…何だよこれ。キャスターが抵抗もしないとかどうなってんだよ。
しかもこいつらに塩まで送っちゃってさあ、何なんだよマジで。
話が全然違うじゃないか…どうなってんだよイスラアアッ!!!!」
「……済まないリク。僕の見積もりが甘かったらしい」
「…謝るなよ、謝ってんじゃねえよ!
何か、何かないのかよ!?お前がチャンスだって言うからここまで来たんだぞ!?
なのに、なのにこんな……!お前のせいだぞこのハズレサーヴァント!!!」
「…………」
こんなはずではなかった。
イスラはこれまでに聞いていたキャスターの動向と、先ほどのアサシンの存在からキャスターは勝ち抜きを狙っていると確信していた。
というよりその確信があったからこそ今までのイスラの嘘は聞いた者に強い説得力を与えていたのだ。
そもそもキャスターがさしたる願いも目的も持たずに聖杯戦争に参加し、なおかつ自分の娯楽のためだけに場を引っ掻きまわして、思わせぶりな行動を取ってきたなどどうやって想定しろというのか。
否、それを言い出せば彼らの嘘が露見した理由の多くはこれまで知らなかった、知る機会のなかった要素によるものばかりだ。
通常の域を大きく逸脱した解析魔術を扱える衛宮士郎。
キャスターと同郷の出身だった柳洞寺のライダー、太公望の存在。
関係者にのみ通じる第五次聖杯戦争の詳細。
セイバーであるイスラには考えもつかない、土地そのものと契約するという手段によって客観的に自らが遠坂凛のサーヴァントであることを証明したキャスター。
かつてイスラ自身が口にした情報戦における遅れ。
それがこんな、あと一歩という局面で状況を完全にひっくり返す決定打になるとは思いもしなかった。
だがイスラがそう考えるのも無理もないことだ。
何しろ陸とイスラのここまでの道中はあまりにも上手く行き過ぎていた。
有り体に言えばとにかく運が良かった。
綱渡りに等しい遠坂凛の暗殺を見事こなたと映司に気付かれることなく成功させた。
この時キャスターの策で凛の令呪を奪われたが、それは単にキャスターの用意が陸とイスラを上回っていただけだ、二人の失策ではない。
さらに事前に用意した反魔の水晶がギアスに対してこれ以上無いほどに効果を示したこと。
つい先刻の切嗣陣営の襲撃の際最も少ない被害で切り抜けられたこと。
切嗣の策によって結果的に柳洞寺にキャスターが孤立し、さらに能力面で厄介な士郎のセイバーにキャスター討伐を押し付けることに成功したこと。
これだけの幸運に恵まれたことが、陸とイスラの行動を大胆にさせた事は否めない。
最早情報戦の遅れは完全に覆した、後は柳洞寺の魔力の流れを乗っ取れば策を弄する必要もない。
キャスターや士郎らもお互い潰し合わせさえすれば、ここまで温存してきたイスラの魔力でどうとでも処理できる、イスラをしてそう信じて疑わないほどの好機だった。
その先が奈落の底に続く落とし穴であることなど考えもせずに。
だがそれを誰が責められようか。
聖杯戦争において敵が戦力を分断させた時を狙って仕掛けるのも、大量の魔力を得られる好機を逃さないのも正しい戦略だ。
そもそもキャスターがイスラの予想した通りの勝利を狙う、常道のサーヴァントであれば彼らの行動が問題になる事など本来有り得ない筈だった。
繰り返すが彼らの取った戦略は普通なら正解であり、成功への最短ルートだった筈なのだ。
(しかしそれでも…もっと慎重に事を進めるべきだったのかもしれない)
後悔は決して先に立つことなど無いが、それでも悔やんでも悔やみきれない。
振り返って考えれば、イスラが陸に性急な行動を提案した背景にはあの男、衛宮切嗣の影があったのだろう。
自分達の嘘が一切通じる余地のない危険な敵手、それに少しでも対抗するにはこちらも力をつける必要がある、そう思った。
衛宮切嗣のサーヴァント、仮面ライダーディケイドとやらがこなたのライダー、オーズを倒すことに執着しているらしいというのもあった。
何せこの先こなたらと行動を共にする限り常にあの陣営の脅威に晒されることになるのだ。
先ほどはルルーシュが標的になり、士郎のセイバーが盾代わりになってくれたおかげで事なきを得たが、これからはそうではないのだ。
そういった理由から敢えて別行動を取るという考えに至ったのだ。
上手くすればイスラが柳洞寺の魔力を得るまでの間、こなたらが切嗣とディケイドをおびき寄せる囮になってくれるのではないかという考えもあった。
結局のところ、そうした目論見は全てにおいて裏目に出たのだが。
ここまでの幸運の連続こそが逆に陸とイスラから慎重さを奪う不幸の原因だったのだ。
「シロウ、決断を。この者たちを放置すればコナタを始めとした多くの参加者にとっての災厄となるでしょう」
思考している間にも士郎のセイバーが主人に陸とイスラの処断を促す。
キャスターが戦わなかったせいでセイバーの魔力はほぼ全く消耗されていない。
まともに戦えば分が悪いどころではない。
とはいえこちらがそれに付き合う道理はない。
(リク、ここは一度退いて態勢を立て直そう。
不意をついて令呪を逃走用に使ってくれれば十分に―――)
「……ろせ」
(リク……?)
「あいつらを殺せ!!イスラアアアアアアアッ!!!」
陸の腕から令呪の輝きが放たれる。
その強大な魔力は逃走ではなく殺戮の強制としてイスラにのしかかる。
「なっ…リク!?一体何を―――」
「お前こそ何言ってんだよ!状況わかってんのか!?
バレたんだよ全部!!なのに逃げてどうするってんだよ、ええ!?
こいつらが泉やルルーシュにオレ達の事を話せば全部終わりだろうが!
だったら…だったらもう殺すしかないじゃないかっ!!」
陸の表情は今までイスラが見たこともないほど強ばり、眼は血走り微かに涙が滲んでいる。
剣を握る手は震え呼吸は荒く、平静を失い半狂乱になっていることは火を見るより明らかだった。
無理もないことだ、全てが上手くいっていた状況から瞬く間にどん底まで叩き落とされたのだ。
天海陸はイスラ・レヴィノスほど完成されたメンタリティは有していないのだから。
「………“紅の暴君(キルスレス)”」
イスラもまた事ここに至って陸を諌めることは不可能だと悟った、悟らざるを得なかった。
今まで陸がイスラに一方的に同族嫌悪の感情を抱きながらも主従関係が成立していたのは、イスラの知略が多大な成果をもたらし、陸もそれを割り切って受け入れてきたからだ。
だが今回のあまりにも大きな失態によってイスラは陸の信用を大きく損なってしまった。
実際には失態と呼ぶには酷なものであるとしても今の陸にそこまで冷静に判断する力は無い。
ここでこれ以上陸に意見すれば例えこの苦境を切り抜けたとしても、この先の関係修復が不可能になってしまう。
それならば無理に令呪に逆らわず、全力で目の前の敵を屠る事に専心するべきだ。
魔剣の真名を解放し容姿が大きく変化したイスラだが、当然それだけの事で終わる筈が無い。
その身から発される魔力は今までが嘘のように荒く猛々しい。
「シロウ!この者の相手は私が引き受けます!」
その禍々しい力がマスターに及ぶ事を警戒したのだろうセイバーがイスラに突進し、引き離しにかかる。
イスラもまた陸の力量を信じてセイバーの誘いに乗る形となった。
そして陸も刃旗を手にし、常人には視認すら困難な速さで士郎に斬りかかった。
咄嗟に投影した干将・莫耶で受け止めるが、膂力が違いすぎるためにジリジリと押される格好となる。
「ぐっ―――!天海、お前は………!」
「そうさ、お前らさえ、お前らさえ消せばまだやり直せるんだ!
遠坂だって殺ってやったんだ、もう躊躇うもんかよ!!」
先ほど戦ったランサーのマスターが操っていたイザナギですら可愛く思えるほどのパワーとスピードの前にまたも防戦を余儀なくされる。
技量はまだまだ発展途上ながら、サーヴァントにすら迫る理不尽なまでの身体能力はただそれだけでほとんどのマスターを圧倒する。
―――だがここに一つの例外が存在する。
「隙だらけなんだよっ!!」
陸の横薙ぎの斬撃ががら空きになった士郎の右脇腹を襲う。
必中を確信して振った大剣はしかし、白と黒の双剣に受け流された。
僅かに態勢を崩した陸を士郎の反撃が襲うが意識圏によって止められる。
だが完全ではない、短剣が障壁をガリガリと削り、ついには意識圏を叩き切った。
「くそっ、意識圏が!?」
予想だにしなかった事態に慌てて距離を取る。
サーヴァントならばいざ知らず、魔術師の物理攻撃で意識圏を断ち切られるなど想定外だ。
いや、よくよく見れば士郎が手にしている双剣からはイスラが持っている紅の暴君と同じ気配を感じる。
(宝具ってことかよ…!チートしてるんじゃないだろうなコイツ!?)
物理攻撃に対して絶大な防御力を発揮し、棺守や同じ刃旗使い、あるいは超常の存在たるサーヴァントでなければ傷つける事すら不可能に近い意識圏。
だがそれは決して全てのマスターに対して無敵を誇る事を意味しない。
陸と同じく英霊に迫る戦闘能力に加え、高ランクの宝具の担い手でもあるベルンの覇王・ゼフィール。
そして特異な起源と魔術特性から宝具級の神秘すら投影で再現してのける錬鉄の魔術師・衛宮士郎。
彼らの操る宝具の強力な神秘は刃旗使いの意識圏を突破することすら可能とする。
そう、この二人だけはこの聖杯戦争において例外的に正面から天海陸と対等に戦える存在なのだ。
「でもな、スペックじゃこっちが圧倒的なんだよ!!」
気を取り直して再度高速で斬りかかる。
伊達に棺守との戦いを生き抜いてはいない、相手に意識圏を突破する手段があるとわかっていれば相応の戦い方をすれば良いだけだ。
「づ、は―――!」
しかし士郎も粘る。怒涛の勢いで連撃を浴びせかけるも、常にあと一歩というところで受け流されてしまう。
時折大きな隙を見つけて、そこに正確に打ち込んでいるにも関わらず必ず防がれるのだ。
(何なんだコイツ!?強くはないのにやりにくい!)
決して力強くもなければ速さもない凡庸な剣捌きを攻めあぐねているという現実に焦りが募る。
最初から刃旗使いとしては強大な力を持っていた陸には思いつくことさえ出来ないだろう。
衛宮士郎が天海陸に白兵戦において格段に劣っている、その事実こそを武器にして渡り合っているなどとは。
士郎はただ守るだけでは陸の猛攻を凌げないと判断するや、時折わざと隙を作ることで陸の攻撃箇所を誘導しているのだ。
かつて自身の未来の姿、英霊エミヤの腕を移植されていた時期に頭に流れてきたあの男の経験値がこの無謀ともいえる策を可能としていた。
とはいえ今の士郎自身の力量は英霊エミヤに到底及ばない。
この戦法とて一級のサーヴァント相手に通じるほどの域には達していないが、今の冷静さを失い視野狭窄に陥った天海陸になら十分に通用する。
だがそれも長くは続かない。
膂力や俊敏性に限らず、持久力や反応速度などあらゆる身体的要素において衛宮士郎は天海陸に大きく遅れを取っている。
意識圏を破る手段を持っていようが戦闘者としての基本性能の差は小手先の戦術だけでカバーしきれるものではない。
あと十分と持たずに衛宮士郎は天海陸に押し切られてその身を両断されて敗北する。
「―――投影開始(トレースオン)」
ならば勝てるものを用意すればいい。
陸の剣戟を防ぎながらも自己の内に埋没し、投影する剣を選んでいく。
「――――憑依経験、共感終了」
呪文を紡ぎ、衛宮士郎だけの弾丸を順に装填していく。
「―――工程完了。全投影、待機(ロールアウト、バレットクリア)。
―――停止解凍(フリーズアウト)」
ここに来てようやく陸の目にもその異常が見てとれた。
陸の攻撃を防いでいる士郎の真上に十六もの刀剣が突如として出現した。
魔術師ではない陸でもわかる、宙に浮かぶその剣群はどれもが一級品、すなわち宝具であるのだと。
「おい、冗談だろ……?こんなの反則どころじゃないだろ……!」
まるで悪夢だ。
あれらが一発でも直撃すれば刃旗使い、いやサーヴァントであっても致命傷になり得る。
意識圏で防げるか?馬鹿か、そんな生温い手を打つ相手なものか。
何より相手の懐に飛び込みすぎた、命脈を保つべく意識圏を全開で展開しつつ全速力で飛び退くが間に合うか。
「―――全投影連続層写(ソードバレルフルオープン)!!」
宙空から剣群が陸の命を刈り取るべく一斉に襲いかかる。
だが活路はある、一発でも命中すればそれで十分と考えているのか剣群は陸の周囲を円状に覆うように飛来している。
(―――いける、真ん中が手薄だ!)
敢えて中央へ動き、万全の態勢を整える。
下手に大きく動いて直撃するよりは中央で腰を据えて迎撃するのが上策。
「な、めるなああああ!!」
十六の剣のうち陸に命中するのは三本。
大剣で二本を弾き飛ばし一本を意識圏で逸らした。
残りは全て陸の周囲を囲うように地面に突き刺さった。
凌いだ、その確信を得たまさにその瞬間だった。
「壊れた幻想(ブロークンファンタズム)」
呪文と同時、弾き、回避した三本と周囲の十三本の剣が一斉に轟音を立てて爆発した。
意識圏でもカバーしきれない、全方位からの爆発と衝撃によって陸の身体は嵐に巻き込まれた木ノ葉のように軽々と吹き飛ばされた。
「ぎ、ああああああああっっ!!!!!」
魔術師ではない陸には何が起こったかもわからない。
棺守や刃旗狩りの男・タカオとの戦いを経た陸だが剣が爆発するなどという知識はない。
もし事前知識があれば真ん中に飛び込んで迎撃するという選択肢は排除して考えていただろう。
壊れた幻想(ブロークンファンタズム)。
宝具に内包された神秘を魔力による爆発に変える宝具の変則的使用法。
その威力は爆発させた宝具本来のランクより一段上の破壊力を持つ。
だが本来聖杯戦争においてこの技が用いられることは無い。
宝具とは担い手の半身、自らの相棒たる宝具を一度きりの爆弾にする英霊などまずいない。
だが何事にも例外は存在する。
特殊な投影魔術によって魔力が続く限り衛宮士郎はいくらでも宝具を用意できる。
この特性を活かせばこのように宝具を使い捨ての砲弾のように扱う事すら可能だ。
もっともこれですら対魔力を持つサーヴァントには多少厄介ではあっても必殺にはなり得ないのだが。
「が…ぐ……、くそっ……!」
朦朧とする意識を気合いで保ちながらよろよろと立ち上がる陸だがその足取りは覚束ない。
反魔の水晶を奪われたことによって対魔力の加護を得られなかったために甚大なダメージを被ったのだ。
服と全身は焼け焦げ、爆発の際に飛んできた様々な破片で体の至るところに切り傷が出来ている。
さらに全方位からの爆音を至近距離で聞いたために聴力にも軽度ながら異常が起きている。
意識圏による防御すら宝具の爆撃に対しては気休め程度にしかなりはしなかった。
「その障壁は全方位には張れないらしいな。
…天海、もうやめろ。言っておくが俺はその気になれば一度に二十七本まで剣を投影して発射できる。
そんな有り様じゃもう避けることも、さっきみたいに戦うことも出来ないはずだ」
これはハッタリだ。
今の士郎には二十七どころか先ほどの半数を投影できるか否かという程度の魔力しか残っていない。
先ほどのアサシンに対して行なった赤原猟犬の真名解放、そして金霞帽の投影と行使。
セイバーの魔力を温存するために支払った代償としては安いが、今この場の戦いには大きな影響を及ぼしている。
「…………」
しかし魔術師でない陸にはそれがハッタリかどうかを判別できない。
士郎も一般人でありながら聖杯戦争に参加した金田一という実例や、ここまでの陸の魔術師らしからぬ言動から陸に魔術の心得はないと当たりをつけていた。
陸は未だ気付いていない。自分が魔術師でなく、魔術の知識も不十分であるという事実がどれほど足を引っ張っているのかを。
(これでもし天海がさっきと同じ調子で攻めてきたら……)
(もしアイツの言ってる事が本当で、まだあれ以上の剣を用意できるのなら……)
お互いに限界が近い、それ故に僅かな時間戦況は膠着する。
―――だとすれば、勝負を決するのは彼らの従者に他ならない。
「はぁああっ!!」
「っ、ぐ―――!」
金属と金属の打ち合う音が響きわたる。
衛宮士郎と天海陸、彼らの主人の戦場より幾分距離を離した池の周辺で二人のサーヴァントは余人には視認すら適わぬ剣戟を繰り広げていた。
攻めているのは衛宮士郎のサーヴァント、アルトリア・ペンドラゴン。
防御に回っているのは天海陸のサーヴァント、イスラ・レヴィノス。
百を越え、千に届くのではないかという程の打ち合いを経ても未だに天秤は傾かない。
「さっきの見えない剣は、く、やらないの、かい―――!?」
「知れた事を、先ほど我が剣を見せた貴様に風王結界が通じると思うほど私は愚かではない」
セイバーは今、手にした黄金の剣カリバーンに不可視の風を纏わせずに戦っている。
何しろ初対面の時に一度真名と共に見せているのだ、サーヴァントならばそれだけで刃渡りや間合いも正確に計れただろう。
ならば通用する望みのない風王結界ではなく、全身の魔力放出に上乗せする。
それに敢えて刀身を晒す事で切れ味は大きく増す。
この敵を相手取るにはこれこそが最上の策だとセイバーは看破していた。
(参ったね、こうまで地力に差があるとは思わなかった。
リク、令呪を使った君の判断は正しかった)
一方のイスラは想像以上の敵の力量に舌を巻いていた。
伐剣覚醒による大幅な能力向上に加え、マスターからの魔力供給不足によって低下していたスキルのランクも令呪のブーストにより一時的に生前同様まで戻った。
はっきり言えば、今この時に限ればイスラは生前を僅かながら上回るほどの性能を得ている。
だからこそセイバーの全力の剣捌きにも一歩も引くことなく渡り合い、時折反撃に転じるまでに拮抗する事が出来ている。
だがそれだけだ。
圧倒的な能力ブーストを得ていてもイスラの剣が騎士王に届くことは無い。
そもそも剣の才能が違う。剣に生きた年月が違う。努力の密度が違う。
悲しいかな、セイバーにとってイスラの太刀筋はどこまでも凡庸な、読みやすいものでしかない。
サーヴァントとしてのステータス以前の、英霊イスラ・レヴィノスの限界ともいうべき壁。
如何に令呪が様々な奇跡を起こせるとはいえ、サーヴァントの技量を限界以上に高めることは流石に出来ない。
どれだけカタログスペックを底上げしようが、剣の力量が英雄レベルに達しないイスラが一級のセイバークラスの英霊と曲りなりにも互角の体を為しているという事実が既にして奇跡なのだ。
ならばイスラが最も得意とする召喚魔法ならばどうか。
確かに竜の因子を持つ騎士王が誇る破格の対魔力の前では暴走召喚とて通じる望みは薄い。
だが何一つとして通用しないわけではない。
例えばダークブリンガーのような物理的な攻撃手段ならば対魔力でも防ぐことは出来ない。
それが暴走召喚、更には令呪の加護も付加されるとあれば必殺の域にまで昇華される。
だが、それは撃てればという仮定の話だ。
「させんっ!」
「ぐっ……!!」
バックステップで距離を取ったイスラだったがセイバーはその上を行く。
魔力放出による急加速で瞬く間に距離を詰め、竜の咆哮の如き一撃を見舞う。
極限まで能力を強化されたイスラでも数歩分の後退を余儀なくされる剛剣からの呵責の無い追撃に晒され、再び剣戟に持ち込まれる。
先ほどから召喚魔法を使おうとする度にこの調子だ。
セイバーの未来予知じみた直感はイスラの召喚魔法の余兆を決して見逃さない。
最高ランクの対魔力を誇るこの身に対して尚魔法を用いようとするその動き。
それこそがイスラがセイバーを倒し得る手段を有しているという何よりの証左。
であればそもそも撃たせないという事が唯一最大の対策になり得る。
これが聖杯戦争。
真名を暴いたことでセイバーはイスラがどのような手札を持つかをある程度把握している。
無論マスターに与えられた透視能力のように詳細にスキルを見れるわけではない。
だが真名がわかれば相手の逸話や偉業といったおおよその得意、または苦手分野もわかる。
それ故に消極的であっても対策を打つ事が可能になるのだ。
「ハアッ!!」
セイバーの黄金の剣が防ぎきれなくなったイスラの身を削る。
覚醒の恩恵ですぐさま傷は塞がるもののその度に魔力を余計に消耗する。
だがイスラにとってはそれ以上に不都合な事がある。
(あの剣、確かアーサー王の選定の剣カリバーンだったか。
間違いなくAランク以上の聖剣だ、これでは呪いを活かすのも難しい…か)
イスラ・レヴィノスはその身に不死の呪いをかけられている。
Aランクに満たない攻撃では決して死に至ることは無い強力なその呪詛は聖杯戦争において極めて有用なスキルだ。
この呪詛を上手く活かせば敢えて敵の攻撃を受けてそこから反撃に転じるという戦法も使えるのだ。
だが通常攻撃がAランクに該当するセイバーの剣にはこの戦法が使えない。
ただでさえ剣士としての地力に開きがあるのだ。
下手に呪いを当てにした戦い方をしようものならそれこそ一瞬で致命傷を受けてしまう。
手詰まり、その単語が脳裏を過ぎる。
「……リクっ!?」
ちょうどその瞬間、イスラの脳をひりつくような感覚が襲った。
それはすなわち、マスターである陸が危機的状況に陥った事を示す。
ほんの一瞬気を取られた、それが不味かった。
「余所見をしている余裕があるのか!」
イスラが陸に気を取られたのを好機と見たセイバーが強烈な大上段を見舞う。
咄嗟に受け止めたが態勢を大きく崩され、次の薙ぎ払いを受け止めた衝撃で大きく吹き飛ばされた。
(不味い、令呪の効果が……!)
これまでセイバーとの戦いを互角たらしめていたブーストの効果が途切れた。
それ故に先ほどまで耐えられた一撃を持ちこたえられなかった。
「リク……!」
いつの間にかマスター達の近くまで移動していたらしい。
陸の方を見やれば明らかに深手を負っている。
何やら士郎と会話しているようだが距離があって聞き取れない。
ともかくこのままではジリ貧になる一方だ。
伐剣覚醒は維持するだけでも大量の魔力を消費するのだから。
先ほどアサシン相手に召喚魔法を数発使わされた事も響いている。
この先に大きく影響するが背に腹は代えられない、改めてこの場からの逃走に令呪を使うよう念話を送ろうとして―――
「イスラ、次の一撃でセイバーを殺せええっ!!!」
主の令呪に再びその身を縛られた。
「その障壁は全方位には張れないらしいな。
…天海、もうやめろ。言っておくが俺はその気になれば一度に二十七本まで剣を投影して発射できる。
そんな有り様じゃもう避けることも、さっきみたいに戦うことも出来ないはずだ」
士郎が降伏を促してくる。
ふざけるな、そんな真似をするぐらいなら最初から聖杯戦争になど参加していない。
だが怒り猛る精神に反して体はついてきてくれない。
全身は絶え間なく苦痛を訴え、足腰がまるで自分のものではないかのように言うことを聞かない。
(もしアイツの言ってる事が本当で、まだあれ以上の剣を用意できるのなら……)
今度こそ天海陸は終わりだ。
ハッタリという可能性もあるが、それがただの楽観でない保証がない。
剣を飛ばす前に斬り伏せるか。無理だ、奴は戦いながらでも剣を生み出せる。
イスラを信じて時間を稼ぐか。論外だ、性質がキャスターに近いイスラは騎士王とは恐ろしく相性が悪い。
(うっ…くそっ、あの野郎容赦なく持っていきやがって……!)
しかも陸の魔力、というより生命力は時間とともに戦闘中のイスラに流れていく。
これでは何のために凛から魔力を奪ったのかわからない。
「…くそっ、くそくそくそ、あんな奴がサーヴァントじゃなければ!
あいつのせいでこんな事になってるってのに、魔力だけは一人前に欲しがる気かよ…!
こんなはずじゃないんだ、こんな……!」
実際のところ、イスラが陸からも魔力供給を受けなければ戦えない原因の一端は陸自身が使った令呪にもある。
令呪の加護で限界を超えた力を発揮しているイスラだが、そこまでして能力を底上げするということは維持に必要な魔力も普段より増すということである。
通常のサーヴァントならば令呪の膨大な魔力で賄われるので問題にはならない。
だが伐剣覚醒を行なったイスラは著しく燃費が悪くなるため、令呪だけでは不足してしまうのだ。
「…天海、どうして遠坂を殺したんだ?
正直遠坂を殺したお前が憎くないと言えば嘘になる。
けど、お前が人殺しに慣れてるわけでも、やりたくてやってるわけでもないのは俺から見てもわかる。
そこまでして叶えたい願いがあるって事なのか?」
「…………」
その言葉にひどく苛立つ。
何を言っているんだこいつは、そんなものは当たり前だ。
願いを叶えるための殺し合いが聖杯戦争だろうに。
そんな事を思ったからだろうか。
気付けば口は今まで鬱積していた感情を吐き出していた。
「…ああ、そうだよ!悪いかよ!
だってそれが聖杯戦争なんだろ!?
遠坂は敵だったんだ!ルールなんだから殺したって仕方ないだろ!?
願いは無いとか聖杯を壊すだとか、お前らの方がおかしいんだ!!
人の気も知らないで勝手なことばっかり言いやがって!!
オレが好き好んで人殺しなんかやってると思ってるのかよ!?」
一気に捲し立てて荒い息をつく。
平時の陸なら決して口にしないような事だが、大きく精神が乱れた今の陸にそんな分別は無い。
「…確かに俺はお前が何を願って参加したのかなんて知らない。
でもな天海、これだけは言えるぞ。
お前の気持ちや願いが誰にもわからないのは―――お前が嘘をついたからだ」
「――――――!!」
無表情で告げた士郎の言葉は、これ以上無いほどの正論だった。
嘘をついたのなら本当の気持ちが誰にも伝わらないのは至極当然だ。
「はっきり言うぞ、お前に殺し合いなんて向いてない。
お前が持つべきだったのは嘘をついて人を殺す意思なんかじゃない。
遠坂や泉みたいな、人を思いやれるやつに本当の気持ちを打ち明ける勇気だったんだ。
お前の願いが何かはわからないけど、それでも何かは違ったはずだ。
……それだけで、良かったんじゃないのか?」
「……まれ。黙れ、黙れよっ!!」
言うな、それ以上言わないでくれ。
だって自分はもう既に人を殺してしまった、伸ばされた手をはねのけた。
認めてしまえば自分のしたことは全て無駄になってしまう。
この聖杯戦争だけではない、もう一度天音に会うために嘘をついたことも、戦ってきたことも何もかもを無駄にしてしまう。
その時金属音が聞こえ、遠目にイスラが吹き飛ばされているのが見えた。
(―――ふざけるなよ)
倒せないのはまだしも、令呪を使ったにも関わらずこうまで押されるとはどういう了見なのか。
あまりの逆境の連続に、陸の頭の中でプツリ、と何かが切れる音がした。
殺せ、殺せ、殺せ。
あのセイバーも、うるさい衛宮士郎も殺してしまえばこの苦境もチャラに出来る。
目の前の現実に嘘をつき、逃避するために陸はついに二画目の令呪に手をかけた。
「イスラ、次の一撃でセイバーを殺せええっ!!!」
左手の甲から強烈な輝きが放たれる。
次の一撃で打倒する、これ以上なくシンプルかつ強固な命令による最強の一撃は如何に騎士王といえど耐えられまい。
「天海―――!くっ、セイ……っ!?」
間を置かず士郎に斬りかかる。
令呪は使わせない。元々サーヴァントに力量差があるのに令呪を使われればその時点で敗北が確定してしまう。
度重なるストレスの連続でもはや理性が崩壊しつつある陸にもまだその程度の判断力は残されていた。
「だぁぁあああああああああああーーーーー!!!!」
「ぐっ、クソっ……!」
完全に我を忘れたかのような激情に身を任せた突撃もこの時ばかりは極めて効果的だった。
思考も戦術もない単純極まる剣捌きは、対峙する両者の身体能力に開きがあるならばそれだけで脅威となる。
少しでも令呪の使用に集中しようとすれば一瞬で両断される猛攻の前に士郎にはただ防ぐ以外の選択肢がない。
一方でイスラもまた令呪の強制力によってセイバーを滅するべくかつてない最短動作で本来の暴走召喚の限界すら超えた召喚魔法を放とうとしていた。
陸がこうなる事を止められなかった後悔はある、だがそれも目の前の敵を葬ってからだと自身に言い聞かせる。
如何にセイバーといえどこれは止められないし、防ぐことも出来まい。
避けるという選択肢はあるがそれもさせる気はない。
この二度とはない最強の一撃は常套の手段では躱せまい。
―――だが、敵もまた常套ではない手段を用いてくるとまではイスラにも想定できなかった。
「やらせんっ!!」
何を思ったかセイバーは自らの半身であるはずの黄金の剣を、手首のスナップを利かせた最短動作のスローイングで投げつけたのだ。
頭部を狙った投擲に止む無くイスラが迎撃しようとしたまさにその瞬間、セイバーは壊れた幻想でカリバーンを爆破した。
「ガッ!?」
上級宝具の壊れた幻想による爆発には不死の呪いと令呪の援護を受けたイスラもたまらず顔を抑えてよろめく。
(ここだ―――!)
立て直しにかかるごく僅かな瞬間、常勝の王はそれを決して見逃さない。
ここを逃せば討たれるのはセイバー自身であると理解しているが故に。
瞬時に顕現させたセイバーの真なる宝具、その剣に纏わせた風を解放する。
「風よ―――吼え上がれ!!」
セイバーの持つ宝具の一つ、“風王鉄槌(ストライク・エア)”
その変則使用、荒れ狂う暴風の塊は魔剣の担い手の肉体を押し潰し、空高く打ち上げる。
そして至高の聖剣が輝きを発し、隠された真価を発揮しようとしていた。
その剣が示すは全ての人々の祈り。
想念によって鍛えられた最強の聖剣。
その身を風の鉄槌で潰され空高く打ち上げられながらも、イスラは確かにそれを見た。
最初に自分が殺した赤の少女がいた。
白い長髪に赤い瞳の雪のような少女がいた。
雪の少女の傍らに立つ巨大な鎧武者がいた。
ボサボサの髪を後ろに結った少年がいた。
少年の後ろに立つ道士服の男がいた。
つい先ほど踏み越えた群青色の侍がいた。
セイバーの真なる剣は輝きを増し、今ここに騎士王は手にする奇跡の真名を謳う。
魔剣の伐剣者(セイバー)よこの輝きの前に退け、虚飾を払うは星の聖剣。
其は―――
「―――“約束された(エクス)」
「勝利の剣(カリバー)”――――――ッ!!!」
その極光はさながら星の輝きの体現であった。
ただ一人のヒトガタに向けて放つにはあまりに巨大な光の斬撃は身動きの取れないイスラ・レヴィノスを容易く飲み込む。
その身にかけられた不死の呪いなどこの最強の聖剣の前では如何ほどの意味も持たない。
まるで英雄譚に出てくる三流悪役のようだ。
エクスカリバーの極光に身を焼かれながら、最期にイスラはそんな事を思った。
魔剣の適格者たる自分が聖剣の担い手に討たれるとは何たる皮肉か。
しかしそれは些細な事だ、どうせ自分はまたあの無間地獄に戻るだけだ。
だがこの敗北を悔しいと感じるのは間もなく自分の後を追うことになるマスターのせいだろうか。
口ではからかいながらも、イスラは内心陸を認め、少なくとも先ほどからは本気で力になろうと思っていた。
だがそれを伝える機会はなかった、嘘つきでしかない自分に真心を口にすることは許されないということか。
陸を勝者にすることが出来なかった、姉を求めた自分と重なる少年の望みを叶えることが出来なかった、ただそれだけが心残りだ。
結局自分達はキャスターの掌の上で踊らされていただけだったというのか。
(これでは、あまりにも――――――無念だ)
その刹那の思考を最後に、嘘と謀略で勝利を掴もうとした反英雄は跡形もなく消え去った。
その存在そのものが、最初から実体のない嘘であったかのように。
セイバーがエクスカリバーを放つ直前、二人のマスターの戦いも佳境を迎えていた。
重傷を負っているにも関わらずこれまで以上のパフォーマンスを見せる陸に士郎の防御も限界が近づいていた。
あまりにも出鱈目に大剣を振り回されるせいで攻撃の誘導どころではない。
そもそもそんな思考が相手に残っているかも怪しい。
ならば―――――
「―――投影開始(トレースオン)」
生き残るために、天海陸を殺す他ない。
限界に近い魔力でも実行可能な投影で決着を着ける。
先ほどの金田一の遺した言葉が脳裏を過ぎり、すぐに振り切った。
(悪い金田一、俺は―――お前みたいな“正義の味方”にはなれない)
かつて綺麗と思い、憧れた理想があった。
いつかその理想を実現できる、誰もを救える正義の味方になりたかった。
だが今は―――
「―――鶴翼、欠落ヲ不ラズ(しんぎ、むけつにしてばんじゃく)」
バックステップと同時、両手の干将・莫耶を左右に弧を描くように投擲する。
「今さらこんなもんにっ!!!」
それらは当然のように陸の大剣に弾かれる。
だがそれで良い、そうでなければこの技は完成しない。
「―――心技、泰山ニ至リ(ちから、やまをぬき)」
再度干将・莫耶を投影、後退しつつ再び投擲する。
予定調和のようにまたも弾かれる、相手の頭に血が上っているせいかあまりにも上手くいっているようにも感じられる。
「―――心技、黄河ヲ渡ル(つるぎ、みずをわかつ)」
またも双剣を手に投影しつつ出方を窺う。
これで倒れてくれるかどうか。
「なっ!?」
ここで漸く陸が異常に気付いた。
有り得ざる奇襲、二度弾き飛ばした四本の双剣が孤影を描いて再度陸へと殺到する。
これが夫婦剣、干将・莫耶の真の特性。
互いに引き合う性質を持った白と黒の陰陽剣は円の結界のように天海陸を包囲した。
「っぁぁああああああああっ!!!!!」
だが陸はそれでも倒れない。
生存本能の為せる業か、瞬時に全方位に大剣を振り再度四本の夫婦剣を弾き飛ばした。
その一撃たるや、下級の英霊をすら打倒し得るほどの苛烈さだ。
だが、だからこそ天海陸の命脈はこれ以上は続かない。
「―――唯名、別天ニ納メ(せいめい、りきゅうにとどき)。
―――終わりだ、天海」
双剣を手に士郎が駆ける。
無理に渾身の一撃を振るったことで陸の全身は硬直を余儀なくされる。
そして意識圏では士郎の全身全霊で振るわれる双剣を防げない。
さらに投擲された四本の夫婦剣も弾いただけだ、駆け出した士郎に自ら呼吸を合わせるように再び陸を包囲し襲いかかる。
これこそ双剣干将・莫耶の性質を生かした斬撃と投擲から成る連携技“鶴翼三連”。
先のアサシンの燕返しとは異なる、相手に回避をさせない状況を作り出した上での必殺剣。
初見では白兵に優れた一級の英霊でも深手を免れない悪辣な一手を凌ぐ手段を天海陸は有さない。
「い、嫌だ!何でこんな事に……!
オレは、オレはただ―――!」
「―――両雄、共ニ命ヲ別ツ(われら、ともにてんをいだかず)」
その先は言葉にならなかった。
意識圏を突き破った士郎の斬り抜けで胴体を、空を駆ける四本の双剣に頭部と両腕をバラバラに寸断されたからだ。
「壊れた幻想(ブロークンファンタズム)」
最後に握った双剣を背後に放り、爆発させた。
嘘をつき続けた少年に真実を口にする機会は訪れない、六本の双剣の爆発によって天海陸の総身は骨すら残らず消え去った。
奇しくもセイバーのエクスカリバーが放たれたのとほぼ同時の事だった。
「シロウ」
疲労と魔力の消耗が重なり肩で息をつく士郎の下にイスラを下したセイバーが駆けつけた。
自身も大量の魔力を消費したが士郎に比べればまだ戦える範疇だ。
「…その、辛いでしょうがこれも戦争です。
裏切りや策謀は常に戦いの裏側に存在している。
リクにしてもそれは同じ、彼も志願して聖杯戦争に臨んだのです。
戦いの中で果てる覚悟はあったでしょう」
「……本当にそう思うか?」
セイバーの気遣いはありがたいが、士郎には陸が死を諦観した魔術師、あるいは死を覚悟した戦士だとはどうしても思えなかった。
例えるならばそう、今は亡き友人である間桐慎二のような、一般人に近い感覚の持ち主だったように見えた。(金田一を基準にするのは間違っているように思えた)
「金田一が言ってたよ。この聖杯戦争に参加するのはどうにもならないくらい追い詰められたやつだって。
天海もきっとそうだったんだ。もちろん遠坂を殺した事を許せるかって言われればとてもそんな気はしない。
でもあいつはあいつで誰かに、何かに助けを求めてたような気がするんだ」
そして、そんな人間を殺したのは他ならぬ士郎自身だ。
きっと、この戦いに明確な悪などどこにもいなかった。
いたのは救いを求めていた天海陸と、その命を己のエゴで切り捨てた衛宮士郎だけだ。
「…あるいは、そうなのかもしれません。
しかしどちらにせよ彼らは殺し合いに乗っていた。
そうである以上我々と相容れることは無かったでしょう、それだけは間違いのない事です。
それよりもシロウ、今のうちにライダーの遺したレコーダーの続きを聞くべきでは?」
露骨に話題を変えてきたセイバーに敢えて同意し、ICレコーダーのスイッチを入れた。
『ではここからはこの聖杯戦争の背景、わしのマスター命名“影の主催者”についてわしから考察を伝えたい。
そもそも何故わしらが殺し合いに乗らなかったのか、何故聖杯戦争の背景事情を疑ってかかっているのかと言えば―――』
ここは昨晩大空洞で情報交換をした時に話していたことだ。
それでわかった。恐らくこのレコーダーは本来自分達ではない、誰かに向けて用意したものなのだと。
最悪自分達が全滅ないし瓦解した後、それでも殺し合いに乗らずに脱出を目指す他の誰か、それこそ泉こなたのような力なき人間の助けになるように。
常に自分や、あるいはルルーシュ以上に巨視的な視野で物事を見ていたあの男なら十分に有り得る。
消滅する間際、ライダーがこのレコーダーの事を話さなかったのは元々彼にその気がなかったからなのだろう。
『―――わしらの考察は大体こんなところだ。
だがどちらにせよこの冬木市という会場からの脱出方法を確保することは至上命題であろう。
残念ながらわしの力ではこの会場の全てを解き明かすことは叶わなかった。
故にまずは量子空間の解析能力に優れた者、霊子ハッカーやそれに近い能力を持ったサーヴァントを味方につけるのだ。
無茶な注文をつけているのはわかっておるが、そうでもせねば脱出の可能性はまず見い出せまい。
そして最後に―――この聖杯戦争はムーンセルの変質、つまり並行世界との接触を経たことで開かれたことは疑いない。
だがそれは外部の働きかけだけでムーンセルを動かしたわけではあるまい。
ただの記録装置はひとりでには狂わんし、外部からの働きかけがあったとしても自ら変質するという選択肢は本来なら存在しないはずなのだ。
言い換えればこの聖杯戦争が行われる前、いや、もっとずっと以前からムーンセルのどこかに潜み、月の改変を望む者の存在が必ずあったはずだ。
その者の存在を暴き、そして見極めるのだ。そうして初めてこの聖杯戦争が開かれた目的が見えてくるはずだ』
記録音声はそこで終わった。
これからやるべき事はいくらでもある、まずはこなたとライダーに事情を話さなければならない。
一応反魔の水晶という証拠品もあるにはあるが、それでも純粋な一般人であろうこなたが納得するかと言えばわからない。
最悪こなたと対立する可能性すらあるのだ。
そして太公望の言う空間の解析が出来る仲間を探す必要もある。
正直士郎には太公望や金田一のように上手に他人を説得出来る自信はない。
それでも彼らの遺志を無駄にするわけにはいかない。
そして切嗣とどう向かい合うのか、そこからも目を背けるわけにはいかない。
だが今は―――
「…少し休もう、セイバー。
悪いけどしばらく動ける気がしない」
「はい、それが良いでしょう。
この地で体を休めた方が魔力も早く回復するはずです」
少しぐらい休息を取ってもバチは当たらないだろう。
セイバーと二人、戦闘の余波でまたも破壊された本堂を横目に大木の下に腰掛ける。
(俺と天海は同じだ、俺だってもし桜が死んでいたらどうなるかなんてわからない。
もしかしたら、地上とは違うここの聖杯に縋って殺し合いに乗ってしまうかもしれない。
セイバー、お前は俺がそんなやつでも一緒に戦ってくれるのか?)
口には決して出せない弱音を飲み込みながら、天海陸の事を思い出す。
言峰綺礼や間桐臓硯とは違う、本来は悪ではないにも関わらず殺し合いに乗ってしまった者。
せめて、そういう人間がいた事は覚えておこうと心に誓った。
【天海陸@ワールドエンブリオ 死亡】
【セイバー(イスラ・レヴィノス)@サモンナイト3 消滅】
【深山町・柳洞寺/昼】
【衛宮士郎@Fate/stay night】
[令呪]:3画
[状態]:疲労(大)、魔力消費(特大)
[装備]:携帯電話、ICレコーダー、反魔の水晶@サモンナイト3
【セイバー(アルトリア・ペンドラゴン)@Fate/stay night】
[状態]:魔力消費(大)
※陸の持っていたニューナンブは戦闘で破壊されました。
※ICレコーダー@現実…太公望が自分達が全滅した時の備えとして、仲間達の目を盗んで金田一のクレジットカードをスって勝手に購入したもの。
午前9時時点での太公望の考察が記録されている。
尚、これは本来士郎やルルーシュなど身近な仲間ではなく他に脱出を目指す誰かに向けて残されたものだった。
しかし妲己は自分の無実を証明するために杏黄旗と同じ場所に埋められていたこれを掘り出し、結果的には衛宮士郎の手に渡った。
柳洞寺。
冬木における聖杯降霊の候補地の一つとされ、第五次聖杯戦争の終結の場となる地。
並行世界の記録をも可能としたムーンセルはこの地における戦いの結末をも記録している。
正義の味方を目指す少年と「答え」を見出した騎士王がこの世全ての悪の生誕を望む神父と人類最古の英雄王を打ち倒し、永遠の別れを迎える世界。
自らの未来を見せつけられ、そして乗り越えた少年が英雄王を打ち破り、かつての理想を失っていた錬鉄の英雄が「答え」を得る世界。
かつて養父から受け継いだ理想を捨て去り、ただ一人の少女の味方になることを決めた少年と、少年の味方になることを決めた少女が真に聖杯戦争を終わらせる世界。
そして今、月のSE.RA.PHに再現されたこの柳洞寺にて、どの歴史とも異なる戦いが始まろうとしていた。
・侍
今しがた降りてきた階段を一歩一歩と登っていく。
心なしか周囲には甘ったるい、蠱惑的な空気が満ちているように感じられた。
衛宮士郎とセイバー、ある世界において地上の聖杯戦争の勝者となった主従は遠坂凛殺害の元凶たるキャスターのサーヴァント、蘇妲己を討つべく歩みを進めていた。
この聖杯戦争が始まってからいくつもの苦難に晒されたためか強ばった表情で横を歩く士郎を気にかけながら、セイバーは己の内にある違和感を拭いきれずにいた。
キャスターは衛宮切嗣と内応し、ルルーシュにギアスを使わせ金田一とライダーの死因を作った。
天海陸や彼のサーヴァントらの話から考えれば、これが間違えようのない結論である。
だが、それでも騎士王の類い稀な直感は自身でも正体のわからない警鐘を鳴らしていた。
(この違和感が一体何を意味するのかはわからない、だが、それならば前へ進む事で確かめるまで)
これから待ち受けているのは最弱のクラスなれど容易ならざる敵手だ。
セイバーは脳裏に渦巻く疑念を振り払い、視界に入った山門を向き―――
「止まってください、シロウ!」
山門に立ちはだかる、その男を捉えた。
群青色の陣羽織を身に纏い、およそ非常識なまでに長大な日本刀を手にしたその姿は、まさしく日本の侍そのものであった。
だが問題はそんな事ではない、真に異常なのは男の纏うその気配。
他の英霊たちと比して非常に微弱であるものの、確かにサーヴァントとしての存在感を放っていた。
だがこれはどういう事だ。
衛宮切嗣のサーヴァントはライダー、如何にキャスターと繋がっていたといえど切嗣とこのサーヴァントに関係性があるとは考えにくい。
いや、そもそもつい先ほどまで山門の警備に就いていたガウェインが他のサーヴァントの存在を見落とすなど有り得るのか。
「如何に精巧に似せようとも、やはりここは偽りの箱庭でしか有り得ぬ。
私が愛した花鳥風月はここには無い、何とも侘しいことよ。
貴様もそうは思わぬか、セイバー」
「…貴公が何者かはあえて問うまい。だが何故私がセイバーだと断定できる。
私がこの手に握るのは何も剣とは限るまい、それともキャスターの入れ知恵か」
いつでも斬りかかれる態勢のまま、慎重に探りを入れる。
だが、侍は一瞬不思議そうな顔をした後、何かに納得したのか鷹揚に頷いた。
「…そうか、私は貴様を知っているが、貴様は私を知らぬのだな。
いや、これも並行世界とやらの妙というやつか、ままならぬものだ。
しからば改めて名乗ろう。私はアサシンのサーヴァント、佐々木小次郎。
貴様らが討たんとする女狐めがこの地に招きし亡霊よ」
「―――!?」
真名とはサーヴァントにとって絶対に秘すべきもの。
この異常な聖杯戦争であってもその本質が変わることはない。
だというのにこの男は堂々と己が真名を謳い上げた。
セイバーの驚愕は無理からぬ事であろう。
その表情を読み取ったアサシンは微笑を浮かべた。
「言ったはずだぞ、私は貴様を知っていると。
であればこちらから名乗るは当然の礼儀であろう?
それに―――私が名乗ったところで、貴様にとっての私は倒すべき障害でしかない。
そら、お互い為すべき事は何も変わりはすまい?」
「―――成る程、確かにその通りだ。
だが生憎と我々は先を急いでいる、まかり通るぞアサシン!」
セイバーの全身から魔力が猛り、風が唸りを上げる。
セイバーの世界ではついに実現しなかった異色の暗殺者との戦いの火蓋が切って落とされようとしたところで―――
「待て、セイバー!」
これまで沈黙を保ってきた彼女のマスターの制止が入った。
「シロウ?」
「俺達が倒すべきなのはキャスターだ。
お前をこんなところで消耗させるわけにはいかない」
あのアサシンが何者であれ、キャスターが召喚したサーヴァントである以上考えられる目的は時間稼ぎとセイバーの力を削る事と見て間違いない。
それにキャスターは奥からこちらの様子を窺っていることだろう。
衛宮士郎とセイバー、どちらの手の内を隠しておくべきかなど思考するまでもなく明白だ。
「勝算はあるのですか?」
「俺一人で何とか出来るとは言わない、でも隙ぐらいは作ってみせる。
だからセイバー、俺を信じてチャンスを待っていてくれ」
セイバーは無言で頷き、再び剣を構え直した。
だがその構えは攻めのそれではない、アサシンを近づけない守りの姿勢だ。
「ふむ、私は一向に構わぬぞ少年。
男子三日会わざればというやつか、随分と見違えた。
そなたの磨いた牙、見事私に突き立ててみよ」
アサシンはといえば、何故か構えを取らぬまま自然体の様相だ。
だが不思議と侮られているとは思わなかった。
きっとこの男にとってはこれが戦いの姿勢なのだろう。
「言ってろ。投影、開始(トレースオン)」
自己の内に埋没し、この状況に最も適した剣を探し出す。
見たところあのアサシンが持つ刀は普通の刀剣と比べれば業物の部類には入るが、英霊たちの持つ宝具と比較すればなまくらも同然。
「I am the born of my sword(体は剣で出来ている)」
ならばこの宝具こそが奴にとっての弱点となるだろう。
この剣の前では魔術師とサーヴァントの実力差など何の意味も持ちはしない。
もっともセイバーが壁になってくれているからこそ安全に撃てるのであまり偉そうな事は言えないが。
同時に投影した黒塗りの弓にそれをつがえ、魔力を込める。
アサシンは動かない、否、動けない。
彼はセイバーの実力をその身を以って知っている。
防戦でこそ最も力を示すアサシンが無理に斬りかかったところでセイバーを突破することなど到底不可能。
故に侍は動かず留まる。その美貌に不敵な笑みを浮かべたまま。
「食らいつけ―――“赤原猟犬”(フルンディング)!!」
二十秒か、あるいは三十秒か。
刹那とも永遠ともいえる膠着の後、衛宮士郎のつがえた弓から鮮烈な赤光が放たれた。
北欧の英雄ベオウルフが用いたとされるこの剣は必ず敵を斬るという概念を持つ。
魔弾として射出された魔剣は音速をも凌駕しアサシンへと殺到する。
「ほう、生前合戦に出た事などついぞ無かったが、燕ではなく矢を斬るもまた一興」
だが、それでも尚この侍は悠然とした物腰を崩さない。
この程度の獲物を斬れぬなら、この身は決して燕を斬る事など出来はしなかった。
如何に速かろうと、ただこちらへ飛ぶだけの矢弾などアサシンには何ほどの脅威でもない。
「ふっ―――!」
一閃。
アサシンが長刀を持った腕を振るう。
だがその動作の何と速く、流麗な事か。
態勢すら崩さぬただのひと振りは宝具である魔弾をいともたやすく弾いた。
「なっ―――!」
その光景に、驚きを隠せない。
赤原猟犬を弾かれた、という事実にではない。敵はサーヴァント、そんな事は予想の範疇だ。
真の異常はその後、未だ刃こぼれ一つないその得物である
群青色の侍が手にするは宝具ですらないただの長刀。
そんななまくらで真名解放を行なった宝具を迎撃しようものなら一撃で刀身を折られるが道理。
されど、その道理を覆すのが魔剣士、佐々木小次郎だ。
アサシンは力によって赤原猟犬を弾いたのではない。もとよりそんな膂力は無い。
彼はただ、魔弾の力に逆らわず刀身で威力を殺し受け流すことによって見事得物を失うことなく弾いてみせたのだ。
言葉にすればそれだけだが、音速を超える矢の弾速、重量、威力、そして刀を振るうタイミング。
それらを一つも過つ事なく見切ったその絶技がただの一刀に込められていた。
―――だが、北欧の魔剣の真価はここより発揮される。
「むっ―――!?」
逸早く異変を察知したのは暗殺者のサーヴァント。
その有り得ざる異常に目を奪われる。
本来、どれほどの腕を誇る射手であろうと一度放たれた矢の軌道を変える事など不可能。
それはこと弓術という一点ならば英霊にも比肩する腕を持つ衛宮士郎であろうと同じ事。
しかし必ず敵を斬る概念を帯びたこの剣はその定理を覆す。
矢として撃ち出されたこの宝具は射手が健在である限り何度でも標的へ食らいつく。
対抗手段はただ一つ、魔弾に射抜かれるよりも早く射手を倒すこと。
だが最高の俊敏さを誇るアサシンを以ってしてもそれを実行に移すことは出来ない。
射手である士郎の前にはセイバーというあまりにも強大な護衛がいるからだ。
この状況、既にしてアサシンは王手をかけられている。
「はっ―――!」
再び一閃。
侍の超絶技巧は二度も猟犬の顎をいなしてみせた。
だが、それも程なくして限界が訪れる。
(なるほど、これが合戦場を飛び交う矢というものか。
しかし……これ以上は流石に刀が保たぬか)
その事実は誰よりもアサシンが認識していた。
彼自身の剣の力量は全サーヴァントでも頂点に立つ程だ。
―――だが悲しいかな、アサシンの愛刀物干し竿の強度は主人の技量に対して絶望的なまでに脆い。
むしろ二度も赤原猟犬を退けたことが埒外の奇跡なのだ。
だがそれもここで終わり。三度目を防いだ時がこの刀の折れる時。
そして四度目でアサシンは凶弾の前に為す術も無くその身を撃ち抜かれる。
(ならば―――)
だが、それはアサシンの終焉を意味しない。
なるほど確かにただの一閃では空を駆ける猟犬を地に落とすにはまるで不足だ。
だが知るがいい錬鉄の魔術師よ、この侍が生涯を懸けて到達せし秘奥の剣を。
「秘剣――――――」
ここに来てアサシンが初めて構えを取る。
それは無形を常とするこの侍が会得したただ一つの必殺剣。
この男にのみ許された究極の魔技。
「――――――燕返し」
それは果たしてただの一閃であったのか。否、断じて否だ。
セイバーは確かに見た。
軌道を変え三度迫り来る赤原猟犬、その切っ先ではなく剣の腹に向けて振るわれた三つの斬撃を。
縦、横、斜めの三方向から全く同時に繰り出された円の結界の如き剣閃は迫る魔剣の刀身を見事断ち切ってみせた。
これこそが佐々木小次郎、その名を冠した無銘の剣士が空を飛ぶ燕を打ち落とすためだけに生涯に渡って剣を振るい続けた果てに到達した魔法の剣技。
多重次元屈折現象(キシュア・ゼルレッチ)。
生涯を剣に捧げた男の才と努力、その結実は宝具である魔弾をすら凌駕した。
そして。
「――――――こ、ふっ……!」
男の命運もまた、そこで燃え尽きた。
因果逆転の魔槍とは異なる意味での必殺魔剣。
それを振り抜いた瞬間にのみ生ずる刹那の隙を剣の英霊は見逃さなかった。
神速の踏み込みでアサシンを切り裂いたセイバーは惜しみない暗殺者に惜しみない賛辞を贈る。
「私には、いや、我が円卓の騎士の誰であっても到達し得ないであろう見事な剣技でした。
貴方にとってこの結末は不本意なものでしょうが―――」
「良い、気にするな。お互い巡り合わせが悪かったのだろうよ。
それに―――私とそなたの勝負付けは既に終わっていた。
もとより、招かれざる亡霊には過ぎた夢だったのだ」
口から、切り裂かれたその身から夥しいまでの血液が溢れる。
だがそれでも尚、アサシンからは些かも優雅さは失われていなかった。
「征け。女狐めは奥でお前達を待っている。
かつて地上で私を呼んだ魔女も大概の魔性だったが、あれはそれ以上よ。
どうせ碌な性根ではあるまい、速やかに止めを刺すが人のためというもの」
士郎もセイバーも、無言で頷き山門の先へと進む。
最後に一度だけ、誇り高き剣士の姿をその目に焼き付けて。
・オオカミ少年は牙を隠す
「嘘……」
「………」
情報を集めるために月海原学園へと足を踏み入れた陸、こなたら一行。
真っ先に確認した脱落者を表示した掲示板に記された名前の数は彼らの想像を遥かに越えていた。
「19人だって……!?まだ始まってから半日と少ししか経ってないんだぞ!?」
陸が嘘を交えない、心底からの驚愕を口にする。
それはこの四人の心中を代弁するものであった。
遠坂凛と金田一一に関しては覚悟はしていたが、それでもこの人数は異常に過ぎる。
「…何で?どうしてみんなそんなに殺し合いなんてしたがるの?
わからない、わかりたくない、だっておかしいでしょこんなの!」
「こなたちゃん、落ち着いて!」
取り乱すこなたを映司が宥めすかす。
無理もない、と陸は思う。
あくまで勝ち残る事を選んだ自分と違ってこなたは完全に巻き込まれた一般人なのだ。
むしろここまで曲りなりにも平静さを保っていた事をこそ賞賛すべきだろう。
そしてこれから先、自分はそんな彼女をも殺すのだ。
「みんな、動揺するのはわかるけどとにかく一旦冷静になろう。
脱落した参加者はこれで全体の約四割、確かに多いが悲観していても始まらない。
この脱落者に関して僕なりに考察した事を聞いてほしい」
そんなメンバーの間に広がった悪い空気すらも利用しようというのだろう、イスラがさも沈痛そうな面持ちで場をまとめにかかる。
その悪辣さに思うところが無いわけでもないが、だからといって止める理由もない。
こなたや映司と同じように黙って続きを促すことにした。
「まずどうして半日でこれだけの犠牲が出たのか、それは参加者間のやる気、モチベーションの差だと思う。
この聖杯戦争にはさっきの衛宮切嗣のような勝ち残るために容赦なく敵を殺しに回る人間もいれば、リクやリン、コナタのように殺し合いに反対する人間もいる。
幸い僕らは早期に手を結ぶことが出来たが他のマスターはそうじゃなかった。
勝ち残る覚悟を決めた者とそうでない者、遭遇して戦闘になった時、どちらが勝つかなんて事は語るまでもないだろう」
確かにそういう考え方もあるか、と納得した。
考えてみればこなたや凛はもとより柳洞寺にいた衛宮士郎らも殺し合いに乗っていなかった。
だとすればそんな思考のマスターがもっといた、という結論は不思議でもなんでもない。
「セイバー、君は俺達も殺し合いに乗った方が良いと思うのか?」
「そうは言わないよ、第一こう言っては何だけどリクやコナタが無理をしてやる気を出したところで戦い慣れした連中相手に勝ち残れるとは思えない。
僕らはこれまで通り、殺し合いに反抗するスタンスを通そう。
それにしばらくは大規模な戦いは起こらないだろうからね」
「「どうしてそんな事が言い切れるんだよ?」」
上手く間を持たせるために適度に質問する振りをしながらイスラに先を促す。
それにイスラは鷹揚に頷きながら答えた。
「これだけの犠牲者が出るほど各地で戦いが起こったんだ、どの陣営も大きく疲弊しているだろう。
となれば少なくとも夜まで、場合によっては丸一日は休息や偵察に費やされるはずさ。
だから、今すぐ僕らが他の参加者に襲われる可能性はかなり低い。
そこでだ、ここらで当初の目的を達成しておこうじゃないか。
コナタとライダーには図書室で情報を集めた後、リンの家に向かってほしい」
「えっ、ちょっと待ってよ。りっくんとセイバーさんは?」
「「さっきセイバーと話し合って決めたことなんだけど…オレ達は柳洞寺へ行こうと思う」」
陸の言葉にこなたと映司が愕然とする。
当然だ、危険な鉄火場とわかっている戦場に限りなく最弱に近い二人が踏み込もうというのだから。
「…駄目だ、それは。士郎君たちの援護に行くなら俺の方が向いている。
第一セイバー、キャスターには天敵一人で当たった方が良いと言ったのは君だろう」
「確かにシロウ達の援護という意味もあるけど、それ以上に僕自身の戦力補強の意味合いが大きいね。
まだ詳しくは話せないが、僕はマナ、要するに大気中の魔力が集まる霊地にある儀式を行うことによってその場の魔力を自身に集める事ができるんだ。
そうすれば僕の戦力は格段に上がる。もう君達のお荷物にはならないさ」
やや自嘲を込めて虚実を交えた説明をするイスラ。
知らない人間が見れば、こいつは本気で今まで足を引っ張ってきたことを悔やんでいると思うのだろう。
やはりどれだけ付き合ってもイスラを好きにはなれそうもないが、ここはこのサーヴァントに同調しなければならない。
「「火野さ…ライダーは今までずっとオレ達を体を張って守ってくれた。
だから今度はオレ達がみんなのために命を賭ける番だ。
それに…多分より危険なのは泉達の方だ、考えてもみてくれ、柳洞寺には間違いなくオレ達に味方してくれる衛宮がいるけど遠坂邸は今どうなってるかわからない。
オレ達が合流するまで絶対に無理はしないでくれ。…もう仲間を失うのはたくさんだ」」
「りっくん…」
自分でも反吐が出るような酷い嘘で同情を誘う。
ああ、きっと今オレは演技でもないのに酷い顔をしてるんだろう。
その証拠に二人は心から心配そうに自分を見ている。
「今までお荷物だった僕が言っても説得力が無いかもしれないが、例えキャスターがまだ生き残っていたとしてもやられてやるつもりはないさ。
さっきまでは不意打ちだったから不甲斐ないところを見せてしまったが、相手がキャスターだとわかっていればやりようはある。
僕の貯蔵魔力を度外視すれば切り札を使うことも出来ないわけじゃない。
それに、これからの事を考えれば今のうちに戦力を増強しておく必要があるんだ。
これだけの人数が脱落したんだ、今生き残っているのはそれなりに修羅場を潜った者ばかりだろう。
そんな連中を相手に生き残るには僕達も力をつけなければいけない」
駄目押しとばかりに別行動の必要性を説くイスラにこなたと映司もようやく納得した。
出発の前に映司の口から衛宮切嗣のライダー、仮面ライダーディケイドの情報を教えてもらい、学園を離れる。
「りっくん!約束だよ、絶対にまた会おうね!」
嘘にまみれた剣の主従の真意など知る由もなく、こなたと映司は自分達に出来ることをと図書室に足を運んでいった。
【深山町・月海原学園/昼】
【泉こなた@らき☆すた】
[令呪]:3画
[状態]:健康
[装備]:携帯電話、乗用車
【ライダー(火野映司)@仮面ライダーOOO/オーズ】
[状態]:魔力消費(微)
「くっくく、アーッハハハハハハハハ!!
いやあ見事な演技だったよリク!見たかいコナタとライダーのあの顔!
君も一段と演技が堂に入ってきたじゃないか!ぷっくくくく…」
「だから爆笑するなって言ってるだろこの馬鹿!」
柳洞寺に続く階段を登りながら、先ほどから人目がないのを良いことに爆笑するイスラに辟易しつつ先を目指す。
目指す先は柳洞寺の敷地、その中枢だ。
だが、先にこなた達に語った別行動の目的は半分が真実、半分が嘘だ。
柳洞寺にイスラの宝具、紅の暴君(キルスレス)を突き立てて大量の魔力を得る、というのは紛れもない真実だ。
ついでに言えばこれからに備えて、とりわけ衛宮切嗣に対抗するため戦力を増強する必要があるというのも偽らざる本音である。
しかし、戦力を得る理由はこなたらを守るためなどでは断じてない。
「シロウ達なら首尾良くキャスターを打倒できるだろう。
でもキャスターもそれは承知している、あらゆる手を尽くして彼らに消耗を強いてくる。
僕らはそうしてキャスター討伐で疲弊したシロウとセイバーを後ろから撃てば良い」
「そりゃあそうだろうけどな、キャスターの方が生き残る可能性もあるんじゃないのか?
オレ達はキャスターの事を何も知らない、思いもよらない切り札を持ち出してくるかもしれないだろ」
「その場合でも問題は無いよ、リク。
そもそもキャスターがセイバー、それも名高いアーサー王を相手にして戦力を出し惜しみするなんて土台不可能だ。
つまり万に一つキャスターがシロウとセイバーを下せてもまず間違いなく余力なんて残らない。
君の言う切り札とやらが僕らに向けられる可能性は無視しても良いほど小さいものだ」
そう、陸とイスラにはこなた達と共に行動できない理由があった。
まず第一に紅の暴君で魔力を汲み上げる様子を見られることによって真名が露見するリスク。
サーヴァント達は聖杯から時空を越えた知識を授けられている。
裏切りの反英雄であるイスラの真名を知られれば、いくらお人好しなこなたや映司といえどもこちらへの信用を大きく落とすことになるだろう。
そして―――こちらが最も大きな理由だが、陸とイスラはこの機を生かして衛宮士郎と、可能ならルルーシュをも葬り去る算段であった。
二人とも今は自分達の嘘に騙されていてくれているが、この先何かの拍子に真実に辿り着く可能性も決して零ではないのだ。
キャスターに加え、キャスターから話を聞いたであろう士郎とルルーシュを始末すればもう凛を殺害した件を咎めることが出来る者はいなくなる。
それに今を逃せばもっともらしい理由をつけてこなた達と別行動できる機会はもう巡ってこないかもしれないし、時間が経てば第三者に柳洞寺を占拠される可能性も否めない。
リスクがあるのは承知の上、だからこそこれまで温存していた力が活きてくる。
「キャスター戦で疲弊したシロウ達はもとより、この山の霊脈を乗っ取ってしまえば令呪を2画失ったルルーシュも敵じゃない。
まあ流石にガウェイン卿を相手にして僕自身が正面から倒せる自信は無いけどリク、君は別だろう?
随分我慢させてしまったね、これでようやく僕達の聖杯戦争を始められる」
そうなのだ、刃旗という圧倒的な力を有しながら陸がこれまで策謀に徹さざるを得なかった理由は偏にイスラの弱さにある。
紅の暴君を用いた伐剣覚醒、その比類なき力を魔力不足で引き出すことが出来なかったが故にイスラ・レヴィノスは最弱だった。
しかしこれからは違う、この冬木市最大の魔力集積地を利用すればイスラは最優のクラスの名に恥じない力を取り戻す。
そして全マスターでも最強に近い陸の戦力で以って正面から全ての敵を打倒することも夢ではない。
「…ああ、そうだな。こうなったらもう泉や火野さんも用済みだ。
それに遠坂から奪った魔力はまだ温存してるんだろ?」
「もちろん。少し性能は落ちるしそう長時間は無理だが伐剣覚醒そのものは使えるよ。
これを使う相手がシロウ達になるかキャスターになるかはここからじゃまだ分からないけどね。
それとリク、コナタとライダーはせっかく僕達を味方と思ってくれてるんだ、用済みなんてひどいこと言わずに最後の最後まで利用し尽くしてあげようじゃないか」
「お前にだけはひどいと言われたくないよ」
そんな応酬をしながらついに山門近くまで辿り着いた。
ここからは無駄口は無しだ、お互いにそう気を引き締め―――
「良からぬ気配が近づいてきているとは感じておったが、よもや人の皮を被った蛇蝎の類であったとは。
あの少年とセイバーを葬るとはまた穏やかではないな、そうであれば私も門番の役目を果たさねばなるまいよ」
―――既にここにいるはずのない男の声を聞いた。
・再びの魔剣士
「サーヴァント……!?」
「いかにもこの身はアサシンのサーヴァント、佐々木小次郎に相違ない」
「はあ!?真名を!?」
山門に立ち塞がるように現れた別のサーヴァント。
日本の剣豪・佐々木小次郎を名乗ったその男はどこから出てきたサーヴァントだというのか。
少なくとも先ほどまで柳洞寺にいた面子のサーヴァントでは有り得ない。
もしそうなら彼らの口からこの男の存在が出なかったことに説明がつかない。
かといって陸やイスラと同じく漁夫の利を狙ったマスターの差し金とも考えにくい。
そう考えるにはあまりに動きが早すぎるし何よりサーヴァントのこのような酔狂な名乗りを許しはしまい。
だとすれば、俄には信じ難いが残る可能性はただ一つ。
「キャスターの用意した手駒、そんなところかい?」
「然り。如何な外法を用いたか、あの女狐めが亡霊に過ぎぬこの身を山門を憑き代に呼び出したというわけだ」
「おい、ちょっと待てよセイバー!
サーヴァントがサーヴァントを召喚したっていうのか!?
そんなルール違反が出来るのかよ!?」
「出来なくはないだろうね、何しろ向こうは本職のキャスターだ。
媒介はそうだな…さっき死んだという、ライダーのマスターの令呪じゃないかな?」
イスラの推測にアサシンは沈黙を以って応じた。
その沈黙をイスラは肯定と受け取った。
あるいは、もう言葉を話す事すら苦痛なのかもしれない。
「しかしまあ、そんなことはどうでもいいか。
少なくとも、今君がこうして存在している理由に比べれば些細な事さ。
まったく君のそれは一体どうなっているんだい?僕の呪いが形無しじゃないか」
―――信じ難い事に、アサシンは明らかな致命傷を負いながら未だ気力だけで存在を保っていた。
「何、おぬしらの良からぬ気配を感じたものでな。
これはまだ死んではおれぬと思い立ったまでのこと。
いや、醜く生き足掻いてこそ得られるものもまたあったようだ。
―――何しろ、セイバーの戦を邪魔立てする不埒者どもをこの手で斬れるのだからな」
その口と胴体からは生きているのが不思議なほどの血液が流れていた。
元々は優美であったのだろう陣羽織は血に染まり、今や見る影もない。
手にした長刀物干し竿は先ほど赤原猟犬を迎撃し、打ち落とした代償に刀身が歪んでいる。
だが、そんな死に体であってもイスラにはアサシンの戦力は些かも衰えていないように感じられた。
「やれやれ、たかが敵サーヴァントにどうしてそこまで入れ込むのか僕には理解できないよ」
「この月の聖杯戦争にしか招かれなかった貴様らには知り得ぬ事よ。
―――ああ、そうだな。確かにあの時私は次こそはと月に願ったものだ。
いやいや我ながら実に未練がましい、またもこうして化けて出てしまったのだからな」
陸とイスラの知らない何かへの執着を振り払うように一度だけ頭を振り、刀を掲げる。
その静謐な闘志は陸にとって全く未知のものだった。
だがイスラはそんな相手の心情などお構いなしに紅剣を手に取り、召喚術の構えを取る。
「生憎と僕は純正なセイバーじゃなくてね、代わりといっては何だけどキャスターの真似事が出来る。
だから君がそこから動けない存在だということも手に取るようにわかる。
さて、そこまで分かっていて僕が君の得意そうな距離に入るとでも?」
決まりきった結末を記す必要はない。
佐々木小次郎の名で召喚された無銘の魔剣士は異界の召喚術士の前に一太刀浴びせることも適わず月の聖杯戦争から完全に退場した。
招かれざる亡霊は露と消え、後には荒れ果てた瓦礫だけが残された。
“……ここまでか、先に逝っているぞセイバー。
いや、良い夢を見させてもらった―――“
&COLOR(#FF2000){【アサシン(佐々木小次郎)@Fate/stay night 消滅】}
アサシンを無傷で撃破した後、山門を潜り境内へ入る。
警戒しながら中に入ると、そこにはキャスターの気配は微塵も感じられず、代わりにどこから調達したのか黒塗りの洋弓を手にし、ムーンセルによる修復が始まった本堂を見つめる見知った少年がいた。
「「衛宮、無事だったんだな。
キャスターは…どうしたんだ?それにあんたのセイバーは?」」
「…キャスターは俺達が倒した。
セイバーは…少し席を外してる、まあすぐ戻るよ」
こちらに向き直った士郎だが、どうも様子がおかしい。
その表情はどこか凍っているようにも感じられ、遠坂凛の仇敵を討ち果たしたという達成感はどこにも見られない。
「それよりお前らこそどうしたんだ。
泉とライダーは一緒じゃないのか?
それにさっきの物音は?」
「いや、実は死にかけのサーヴァントの妨害に遭ってね。
それと二人には学園に残ってもらっているよ。
調べ物をしてもらってからリンの家で落ち合う予定でいる。
君らも一緒に来ないか?
キャスターを倒したなら、これからの事を考える必要がありそうだしね。
さっきのアサシンの事を含めて本格的な情報交換をするべきだろう」
イスラが友好的な笑顔を貼り付けたまま士郎の隙を伺う。
凛の一件から令呪を警戒しているのか、すぐに襲いかかる気はなさそうだ。
「そうか。本当にあいつらはいないんだな、良かった」
「………?」
イスラも気付いたようだがやはり何かがおかしい。
まるで自分達が何か致命的な見落としをしていて、まだそれに気付けていないかのような―――
いや、そもそも“何故士郎は陸とイスラがここに来た事に全く驚きを見せないのか?”
「なあセイバー、いや、天海でもいい。
アンリマユ、宝石剣ゼルレッチ、大聖杯に小聖杯。
この単語のうちどれか一つでも聞き覚えはないか?」
「「……いや、オレは知らない。セイバーは?」」
「残念ながら僕も知らない、リンや君が参加したという聖杯戦争に関わることなのかい?」
イスラが警戒の度合いを若干引き上げながら答える。
士郎はといえば一度だけ目を閉じて天を仰ぎ、無表情のままこちらを見つめる。
「そうか、やっぱり知らないのか。
…キャスターは知ってたぞ」
その言葉が引鉄だった。
身体能力を強化しているのか素早い動作でどこからか矢を取り出し、陸に二射続けて撃ち放った。
「ハッ!」
だがそれらは当然のように陸の前に出たイスラの魔剣に阻まれる。
しかし事はそれだけで終わらなかった。
「…!リク、横だっ!!」
爆音と共に林からミサイルの如きスピードで飛び出してきたセイバー、アルトリア・ペンドラゴン。
その手に握る不可視の剣の切っ先は真っ直ぐ陸に向けられていた。
士郎の射撃とほぼ同時の変則的十字砲火(クロスファイア)。
陸の前に飛び出し、矢を迎撃したイスラは間に合わない。
「う、うわああああああっ!!!」
恐怖と生存本能から無意識のうちに顕醒し、意識圏を張った。
だが無情にもセイバーの剛剣は意識圏を容易く切り裂き、刃の直撃こそ免れたが風王結界の衝撃だけで十数メートルも吹き飛ばされ、反対側の林の木に全身を打ちつけられた。
すぐさまイスラが駆け寄り、陸を庇う形で前に立つ。
「なるほど。姿を変え、大剣を持ち既存の魔術とは異なる障壁か。
それにこの反応速度、確かにこれならばサーヴァントであっても短時間ならば引きつけられる。
やはり我々を欺き、凛を殺したのは貴方達だったか」
「…これは一体どういうつもりだい?
しかもいきなり濡れ衣を着せにくるとは大した挨拶じゃないか。
大体僕らがリンを殺しただなんて、まさかキャスターにでも操られているのか?」
「この期に及んでまだそのような戯言を口にするか。
確かにキャスターは潔白ではなかった、だから我々が倒した。
だが同時に、凛を直接殺したのは彼女ではないとはっきり分かったのだ」
「何…だと…?」
確信を込めて敵意をぶつけるセイバーにさしものイスラも一瞬頭が真っ白になった。
何故だ、どこで露見した。
いや、状況から考えて情報の出どころがキャスターであることは間違いない。
だが何故あれほど憎んでいたキャスターの言を今になって信じる気になっている。
一体何がどうなればさっきの今でここまで態度が変わるのか。
イスラが事態を好転させようと必死に思考を巡らせている時、士郎が地面に落ちた反魔の水晶を拾い眼前に突き出した。
「言ってなかったけどな、俺はある魔術に特化した魔術使いなんだ。
その魔術からの派生で、物の構造を把握する解析の魔術が使えるんだよ。
その物の創造理念から基本骨子、構成材質、製作技術、成長経験に蓄積年月に至るまで全て解析できる。
リィンバウムだとかわからない単語もあるけど、とにかくコイツが対魔力の代わりになるような魔術道具の一種だってことは今解析したことで服の上からでもすぐにわかった。
要するに天海、お前はルルーシュのギアスにかかってもいなければただの一般人でもないって事だ」
「「ま、待ってくれ、違うんだ。確かにこの力を隠してたことは謝るよ。
で、でもだからってオレ達は間違っても遠坂を殺したりなんかしてない!
その水晶だって、ルルーシュにギアスをかけられた後でセイバーに頼んで作って」」
「天海」
弁解の言葉は士郎の大声に阻まれた。
その双眸からは今や怒りの色がはっきりと見て取れる。
「…お前、俺の話を聞いてたか?
俺は物の構造を全て解析できると言ったんだぞ。
この水晶がどこかから“呼び出された”のは今日の午前7時49分22秒から37秒までの間。
ルルーシュが柳洞寺を出たのが午前9時、どう考えても時間が合わないんだよ。
仮にこれを用意した理由がキャスターへの対策だったとしたって、お前がギアスにかかっていない事だけは絶対に間違いのない真実だ」
「な…馬鹿な…そんな……」
聞いていない、そんな自分達の嘘をピンポイントで暴ける魔術が存在するなんて聞いてない。
皮肉にも、嘘がバレないようにと用意した反魔の水晶と刃旗使いとしての今の陸の姿が彼らの嘘を裏付ける動かぬ証拠となってしまったのだ。
金魚のように口をパクパクと動かしながら愕然とする陸に追い討ちをかけるように更なる衝撃を突きつけられる。
「それからお前のセイバーが持ってる宝具、そいつには確かに魔力を吸奪する機能があるな。
…いや、その剣は本来世界から魔力を汲み出して使うものなんだ。
銘は“紅の暴君(キルスレス)”。セイバー、これでアイツの真名わかるか?」
「はい、生まれた時より絶息の呪詛を与えられ、その苦しみから逃れるために多くの組織を渡り歩き裏切り続けた反英雄イスラ・レヴィノス。
どうやら異界のサーヴァントに関する知識は私にも付与されていたようです」
「……!!」
イスラの表情が衝撃と絶望に歪む。
魔術師という存在を侮っていたつもりは毛頭なかった。
しかしそれでもこの衛宮士郎という魔術師はあまりにも異常だ。
この宝具にどれだけの神秘が込められていると思っている、それを何故そうも簡単に分析できる。
この男に疑われ解析の魔術を使われた、たったそれだけの事でこれまで陸とイスラが苦心して積み上げてきた戦略は呆気なく崩壊した。
陸の刃旗と反魔の水晶を見られたことにより発覚した二人の嘘、更にはこれまでひた隠しにしてきた悪名高いイスラの真名。
それらが全て露見してしまった今、如何に舌先三寸を得意とするイスラもこの状況を覆して士郎とセイバーを騙せる策を弄することは出来なかった。
「一つ聞かせてくれ、どうして君達は僕らが疑わしいと思ったんだい?」
どうして自分達の嘘がわかったのか、とは聞かない。
それはイスラにとってささやかな最後の抵抗だった。
「ああ、俺達も最初はお前らを全く疑ってなかった。
そこに疑問を抱いたのは――――――」
・妲己ちゃんのスーパーネタばらしタイム
―――時をしばらく遡る。
アサシンを撃破して山門を通り、奥まで進むと焼け落ちた本堂の前で佇む一人の女、キャスターを見つけた。
しかしどうもおかしい、キャスターのサーヴァントならばセイバークラスのサーヴァントを迎撃するにあたって必須ともいえる魔術工房、あるいは神殿らしき空間はどう見てもここには存在しない。
「あらぁ~ん、いらっしゃぁ~い。
あの小次郎ちゃんをほとんど消耗ZEROで倒しちゃうなんてわらわビックリだわぁん」
「そのような世辞は結構。確認するがキャスター、先のアサシンは貴様がハジメの令呪を使って召喚した者だな?
如何に魔術師の英霊といえど相応の媒介が無ければサーヴァントレベルの存在を召喚するなど不可能、可能に出来るものがあったとすれば彼しか考えられない」
「さっすが普通に魔術が世間に在る時代に生きたセイバーちゃんは見る目が違うわねぇん。
でもぉん、それがどうしたのぉん?
わらわの立場なら利用できるものは全て利用するのは当たり前でしょぉん?」
「確かに、許し難くはあるが貴様の立場からすれば最善の方法だったのだろう。
だが―――私からすれば貴様を討つ事への躊躇いがまた一つ消えただけの事だ……!」
不可視の刀身をキャスターに向け構えを取る。
最弱の英霊といえどここまで自分達を苦しめた相手だ、油断はしない。
士郎もまた、魔術回路を励起させ不意打ちに備える。
だが、予想に反してキャスターはこちらにフッと微笑んだ後両手に持つ扇型の宝具、五火七禽扇(ごかしちきんおう)を地面に投げ捨てた。
「やーめたぁん♥」
「なっ……!?」
「…どういうつもりだ、よもや事ここに至って命乞いが通るとでも思っているのか?」
「だぁってぇ~ん、ここでわらわが頑張って戦ってもお互いデッドエンドからの道場行き確定なのよぉん?
それなら貴方たちを助けてあげた方がまだ実りがあるでしょぉん?」
デッドエンドだの道場だの訳の分からない単語は聞き流すとしてキャスターの発言と行動の意図がわからない。
いやそもそも何故追い込まれているからといって戦いを放棄するのか。
このキャスターならば最悪この土地との契約を切って捲土重来を期すことも不可能ではないはずだ。
「世迷言も甚だしい。ここで倒れるのは貴様だけだ、キャスター」
「いつでもどこでもわらわって信用が無いのねぇん、悲しいわぁ~ん。
ああ見える、見えるわぁん!味方と信じた人間に後ろから刺されて道場送りにされる士郎ちゃんとセイバーちゃんの姿が!」
あまりにも白々しい大粒の涙を流しながら相変わらず要領を得ない発言を繰り返す。
警戒を解いたわけではないが、これでは埒があかないと士郎が話しかける。
「ちょっと待て、味方に刺されるってどういう意味だよ。
言っとくけどな、ルルーシュや他に俺達に味方してくれてる奴らはしばらくここには入ってこないぞ。
お前みたいな奴には天敵になるサーヴァント一人で戦った方が良いからな」
「ふぅ~ん、それって天海陸ちゃんのサーヴァントの入れ知恵かしらぁん?」
「何でそれを…!いや、そうか。お前のその帽子は…!」
解析魔術を使ったことによって性能が判明したキャスターの宝具、金霞帽(きんかぼう)。
使い魔の類ではなくその宝具の索敵能力で自分達の動きを察知していたという事か。
「じゃあわらわも聞きたいのだけどぉん、どうしてその陸ちゃんが自分のサーヴァントだけを連れてこっちに向かってきているのかしらぁん?」
「何だと…!?いや、その手には乗らない。
これ以上虚言を弄するならすぐにでも斬って捨てるぞキャスター!」
猛るセイバーを歯牙にもかけずにクスクスと不気味な笑いを浮かべるキャスター。
そんなセイバーに取り合わずに士郎にある提案を持ちかける。
「士郎ちゃん、もし気になるならこの場でわらわの金霞帽を投影しても構わないわよぉん?
貴方解析とかコピーとか得意でしょぉん?
これが貴方にとって投影したら危険なものかどうかなんてもうわかってるはずよぉん」
「…………わかった、今だけ乗ってやる。投影開始(トレースオン)」
セイバーを手で制しつつ金霞帽を投影する。
神秘と化学の両側面が入り交じった仙人界の宝貝は士郎の投影魔術とは相性が悪く、ワンランクどころの性能低下では済まなかった。
しかしそれでも今この場では必要十分な性能を発揮した。
衛宮士郎と投影した金霞帽の組み合わせで可能なことは精々が数百メートルをごく短時間索敵する程度のことだ。
しかも燃費も異常に悪く姿を隠す機能は再現できない、本物と比べれば贋作どころか粗悪品と呼ぶしかない。
だがそれで十分だった。
肥大化した視野は学園から離れて柳洞寺に向けて移動している天海陸と実体化した陸のセイバーをしっかりと捉えていた。
こちらへの援軍か?だがそれにしてはあまりにも歩みが遅すぎる。
何より目を疑ったのは―――何がおかしいのかゲラゲラと嗤う陸のセイバーだ。
先ほどの温和ながら誠実そのものだった印象とは似ても似つかない。
(何だ、これ―――?)
士郎の背筋を冷たいものが走った。
自分達は何か、とんでもない間違いを犯したままここに来てしまったのではないか。
未だ確かな正体のわからない不安が際限なく膨れ上がっていく。
「シロウ……これは……」
パスが繋がっているからか、セイバーにも同じ光景が知覚できたようだ。
表情から察するに彼女もまた士郎と同じことを考えていたようだ。
キャスターの方を見れば、いっそう不気味な笑いを浮かべている。
「ねえ士郎ちゃん、セイバーちゃん。
貴方たちは“何を理由にして何のために”わらわを討ちに来たのぉん?」
「…それは。いや、貴様が凛のサーヴァントでないことは既に分かっている!
貴様はアーチャーを殺し彼女の新たなサーヴァントに収まり、令呪を使われた腹いせに凛を殺したのだ!
それだけではない!先ほども切嗣と結託してルルーシュのギアスの情報を切嗣に流し、ガウェインを操らせて貴様を最も警戒していたライダーとハジメを殺させた!
百歩譲ってリクたちが殺し合いに乗っていて、漁夫の利を得るためにここに向かっているのだとしてもこの事実は最早動かない!」
「アンリマユ、宝石剣ゼルレッチ、大聖杯にアインツベルンの用意した小聖杯」
「っ!?」
キャスターの口にした四つの単語は二人を動揺させるには十分な重みがあった。
ムーンセルの事情に詳しい太公望やガウェインも士郎達に聞くか学園で調べるまで第五次聖杯戦争の詳細は知りもしなかった。
であれば、それはキャスターが真実遠坂凛のサーヴァント、それも殺し合いの末の妥協混じりの契約ではなく初期から彼女に配され、一定の信用を得ていたのでなければ知り得ぬ情報ではないのか―――
「それともう一つ、わらわがその切嗣ちゃんとかいう子と結託して太公望ちゃんを排除する。
確かによく出来た筋書きではあるけれど、何か肝心な事を忘れてないかしらぁん?
実際にわらわ側にはそれなりに利益があったけれど、その切嗣ちゃんとやらはマスターの制御のないキャスターのサーヴァントの言う事をあっさり真に受けて数時間足らずで作戦決行しちゃうようなお間抜けさんなのぉん?」
「!!!」
セイバーの瞳が限界まで見開かれる。
わかった、先ほどから感じていた僅かな違和感の正体がわかってしまったのだ。
セイバーはかつて衛宮切嗣のサーヴァントであったが故に。
切嗣は良くも悪くも非常に慎重かつ周到な男である。
そして切嗣が動く時は殆どの場合一定以上の勝機あってのことだ。
その切嗣が裏切りのクラスたるキャスターの齎した情報を元にして動く?
有り得ない、そんなことは決して有り得ない。
それが衛宮士郎の養父ではなく魔術師殺し・衛宮切嗣であればなおさらだ。
「先ほどのランサーとの戦闘はお互い宝具を使った以上相当に目立っていたはず。
切嗣かあのライダーがそれを監視していたとすれば、キャスターからの情報提供などなくてもルルーシュのギアスは把握できる…!
いや、それだけの確信がなければ切嗣がああも大胆な策に出るはずがない!」
「…セイバー、それだけじゃない。
こいつの宝具と能力でアーチャーを、あの野郎を倒すのは…恐らく無理だ。
こいつは防性に特化したサーヴァントだ、攻撃にはまるで向いていない」
地面に落ちた五火七禽扇とキャスター自身を見比べた士郎が分析の結果を伝える。
確かにこのキャスター、蘇妲己は魔術師の英霊としては一級品だ。
が、それは戦闘者として一流であることを意味しない。
それに無限の武具を扱えるアーチャーを五火七禽扇だけで圧倒するのは無理がある。
先ほど失った宝具、傾世元禳にしても同じ事だ。
アーチャー、英霊エミヤが持つ固有結界“無限の剣製”には使い方次第でAランク以上の威力を叩き出す剣も防御突破の概念を持つ剣もいくらでも存在する。
加えて奴自身防御用の宝具も少数ながら投影できる。
こと直接戦闘で英霊エミヤシロウが蘇妲己に痛手も与えられず完敗する事など士郎には考えられない。
遠坂凛という強力なマスターがついているのであれば尚更だ。
「それに、貴方たちが信じていた“妲己ちゃん☆黒幕説”を吹き込んだ人間。
それって果たして誰だったのかしらねぇん?」
「…!確かにこれは全てリクや彼のサーヴァントが言っていた事だ。
だがリクはルルーシュのギアスにかかっていた!
我々に嘘などつける、はずが……いや、待て」
嘘がつけない?ギアスにかかっていた?
その理屈では直前にキャスターの襲撃を受けているのに陸のセイバーが何の対策もしなかったということになる。
ルルーシュのギアスはサーヴァントからすれば直前の魔力の高まりや微細な予備動作が丸見えだ。
キャスターに敗北したという前例があるのにそれを未然に防げなかった、というのは流石に手落ちが過ぎないだろうか?
それに金田一も陸のセイバーの不自然な能力の低さに疑問を持っていた。
加えて短い間だが行動を共にしたことで彼のセイバーが何らかの形でキャスターの適性を持っている可能性は十分有り得るとセイバーは踏んでいる。
にも関わらず主人を守るために何の対策も用意せずルルーシュのギアスを止める素振りすらなかったというのか?
「なあセイバー、もし天海のセイバーが魔術やそれに近い能力を持ってるとしたら、前提が全てひっくり返ることになる。
実際俺から見てもあいつは純粋な剣使いって感じじゃなかった。
お前と一緒に戦ってるんだからそのぐらいは見分けられる」
「…今となってはその可能性も疑わざるを得ないようですね。
私はキャスターならばどのような小細工を弄していても不思議ではない、そう思っていた。
勿論今もこのキャスター、蘇妲己は信用に値しないサーヴァントです。
しかし、リクのセイバーに魔術の心得があるとすれば、小細工を使うという可能性はそのまま彼らにも該当する…!」
例えば、天海陸とそのサーヴァントには最初からギアスあるいは魔術への対抗策があったとすれば。
士郎とセイバーが信じてきた“ギアスをかけられた人間は嘘がつけない”という論拠は根本から崩れることになる。
そしてギアスをかけられた際に天海陸が嘘の証言を行なったとすれば、そうする理由はもはや一つしかないのでは―――?
「…しかし、だからといってキャスター、貴様が信用できるという事にはなり得ない。
確かにリクにも注意を向けるべきなのかもしれない。
だが、我々の思考を誘導する貴様の罠という可能性とて捨てきれない」
「確かにわらわの言葉ではこれが限界ねぇん。
魔術師のサーヴァントは信用できない、実に正しい一般論よぉん。
じゃあ、わらわ以外の貴方達が信用する人間の言葉ならどうかしらぁん?」
そう言うやキャスターは懐から黒い長方形の物体を取り出し、士郎の足元に転がした。
見たところそれはICレコーダーのようだった。
罠に乗るようで癪ではあったが自分達の考えが正しければ既に事態は切迫しつつある。
魔術的な仕掛けが施されていない事を確認し、慎重に再生ボタンを押した。
『あ~テステス、本日は晴天なり。
って聖杯戦争中のSE.RA.PHで雨なんぞ降るわけもないか。
わしはライダーのサーヴァント、真名は太公望。
今これを誰かが聞いておるという事はわしらは道半ばで脱落したという事だろう。
もしこれを聞いている者が殺し合いに乗らず、この聖杯戦争からの脱出を考えておるのであれば今からわしが話すことを聞いてほしい』
聞こえてきたのはつい先ほど消滅した仲間、太公望の声だった。
しかし何故こんなものが、そもそもこんな代物を残しているなら何故教えてくれなかったのか。
そんな士郎の疑念に答えるはずもなく、ICレコーダーはただ機械的に仲間の声を再生していく。
『まず話しておきたいのは脱出を志す人間にとってある意味最大の障害となるであろう者たちと現在わしらが関わっておる参加者の死の真相についてだ。
事の発端は午前8時20分頃、マスターを失ったキャスターのサーヴァント、わしの同郷でもある蘇妲己が柳洞寺に駆け込んできたことだった――――――』
ここからは士郎達も知っている事だった。
といってもあの時点でキャスターが話した情報が主だったものであるが。
一応この段階で判明していた陸とこなた及び彼らのサーヴァントの情報も入っていた。
『―――以上がわしと仲間たちで協議した現時点での行動方針だ。
そしてここからはわし自身のこの事件に関する見解を述べたい』
「っ!!」
これは士郎達も聞いていないことだ。
いや、恐らく太公望自身落ち着いたら話す気でいたのかもしれない。
何しろルルーシュは別行動中で士郎に至ってはお世辞にも平静とはいえない精神状態だったのだから。
『まず恐らく最も怪しいであろう妲己だが…わしはこやつが遠坂凛殺しの直接の犯人ではないと思う。
だがこやつが潔白ということもない。
こやつは索敵と自身の隠匿に特化した宝具“金霞帽”と絶大な防御力と強力な誘惑(テンプテーション)能力を備える羽衣型の宝具“傾世元禳”を持っておる。
まず口実を作ってマスターと別行動を取り、それら宝具を上手く使い他者が遠坂凛を殺しやすい状況を作り出す。
そして首尾良く遠坂凛を殺させた後、魔力探知にかかりにくいNPCを操ってマスターの令呪のみを手にし、この円蔵山という土地と契約した。
まあぶっちゃけわしがあやつに直接聞いて確かめたというのもあるがな。
ともかくあやつは自分は極力手を汚さず他人に手を下させるタイプだ、直接マスターを殺すなんてチープな真似はするまいよ』
そんな話は初耳だ、しかし太公望を責めるのも酷だろう。
知り合い同士でしか通じない論拠をあの状態の士郎が素直に受け入れられたかどうかは怪しい。
『もちろんそれだけというわけではない。
最大の理由はあやつがこの土地との契約が出来たという点だ。
人間相手の契約と違って土地との契約というのはあまり融通がきかん。
加えてムーンセルは管理の怪物、自らのマスター以外の令呪で土地との再契約が出来るなどという事態を容認することはまず有り得ん。
そもそも本来マスターが主体となる聖杯戦争で、サーヴァントだけが他人と再契約することも消滅の危機もなく存命しているという事自体が反則ギリギリの行為だからな。
それは妲己であろうと変わらん。他人から見れば万能に見えるあやつもサーヴァント化している以上少なからず制約は受ける。
これらの事から、少なくとも妲己のマスターが遠坂凛であったというのはほぼ疑いない事実だ』
「…………」
太公望の解説を聞きながらキャスターを見れば、妙に得意げな顔で笑っている。
やはりこれは―――
「わらわの用意したもの、ではないわよぉん」
こちらの考えを見透かしたように否定の言葉が入った。
「わらわならNPCを操ってこういう現代機器を手に入れることは出来るわぁん。
でもそれを読まれる可能性がある時点でこれを使って自分の潔白を証明なんて策は取らないわぁん。
多分太公望ちゃんが金田一ちゃんのクレジットカードを使って勝手に買ったものでしょうねぇん。
もしかしたらスープーちゃんに買いに行かせた可能性もあるけれどぉん」
ちっちっちと指を振りながら語るキャスターに釈然としないものを感じながらも続きを聞く。
『では妲己でなければ誰が遠坂凛を殺したのか。
…うむ、もったいぶってすまんが、これに関してはハッキリとした名前を出す事は控えたい。
現時点でわしらが知っておる情報は大半が伝聞かつ断片的なのだ。
わしが少ない情報から誤った推理をし、全くの見当違いな人物を犯人として脳裏に浮かべている可能性があるからだ。
だが伝えられることが何もないというわけでもない。
これは聖杯戦争だ、敵マスターを殺すという行為に至ったからには必ず相応の理由がある。
もしこれが内部犯であれば、犯人には単に敵マスターを倒す以上に、遠坂凛個人を殺すことによって得られる明確なメリットがあったはずだ。
故にもしこの件について調べるのであれば当時遠坂凛の周辺にいた人物。
とりわけ遠坂凛の死亡後に利益や恩恵を得た人間がいたかどうかをまずは疑うのだ。
最も利益を得た人間こそが最も疑わしい、まあ推理の基本と言われれば反論は出来んのだが。
それとわしが脱落した後もまだ妲己が生きているようであれば、早急に止めを刺すのだ。
あやつは文字通りの意味で人を人とも思わぬ愉快犯、わしらの監視が無くなれば何をしたとしても不思議ではない。
良いか、止めを刺すのだぞ。絶対にキッチリと止めを刺すのだぞ』
一度再生を切る。続きはあるようだが今は状況が差し迫っている。
目の前にはキャスターが、そして今や限りなく怪しい人物となった天海陸とセイバーが何を狙ってかこの柳洞寺に近づいている。
早急に結論を出さなければならない。
「…最も利益を得た人間。少なくともコナタとライダーではないでしょう。
特にライダーは先ほども私と共に最前線で戦っていた。
その他の状況から鑑みても凛の死で大きな恩恵を得たとは考えにくい」
「だとしたら……天海、なのか?」
「マスターとサーヴァント、どちらが主導しているのかまではわかりませんが恐らく。
現に彼ら、特にセイバーの方は能力の低さ故に先ほどは危険度の低いルルーシュ達の護衛に回っていました。
切嗣のライダーに狙撃こそされましたがあれは誰にとっても計算に入れられる要素ではなかった。
そして何より、私達はリクのセイバーの助言に従ってキャスター討伐に赴いた。
いいえ、はっきりと言えばあのセイバーこそがリク達の集団の中で最も大きな発言力を持っている」
「ああ、確かにあいつがリーダーシップを取っていた。
あとは遠坂を殺した理由か目的だけど、あいつの能力の低さから考えたら答えは一つしかない。
弱いサーヴァントが手っ取り早く自分を強化するなら魂喰いしかないんだ。
そしてターゲットが遠坂なら、その効率だって段違いだ」
これまでバラバラだった点と点が繋がり、一本の線になっていく。
未だ確定ではないが、もう彼らを無条件で味方とは考えるべきではないだろう。
とすれば残る問題は―――
「お話は終わったかしらぁ~ん?
さっ、わらわの気が変わらないうちにザクっとスパっとやっちゃってぇ~ん♥
一流の悪役ヒロインは引き際を弁えてるものなのよぉん」
相変わらず抵抗の様子すら見せないキャスターである。
この女は聖杯戦争の趨勢自体眼中にないのではないだろうか?
「その前に問うておこう、貴様が凛を見殺しにしたというのは事実か?」
「そうよぉん、ご主人様は魔術師のわりに良い人だったのだけれど、ちょっと正義感が強すぎたわぁん。
わらわって束縛されるのあんまり好きじゃないのよねぇん」
「……そうか、ならば最早何も言うことはない」
今度こそ迷わず剣を構え念のため周囲の魔力に気を配り、そして一息に無防備なキャスターに迫り、その心臓に刃を突き立てた。
微かな吐血を漏らしながらもその微笑が崩れることはない。
「…キャスター、あんた一体何を考えてるんだ?
あんたは間接的でも遠坂を裏切ったんだろ?
だったら、どうして俺達に手を貸すような真似をしたんだ?
アサシンまで召喚したのは勝つためじゃなかったのか?」
その微笑みの意味が、彼女の思考がわからなくて。
思わず士郎の口から出たのは最も気になっていたことだった。
全身が崩れゆく中、キャスターは最期の時まで超越者じみた余裕を崩すことなく答えた。
「わらわは基本楽しければオールオッケーなのよん。
小次郎ちゃんを召喚したのもその方が面白そうだから。
この聖杯戦争も最上とはいかなかったけど中々楽しかったわぁん。
陸ちゃんへのささやかな意趣返しも出来たし、士郎ちゃんたちの苦悶に歪む顔も中々見ごたえがあったわねぇん。
でもそうねぇん、敢えて一つだけ理由を挙げるなら―――」
一度だけ意味深に目を閉じ、悪戯っぽい笑みを浮かべた。
「―――わらわが遠坂凛のサーヴァントだから、かしらぁん」
そんな言葉を残して、稀代の悪女・蘇妲己は完全に消滅した。
主を策略で見殺しにしながら、最後の最後で主命を果たした魔術師の英霊。
その真意はどこにあったのか、それを知る者はもういない。
&COLOR(#FF2000){【キャスター(蘇妲己)@藤崎竜版封神演義 消滅】}
・虚飾を払うは―――
それからはほとんど陸とイスラも知っている通りだ。
二人に強い不信感を抱いた士郎とセイバーは一計を案じた。
まず士郎が二人に第五次聖杯戦争に関する事柄を聞く。
このムーンセルの聖杯戦争にしか参加していない英霊でもその事について知っている可能性、つまりは蘇妲己が凛のサーヴァントではないという可能性もまだ僅かには存在していたからだ。
そしてイスラの返答によって蘇妲己が凛のサーヴァントであることが概ね証明されたと同時、士郎の射撃と数百メートル以上離れた地点から全開の魔力放出で一瞬にして距離を詰めたセイバーの同時攻撃で陸とイスラの正体を暴いた。
といってもこの攻撃で二人を殺すつもりはなかった。
一瞬でもイスラを足止めし、セイバーの直接攻撃―――本当に何の能力も持っていないようなら寸止めが出来るよう剣に込めた力は三割程度に抑えていたが―――で陸の正体を見極めるという策だった。
いや、実際には策とも呼べない強引な賭けだった。
これでもし陸とイスラがシロであれば今度こそ殺人者の謗りを免れないところだったのだ。
この場にルルーシュでもいればもっと穏当かつ確実な策を閃いたのかもしれないが。
しかし結果としてこれで陸とイスラの正体はほぼ完全に露見した。
どころか陸がギアスにかかっていなかったという物証まで入手できたのは期待以上の成果といっていい。
「これで全ての疑問は解決した。
凛を殺す際、どうやってあのオーズを引き離したかが引っ掛かっていた。
しかしそれほどの力ならばごく短時間彼の注意を引くぐらいは可能だったはずだ。
…まだ何か言うことはありますか?」
セイバーの最後通牒に等しい言葉に陸もこれ以上言い逃れは出来ないことを悟った。
「ハハッ…何だよこれ。キャスターが抵抗もしないとかどうなってんだよ。
しかもこいつらに塩まで送っちゃってさあ、何なんだよマジで。
話が全然違うじゃないか…どうなってんだよイスラアアッ!!!!」
「……済まないリク。僕の見積もりが甘かったらしい」
「…謝るなよ、謝ってんじゃねえよ!
何か、何かないのかよ!?お前がチャンスだって言うからここまで来たんだぞ!?
なのに、なのにこんな……!お前のせいだぞこのハズレサーヴァント!!!」
「…………」
こんなはずではなかった。
イスラはこれまでに聞いていたキャスターの動向と、先ほどのアサシンの存在からキャスターは勝ち抜きを狙っていると確信していた。
というよりその確信があったからこそ今までのイスラの嘘は聞いた者に強い説得力を与えていたのだ。
そもそもキャスターがさしたる願いも目的も持たずに聖杯戦争に参加し、なおかつ自分の娯楽のためだけに場を引っ掻きまわして、思わせぶりな行動を取ってきたなどどうやって想定しろというのか。
否、それを言い出せば彼らの嘘が露見した理由の多くはこれまで知らなかった、知る機会のなかった要素によるものばかりだ。
通常の域を大きく逸脱した解析魔術を扱える衛宮士郎。
キャスターと同郷の出身だった柳洞寺のライダー、太公望の存在。
関係者にのみ通じる第五次聖杯戦争の詳細。
セイバーであるイスラには考えもつかない、土地そのものと契約するという手段によって客観的に自らが遠坂凛のサーヴァントであることを証明したキャスター。
かつてイスラ自身が口にした情報戦における遅れ。
それがこんな、あと一歩という局面で状況を完全にひっくり返す決定打になるとは思いもしなかった。
だがイスラがそう考えるのも無理もないことだ。
何しろ陸とイスラのここまでの道中はあまりにも上手く行き過ぎていた。
有り体に言えばとにかく運が良かった。
綱渡りに等しい遠坂凛の暗殺を見事こなたと映司に気付かれることなく成功させた。
この時キャスターの策で凛の令呪を奪われたが、それは単にキャスターの用意が陸とイスラを上回っていただけだ、二人の失策ではない。
さらに事前に用意した反魔の水晶がギアスに対してこれ以上無いほどに効果を示したこと。
つい先刻の切嗣陣営の襲撃の際最も少ない被害で切り抜けられたこと。
切嗣の策によって結果的に柳洞寺にキャスターが孤立し、さらに能力面で厄介な士郎のセイバーにキャスター討伐を押し付けることに成功したこと。
これだけの幸運に恵まれたことが、陸とイスラの行動を大胆にさせた事は否めない。
最早情報戦の遅れは完全に覆した、後は柳洞寺の魔力の流れを乗っ取れば策を弄する必要もない。
キャスターや士郎らもお互い潰し合わせさえすれば、ここまで温存してきたイスラの魔力でどうとでも処理できる、イスラをしてそう信じて疑わないほどの好機だった。
その先が奈落の底に続く落とし穴であることなど考えもせずに。
だがそれを誰が責められようか。
聖杯戦争において敵が戦力を分断させた時を狙って仕掛けるのも、大量の魔力を得られる好機を逃さないのも正しい戦略だ。
そもそもキャスターがイスラの予想した通りの勝利を狙う、常道のサーヴァントであれば彼らの行動が問題になる事など本来有り得ない筈だった。
繰り返すが彼らの取った戦略は普通なら正解であり、成功への最短ルートだった筈なのだ。
(しかしそれでも…もっと慎重に事を進めるべきだったのかもしれない)
後悔は決して先に立つことなど無いが、それでも悔やんでも悔やみきれない。
振り返って考えれば、イスラが陸に性急な行動を提案した背景にはあの男、衛宮切嗣の影があったのだろう。
自分達の嘘が一切通じる余地のない危険な敵手、それに少しでも対抗するにはこちらも力をつける必要がある、そう思った。
衛宮切嗣のサーヴァント、仮面ライダーディケイドとやらがこなたのライダー、オーズを倒すことに執着しているらしいというのもあった。
何せこの先こなたらと行動を共にする限り常にあの陣営の脅威に晒されることになるのだ。
先ほどはルルーシュが標的になり、士郎のセイバーが盾代わりになってくれたおかげで事なきを得たが、これからはそうではないのだ。
そういった理由から敢えて別行動を取るという考えに至ったのだ。
上手くすればイスラが柳洞寺の魔力を得るまでの間、こなたらが切嗣とディケイドをおびき寄せる囮になってくれるのではないかという考えもあった。
結局のところ、そうした目論見は全てにおいて裏目に出たのだが。
ここまでの幸運の連続こそが逆に陸とイスラから慎重さを奪う不幸の原因だったのだ。
「シロウ、決断を。この者たちを放置すればコナタを始めとした多くの参加者にとっての災厄となるでしょう」
思考している間にも士郎のセイバーが主人に陸とイスラの処断を促す。
キャスターが戦わなかったせいでセイバーの魔力はほぼ全く消耗されていない。
まともに戦えば分が悪いどころではない。
とはいえこちらがそれに付き合う道理はない。
(リク、ここは一度退いて態勢を立て直そう。
不意をついて令呪を逃走用に使ってくれれば十分に―――)
「……ろせ」
(リク……?)
「あいつらを殺せ!!イスラアアアアアアアッ!!!」
陸の腕から令呪の輝きが放たれる。
その強大な魔力は逃走ではなく殺戮の強制としてイスラにのしかかる。
「なっ…リク!?一体何を―――」
「お前こそ何言ってんだよ!状況わかってんのか!?
バレたんだよ全部!!なのに逃げてどうするってんだよ、ええ!?
こいつらが泉やルルーシュにオレ達の事を話せば全部終わりだろうが!
だったら…だったらもう殺すしかないじゃないかっ!!」
陸の表情は今までイスラが見たこともないほど強ばり、眼は血走り微かに涙が滲んでいる。
剣を握る手は震え呼吸は荒く、平静を失い半狂乱になっていることは火を見るより明らかだった。
無理もないことだ、全てが上手くいっていた状況から瞬く間にどん底まで叩き落とされたのだ。
天海陸はイスラ・レヴィノスほど完成されたメンタリティは有していないのだから。
「………“紅の暴君(キルスレス)”」
イスラもまた事ここに至って陸を諌めることは不可能だと悟った、悟らざるを得なかった。
今まで陸がイスラに一方的に同族嫌悪の感情を抱きながらも主従関係が成立していたのは、イスラの知略が多大な成果をもたらし、陸もそれを割り切って受け入れてきたからだ。
だが今回のあまりにも大きな失態によってイスラは陸の信用を大きく損なってしまった。
実際には失態と呼ぶには酷なものであるとしても今の陸にそこまで冷静に判断する力は無い。
ここでこれ以上陸に意見すれば例えこの苦境を切り抜けたとしても、この先の関係修復が不可能になってしまう。
それならば無理に令呪に逆らわず、全力で目の前の敵を屠る事に専心するべきだ。
魔剣の真名を解放し容姿が大きく変化したイスラだが、当然それだけの事で終わる筈が無い。
その身から発される魔力は今までが嘘のように荒く猛々しい。
「シロウ!この者の相手は私が引き受けます!」
その禍々しい力がマスターに及ぶ事を警戒したのだろうセイバーがイスラに突進し、引き離しにかかる。
イスラもまた陸の力量を信じてセイバーの誘いに乗る形となった。
そして陸も刃旗を手にし、常人には視認すら困難な速さで士郎に斬りかかった。
咄嗟に投影した干将・莫耶で受け止めるが、膂力が違いすぎるためにジリジリと押される格好となる。
「ぐっ―――!天海、お前は………!」
「そうさ、お前らさえ、お前らさえ消せばまだやり直せるんだ!
遠坂だって殺ってやったんだ、もう躊躇うもんかよ!!」
先ほど戦ったランサーのマスターが操っていたイザナギですら可愛く思えるほどのパワーとスピードの前にまたも防戦を余儀なくされる。
技量はまだまだ発展途上ながら、サーヴァントにすら迫る理不尽なまでの身体能力はただそれだけでほとんどのマスターを圧倒する。
―――だがここに一つの例外が存在する。
「隙だらけなんだよっ!!」
陸の横薙ぎの斬撃ががら空きになった士郎の右脇腹を襲う。
必中を確信して振った大剣はしかし、白と黒の双剣に受け流された。
僅かに態勢を崩した陸を士郎の反撃が襲うが意識圏によって止められる。
だが完全ではない、短剣が障壁をガリガリと削り、ついには意識圏を叩き切った。
「くそっ、意識圏が!?」
予想だにしなかった事態に慌てて距離を取る。
サーヴァントならばいざ知らず、魔術師の物理攻撃で意識圏を断ち切られるなど想定外だ。
いや、よくよく見れば士郎が手にしている双剣からはイスラが持っている紅の暴君と同じ気配を感じる。
(宝具ってことかよ…!チートしてるんじゃないだろうなコイツ!?)
物理攻撃に対して絶大な防御力を発揮し、棺守や同じ刃旗使い、あるいは超常の存在たるサーヴァントでなければ傷つける事すら不可能に近い意識圏。
だがそれは決して全てのマスターに対して無敵を誇る事を意味しない。
陸と同じく英霊に迫る戦闘能力に加え、高ランクの宝具の担い手でもあるベルンの覇王・ゼフィール。
そして特異な起源と魔術特性から宝具級の神秘すら投影で再現してのける錬鉄の魔術師・衛宮士郎。
彼らの操る宝具の強力な神秘は刃旗使いの意識圏を突破することすら可能とする。
そう、この二人だけはこの聖杯戦争において例外的に正面から天海陸と対等に戦える存在なのだ。
「でもな、スペックじゃこっちが圧倒的なんだよ!!」
気を取り直して再度高速で斬りかかる。
伊達に棺守との戦いを生き抜いてはいない、相手に意識圏を突破する手段があるとわかっていれば相応の戦い方をすれば良いだけだ。
「づ、は―――!」
しかし士郎も粘る。怒涛の勢いで連撃を浴びせかけるも、常にあと一歩というところで受け流されてしまう。
時折大きな隙を見つけて、そこに正確に打ち込んでいるにも関わらず必ず防がれるのだ。
(何なんだコイツ!?強くはないのにやりにくい!)
決して力強くもなければ速さもない凡庸な剣捌きを攻めあぐねているという現実に焦りが募る。
最初から刃旗使いとしては強大な力を持っていた陸には思いつくことさえ出来ないだろう。
衛宮士郎が天海陸に白兵戦において格段に劣っている、その事実こそを武器にして渡り合っているなどとは。
士郎はただ守るだけでは陸の猛攻を凌げないと判断するや、時折わざと隙を作ることで陸の攻撃箇所を誘導しているのだ。
かつて自身の未来の姿、英霊エミヤの腕を移植されていた時期に頭に流れてきたあの男の経験値がこの無謀ともいえる策を可能としていた。
とはいえ今の士郎自身の力量は英霊エミヤに到底及ばない。
この戦法とて一級のサーヴァント相手に通じるほどの域には達していないが、今の冷静さを失い視野狭窄に陥った天海陸になら十分に通用する。
だがそれも長くは続かない。
膂力や俊敏性に限らず、持久力や反応速度などあらゆる身体的要素において衛宮士郎は天海陸に大きく遅れを取っている。
意識圏を破る手段を持っていようが戦闘者としての基本性能の差は小手先の戦術だけでカバーしきれるものではない。
あと十分と持たずに衛宮士郎は天海陸に押し切られてその身を両断されて敗北する。
「―――投影開始(トレースオン)」
ならば勝てるものを用意すればいい。
陸の剣戟を防ぎながらも自己の内に埋没し、投影する剣を選んでいく。
「――――憑依経験、共感終了」
呪文を紡ぎ、衛宮士郎だけの弾丸を順に装填していく。
「―――工程完了。全投影、待機(ロールアウト、バレットクリア)。
―――停止解凍(フリーズアウト)」
ここに来てようやく陸の目にもその異常が見てとれた。
陸の攻撃を防いでいる士郎の真上に十六もの刀剣が突如として出現した。
魔術師ではない陸でもわかる、宙に浮かぶその剣群はどれもが一級品、すなわち宝具であるのだと。
「おい、冗談だろ……?こんなの反則どころじゃないだろ……!」
まるで悪夢だ。
あれらが一発でも直撃すれば刃旗使い、いやサーヴァントであっても致命傷になり得る。
意識圏で防げるか?馬鹿か、そんな生温い手を打つ相手なものか。
何より相手の懐に飛び込みすぎた、命脈を保つべく意識圏を全開で展開しつつ全速力で飛び退くが間に合うか。
「―――全投影連続層写(ソードバレルフルオープン)!!」
宙空から剣群が陸の命を刈り取るべく一斉に襲いかかる。
だが活路はある、一発でも命中すればそれで十分と考えているのか剣群は陸の周囲を円状に覆うように飛来している。
(―――いける、真ん中が手薄だ!)
敢えて中央へ動き、万全の態勢を整える。
下手に大きく動いて直撃するよりは中央で腰を据えて迎撃するのが上策。
「な、めるなああああ!!」
十六の剣のうち陸に命中するのは三本。
大剣で二本を弾き飛ばし一本を意識圏で逸らした。
残りは全て陸の周囲を囲うように地面に突き刺さった。
凌いだ、その確信を得たまさにその瞬間だった。
「壊れた幻想(ブロークンファンタズム)」
呪文と同時、弾き、回避した三本と周囲の十三本の剣が一斉に轟音を立てて爆発した。
意識圏でもカバーしきれない、全方位からの爆発と衝撃によって陸の身体は嵐に巻き込まれた木ノ葉のように軽々と吹き飛ばされた。
「ぎ、ああああああああっっ!!!!!」
魔術師ではない陸には何が起こったかもわからない。
棺守や刃旗狩りの男・タカオとの戦いを経た陸だが剣が爆発するなどという知識はない。
もし事前知識があれば真ん中に飛び込んで迎撃するという選択肢は排除して考えていただろう。
壊れた幻想(ブロークンファンタズム)。
宝具に内包された神秘を魔力による爆発に変える宝具の変則的使用法。
その威力は爆発させた宝具本来のランクより一段上の破壊力を持つ。
だが本来聖杯戦争においてこの技が用いられることは無い。
宝具とは担い手の半身、自らの相棒たる宝具を一度きりの爆弾にする英霊などまずいない。
だが何事にも例外は存在する。
特殊な投影魔術によって魔力が続く限り衛宮士郎はいくらでも宝具を用意できる。
この特性を活かせばこのように宝具を使い捨ての砲弾のように扱う事すら可能だ。
もっともこれですら対魔力を持つサーヴァントには多少厄介ではあっても必殺にはなり得ないのだが。
「が…ぐ……、くそっ……!」
朦朧とする意識を気合いで保ちながらよろよろと立ち上がる陸だがその足取りは覚束ない。
反魔の水晶を奪われたことによって対魔力の加護を得られなかったために甚大なダメージを被ったのだ。
服と全身は焼け焦げ、爆発の際に飛んできた様々な破片で体の至るところに切り傷が出来ている。
さらに全方位からの爆音を至近距離で聞いたために聴力にも軽度ながら異常が起きている。
意識圏による防御すら宝具の爆撃に対しては気休め程度にしかなりはしなかった。
「その障壁は全方位には張れないらしいな。
…天海、もうやめろ。言っておくが俺はその気になれば一度に二十七本まで剣を投影して発射できる。
そんな有り様じゃもう避けることも、さっきみたいに戦うことも出来ないはずだ」
これはハッタリだ。
今の士郎には二十七どころか先ほどの半数を投影できるか否かという程度の魔力しか残っていない。
先ほどのアサシンに対して行なった赤原猟犬の真名解放、そして金霞帽の投影と行使。
セイバーの魔力を温存するために支払った代償としては安いが、今この場の戦いには大きな影響を及ぼしている。
「…………」
しかし魔術師でない陸にはそれがハッタリかどうかを判別できない。
士郎も一般人でありながら聖杯戦争に参加した金田一という実例や、ここまでの陸の魔術師らしからぬ言動から陸に魔術の心得はないと当たりをつけていた。
陸は未だ気付いていない。自分が魔術師でなく、魔術の知識も不十分であるという事実がどれほど足を引っ張っているのかを。
(これでもし天海がさっきと同じ調子で攻めてきたら……)
(もしアイツの言ってる事が本当で、まだあれ以上の剣を用意できるのなら……)
お互いに限界が近い、それ故に僅かな時間戦況は膠着する。
―――だとすれば、勝負を決するのは彼らの従者に他ならない。
「はぁああっ!!」
「っ、ぐ―――!」
金属と金属の打ち合う音が響きわたる。
衛宮士郎と天海陸、彼らの主人の戦場より幾分距離を離した池の周辺で二人のサーヴァントは余人には視認すら適わぬ剣戟を繰り広げていた。
攻めているのは衛宮士郎のサーヴァント、アルトリア・ペンドラゴン。
防御に回っているのは天海陸のサーヴァント、イスラ・レヴィノス。
百を越え、千に届くのではないかという程の打ち合いを経ても未だに天秤は傾かない。
「さっきの見えない剣は、く、やらないの、かい―――!?」
「知れた事を、先ほど我が剣を見せた貴様に風王結界が通じると思うほど私は愚かではない」
セイバーは今、手にした黄金の剣カリバーンに不可視の風を纏わせずに戦っている。
何しろ初対面の時に一度真名と共に見せているのだ、サーヴァントならばそれだけで刃渡りや間合いも正確に計れただろう。
ならば通用する望みのない風王結界ではなく、全身の魔力放出に上乗せする。
それに敢えて刀身を晒す事で切れ味は大きく増す。
この敵を相手取るにはこれこそが最上の策だとセイバーは看破していた。
(参ったね、こうまで地力に差があるとは思わなかった。
リク、令呪を使った君の判断は正しかった)
一方のイスラは想像以上の敵の力量に舌を巻いていた。
伐剣覚醒による大幅な能力向上に加え、マスターからの魔力供給不足によって低下していたスキルのランクも令呪のブーストにより一時的に生前同様まで戻った。
はっきり言えば、今この時に限ればイスラは生前を僅かながら上回るほどの性能を得ている。
だからこそセイバーの全力の剣捌きにも一歩も引くことなく渡り合い、時折反撃に転じるまでに拮抗する事が出来ている。
だがそれだけだ。
圧倒的な能力ブーストを得ていてもイスラの剣が騎士王に届くことは無い。
そもそも剣の才能が違う。剣に生きた年月が違う。努力の密度が違う。
悲しいかな、セイバーにとってイスラの太刀筋はどこまでも凡庸な、読みやすいものでしかない。
サーヴァントとしてのステータス以前の、英霊イスラ・レヴィノスの限界ともいうべき壁。
如何に令呪が様々な奇跡を起こせるとはいえ、サーヴァントの技量を限界以上に高めることは流石に出来ない。
どれだけカタログスペックを底上げしようが、剣の力量が英雄レベルに達しないイスラが一級のセイバークラスの英霊と曲りなりにも互角の体を為しているという事実が既にして奇跡なのだ。
ならばイスラが最も得意とする召喚魔法ならばどうか。
確かに竜の因子を持つ騎士王が誇る破格の対魔力の前では暴走召喚とて通じる望みは薄い。
だが何一つとして通用しないわけではない。
例えばダークブリンガーのような物理的な攻撃手段ならば対魔力でも防ぐことは出来ない。
それが暴走召喚、更には令呪の加護も付加されるとあれば必殺の域にまで昇華される。
だが、それは撃てればという仮定の話だ。
「させんっ!」
「ぐっ……!!」
バックステップで距離を取ったイスラだったがセイバーはその上を行く。
魔力放出による急加速で瞬く間に距離を詰め、竜の咆哮の如き一撃を見舞う。
極限まで能力を強化されたイスラでも数歩分の後退を余儀なくされる剛剣からの呵責の無い追撃に晒され、再び剣戟に持ち込まれる。
先ほどから召喚魔法を使おうとする度にこの調子だ。
セイバーの未来予知じみた直感はイスラの召喚魔法の余兆を決して見逃さない。
最高ランクの対魔力を誇るこの身に対して尚魔法を用いようとするその動き。
それこそがイスラがセイバーを倒し得る手段を有しているという何よりの証左。
であればそもそも撃たせないという事が唯一最大の対策になり得る。
これが聖杯戦争。
真名を暴いたことでセイバーはイスラがどのような手札を持つかをある程度把握している。
無論マスターに与えられた透視能力のように詳細にスキルを見れるわけではない。
だが真名がわかれば相手の逸話や偉業といったおおよその得意、または苦手分野もわかる。
それ故に消極的であっても対策を打つ事が可能になるのだ。
「ハアッ!!」
セイバーの黄金の剣が防ぎきれなくなったイスラの身を削る。
覚醒の恩恵ですぐさま傷は塞がるもののその度に魔力を余計に消耗する。
だがイスラにとってはそれ以上に不都合な事がある。
(あの剣、確かアーサー王の選定の剣カリバーンだったか。
間違いなくAランク以上の聖剣だ、これでは呪いを活かすのも難しい…か)
イスラ・レヴィノスはその身に不死の呪いをかけられている。
Aランクに満たない攻撃では決して死に至ることは無い強力なその呪詛は聖杯戦争において極めて有用なスキルだ。
この呪詛を上手く活かせば敢えて敵の攻撃を受けてそこから反撃に転じるという戦法も使えるのだ。
だが通常攻撃がAランクに該当するセイバーの剣にはこの戦法が使えない。
ただでさえ剣士としての地力に開きがあるのだ。
下手に呪いを当てにした戦い方をしようものならそれこそ一瞬で致命傷を受けてしまう。
手詰まり、その単語が脳裏を過ぎる。
「……リクっ!?」
ちょうどその瞬間、イスラの脳をひりつくような感覚が襲った。
それはすなわち、マスターである陸が危機的状況に陥った事を示す。
ほんの一瞬気を取られた、それが不味かった。
「余所見をしている余裕があるのか!」
イスラが陸に気を取られたのを好機と見たセイバーが強烈な大上段を見舞う。
咄嗟に受け止めたが態勢を大きく崩され、次の薙ぎ払いを受け止めた衝撃で大きく吹き飛ばされた。
(不味い、令呪の効果が……!)
これまでセイバーとの戦いを互角たらしめていたブーストの効果が途切れた。
それ故に先ほどまで耐えられた一撃を持ちこたえられなかった。
「リク……!」
いつの間にかマスター達の近くまで移動していたらしい。
陸の方を見やれば明らかに深手を負っている。
何やら士郎と会話しているようだが距離があって聞き取れない。
ともかくこのままではジリ貧になる一方だ。
伐剣覚醒は維持するだけでも大量の魔力を消費するのだから。
先ほどアサシン相手に召喚魔法を数発使わされた事も響いている。
この先に大きく影響するが背に腹は代えられない、改めてこの場からの逃走に令呪を使うよう念話を送ろうとして―――
「イスラ、次の一撃でセイバーを殺せええっ!!!」
主の令呪に再びその身を縛られた。
「その障壁は全方位には張れないらしいな。
…天海、もうやめろ。言っておくが俺はその気になれば一度に二十七本まで剣を投影して発射できる。
そんな有り様じゃもう避けることも、さっきみたいに戦うことも出来ないはずだ」
士郎が降伏を促してくる。
ふざけるな、そんな真似をするぐらいなら最初から聖杯戦争になど参加していない。
だが怒り猛る精神に反して体はついてきてくれない。
全身は絶え間なく苦痛を訴え、足腰がまるで自分のものではないかのように言うことを聞かない。
(もしアイツの言ってる事が本当で、まだあれ以上の剣を用意できるのなら……)
今度こそ天海陸は終わりだ。
ハッタリという可能性もあるが、それがただの楽観でない保証がない。
剣を飛ばす前に斬り伏せるか。無理だ、奴は戦いながらでも剣を生み出せる。
イスラを信じて時間を稼ぐか。論外だ、性質がキャスターに近いイスラは騎士王とは恐ろしく相性が悪い。
(うっ…くそっ、あの野郎容赦なく持っていきやがって……!)
しかも陸の魔力、というより生命力は時間とともに戦闘中のイスラに流れていく。
これでは何のために凛から魔力を奪ったのかわからない。
「…くそっ、くそくそくそ、あんな奴がサーヴァントじゃなければ!
あいつのせいでこんな事になってるってのに、魔力だけは一人前に欲しがる気かよ…!
こんなはずじゃないんだ、こんな……!」
実際のところ、イスラが陸からも魔力供給を受けなければ戦えない原因の一端は陸自身が使った令呪にもある。
令呪の加護で限界を超えた力を発揮しているイスラだが、そこまでして能力を底上げするということは維持に必要な魔力も普段より増すということである。
通常のサーヴァントならば令呪の膨大な魔力で賄われるので問題にはならない。
だが伐剣覚醒を行なったイスラは著しく燃費が悪くなるため、令呪だけでは不足してしまうのだ。
「…天海、どうして遠坂を殺したんだ?
正直遠坂を殺したお前が憎くないと言えば嘘になる。
けど、お前が人殺しに慣れてるわけでも、やりたくてやってるわけでもないのは俺から見てもわかる。
そこまでして叶えたい願いがあるって事なのか?」
「…………」
その言葉にひどく苛立つ。
何を言っているんだこいつは、そんなものは当たり前だ。
願いを叶えるための殺し合いが聖杯戦争だろうに。
そんな事を思ったからだろうか。
気付けば口は今まで鬱積していた感情を吐き出していた。
「…ああ、そうだよ!悪いかよ!
だってそれが聖杯戦争なんだろ!?
遠坂は敵だったんだ!ルールなんだから殺したって仕方ないだろ!?
願いは無いとか聖杯を壊すだとか、お前らの方がおかしいんだ!!
人の気も知らないで勝手なことばっかり言いやがって!!
オレが好き好んで人殺しなんかやってると思ってるのかよ!?」
一気に捲し立てて荒い息をつく。
平時の陸なら決して口にしないような事だが、大きく精神が乱れた今の陸にそんな分別は無い。
「…確かに俺はお前が何を願って参加したのかなんて知らない。
でもな天海、これだけは言えるぞ。
お前の気持ちや願いが誰にもわからないのは―――お前が嘘をついたからだ」
「――――――!!」
無表情で告げた士郎の言葉は、これ以上無いほどの正論だった。
嘘をついたのなら本当の気持ちが誰にも伝わらないのは至極当然だ。
「はっきり言うぞ、お前に殺し合いなんて向いてない。
お前が持つべきだったのは嘘をついて人を殺す意思なんかじゃない。
遠坂や泉みたいな、人を思いやれるやつに本当の気持ちを打ち明ける勇気だったんだ。
お前の願いが何かはわからないけど、それでも何かは違ったはずだ。
……それだけで、良かったんじゃないのか?」
「……まれ。黙れ、黙れよっ!!」
言うな、それ以上言わないでくれ。
だって自分はもう既に人を殺してしまった、伸ばされた手をはねのけた。
認めてしまえば自分のしたことは全て無駄になってしまう。
この聖杯戦争だけではない、もう一度天音に会うために嘘をついたことも、戦ってきたことも何もかもを無駄にしてしまう。
その時金属音が聞こえ、遠目にイスラが吹き飛ばされているのが見えた。
(―――ふざけるなよ)
倒せないのはまだしも、令呪を使ったにも関わらずこうまで押されるとはどういう了見なのか。
あまりの逆境の連続に、陸の頭の中でプツリ、と何かが切れる音がした。
殺せ、殺せ、殺せ。
あのセイバーも、うるさい衛宮士郎も殺してしまえばこの苦境もチャラに出来る。
目の前の現実に嘘をつき、逃避するために陸はついに二画目の令呪に手をかけた。
「イスラ、次の一撃でセイバーを殺せええっ!!!」
左手の甲から強烈な輝きが放たれる。
次の一撃で打倒する、これ以上なくシンプルかつ強固な命令による最強の一撃は如何に騎士王といえど耐えられまい。
「天海―――!くっ、セイ……っ!?」
間を置かず士郎に斬りかかる。
令呪は使わせない。元々サーヴァントに力量差があるのに令呪を使われればその時点で敗北が確定してしまう。
度重なるストレスの連続でもはや理性が崩壊しつつある陸にもまだその程度の判断力は残されていた。
「だぁぁあああああああああああーーーーー!!!!」
「ぐっ、クソっ……!」
完全に我を忘れたかのような激情に身を任せた突撃もこの時ばかりは極めて効果的だった。
思考も戦術もない単純極まる剣捌きは、対峙する両者の身体能力に開きがあるならばそれだけで脅威となる。
少しでも令呪の使用に集中しようとすれば一瞬で両断される猛攻の前に士郎にはただ防ぐ以外の選択肢がない。
一方でイスラもまた令呪の強制力によってセイバーを滅するべくかつてない最短動作で本来の暴走召喚の限界すら超えた召喚魔法を放とうとしていた。
陸がこうなる事を止められなかった後悔はある、だがそれも目の前の敵を葬ってからだと自身に言い聞かせる。
如何にセイバーといえどこれは止められないし、防ぐことも出来まい。
避けるという選択肢はあるがそれもさせる気はない。
この二度とはない最強の一撃は常套の手段では躱せまい。
―――だが、敵もまた常套ではない手段を用いてくるとまではイスラにも想定できなかった。
「やらせんっ!!」
何を思ったかセイバーは自らの半身であるはずの黄金の剣を、手首のスナップを利かせた最短動作のスローイングで投げつけたのだ。
頭部を狙った投擲に止む無くイスラが迎撃しようとしたまさにその瞬間、セイバーは壊れた幻想でカリバーンを爆破した。
「ガッ!?」
上級宝具の壊れた幻想による爆発には不死の呪いと令呪の援護を受けたイスラもたまらず顔を抑えてよろめく。
(ここだ―――!)
立て直しにかかるごく僅かな瞬間、常勝の王はそれを決して見逃さない。
ここを逃せば討たれるのはセイバー自身であると理解しているが故に。
瞬時に顕現させたセイバーの真なる宝具、その剣に纏わせた風を解放する。
「風よ―――吼え上がれ!!」
セイバーの持つ宝具の一つ、“風王鉄槌(ストライク・エア)”
その変則使用、荒れ狂う暴風の塊は魔剣の担い手の肉体を押し潰し、空高く打ち上げる。
そして至高の聖剣が輝きを発し、隠された真価を発揮しようとしていた。
その剣が示すは全ての人々の祈り。
想念によって鍛えられた最強の聖剣。
その身を風の鉄槌で潰され空高く打ち上げられながらも、イスラは確かにそれを見た。
最初に自分が殺した赤の少女がいた。
白い長髪に赤い瞳の雪のような少女がいた。
雪の少女の傍らに立つ巨大な鎧武者がいた。
ボサボサの髪を後ろに結った少年がいた。
少年の後ろに立つ道士服の男がいた。
つい先ほど踏み越えた群青色の侍がいた。
セイバーの真なる剣は輝きを増し、今ここに騎士王は手にする奇跡の真名を謳う。
魔剣の伐剣者(セイバー)よこの輝きの前に退け、虚飾を払うは星の聖剣。
其は―――
「―――“約束された(エクス)」
「勝利の剣(カリバー)”――――――ッ!!!」
その極光はさながら星の輝きの体現であった。
ただ一人のヒトガタに向けて放つにはあまりに巨大な光の斬撃は身動きの取れないイスラ・レヴィノスを容易く飲み込む。
その身にかけられた不死の呪いなどこの最強の聖剣の前では如何ほどの意味も持たない。
まるで英雄譚に出てくる三流悪役のようだ。
エクスカリバーの極光に身を焼かれながら、最期にイスラはそんな事を思った。
魔剣の適格者たる自分が聖剣の担い手に討たれるとは何たる皮肉か。
しかしそれは些細な事だ、どうせ自分はまたあの無間地獄に戻るだけだ。
だがこの敗北を悔しいと感じるのは間もなく自分の後を追うことになるマスターのせいだろうか。
口ではからかいながらも、イスラは内心陸を認め、少なくとも先ほどからは本気で力になろうと思っていた。
だがそれを伝える機会はなかった、嘘つきでしかない自分に真心を口にすることは許されないということか。
陸を勝者にすることが出来なかった、姉を求めた自分と重なる少年の望みを叶えることが出来なかった、ただそれだけが心残りだ。
結局自分達はキャスターの掌の上で踊らされていただけだったというのか。
(これでは、あまりにも――――――無念だ)
その刹那の思考を最後に、嘘と謀略で勝利を掴もうとした反英雄は跡形もなく消え去った。
その存在そのものが、最初から実体のない嘘であったかのように。
セイバーがエクスカリバーを放つ直前、二人のマスターの戦いも佳境を迎えていた。
重傷を負っているにも関わらずこれまで以上のパフォーマンスを見せる陸に士郎の防御も限界が近づいていた。
あまりにも出鱈目に大剣を振り回されるせいで攻撃の誘導どころではない。
そもそもそんな思考が相手に残っているかも怪しい。
ならば―――――
「―――投影開始(トレースオン)」
生き残るために、天海陸を殺す他ない。
限界に近い魔力でも実行可能な投影で決着を着ける。
先ほどの金田一の遺した言葉が脳裏を過ぎり、すぐに振り切った。
(悪い金田一、俺は―――お前みたいな“正義の味方”にはなれない)
かつて綺麗と思い、憧れた理想があった。
いつかその理想を実現できる、誰もを救える正義の味方になりたかった。
だが今は―――
「―――鶴翼、欠落ヲ不ラズ(しんぎ、むけつにしてばんじゃく)」
バックステップと同時、両手の干将・莫耶を左右に弧を描くように投擲する。
「今さらこんなもんにっ!!!」
それらは当然のように陸の大剣に弾かれる。
だがそれで良い、そうでなければこの技は完成しない。
「―――心技、泰山ニ至リ(ちから、やまをぬき)」
再度干将・莫耶を投影、後退しつつ再び投擲する。
予定調和のようにまたも弾かれる、相手の頭に血が上っているせいかあまりにも上手くいっているようにも感じられる。
「―――心技、黄河ヲ渡ル(つるぎ、みずをわかつ)」
またも双剣を手に投影しつつ出方を窺う。
これで倒れてくれるかどうか。
「なっ!?」
ここで漸く陸が異常に気付いた。
有り得ざる奇襲、二度弾き飛ばした四本の双剣が孤影を描いて再度陸へと殺到する。
これが夫婦剣、干将・莫耶の真の特性。
互いに引き合う性質を持った白と黒の陰陽剣は円の結界のように天海陸を包囲した。
「っぁぁああああああああっ!!!!!」
だが陸はそれでも倒れない。
生存本能の為せる業か、瞬時に全方位に大剣を振り再度四本の夫婦剣を弾き飛ばした。
その一撃たるや、下級の英霊をすら打倒し得るほどの苛烈さだ。
だが、だからこそ天海陸の命脈はこれ以上は続かない。
「―――唯名、別天ニ納メ(せいめい、りきゅうにとどき)。
―――終わりだ、天海」
双剣を手に士郎が駆ける。
無理に渾身の一撃を振るったことで陸の全身は硬直を余儀なくされる。
そして意識圏では士郎の全身全霊で振るわれる双剣を防げない。
さらに投擲された四本の夫婦剣も弾いただけだ、駆け出した士郎に自ら呼吸を合わせるように再び陸を包囲し襲いかかる。
これこそ双剣干将・莫耶の性質を生かした斬撃と投擲から成る連携技“鶴翼三連”。
先のアサシンの燕返しとは異なる、相手に回避をさせない状況を作り出した上での必殺剣。
初見では白兵に優れた一級の英霊でも深手を免れない悪辣な一手を凌ぐ手段を天海陸は有さない。
「い、嫌だ!何でこんな事に……!
オレは、オレはただ―――!」
「―――両雄、共ニ命ヲ別ツ(われら、ともにてんをいだかず)」
その先は言葉にならなかった。
意識圏を突き破った士郎の斬り抜けで胴体を、空を駆ける四本の双剣に頭部と両腕をバラバラに寸断されたからだ。
「壊れた幻想(ブロークンファンタズム)」
最後に握った双剣を背後に放り、爆発させた。
嘘をつき続けた少年に真実を口にする機会は訪れない、六本の双剣の爆発によって天海陸の総身は骨すら残らず消え去った。
奇しくもセイバーのエクスカリバーが放たれたのとほぼ同時の事だった。
「シロウ」
疲労と魔力の消耗が重なり肩で息をつく士郎の下にイスラを下したセイバーが駆けつけた。
自身も大量の魔力を消費したが士郎に比べればまだ戦える範疇だ。
「…その、辛いでしょうがこれも戦争です。
裏切りや策謀は常に戦いの裏側に存在している。
リクにしてもそれは同じ、彼も志願して聖杯戦争に臨んだのです。
戦いの中で果てる覚悟はあったでしょう」
「……本当にそう思うか?」
セイバーの気遣いはありがたいが、士郎には陸が死を諦観した魔術師、あるいは死を覚悟した戦士だとはどうしても思えなかった。
例えるならばそう、今は亡き友人である間桐慎二のような、一般人に近い感覚の持ち主だったように見えた。(金田一を基準にするのは間違っているように思えた)
「金田一が言ってたよ。この聖杯戦争に参加するのはどうにもならないくらい追い詰められたやつだって。
天海もきっとそうだったんだ。もちろん遠坂を殺した事を許せるかって言われればとてもそんな気はしない。
でもあいつはあいつで誰かに、何かに助けを求めてたような気がするんだ」
そして、そんな人間を殺したのは他ならぬ士郎自身だ。
きっと、この戦いに明確な悪などどこにもいなかった。
いたのは救いを求めていた天海陸と、その命を己のエゴで切り捨てた衛宮士郎だけだ。
「…あるいは、そうなのかもしれません。
しかしどちらにせよ彼らは殺し合いに乗っていた。
そうである以上我々と相容れることは無かったでしょう、それだけは間違いのない事です。
それよりもシロウ、今のうちにライダーの遺したレコーダーの続きを聞くべきでは?」
露骨に話題を変えてきたセイバーに敢えて同意し、ICレコーダーのスイッチを入れた。
『ではここからはこの聖杯戦争の背景、わしのマスター命名“影の主催者”についてわしから考察を伝えたい。
そもそも何故わしらが殺し合いに乗らなかったのか、何故聖杯戦争の背景事情を疑ってかかっているのかと言えば―――』
ここは昨晩大空洞で情報交換をした時に話していたことだ。
それでわかった。恐らくこのレコーダーは本来自分達ではない、誰かに向けて用意したものなのだと。
最悪自分達が全滅ないし瓦解した後、それでも殺し合いに乗らずに脱出を目指す他の誰か、それこそ泉こなたのような力なき人間の助けになるように。
常に自分や、あるいはルルーシュ以上に巨視的な視野で物事を見ていたあの男なら十分に有り得る。
消滅する間際、ライダーがこのレコーダーの事を話さなかったのは元々彼にその気がなかったからなのだろう。
『―――わしらの考察は大体こんなところだ。
だがどちらにせよこの冬木市という会場からの脱出方法を確保することは至上命題であろう。
残念ながらわしの力ではこの会場の全てを解き明かすことは叶わなかった。
故にまずは量子空間の解析能力に優れた者、霊子ハッカーやそれに近い能力を持ったサーヴァントを味方につけるのだ。
無茶な注文をつけているのはわかっておるが、そうでもせねば脱出の可能性はまず見い出せまい。
そして最後に―――この聖杯戦争はムーンセルの変質、つまり並行世界との接触を経たことで開かれたことは疑いない。
だがそれは外部の働きかけだけでムーンセルを動かしたわけではあるまい。
ただの記録装置はひとりでには狂わんし、外部からの働きかけがあったとしても自ら変質するという選択肢は本来なら存在しないはずなのだ。
言い換えればこの聖杯戦争が行われる前、いや、もっとずっと以前からムーンセルのどこかに潜み、月の改変を望む者の存在が必ずあったはずだ。
その者の存在を暴き、そして見極めるのだ。そうして初めてこの聖杯戦争が開かれた目的が見えてくるはずだ』
記録音声はそこで終わった。
これからやるべき事はいくらでもある、まずはこなたとライダーに事情を話さなければならない。
一応反魔の水晶という証拠品もあるにはあるが、それでも純粋な一般人であろうこなたが納得するかと言えばわからない。
最悪こなたと対立する可能性すらあるのだ。
そして太公望の言う空間の解析が出来る仲間を探す必要もある。
正直士郎には太公望や金田一のように上手に他人を説得出来る自信はない。
それでも彼らの遺志を無駄にするわけにはいかない。
そして切嗣とどう向かい合うのか、そこからも目を背けるわけにはいかない。
だが今は―――
「…少し休もう、セイバー。
悪いけどしばらく動ける気がしない」
「はい、それが良いでしょう。
この地で体を休めた方が魔力も早く回復するはずです」
少しぐらい休息を取ってもバチは当たらないだろう。
セイバーと二人、戦闘の余波でまたも破壊された本堂を横目に大木の下に腰掛ける。
(俺と天海は同じだ、俺だってもし桜が死んでいたらどうなるかなんてわからない。
もしかしたら、地上とは違うここの聖杯に縋って殺し合いに乗ってしまうかもしれない。
セイバー、お前は俺がそんなやつでも一緒に戦ってくれるのか?)
口には決して出せない弱音を飲み込みながら、天海陸の事を思い出す。
言峰綺礼や間桐臓硯とは違う、本来は悪ではないにも関わらず殺し合いに乗ってしまった者。
せめて、そういう人間がいた事は覚えておこうと心に誓った。
&COLOR(#FF2000){【天海陸@ワールドエンブリオ 死亡】}
&COLOR(#FF2000){【セイバー(イスラ・レヴィノス)@サモンナイト3 消滅】}
【深山町・柳洞寺/昼】
【衛宮士郎@Fate/stay night】
[令呪]:3画
[状態]:疲労(大)、魔力消費(特大)
[装備]:携帯電話、ICレコーダー、反魔の水晶@サモンナイト3
【セイバー(アルトリア・ペンドラゴン)@Fate/stay night】
[状態]:魔力消費(大)
※陸の持っていたニューナンブは戦闘で破壊されました。
※ICレコーダー@現実…太公望が自分達が全滅した時の備えとして、仲間達の目を盗んで金田一のクレジットカードをスって勝手に購入したもの。
午前9時時点での太公望の考察が記録されている。
尚、これは本来士郎やルルーシュなど身近な仲間ではなく他に脱出を目指す誰かに向けて残されたものだった。
しかし妲己は自分の無実を証明するために杏黄旗と同じ場所に埋められていたこれを掘り出し、結果的には衛宮士郎の手に渡った。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: