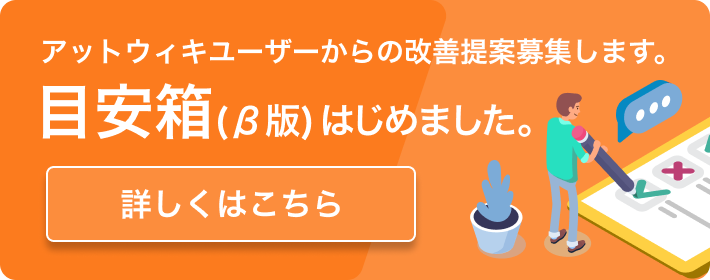「ヒトクイフラグメント」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「ヒトクイフラグメント」(2013/02/03 (日) 01:00:51) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
【0】
成る程、理解した。
やはりお前は正気ではない。
【1】
”勝利”とは、ひとえに何を意味するのだろうか。
『決まってんだろーが。目の前にいるそいつをぶっ殺しちまうことじゃねーのかよ、かはは』
『随分つまんねーことを聞くんだな、お前。あたしが戦ったらそれでもう”勝利”に決まってんだろ』
『《何を意味するのだろうか》——ふん。そんなことは簡単だ、呆れるほどにな。答えは、——《同じこと》だ』
『……さあね。それこそ、戯言だろ』
——頭の中で、記憶の中の存在が好き勝手に答えていく。
そんな思い思いの回答を聞いた上で、やはり匂宮出夢はそれを《つまらねえ》と皮肉混じりの一笑に伏した。
たとえばドラマや少年漫画なんかでよく目にする、スポーツの大会なんかでみんなで努力して優勝するシーンで例えてみよう。
遊ぶ時間も惜しんで勝つために仲間と切磋琢磨し、一歩ずつ日々前進を重ね、その努力が報われて栄冠を勝ち取る。
——ああ、確かにそれは勝利だろう。
友情・努力・勝利の三原則を満たした上で確約された、尊くて美しい、誰にでも誇れる名誉ある勝利といっていいだろう。
だがしかしだ。
一度でも疑問に思ったことはないだろうか。
《ほんとうに、勝利すべきは彼らだったのか》——と。
そういった漫画の世界では大抵ライバルに強豪校がいて、その中でもエースとされるプロ顔負けの選手がいるのがお約束だ。
そんな奴らを飛び越えて勝つことにこそ意義がある。
そういう努力にこそ、読者たちは燃えるのだ。
そういう努力に憧れて、読者たちはコミックスを買うのだ。
けれど。けれど、主人公たちは本当に一番頑張っていたのか。
もしかしたら、一回戦で負けてしまったような弱小高校の方が血の滲むような努力と友情を積み重ねていたかもしれない。
でも彼らに勝利は約束されなかった。
勝負は時の運とはいうが、これでは主人公たちは真の勝者に相応しい存在かと問われると、疑問点が残る。
もしも、今例に出した弱小校が一回戦で万年一回戦負けのジンクスを打ち破ったなら、それこそもっとも価値ある勝利ではないか。
こんな風にだ。
勝者と敗者の区別なんて平仮名の《カ》と漢字の《力》くらいに曖昧で、ゆえに明確な回答なんて導くことは出来ない。
——なんて、戯言。
そもそも匂宮出夢は、この問いに正面から向かい合うことが出来ない。
何故なら、彼女の人生に敗北は存在しなかったからだ。
白髪の殺人鬼との戦いでも、狂的な糸使いとの血闘でも、再弱な戯言遣いとの茶番でも、最強な最強との決戦でも。
そして、最終な橙色との最期でも、明確な答えは得られなかった。
だから彼女は知りたいと思う、願う。
敗北の味を知りたいと切に願う。
甲子園の土を泣きながら持ち帰る敗北者の気分を、恋に破れてハンカチを噛む失恋者の気分を、踏み潰される奴隷の気分を知りたい。
もちろん、主人公に倒されるライバルの清々しい敗北でも構わない。
敗北を知らない幼子の為に。
強い身体の代償に無知を背負った怪物の為に。
彼女に敗北を与える為に——ムーンセルは微笑んだのかもしれない。
これはきっと、今輪の際の儚い幻想(ユメ)。
終わったら静かに消えゆくだけの下らない妄想世界。
真実は違えど彼女にとっては所詮絵空事。
願うことなど当に止めた、多分前世くらいで。
ゆえに彼女は戦士ではない。
彼女は探求者だ。
ゆえに彼女は戦死はしない。
彼女に与えられるのは探求死だ。
つまりこれは奇跡だったのだと思う。
神様が生まれながらに咎を背負った少女へと哀れみでもくれたのだろうと、そういう風に思うことにしている。
出夢は聖杯戦争に興味がない。
戦争なんてものは飽きるほどに経験したし、血で血を洗う争いの先に誰かの欲望が満たされる憧憬を見たことは、生憎皆無だった。
ご苦労さんなこったと思った。必死に願いなんて下らないモノに縋ろうとする戦士どもを、言葉にはせずとも憐れんですらいた。
そんな傍観者の視点を持ち合わせていたのにも関わらず、匂宮出夢は聖杯戦争を破壊しようと動く真似に出ることはなかった。
戦争での勝利を求めることは探求者の専門分野の外になる。
だが、戦争での結果を求めることはまさしく探求者の存在理由だ。
レゾンテートル、もといアイデンティティ。
欠けてはならないパーソナルリアリティー。
この児戯に一人の雑魚を登場させよう。
名前は知らない。生前で結構な縁を持っていたと記憶しているが、その名前を聞いたことは《幸か不幸か》一度だってなかったはずだ。
彼もまた、願いなんてものを求める醜態は晒さないだろう。
散々情けなく惑った末に、殆ど成り行きで聖杯戦争の打破に力を貸すことになるに違いない。
そしてそれを遂げるだろう。
嘘を吐いて、沢山殺して惑わせて、自分だって満足できない偽善にも満たない何かを布いて、それでも終わりへたどり着くだろう。
隣に誰かがいるかもしれないし、ひとりぼっちかもしれない。
でも確かに、彼の勝利への道筋には幾多の屍がある筈だ。
無意識に、意図せずに、望まずに、知らずに、感じずに、殺さずに、気付かずに、傷つけずに、知らずに、忍ばずに、彼は殺す。
吐き気がするほど最悪な最弱の戦いには、犠牲がつきものだ。
だから彼は絶対に勝利に笑わない。
自分の勝利が、正しくは勝ちにも負けにもなれない宙ぶらりんの腐乱死体にも等しい、無価値で惨めなものだと知っているからだ。
——ああ、いや。ひょっとすると、《結末》に辿り着きすらしないままに、誰の目にもつかずにひっそりと死んでいるかもしれない。
本当のところは誰にもわからない。
だってあの大嘘つきはここにはいないのだから。
仮にいたとしても、彼を理解できる者なんて居て一人が限度。
現に匂宮出夢だって、あの欠陥製品の本質は、遂にわからず仕舞いだったのだから。
僕はやっぱし、あのおにーさんにはなれねえな。
出夢は小さく笑った。
匂宮出夢と《ここにはいない》青年は決して重ならない存在だ。
本来のままの人生を生きていたら関わり合いにすらならなかったような存在、まさしく彼との出会いは神の気紛れであった。
「僕はやっぱし、《匂宮》なんだよなー」
『かはは、当たり前だろ。てめえが普通の女の子だとか抜かすようになった日には、俺ぁ怖くておちおち生きていけねえよ』
頭の中の誰かが皮肉る。かははと笑う。
二度と会えない宿敵にして、一度は恋した殺人鬼。
にぃっと口元を歪める出夢だが、その笑みは好戦の笑みではなくどこか寂しげな、振り返るような笑みだった。
実に下らない傑作だ。
彼女の物語を知らない読者諸君にしてみれば、読むことが億劫になる程の、甘ったるくて冗長な戯言だ。
匂宮出夢と従者サブラクの相性は、悪くないはずだ。
悪くない筈だが、過去に自分の相棒——否、正しく《半身》であった少女にするように気を許すことは出来ない。
理由はなんてことのない、只の下らない同族嫌悪だ。
あるいは、同属嫌悪だろうか。戯言だけれど。
サブラクの在り方は正しく暗殺者だ。
それに対して出夢の在り方は正しく殺し屋だ。
同義語のように見えるが、サブラクに問うてもきっと出夢と同じ答えを返すだろう、《匂宮出夢と自分は決して重ならない》と。
そういうものなのだ。
実に下らないことだが、そういうものなのだ。
匂宮出夢は苛烈極まる殺戮中毒(ワーカー・ホリック)の殺し屋で、サブラクは確実に敵を仕留める忍のごとき暗殺者。
違う。違うからこそ、互いに真の友情は築き得ない。
だけれど。
出夢の欲望をサブラクはきちんと把握しているし、サブラクが自分とは違って勝利を望んでいることを出夢はきちんと汲んでいる。
互いが互いを尊重してこの戦争に臨んでいるあたり、似た者同士で同族嫌悪で同属嫌悪な彼らの主従は、しかし決して弱くないのだ。
二人とも子供ではない。
出夢は身体は子供でも、世界を下手な知識人気取りのコメンテーターなんかよりずっと知り尽くしている。
サブラクは知識で出夢に劣れど彼女の理解の及ばぬ境地を知っている。そして二人とも、現実の厳しさを知っている。
だから彼らは強くてしぶとい。
蔓延るだろう。
油汚れのようにしぶとく見苦しく、でも笑って蔓延るだろう。
——それでも出夢は知っている。
自分は決して最期まで残ることは出来ないと。
本能的な直感或いは超常的な触感で、わかっている。
自分にはいずれ終わりがやってくる。
願いを叶える万能の器にこの手が触れることは有り得ない。
約束された、敗北がある。
ゆえに彼女の物語は、書籍のようなものだ。
結末のわからない現実(リアル)なんかじゃなくて、ページ数に上限があるから終わりがあると察してしまう虚実(フィクション)だ。
匂宮出夢を正面から打ち倒す者が現れるとき、人喰いの宿命を背負わされた殺戮者には漸く安息が訪れる。
——だから。
それも、悪くない。
.
【2】
人を殺すにはどうしたらいいのだろうか。
……正直、ここまで陳腐な問いもそうそうない。
生命活動を停止させたくば胸を刺せばいい。
ピアノ線を使ったちょっとした仕掛けでなら、血を浴びずに憎いあいつを殺してやることだって楽勝だ。
自殺に追い込みたいなら悪評を撒けばいい。
苦しませて殺したいくらいに憎いのならば、四肢をもいで片目を潰し、そのまま放置しておけば酷い苦しみと絶望の果てに死ぬだろう。
そう、こんなにも人は殺しやすい。
ちょっとした下らないことで人は死んでしまう。
砂糖の塊のように脆くて儚くて、消えたら終わりの泥人形だ。
ワイドショーなんかでは《殺すつもりじゃなかった》なんて言い訳をする犯罪者が報じられるが、プロの観点からいえばあれはむしろ正しい。
人なんて、殺すつもりが無くたって死ぬ。殺されてしまう。
殺し屋や暗殺者なんて、だから大したことはしていないのだ。
悲しいくらいに死に易い人間を、ちょっと後押しして殺すだけが仕事。
それで高い報酬を貰えるなんて、正直相手に悪いレベルとさえいえる。
そんな《簡単なお仕事》を究極まで極めたのが——匂宮出夢・サブラクのチームアサシン主従である。
彼らは殺し尽くす。
万が一なんてことのないように、徹底して殺す。
殺して殺して、知り合いだって容赦なく引き裂き殺す。
そして終わる。ただそれだけの簡単なお仕事。
ゲーム感覚で人を殺すから暴力ゲームは有害だ? 馬鹿を言え、その理屈が通るなら少年たちはみんな虐殺者になっている。
世の中の大きなお友達のみんななんて、もうモテモテのハーレム花園人生を謳歌していることだろう。
何も知らないヤツの言葉はやはりアテにならない。
現に出夢は、ゲームなんてロクに遊んだことすらないのにも関わらず、ゲーム感覚で殺戮を楽しんでいるのだから。
ゲームは極めたら強くなれる。
スポーツみたいに運動神経が関わってくるわけじゃない。
身体的ハンディキャップだって、その気になれば埋められる。
そう、ゆえにプロの殺し屋なんて大したものじゃないのだ。
彼らにすれば、ゲームを遊んでいたら強くなっていただけで——
——青春的な努力をした者なんて、ごくごく一握りなのだから。
出夢は基本的には前者である。
でも彼女の場合は少し違う。
生まれながらに怪物として生み出された彼女は強制的にゲームを遊ぶしかなかったし、それが娯楽であるとは思っていても、自分がやりたいからやるのではなく、やらされている内に上達して、それがいつしか仕事から楽しみへと変わっていただけにすぎない。
——これほどか。
人の身でこれほどの境地へ辿り着くのか。
やはり幸運らしい。
これならば、他のマスターによる謀殺はまず有り得ない。
「どうだい旦那? これが僕なりに時間をかけて編み出した《改良版・一喰い》なんだがよ」
目の前にあるのは、破壊された住宅。
空き家のようだったので、思う存分やらせて貰った。
驚くべきことに、これはただの二発で起こった崩壊である。
元々、人類最強の赤色に単純な力比べでは勝るポテンシャルを秘めた、天才的才能を保持する彼女が全力で極めた結果の、決壊である。
一度死んだ経験は、彼女にとって確実に有益だった。
《人類最終》との決戦では呆気なく隙を突かれて腹を穿たれたが、今回の改良ではその溜めによる隙そのものを、削り取った。
結果として、威力は僅かに落ちたが隙が無くなった。
だがそれでは不満足。
実戦用の技が威力を落としては改良の意味がない。
そこで彼女が再現しようとしたのは、枢木スザクとの殺し合いで目にしたあの《超動作》——つまり、ギアスによる自動行動。
あの動きはこれまで見てきたどの敵にもなかったそれだ。
《人類最強》や《人類最終》ならばモノに出来るだろうが、あの二人だってあのようなスキルは持っていなかった筈だ。
ゆえに出夢は強引にそれを極めんとした。
当然、あれが枢木スザクの平常の身体能力でないのは知っている。
出夢の知る家系に、《時宮》という忌まわしい宿敵があった。
その《時宮》は目を合わせることで相手を《操想術》という暗示の術中に置く、特殊な技術を有していた。
それと同じ。
あの動きは、何らかの暗示による無意識的反応だ。
それを有意識的行動へと昇華させるのは骨が折れた。
ざっと二時間はかかってしまった。
改良版一喰いの修得よりも永く、かかったのだ。
「俺はマスターを見くびっていた」
サブラクは素直に自分の目が曇っていたことを認める。
もしも、サーヴァントに神秘の内包されていない攻撃が通らないというルールが存在しなかったら、自分たちは最強だった。
恐らくマスターで出夢に勝てる者はいない。
サブラクは何の贔屓も美化も無しにして、戦場を踏んできた者としての本音からそう思った。
「どうしてマスターなのだろうな、お前は。どう考えたって、《こちら側》寄りだぞ、その強さは」
「まぁ、僕はサーヴァントなんて胡散臭え肩書きは似合わねえさ」
ぎゃははは、と出夢は豪快に笑う。
その後で少し真剣な表情になると、
「………、でもまあ、あれだな。あんたらみてえな連中と殺し合えねえってのもまた、興醒めな話だぜ、まったく」
出夢は、戦いを好んでいた。
もっともそれは、とある出来事があるより以前の話だ。
彼女には半身がいた。
匂宮兄妹の妹の方・《名探偵》匂宮理澄。
理澄は戦闘能力に欠けていたが、情報の収集と考察・つまり調査においてなら他の追随を許さないほどに優れた妹だった。
そんな妹を喪ってから、出夢は今までの疲れに襲われた。
肉体的にはまだまだ現役なのだが、急にこれまで求めていた激しい闘争をすることに言いしれぬ疲れを覚えるようになったのだ。
脱力感。
喪失感。
虚脱感。
虚無感。
敗北感。
勝利感。
どれだったかなんてどうでもいいし、わからない。
しかし今は少しだけ違っていた。
どうせこれは、じきに終わる夢だ。
夢ならば楽しんでやる。
その為にも、サーヴァントなるけったいな存在とも矛を交えてみたいものだったが——やはり、興の乗らないルールだ。
(ほんとうに——恐るべきものだな。ただの数時間だぞ? ただそれだけの時間で、経験と記憶だけを元にここまで作り上げる。
そんなものは人間の、あまつさえ小娘の芸当などではない。俺のマスターは、生まれてくる場所を完全に間違えている)
彼女のような存在は、自分のような超常の世界に生きる者としてこの世に生まれ落ちるべきだったのだ。
サブラクの知る人間は少なくとも二発の打撃で家を壊さない。
ましてや、たった数時間で数年分の修行を極めない。
そんな彼にしてみれば、彼女からうっすらと聞いていた《自分をも超える存在》二人の話はまさしく荒唐無稽なものだった。
最強と最終、そして人喰い。
力関係では出夢が恐らく一番下になるとのことだったが、まったくこいつらは空気の代わりに何か別のモノを吸っているんじゃないのか。
あのキチ○イ教授が見たら喜んで飛びつきそうな人材だな——と、サブラクは半ば呆れ混じりに思った。
「で、アサシンの旦那。どーすんだい、これから? 幸いまだ《時間》は残っているようだけどよ」
「答えるまでもないだろう。時間にしてあと約半時、敵の殲滅を行う」
淡々とサブラクは告げる。
既に二組の主従を脱落させ、そして出夢も一人のマスターの片腕を奪い取るなど上々の戦果を獲得している。
だがまだだ。
まだ戦えるのなら、戦っておくべき。
「あ、そうそう」
出夢が思い出したように切り出した。
まるでガムでも食うかと誘うような口振りだった。
なんだ、とサブラクが振り返れば、出夢は隣の住居の前に立っている。
住居が倒壊しているのにも関わらず町が静かと云うことは、やはりこの町が偽りのものだと実感させてくれた。
この家は無人ではないようだが——と、思ったその時だ。
「もう一個あったわ、僕の新技。それとも切り札かな?」
待てとサブラクが制す。
たかが一家を殺戮するくらいならペナルティの心配はないだろうが、それでもどうせなら魂を喰っておきたい。
そんなサブラクの意見が吐かれるより先に、暴風は吹いた。
否、正しくは——巨大な魔物のあぎとだったかもしれない。
「改良版(ニュー)——暴飲暴食ッ!!」
二発で住居を倒壊させる、一喰い。
その両手打ちは、まさしく龍の顎のようだった。
衝撃の面積でいえば決して大きくない、しかし匂宮出夢の手加減抜きを全力でぶつければ、どうなるか。
答えは単純明快。
住宅など、発泡スチロール同然になる。
「…………どうだい! ザ・ニューいずむん爆誕っ!!」
「少しは他のマスターに見つかる可能性を汲めよ!」
男サブラク、流石にちょっとキレた。
轟音が響いたし、中のNPCは全員圧死は免れないだろう。
そこにある瓦礫の山をちらりと一瞥すると、サブラクはいち早くこの場から離れるために出夢を抱えて走り出した。
目的地は特にない。
とりあえず相手に先手を与えたくはなかった。
「ヒューッ! 女の子を抱えてダッシュたぁやるねぇ旦那! 《天下無敵の暗殺者、ただし趣味はおままごと》みたいな!!」
「もうお前は一度黙っていろ!」
騒がしい主従だった。
【3】
——間違えた手段で手に入れた結果に意味はない。
そんな綺麗事を唱えていたこともスザクにはあった。
それが綺麗事だと気付いた時には、取り返しはつかなかった。
沢山の人を自分のせいで死なせた。
ギアスという絶対遵守の呪いに冒されたことが原因ではあるが、最初から自分の愚かしい理想に気付けていればあんなことにはならなかった筈。
要するに、枢木スザクは間違い過ぎてしまったのだ。
間違って間違って、多くを犠牲にして、そしてここへ辿り着いた。
聖杯戦争——どんな願いも叶う戦いへと。
上手くやれていると思っていた。
騎士として褒められたものかどうかは知らないが、それでも確かに都邑までは順調だったと心から思える。
匂宮出夢という怪物に襲われて片腕を失ったことも、些末だ。
自らの従者・バーサーカーことサー・ランスロットとも言葉を交わし、上手く強者たちと同盟を結ぶことにも成功した。
それが、今こうして惨めに倒れている。
他のマスターやサーヴァントに見つかれば終わりだ。
まず確実に殺される。
ギアスによる抵抗も出来ない。
しようにも四肢がすべて使えないのでは、満足な移動も出来ない。
「クソっ」
スザクは小さく漏らす。
自分からバーサーカーを奪った間桐慎二が、自分を連れて行くことをしなかったのは単に彼のミスだろう。
それが幸か不幸かで言ったなら、間違いなく不幸だった。
慎二の傀儡同然の扱いであったとしても、生きていれば彼を騙してでも一矢を報いることは出来たかもしれない。
なのに。これじゃあ——
これじゃあ——
これ、じゃあ——
「クソっ、クソっ、クソっ、クソっ、クソぉぉおおおおおお————ッッ!!」
——これじゃあ、どうしようもない。
スザクは慟哭の叫びをあげる。
すべて自分のミスだった。
運が悪すぎたし、自分には親友だった少年のように明晰な、逆境を覆すような奇策謀術を編み出す頭もない。
そのせいで、取り返せない痛手を負った。
「どうしてだ……どうして、こうなるんだ…………!!」
本当に、どうしてこんなことになるのだろう。
自分はただ、欲しかったのだ。
誰もが笑っている世界が。
ルルーシュが、ナナリーが、ユフィが、シャーリーが、みんなが。
そんな世界のために戦っていた。
正しい手段じゃ手に入れることは出来ないと分かったから、聖杯の奇跡などという間違った手段に縋ることを選んだ。
その結果がこれだなんて、あんまりではないか。
所詮自分の、枢木スザクの抱えていた理想(ユメ)なんて——戯言にも満たない、笑えない傑作でしかなかったのだろうか。
「俺は、俺は、ただ…………ッ!」
スザクは涙を流す。
全身を襲う激痛による涙ではない。
それは、敗れた男の慟哭だった。
否定され、踏みにじられ、失敗し、何も残らなかった男の叫びだ。
「ルルーシュ……せめて、君が勝ち取ってくれ……」
ルルーシュ・ランペルージ——もとい、ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア。ブリタニア皇帝シャルルの嬰児にして、親友だった少年。
彼もまた、願うところは同じである筈。
世界を敵に回してまで、ゼロという仮面を被って多くを犠牲にしてまで、彼は正しい世界の為に戦っていた。
彼の背負った痛みは、自分の比ではないだろう。
今なら分かる。
正しいのは——彼だったのだ。
「俺はもう、ダメだ」
涙の痕を顔に残したまま、スザクは微笑む。
散りゆくものの笑みだった。
傷口が原因での死は分からないが、とりあえず自分の末路は通り縋った他の主従によっての殺害であると悟っていた。
だから、迫る足音を聞く心境もどこか悟ったものだった。
恐怖はない。後悔はあった。
「あっれ? あん時のおにーさんじゃねえか」
現れたのは、見覚えのある少女とサーヴァントらしき男だった。
彼女は匂宮出夢。体術のみでスザクを上回り、その片腕を奥義でもって奪っていった、文字通り化け物じみたマスターだ。
君か、とスザクは呟く。
出夢はなんの躊躇いもなくスザクへ近付いていくと、彼を見下ろした。
「どったん? なーんかあるべきモンが三本ほど足りねえけど……って、一本は僕がやったんだったな、ぎゃははは!!」
明らかな大傷を抱えたスザクにも、彼女は憚ることなく笑う。
出夢にデリカシーを期待する方が間違いなのだ。
「……やられたよ。サーヴァントをニ体も連れているなんて思わなかった。完全に、俺の負けだ」
「サーヴァントをニ体、ねえ。あー、そういうことか。なんつーか、性根の腐った野郎がやりそうなこったな、そりゃ」
令呪を用いさせての、疑似的な主従契約。
この戦争では、なかなかの妙手といえる一手だと出夢は思う。
しかし気に入らなくはあった。
そういうやり方は、宿敵の《時宮》やいけ好かない《闇口》の連中がやりそうな手口だからだ。
ちなみに出夢は、幼い頃から《時宮》の人間を見たら容赦なく全力で薙払えと教育を受けている。対極の対極の、そのまた対極。
「で、あんたもサーヴァントを奪われたってか。ぎゃははは、災難だね」
「まったくさ。ところで出夢……だったよな」
「ああ、出夢ちゃんだぜ。くんかな?」
スザクは
「俺を殺すんだろ? だったらその前に、一つ聞いてくれ」
——と、あっさりと言い放った。
彼は死への恐怖を持っていない。
ギアスはまだ反応しないが、恐らく《その時》になれば反応を示して、見苦しいほどに逃れようとするだろう。
つくづく面倒な呪いだった。
でも、目の前の少女なら逃さずに殺す筈だ。
ギアスによる加速を用いても片腕をもぎ取っていくような怪物だ、手足の欠けた人間一人くらいは数秒とかからずにあの世送りである。
「ルルーシュという男に出会ったら、枢木スザクが謝っていたと伝えてくれないか? そして、俺は死んだと」
ルルーシュとは因縁がある。それも、浅からぬものが。
初恋の少女は彼のギアスにかかり、銃殺された。
多くの兵士が死んだ。彼のやり方は正しくなんてなかった。
でももう彼を笑えない。
自分だって、間違った方法を執ってしまった。
その結果がこの様だなんて、哀れなこと極まりないが。
だから、彼に謝りたかった。どうせ最期なのだ——自分の望んだ世界はきっと、ルルーシュによって実現される。
「んー、一つ聞きたいんだけど」
出夢は頼みを承諾するでもなく断るでもなく、逆に問う。
彼女にしてみれば、予想外だったようだ。
スザクが自ら死を選んでくることが。
「おにーさんさ、本当にもういいのかい?」
「…………え?」
くるくると髪の毛を弄びながら、出夢はしゃがんでスザクの顔を見る。
スザクには出夢の質問の意味が分からなかった。
この現状がどれほど絶望的なものであるかなんて、殺し屋の彼女が一番よく分かっているようなものなのに、何故尚も問う?
「いい——とかじゃない。この様では、もう終わりは見えているだろ?」
「はぁん、そういうことかよ」
出夢はにぃっと口角をつり上げ笑った。
まるでそれは、間違いを指摘する教師のようにどこか嗜虐的だ。
「僕に言わせりゃ、おにーさんの絶望はまだまだ甘えぜ。諦めるにも速すぎるし、早さが足りすぎてるってモンよ。ぎゃははは!!」
匂宮出夢の知り合いや敵はとんでもない連中ばかりだった。
印象深い《殺人鬼》や《最強》《最終》《糸遣い》。
更には世界の終わりなんてばかげたものを本気で目指した《狐》、大人の癖して異常に泣き虫な《ドクター》。
《十三階段》、《零崎》、《闇突》、《直木》、《最弱》。
印象に残らないモブキャラ同然の雑魚どもも沢山ブチ殺してきたが、明らかな瀕死からなおも手こずらせた輩までいた。
その観点から言うと、スザクはまだまだ戦える。
令呪を失った?——バカを言え、命令権など本来は無いものだ。
手足が使えない?——頭が動くなら策は練れるだろう。
這ってでも移動できる。諦めるには早すぎる。
「まだ……俺は戦えるっていうのか?」
「そういうわけだ」
しかしスザクの顔色は優れない。
どういうわけか知らないが、出夢たちは今ここで自分を殺す気はないらしいことはどうにか分かった。
その意図は知らない。でも、バーサーカーを取り返せない以上は自分に戦う術など欠片すらもないではないか。
これでどうやって立てばいい。
「まー、あれだ。僕はちぃっと厄介な性格してっからよー。いつ死んじまうかも分からねえってのが現状なんだわ、うん」
サブラクは既に出夢から聞いている。
彼は確かに食い下がったが、このマスターは自分が何と言ったところで肝心な部分は曲げないだろうとすぐに悟った。
故に。故にだ。
「つーわけで、僕と同盟しないかい、おにーさん? ……いや違う。うーんと、えーっと……そうだそうだ、こういうんだったぜ」
にっと笑んで出夢は言う。
枢木スザクにとっては願ってもない台詞を。
彼にとっての希望となるかもしれない台詞を——。
「僕に依頼しろよ、おにーさん。簡単だ、聖杯を穫る為に俺の剣となれー、って感じで命令してくれりゃあそれでいい。
報酬はこの聖杯戦争で戦うことそのものだ。条件は、僕の死後にアサシンの旦那のマスターになること。それで文句はねえ」
「…………それは」
それは、願ってもいない話だった。
ランスロットを奪われた今、どうやったって勝ちの目はない。
それに、手負いのランスロットよりもどう見ても出夢のアサシンの方が強いだろう。勝つ上では、うってつけといってもいい。
しかしだ。ここでスザクは、ランスロットとかわした言葉を思い出し、一歩を踏み出せずにいた。
騎士同士の契りを、無にすること。
これはそういう契約だ。
本当にいいのか?
ランスロットとの契りを、無碍にしてしまっても?
スザクは自問自答を繰り返す。
「自分のサーヴァントは心配しなくてもイイぜ」
そんなスザクの心情をまるで見透かしているかのように出夢は言った。
「あんたのサーヴァントはこれから取り返せばいいだけのことだ。
そのついでにどっかの操想術士を思い出させる腐れ野郎をプチッとぶち殺して、なんだっけ?
もう一人のサーヴァント奪われてる奴も助けちまえばいい——後はそっちで決めろよ。心配しなくても僕は裏切らねえぜ」
スザクは知らないことだが、間桐慎二は羽瀬川小鳩という少女から拷問の末にサーヴァントを奪ってもいる。
スザクが見たなら、如何に心を鬼にした彼でも激情を催すような仕打ちを考えるような地獄で、彼女は拷問されている。
出夢はそれを潰す気だった。
後がない連中ならすぐに脅威にはならない。
どうせ敗北が目当てなのだ、誰の手にサブラクが渡ろうとどうでもいい。しかもこれはサブラクとも合意していることだった。
「俺も同じだ。……サーヴァントの観点から言うなら、力ずくでも止めたいがな、
生憎我がマスターにそれをやると躊躇無く自害の命令が飛んできそうだ……まあ、俺も異存はない。
聖杯の報酬もまだ揃えていないことだしな。後は勝手にやって構わない」
サブラクが初めて口を開いた。
スザクは迷う。
どうするか。
乗るか乗らないか、しばしの間よくよく考えて——
「……わかった。出夢——僕を、守れ」
「引き受けた」
——ここに契約は結ばれた。
【4】
そして時は動き出す。
出夢とサブラクは、間桐邸へと向かっていた。
枢木スザクのサーヴァントを取り返すために。
スザクは戦えない現状、NPCの住居へと預けてきた。
「殺されたくなきゃこいつを預かってな」
そんな脅迫に近い《お願い》をすると、住人らしき老夫婦は震えながらも承諾してくれた。
スザクは当分は安全だろう。
後々、カードを使って義手や義足を揃えてやれば、彼がもう一度戦線へ復帰できるようになるのも遠くはない筈だ。
「悪いね旦那。突き合わせちまって」
「気にするな。令呪を使われるよりかはずっとマシだ」
それよりだ、とサブラクは一本の短剣を出夢へ渡す。
それは彼がメアより預かった、笑って再会を迎えるための剣。
彼もまた承知しているのだろう。
この戦は死線であると。
だからこそサブラクは、自らの唯一無二の宝具”戯睡郷”メアをマスターの少女へと渡すような真似をしたのだ。
これを用いることで、出夢はサーヴァントと戦えるようになる。
僅かであれど神秘を宿しているこの短剣でならば、サーヴァントの肉を切り裂くことができるのだから。
「必ず返せ、マスター。壊すようなことがあっては、俺はお前をひょっとすると殺してしまいかねないぞ」
「ああ、それは分かってる。きっと返すさ。ありがとよ、旦那」
出夢は素直に礼を述べた。
彼女にとって宝具はまさに最高の品。
これを介せばサーヴァントどもに傷を付けることが出来るだけでなく、暴飲暴食などと合わせて用いても自壊することがない。
勝とう。いや、勝たねばならない。
勝利を必ずやこの手に。出夢は夜の街へと叫ぶ。
「ぎゃははははっ! 行くぜェッ、震えるぞハート、燃え尽きるほどヒートッ! ブチ殺すぜェェェェえええええええッッッッ!!!!」
それは猛獣の雄叫び。
戦乱の時は、刻一刻と迫っている。
【深山町・民家/早朝】
【匂宮出夢@戯言シリーズ】
【状態:健康、残令呪使用回数3画、”戯睡郷”メアを所持】
※《一喰い》《暴飲暴食》の隙を解消し威力も向上しました
※ギアス発動下の枢木スザクの動き方を疑似的にではありますが修得しました
【アサシン(”壊刃”サブラク)@灼眼のシャナ】
【状態:健康、魔力消費(小)】
【枢木スザク@コードギアス 反逆のルルーシュ】
【状態:疲労(大)、右腕骨折、左腕欠損(処置済)、両足喪失、残令呪使用回数1画】
※民家の老夫婦に預けられています
※匂宮出夢に《依頼》を行いました
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: