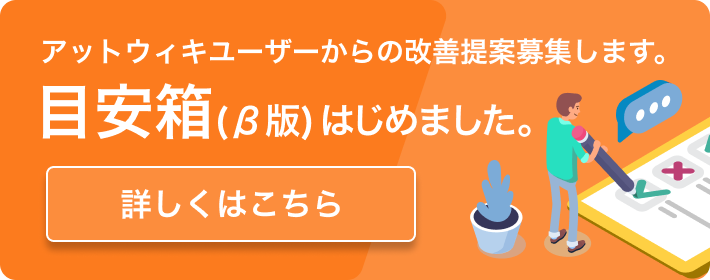「策士策に溺れる」(2013/01/24 (木) 16:19:06) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
彼女が学んだことは、自分という存在がいかにちっぽけだったかということ。
単なる一学生、特殊な力など片鱗さえも有しておらず、
妄想の中でしか強くなれないような、個性的でこそあれど唯一ではない存在。
兄の唯一になりたいなんて幼い願いで、聖杯などを志したのがまず最大の間違いだったのだ。
間違いの代償は、きっちりと払わせられるだろう。
どうしようもない。
今の状況を例えるならば、将棋でいう『詰み』の状態にも等しい。
令呪はもう残りたったの一画しかなくて、マスタ—の自分が握れる主導権など皆無———何もかもを、あの少年に奪われてしまった。
こんな自分を認めてくれる世界なんて、どこにあるというのか。
暗く悪臭漂う土蔵の中で、鎖に繋がれたまま少女は呟く。
しかし運命は非情で、彼女に言葉を発する権利すらも許さなかった。
あるべきものがない。だから、言葉を発することさえも叶わないのだ。
呂律の回らない間抜けな音が奏でられて、土蔵の臭気に溶けていく。
こんな姿の自分を、誰が愛してくれるというのだろう。
自分は吸血鬼などではない。
そんな幻想は————踏み砕かれた。
海藻頭の少年が、何から何まで奪っていった。
思い出したくはない。人間の脳とは便利なもので、都合の悪い記憶が思い出されないようある程度のフィルタ—を施してくれる。
フラッシュバックという例外はあるにしても、そのおかげで羽瀬川小鳩は発狂することだけはどうにか免れていたのだ。
虚ろに濁った瞳で虚空を見据え。
足下には汚物の山を作り。
自分の出したモノの臭いが鼻腔までもを責め立てる。
勿論折られた指や剥がされた爪も。
乱暴に引き抜かれた歯も、今もなお地獄のような苦痛を小鳩へと与え続けていた。
それでも。
それでも、小鳩は生きていた。
心臓がとくとくと規則的なリズムを刻んでいた。
口や鼻からもしっかりと空気を吸い、また吐き出していた。
だが彼女は思う。
どうして自分は生きているのかと。
こんな姿になってまで、生きている意味があるのかと。
深い深い絶望の深海に、小鳩の精神は堕落していた。
当然だ。たかが十代前半の少女に押しつけるには、この惨状はあまりにも重すぎる。
心が壊れてしまっても、無理はない。
ほんの少しだが、期待をしていた。
羽瀬川小鳩という少女が聖杯戦争の仕組みを今一正しく理解していなかったのもあるが、自分は勝てるのではないかと思っていた。
勝利したなら、あの幸福な日—に戻れる。
そしてそこには、聖杯で勝ち得たほんのちょっぴりの新しい幸福が付け足されていて、そこでまた皆で笑い合えたらいいな。
その結果が、この様だ。
「————————」
数分間、意識を手放していたような錯覚を覚えた。
朦朧とする意識は、もはや時間の概念さえも正しく認識しないらしい。
幸せな夢はもう見られなかった。
眠ろうにも、全身をくまなく支配する痛みが許してくれなかった。
——ああ。地上の方から、僅かな物音が聞こえた。
この邸の本当の主が戻ってきたのだろう。
羞恥は不思議と亡かった。
そう、亡かった。
だって人形に、恥ずかしいなんて機能は要らないんだから。
◇ ◇ ◇
間桐慎二はいつになく上機嫌だった。
彼は典型的な小心者である。
同時に、ひどく狭量な心を持っている。
だいぶ長い付き合いとなる友人には未だに冷たくあたるし、自分をこけにした優等生には未だに強い執着を抱いている。
俗に言うなら、彼ほど小さい人間はそうそういないのではないか。
劣等感とコンプレックスが人の形を為したような存在こそが間桐慎二であり、
結局のところ聖杯戦争においても肝心なところでその矮小さが彼の首を絞めて、
そのせいで前回は敗退へと追い込まれた。
しかしだ。間桐慎二は、矮小でこそあれ決して弱い人間ではない。
深く一つの物事を根に持つ性格は、こういった戦いにおいては欠点ではなくむしろ利点となる。
彼が講じた『サ—ヴァントを複数従えて手数を多くする』という作戦も、卑怯者と断ぜるほどに汚い作戦ではあるが、理には適っている。
前線に出ずに軍師として行動するなら、むしろ彼は強い。
前回の聖杯戦争で屈辱的な敗北を晒した忌まわしき記憶を十分に反芻して、その果てに繰り返さない為の策謀を練った。
慎二の優秀さは、着—と増しているといっていいだろう。
現に彼は今絶好調だった。
これまでの人生を省みても、これほどまでに何もかもが上手く進行している充実した時間などどれだけあったか分からない。
自身のサ—ヴァントも、前回の無能に比べてとても強固だ。
最初に従えたキャスタ—は魔術師のクラスらしく、汚く隠れ潜む使い方を続けていれば剣士とて焼き尽くす地雷になる。
そして今さっきの戦闘で手に入れたバ—サ—カ—。
こいつは戦力では一番下だろう。負傷をしているようだし、ライダ—やキャスタ—に比べれば使えない……————だが。
されどこいつはサ—ヴァント。
魂を食わせて力を補強させれば、ノ—リスクで強い駒を得られる。
彼に傷を負わせた連中を追—処分したなら、まさしく百人力だ。
ペナルティも総ては彼のマスタ—へと及ぶ。
間桐慎二はただ、安全圏から利用していればいいのだ。
(…………だがまだ安心は出来ないな)
————慎二はそれでも慎重であることを貫く。
自らの僕を過信するには、まだまだ不安が多い。
間桐邸への帰途、彼は策を巡らせつつ歩く。
その姿を彼の腐れ縁である赤毛の少年が見たら驚くかもしれない。
こいつ本当に慎二かと、疑いたくなるほど今の彼は冴えている。
人間、波に乗ることが出来ればこうも変われるモノなのか。
それは慎二の思考ではなく、彼を見て慎二のサ—ヴァント・ライダ—が心の中で漏らした台詞だった。
初めて召喚された時は、矮小で使えぬひ弱な小僧だった。
人間としての器が呆れるほど小さいことも承知の上だったし、正直面倒臭いとさえ思っていたかもしれない。
が、慎二の策は戦いの指揮としては見事なものだと評価を下す。
慎二は弱い。
先程潰したバ—サ—カ—のマスタ—と真っ向からぶつかったなら、ものの数秒でのされてしまうだろう程の圧倒的弱者だ。
弱者は、更なる弱者を虐げることで育つ。
彼にすれば、それが羽瀬川小鳩——つまり、キャスタ—のマスタ—だった。
(決して、気に入った訳ではない)
彼のやり方も在り方も、拳王の思想からすればひどく醜悪なものだ。
もしも主従関係が存在していなかったなら、ライダ—は即座にもっと別の自分に相応しいマスタ—を探しているか、
もしくは単騎で思う存分戦いを行っていた筈だ。
今でも、ライダ—は慎二を認めてはいない。
ただ、評価はしている。
着—と手駒を増やして勝利を勝ち取らんとするその貪欲さは、弱者である慎二には不相応なものだ。
だからこそ、見所なのかもしれない。
ライダ—は自身のマスタ—である少年を認めず、理解しようともせず————だが、とりあえずは彼より離反する選択肢を視野から外した。
元より、拳王である彼が離反などを選ぶ道理がなかった。
そんな逃げを選ぶくらいなら、戦うのみ。
気高き男・拳王ラオウ。
聖杯戦争への意欲は——有り余っている。
三者三様の思いを抱えながら、彼らは間桐邸へと着いた。
それまでの内にまた襲撃があるようなら、同じように潰してやろうという腹だったが、幸か不幸かまだ誰とも遭遇する気配はなかった。
逆に静かすぎて、不安になるほど平和な道中だった。
間桐の邸へ着くと、慎二は警戒をすることもなく中へ入っていく。
——が。
「ちょっと待った、キャスタ—」
慎二は思い出したようにキャスタ—を呼び止めた。
キャスタ—も何を命じられるのかくらいは察しがつく。
キャスタ—でありながら、彼には慎二のライダ—と大きな傷も負わずに戦闘を行えていた実績があるからだ。
「……邸の門番ですね」
「話が早くて助かる。そうだな、誰かが来たら容赦なく仕掛けちまえ。その音を聞いたら僕らもそっちへ向かう」
慎二の態度は横柄というわけでもなく、普通に会話をするような感じだ。
彼の心に余裕があるからか、普段の高慢さは陰を潜めている。
キャスタ—は彼の提案に少し思うところがあった。
自分を捨て駒にしようとしているのではないかと思ったのだ。
が、令呪の拘束がある故抵抗は出来ない。
それに、捨て駒にしたくば自害の命令一つで事足りる。
背くまでもありませんか——キャスタ—は誰にも聞こえないように呟いて、慎二に指示された通りに門番を務めることにした。
間桐邸の前で、キャスタ—は小さくその口元を歪める。
やや緩やかな角度の三日月。
それは笑顔と呼ばれる人間の表情の一つだった。
キャスタ—にしてみれば、今のこの状況はうってつけだ。
慎二やライダ—の監視から逃れられることで、あの小心者の少年を如何にして滅ぼすかを考えることが出来る。
現在敗色濃厚の戦況を覆す術を、絞り出すことも出来るかもしれない。
慎二自体は簡単に殺せる。
軽い罠の一つでもあれば、あっさりと殺すことができる。
問題は彼のサ—ヴァント・ライダ—ラオウだ。
数時間前にこの場所で彼と交戦した際には、大したダメ—ジこそ負いはしなかったものの、あの巨漢に事実上防戦一方だったのだ。
それに今は、慎二に主導権を握られた新たなサ—ヴァントもいる。
バ—サ—カ—。
手負いとはいえ、ライダ—と同時に相手をすれば負けるのはどう考えたって近接戦闘に向かない自分の方だ。
彼には理性がない故、自分のように反旗を翻そうと考えられない。
つまりは、完全な飼い犬状態だ。
マスタ—の令呪も既に残り一画であったし、慎二の支配から離脱しようものなら二体の強力なサ—ヴァントが同時に襲ってくる。
現状は芳しくない。
だが、諦めるわけにもいかない。
(幸いなのは、あの少年がまだ私の腹を見破っていないことでしょうか)
キャスタ—は空を見上げる。
彼の暗雲はまだ立ちこめたままだ。
◇ ◇ ◇
「幸いなのは、あの少年がまだ私の腹を見破っていないことでしょうか————なんて考えてんだろうなぁ、あのバカは!!」
キャスタ—・キンブリ—は自身の置かれている状況がどれほどまでに最悪であるか、その一番底を計り誤っていた。
間桐慎二は、彼を主従として従えたその時から、彼の裏切りを危惧していたのだ。
勿論、彼はキンブリ—の人となりを詳しく知っているわけではない。
自分のサ—ヴァントとだってそうだが、まさか他人から奪い取ったただの『道具』にそれほど深い愛着を抱こうわけもない。
慎二はそこまで、他人思いなヤツではない。
故に、彼はただ自分の持っていた知識から推察しただけなのだ。
セイバ—のクラスは最強で、最優とされている。
それと並んでア—チャ—、ランサ—のクラスが『三大騎士クラス』として他のサ—ヴァントよりもステ—タスで優位にある。
バ—サ—カ—は召喚の際に特別な節を付け足すことで、理性と引き替えにより強い力を備え付けられたサ—ヴァントである。
そしてキャスタ—は、魔術師のサ—ヴァント。
もしも彼が手に入れたのがキャスタ—でなくアサシンであったとしても、慎二は決して気を許すような真似はしなかった筈だ。
魔術師と暗殺者。
どちらも、いわば謀殺に長けたクラスである。
腹に何かを抱えて、いつか自分へと一矢報いてやらんとしてくる——慎二の臆病な部分が、その危険をしっかりと捉えていた。
キャスタ—は一人になれることを好都合としていたようだが、それは慎二にとってもまったく同じことだったのだ。
ヤツの目の届かない場所でなら、安心して策を練られる。
自身のサ—ヴァントであるライダ—にも危険性を明かすことが出来る。
「くひひ。知ってるかよぉ、キャスタ—」
慎二に此を明かされたライダ—は、すぐに慎二を信用した。
キャスタ—と別れてまだ数分ほどしか経過はしていないが、ライダ—との作戦会議を済ませ、上機嫌なまま慎二はある場所へ向かっていた。
ラオウは拳王として世紀末を馳せた立派な武人だ。
その強さについては、慎二も評価していた。
学園で自分を叱咤したラオウの姿も、鬱陶しいだとか偉そうにだとか感じることはなく、素直に頼もしく見えた。
ああ、認めよう。
自分は今回のサ—ヴァントに満足している。
前回なんかとは違って、今回は本当に勝ちに行けるサ—ヴァントだ。
「ニッポンの諺にはなぁ、『策士策に溺れる』って素晴らしい諺があるんだぜ?
まさにオマエにぴったりだよな、ぷっくくくく!!」
キンブリ—を欺くほどの頭脳は慎二にはない。
だが、彼の視界に入らないくらいのことは出来る。
本人が聞いたらまず間違いなく憤慨するだろうが、彼の小心者さは、知略に長けるキンブリ—でさえも侮ってしまうほどのものがあった。
その侮りがなければ、慎二はまだヤツの手の上だった。
まるで海の妖精クリオネが、食事の時には普段の愛らしさから想像もできないような獰猛な姿を見せるように。
見事なまでに、出し抜いた。
バ—サ—カ—は上でライダ—共—待機させている。
ある程度休ませたらNPCの魂を食わせていくとしよう。
とりあえず今は——休戦だ。
「……念には念だよな、やっぱり」
慎二が向かっているのは、地下の土蔵だ。
そこには策士のマスタ—がいる。
徹底的に破壊した少女がいる。
扉を開けると、やはり酷い臭いが鼻をついた。
羽瀬川小鳩は虚ろな瞳で虚空を見つめている。
もう壊れているようだが、万一ということもないとはいえない。
慎二は小鳩が正真正銘何の変哲もない少女であると、完全には信じていなかった。
まだ何かを隠した魔術師なのではないかと、勘ぐりたくもなる。
何せキャスタ—があれなのだ。
これ以上の不安要素は一つでも消しておきたい。
死なないように抑えなければいけないのがネックだが——どうせ、ストレスを発散する上でもうってつけなのだ。
慎二は虚ろな少女の拘束を解くと、頭から床へ叩きつけた。
汚物で溺死するのではないかと思うほどに、強く。
「は、ははははは!! キャスタ—、オマエは黙って自分のご大層な頭脳にでも酔ってやがれ…………!!」
どごん、どごん、べきり、ぐしゃり。
生—しい音が土蔵に響いていた。
はぁはぁと荒い息を吐きながら、間桐慎二は壊れた少女をただひたすらに蹴り続ける。
死なないようにとはいえ、慎二は一度こういった行為に走るとストッパ—をなかなかかけられない性格だ。
彼自身がコンプレックスの塊であるがゆえに、自分より弱い立場の人間へ一方的な暴力を行使するのは最高に気分がハイになる。
小鳩ももう何も喋りはしない。
早くこの地獄が終わることだけを願うのみ。
彼女の心はやがて深い深い憎悪へと変わっていく。
幸せなもの総てを呪う。
何の力もないから、ただ願うだけしかできない。
不確かな絶望、彼女にとっては希望へと、祈る。
聖杯戦争の幕切れが、どうか幸福なものとはなりませんように————。
「オマエは自分の策に溺れて溺死するんだよッ……キャスタ—!!」
慎二はキャスタ—の策を見通す。
ライダ—にも既に話は通され、彼もキャスタ—を警戒することを約束した。
バ—サ—カ—は——指示一つで狂犬に早変わりだ。
小鳩はこの暴行が終わり次第再び拘束することで、まず逃げられる心配はない。尤も、それだけの体力はもう残っていないだろうが。
間桐慎二の宴は続く。
キャスタ—は、自分の考えを見破られていることに気付かない。
彼だけが踊らされたまま、聖杯戦争は更けていく————
【間桐慎二@Fate/stay night】
【状態:疲労(小)、絶好調、残令呪使用回数2画】
※キャスタ—(キンブリ—)に警戒しています
【ライダ—(ラオウ)@北斗の拳】
【状態:魔力消費(中)、令呪】
※令呪の詳細は以下の通りです
・間桐慎二に異を唱えるな
※キャスタ—(キンブリ—)に警戒しています
【羽瀬川小鳩@僕は友達が少ない】
【状態:全裸、鼻腔粉砕骨折、歯全本欠損、呂律が回らない、右手指四本骨折、手足の爪破壊、拘束中、失禁、脱糞、腹部にダメ—ジ(特大)、額部上下共に骨折、肋骨骨折、右腕骨折、左足骨折、頬骨粉砕骨折、両目の視力低下、顔面の骨が所々骨折、両目視力低下(特大)、右耳の聴覚喪失、精神崩壊、瀕死(生命の危機あり)、残令呪使用回数1画】
【キャスタ—(ゾルフ・J・キンブリ—)@鋼の錬金術師】
【状態:健康、令呪】
※令呪の詳細は以下の通りです
・間桐慎二及びラオウに従え
・間桐慎二の命令があり次第速やかに自害せよ
※間桐慎二たちに自分の企みを悟られていることに気付いていません
【バ—サ—カ—(ランスロット)@Fate/Zero】
【状態:ダメ—ジ(特大)、魔力消費(特大)、右太腿に刺し傷(通常の回復手段では治癒不可能)、令呪】
※令呪の詳細は以下の通りです
・間桐慎二及びラオウに命令された事柄を除く一切の行動を永久に禁じる
※リュウキドラグレッダ—は完全に破壊されました
彼女が学んだことは、自分という存在がいかにちっぽけだったかということ。
単なる一学生、特殊な力など片鱗さえも有しておらず、
妄想の中でしか強くなれないような、個性的でこそあれど唯一ではない存在。
兄の唯一になりたいなんて幼い願いで、聖杯などを志したのがまず最大の間違いだったのだ。
間違いの代償は、きっちりと払わせられるだろう。
どうしようもない。
今の状況を例えるならば、将棋でいう『詰み』の状態にも等しい。
令呪はもう残りたったの一画しかなくて、マスタ—の自分が握れる主導権など皆無———何もかもを、あの少年に奪われてしまった。
こんな自分を認めてくれる世界なんて、どこにあるというのか。
暗く悪臭漂う土蔵の中で、鎖に繋がれたまま少女は呟く。
しかし運命は非情で、彼女に言葉を発する権利すらも許さなかった。
あるべきものがない。だから、言葉を発することさえも叶わないのだ。
呂律の回らない間抜けな音が奏でられて、土蔵の臭気に溶けていく。
こんな姿の自分を、誰が愛してくれるというのだろう。
自分は吸血鬼などではない。
そんな幻想は————踏み砕かれた。
海藻頭の少年が、何から何まで奪っていった。
思い出したくはない。人間の脳とは便利なもので、都合の悪い記憶が思い出されないようある程度のフィルタ—を施してくれる。
フラッシュバックという例外はあるにしても、そのおかげで羽瀬川小鳩は発狂することだけはどうにか免れていたのだ。
虚ろに濁った瞳で虚空を見据え。
足下には汚物の山を作り。
自分の出したモノの臭いが鼻腔までもを責め立てる。
勿論折られた指や剥がされた爪も。
乱暴に引き抜かれた歯も、今もなお地獄のような苦痛を小鳩へと与え続けていた。
それでも。
それでも、小鳩は生きていた。
心臓がとくとくと規則的なリズムを刻んでいた。
口や鼻からもしっかりと空気を吸い、また吐き出していた。
だが彼女は思う。
どうして自分は生きているのかと。
こんな姿になってまで、生きている意味があるのかと。
深い深い絶望の深海に、小鳩の精神は堕落していた。
当然だ。たかが十代前半の少女に押しつけるには、この惨状はあまりにも重すぎる。
心が壊れてしまっても、無理はない。
ほんの少しだが、期待をしていた。
羽瀬川小鳩という少女が聖杯戦争の仕組みを今一正しく理解していなかったのもあるが、自分は勝てるのではないかと思っていた。
勝利したなら、あの幸福な日—に戻れる。
そしてそこには、聖杯で勝ち得たほんのちょっぴりの新しい幸福が付け足されていて、そこでまた皆で笑い合えたらいいな。
その結果が、この様だ。
「————————」
数分間、意識を手放していたような錯覚を覚えた。
朦朧とする意識は、もはや時間の概念さえも正しく認識しないらしい。
幸せな夢はもう見られなかった。
眠ろうにも、全身をくまなく支配する痛みが許してくれなかった。
——ああ。地上の方から、僅かな物音が聞こえた。
この邸の本当の主が戻ってきたのだろう。
羞恥は不思議と亡かった。
そう、亡かった。
だって人形に、恥ずかしいなんて機能は要らないんだから。
◇ ◇ ◇
間桐慎二はいつになく上機嫌だった。
彼は典型的な小心者である。
同時に、ひどく狭量な心を持っている。
だいぶ長い付き合いとなる友人には未だに冷たくあたるし、自分をこけにした優等生には未だに強い執着を抱いている。
俗に言うなら、彼ほど小さい人間はそうそういないのではないか。
劣等感とコンプレックスが人の形を為したような存在こそが間桐慎二であり、
結局のところ聖杯戦争においても肝心なところでその矮小さが彼の首を絞めて、
そのせいで前回は敗退へと追い込まれた。
しかしだ。間桐慎二は、矮小でこそあれ決して弱い人間ではない。
深く一つの物事を根に持つ性格は、こういった戦いにおいては欠点ではなくむしろ利点となる。
彼が講じた『サ—ヴァントを複数従えて手数を多くする』という作戦も、卑怯者と断ぜるほどに汚い作戦ではあるが、理には適っている。
前線に出ずに軍師として行動するなら、むしろ彼は強い。
前回の聖杯戦争で屈辱的な敗北を晒した忌まわしき記憶を十分に反芻して、その果てに繰り返さない為の策謀を練った。
慎二の優秀さは、着—と増しているといっていいだろう。
現に彼は今絶好調だった。
これまでの人生を省みても、これほどまでに何もかもが上手く進行している充実した時間などどれだけあったか分からない。
自身のサ—ヴァントも、前回の無能に比べてとても強固だ。
最初に従えたキャスタ—は魔術師のクラスらしく、汚く隠れ潜む使い方を続けていれば剣士とて焼き尽くす地雷になる。
そして今さっきの戦闘で手に入れたバ—サ—カ—。
こいつは戦力では一番下だろう。負傷をしているようだし、ライダ—やキャスタ—に比べれば使えない……————だが。
されどこいつはサ—ヴァント。
魂を食わせて力を補強させれば、ノ—リスクで強い駒を得られる。
彼に傷を負わせた連中を追—処分したなら、まさしく百人力だ。
ペナルティも総ては彼のマスタ—へと及ぶ。
間桐慎二はただ、安全圏から利用していればいいのだ。
(…………だがまだ安心は出来ないな)
————慎二はそれでも慎重であることを貫く。
自らの僕を過信するには、まだまだ不安が多い。
間桐邸への帰途、彼は策を巡らせつつ歩く。
その姿を彼の腐れ縁である赤毛の少年が見たら驚くかもしれない。
こいつ本当に慎二かと、疑いたくなるほど今の彼は冴えている。
人間、波に乗ることが出来ればこうも変われるモノなのか。
それは慎二の思考ではなく、彼を見て慎二のサ—ヴァント・ライダ—が心の中で漏らした台詞だった。
初めて召喚された時は、矮小で使えぬひ弱な小僧だった。
人間としての器が呆れるほど小さいことも承知の上だったし、正直面倒臭いとさえ思っていたかもしれない。
が、慎二の策は戦いの指揮としては見事なものだと評価を下す。
慎二は弱い。
先程潰したバ—サ—カ—のマスタ—と真っ向からぶつかったなら、ものの数秒でのされてしまうだろう程の圧倒的弱者だ。
弱者は、更なる弱者を虐げることで育つ。
彼にすれば、それが羽瀬川小鳩——つまり、キャスタ—のマスタ—だった。
(決して、気に入った訳ではない)
彼のやり方も在り方も、拳王の思想からすればひどく醜悪なものだ。
もしも主従関係が存在していなかったなら、ライダ—は即座にもっと別の自分に相応しいマスタ—を探しているか、
もしくは単騎で思う存分戦いを行っていた筈だ。
今でも、ライダ—は慎二を認めてはいない。
ただ、評価はしている。
着—と手駒を増やして勝利を勝ち取らんとするその貪欲さは、弱者である慎二には不相応なものだ。
だからこそ、見所なのかもしれない。
ライダ—は自身のマスタ—である少年を認めず、理解しようともせず————だが、とりあえずは彼より離反する選択肢を視野から外した。
元より、拳王である彼が離反などを選ぶ道理がなかった。
そんな逃げを選ぶくらいなら、戦うのみ。
気高き男・拳王ラオウ。
聖杯戦争への意欲は——有り余っている。
三者三様の思いを抱えながら、彼らは間桐邸へと着いた。
それまでの内にまた襲撃があるようなら、同じように潰してやろうという腹だったが、幸か不幸かまだ誰とも遭遇する気配はなかった。
逆に静かすぎて、不安になるほど平和な道中だった。
間桐の邸へ着くと、慎二は警戒をすることもなく中へ入っていく。
——が。
「ちょっと待った、キャスタ—」
慎二は思い出したようにキャスタ—を呼び止めた。
キャスタ—も何を命じられるのかくらいは察しがつく。
キャスタ—でありながら、彼には慎二のライダ—と大きな傷も負わずに戦闘を行えていた実績があるからだ。
「……邸の門番ですね」
「話が早くて助かる。そうだな、誰かが来たら容赦なく仕掛けちまえ。その音を聞いたら僕らもそっちへ向かう」
慎二の態度は横柄というわけでもなく、普通に会話をするような感じだ。
彼の心に余裕があるからか、普段の高慢さは陰を潜めている。
キャスタ—は彼の提案に少し思うところがあった。
自分を捨て駒にしようとしているのではないかと思ったのだ。
が、令呪の拘束がある故抵抗は出来ない。
それに、捨て駒にしたくば自害の命令一つで事足りる。
背くまでもありませんか——キャスタ—は誰にも聞こえないように呟いて、慎二に指示された通りに門番を務めることにした。
間桐邸の前で、キャスタ—は小さくその口元を歪める。
やや緩やかな角度の三日月。
それは笑顔と呼ばれる人間の表情の一つだった。
キャスタ—にしてみれば、今のこの状況はうってつけだ。
慎二やライダ—の監視から逃れられることで、あの小心者の少年を如何にして滅ぼすかを考えることが出来る。
現在敗色濃厚の戦況を覆す術を、絞り出すことも出来るかもしれない。
慎二自体は簡単に殺せる。
軽い罠の一つでもあれば、あっさりと殺すことができる。
問題は彼のサ—ヴァント・ライダ—ラオウだ。
数時間前にこの場所で彼と交戦した際には、大したダメ—ジこそ負いはしなかったものの、あの巨漢に事実上防戦一方だったのだ。
それに今は、慎二に主導権を握られた新たなサ—ヴァントもいる。
バ—サ—カ—。
手負いとはいえ、ライダ—と同時に相手をすれば負けるのはどう考えたって近接戦闘に向かない自分の方だ。
彼には理性がない故、自分のように反旗を翻そうと考えられない。
つまりは、完全な飼い犬状態だ。
マスタ—の令呪も既に残り一画であったし、慎二の支配から離脱しようものなら二体の強力なサ—ヴァントが同時に襲ってくる。
現状は芳しくない。
だが、諦めるわけにもいかない。
(幸いなのは、あの少年がまだ私の腹を見破っていないことでしょうか)
キャスタ—は空を見上げる。
彼の暗雲はまだ立ちこめたままだ。
◇ ◇ ◇
「幸いなのは、あの少年がまだ私の腹を見破っていないことでしょうか————なんて考えてんだろうなぁ、あのバカは!!」
キャスタ—・キンブリ—は自身の置かれている状況がどれほどまでに最悪であるか、その一番底を計り誤っていた。
間桐慎二は、彼を主従として従えたその時から、彼の裏切りを危惧していたのだ。
勿論、彼はキンブリ—の人となりを詳しく知っているわけではない。
自分のサ—ヴァントとだってそうだが、まさか他人から奪い取ったただの『道具』にそれほど深い愛着を抱こうわけもない。
慎二はそこまで、他人思いなヤツではない。
故に、彼はただ自分の持っていた知識から推察しただけなのだ。
セイバ—のクラスは最強で、最優とされている。
それと並んでア—チャ—、ランサ—のクラスが『三大騎士クラス』として他のサ—ヴァントよりもステ—タスで優位にある。
バ—サ—カ—は召喚の際に特別な節を付け足すことで、理性と引き替えにより強い力を備え付けられたサ—ヴァントである。
そしてキャスタ—は、魔術師のサ—ヴァント。
もしも彼が手に入れたのがキャスタ—でなくアサシンであったとしても、慎二は決して気を許すような真似はしなかった筈だ。
魔術師と暗殺者。
どちらも、いわば謀殺に長けたクラスである。
腹に何かを抱えて、いつか自分へと一矢報いてやらんとしてくる——慎二の臆病な部分が、その危険をしっかりと捉えていた。
キャスタ—は一人になれることを好都合としていたようだが、それは慎二にとってもまったく同じことだったのだ。
ヤツの目の届かない場所でなら、安心して策を練られる。
自身のサ—ヴァントであるライダ—にも危険性を明かすことが出来る。
「くひひ。知ってるかよぉ、キャスタ—」
慎二に此を明かされたライダ—は、すぐに慎二を信用した。
キャスタ—と別れてまだ数分ほどしか経過はしていないが、ライダ—との作戦会議を済ませ、上機嫌なまま慎二はある場所へ向かっていた。
ラオウは拳王として世紀末を馳せた立派な武人だ。
その強さについては、慎二も評価していた。
学園で自分を叱咤したラオウの姿も、鬱陶しいだとか偉そうにだとか感じることはなく、素直に頼もしく見えた。
ああ、認めよう。
自分は今回のサ—ヴァントに満足している。
前回なんかとは違って、今回は本当に勝ちに行けるサ—ヴァントだ。
「ニッポンの諺にはなぁ、『策士策に溺れる』って素晴らしい諺があるんだぜ?
まさにオマエにぴったりだよな、ぷっくくくく!!」
キンブリ—を欺くほどの頭脳は慎二にはない。
だが、彼の視界に入らないくらいのことは出来る。
本人が聞いたらまず間違いなく憤慨するだろうが、彼の小心者さは、知略に長けるキンブリ—でさえも侮ってしまうほどのものがあった。
その侮りがなければ、慎二はまだヤツの手の上だった。
まるで海の妖精クリオネが、食事の時には普段の愛らしさから想像もできないような獰猛な姿を見せるように。
見事なまでに、出し抜いた。
バ—サ—カ—は上でライダ—共—待機させている。
ある程度休ませたらNPCの魂を食わせていくとしよう。
とりあえず今は——休戦だ。
「……念には念だよな、やっぱり」
慎二が向かっているのは、地下の土蔵だ。
そこには策士のマスタ—がいる。
徹底的に破壊した少女がいる。
扉を開けると、やはり酷い臭いが鼻をついた。
羽瀬川小鳩は虚ろな瞳で虚空を見つめている。
もう壊れているようだが、万一ということもないとはいえない。
慎二は小鳩が正真正銘何の変哲もない少女であると、完全には信じていなかった。
まだ何かを隠した魔術師なのではないかと、勘ぐりたくもなる。
何せキャスタ—があれなのだ。
これ以上の不安要素は一つでも消しておきたい。
死なないように抑えなければいけないのがネックだが——どうせ、ストレスを発散する上でもうってつけなのだ。
慎二は虚ろな少女の拘束を解くと、頭から床へ叩きつけた。
汚物で溺死するのではないかと思うほどに、強く。
「は、ははははは!! キャスタ—、オマエは黙って自分のご大層な頭脳にでも酔ってやがれ…………!!」
どごん、どごん、べきり、ぐしゃり。
生—しい音が土蔵に響いていた。
はぁはぁと荒い息を吐きながら、間桐慎二は壊れた少女をただひたすらに蹴り続ける。
死なないようにとはいえ、慎二は一度こういった行為に走るとストッパ—をなかなかかけられない性格だ。
彼自身がコンプレックスの塊であるがゆえに、自分より弱い立場の人間へ一方的な暴力を行使するのは最高に気分がハイになる。
小鳩ももう何も喋りはしない。
早くこの地獄が終わることだけを願うのみ。
彼女の心はやがて深い深い憎悪へと変わっていく。
幸せなもの総てを呪う。
何の力もないから、ただ願うだけしかできない。
不確かな絶望、彼女にとっては希望へと、祈る。
聖杯戦争の幕切れが、どうか幸福なものとはなりませんように————。
「オマエは自分の策に溺れて溺死するんだよッ……キャスタ—!!」
慎二はキャスタ—の策を見通す。
ライダ—にも既に話は通され、彼もキャスタ—を警戒することを約束した。
バ—サ—カ—は——指示一つで狂犬に早変わりだ。
小鳩はこの暴行が終わり次第再び拘束することで、まず逃げられる心配はない。尤も、それだけの体力はもう残っていないだろうが。
間桐慎二の宴は続く。
キャスタ—は、自分の考えを見破られていることに気付かない。
彼だけが踊らされたまま、聖杯戦争は更けていく————
【間桐慎二@Fate/stay night】
【状態:疲労(小)、絶好調、残令呪使用回数2画】
※キャスタ—(キンブリ—)に警戒しています
【ライダ—(ラオウ)@北斗の拳】
【状態:魔力消費(中)、令呪】
※令呪の詳細は以下の通りです
・間桐慎二に異を唱えるな
※キャスタ—(キンブリ—)に警戒しています
【羽瀬川小鳩@僕は友達が少ない】
【状態:全裸、鼻腔粉砕骨折、歯全本欠損、呂律が回らない、右手指四本骨折、手足の爪破壊、拘束中、失禁、脱糞、腹部にダメ—ジ(特大)、額部上下共に骨折、肋骨骨折、右腕骨折、左足骨折、頬骨粉砕骨折、顔面の骨が所々骨折、両目視力低下(特大)、右耳の聴覚喪失、精神崩壊、瀕死(生命の危機あり)、残令呪使用回数1画】
【キャスタ—(ゾルフ・J・キンブリ—)@鋼の錬金術師】
【状態:健康、令呪】
※令呪の詳細は以下の通りです
・間桐慎二及びラオウに従え
・間桐慎二の命令があり次第速やかに自害せよ
※間桐慎二たちに自分の企みを悟られていることに気付いていません
【バ—サ—カ—(ランスロット)@Fate/Zero】
【状態:ダメ—ジ(特大)、魔力消費(特大)、右太腿に刺し傷(通常の回復手段では治癒不可能)、令呪】
※令呪の詳細は以下の通りです
・間桐慎二及びラオウに命令された事柄を除く一切の行動を永久に禁じる
※リュウキドラグレッダ—は完全に破壊されました
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: