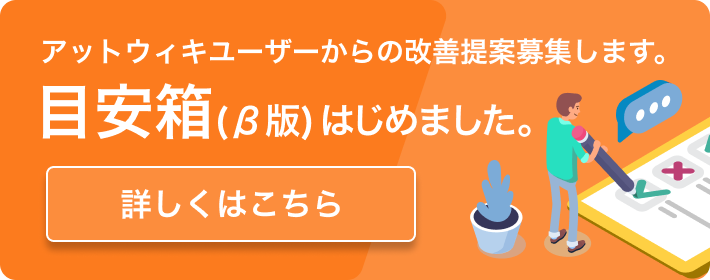「FINAL DEAD LANCER(中編)」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「FINAL DEAD LANCER(中編)」(2014/02/21 (金) 21:58:19) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
「シロウはどこに行ったのー!?」
時間は士郎とルルーシュが柳洞寺に到着したところまで遡る。
謎のサーヴァントとの戦闘の後、イリヤスフィールとランサーは、再度の襲撃を警戒して大きく回り道をしてから衛宮邸に向かった。
あの正体不明のサーヴァントを士郎に近づけたくなかったが故の行動だったが、そのためにまっすぐ柳洞寺へ向かった士郎らと入れ違いになってしまった。
セイバー二人もランサーもサーヴァントとしては索敵範囲が狭いため、お互いの接近に気付けなかったのだ。
士郎の不在に一度は憤慨したイリヤスフィールだったが、深呼吸して落ち着くと、すぐに士郎が向いそうな場所を導き出した。
「多分柳洞寺ね。前もキャスターが居座ってたし、リンを探してから行くなんて回りくどいことをシロウがするとも思えないし」
あの場に遠坂凛がいたかどうかは覚えていないが、彼女はこの冬木のセカンドオーナーだ。
例えマスター候補として招かれていなかったとしても、独自に行動しているに違いない。
そう結論付けたイリヤスフィールは、霊体化したランサーを伴って柳洞寺へと歩いていった。
ランサーに乗って飛んでいったほうが遥かに早いが、先ほどのサーヴァントの存在がその考えを躊躇わせた。
そのまましばらく歩いて柳洞寺へ向かっていたが、異変を感じて立ち止まった。先ほどまではいたはずの通行人が、今では影も形もない。
「人避けの結界、ね…」
そう呟き、あたりを窺う。結界が張られたということは、間違いなくサーヴァントが近くにいる筈だ。そこに、
「坊主もセイバーも留守か。あいつらならこっちの聖杯戦争にも参加してるかとも思ったが、気のせいだったか?」
聞き覚えのある声が聞こえてきた。
「よう、アインツベルンのお嬢ちゃん。元気そうで何よりだ」
まるで十年来の友人にでも会ったかのような気さくさで声を掛けてきたのは、前の聖杯戦争で言峰綺礼のサーヴァントとして暗躍していた蒼い槍兵だった。
黒いバーサーカーを退けた後、悠とランサーは腹ごしらえのために学園地下の食堂に立ち寄り、何故か置いてあった中華料理店・愛家のスペシャル肉丼を二つ注文、連戦で腹が空いていた事もあってすぐに二人とも完食した。(他にも泰山の激辛麻婆豆腐やムドオンカレー、一撃オムライス、妲己ちゃん特製☆ハンバーグの4つのメニューがあったがそっとしておいた)
その後、ランサーの提案で地上の聖杯戦争の勝者が住んでいたという屋敷を訪れたところ、マスターと思しき銀髪の少女を発見した。
菜々子よりも少し上程度の年齢の少女(実際には悠より年上だが)がマスターとして参加しているという事実に驚きを隠せない悠だったが、ランサー曰く彼女はホムンクルスという魔術の結晶のような存在であり、マスターとしての適性だけなら悠など問題にもならないレベルの相手だという。
しばらく迷ったが、どのみち最終的には倒さなければならない相手と割り切って仕掛けることにした。
「ふうん、彼が貴方の今度のマスター?相変わらずマスターに恵まれないのね、クー・フーリン」
「っ!?」
既に自分のサーヴァントの真名が知られている事に動揺する悠に、哀れみすら含んだ視線を向けるイリヤスフィール。
先ほどのサーヴァントのような正体不明の相手ならいざ知らず、正体も割れている相手を恐れるわけもない。
事実、目の前の蒼い槍兵は前の聖杯戦争で自分のサーヴァントであったバーサーカーに一矢も報いる事なく無様に撤退しただけなのだから。
その時と比べて特にステータスに変化もない以上、彼女の余裕も当然の事ではあった。
ただ、マスターの青年が宝具らしき剣を持っていることだけが若干気がかりではあったが。
「そんなに死にたいなら相手をしてあげるわ。ランサー、やれる?」
イリヤスフィールの声に応えて彼女のランサー、本多忠勝が実体化する。
霊核に負った損傷は完全には癒えていないが、先ほどの汚名を返上せんとばかりに意気軒高であった。
ちなみに、忠勝の姿を見た悠が「…ガ○ダム?」と呟いたが、幸か不幸か聞いている者はいなかった。
ともあれ、ここにこの聖杯戦争で初となる同クラス同士のサーヴァントによる戦闘が実現した。
戦闘はクー・フーリンの先制から始まった。
神速の踏み込みから放たれた刺突は、下手なハンマーよりもなお重い一撃だったが、忠勝の装甲はそれを難なく弾き返す。
そしてお返しとばかりに機巧槍によるカウンターを見舞う。
獣の如き瞬発力でその反撃を躱したクー・フーリンだったが、次の瞬間、魔力による衝撃波に襲われ大きく吹き飛ばされる。
しかし、咄嗟に槍を構えて防御姿勢を取った事でダメージを最小限に抑えた。
「チッ、固いっていうレベルじゃねえな、こりゃ。大方前のバーサーカーと同じタイプの宝具なんだろうが…。そこにセイバー並みの魔力放出とはな」
舌打ちしながらも再度攻撃を仕掛けるが、その直前、忠勝の背中から小型の兵器と思しき物体が数基飛び出し、クー・フーリンを襲う。
これこそが忠勝の変化スキルを用いた武装のひとつ、援護形態。対象を追尾し続けるビット射撃により、自身の攻撃の隙をカバーすることができる。
だが、クー・フーリンは最小限の動きだけでビットを的確に躱し、忠勝と打ち合う。
またも弾かれる結果に終わったが、ビットの追撃も意に介さずあっさりと後退してのける。
この一連の動きから、敵が自分と同じ矢よけの加護を有している事を悟った忠勝は、ならばと攻撃形態に切り替え、連装プラズマ砲で相手のマスター諸共吹き飛ばす手段に出る。
面制圧能力の高い射撃であれば、矢よけの加護も意味を為さない。
「調子に乗るな、たわけ!」
咄嗟に張ったルーンにより、戦車砲すら凌ぐ威力を持つプラズマ砲は呆気なくかき消される。
原初18のルーンを修めたクー・フーリンのルーンによる防御は上級宝具すらも防ぎきる性能を持つのだ。
「へえ、思ったよりはやるのね。でも、貴方じゃ私のランサーには傷一つつけられないわよ?もっとも、シロウを狙う以上逃がしてあげる気もないけど」
「………」
余裕のあるイリヤスフィールとは裏腹に忠勝の内心には焦りがあった。
ステータスでも武装の数でもマスターの魔力量でも圧倒しているにも関わらず、ただの一度も有効打を与えられていないのだ。
無論、忠勝は手を抜いてなどいない。全ての攻撃を必殺の意気で放っている。
なのに穿てない。なのに捉えられない。それでいて底が見えない。
少なくとも純粋な技量においては先ほどの仮面ライダーと名乗ったサーヴァントよりも数段上と見ていいだろう。
これまで以上に気合いを込めて槍を構えたその時、マスターの青年から魔力の高まりを感じた。
「ペルソナ」
呪文のような言葉とともに実体化した黒い戦士がクー・フーリンに魔術らしきものをかけた。
同時に、クー・フーリンは自身の全身と得物である朱槍にルーンを刻んでいく。
「―――え?」
イリヤスフィールの口から驚愕が漏れる。
弱敵と侮っていた槍兵から感じられる威圧感は今や彼女の以前のサーヴァント、ヘラクレスにも匹敵するほどのものになっていた。それを証明するように、ステータスも大きく変化した。
【筋力】A+ 【耐久】A+ 【敏捷】A 【魔力】A+ 【幸運】E 【宝具】A
「何よ……それ」
力なく呟くイリヤスフィールの声が虚しく空に消える。
これが前回の聖杯戦争では使われなかったクー・フーリンの奥の手、原初のルーン。
全身にルーン文字を刻むことによって、敏捷と幸運以外のステータスを大きく引き上げる規格外の魔術である。
更にイザナギの補助スキル“マハタルカジャ”と“マハラクカジャ”による支援と宝具そのものにもルーンを刻む事によって、今回の聖杯戦争で現界した全サーヴァントでもトップクラスの能力値に変貌し、一時的にだが限りなく生前に近い力を振るえるようになった。
「真名が割れてるなら出し惜しみをする必要もない。さて、第2ラウンドといこうぜ」
獰猛な笑みを浮かべ、肩慣らしとばかりに朱槍を振り回し、下段に構え直してから、イリヤスフィールと忠勝にとっての死刑宣告を口にした。
「赤枝の騎士団、クー・フーリン。―――推して参る」
先制は、またしてもクー・フーリンからだった。
「砕け―――」
先ほどまでよりも遥かに力強い踏み込みで飛び込むクー・フーリンに、忠勝はすぐさま防御形態を発動し、両腕に盾を装備して攻撃に備える。
カウンターなど考えていては、自分が死ぬだけだと理解していたが故の行動だった。
「―――中つ槍!!!」
だが、そんな備えは真価を発揮した光の御子の前では全くの無意味だった。
クー・フーリンの乾坤一擲の剛槍はガードした忠勝の右腕を盾ごと貫通した。
忠勝の宝具“鉄壁たる鋼の武将(けっしてきずつかぬぶしょう)”の性質はダメージの軽減ではなく、あくまでAランクまでのダメージを無効化するというもの。
逆に言えば、それを超えるダメージは(本人の重装甲があるとはいえ)一切軽減できずにそのまま受けるというマイナスの側面もあるのだ。
そして、忠勝の宝具はランクA+の筋力とランクAに引き上げられた宝具を持つ今のクー・フーリンに対しては必殺技どころか通常攻撃にも耐えられない程度の効果しか発揮できなかった。
「ラ、ランサー!!」
「…………!!」
悲痛な声をあげるイリヤスフィールから悲しみを取り除かんと、忠勝は機巧槍を左手に持ち替え全身全霊の薙ぎ払いを見舞う。
「遅えよ、間抜け」
しかし現実は非情であった。
クー・フーリンはすぐさま忠勝の右腕に刺した朱槍を引き抜くと、忠勝の渾身の反撃を事も無げに受け止めた。
無論、そんな事をすれば忠勝の魔力放出の直撃を被ることになるが、それすらも“マハラクカジャ”と全身のルーンにより防御力の跳ね上がった今のクー・フーリンには全く通用せず、完全に打ち消されてしまった。
「そら、貴様も英雄ならこの程度凌いでみせろ―――!!」
無防備に近い状態になった忠勝を瀑布の如き怒涛の連撃が襲う。
どうにか対応しようとはするが、右腕を損傷した状態では十全に防ぎきれず、たった数秒の間に全身を穴あきチーズのように穿たれる。
左腕の盾も文字通りあっという間に破砕された。
「そんな、何で……!?」
イリヤスフィールが理解できないのも無理はない。
数値上においてはクー・フーリンと忠勝の敏捷値には1ランク程度の差しかない。額面通りに受け取るならば、こうまで忠勝が一方的に攻撃を受けるのは有り得ない。
しかしイリヤスフィールは知らなかった。
サーヴァントの敏捷値とは、機動力と反応速度の総合値で判定されるのだ。
例えば剣豪・佐々木小次郎の場合は機動力よりも反応速度に寄った状態でのランクA+、クー・フーリンは二つを均等にした状態でのランクA、そして本多忠勝は機動力に大きく偏ったランクB。
実際のところ、忠勝のクロスレンジにおける反応速度と運動性は並みのサーヴァントと大差ないレベルしかない。
重量級の武器による戦闘スタイルも相まって、自らの宝具が通用しない相手に懐に入られると、途端に脆弱さを曝け出してしまうのだ。
「何だ、蓋を開けてみりゃ宝具頼みの木偶の坊かよ。本気を出して損したぜ。生前、自分より強い相手と戦った事なかっただろ、お前」
失望したといわんばかりの態度を隠しもしないクー・フーリンに対して、忠勝は最早立っているのもやっとという有様だった。
戦闘続行のスキルが無ければ今頃既に倒れ伏していただろう。そして、クー・フーリンは未だ宝具すら使っていないのだ。
結局のところ、英霊としての格においてクー・フーリンと本多忠勝には隔絶した開きが存在していた。
確かに忠勝は戦国最強の名に恥じない、サーヴァント全体でも平均以上の実力を持つ猛者だったが、その最強という称号もあくまで神秘が薄れ、幻獣や外敵の危機に晒されることのない島国の中でしか通用しないものだった。
加えて、生まれついての絶対強者だった彼は自身と比肩しうる者と戦った経験に乏しく、事実、彼は心眼・真に代表される不利な状況を打開する技能を全くといっていいほど有していなかった。
対して、クー・フーリンはその逸話の中で自身よりも速い者、自身よりも強い者、自身よりも知略に秀でた者と何度も戦ってきた。
彼は最初から強かったわけではなかったが、それでも研鑽を重ね、生きて帰るための準備を整え、時には文字通り血反吐を吐きながら強大な敵に立ち向かっていった。なにより彼自身、強敵との死力を尽くした戦いを望む、飽くなき向上心を持っていた。
敵が理不尽な能力を備えていることも、クー・フーリンにとっては予想外でもなんでもない、ただの日常で大前提でしかない。
そうした生き様の違いが勝敗を分かつ決定的な要因になった。
忠勝が善戦できていたのはお互いの知名度による補正の差とイリヤスフィールの高いマスター適性あったればこそ。その優位性が立ち消えになった今、こうなるのは必然であった。
「正直興醒めもいいところだが、またどこかから横槍を入れられるのも癪なんでな。
じゃあな。その心臓、貰い受ける―――!」
確実にとどめを刺すべく己の朱槍に魔力を込め、必殺の一撃、即ち宝具を使用する準備を整える。
通常なら忠勝の宝具に弾かれるだけだが、今のクー・フーリンの朱槍はルーンの付与によりランクアップしている。
そこから放たれる真名解放の一撃は、忠勝のいかなる防御をも貫くだろう。
そして、忠勝には魔槍の因果逆転の呪いを跳ね返す幸運もない。否、あったとしても動きの鈍重な忠勝ではまず回避できない。
「……駄目」
それが理解できる、いや、理解できてしまうからこそ、イリヤスフィールは頬を伝う涙を止めることができなかった。
だが、ひとつだけ定められた死の運命を覆す手段があった。
「―――刺し穿つ死棘の槍(ゲイ・ボルク)!!!」
クー・フーリンの魔槍が迫る。禍々しい程の魔力をもって放たれた攻撃は、間もなく忠勝の心臓を貫くだろう。
「死なないで、ランサアアアアアーーーー!!!」
イリヤスフィールの左手から令呪が一画消える。
死ぬなという絶対の命令を受けたランサーは、それまでからは考えられない速度でガッチリと心臓をガードする。必ず心臓を貫くとわかっているのならば、そこを守り通す。
魔槍がガードした忠勝の機巧槍を砕き、真っ二つにする。ならば自身の腕で防ぐのみ。
令呪によって生じた魔力と魔槍が轟音を上げて拮抗する。数秒の拮抗の後、魔槍が忠勝の左腕を貫通し、そのまま身体に浅く突き刺さり、そこで止まった。
鋼の英雄は、大英雄の因果逆転の魔槍を前に見事命脈を繋いでみせたのだ。
「令呪があったとはいえ、よく凌いだ―――」
クー・フーリンから贈られる惜しみない賞賛。
「―――と言いたいところだが、詰んだぜ、お前」
そして、死。
とうの昔に“チャージ”を仕込み終え、湖の騎士から奪い取った漆黒の聖剣を持ったイザナギがクー・フーリンの後ろから姿を現し、忠勝の首を斬り飛ばした。
それは、激突する英雄たちに比べて余りにも矮小な存在だった。
だがそれ故に、忠勝はその存在を無意識のうちに忘れてしまっていた。
「最後に一つだけ忠告しておいてやる。お前らはうちのマスターをナメすぎだ」
聖杯戦争とは何もサーヴァントだけの戦いではない。
英霊に比べれば卑小な存在であっても、マスターもまた戦場に確かに存在し、場合によっては英霊にも届く攻撃手段を持つ者もいるのだから。
&COLOR(#FF2000){【ランサー(本多忠勝)@戦国BASARA 消滅】}
「ラ、ランサー……」
サーヴァントを失ったイリヤスフィールがその場にへたり込む。
彼女にとって忠勝はただのサーヴァントではなく、自分に愛情をもって接してくれる心許せる存在だった。
茫然自失としていたが、その時間はすぐに終わりを告げた。
「―――かっ、ぁ……!?」
サーヴァント消滅による電脳死を待つまでもなく、蒼い槍兵の朱槍で心臓を貫かれたからだ。
それはあまりに迅速で、痛みを感じる暇さえ与えられなかった。
「ムーンセルに削除されるまでのたうちまわらせるのは趣味じゃねえ。せめて苦しまずに逝ってくれや」
「ぁ…し、ろ……」
胸からドクドクと血が溢れ、力が抜けていく。
消えゆく意識の中、最期に聞こえたのは自分を呼ぶひどく懐かしい声だった。
&COLOR(#FF2000){【イリヤスフィール・フォン・アインツベルン@Fate/stay night 死亡】}
衛宮士郎とセイバーがその場所に到着した時には、全てが手遅れだった。
「よう、坊主にセイバーじゃねえか。やっぱりお前らも参加してたか。
俺の勘も捨てたもんじゃあなかったらしいな」
見覚えのある槍兵が街角で偶然友人に会ったかのように気安く声を掛けてくる。
もし状況が違えばあるいは士郎も多少は友好的な返事を返したかもしれない。
少なくとも、ランサーが自分の義姉であるイリヤスフィールの心臓に朱槍を突き刺しているという状況下でなければ。
「イリヤぁッ!!」
手遅れと知りながらも、心臓から槍が引き抜かれ、血の海に沈んだイリヤスフィールに駆け寄った。
だが士郎の手が彼女の遺体に触れる寸前、イリヤスフィールの身体は流れ出た血液ごと粒子となって消え去った。
「なっ……!?」
魔術でもこうはならないであろう、と思われる光景に思わず固まってしまう。
ショックから立ち直れない士郎に、ランサーが訝しげに話し掛けてくる。
「何だ、知らなかったのか坊主?こっちの聖杯戦争じゃ敗者は皆ムーンセルにきれいさっぱり消される事になってるんだとよ。まあ俺も見るのは初めてなわけだが」
「ラン、サー……!!」
イリヤスフィールを殺しておきながら悪びれもしないランサーに視線だけで人間を殺せそうなほどの怒りと殺意を剥き出しにする。
だが、ランサーがその程度のことで怯むわけもなく、むしろ呆れた風ですらあった。
「がなるなよ、坊主。戦争で顔見知りが死ぬなんざ当たり前のことだろうが」
「………っ!!」
歯軋りし、今にも双剣を投影してランサーに斬りかからんとする士郎を傍らのセイバーが諌めた。
「シロウ、気持ちはわかりますがどうか落ち着いて下さい。それに、彼らが下したのはイリヤスフィールのサーヴァントだけではないようだ」
そう言って、忠勝を斬ったと同時に実体化を解いたイザナギから再度受け取った聖剣を持つ悠を睨みつける。
「魔術師(メイガス)、その剣をどこで手に入れた」
その剣は、セイバーにとって見覚えのありすぎるものだった。
名を“無毀なる湖光(アロンダイト)”。彼女の右腕だった騎士、ランスロットが所有していた宝具である。セイバーの鋭い眼光に臆した風もなく、銀髪の青年は「拾った」とだけ答えた。
何とも掴みどころのないマスターだとセイバーは思ったが、今わかっているのは前々回と同じくランスロットがサーヴァントとして現界している事、そしていかなる手段を使ったか目の前のランサー主従がランスロットを下して彼の宝具を奪取した事(宝具が残っているところを見るに倒されたわけではないようだ)、そして今イリヤスフィールのサーヴァントを大した消耗もなく撃破したという事だけだ。
言葉にすればそれだけだが、それがどれほどの困難か二度に渡って聖杯戦争を経験したセイバーは嫌というほど熟知していた。
その証左に、ランサーから感じられる圧力は前回対峙した時とは比べものにならないほどだ。
あれが彼の全力だったとはセイバーも思っていなかったが、それでも別人と見紛うほどだ。
あるいは、あの神父の事だから何らかの制約をランサーに課していたのかもしれない。
「実を言えば少しばかり消化不良気味だったんでな。
折角だ、ここで決着着けようじゃねえか、セイバー」
朱槍を下段に構え戦闘態勢をとったランサーに、セイバーもまた不可視の剣を取り出し応戦の構えを見せる。
もとより敏捷性においてはランサーが上。まず逃がしてはくれないだろう。
「頼む、セイバー。…イリヤの仇を、取ってくれ」
悔しげな士郎の言葉に無言で頷く。本当なら士郎自身が仇を討ちたいが、サーヴァントであるランサーに人間である士郎が挑むのは無謀の極みだ。
だからこそ、セイバーに全てを託すしかない。
「ペルソナ」
悠もまた、イザナギを呼び出し既に効果の切れていた補助スキルをかけ直す。
その最中、悠は赤髪の青年と先ほど殺した白い少女に何故か自身と菜々子の影を見出していた。
いや、事実自分はあの青年から自分にとっての菜々子を奪ったのだ。
その罪を噛み締めながらも、それでも歩みを止めないと誓う。
自分にも譲れない願いがある。ランサーもこんな自分に力を貸してくれている。
何より、直接殺したわけではないとはいえ既に自分は四人、いや、先ほどの主従を加えれば六人もの生命と願いを踏み躙ってここにいる。
もう後戻りなどできないし、してはならない。
「さあ、行こうか」
踏み躙った生命を無駄にしないためにも、必ず最後まで勝ち抜いてみせる。
戦いの第二幕が開けた。
to be Continued……
「シロウはどこに行ったのー!?」
時間は士郎とルルーシュが柳洞寺に到着したところまで遡る。
謎のサーヴァントとの戦闘の後、イリヤスフィールとランサーは、再度の襲撃を警戒して大きく回り道をしてから衛宮邸に向かった。
あの正体不明のサーヴァントを士郎に近づけたくなかったが故の行動だったが、そのためにまっすぐ柳洞寺へ向かった士郎らと入れ違いになってしまった。
セイバー二人もランサーもサーヴァントとしては索敵範囲が狭いため、お互いの接近に気付けなかったのだ。
士郎の不在に一度は憤慨したイリヤスフィールだったが、深呼吸して落ち着くと、すぐに士郎が向いそうな場所を導き出した。
「多分柳洞寺ね。前もキャスターが居座ってたし、リンを探してから行くなんて回りくどいことをシロウがするとも思えないし」
あの場に遠坂凛がいたかどうかは覚えていないが、彼女はこの冬木のセカンドオーナーだ。
例えマスター候補として招かれていなかったとしても、独自に行動しているに違いない。
そう結論付けたイリヤスフィールは、霊体化したランサーを伴って柳洞寺へと歩いていった。
ランサーに乗って飛んでいったほうが遥かに早いが、先ほどのサーヴァントの存在がその考えを躊躇わせた。
そのまましばらく歩いて柳洞寺へ向かっていたが、異変を感じて立ち止まった。先ほどまではいたはずの通行人が、今では影も形もない。
「人避けの結界、ね…」
そう呟き、あたりを窺う。結界が張られたということは、間違いなくサーヴァントが近くにいる筈だ。そこに、
「坊主もセイバーも留守か。あいつらならこっちの聖杯戦争にも参加してるかとも思ったが、気のせいだったか?」
聞き覚えのある声が聞こえてきた。
「よう、アインツベルンのお嬢ちゃん。元気そうで何よりだ」
まるで十年来の友人にでも会ったかのような気さくさで声を掛けてきたのは、前の聖杯戦争で言峰綺礼のサーヴァントとして暗躍していた蒼い槍兵だった。
黒いバーサーカーを退けた後、悠とランサーは腹ごしらえのために学園地下の食堂に立ち寄り、何故か置いてあった中華料理店・愛家のスペシャル肉丼を二つ注文、連戦で腹が空いていた事もあってすぐに二人とも完食した。(他にも泰山の激辛麻婆豆腐やムドオンカレー、一撃オムライス、妲己ちゃん特製☆ハンバーグの4つのメニューがあったがそっとしておいた)
その後、ランサーの提案で地上の聖杯戦争の勝者が住んでいたという屋敷を訪れたところ、マスターと思しき銀髪の少女を発見した。
菜々子よりも少し上程度の年齢の少女(実際には悠より年上だが)がマスターとして参加しているという事実に驚きを隠せない悠だったが、ランサー曰く彼女はホムンクルスという魔術の結晶のような存在であり、マスターとしての適性だけなら悠など問題にもならないレベルの相手だという。
しばらく迷ったが、どのみち最終的には倒さなければならない相手と割り切って仕掛けることにした。
「ふうん、彼が貴方の今度のマスター?相変わらずマスターに恵まれないのね、クー・フーリン」
「っ!?」
既に自分のサーヴァントの真名が知られている事に動揺する悠に、哀れみすら含んだ視線を向けるイリヤスフィール。
先ほどのサーヴァントのような正体不明の相手ならいざ知らず、正体も割れている相手を恐れるわけもない。
事実、目の前の蒼い槍兵は前の聖杯戦争で自分のサーヴァントであったバーサーカーに一矢も報いる事なく無様に撤退しただけなのだから。
その時と比べて特にステータスに変化もない以上、彼女の余裕も当然の事ではあった。
ただ、マスターの青年が宝具らしき剣を持っていることだけが若干気がかりではあったが。
「そんなに死にたいなら相手をしてあげるわ。ランサー、やれる?」
イリヤスフィールの声に応えて彼女のランサー、本多忠勝が実体化する。
霊核に負った損傷は完全には癒えていないが、先ほどの汚名を返上せんとばかりに意気軒高であった。
ちなみに、忠勝の姿を見た悠が「…ガ○ダム?」と呟いたが、幸か不幸か聞いている者はいなかった。
ともあれ、ここにこの聖杯戦争で初となる同クラス同士のサーヴァントによる戦闘が実現した。
戦闘はクー・フーリンの先制から始まった。
神速の踏み込みから放たれた刺突は、下手なハンマーよりもなお重い一撃だったが、忠勝の装甲はそれを難なく弾き返す。
そしてお返しとばかりに機巧槍によるカウンターを見舞う。
獣の如き瞬発力でその反撃を躱したクー・フーリンだったが、次の瞬間、魔力による衝撃波に襲われ大きく吹き飛ばされる。
しかし、咄嗟に槍を構えて防御姿勢を取った事でダメージを最小限に抑えた。
「チッ、固いっていうレベルじゃねえな、こりゃ。大方前のバーサーカーと同じタイプの宝具なんだろうが…。そこにセイバー並みの魔力放出とはな」
舌打ちしながらも再度攻撃を仕掛けるが、その直前、忠勝の背中から小型の兵器と思しき物体が数基飛び出し、クー・フーリンを襲う。
これこそが忠勝の変化スキルを用いた武装のひとつ、援護形態。対象を追尾し続けるビット射撃により、自身の攻撃の隙をカバーすることができる。
だが、クー・フーリンは最小限の動きだけでビットを的確に躱し、忠勝と打ち合う。
またも弾かれる結果に終わったが、ビットの追撃も意に介さずあっさりと後退してのける。
この一連の動きから、敵が自分と同じ矢よけの加護を有している事を悟った忠勝は、ならばと攻撃形態に切り替え、連装プラズマ砲で相手のマスター諸共吹き飛ばす手段に出る。
面制圧能力の高い射撃であれば、矢よけの加護も意味を為さない。
「調子に乗るな、たわけ!」
咄嗟に張ったルーンにより、戦車砲すら凌ぐ威力を持つプラズマ砲は呆気なくかき消される。
原初18のルーンを修めたクー・フーリンのルーンによる防御は上級宝具すらも防ぎきる性能を持つのだ。
「へえ、思ったよりはやるのね。でも、貴方じゃ私のランサーには傷一つつけられないわよ?もっとも、シロウを狙う以上逃がしてあげる気もないけど」
「………」
余裕のあるイリヤスフィールとは裏腹に忠勝の内心には焦りがあった。
ステータスでも武装の数でもマスターの魔力量でも圧倒しているにも関わらず、ただの一度も有効打を与えられていないのだ。
無論、忠勝は手を抜いてなどいない。全ての攻撃を必殺の意気で放っている。
なのに穿てない。なのに捉えられない。それでいて底が見えない。
少なくとも純粋な技量においては先ほどの仮面ライダーと名乗ったサーヴァントよりも数段上と見ていいだろう。
これまで以上に気合いを込めて槍を構えたその時、マスターの青年から魔力の高まりを感じた。
「ペルソナ」
呪文のような言葉とともに実体化した黒い戦士がクー・フーリンに魔術らしきものをかけた。
同時に、クー・フーリンは自身の全身と得物である朱槍にルーンを刻んでいく。
「―――え?」
イリヤスフィールの口から驚愕が漏れる。
弱敵と侮っていた槍兵から感じられる威圧感は今や彼女の以前のサーヴァント、ヘラクレスにも匹敵するほどのものになっていた。それを証明するように、ステータスも大きく変化した。
【筋力】A+ 【耐久】A+ 【敏捷】A 【魔力】A+ 【幸運】E 【宝具】A
「何よ……それ」
力なく呟くイリヤスフィールの声が虚しく空に消える。
これが前回の聖杯戦争では使われなかったクー・フーリンの奥の手、原初のルーン。
全身にルーン文字を刻むことによって、敏捷と幸運以外のステータスを大きく引き上げる規格外の魔術である。
更にイザナギの補助スキル“マハタルカジャ”と“マハラクカジャ”による支援と宝具そのものにもルーンを刻む事によって、今回の聖杯戦争で現界した全サーヴァントでもトップクラスの能力値に変貌し、一時的にだが限りなく生前に近い力を振るえるようになった。
「真名が割れてるなら出し惜しみをする必要もない。さて、第2ラウンドといこうぜ」
獰猛な笑みを浮かべ、肩慣らしとばかりに朱槍を振り回し、下段に構え直してから、イリヤスフィールと忠勝にとっての死刑宣告を口にした。
「赤枝の騎士団、クー・フーリン。―――推して参る」
先制は、またしてもクー・フーリンからだった。
「砕け―――」
先ほどまでよりも遥かに力強い踏み込みで飛び込むクー・フーリンに、忠勝はすぐさま防御形態を発動し、両腕に盾を装備して攻撃に備える。
カウンターなど考えていては、自分が死ぬだけだと理解していたが故の行動だった。
「―――中つ槍!!!」
だが、そんな備えは真価を発揮した光の御子の前では全くの無意味だった。
クー・フーリンの乾坤一擲の剛槍はガードした忠勝の右腕を盾ごと貫通した。
忠勝の宝具“鉄壁たる鋼の武将(けっしてきずつかぬぶしょう)”の性質はダメージの軽減ではなく、あくまでAランクまでのダメージを無効化するというもの。
逆に言えば、それを超えるダメージは(本人の重装甲があるとはいえ)一切軽減できずにそのまま受けるというマイナスの側面もあるのだ。
そして、忠勝の宝具はランクA+の筋力とランクAに引き上げられた宝具を持つ今のクー・フーリンに対しては必殺技どころか通常攻撃にも耐えられない程度の効果しか発揮できなかった。
「ラ、ランサー!!」
「…………!!」
悲痛な声をあげるイリヤスフィールから悲しみを取り除かんと、忠勝は機巧槍を左手に持ち替え全身全霊の薙ぎ払いを見舞う。
「遅えよ、間抜け」
しかし現実は非情であった。
クー・フーリンはすぐさま忠勝の右腕に刺した朱槍を引き抜くと、忠勝の渾身の反撃を事も無げに受け止めた。
無論、そんな事をすれば忠勝の魔力放出の直撃を被ることになるが、それすらも“マハラクカジャ”と全身のルーンにより防御力の跳ね上がった今のクー・フーリンには全く通用せず、完全に打ち消されてしまった。
「そら、貴様も英雄ならこの程度凌いでみせろ―――!!」
無防備に近い状態になった忠勝を瀑布の如き怒涛の連撃が襲う。
どうにか対応しようとはするが、右腕を損傷した状態では十全に防ぎきれず、たった数秒の間に全身を穴あきチーズのように穿たれる。
左腕の盾も文字通りあっという間に破砕された。
「そんな、何で……!?」
イリヤスフィールが理解できないのも無理はない。
数値上においてはクー・フーリンと忠勝の敏捷値には1ランク程度の差しかない。額面通りに受け取るならば、こうまで忠勝が一方的に攻撃を受けるのは有り得ない。
しかしイリヤスフィールは知らなかった。
サーヴァントの敏捷値とは、機動力と反応速度の総合値で判定されるのだ。
例えば剣豪・佐々木小次郎の場合は機動力よりも反応速度に寄った状態でのランクA+、クー・フーリンは二つを均等にした状態でのランクA、そして本多忠勝は機動力に大きく偏ったランクB。
実際のところ、忠勝のクロスレンジにおける反応速度と運動性は並みのサーヴァントと大差ないレベルしかない。
重量級の武器による戦闘スタイルも相まって、自らの宝具が通用しない相手に懐に入られると、途端に脆弱さを曝け出してしまうのだ。
「何だ、蓋を開けてみりゃ宝具頼みの木偶の坊かよ。本気を出して損したぜ。生前、自分より強い相手と戦った事なかっただろ、お前」
失望したといわんばかりの態度を隠しもしないクー・フーリンに対して、忠勝は最早立っているのもやっとという有様だった。
戦闘続行のスキルが無ければ今頃既に倒れ伏していただろう。そして、クー・フーリンは未だ宝具すら使っていないのだ。
結局のところ、英霊としての格においてクー・フーリンと本多忠勝には隔絶した開きが存在していた。
確かに忠勝は戦国最強の名に恥じない、サーヴァント全体でも平均以上の実力を持つ猛者だったが、その最強という称号もあくまで神秘が薄れ、幻獣や外敵の危機に晒されることのない島国の中でしか通用しないものだった。
加えて、生まれついての絶対強者だった彼は自身と比肩しうる者と戦った経験に乏しく、事実、彼は心眼・真に代表される不利な状況を打開する技能を全くといっていいほど有していなかった。
対して、クー・フーリンはその逸話の中で自身よりも速い者、自身よりも強い者、自身よりも知略に秀でた者と何度も戦ってきた。
彼は最初から強かったわけではなかったが、それでも研鑽を重ね、生きて帰るための準備を整え、時には文字通り血反吐を吐きながら強大な敵に立ち向かっていった。なにより彼自身、強敵との死力を尽くした戦いを望む、飽くなき向上心を持っていた。
敵が理不尽な能力を備えていることも、クー・フーリンにとっては予想外でもなんでもない、ただの日常で大前提でしかない。
そうした生き様の違いが勝敗を分かつ決定的な要因になった。
忠勝が善戦できていたのはお互いの知名度による補正の差とイリヤスフィールの高いマスター適性あったればこそ。その優位性が立ち消えになった今、こうなるのは必然であった。
「正直興醒めもいいところだが、またどこかから横槍を入れられるのも癪なんでな。
じゃあな。その心臓、貰い受ける―――!」
確実にとどめを刺すべく己の朱槍に魔力を込め、必殺の一撃、即ち宝具を使用する準備を整える。
通常なら忠勝の宝具に弾かれるだけだが、今のクー・フーリンの朱槍はルーンの付与によりランクアップしている。
そこから放たれる真名解放の一撃は、忠勝のいかなる防御をも貫くだろう。
そして、忠勝には魔槍の因果逆転の呪いを跳ね返す幸運もない。否、あったとしても動きの鈍重な忠勝ではまず回避できない。
「……駄目」
それが理解できる、いや、理解できてしまうからこそ、イリヤスフィールは頬を伝う涙を止めることができなかった。
だが、ひとつだけ定められた死の運命を覆す手段があった。
「―――刺し穿つ死棘の槍(ゲイ・ボルク)!!!」
クー・フーリンの魔槍が迫る。禍々しい程の魔力をもって放たれた攻撃は、間もなく忠勝の心臓を貫くだろう。
「死なないで、ランサアアアアアーーーー!!!」
イリヤスフィールの左手から令呪が一画消える。
死ぬなという絶対の命令を受けたランサーは、それまでからは考えられない速度でガッチリと心臓をガードする。必ず心臓を貫くとわかっているのならば、そこを守り通す。
魔槍がガードした忠勝の機巧槍を砕き、真っ二つにする。ならば自身の腕で防ぐのみ。
令呪によって生じた魔力と魔槍が轟音を上げて拮抗する。数秒の拮抗の後、魔槍が忠勝の左腕を貫通し、そのまま身体に浅く突き刺さり、そこで止まった。
鋼の英雄は、大英雄の因果逆転の魔槍を前に見事命脈を繋いでみせたのだ。
「令呪があったとはいえ、よく凌いだ―――」
クー・フーリンから贈られる惜しみない賞賛。
「―――と言いたいところだが、詰んだぜ、お前」
そして、死。
とうの昔に“チャージ”を仕込み終え、湖の騎士から奪い取った漆黒の聖剣を持ったイザナギがクー・フーリンの後ろから姿を現し、忠勝の首を斬り飛ばした。
それは、激突する英雄たちに比べて余りにも矮小な存在だった。
だがそれ故に、忠勝はその存在を無意識のうちに忘れてしまっていた。
「最後に一つだけ忠告しておいてやる。お前らはうちのマスターをナメすぎだ」
聖杯戦争とは何もサーヴァントだけの戦いではない。
英霊に比べれば卑小な存在であっても、マスターもまた戦場に確かに存在し、場合によっては英霊にも届く攻撃手段を持つ者もいるのだから。
&COLOR(#FF2000){【ランサー(本多忠勝)@戦国BASARA 消滅】}
「ラ、ランサー……」
サーヴァントを失ったイリヤスフィールがその場にへたり込む。
彼女にとって忠勝はただのサーヴァントではなく、自分に愛情をもって接してくれる心許せる存在だった。
茫然自失としていたが、その時間はすぐに終わりを告げた。
「―――かっ、ぁ……!?」
サーヴァント消滅による電脳死を待つまでもなく、蒼い槍兵の朱槍で心臓を貫かれたからだ。
それはあまりに迅速で、痛みを感じる暇さえ与えられなかった。
「ムーンセルに削除されるまでのたうちまわらせるのは趣味じゃねえ。せめて苦しまずに逝ってくれや」
「ぁ…し、ろ……」
胸からドクドクと血が溢れ、力が抜けていく。
消えゆく意識の中、最期に聞こえたのは自分を呼ぶひどく懐かしい声だった。
&COLOR(#FF2000){【イリヤスフィール・フォン・アインツベルン@Fate/stay night 死亡】}
衛宮士郎とセイバーがその場所に到着した時には、全てが手遅れだった。
「よう、坊主にセイバーじゃねえか。やっぱりお前らも参加してたか。
俺の勘も捨てたもんじゃあなかったらしいな」
見覚えのある槍兵が街角で偶然友人に会ったかのように気安く声を掛けてくる。
もし状況が違えばあるいは士郎も多少は友好的な返事を返したかもしれない。
少なくとも、ランサーが自分の義姉であるイリヤスフィールの心臓に朱槍を突き刺しているという状況下でなければ。
「イリヤぁッ!!」
手遅れと知りながらも、心臓から槍が引き抜かれ、血の海に沈んだイリヤスフィールに駆け寄った。
だが士郎の手が彼女の遺体に触れる寸前、イリヤスフィールの身体は流れ出た血液ごと粒子となって消え去った。
「なっ……!?」
魔術でもこうはならないであろう、と思われる光景に思わず固まってしまう。
ショックから立ち直れない士郎に、ランサーが訝しげに話し掛けてくる。
「何だ、知らなかったのか坊主?こっちの聖杯戦争じゃ敗者は皆ムーンセルにきれいさっぱり消される事になってるんだとよ。まあ俺も見るのは初めてなわけだが」
「ラン、サー……!!」
イリヤスフィールを殺しておきながら悪びれもしないランサーに視線だけで人間を殺せそうなほどの怒りと殺意を剥き出しにする。
だが、ランサーがその程度のことで怯むわけもなく、むしろ呆れた風ですらあった。
「がなるなよ、坊主。戦争で顔見知りが死ぬなんざ当たり前のことだろうが」
「………っ!!」
歯軋りし、今にも双剣を投影してランサーに斬りかからんとする士郎を傍らのセイバーが諌めた。
「シロウ、気持ちはわかりますがどうか落ち着いて下さい。それに、彼らが下したのはイリヤスフィールのサーヴァントだけではないようだ」
そう言って、忠勝を斬ったと同時に実体化を解いたイザナギから再度受け取った聖剣を持つ悠を睨みつける。
「魔術師(メイガス)、その剣をどこで手に入れた」
その剣は、セイバーにとって見覚えのありすぎるものだった。
名を“無毀なる湖光(アロンダイト)”。彼女の右腕だった騎士、ランスロットが所有していた宝具である。セイバーの鋭い眼光に臆した風もなく、銀髪の青年は「拾った」とだけ答えた。
何とも掴みどころのないマスターだとセイバーは思ったが、今わかっているのは前々回と同じくランスロットがサーヴァントとして現界している事、そしていかなる手段を使ったか目の前のランサー主従がランスロットを下して彼の宝具を奪取した事(宝具が残っているところを見るに倒されたわけではないようだ)、そして今イリヤスフィールのサーヴァントを大した消耗もなく撃破したという事だけだ。
言葉にすればそれだけだが、それがどれほどの困難か二度に渡って聖杯戦争を経験したセイバーは嫌というほど熟知していた。
その証左に、ランサーから感じられる圧力は前回対峙した時とは比べものにならないほどだ。
あれが彼の全力だったとはセイバーも思っていなかったが、それでも別人と見紛うほどだ。
あるいは、あの神父の事だから何らかの制約をランサーに課していたのかもしれない。
「実を言えば少しばかり消化不良気味だったんでな。
折角だ、ここで決着着けようじゃねえか、セイバー」
朱槍を下段に構え戦闘態勢をとったランサーに、セイバーもまた不可視の剣を取り出し応戦の構えを見せる。
もとより敏捷性においてはランサーが上。まず逃がしてはくれないだろう。
「頼む、セイバー。…イリヤの仇を、取ってくれ」
悔しげな士郎の言葉に無言で頷く。本当なら士郎自身が仇を討ちたいが、サーヴァントであるランサーに人間である士郎が挑むのは無謀の極みだ。
だからこそ、セイバーに全てを託すしかない。
「ペルソナ」
悠もまた、イザナギを呼び出し既に効果の切れていた補助スキルをかけ直す。
その最中、悠は赤髪の青年と先ほど殺した白い少女に何故か自身と菜々子の影を見出していた。
いや、事実自分はあの青年から自分にとっての菜々子を奪ったのだ。
その罪を噛み締めながらも、それでも歩みを止めないと誓う。
自分にも譲れない願いがある。ランサーもこんな自分に力を貸してくれている。
何より、直接殺したわけではないとはいえ既に自分は四人、いや、先ほどの主従を加えれば六人もの生命と願いを踏み躙ってここにいる。
もう後戻りなどできないし、してはならない。
「さあ、行こうか」
踏み躙った生命を無駄にしないためにも、必ず最後まで勝ち抜いてみせる。
戦いの第二幕が開けた。
to be Continued……
----
|NEXT|
|[[FINAL DEAD LANCER(後編)]]|
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: