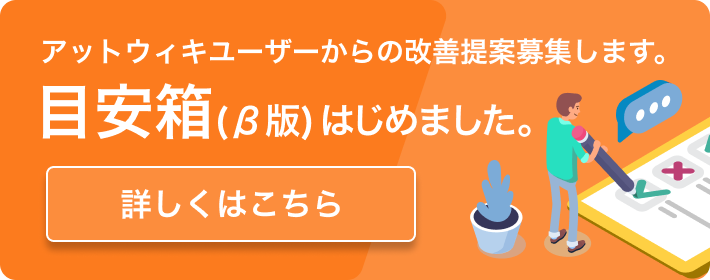「ズッコケ二人組と一匹~聖杯戦争から脱出せよ~」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「ズッコケ二人組と一匹~聖杯戦争から脱出せよ~」(2012/10/15 (月) 20:42:42) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
*ズッコケ二人組と一匹~聖杯戦争から脱出せよ~
「なあライダー、こんなとこに何があるんだよ?」
「まあ慌てるでない、ついてくればわかる」
少年探偵・金田一一とそのサーヴァント・ライダー。
二人は自己紹介を済ませた後、最初に降り立った柳洞寺の境内を調べに………行くことはせず、山門の横の茂みの中を歩いていた。
運動が得意ではない金田一だが、その足取りは決して重くはない。
普段から旅行などで山道を歩く機会が多く、身体が慣れてしまっているからである。(もっとも、その旅先で毎度のように殺人事件に巻き込まれるのだが)
「ふむ、ここらでよかろう」
ある程度開けた場所に出たところで、ライダーは立ち止まった。
しかし、金田一から見て、何か特筆すべきものがあるようには見えない。
「ここったって……別に何もないぜ?」
「いやいや、何もない場所だから良いのだ。今からすることを考えればな」
そう言って、ライダーは懐から白い教鞭のようなものを取り出した。
先端に陰陽のマークのような球体が付いているのが印象的だった。
そして、ライダーは咳払いをしてから、真剣な表情で語り始めた。
「金田一、おぬしは知略を駆使して戦うタイプの人間だ。
しかし、それを生かすには適切な情報が必要不可欠。
故に、まずは知らねばならん。
おぬしが巻き込まれた、この聖杯戦争の知識をな」
「………ああ」
確かにライダーの言う通りだ。
殺し合いを止めようにも、そのために必要な情報を理解していなければ立ち行かない。
金田一もまた、気持ちを切り替えて真剣にライダーの説明を聞き始めた。
「まずは目を閉じて、意識を集中するのだ。
おぬしにとって最もイメージしやすい形でわしのサーヴァントとしてのステータスが見えてくるはずだ」
言われた通り、目を閉じると、ライダーの能力らしきものが浮かんできた。
【クラス】ライダー
【マスター】金田一一
【真名】太公望
【性別】男性
【身長・体重】不明
【属性】中立・善
【筋力】D 【耐久】D 【敏捷】C 【魔力】B+ 【幸運】A+ 【宝具】??
どうやらライダーは身体能力で少々劣るサーヴァントらしい。(その代わり魔力や幸運は優れているようだが)
「今は最低限の情報しか見えぬであろうが、いずれは全ての情報が開示されるはずだ。
それと、目視さえすれば他のサーヴァントの情報も分かるようになっておる。
常にチェックしておくのだぞ」
「ああ、わかった。ところで、宝具ってのがステータスに載ってたんだけど、宝具って何なんだ?」
素直に疑問を口にする。
名前の響きからして、重要そうな部分だとは思うのだが、ライダーのそれは今の金田一にはまだ読み取れなかった。
「うむ、宝具とは、サーヴァントにとってのシンボルであり、半身のようなものだ。
宝具の種類にも色々あるが、まあ今は必殺技のようなものだと思っておけば良い」
そして、ライダーは先ほどの教鞭のようなものをこれみよがしに掲げた。
「例えば、わしの宝具のうちのひとつがこの打神鞭だ。
これは、大気を自在に操る宝具だ、ほれ、このようにな」
「うわっ!?」
ライダーが打神鞭を振ると、金田一とライダーの間に猛烈な風が発生した。
それは金田一にも目視できるほど濃密な風のうねりであり、その勢いに思わず尻餅をついてしまった。
「す、凄いんだな、宝具って………」
「何を言っておるのだ、今のはわしにとってはほんのそよ風に過ぎん。
本気で撃てば、この山など軽く吹き飛ぶぞ」
しれっととんでもない事を口にするライダーに、金田一は頬が引き攣るのを止められなかった。
そんな彼を他所に、ライダーは手近かな地面に向かって打神鞭を振りかぶっていた。
その顔には邪悪な笑みが浮かんでいる。
嫌な予感しかしない。
その予感は果たして的中し、ライダーは打神鞭を振り下ろし、掘削機の要領で地面に穴を掘り始めた。
「わーっはっはっはっはっはっは!!」
「ちょ、ここって私有地じゃ……」
「はーっはっはっはっはっは!!」
「いや、だからやめ……」
「はーっはっはっはっはっはっは!!」
金田一の制止など気にも留めず、ライダーは不気味な高笑いを上げながら地面を掘り進めていく。
そして、数メートルほど掘り進めたところで、満足したのか手を止めた。
こんな穴を作ってどうするつもりなのか、金田一には見当もつかない。
「どうすんだよ、こんな事して。
寺の人に怒られるんじゃあ………」
「固いことを言うでない。
それより、ここからが本番だ。
この打神鞭に付いたスイッチを…ポチっとな」
そう言うや否や、打神鞭から旗のようなものが飛び出した。
「これぞわしの第2の宝具、杏黄旗だ!」
ライダーは非常に誇らしげだ。
旗が飛び出た時キコキコキコーンという謎の擬音が聞こえたような気がしたが、多分気のせいだろう。
ステータス欄が更新されたことから、残念なことにこれは本当に宝具らしい。
「な、何だその目は!
これは戦略上とても重要な宝具なのだぞ!」
金田一の可哀想な人を見るような視線に耐えかねたのか、ライダーが声を張り上げた。
「いや、でもそれ………旗だろ?」
「ただの旗ではない!この布は魔力の受信機のようなものだ。
本来はこういう使い方をするものではないが、まあ聖杯戦争に合わせた仕様変更というやつだ。
この布を半分ほど破って……今掘った穴にポイっとな」
そう言って半分に破った杏黄旗の布を穴に投げ入れると、ライダーは何やら呪文のようなものを唱え始めた。
その顔は真剣そのものであり、決してただのお遊びではないことを伺わせる。
数十秒後、詠唱を終えたライダーは金田一の方に向き直った。
「実は、今わしらがいるこの円蔵山は、自然の魔力が集まる霊脈と呼ばれる場所なのだ。
わしの杏黄旗は、そういった土地に敷設することで、本体である打神鞭に魔力を供給する仕組みになっておる。
わざわざ獣道を通ってここに設置したのも、馬鹿正直に敷地の真ん中に埋めては戦闘の余波で破壊されてしまう可能性が高かったからだ」
「そうだったのか………。
でもこの穴、どうすんだ?そのままってわけにもいかないだろ?」
「うむ、それについてもわしにいい考えがある。
というわけで、カモーン!スープー!」
ライダーが天に向かって指をパチンと鳴らすと、煙とともに何かが現れた。
それは不思議な生き物だった。
ティーカップの皿のように大きくつぶらな瞳、ふわりとしたたてがみ、頭に生えた二本の角。
全体的に丸みを帯びたシルエットは、金田一に昔幼馴染と共に見たとあるアニメを想起させた。
「こやつがわしの霊獣にして相棒の四不象だ。
わしがライダーのクラスで現界している所以でもある」
「す、すっげえ……!」
金田一は目を輝かせながら四不象に見入っていた。
生前はその外見から侮られることが多かっただけに、四不象はとても誇らしげな表情、いわゆるドヤ顔状態になっていた。
「空飛ぶ白いカバだ!」
その場の空気が凍りついた。
普段なら四不象がカバ呼ばわりされてもニヤニヤしながら見守るだけのライダーも、金田一のあまりの悪気のなさに
流石に気まずくなり、フォローを入れようとする。
しかし、遅かった。金田一は四不象にアイルランドの光の御子が愛用する因果逆転の魔槍の如き威力の
言葉の暴力を(本人に全く悪気は無いが)次々に浴びせていく。
「うっわぁ~、本当にすげえ!ムー○ンみてえ!
そういや美雪があれのぬいぐるみ持ってたよな~。
あ、お手」
「あ、いや、金田一。そやつは……」
四不象はすでに俯いてプルプルと震えているのだが、金田一は全く気がついていない。
そして……
「ボ、ボクはカバじゃないっスーーーーーー!!!!」
「お手」の部分にキレたのか、ついに四不象が爆発した。
しかし、金田一の反応は非情なものだった。
「うわっ!?カバが喋った!?」
さらに(悪気は無いが)追い討ちをかける金田一。
よほど驚いたらしく、腰を抜かしている。
「だからカバじゃないっスよ!召喚直後にこの言葉責めはあんまりっスよ!」
「う、うむ。こやつは見た目はまあアレだがれっきとした霊獣なのだ。
というかおぬし、もう少しデリカシーというものを身に付けた方が良いぞ」
すかさずフォローを入れるライダー。
主人の援護に四不象もようやく怒りを鎮めた。
「ところで御主人、ボクを呼び出したってことは敵が現れたってことっスか!?
ボクの活躍の場面っスか!?」
度重なるカバ呼ばわりがまだ尾を引いているのか、四不象は何とかして自分の勇姿を金田一に見せつけたいようである。
「うむ、おぬしはこれからわしらと一緒にこの穴を埋める作業をするのだ」
「了解(ラジャー)っス!金田一くん、ボクの勇姿を…………って、え?
御主人、今何て言ったっスか?」
「だから、わしらと一緒に穴を埋める手伝いをしろと言ったのだ」
四不象はショックで再び凍りついた。
召喚されてからいきなりのダブルパンチで、四不象のライフはもうゼロである。
「ボクの聖杯戦争の初仕事が後片付けっスか!?
ひどいっスよ御主人!こんなの絶対おかしいっスよ!?」
「っていうかこれ、俺もやるのかよ!?」
「ええい、やかましい!ちょっと掘りすぎてしまって人手が足りんのだ!
わしらは一心同体一連托生!さっさと片付けるぞ!」
とまあ、このように漫才を繰り広げながら杏黄旗敷設のために掘った穴を埋める作業に勤しむ二人と一匹であった。
「つ、疲れた………。
んでもって、何だよこの長い階段……」
「頑張るっスよ金田一くん。
でも、もうちょっと体力つけた方が良いっスよ」
二人と一匹で穴を埋めた(ただし、ライダーは寺の偵察と称して途中で抜けた)後、金田一と四不象は長い階段を通って柳洞寺の境内に入ろうとしていた。
元々体力のある方ではない金田一にとってはかなりの重労働だったらしく、その表情には疲労の色が濃い。
「とにかく、中に入って一休みするっスよ。
御主人も先に中にいるはずっスから」
「でも、良いのかな。
勝手に入ったら警察呼ばれるんじゃ…………ん?」
「?どうしたっスか?金田一くん」
警察という単語を口にした途端、金田一の表情が一変した。
それは、忘れていた重要な事を思い出した時のような表情だった。
「そうだよ!警察だよ!!
早く警察に通報すれば良かったんだ!!
悪い四不象、ちょっくら電話借りてくる!」
「えっ?ちょ、金田一くん、それは……」
言うが早いか、金田一は寺に向かって駆け出した。
そのスピードたるや、先ほどまでの疲労を全く感じさせないほどの速さだった。
「すいませーん!少し電話貸してくださーい!」
誰もいないのをいいことに、寺の母屋に駆け込んだ金田一は、電話を探して駆け回る。
「どうしたのだ金田一、そんなに慌てて。
電話がどうのと言っていたようだが……」
「あ、ライダー!ちょっと警察に電話してくる!
あと、寺の人がいたら謝っといてくれ!」
廊下から姿を現したライダーを見つけるや、早口で用件を伝えてその場を立ち去ろうとする金田一。
そんな彼を、ライダーが腕を掴んで引き止めた。
「ちょっと待て金田一!警察に電話すると言っても……」
「何だよ!そりゃ普通の警官じゃサーヴァントには勝てないかもしれないけど、それでもこんな状況なんだ!
警察がいるといないとじゃ全然違うはずだ!
大丈夫だって!剣持のオッサンや明智さんなら聖杯戦争のことだって信じてくれる!」
「いや、そういう問題ではなく……」
「考えてみりゃおかしかったんだ!さっきの山だって人がいない獣道のわりに落ち葉がよけたような痕跡があった。
多分、ここはつい最近まで生活してた人たちを無理矢理立ち退かせて用意した会場なんだ!
普通なら考えられないけど、それこそサーヴァントみたいな力を使えば不可能じゃないのかもしれない。
つまり俺たちが今するべきことは、何とかして外に助けを求めることだったんだよ!」
早口で自らの推理を捲し立てる金田一に対して、徐々に脱力していくライダー。
そんなライダーを振り切り、金田一は電話を見つけ出し、警察に電話をかけた。
「あっ、もしもし警察ですか!?本庁の剣持警部か明智警視につないで下さい!
変な神父が殺し合いをしろって言ってるんですよ!」
なるべくサーヴァントのことは伏せて説明を試みる。
しかし………
「ああ、聖杯戦争の事ですか?
申し訳ありませんが、当方では聖杯戦争に関する一切の質問・要望等を受け付けておりません。
聖杯戦争の知識をお求めでしたら、月海原学園図書室をご利用下さい」
「はい!?ちょ、ちょっとあんた、何でその事を……って、あっ、ちょっと!?」
不気味ほど事務的な対応を取られた末に一方的に切られてしまった。
間違い電話をかけてしまったのかとも思ったがそんなこともない。
もしや聖杯戦争の魔手は警察にまで及んでいるのだろうか?
「……いや、まだだ。警察が駄目なら他の人に頼めばいい!
えーっと、いつきさんに佐木に針生さんに結城先生に黒沢オーナー、後は……心配かけちまうけど、美雪やお袋に玲香ちゃん、他には――――――」
思いつく限りの知り合いの名前を列挙し、電話をかけようとする。
そんな金田一の肩を、脱力しきった様子のライダーが叩く。
「……金田一、おぬしの言いたいことは分かった。
分かったから、ちょっとこっちに来てわしの話を聞いてくれ」
「?ああ、わかった」
妙に疲れた様子のライダーを不思議に思いながらも金田一はライダーの話を聞くことにした。
「はぁ!?ここがバーチャル空間だって!?」
「そうだ。ついでに言えば、そもそも地球ですらない。
月に存在する巨大な演算装置にして観測装置、ムーンセル・オートマトン。
その中に展開された電脳空間こそが、この聖杯戦争の会場の正体だ。
おぬしの言う妙な神父も、進行役として選出されたNPCであろう」
場所は変わって柳洞寺の本堂。
そこで金田一はライダーから今回の聖杯戦争の舞台、ムーンセルについての説明を受けていた。
ちなみに、いつの間に用意したのか、ライダーは本堂の中に自分のコーナーを作っており、さらに山のように茶菓子を置いていた。
ライダー曰く「このような大きな寺院にはそれ相応の人数の檀家がいるはず。となれば、そういった者たちをもてなすために、常に茶請けの類を母屋の台所に用意していると睨んでいた」との事。
閑話休題。
数多くの事件やトリックを解明し、今回に至ってはサーヴァントなどという超常現象に遭遇した金田一だが、流石に今、自らが五感で感じている現実をバーチャルなどと言われて素直に信じることはできなかった。
「………そんな話を信じろっていうのかよ。
大体、月にそんなすごいものがあるんだったら、ニュースになってないはずがないじゃないか。そんな話、聞いたこともないぜ?」
「それは、おぬしがムーンセルの存在しない平行世界から呼ばれたからであろう。
聖杯の力を“使えば”不可能なことでもあるまい。
というかおぬし、わしやスープーのことはあっさり信じたではないか」
「だってライダーも四不象も俺の目の前にいるじゃないか。
実際に目にしたことまで疑ってたらきりがないだろ。
少なくとも、ムーンセルだの並行世界だのよりはまだ信じられるよ」
金田一とて超常現象の類を一切合財否定するほど頑固でも狭量でもない。
聖杯戦争にしても、現実的な殺し合いや、今や日常茶飯事といっても過言ではないほどの頻度で遭遇する殺人事件に置き換えればどうにか理解できる事ではある。
しかし、ムーンセルや平行世界といった話は、金田一の想像力の範疇を大きく越えていた。
一言で言えば、話の規模が大きすぎてピンとこないのである。
「それに、その話を全部信じるにしたってまだおかしい事があるぜ。
そのムーンセルが観測装置だっていうのなら、どうして殺し合いをさせて願いを叶えるなんて話になるんだ?
最後まで生き残った者が願いを叶えられるっていうのも一体どんな基準で決めたんだよ?」
金田一の疑問に対し、ライダーはやや満足そうに頷きながら答えた。
「いい質問だ、金田一。
そもそもムーンセルとは、太古の昔から地球上のあらゆる記録を観測するために存在してきた。
過去にもムーンセルが記録活動の一環として人間を招き、殺し合わせた実例もあるが、並行世界の人間までもを呼び寄せて聖杯戦争を開いたという記録は無い。
少なくとも、聖杯からわしに与えられた知識にそのような記録が無いことは事実だ。
では、何故この聖杯戦争が起こったのか。
金田一よ、多くの事件を解決してきたおぬしならわかるのではないか?」
試すようなライダーの言動に、金田一は少々困惑しながらも思考を巡らせる。
ライダーは何故か“多くの事件を解決してきた”という部分を強調して言った。
だとすれば、自分が今まで関わった事件にヒントがあるという事だろうか?
(でも、俺が関わった事件なんてそれこそ思い出してたらきりがないぐらい多いんだよな。
なら、少しでもこの聖杯戦争に近い性質を持った事件……。
そこに鍵があるのかもしれない)
そう考えて思い出すのは、かつてバルト城で起こった、ミステリーナイトツアーという名目で行われた連続殺人事件。
やや乱暴な考え方だが、催し物を装って誰かを招き、人を殺し、自らは目立つ主催者の影に隠れるという点では聖杯戦争と共通していると言えなくもない。
そしてこの事件を聖杯戦争が起こった理由と関連付けて考えた時、金田一の脳裏に一つの仮説が浮かんだ。
「まさか……この聖杯戦争も、誰かが仕組んだものなのか?」
「うむ、少なくともわしはそう睨んでおる。
さっきも言ったが、ムーンセルは、この世界の地球上の記録を観測することしかせぬ。
並行世界の人間を観測するのは、その本義から外れたことだ」
「でも、最近になってそっちの方も記録するようになったって可能性もあるんじゃないか?」
「では聞くが金田一よ、並行世界というものは一体いくつあると思う?
例えば、もしおぬしが今の疑問を思いつかなかったら。
警察に電話することを思いつかなかったら。
もっと言えば、昨日の昼食の内容が変わっていたら。
そういった僅かな変化から生まれた分岐が、一つ一つの並行世界になると考えた場合でだ」
あまりに無茶なライダーの質問に、さしもの金田一も閉口する。
「そんなの、数え切れるわけないだろ。
むしろ、数えるだけ無駄じゃないか、そんなの」
抗議のつもりで言った言葉に、ライダーはむしろ我が意を得たりといった表情で答えた。
「その通り。数えるだけ無駄だ。
だからこそ意味が無いのだ。
如何にムーンセルが膨大な記憶容量を誇るといっても、それは単一の世界を基準とした場合だ。
無限の並行世界の地球の観測までしていては、すぐにオーバーロードを起こして自壊するのは自明の理。
つまり、ムーンセルの本来の目的から言えば、並行世界の扉を開き、人を招くこと自体が非合理的な無駄の極みなのだ」
「だから人間が仕組んだ、って事になるのか……。
ってちょっと待てよ、だとしたら、順序が逆になる……!
ライダー、お前さっき聖杯の力を使えば並行世界の人間でも呼べる、みたいなこと言ったよな?
だったら、願いを叶える人間を決めるために殺し合いをさせるんじゃなく、既に聖杯を手にして願いを叶えた人間が俺たちに殺し合いをさせてるってことになるんじゃないのか!?」
自ら思いついた仮説に青ざめる金田一。
もしこの考えが事実なら、自分たちが何をしても殺し合いを打破することなど不可能、という事になりかねない。
何しろ相手は既に聖杯を手に入れた人間だ。
少しでも殺し合いに反抗した者を消すなど造作もないだろう。
「いや、厳密には少し違うであろう。
本当に聖杯を掌握し、願いを叶えたのなら、わざわざ聖杯戦争を起こす理由が無い。
恐らくそやつは、聖杯にある程度干渉することはできても、完全に掌握し、目的を達成するには至っていないのであろう。
つまり、この聖杯戦争は目的達成のための手段として引き起こされた可能性が高い。
願いを叶えるという触れ込みや、バトルロイヤルという形式にしても参加者に疑問を抱かせないようにするための方策であろう。
この調子なら、他にも何か信憑性を高めるための布石を打っているやもしれぬな」
ライダーの返答に少しだけ安堵した。
考えてみれば、こうして自分たちが聖杯戦争の裏について議論することが出来ている時点でこの聖杯戦争の仕掛け人が完全な力を持っているわけではないことは明白だ。
そして、聖杯戦争を開催した理由についても、提示された勝利条件を考えればある程度の推測はできる。
「最後に残った一組みに願いを叶える権利が与えられる……って事は、殺し合いが完遂される事が目的の達成に必要な条件ってことになるよな」
口にするだけで苦い思いがこみ上げてくるが、考えることをやめるわけにはいかない。
金田一が持つ唯一の力が、この推理力なのだから。
「うむ、十中八九そう考えて間違いない。
となれば、わしらの取るべき方針は聖杯戦争の完遂を阻止することに絞られる。
しかし、これだけでは時間稼ぎにしかならぬ」
そこまで言うと、ライダーの表情が悪戯を思いついた子供のそれに変わった。(もっとも、ライダーの外見年齢は中学生ぐらいの子供といっても良いほど若いが)
「故に、わしらはどうにかしてこの会場、冬木市から脱出する必要がある。
そして、優勝以外の方法で聖杯に辿り着き、最終的には聖杯の近くにいるであろう黒幕をやっつけて、わしらで聖杯を独占するのだ。
殺し合いに乗ったマスターも、聖杯を他の参加者に握られては黙らざるを得まい」
あまりに突拍子の無いライダーの提案に、金田一は開いた口が塞がらない。
勿論それが出来ればベストなのだろうが、そう簡単に上手くいくとは思えない。
そんな金田一の表情を読み取ったのか、ライダーが微笑みながら説明を続ける。
「なーに、わしとて根拠も無く言っているわけではない。
如何に舞台がムーンセルといえども、この聖杯戦争自体は人間が考えたものだ。
まして並行世界の人間を招くという無茶までした以上、完璧ということはあるまい。
必ずどこかに隙があるはずだ」
殊更力強く話すライダーに、金田一もまた勇気づけられるのを感じた。
方針は固まった。ここからは行動すべき時だろう。
「よし!そうと決まれば街に出て情報収集だ!
できたら他のマスターにも接触して―――」
「駄目」
「……は?」
唐突に冷や水を浴びせられた。
「わしらは当面、この柳洞寺に籠城する。
幸いここには食糧もあるからな」
「な、何でだよ!?もう準備は十分だろ!?
こうしている間にも殺し合いが起こってるかもしれないのに……!」
「まあ理由はいくつかあるが、一つはおぬしの言う他のマスターについてだ。
この聖杯戦争に参加を決めた者の多くは魔術を始めとした何らかの超常的な力を有しておるだろう。
強い力を持ち、自ら望んで殺し合いに参加した者など、精々潰し合ってもらえば良い。
おぬしが気に病むことではない」
これまでとは打って変わったライダーの残酷な言動に、金田一は動揺を隠せなかった。
「でも、だからって死ねば良いなんてことにはならないだろ!
それに、俺みたいに巻き込まれる形で参加させられた奴だっているかもしれない。
誰かが死ぬかもしれないって分かってて、見過ごすなんて出来ねえよ……!」
「金田一」
今までで一番真剣な表情と共に、ライダーが口を開いた。
「おぬしの気持ちは、わしもわかるつもりだ。
だが、今は耐えるのだ。
殺し合いを止めようにも、今のわしらが打てる手はあまりに少ない。
それに、今はここに立て篭る事こそが殺し合いを止めるために打てる最大の一手なのだ」
「……どういう事だよ?」
納得がいかないながらも、続きを促す。
「もう一つの問題は他のサーヴァント、とりわけキャスターだ。
魔術師のクラスに位置付けられておる彼のサーヴァントなら、スキルと魔力量次第でこの冬木市全体への魔術行使すら可能になるであろう。
そして、それに最も適した土地がこの柳洞寺なのだ。
つまり、ここを占拠される事は、魔術への抵抗力を持たぬおぬしや他の一般人のマスターにとっては死活問題になる。
それだけは避けねばならん」
ライダーの語る言葉に嘘は無いことは、その表情から伺い知ることができた。
恐らく、ライダーの言う通りにするのが現状ではベストなのだろう。
一瞬、令呪に訴えることも考えたが、それは徒にライダーとの関係に溝を作る結果にしかならないだろう。
また、本人はあまり自覚していないが、金田一自身、理詰めで物事を判断しやすい性格であることも彼をこの場に留まらせる一因になっていた。
しかし、同時に、諦めることを決してしないことも金田一の持ち味だった。
彼は、無言のままライダーの隣に座ると、茶菓子の包を手に取り、腕を組んで何やら考え事を始めた。
「…?どうした、金田一」
「考えるんだよ。
確かに今、俺はライダーの考えた作戦を上回るようなアイデアを示すことができない。
でも、それは今の話だ。
ライダー、俺は諦めないからな。
誰も死なせない、お前も認めるような方法を必ず考えてみせる」
そう言って、そっぽを向いて茶菓子(薄皮饅頭)を食べ始めた金田一の背中を、ライダーはどこか嬉しそうに見つめていた。
同時に、今後の展望についてもある程度の考えを巡らせていた。
ライダーとて、いつまでも柳洞寺に篭っているつもりはない。
彼は、生前と同じように、殺し合いを打破するための仲間を募るつもりだった。
(戦局が動くとすれば恐らく今から明朝までの間。
その間に戦闘で消耗したマスターとサーヴァントがこの地の霊脈を求めて来る可能性は高い。
そして、その時こそが交渉のチャンスだ)
消耗しているであろう相手と杏黄旗と霊脈によって魔力の充実したライダー。
そして、脱出の可能性と聖杯を山分けするという実利。
これらの条件をカードにして他のマスターと同盟を組み、ある程度数が揃ったら打って出る、というのが彼の戦略だった。
他のマスターが真っ先にこの柳洞寺に乗り込んで来る可能性もあるが、この序盤戦でそのような行動に出るのは十中八九キャスターのマスターだろうとライダーは考えていた。
その場合、戦いは避けられないだろうが、流石に陣地作成スキルの恩恵も受けていないキャスターに敗れるつもりはない。
Bランクの対魔力は伊達ではないのだ。
逆に、キャスターを仲間に加えることが出来れば心強いとも思う。
(殺し合いに乗っていない熟達の魔術師がマスターで、聖杯にかける願いの無いキャスターを従えている、そんな者たちと手を組めれば………はは、我ながらなんと無茶苦茶な)
あまりに虫の良すぎる発想に、思わず苦笑する。
常識的に考えて、そんなマスターとサーヴァントの組み合わせが有り得るはずがない。
(まあ、それはともかく……何故ここにはNPCがいない?
このような僻地にNPCを配置するリソースを割くことをムーンセルが無駄と捉えたか、あるいは霊脈としてのアドバンテージを得られるこの地に魔力炉になるNPCを配置することをある種の不公平と取ったか、あるいはその両方、か?)
例えば、もしも自分たちではなくキャスターが最初にこの地を抑え、更にNPCを魔力炉に利用したならば。
恐るべき早さで工房、あるいは神殿を形成し、序盤から圧倒的な優位に立っていただろう。
ここにNPCがいないことも、ある程度の公平性を期すための措置と考えれば納得できなくはない。
どこか釈然としない気持ちもあるが、いないものはいないのだ。
これに関しては、今は置いておいても構わないだろう。
それよりも、考えるべき問題が山積みなのが現状だ。
ちらりと、考え事をしている金田一の方を見やる。
正義感が強く、危ういところもあるが、サーヴァントとしてだけでなく、太公望という個人としてもこの少年を死なせたくはない。
一方で、金田一ならこの状況を打破する妙案を考えてくれるのではないか、という期待もある。
若き少年探偵の背中に、ライダーは微かな、しかし確かな希望を見出していた。
【柳洞寺・本堂/深夜】
【金田一一@金田一少年の事件簿】
[状態]:健康(残令呪使用回数:3)
※「怪奇サーカスの殺人」開始直前からの参戦です。
【ライダー(太公望)@藤崎竜版封神演義】
[状態]:健康・魔力充実
※杏黄旗により、どこにいても円蔵山から魔力供給が受けられます。
ただし、短時間の内にあまりにも大量の魔力を吸い出した場合、霊脈に異常をきたす可能性があります。
※裏に聖杯戦争を仕組んだ人間がいると考えていますが、その考察が的中しているとは限りません。
※柳洞寺周辺にNPCはいません。
----
|BACK||NEXT|
|027:[[Cyclone]]|投下順|029:[[初期不良]]|
|027:[[Cycloned]]|時系列順|029:[[初期不良]]|
|BACK|登場キャラ|NEXT|
|014:[[No.14]]|金田一一&ライダー|040:[[FINAL DEAD LANCER(前編)]]|
----
*ズッコケ二人組と一匹~聖杯戦争から脱出せよ~
「なあライダー、こんなとこに何があるんだよ?」
「まあ慌てるでない、ついてくればわかる」
少年探偵・金田一一とそのサーヴァント・ライダー。
二人は自己紹介を済ませた後、最初に降り立った柳洞寺の境内を調べに………行くことはせず、山門の横の茂みの中を歩いていた。
運動が得意ではない金田一だが、その足取りは決して重くはない。
普段から旅行などで山道を歩く機会が多く、身体が慣れてしまっているからである。(もっとも、その旅先で毎度のように殺人事件に巻き込まれるのだが)
「ふむ、ここらでよかろう」
ある程度開けた場所に出たところで、ライダーは立ち止まった。
しかし、金田一から見て、何か特筆すべきものがあるようには見えない。
「ここったって……別に何もないぜ?」
「いやいや、何もない場所だから良いのだ。今からすることを考えればな」
そう言って、ライダーは懐から白い教鞭のようなものを取り出した。
先端に陰陽のマークのような球体が付いているのが印象的だった。
そして、ライダーは咳払いをしてから、真剣な表情で語り始めた。
「金田一、おぬしは知略を駆使して戦うタイプの人間だ。
しかし、それを生かすには適切な情報が必要不可欠。
故に、まずは知らねばならん。
おぬしが巻き込まれた、この聖杯戦争の知識をな」
「………ああ」
確かにライダーの言う通りだ。
殺し合いを止めようにも、そのために必要な情報を理解していなければ立ち行かない。
金田一もまた、気持ちを切り替えて真剣にライダーの説明を聞き始めた。
「まずは目を閉じて、意識を集中するのだ。
おぬしにとって最もイメージしやすい形でわしのサーヴァントとしてのステータスが見えてくるはずだ」
言われた通り、目を閉じると、ライダーの能力らしきものが浮かんできた。
【クラス】ライダー
【マスター】金田一一
【真名】太公望
【性別】男性
【身長・体重】不明
【属性】中立・善
【筋力】D 【耐久】D 【敏捷】C 【魔力】B+ 【幸運】A+ 【宝具】??
どうやらライダーは身体能力で少々劣るサーヴァントらしい。(その代わり魔力や幸運は優れているようだが)
「今は最低限の情報しか見えぬであろうが、いずれは全ての情報が開示されるはずだ。
それと、目視さえすれば他のサーヴァントの情報も分かるようになっておる。
常にチェックしておくのだぞ」
「ああ、わかった。ところで、宝具ってのがステータスに載ってたんだけど、宝具って何なんだ?」
素直に疑問を口にする。
名前の響きからして、重要そうな部分だとは思うのだが、ライダーのそれは今の金田一にはまだ読み取れなかった。
「うむ、宝具とは、サーヴァントにとってのシンボルであり、半身のようなものだ。
宝具の種類にも色々あるが、まあ今は必殺技のようなものだと思っておけば良い」
そして、ライダーは先ほどの教鞭のようなものをこれみよがしに掲げた。
「例えば、わしの宝具のうちのひとつがこの打神鞭だ。
これは、大気を自在に操る宝具だ、ほれ、このようにな」
「うわっ!?」
ライダーが打神鞭を振ると、金田一とライダーの間に猛烈な風が発生した。
それは金田一にも目視できるほど濃密な風のうねりであり、その勢いに思わず尻餅をついてしまった。
「す、凄いんだな、宝具って………」
「何を言っておるのだ、今のはわしにとってはほんのそよ風に過ぎん。
本気で撃てば、この山など軽く吹き飛ぶぞ」
しれっととんでもない事を口にするライダーに、金田一は頬が引き攣るのを止められなかった。
そんな彼を他所に、ライダーは手近かな地面に向かって打神鞭を振りかぶっていた。
その顔には邪悪な笑みが浮かんでいる。
嫌な予感しかしない。
その予感は果たして的中し、ライダーは打神鞭を振り下ろし、掘削機の要領で地面に穴を掘り始めた。
「わーっはっはっはっはっはっは!!」
「ちょ、ここって私有地じゃ……」
「はーっはっはっはっはっは!!」
「いや、だからやめ……」
「はーっはっはっはっはっはっは!!」
金田一の制止など気にも留めず、ライダーは不気味な高笑いを上げながら地面を掘り進めていく。
そして、数メートルほど掘り進めたところで、満足したのか手を止めた。
こんな穴を作ってどうするつもりなのか、金田一には見当もつかない。
「どうすんだよ、こんな事して。
寺の人に怒られるんじゃあ………」
「固いことを言うでない。
それより、ここからが本番だ。
この打神鞭に付いたスイッチを…ポチっとな」
そう言うや否や、打神鞭から旗のようなものが飛び出した。
「これぞわしの第2の宝具、杏黄旗だ!」
ライダーは非常に誇らしげだ。
旗が飛び出た時キコキコキコーンという謎の擬音が聞こえたような気がしたが、多分気のせいだろう。
ステータス欄が更新されたことから、残念なことにこれは本当に宝具らしい。
「な、何だその目は!
これは戦略上とても重要な宝具なのだぞ!」
金田一の可哀想な人を見るような視線に耐えかねたのか、ライダーが声を張り上げた。
「いや、でもそれ………旗だろ?」
「ただの旗ではない!この布は魔力の受信機のようなものだ。
本来はこういう使い方をするものではないが、まあ聖杯戦争に合わせた仕様変更というやつだ。
この布を半分ほど破って……今掘った穴にポイっとな」
そう言って半分に破った杏黄旗の布を穴に投げ入れると、ライダーは何やら呪文のようなものを唱え始めた。
その顔は真剣そのものであり、決してただのお遊びではないことを伺わせる。
数十秒後、詠唱を終えたライダーは金田一の方に向き直った。
「実は、今わしらがいるこの円蔵山は、自然の魔力が集まる霊脈と呼ばれる場所なのだ。
わしの杏黄旗は、そういった土地に敷設することで、本体である打神鞭に魔力を供給する仕組みになっておる。
わざわざ獣道を通ってここに設置したのも、馬鹿正直に敷地の真ん中に埋めては戦闘の余波で破壊されてしまう可能性が高かったからだ」
「そうだったのか………。
でもこの穴、どうすんだ?そのままってわけにもいかないだろ?」
「うむ、それについてもわしにいい考えがある。
というわけで、カモーン!スープー!」
ライダーが天に向かって指をパチンと鳴らすと、煙とともに何かが現れた。
それは不思議な生き物だった。
ティーカップの皿のように大きくつぶらな瞳、ふわりとしたたてがみ、頭に生えた二本の角。
全体的に丸みを帯びたシルエットは、金田一に昔幼馴染と共に見たとあるアニメを想起させた。
「こやつがわしの霊獣にして相棒の四不象だ。
わしがライダーのクラスで現界している所以でもある」
「す、すっげえ……!」
金田一は目を輝かせながら四不象に見入っていた。
生前はその外見から侮られることが多かっただけに、四不象はとても誇らしげな表情、いわゆるドヤ顔状態になっていた。
「空飛ぶ白いカバだ!」
その場の空気が凍りついた。
普段なら四不象がカバ呼ばわりされてもニヤニヤしながら見守るだけのライダーも、金田一のあまりの悪気のなさに
流石に気まずくなり、フォローを入れようとする。
しかし、遅かった。金田一は四不象にアイルランドの光の御子が愛用する因果逆転の魔槍の如き威力の
言葉の暴力を(本人に全く悪気は無いが)次々に浴びせていく。
「うっわぁ~、本当にすげえ!ムー○ンみてえ!
そういや美雪があれのぬいぐるみ持ってたよな~。
あ、お手」
「あ、いや、金田一。そやつは……」
四不象はすでに俯いてプルプルと震えているのだが、金田一は全く気がついていない。
そして……
「ボ、ボクはカバじゃないっスーーーーーー!!!!」
「お手」の部分にキレたのか、ついに四不象が爆発した。
しかし、金田一の反応は非情なものだった。
「うわっ!?カバが喋った!?」
さらに(悪気は無いが)追い討ちをかける金田一。
よほど驚いたらしく、腰を抜かしている。
「だからカバじゃないっスよ!召喚直後にこの言葉責めはあんまりっスよ!」
「う、うむ。こやつは見た目はまあアレだがれっきとした霊獣なのだ。
というかおぬし、もう少しデリカシーというものを身に付けた方が良いぞ」
すかさずフォローを入れるライダー。
主人の援護に四不象もようやく怒りを鎮めた。
「ところで御主人、ボクを呼び出したってことは敵が現れたってことっスか!?
ボクの活躍の場面っスか!?」
度重なるカバ呼ばわりがまだ尾を引いているのか、四不象は何とかして自分の勇姿を金田一に見せつけたいようである。
「うむ、おぬしはこれからわしらと一緒にこの穴を埋める作業をするのだ」
「了解(ラジャー)っス!金田一くん、ボクの勇姿を…………って、え?
御主人、今何て言ったっスか?」
「だから、わしらと一緒に穴を埋める手伝いをしろと言ったのだ」
四不象はショックで再び凍りついた。
召喚されてからいきなりのダブルパンチで、四不象のライフはもうゼロである。
「ボクの聖杯戦争の初仕事が後片付けっスか!?
ひどいっスよ御主人!こんなの絶対おかしいっスよ!?」
「っていうかこれ、俺もやるのかよ!?」
「ええい、やかましい!ちょっと掘りすぎてしまって人手が足りんのだ!
わしらは一心同体一連托生!さっさと片付けるぞ!」
とまあ、このように漫才を繰り広げながら杏黄旗敷設のために掘った穴を埋める作業に勤しむ二人と一匹であった。
「つ、疲れた………。
んでもって、何だよこの長い階段……」
「頑張るっスよ金田一くん。
でも、もうちょっと体力つけた方が良いっスよ」
二人と一匹で穴を埋めた(ただし、ライダーは寺の偵察と称して途中で抜けた)後、金田一と四不象は長い階段を通って柳洞寺の境内に入ろうとしていた。
元々体力のある方ではない金田一にとってはかなりの重労働だったらしく、その表情には疲労の色が濃い。
「とにかく、中に入って一休みするっスよ。
御主人も先に中にいるはずっスから」
「でも、良いのかな。
勝手に入ったら警察呼ばれるんじゃ…………ん?」
「?どうしたっスか?金田一くん」
警察という単語を口にした途端、金田一の表情が一変した。
それは、忘れていた重要な事を思い出した時のような表情だった。
「そうだよ!警察だよ!!
早く警察に通報すれば良かったんだ!!
悪い四不象、ちょっくら電話借りてくる!」
「えっ?ちょ、金田一くん、それは……」
言うが早いか、金田一は寺に向かって駆け出した。
そのスピードたるや、先ほどまでの疲労を全く感じさせないほどの速さだった。
「すいませーん!少し電話貸してくださーい!」
誰もいないのをいいことに、寺の母屋に駆け込んだ金田一は、電話を探して駆け回る。
「どうしたのだ金田一、そんなに慌てて。
電話がどうのと言っていたようだが……」
「あ、ライダー!ちょっと警察に電話してくる!
あと、寺の人がいたら謝っといてくれ!」
廊下から姿を現したライダーを見つけるや、早口で用件を伝えてその場を立ち去ろうとする金田一。
そんな彼を、ライダーが腕を掴んで引き止めた。
「ちょっと待て金田一!警察に電話すると言っても……」
「何だよ!そりゃ普通の警官じゃサーヴァントには勝てないかもしれないけど、それでもこんな状況なんだ!
警察がいるといないとじゃ全然違うはずだ!
大丈夫だって!剣持のオッサンや明智さんなら聖杯戦争のことだって信じてくれる!」
「いや、そういう問題ではなく……」
「考えてみりゃおかしかったんだ!さっきの山だって人がいない獣道のわりに落ち葉がよけたような痕跡があった。
多分、ここはつい最近まで生活してた人たちを無理矢理立ち退かせて用意した会場なんだ!
普通なら考えられないけど、それこそサーヴァントみたいな力を使えば不可能じゃないのかもしれない。
つまり俺たちが今するべきことは、何とかして外に助けを求めることだったんだよ!」
早口で自らの推理を捲し立てる金田一に対して、徐々に脱力していくライダー。
そんなライダーを振り切り、金田一は電話を見つけ出し、警察に電話をかけた。
「あっ、もしもし警察ですか!?本庁の剣持警部か明智警視につないで下さい!
変な神父が殺し合いをしろって言ってるんですよ!」
なるべくサーヴァントのことは伏せて説明を試みる。
しかし………
「ああ、聖杯戦争の事ですか?
申し訳ありませんが、当方では聖杯戦争に関する一切の質問・要望等を受け付けておりません。
聖杯戦争の知識をお求めでしたら、月海原学園図書室をご利用下さい」
「はい!?ちょ、ちょっとあんた、何でその事を……って、あっ、ちょっと!?」
不気味ほど事務的な対応を取られた末に一方的に切られてしまった。
間違い電話をかけてしまったのかとも思ったがそんなこともない。
もしや聖杯戦争の魔手は警察にまで及んでいるのだろうか?
「……いや、まだだ。警察が駄目なら他の人に頼めばいい!
えーっと、いつきさんに佐木に針生さんに結城先生に黒沢オーナー、後は……心配かけちまうけど、美雪やお袋に玲香ちゃん、他には――――――」
思いつく限りの知り合いの名前を列挙し、電話をかけようとする。
そんな金田一の肩を、脱力しきった様子のライダーが叩く。
「……金田一、おぬしの言いたいことは分かった。
分かったから、ちょっとこっちに来てわしの話を聞いてくれ」
「?ああ、わかった」
妙に疲れた様子のライダーを不思議に思いながらも金田一はライダーの話を聞くことにした。
「はぁ!?ここがバーチャル空間だって!?」
「そうだ。ついでに言えば、そもそも地球ですらない。
月に存在する巨大な演算装置にして観測装置、ムーンセル・オートマトン。
その中に展開された電脳空間こそが、この聖杯戦争の会場の正体だ。
おぬしの言う妙な神父も、進行役として選出されたNPCであろう」
場所は変わって柳洞寺の本堂。
そこで金田一はライダーから今回の聖杯戦争の舞台、ムーンセルについての説明を受けていた。
ちなみに、いつの間に用意したのか、ライダーは本堂の中に自分のコーナーを作っており、さらに山のように茶菓子を置いていた。
ライダー曰く「このような大きな寺院にはそれ相応の人数の檀家がいるはず。となれば、そういった者たちをもてなすために、常に茶請けの類を母屋の台所に用意していると睨んでいた」との事。
閑話休題。
数多くの事件やトリックを解明し、今回に至ってはサーヴァントなどという超常現象に遭遇した金田一だが、流石に今、自らが五感で感じている現実をバーチャルなどと言われて素直に信じることはできなかった。
「………そんな話を信じろっていうのかよ。
大体、月にそんなすごいものがあるんだったら、ニュースになってないはずがないじゃないか。そんな話、聞いたこともないぜ?」
「それは、おぬしがムーンセルの存在しない平行世界から呼ばれたからであろう。
聖杯の力を“使えば”不可能なことでもあるまい。
というかおぬし、わしやスープーのことはあっさり信じたではないか」
「だってライダーも四不象も俺の目の前にいるじゃないか。
実際に目にしたことまで疑ってたらきりがないだろ。
少なくとも、ムーンセルだの並行世界だのよりはまだ信じられるよ」
金田一とて超常現象の類を一切合財否定するほど頑固でも狭量でもない。
聖杯戦争にしても、現実的な殺し合いや、今や日常茶飯事といっても過言ではないほどの頻度で遭遇する殺人事件に置き換えればどうにか理解できる事ではある。
しかし、ムーンセルや平行世界といった話は、金田一の想像力の範疇を大きく越えていた。
一言で言えば、話の規模が大きすぎてピンとこないのである。
「それに、その話を全部信じるにしたってまだおかしい事があるぜ。
そのムーンセルが観測装置だっていうのなら、どうして殺し合いをさせて願いを叶えるなんて話になるんだ?
最後まで生き残った者が願いを叶えられるっていうのも一体どんな基準で決めたんだよ?」
金田一の疑問に対し、ライダーはやや満足そうに頷きながら答えた。
「いい質問だ、金田一。
そもそもムーンセルとは、太古の昔から地球上のあらゆる記録を観測するために存在してきた。
過去にもムーンセルが記録活動の一環として人間を招き、殺し合わせた実例もあるが、並行世界の人間までもを呼び寄せて聖杯戦争を開いたという記録は無い。
少なくとも、聖杯からわしに与えられた知識にそのような記録が無いことは事実だ。
では、何故この聖杯戦争が起こったのか。
金田一よ、多くの事件を解決してきたおぬしならわかるのではないか?」
試すようなライダーの言動に、金田一は少々困惑しながらも思考を巡らせる。
ライダーは何故か“多くの事件を解決してきた”という部分を強調して言った。
だとすれば、自分が今まで関わった事件にヒントがあるという事だろうか?
(でも、俺が関わった事件なんてそれこそ思い出してたらきりがないぐらい多いんだよな。
なら、少しでもこの聖杯戦争に近い性質を持った事件……。
そこに鍵があるのかもしれない)
そう考えて思い出すのは、かつてバルト城で起こった、ミステリーナイトツアーという名目で行われた連続殺人事件。
やや乱暴な考え方だが、催し物を装って誰かを招き、人を殺し、自らは目立つ主催者の影に隠れるという点では聖杯戦争と共通していると言えなくもない。
そしてこの事件を聖杯戦争が起こった理由と関連付けて考えた時、金田一の脳裏に一つの仮説が浮かんだ。
「まさか……この聖杯戦争も、誰かが仕組んだものなのか?」
「うむ、少なくともわしはそう睨んでおる。
さっきも言ったが、ムーンセルは、この世界の地球上の記録を観測することしかせぬ。
並行世界の人間を観測するのは、その本義から外れたことだ」
「でも、最近になってそっちの方も記録するようになったって可能性もあるんじゃないか?」
「では聞くが金田一よ、並行世界というものは一体いくつあると思う?
例えば、もしおぬしが今の疑問を思いつかなかったら。
警察に電話することを思いつかなかったら。
もっと言えば、昨日の昼食の内容が変わっていたら。
そういった僅かな変化から生まれた分岐が、一つ一つの並行世界になると考えた場合でだ」
あまりに無茶なライダーの質問に、さしもの金田一も閉口する。
「そんなの、数え切れるわけないだろ。
むしろ、数えるだけ無駄じゃないか、そんなの」
抗議のつもりで言った言葉に、ライダーはむしろ我が意を得たりといった表情で答えた。
「その通り。数えるだけ無駄だ。
だからこそ意味が無いのだ。
如何にムーンセルが膨大な記憶容量を誇るといっても、それは単一の世界を基準とした場合だ。
無限の並行世界の地球の観測までしていては、すぐにオーバーロードを起こして自壊するのは自明の理。
つまり、ムーンセルの本来の目的から言えば、並行世界の扉を開き、人を招くこと自体が非合理的な無駄の極みなのだ」
「だから人間が仕組んだ、って事になるのか……。
ってちょっと待てよ、だとしたら、順序が逆になる……!
ライダー、お前さっき聖杯の力を使えば並行世界の人間でも呼べる、みたいなこと言ったよな?
だったら、願いを叶える人間を決めるために殺し合いをさせるんじゃなく、既に聖杯を手にして願いを叶えた人間が俺たちに殺し合いをさせてるってことになるんじゃないのか!?」
自ら思いついた仮説に青ざめる金田一。
もしこの考えが事実なら、自分たちが何をしても殺し合いを打破することなど不可能、という事になりかねない。
何しろ相手は既に聖杯を手に入れた人間だ。
少しでも殺し合いに反抗した者を消すなど造作もないだろう。
「いや、厳密には少し違うであろう。
本当に聖杯を掌握し、願いを叶えたのなら、わざわざ聖杯戦争を起こす理由が無い。
恐らくそやつは、聖杯にある程度干渉することはできても、完全に掌握し、目的を達成するには至っていないのであろう。
つまり、この聖杯戦争は目的達成のための手段として引き起こされた可能性が高い。
願いを叶えるという触れ込みや、バトルロイヤルという形式にしても参加者に疑問を抱かせないようにするための方策であろう。
この調子なら、他にも何か信憑性を高めるための布石を打っているやもしれぬな」
ライダーの返答に少しだけ安堵した。
考えてみれば、こうして自分たちが聖杯戦争の裏について議論することが出来ている時点でこの聖杯戦争の仕掛け人が完全な力を持っているわけではないことは明白だ。
そして、聖杯戦争を開催した理由についても、提示された勝利条件を考えればある程度の推測はできる。
「最後に残った一組みに願いを叶える権利が与えられる……って事は、殺し合いが完遂される事が目的の達成に必要な条件ってことになるよな」
口にするだけで苦い思いがこみ上げてくるが、考えることをやめるわけにはいかない。
金田一が持つ唯一の力が、この推理力なのだから。
「うむ、十中八九そう考えて間違いない。
となれば、わしらの取るべき方針は聖杯戦争の完遂を阻止することに絞られる。
しかし、これだけでは時間稼ぎにしかならぬ」
そこまで言うと、ライダーの表情が悪戯を思いついた子供のそれに変わった。(もっとも、ライダーの外見年齢は中学生ぐらいの子供といっても良いほど若いが)
「故に、わしらはどうにかしてこの会場、冬木市から脱出する必要がある。
そして、優勝以外の方法で聖杯に辿り着き、最終的には聖杯の近くにいるであろう黒幕をやっつけて、わしらで聖杯を独占するのだ。
殺し合いに乗ったマスターも、聖杯を他の参加者に握られては黙らざるを得まい」
あまりに突拍子の無いライダーの提案に、金田一は開いた口が塞がらない。
勿論それが出来ればベストなのだろうが、そう簡単に上手くいくとは思えない。
そんな金田一の表情を読み取ったのか、ライダーが微笑みながら説明を続ける。
「なーに、わしとて根拠も無く言っているわけではない。
如何に舞台がムーンセルといえども、この聖杯戦争自体は人間が考えたものだ。
まして並行世界の人間を招くという無茶までした以上、完璧ということはあるまい。
必ずどこかに隙があるはずだ」
殊更力強く話すライダーに、金田一もまた勇気づけられるのを感じた。
方針は固まった。ここからは行動すべき時だろう。
「よし!そうと決まれば街に出て情報収集だ!
できたら他のマスターにも接触して―――」
「駄目」
「……は?」
唐突に冷や水を浴びせられた。
「わしらは当面、この柳洞寺に籠城する。
幸いここには食糧もあるからな」
「な、何でだよ!?もう準備は十分だろ!?
こうしている間にも殺し合いが起こってるかもしれないのに……!」
「まあ理由はいくつかあるが、一つはおぬしの言う他のマスターについてだ。
この聖杯戦争に参加を決めた者の多くは魔術を始めとした何らかの超常的な力を有しておるだろう。
強い力を持ち、自ら望んで殺し合いに参加した者など、精々潰し合ってもらえば良い。
おぬしが気に病むことではない」
これまでとは打って変わったライダーの残酷な言動に、金田一は動揺を隠せなかった。
「でも、だからって死ねば良いなんてことにはならないだろ!
それに、俺みたいに巻き込まれる形で参加させられた奴だっているかもしれない。
誰かが死ぬかもしれないって分かってて、見過ごすなんて出来ねえよ……!」
「金田一」
今までで一番真剣な表情と共に、ライダーが口を開いた。
「おぬしの気持ちは、わしもわかるつもりだ。
だが、今は耐えるのだ。
殺し合いを止めようにも、今のわしらが打てる手はあまりに少ない。
それに、今はここに立て篭る事こそが殺し合いを止めるために打てる最大の一手なのだ」
「……どういう事だよ?」
納得がいかないながらも、続きを促す。
「もう一つの問題は他のサーヴァント、とりわけキャスターだ。
魔術師のクラスに位置付けられておる彼のサーヴァントなら、スキルと魔力量次第でこの冬木市全体への魔術行使すら可能になるであろう。
そして、それに最も適した土地がこの柳洞寺なのだ。
つまり、ここを占拠される事は、魔術への抵抗力を持たぬおぬしや他の一般人のマスターにとっては死活問題になる。
それだけは避けねばならん」
ライダーの語る言葉に嘘は無いことは、その表情から伺い知ることができた。
恐らく、ライダーの言う通りにするのが現状ではベストなのだろう。
一瞬、令呪に訴えることも考えたが、それは徒にライダーとの関係に溝を作る結果にしかならないだろう。
また、本人はあまり自覚していないが、金田一自身、理詰めで物事を判断しやすい性格であることも彼をこの場に留まらせる一因になっていた。
しかし、同時に、諦めることを決してしないことも金田一の持ち味だった。
彼は、無言のままライダーの隣に座ると、茶菓子の包を手に取り、腕を組んで何やら考え事を始めた。
「…?どうした、金田一」
「考えるんだよ。
確かに今、俺はライダーの考えた作戦を上回るようなアイデアを示すことができない。
でも、それは今の話だ。
ライダー、俺は諦めないからな。
誰も死なせない、お前も認めるような方法を必ず考えてみせる」
そう言って、そっぽを向いて茶菓子(薄皮饅頭)を食べ始めた金田一の背中を、ライダーはどこか嬉しそうに見つめていた。
同時に、今後の展望についてもある程度の考えを巡らせていた。
ライダーとて、いつまでも柳洞寺に篭っているつもりはない。
彼は、生前と同じように、殺し合いを打破するための仲間を募るつもりだった。
(戦局が動くとすれば恐らく今から明朝までの間。
その間に戦闘で消耗したマスターとサーヴァントがこの地の霊脈を求めて来る可能性は高い。
そして、その時こそが交渉のチャンスだ)
消耗しているであろう相手と杏黄旗と霊脈によって魔力の充実したライダー。
そして、脱出の可能性と聖杯を山分けするという実利。
これらの条件をカードにして他のマスターと同盟を組み、ある程度数が揃ったら打って出る、というのが彼の戦略だった。
他のマスターが真っ先にこの柳洞寺に乗り込んで来る可能性もあるが、この序盤戦でそのような行動に出るのは十中八九キャスターのマスターだろうとライダーは考えていた。
その場合、戦いは避けられないだろうが、流石に陣地作成スキルの恩恵も受けていないキャスターに敗れるつもりはない。
Bランクの対魔力は伊達ではないのだ。
逆に、キャスターを仲間に加えることが出来れば心強いとも思う。
(殺し合いに乗っていない熟達の魔術師がマスターで、聖杯にかける願いの無いキャスターを従えている、そんな者たちと手を組めれば………はは、我ながらなんと無茶苦茶な)
あまりに虫の良すぎる発想に、思わず苦笑する。
常識的に考えて、そんなマスターとサーヴァントの組み合わせが有り得るはずがない。
(まあ、それはともかく……何故ここにはNPCがいない?
このような僻地にNPCを配置するリソースを割くことをムーンセルが無駄と捉えたか、あるいは霊脈としてのアドバンテージを得られるこの地に魔力炉になるNPCを配置することをある種の不公平と取ったか、あるいはその両方、か?)
例えば、もしも自分たちではなくキャスターが最初にこの地を抑え、更にNPCを魔力炉に利用したならば。
恐るべき早さで工房、あるいは神殿を形成し、序盤から圧倒的な優位に立っていただろう。
ここにNPCがいないことも、ある程度の公平性を期すための措置と考えれば納得できなくはない。
どこか釈然としない気持ちもあるが、いないものはいないのだ。
これに関しては、今は置いておいても構わないだろう。
それよりも、考えるべき問題が山積みなのが現状だ。
ちらりと、考え事をしている金田一の方を見やる。
正義感が強く、危ういところもあるが、サーヴァントとしてだけでなく、太公望という個人としてもこの少年を死なせたくはない。
一方で、金田一ならこの状況を打破する妙案を考えてくれるのではないか、という期待もある。
若き少年探偵の背中に、ライダーは微かな、しかし確かな希望を見出していた。
【柳洞寺・本堂/深夜】
【金田一一@金田一少年の事件簿】
[状態]:健康(残令呪使用回数:3)
※「怪奇サーカスの殺人」開始直前からの参戦です。
【ライダー(太公望)@藤崎竜版封神演義】
[状態]:健康・魔力充実
※杏黄旗により、どこにいても円蔵山から魔力供給が受けられます。
ただし、短時間の内にあまりにも大量の魔力を吸い出した場合、霊脈に異常をきたす可能性があります。
※裏に聖杯戦争を仕組んだ人間がいると考えていますが、その考察が的中しているとは限りません。
※柳洞寺周辺にNPCはいません。
----
|BACK||NEXT|
|027:[[Cyclone]]|投下順|029:[[初期不良]]|
|027:[[Cyclone]]|時系列順|029:[[初期不良]]|
|BACK|登場キャラ|NEXT|
|014:[[No.14]]|金田一一&ライダー|040:[[FINAL DEAD LANCER(前編)]]|
----
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: